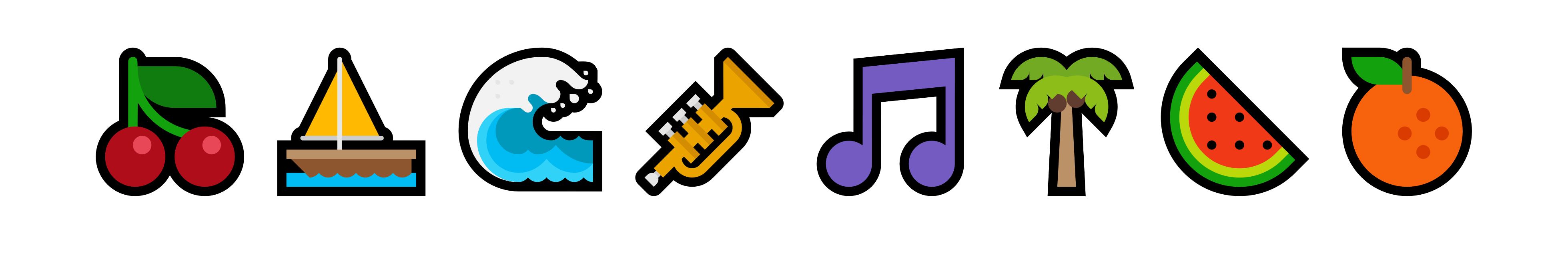- 第一文学 神話
- 第二文学 戯画
- 第三文学 自由
- 第四文学 創造
- 第五文学 羽化
- 第六文学 追憶
- 第七文学 永遠
第一文学 神話
ボーダーに吊るしたライトひとつの舞台。
女子演劇部員に促されて、ひとりの男子生徒が下手から入る。
上手側奥にパイプ椅子があり、男はその椅子に座らされ、目隠しをして、ヘッドホンを掛けられる。
女子演劇部員は
舞台面まで出て、モノローグ。
「紹介します。
この舞台の影の主人公、伊藤弘。
一週間前の放課後、アイスクリーム一個と引き換えに勧誘。
演劇経験、ゼロ」
女子部員は上手に捌け、男は目隠ししたまま。フットライトが灯り、舞台が始まる。
ホリゾントに光が射し、舞台はとある学校、その教室。
冒頭、落下音。
「山下が飛び降りた!」
教室に飛び込んでくる男子生徒の声で、教室が騒然とする。
「山下くんが? どうして?」
「あいつ、いじめられてたから――」
救急車のサイレンが響き、しばらくは混乱が見られるが、やがて山下は一命をとりとめたことがわかる。
そこから、目隠しとヘッドホンをした男――伊藤弘――を背後に置いたまま舞台が進む。
山下がどんないじめを受けていたか、どんな言葉を向けられたか――ひどい暴力と、耳を背ける言葉があった。山下役の役者は明らかに素人。パイプ椅子の男を本気で避けているように見え、たびたびセリフを噛んだ。
ここで勘の良い観客は気付き始める。
――パイプ椅子に座っているのが、リアルで山下をいじめていた本人なのだ、と。
いくつかの場面を経て山下は怪我から回復、友人は告発を薦める。いじめていた相手を演劇地区大会の舞台の上で糾弾する。それが演劇部部長、主演の男からの提案だった。
そのために山下もいまから演劇部に入れ。主演の男が薦める。
いや、でも演劇なんかやったことがないから。
山下が尻込むと男が客席に求める。
拍手を!
会場には小さな拍手が湧き、その拍手と声援に押されて告発の舞台が準備されていく。
告発するだけだ。でも仕返しが。大丈夫、客席全員が味方になる。
――拍手を!
山下が躊躇うたびに主演の男は声援を呼びかけ、その拍手は少しずつ大きくなる。
――拍手を!
むしろこの舞台は、観客たちの声で作られていった。
舞台の終盤、脇に座っていた男が目隠しをしたまま舞台中央に引き出される。
サスペンションライト。
山下を目の前にして、男の目隠しと、ヘッドホンが取られる。
女子演劇部員がまた舞台面に立つ。
「改めて紹介します。
こいつがその山下くんを追い詰めた男、伊藤弘。
みなさん、拍手を」
観客はただ固唾を呑んだ。
戸惑う伊藤の眼の前、山下には部長の手から、ナイフが手渡される。
ナイフの意味は?
山下は拒絶するが、強引にその手に掴まされる。
この舞台は公開の処刑であり、復讐だった。
部長はナイフを渡したあと、汗ばんだ手を学生服で拭った。
山下はそんなことは聞いていない。戸惑う。
パイプ椅子の男も危機を悟っているが、すでに首にテグスをかけられ、両側から固定されている。
主演の男が客席に向かって、しずかに、震えを抑えながら口上を述べる。
「伝統ある藤橋高校演劇部、また、伝統ある当大会をこのような形で汚してしまい、本当に申し訳ないと思います。だけど、僕たちは、僕たちの表現よりも、このことが重要だと思いました」
そのとなりで山下は困惑し、部員に訴える。
このナイフをどうしろというの、ここまでしたいとは思わない。約束と違う、告発するだけでいい。
異様な雰囲気だった。もうだれも演技などしていない。パイプ椅子の男が動くと首のテグスが締り、それを引く部員の手に伝わる。柔らかく肉に食い込む感触に目を背け、涙を流し始める。ひとつの表情から決意と戸惑いとがともに伺えた。
主演の男は静かに、力強く観客席に向かって言った。
「山下に拍手を」
客席は水を打ったように静かだ。
山下が躊躇うたびに拍手を送っていたのが嘘のように。
主演の男は強いまばたきを二回、天井を仰いだのちに息を整えて続ける。
「山下は自殺をはかりました。いまも後遺症があります。彼にはこいつを殺す権利があります。僕たちはそれを十分に訴えたつもりです。どうか、拍手を」
そのセリフを二回噛んだ。
山下がナイフを捨てると部員がそれを拾い、また山下に手渡す。
男の語気は強くなる。
「僕は伊藤を殺すかどうか聞いているんじゃない。伊藤と山下、どちらを生かすべきか聞いてる。あなたたち以外、だれが彼を裁くんですか! 山下のために! どうか、拍手を!」
――最後は涙ながらに訴えるが、だれも拍手を送るものはなかった。
堪えきれなくなった山下が舞台袖に走り、観客に訴えていた男はその背中を追う。
騒然としたままステージライトが消えた。
暗転から開けると、全キャストがまっすぐ横に並び、観客席に向かって頭を下げた。
伊藤も山下も、演劇部員だった。
ただふたりとも――あるいは舞台に立つ全員、役に入り込み過ぎて、その顔に浮かぶのは演劇部員の表情ではなかった。そこにあったのは観客の反応次第でどう動くかわからぬ修羅の形相。
舞台をリードしていた男――
南家タカユキ――演劇部部長は、山下、伊藤役の部員を指して汗に濡れた髪を掻き上げた。
「どうか、ふたりに拍手を」
❡
城戸榛央が第七文学を廃部すると言い出したとき、彼の周囲ははじめてそれが部活であったことを知った。
そもクラスメイトの耳にその第七文学と聞こえた単語が部活や愛好会の類のものとは響かなかったし、その話を聴き入っていたものからも、それは彼の文学理論、あるいは作劇のセオリーのようなものとして受け取られていた。去年、まだ榛央が二年のときに書いた戯曲が、高校演劇の予選でそれなりの評価を得た頃から、榛央が口にした『第七文学』という言葉は、意味もわからないままに人口に膾炙し、特に親しいクラスメイトには世界の秘められた知識を覗かせるような優越、高揚を与え、それはあるものにとっては退屈な高校生活の中での特別な居場所になったし、またあるものには、世界を測るための物指にもなった。
榛央がそれを廃部すると言い出したのもあるいは何か抽象的なこと、いまの部活同様に捉えられた現状からの飛躍か、すわ第八の扉の掲示かにも聞こえ、校内において語られる数万の語彙の中でも殊に第七文学という言葉は謎めき、正しく接続される意味も持たず、それを言の葉に上らせた城戸榛央という男の不可思議を際立たせた。
学校の朝礼は毎週月曜の朝。
その日の朝礼に榛央は姿を見せなかった。
企業の朝礼と学校の朝礼の違いは、原拠とするデータの有無だった。
企業では毎週の売上や、プロジェクトの進捗、取引先との折衝、市場の動向について各部門がデータをもってマイクを握ったが、学校の朝礼はわかりきった学校行事の案内のほかは精神論が中心となった。それも最初に枠が決められているものだから、その枠を埋めるためだけの持ち回りのスピーチも少なくない。フードコートでのマナーが報告されているだの、インフルエンザの流行の兆しがあるだの、真面目に聞くだけの価値のない情報が全校生徒を集めて一方的に垂れ流される。必然、飽きる。そこには対話もないし、オーディエンスの反応を見た即興性もない。それどころか、退屈して欠伸をする聴衆がいたら壇上から叱り飛ばすことさえできた。
これを指して城戸榛央が『第一文学』と呼んだことが始まりだった。
第一文学は神話だった。
思ったことをただ伝えれば、その役割を終えた。
榛央からこのレクチャーを受けたなかに、剣道部の
瑞樹圭吾がおり、その圭吾を通して演劇部の南家貴之がいた。
榛央と貴之は演劇部の部室で意気投合し、果たして文学をそうやって数えると、第いくつまであるかとホワイトボードに書き出し、第二、第三、第四、と例を挙げて語らい、概ね四から五は想定できたが、そこが頂点ではないだろうとの結論に達した。
榛央はその貴之から、三年にあがってすぐ、また新しい戯曲執筆の打診を受けていたが、新作の構想が伝えられたのは五月の末だった。予選の地区大会まではまだ余裕があるが、焦らしに焦らしたわりには、まだペラ一枚の文字すらない。
「図書室の老人について書きたい」
一言目にそう聞いて、貴之はぱっとオペラ座の怪人を思い浮かべた。
まだ十七になったばかりのふたり、それぞれに古典に目を通す機会はあったが、つい五年と二ヶ月前は小学生だ。本を読んでいる量は限られたし、舞台や映画となると目にする機会そのものがなかった。貴之はそれなりに裕福な家に生まれ育ったが、ならばチェーホフの四大戯曲、シェークスピアの三大悲劇を『まともな』舞台で見たかと言えば、見てはいない。活字でなら読んだし、かもめ、ハムレットは動画でなら見た。が、それよりもマイナーなもの、たとえばピーター・ブルック、たとえばサミュエル・ベケットとなると、それがどれほど歴史的に重要な価値を持ち、どれほど本人が憧れていようが観覧は叶わなかった。
「オペラ座の怪人みたいな?」
「いや、知らない。違うと思う」
榛央のこの見栄を張らないところが、貴之には心地良かった。
「高校生に呪いをかけた老人が、いまも図書室にいるんだよ」
榛央は続けた。
「呪いって?」
「だれも知らない」
「だれも知らない呪いって、呪いじゃなくね?」
「そうかな。たとえば、『腹が減る』ってのが呪いだったら、だれも呪いだとは思わないけど、かなり迷惑な呪いだよ」
「そのレベル? すげぇな。それが図書室にいるんだ」
榛央は言葉を選び、『青春の呪い』と言い換えた。
呪いはこのふたりにもあった。
演劇と文学とに憧れてはいるが、幼い頃から漫画とアニメで育った。
中学でカズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を読んだ榛央、同じように野田地図の『Q』を観た貴之は、それぞれに感性を尖らせるようにはなっていたが、それを学校で話したところでまわりはアニメと漫画とで感性を鍛えたものしかいない。他方では、演劇界には幼い頃から劇団に所属し、名のある舞台を何本も目にし、親や恩師から舞台哲学を叩き込まれた血統もいる。だが、貴之はそうではない。呪われているのだ。その彼がチェーホフを演りたいなどと言い出すのも呪い。演劇畑で英才教育を受けていれば、それをやりたいなどとは言わない。言わずともやがて実現するし、ただ目の前に来たもの、それは舞台でもなんでもない夏の避暑地への旅行、あるいは著名人の出版パーティ、そんなものに接していれば、やがて彼らは花を咲かせる。貴之も榛央も水をやらねば枯れる花。それが、呪いだった。
冷房のない五月の午後。講堂に響く声は天井に触れ、ひとの汗の湿度を加えて榛央の耳に返った。風のない講堂に吹き溜まる体温は大気の粘性となって、そこに刻みつける声と音とが彼、彼女らの物語となった。榛央は剣道部の竹刀の放つ音とコーラス部のクワイアとが響き合うなか、足を怪我し、ひとり個人メニューをこなす親友、剣道部エースの瑞樹圭吾にスマホのカメラを向けた。
地区大会の、もう予選にすら出ないだろう級友の練習を動画に収めながら、榛央は呟いた。
「実録・天才剣道少年の軌跡」
天才と言われた男は視線を上げる。
「どうするのその動画?」
「おまえの結婚式で流す」
「なにそれ」
「従兄弟の結婚式でそういうのやってた」
コーラス部の声が横切る。
その声は、来年どこかの大学に進学し、アカペラーサークルに入って新しく知り合ったヴォイスパーカッションとともに学園祭の舞台に立ち、一斉を風靡する声だ。その先、そしてまたその先にも物語がある。榛央の撮る動画のなかで交錯している光と音は、無限の物語の一葉だった。試合に出るあてもなく練習を続ける親友、天才剣道少年、瑞樹圭吾。その人生の輝きも地区大会ごときで変わるものではない。そこにはただ、無限の物語がある。ぞくぞくした。この瞬間の思いは愛にも似ていた。圭吾だけではない。この講堂を埋める声のすべてが榛央のなかを通り抜ける恍惚の風となった。青春には壁があり、立ち向かい、もがき、苦しむなど嘘だ。多くの物語で『壁』と名付けられたそれは、広大な人生につながる光と音の積層だ。
「それ、どんなオチがつくの?」
圭吾が問うた次の瞬間、足元にバスケットボールが転がってきた。
榛央はフレームを動かさず、ただそのボールに意識を集中させて動画を撮り続けた。
わかるか、この物語が、この高揚が。
放課後。雨。
まだ明るい雲に遠雷が混じり、雨の雫が俄にグラウンドを叩き始めると、そこに開放された土の匂いが生徒たちを追い立てる。走る生徒たちの声。雲から引いた陽の光を縫う雨の斜線。グラウンドの熱気が払われていくと、まだ陽の光を残したまま、今日の舞台のいくつかが幕を下ろす。
「今年も脚本書くの?」
昇降口で空を見上げながら、圭吾は聞いた。
「文章では書かない」
「なにそれ」
「文章はいろんなものを閉じ込めてしまう」
「でもあれ、脚本で審査とかはないの?」
「知らん」
「適当だなぁ」
榛央は可笑しかった。
急に降り出した雨の昇降口、多くのものが交錯するなかで、だれもが他人であることが。
榛央は圭吾を抱きしめた。
「天才剣道少年」
耳元に囁いて、首筋の匂いを嗅いだ。
「やめろよ。わけわかんねぇ」
昇降口に引かれた無数の生命のラインがそこで足を止める。
「この可笑しさがわかるか?」
「おかしいって、おまえがおかしいだろ」
元剣道少年は両の人差し指で交互に榛央の脇腹を突いた。
親友に抱きついて匂いを嗅ぎ、脇腹を突かれて腰をくねらせる榛央の姿は、たしかに可笑しかった。
第二文学 戯画
榛央はひとり雀を眺めていた。
心に傷を負うかにも見える影が、渡り廊下に沿う花壇のまえのモルタルの段差に佇むと、見かねたように圭吾が腰を下ろした。
「部活は?」
第七文学を称する帰宅部の予定を、圭吾が尋ねた。
「新しい部を作る」
今日もまた少し、理路に開きがあった。
「あとで聞くわ」
剣道部の練習が始まるまでの刹那、榛央と圭吾、それに貴之を加えた三人はよく語らっていたが、この頃の貴之は自意識の蛹化が進行し、カタカナでタカユキを名乗るようになっていた。第何文学という分類を推し進めた功績や責任はこの男にもある。その日もまた圭吾は眉をニ列にしかめ、耳に入る絡まった音を丁寧にほぐしていた。
榛央と貴之の考察では、アニメーションと漫画の多くが第二文学にとどまるとされた。しかし圭吾には疑義があった。漫画やアニメは様々な物語を描くことができる。日本神話や平家物語から、星新一、日本沈没までアニメになったが、それらのすべてが第二文学というのはおかしい。
対する榛央の意見は明快だった。たしかにアニメの内容は様々だ。しかし、『戯画化されている』という時点で第二文学を超えることはない、と。
いや、それにしてもである。戯画化が果たして文学のカテゴリーの決定要素になるだろうか。
顎に指をあてて口を曲げていた圭吾が、いやしかし――と論理の壁に竹刀を向けた。
「原作小説とアニメみたいな、まったく同じ内容の小説とアニメがあったとして、それでもアニメは第二文学で小説は第三、あるいはもっと上の段階と言える?」
榛央はちらりと圭吾に視線を投げる。
「おそらく」
圭吾の射るような視線から、少し答えを庇った。
「おそらく、なんだ」
「もしかしたら、そうではないものがあるかもしれない」
はっきりしない返答。圭吾は訝り、また同じ問を、同じ構えから繰り返す。
「たとえばガンダムなんか、たしかに戯画化されてるかもしれないけど、リアルな戦争を描いている。あと、小説のほうも少し描写がシビアになるけど基本は変わらない。それでもアニメは第二、小説は第三なの?」
剣道少年が語る戦争ロボットアニメには、当人には気付く由もない格別の美があった。その美こそが、第二文学だ。
「いや、その考え方は違う。どんなにリアルな戦争をモチーフにしようが、戯画化して伝えるという手法が第二文学なんだよ」
三人の他にあと二名ほどのギャラリーが耳を傾けていた。特別にアニメが好きなものは混じっていなかったが、通りすがった生徒のなかには聞き耳を立てたものがいたかもしれない。ニワカがなにか語っている、と。
「第二文学までは現実から切り離された抽象として描かれる」
と、榛央は続けた。
桃太郎という抽象化された英雄の物語に登場するのは、翁と媼、犬、猿、雉であり、具象性はない。それが第二文学だ。物語にアニメの絵を重ねた時点で、登場人物は戯画化され、抽象化している。このため、アニメや漫画がどんなテーマを選ぼうとも、それは第二文学になる。
「つまり、第何文学ってのは手法の問題?」
榛央は圭吾の一挙手一投足のすべてに剣道を重ね合わせた。だがそれこそが戯画だ。戯画化された圭吾がアニメを語っている。この美こそが第二文学であり、それが表現の足枷となり、つきまとう。
「いや、わかんない」
「わかんないのかよ」
戯画化で見えるものと、消えるものがある。役目を終えたら迷わず捨て去るべきものが戯画だ。そしてそれは第何文学といういまの言葉遊びにしてもしかり。
「だって、俺たち第五文学までしか紐解いてない」
「紐解くも何も。第何まであるのさ」
「たぶん七」
「なんで」
「なんとなく、神聖そうな数字だから」
やはりたいした根拠はなかった。どこか綻びがあるものとして聞いていたが、実際に綻びだらけだ。よくもこんな話で盛り上がれるものだ。
「じゃあ、第一文学と第二文学の違いは?」
「第一は疑いのない情報伝達。だからプロパガンダアニメのようなものは第一文学になる。戦時中の戦意高揚アニメだったり、宗教団体の洗脳用だったり」
榛央の説明を引き取って貴之が加えた。
「神話は疑いようがないんだよ。たとえ矛盾があって、つっこんだとしても、それで神話体系が崩れるものでもないし、そも聞く耳をもたない。神の思し召しであって、疑うこと自体が無駄なの。第二文学からようやく批判が可能になる」
第一、第二文学に関して、榛央と貴之の意見はほぼ一致していた。だが――
「いや、第二文学からというか、第二文学特有。第三以降は批判が成立しない」
という榛央の主張には、さすがに貴之も、
「はあ?」
と、ひとが疑問を感じたときに口に漏れる凡庸な音を鳴らした。
「はっきりと物語が成立するのが第二文学の特徴」
「それがアニメの特徴でもある、と」
「そう。戯画化されて物語になる。というか、物語が戯画化の最たるもの。物語が批判を可能にする。第三文学からは究極的には戯画化・物語化は否定され、批判を透過する。批判は物語に対してではなく、それが表現しているもの自体に対するものになる」
「つまり逆に言うと、批判可能なものは第二文学である、と」
「そう。第二文学は『駄目な物語だね』と言える。だけど第三文学からは『好きじゃない』とか『興味ないわ』くらいしか言えない」
「アニメが第三文学になる可能性は?」
「わからない。あるかもしれない。でも、たとえば
狼煙は第一文学を超えないと思うんだよ」
狼煙。いきなりか。榛央は中学時代からこうやって唐突に話題を変え、ペースを乱してくることがあった。
「狼煙って、火を焚いて煙で情報を伝達する、あれ?」
「そう。こういうときにこういう狼煙をあげる、と事前に決めておいて、なにか起きた際にそれを伝達するだけ。もしそれでも『いや、その信号は間違いじゃないか、見直せ』というフィードバックを返せたらギリ第二文学足り得るかもしれない」
という榛央の説明に、貴之が「いや、ないでしょ」と、笑って加える。
「狼煙を使って、二進数で符号化したシェークスピアを伝えたら?」
というケーススタディに、問うた貴之自身が答えを添える。
「僕はそれでも第一文学だと思う」
「どうして?」と、圭吾。
「たとえば朝礼で校長がスピーチする場合、これは第一文学。一方的に確信的に情報を伝達するだけだから。じゃあ、そこで校長がジャン・コクトーを朗読したら第五文学になるかというと、ならない」
「そこがわからない。内容は関係ないの?」
「内容というか、送り手と受け手の関係で決まる」
貴之の解説に榛央が加えると――
「あー、それじゃ……」
と、また貴之が切り出す。
「朝礼やってるー、校長が挨拶するー、次に通りすがりの知らない人が朝礼台に上がるー、オペラ歌い出すー、の場合は?」
「それ、第十五文学くらいいってると思う」
割り込んだのは圭吾。
「頂きました! 第十五文学! 最高記録です!」
と、こちらの反応が城戸榛央。第七文学の提唱者は、いつもこんな調子だった。
アニメの戯画化は、アニメの放送されるスタイル――決まった尺で、固定的な枠に投影されるという仕様全体を指すもので、送り手と受け手の関係もそこで規定される。
「ただその関係が崩れたアニメーションというのはありうる」
「たとえば?」
「屋根裏を漁ったら出てきた8ミリフィルムのジャングル大帝とか」
「それはテレビで見たジャングル大帝とは違うんだ?」
「この場合、それを再生してもだれも物語なんか見ないじゃない。そこには別の意味付けがされてる」
「それは、第何文学なの?」
「第…十八?」
と、圭吾の問に答え、榛央は上目遣いにその白く細い鼻筋を見上げた。
「出ました! 第十八文学! 一気に記録更新です!」
フォローしたのは貴之だった。
❡
六月、暦の上では梅雨、カレンダーは雨。雨傘、紫陽花、かたつむり。六月の挿絵は雨に唄うが、その年の六月は晴れの日が続いた。紫陽花もかたつむりも、鞄の脇の5ミリの綻びにも満たない、架空の存在だった。
晴れた六月、日差しがまっすぐに塗り分けたアスファルトの、足は自然と陰を踏んだ。そこにはわずかにしっとりとした水の感触があった。待ち合わせのベンチには知らない誰かが腰掛け、榛央は少し離れた壁沿いの狭い日陰に身を隠した。左腕に掛かった日差しに幾度か陰が流れ、圭吾が現れた。
「貴之は?」
軽く手を挙げて圭吾が訊いた。
「現地。少し遅れるって」
立川には漫画図書館があった。
正式には立川まんがぱーく。中央線立川駅から歩いて
10分もかからない場所にある四百円――三年まえまでは中学生だったので二百円――で四万冊の漫画が読み放題の公共施設。広い芝生の広場があり、定期的にフリーマーケットが開かれ、プロによる漫画教室などのイベントも催されている。施設内では格安で食事も取れたし、至れり尽くせりの環境ではあったが、すぐ近くには榛央らがライバル視する高校があり、アウェーの緊張感があった。
「立川のやつは漫画なんか読まないよ」
「いや、読むだろ」
「バカが読むんだよ。俺たちみたいな」
わずか数ポイントの偏差値の違いにコンプレックスがあったが、この場合の『バカ』は彼らの誇りだった。
クラスには漫画を読むものと読まないものがあり、読むものの場合、家に親や兄弟姉妹が買った漫画があることが多かった。あるいは従兄弟同士でまわしていたり、あるいは親に連れられてよく通う食事処や病院に漫画が置かれていたり、身近にいるだれかがその扉を開いた。
榛央は父親がよく漫画を買ってくるものだから、常に身近にありはしたが、『大人のもの』という印象があった。暴力的で、ときに汚らわしく、退廃的で無価値で実りのないもの。そのなかでも子どもの自分でも読める四コマ漫画やギャグ漫画を探して読むのが、幼い頃からの漫画との接し方だった。好きか嫌いかとは考えなかったが、どちらかと言えば忌避してきた。女の裸が描かれたページには興奮を覚えると同時に、それを読んでいる父親の姿を想像し、不可解な混乱に見舞われた。中学から図書館に入り浸り、活字を追うようになり更に気持ちは離れ、まともに漫画を読むようになったのは高校に入ってから。友人からどの漫画が面白いと聞いて、家にある雑誌をめくって改めて読み返し、そこではじめて『親が読むもの』以上の意味が生まれた。
親が読んでいた漫画。従兄弟が持ってきた漫画。友だちから借りた漫画。これらはそれぞれに違ったタイプの読者を育てたが、榛央の場合はずいぶん拗れた育ち方になった。いまでも漫画の半分は父親への嫌悪でできている。
剥離骨折からいくらかの時が過ぎたが、圭吾の歩く姿にはまだ少し違和があった。その足元の立川駅からまんがぱーくへの真っ直ぐな道は軽業師の渡る細いロープのように、落ちるはずもない奈落の上を慎重に足を運びながら、
「学校、辞めるかもしれない」
と、榛央が切り出した。
「ああ」
圭吾は薄々その理由を知っており、言葉が喉に絡んだ。
「おまえが辞めると、カッコつけてるふうに見られるけど、いいの?」
否定的な言葉で引き留めをはからない態度は、圭吾らしい前向きさにも見えた。剣道少年。ことあるごとにその竹刀が鼻先をかすめる。
「貧乏がカッコいいかね」
「だれも知らねぇよ。おまえんちの貧乏なんて」
信号が聴覚障害者用の音を鳴らして、ふたりの足を止めた。
「高校通えないくらいなの?」
圭吾はかつて榛央から、父親が家に金を入れず、母親の稼ぎだけでやりくりしている話を聞いていた。車もある、レジャーにも行く、部屋にはルンバもあるが、すべて父親の気分次第。せっかく買ったPCやカメラも半年もすればまた換金されて、新しいおもちゃに変わった。
「母ちゃんなんも言わんし、わからんけど。学校通える気分じゃない」
「伝説になるよ。仮に今度の高校演劇でいい成績残してさ。それで辞めたら」
愚直だが目立ったことを嫌う榛央に向けた修辞法が含まれた、バランスの悪い物言いだった。
「学校なんかつまらないから辞めた。さすが天才少年。次元が違う、って」
「でもさ。『世に倦む』ってよく聞くけど、いまの俺と同じなんじゃないかね。俺もカッコいいと思ってたけど。言い方だよ。どうすればいいかわかんないだけだよ。きっと」
普段の榛央の会話は隙間だらけで、親友の圭吾ですら意味を拾いそこねることがあった。聞き返しても二度目の言葉は、似た意味を持つ意図せぬ言葉に替わるだけ。
「それ、貴之にも言っとけよ」
足元のロープを見ながら圭吾は言った。
「言うよ」
この信号を待ちながら言うはずだった。
「誤算だった」
足を止めて眺めていた鳥が、青い旋律を唄った。
❡
中学以来のまんがぱーくは、新型コロナの流行の頃から整理券制に変わっていた。
室内には押入れのような空間がいくつか用意されているが、早い番号を取らないとそこには入れない。整理券制に変わるまえ、中学時代に来たときはふとしたタイミングで空くこともあったが、午前午後入れ替えでそれぞれ整理券を配るようになったいまはそんな幸運もない。整理券が配布される8時半に来たが、もうひとが並んでいた。整理券の番号は
33。
「押入れいくつあったっけ?」
圭吾に尋ねてみるが、
「知らないよ。初めてだし」
そっけない返事。
「あれ? だれと来たんだっけ?」
「貴之じゃないの?」
「いや、高一のときだから、たぶん違う」
もしかしたら高一と思い込んだ記憶が間違っているかもしれないし、圭吾の思い違いかもしれない。確かなことなど何もない過去は、深層でメルヘンの世界に接続している。
10時の開場までテラスの椅子に座って参考書を開いて、年表の項目を4つほどつまんだ。歴史は楽しかった。無意味な数字と事件の組み合わせが、隣接した地域、近い時代の事件から線を伸ばすと呼吸を始める。興味の欠片もなければ、散乱した数字と文字列はなにも伝えない『無』だ。それがいくつかのきっかけで自ら触手を伸ばすようになる。そうなればあとは自動的に知識として蓄積される。もしこれがテレビゲームであれば、そうやって自動的に蓄積されるところまでチュートリアルされるが、学問の多くはそうではない。おかげで多くの高校生は歴史を覚える記憶領域にゲームのアイテムや魔法名を詰め込む。ゲームはゲームで楽しいし、学ぶべきことは多い。ゲームを学ぶ喜びと現実を学ぶ喜びは基本的に同じものだ。だが、現実は無限の裾野を持つ。紀元前
31年アクティウムの海戦から、今日のこの日のまんがぱーくまで線を結ぶことができる。新しい本を開けば、胸のなかにある様々な知がそれにむかって一斉に手を伸ばす。知は学ぶのではない。絡め取るのだ。
開場し、たまたまひとつだけ取れた『押入れ』に鞄を置いて間もなく、貴之が姿を見せた。ちょうど圭吾が榛央に進めようと、キングダムの1~2巻を手にして押入れに戻ったときだった。貴之は一瞥もせずに荷物を放り込んで、「探してくる」と古い少女漫画の棚に向かい、おおよそ
58秒後、SWANと題された古いバレエ漫画を手に戻ってきた。
「面白いの?」
「面白い」
「ガラスの仮面持ってくるかと思った」
「ガラスの仮面もいい。双璧」
ガラスの仮面は演劇漫画で、SWANはバレエ漫画、時代性もあってか共通点があった。主人公の才能がその世界で名のあるひとに見出されるパターンは、この二作に限らず鉄板だろう。ただ、榛央にはガラスの仮面はピンと来ていないようだった。ガラスの仮面は根性論的な要素が強く、荒唐無稽なところがある。それこそがあの作品の醍醐味であるが、受容体のない読者には響くこともない。それで薦めたのがSWANだった。
少年たちは漫画の貸し借りを通して魂を共有した。そこには公園や、あるいはゲームの仮想空間でともに遊ぶこととは違う意味があった。それは互いの好きなひとを打ち明けることに似ている。塾も、ゲームも、ドッジボールもこれを代替できなかった。それを物理的に介在していたのが漫画雑誌とコミックスだったが、それらが大人のものになって久しい。打ち明けるまえに、そのひとはもう指輪に囚われていた。
漫画にいまひとつ興味を持てなかった榛央にもSWANは響いたようで、それはおそらく端々に登場する実在の人物の名前がリアルな世界との連続を見せたからだろう。現実のなかにある無数の呼吸の糸のいくつかを手繰って、ようやく漫画が意味をもった。そういう意味では圭吾が薦めようとした中国古代史に通じるキングダムも、榛央には向く。
榛央はSWAN、貴之はキングダム、圭吾は榛央から薦められたベルセルクを読み、ともに三巻を読み終える頃に
12時を回った。
午後はまた開演前と同じようにテラスの椅子に座り、コンビニで買ったバターロールを齧って話し込んだ。
「学校の図書室、どうなるんだろう」
榛央が切り出す。
「明るい図書室に生まれ変わるんだよ」
圭吾が答える。
生徒会便りかなにかで見た新しい図書室の完成予想図は、よくニュースで見かける『使いづらい図書館』そのものだった。
「呪いの老人はどうなるの?」
と、貴之が問い返すが、圭吾の耳には初めて届いた。
「あー。あいつも若返って、高校生になるんじゃない?」
「色褪せて青白くなって」
「キャラメルマキアートとか飲んで」
「いや、スタバは入んないけど」
圭吾にはふたりのこの話がなんのことかはわからなかったが、すぐに首を突っ込んでくるタイプでもなかった。ふたりの間でいくつか言葉が行き来し、「それは……」と、榛央が答えに迷ったあたりでようやく、「なんなんだその老人」と、ツッコミを入れた。
「今度の演劇大会のテーマ。らしい」と、貴之。
「名前は徳川トリムネ」
その場のノリなのか、温めていたネタなのか、榛央が口に出す。
「いつ決まったー。トリムネーっ」
「そのほうらここに何をしにきた。もしやグラム
78円のこの儂を、唐揚げにして食らうつもりではあるまいな?」
尋ねても答えは拡散する。これらの言葉のなかに答えがあるわけではなく、この駆け回る子猫の足跡のすべてが答えだった。捕まえた子猫はシュレディンガーの波動関数に沿って収束し、無限の可能性を失う。――そう先週の物理の時間に覚えた。
「若返ったら記憶とかなくなると思う。俺たちにどんな呪いをかけたかも、きれいに」
「その呪い、俺らも忘れてるんだよね?」
「そう。きっれーに忘れてる」
「だったらいいか」
ひとりふたりがかけられた呪いなら気にもなるが、全員がかけられ、全員が忘れ、かけた本人さえ覚えていなければ、それはもう呪いじゃない。
「転校生トリムネーッ!」
「キャラメルマキアートでラブラブキャッチの巻!」
話題の毛先は散り散りに乱れた。
「どういうお話なの、それ」
果たして猫は生きているのか、死んでいるのか、圭吾が散らかった言葉を掃き集めると、榛央は「えっ?」という音を笑みのなかに洩らした。
「なんも考えてない」
「いや、考えてくれよ」
タカユキが呆れて吐き捨てると、5秒ほど榛央は考えた。
「正義について……? とか」
正義。その言葉を剣道少年は素直に受け止めるが、榛央の目の奥には日差しのなかを群れ飛ぶ羽虫の煌めきがあった。
高校生の考える『正義』は概ね『正義など存在しない』に陥り、ひとによっては骨壷のなかにまでそれを引きずる。ともすれば、榛央の次のひとことが圭吾の正義観を決定づけ、一生の呪いになる予感を醸したが、そこは第七文学だった。
「正義を語るとき、必ず戦争が描かれるのはなぜか」
意外な、そして直球でわかりやすく、明快な答えがあるだろう問いを投げかけた。
「正義がぶつかりあうからじゃない?」
直球で投げ返したのはまた、直球で戯画化された剣道少年だった。タカユキは頬杖をついてニヤニヤと笑みをこぼしている。じわじわとテーブルに滲み広がる笑みを、剣道少年はおくびにもかけず、第七文学は右手中指で下唇を歪ませて続けた。
「果たして、その極限状態でひとびとが主張するのが正義か、という問題と、その状況を想定して語られる『正義』にどんな意図があるか、という問題」
という問題――という体言止めに終端を検出できず、やや間をおいて圭吾は問い返す。
「極限状態だから正義が語られるのではなく?」
成立した会話というのは、おそらくフィクションでしか存在しない。AとBで交わされる会話が客観的に意味を介在したかどうかは当事者にはわからず、それがフィクションになることで、会話の当事者ABは消え、無意味に意味だけが残る。その無意味に残った意味が、文学だ。
「アニメも漫画も、『戦争になりました、正義とはなんでしょう』、という架空の問いかけの大喜利なんだよ。その極限状態のなかでだけ語られる『正義』ってのが、そもそも僕らの『正義観』を歪ませている。イコール、戦争を正当化する道具や処世術に矮小化されてる。それはたぶん偽正義であって、本来僕たちが考えないといけない正義じゃない」
そう畳み掛ける榛央の言葉には、密度と速度と質量とがあった。
「でも、戦争も争いもないとしたら正義なんか描きようがないよ」
「んなこたーない。3人で4個のパン買って食べて、割り切れないときにどうする? とかいろいろある。戦争に例えるのは、ある種のショック・ドクトリンだよ。危機を煽って判断力を奪って、その隙に洗脳する。あるいは戦闘機やロボットがカッコいいから、それが売れるからでしょう? それは『偽正義』に『正義』のラベルを貼って売ってるのと変わらない。実際にアニメ好きや漫画好きの多くがロボットや剣を正義の象徴として捉える。しかも、金で買ってんだ、その正義を」
「まあ、言いたいことはわからんでもない。でも、それをどう描くの?」
「どうというと?」
「こんどの演劇大会に出るとして、戦争も喧嘩もなしに正義を描いてなにか伝わるの?」
「いや、伝わらないと思うよ」
「じゃあ、ダメじゃん」
「そうやって伝わる偽正義だけが正義ともてはやされる」
「それが正義だよ。偽正義じゃない」
「本気で正義を描くんだったら、いじめや貧困や差別を描くべきだ。だけどそんなもの、だれも読まない。みんなひとを殴りたいだけだから。戦争は正しいひとの殴り方を教えてくれる。前回の舞台も投身自殺未遂から始まって、舞台の間ずっと観客を揺さぶり続けて、それでやっとだよ。やっと伝わった。でもそれでしか伝わらないんだったら、舞台なんか糞だぞ?」
相手がだれであれ、榛央の話はすれ違うことが多かったが、このすれ違いによって榛央の内面は言語化されていった。圭吾、貴之と出会っていなかったら、これらの言葉もただ意識に薄くかかる靄でしかなかった。
「こうやって三人で語るだけの舞台でもいいよね」
静かに聞き耳を立てていたタカユキが、変な腰掛け方で乗ってきた。
それを――
「逆に、演出家としてはどうなんだよ、それ」
榛央が笑顔で否定した。
貴之は笑った。貴之がテーブルにこぼした5リットルの笑みはテラスいっぱいにひろがり、いつでも火を放つことができた。
「剣道少年とロボットアニメの正義とを語り合うバカふたり」
それこそ演出のやりたい放題だ。どうにでもできる。
「ちょっとまって、バカふたりってだれとだれ?」
「俺は入ってねぇよ」
端的に言うと榛央は、アニメも漫画も嫌いだった。
日が傾く頃にまんがぱーくをあとにして、信号に捕まってようやく榛央は打ち明けた。
「学校、辞めるかもしれん」
さっきから正義のことばかり反芻して歩いていた貴之は、その言葉を聞いて吹き出した。何がどうおかしかったのか、榛央にも圭吾にもわからなかったが、ちょうど頭のなかを巡っていたネタとうまいこと重なったのだろう。
吹き出した鼻水をぬぐって、
「クイズ、僕の中退の理由はなんでしょー」
退学の理由など知る由もない貴之は茶化すように言った。
榛央は相手にせず、
「親父が生活費入れないから、俺が働くしかない。だから辞めるんだよ」
いつになく抑揚のない口調で静かに洩らしたが、
「不正解!」
貴之は手厳しかった。
「なんでだよ」
「それが青春の呪い」
「マジか」
「マジマジ。書くしかないよ、図書館の老人を」
第三文学 自由
『自由』が生まれてまだ二百年しか経っていない。
僕たちが生まれ落ちたときにはすでに『自由』という概念があった。二百年前はさぞや不自由だったのだろうと想像するが、だれもが従い、だれもが迷わずに生きていける束縛があるなら、それは空気のように普通の存在だったはずだ。だれかがそこに『不自由』を発見したのだ。
いまの僕たちが感じる『自由』――空気のようにありふれて僕たちが浴びるように享受しているもの、あるいはそう思いこんでいるものと、二百年前の若者を包んでいた有形無形の『束縛』は、おそらく同じものだ。違いは、僕たちがその不自由に相当する『何か』をまだ発見できていないところにある。
自由はだれかに与えられるのではなく、個人のうちにある。己の考えのもとに生きることが自由だ。自由には責任が伴うというが、伴うのではない。不可分だ。飽くまでも己の頭で、あらゆる責任とリスクとを考えた上で結論を出す。それが自由だ。自由とは、自ら理由を作り出すこと。ひとはその『自由』に悩む。だれも『不自由』で悩んだりはしない。
かつて、『意味』があった。だが自由な世界には、自分のほかにはもう『意味』が存在しない。自由の反対の言葉があるとしたら、それは『束縛』でも『閉塞感』でもなく、『意味』だ。世界に意味を作り出せるものだけが真に自由であり、それ以外のものはもう隷属することすら許されない。なぜならばもう、『不自由』は存在しないのだから。
ひとは自由になったのではなく、『不自由』を発見し、解体した。不自由のない世界で、僕たちは自由になった。
仕事も学校も結婚も、だれかが決めてくれたらそれで良かったのだ。
城戸榛央は第三文学を『自由』であると表現した。
だからそこには物語も、批判も成立しないのだ、と。
改装前の薄暗い図書室には、件の老人だけでなく、多くの亡霊や妖怪がたむろしていた。古い図書室の価値はまさにそこにあった。これを明るく過ごしやすいカフェ併設の本のショールームに変えるものには、その呪いの矛先が向く。榛央も貴之もその警告を受け取り、圭吾にもそれはノートの切れ端に書いて回し読みされていた。その図書室の、なかでも薄暗い妖気の吹き溜まる一角で、呪いの老人の脚本は詰められていった。
「あのさあ」
蜂蜜色の午後に甘く湿らせた喉で、
「アイデアあるんだけど、聞いてくれる?」
聞かなくても勝手に喋る榛央があえて尋ねた。
「どうぞ。聞かないけど」
と促す貴之も聞くことは聞くのではあるが。
「舞台の上の役者が全員風船持ってるってのはどうよ」
榛央はパントマイマーのように右手に風船をかかげた。
「で?」
「舞台には鉄条網があって、それに触れると風船が割れる」
「それ、図書室の老人はどう絡むの?」
「このネタでやるんだったら、老人放っといてハムレットやりたい」
「はあ?」
然しものタカユキも解せなかった。
榛央は「みんなが知ってるネタじゃないと意味がない」と言ったが、ハムレットなど普通は知らない。みんなが知っているのは鬼滅の刃か僕のヒーローアカデミアだ。
「もー、みんながみんな風船持って出てきて、割れたら舞台下手に風船要員が待機していて、新しい風船を渡されんの。たまにすげぇデカい風船渡されたりして」
「で?」
「狂気を装ったハムレットが、体じゅう針だらけで出てくる」
「それ、コントだよね?」
と、黙って聞いていた圭吾も、つい突っ込んだ。
「弱きものよ! 汝の名は女なりパァァァァァァン!」
「うっせぇよ」
「本当は舞台の中央に国宝の壺かなんか置いておきたい。割ったら人生棒に振る」
この話題の展開にはやや飛躍が有り、ふたりを戸惑わせた。刹那2~3言葉を遡って、整理する必要があった。
「まぁ、借りられるんだったらやりたいけどさ」
という榛央と貴之の話を聞いて、果たして脚本とは何であろうか、というのが圭吾の素直な感想だった。これは文学云々の話ではない、コントだ。脚本とはこのようなものを指すのだろうか、と。
「わかった! 俺、考えた」
榛央が手を上げた。
「はい。それじゃあ、城戸くん」
「舞台のうえに、牛乳が入った紙コップ並べてるやつがいるの。そのなかでハムレット」
「ハムレットは決定なんだ」
「みんな紙コップの牛乳を避けながら演技しないといけない。椅子の上とか、セットの上にも置くの。ぶつかったら溢れて、みんなでお掃除しながら舞台続ける」
「あー。あれだ。あえてこう、脚立の上とか、すげぇ倒れそうなとこにも置いたりして」
「それだよ、それ!」
「面白そうだけど、それ、許可降りるの?」
「取らないよ、そんなの。許可が必要だと思ってませんでしたーっ! で突っ張るよ」
「脚本には牛乳のことなんかひとことも書かないし、練習も牛乳なしでやるから、ワンチャン、行ける」
「部員にも本番まで牛乳のことは言わない」
「いや、駄目だろ。ていうか、なんの意味があるんだよ」
「意味って。おまえたとえば口内炎できたときに意味とか考える?」
「口内炎?」
「そう。口内炎と一緒だよ。試験中とかも気になってしょうがないけど、意味とかないだろう?」
「じゃあ、紙コップ係は言い出しっぺの榛央がやるってことで」
「俺? ああ、やるやる」
「牛乳どうする? 買うとしたら何本くらいになると思う?」
「
100本じゃ足りないね。それだけで2万かな」
「絵の具で済ませられない?」
「それじゃ意味がない」
「確実に出禁だよな」
「いやいや、こぼさなきゃいいだけじゃん。そこは頑張ろうよ、演劇部」
「剣の試合んとこでこぼすだろ。ていうか、こぼすとこに置くだろ?」
「置く置く。俺と演劇部の真剣勝負だから」
「勝ち目ねぇよ。ガートルード王妃が毒入りの酒を飲んで七転八倒すんだぞ」
「飲むでない! ガートルード!」
「いただきますわ! うっ! これは!」
「どうした、王妃!」
「これは! メチルアルコール! 目がっ! 目が見えませんわバシャァァァァッ!」
「ガートルードーーーッバシャァァァァッ!」
そして散々脱線した挙げ句――
「面白いけどさぁ。でも、本質じゃないよね」
とあっけなく日和る。これもまた城戸榛央という男の常だった。
近代文学と自由とは切っても切れない関係にあった。
ロマン主義からこちらの小説は、自由を問い続ける大喜利だった。自由とは決して榛央の書くような破天荒な脚本――舞台の上に牛乳が入った紙コップを並べるような――を言うのではない。このケースでは善悪の判断、懲罰を他者に委ねており、『自らを由とする』に反する。行動の結果、責任、懲罰、そのすべてを己のなかで昇華したときに、はじめてひとは自由を得たと言える。もちろん、榛央もそれを知っているから冗談にして切り上げた。
しかし、
「本質だよ。ハムレットという物語を、所詮戯画にすぎないって暴くんだよ」
蛹化が進んだタカユキは、更に一歩踏み込んでくる。
「いや」
タカユキの真面目な返答を聞くと、榛央もギヤを上げずにはおれなかった。
「確かにハムレットは戯画かもしれないけど、たとえば『生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ』って台詞をパロディできるほどの高い視野を、俺たち持ってるか?」
その言葉の意味を蟀谷に添えた指で松果体に巻き取りながら、タカユキは更に言葉を促した。
「くだらないことだったらいくらでも揚げ足を取れるんだよ。だけどハムレットを超越した人間なんていない。あの上にはもう視点がないからパロディにできないんだよ。やるヤツがいたらギャグの意味すら知らないただのバカだ」
話題を切り出し、しかもいままで盛り上げてきた本人から、それを全否定する言葉が飛び出した。そのただのバカは、おまえ自身ではなかったか。
「ハムレットは確かにそう。あれを笑うような視点を僕らは持っていない。わかる。わかるよ。でもさあ、ハムレットの舞台でハムレットを演じるのは、たぶん、俺なんだよ」
主演、兼演出、南家タカユキ自らがそう念を押した。が、そんなことはわかっている。
「つまり?」
と、榛央は促した。
「ハムレットを笑うフリをしながら、俺を笑うの」
道なき道を走るタカユキの後ろ、榛央は植木をなぎ倒し、圭吾がその植木に躓く。
「どういうこと?」
そう問われてタカユキは少し考えて、ゆっくりと言葉を走らせる。
「ハムレットの舞台の真ん中で、テレビを見ている家族がいるんだよ」
「牛乳ではなく」
「そう、牛乳ではなく、お茶の間がある」
机に溢れた息を掬い取るような目で、貴之は続ける。
「そこで卓袱台のお菓子とかコップのジュースとかが蹂躙されるの。子どもはハムレットの足でじゃがりこ蹴られて、ジュースこぼして――でもそれにワクワクしながら――舞台は続く」
「毒入りの酒がタカユキが飲んでる紙コップにも注がれる!」
「飲むでない! タカユキ!」
「これは! ドクターペッパー! カメムシの味がする!」
「食ったことあるんか、カメムシ」
「見てる方は、こいつらハムレットで遊んでる、ろくに理解もしてねぇし敬意もクソもねぇ、騒がしいだけのガキだ、なんで出てきたんだ、って思うじゃない? でもここで描かれているハムレットはシェークスピアが描いたハムレットじゃなく、高校生の俺が演じているハムレットなんだよ。わかるよね?」
「わかるけど難しい」
「いや、わからん」
「そしてそれは少年が見てるテレビのなかのハムレットなの。で、後半はその少年がハムレットを演じる。わかる?」
「わかるけど」
わかる。だけどわかったのは意味ではない。それは言葉にすれば理解の9割が消えていく浅い夢のような理解だ。それでも――
「榛央、わかってるなら説明プリーズ」
と促され、言葉にするしかなかった。
「シェークスピアにかぶれて『生きるべきか死ぬべきか』とか言いながら、無邪気に少年の食卓を蹴散らしてんのよ、タカユキが」
「俺かい」
「おまえじゃん」
「俺だけど」
「シェークスピアやってるけど、まったく理解してもいないし、ネタにして遊んでるだけだとか言われんの。それがいまの俺たちとイコール。で、それを見てるタカユキ少年もまたハムレットを演じる。だれが見ても不快で、中身のないハムレットを」
その物言いは自嘲のようでもあり、怒りのようでもあった。
「永遠に届かないシェイクスピアに憧れて、憧れながらもそれをバカにして、不愉快だクズだと罵られて、『生きるべきか、死ぬべきか』と問うてもネタにしかならないハムレット。……図書室の老人の呪いにふさわしいと思わない?」
思わない? と、聞かれても、である。
「その『生きるべきか、死ぬべきか』は自問ではなく、審査員に問うんだよ。こんな愚かな俺たちを生かしてくれますか? それとも殺しますか? って」
「ごめん。わかんない。それで審査員に通じる?」
「審査員のレベルに合わせる気はない!」
「むしろ審査員ごときに理解できたら恥だね!」
❡
学校の最寄りの国立駅周辺がホームグラウンドだった。
図書館は主に西国分寺にある東京都立多摩図書館を利用していたが、榛央と貴之はそこを『アレクサンドリア図書館』と呼んでいた。古代史に通じていれば有名な名前だが、「明日はアレクサンドリア図書館に行く?」という言葉を聞けば、たいがいのクラスメイトはゲームか何かの話だと受け取った。
「アレクサンドリア図書館って、どのくらいの広さだったんだと思う?」
ちょうどふたりでシェイクスピアの戯曲を調べに来たときの会話だった。アレクサンドリア図書館は紀元前、プトレマイオス朝エジプトにあった巨大な図書館で、ゲームに出てくる巨大な図書館は概ねここを意識している。おそらく閉架式だっただろうし、現代まで残っている施設でもない。ゲームに取り上げられるものはデザイン的にはチェコのストラホフ修道院の図書館などがモチーフになっているのだろうが、そこを気に掛けるユーザーもいない。アレクサンドリア図書館は、アレクサンドリアの大灯台、アレクサンドリアのカタコンベと並んで古代エジプトファンの心をくすぐる観光名所だった。
そのアレクサンドリア図書館を、その場で榛央がスマホで調べると、蔵書数は少なくとも4万、多く見積もれば
40万とあった。あるいは
50万という説もある。立川まんがぱーくが4万冊。つまりそこがアレクサンドリア図書館の下限となる。では上限は? と、いまいる多摩図書館を調べたら約
50万冊だった。
「つまり、まんがぱーくと多摩図書館の間?」
「そうなる」
地元の学校に通う高校生の行動範囲はさほど広くない。西国分寺を超えて国分寺まで出ることは滅多になかった。ほとんどの用は西端の立川で済ませ、たまに東端の西国分寺の図書館を利用する。まんがぱーくと多摩図書館の間がふたりの生活圏だった。すなわちアレクサンドリア図書館には、彼らのすべてが詰まっていた。
「当時の本ってぜんぶ手書き?」
「だと思う。最古の印刷物は法隆寺の『百万塔陀羅尼』の8世紀だから」
「よくするっと出てくるな、それ」
この即応性をもって榛央を天才と称揚するものもいたが、同じクラスには ONE PIECE の悪魔の実をすべて言えるものもいたし、才能そのものはそれと大差ない。得意分野というのはだれにでもある。漫画の話になると置いていかれる榛央は『つまらないひと』というレッテルをすでに
15枚ほど貼られていたので、収支はマイナスだ。
「開架式の図書館っていつ頃できたんだろう」と、榛央。
「わからんけど、そんなに古くはないと思う。そもそもちゃんと製本してないと縦に並ばないし」
「いや、縦にくらいなるだろ」
「でも、パピルスの束だぞ」
「何年前だよそれ」
「よく、『本を大切にしろ』って言うけどさ、アレクサンドリア図書館の司書からしたら、本を縦に置いてるだけでびっくりなんじゃないかな」
「パピルスを縦に!」
と、榛央も一旦乗ってはみたものの、
「って、そこ、本当にパピルスなのか?」
突っ込だ。
「しかも学のない大衆に公開して、勝手に手にとって読んでる!」
「キャラメル・マキアート飲みながら!」
「ウンベルト・エーコの薔薇の名前で、毒殺された男が指舐めてページめくってるじゃない? あれちょっと信じられなかった」
「そうなの?」
「ページに塗られた毒で死ぬくらいの量ベロベロしてんの、司書見たら気ぃ狂うぞ」
「だから毒殺したんだよ」
「だからか」
「背表紙っていつ頃発明されたの?」
「しらん。なんで?」
「背表紙がないとそもそも開架式の図書館って無理じゃん」
「っつか、そもそも開架式の図書館っていつからあるのよ」
「しらん」
「荒俣宏とか知ってそう」
「ああ、知ってそう。聞きに行くか」
「僕が持ってるなかで最も古い本はこれですね、とか言ってすごいの出してきそう」
「パピルス本来たぁぁぁぁっ!」
脚本が完成したのは6月も末。ようやく雨も降り始める。
顧問の教諭から幾度か辞退まで含めた方針転換を迫られながらも通した選択だったが、二転三転した脚本は凡庸で、見るべきものがなかった。また直してもいいが、そろそろ本読みに入りたい。榛央は内心、この脚本を完成させた時点で高校を辞めようと考えていたが、その決心が揺らぐほどの凡作だった。
榛央は件の茶の間を蹂躙するハムレットをまとめた上でこう語った。
「自分をネタにするのは、象徴的には高校生全体をネタにすることになる。そのなかで俺は YouTube で炎上する高校生に対してどんなポジションに立っていいかわからない」
榛央自身は自分は客観的なつもりでいた。炎上する高校生には共鳴する部分もあったが、批判もあった。だからこそそれを己に映し、それを演じ、深層を暴露して見せる。演じるのは貴之だが、それはできる。簡単だ。でもそれを審査員が認めたとき、あるいは認めなかったとき、意味が生まれる。
「前者ならただ大人の立場に立って、炎上する高校生を嘲笑って見せた舞台。後者なら炎上する高校生を代弁して、認められずに散っただけの舞台」
それを打ち明けられた貴之の第一声は、「不正解」だった。
「なんでだよ」
「俺にはただ、榛央がプレッシャーに負けてるだけのように見える」
要は、凡作しか上げられなかった自分への言い訳だ、と自嘲気味に貴之は言った。
榛央もこれが自分のことでなければそう評したかもしれない。あるいは自分にスマホのカメラを向けていれば、そうやってプレッシャーで苦しみ、雑念に汚されていく姿に忘我の悦びを感じたに違いない。YouTube の炎上高校生に自分を重ね合わせたのも、己の無能を認めればこそだ。プレッシャーに苦しむ高校生など、いちばんのモチーフだったはずなのに、こと自分のこととなると見えなくなった。
動画投稿で炎上する高校生を『自由』と評するものもいるが、それは福沢諭吉らが西洋から取り入れた新しい意味の『自由』とは違う。古来日本では、野放図に好き勝手に振る舞い、なんの責任も取らないことを『自由』と呼んだが、百五十年前の近代化とともに変容した。たしかに古代日本の言葉で言えば、炎上高校生は自由だ。だが、その程度の理解しかしていないから『自由には責任が伴う』と言い添えねばならなくなる。自由の意味が明治維新によって変わったなど露も知らず、多くのひとが旧い意味で自由を語る。どこで覚えるでもなく、血がそれを決める。だれに流れる血でもない、日章旗の中心のあの赤い丸が。
自由とは己で考え、すべての責任を受け留めることだ。哲学者であり、実存主義の発端となった小説家でもあるジャン=ポール・サルトルは、己の行動に際しては「全人類に与えた影響の責任を取れ」と言っている。それが自由だ。だけど多くのひとにとって、むしろそれは不自由だ。では果たしてその自由をだれが、なぜ求めるのか。
「ところで」
と、花壇のモルタルに腰掛けた剣道少年が榛央に尋ねた。
「ロカンタンも戯画化されてると思った」
榛央と貴之がしつこくアニメを戯画だというので、ではそうじゃないものを読ませろとせがんで薦められたのが前述のサルトルの『嘔吐』と題された小説で、この言葉はそれを読んでの感想だった。読んだところでろくすっぽ理解は出来ないだろうし、おそらく読まないだろうと思って本を薦めることがあるが、まさにその事例だ。主人公のロカンタンは無自覚な因習的なものを見ると吐き気をもよおした。その理由を探るのが物語の筋立てだが、これは戯画ではないのか、と。
「おりょ?」
よくよく考えればロカンタンの吐き気も、この物語の軸である『実存』も戯画化されている。それは榛央のいう第二文学ではなかったか。
「でもそれ、読みながらああこりゃ戯画だなあって思ったか?」
「いや、読んでるときはピンと来なかったけど……」
聞けば、比較的新しい訳で読んでみたが、起伏のない展開に要領を得ずに、最終的にはウェブの批評も参照して理解したのだという。
「それ、自分から戯画化しにいってない?」
「だからその、戯画化の定義がわからない」
「戯画化して読めば、そりゃ戯画になるよ」
「だから――」
もとより榛央の提唱する『第七文学』という言葉が戯画であり、言葉遊びでしかない。言葉というものがそもそもその性質を帯びているが、それはさておき、この頃には言葉遊びならぬ――まだ本人たちにその自覚はなかったが――『圭吾遊び』のようにもなっていた。
榛央もただ一介の高校生だ。サルトルを齧り、知った気になって親友に薦めはしたが、社会参加などはしていない。サルトルにとっては小説や著作は客引きの看板でしかなく、読者が己の思想を支持し、社会に参加することをこそ望んだはずだ。しかし実際に部活と受験とに忙殺されていたら社会参加などしている暇がない。いや、そもそもと言うなら、フランスのように毎週末どこかでデモがあるようなこともなく、参加するべき社会が身近にない。選挙権がないのは当然ながら、デモや座り込みに行ったことも、駅前で募金に立ったこともない。実際にデモに参加してみても、主題とはズレたシュプレヒコール――森林保護を訴えるというので参加したら、劣化ウラン弾反対まで叫ばされたり――を求められ辟易することもあり、それ以前に参加すべき社会が糞なのだからもうどうしようもない。
赤い羽根や足長育英基金の募金に榛央が見たのは、大人に媚びて利用される学生の姿だ。募金は事務所が何割も抜いている。募金に頼るな、働け。募金に立つのは自己満足だ。俺ならそのぶんアルバイトをしてその金を渡す――と、言いながら、それを実行したことはないが――これではサルトルを読んだとは言えないし、実存主義の小説を語る資格もない。ましてや、書くなど。
演劇部の部室には校舎裏に放置されていた錆びたロッカーが置かれていた。
タカユキがまだ1年の頃に先輩に言われて運び込んだもので、もとから収納が足りないとネタにしていたこともあり、このロッカーも半ば冗談で運び込んだものだった。それがいまでは極彩色のモールと雑誌の切り抜きなどで飾られ、すっかりと部室に馴染んでいる。モールは3年生の追い出しパーティのときに飾った。切り抜きは榛央からもらったものをタカユキが貼り付けたものだ。その部屋で、一年後輩の副部長は、演劇集団キャラメルボックスの作品をやりたいと、タカユキに打ち明けた。榛央とタカユキとで、新作がどうにも形にならないと愚痴ているときに、スルリと差し込んできた。
「今から?」
と、タカユキは驚いて見せたが、そも榛央の新作は何も進んでいない。
「去年候補に上がってたんで、内容はみんな押さえてます」
演劇集団キャラメルボックスは
80年代に設立された、リアルのなかにほんのりと漉き込まれた超自然的な要素に特徴がある小さな劇団。公演時間
60分の戯曲を多く手掛け、高校演劇とも親和性が高い。渡された脚本は
60分のSFだった。
榛央はその場でパラパラと流し読んだが、頭に入れたくなかった。プロの作品と自分とを比べても仕方がないが、どうしても比べてしまう。視界に入れた台詞のいくつかからも粗を探してしまう。それでいて、おそらく良い作品なのだろうことはわかった。だけど、読んでしまえば目標になる。自ら心を揺さぶられて知ったわけでもない、知識として知っただけのものが。それを拒絶するには、作品を否定するしかない。
だけど、目標とはなんだ。
高校は辞めるつもりでいる。働かなければいけないし、そもそも何かを書いて投稿する気もない、演劇をやるつもりもない。待っているのはアルバイトで日銭を稼ぐ日々。
高校生には世界とは接続しない特権があった。
野球でも大学生や社会人なら、極めればプロがあるし、大リーグがあるが、高校生は極めても甲子園があるだけ。箱庭の世界で、なにをやっても割り引かれた評価しか無い。天才剣道少年、天才数学少年、それぞれに舞台が与えられる。演劇少年もまた然り。箱庭のなかの飼いならされた天才と、ただ愚かで騒がしい高校生だけがもてはやされる。
かつて自由が生まれるよりまえ、そこには呪われた社会があった。無数の規範や慣習に縛られた社会が、『不自由』という言葉によって輪郭を炙り出され、破壊された。新たに作り出された自由な世界には、抗うべき不自由はない。その不自由なき世界で、僕たちは自由になった。そして翼のないものはみな、不自由に憧れる。剣道少年も、演劇少年もそう。その歩む先には、彼らを束縛するメダルがある。榛央に与えられるメダルは、どこにもない。自由だからだ。
第四文学 創造
第四の文学は創造だった。
ロマン主義以降の小説の多くは第三文学に分類されたが、それらは人物に焦点が当てられることが多い。対して、社会に焦点が当てられ、その構造を暴き、新たに構築したものを第四文学と定義した。一般に見るSFの大半がこれに当たる。SFとそうでないものの違いはどこにあるのかとよく話題になるが、榛央の定義に拠ると社会を脱構築したものがSFだった。
一般にSFとはサイエンス・フィクション、つまり空想科学を指すとされるが、これをスペキュレイティブ・フィクションと解し、異世界の物語を描いたもの一般を指すというものもいる。その観点からすると、不思議の国のアリスや指輪物語もSFに分類されることになる。奇異に聞こえるかもしれないが、仮に火星を舞台としたハムレットがあれば、多くの人はそれをSFと解する。ただ、舞台が変わっただけで。
「それって、SFなの?」
ひとにそう聞かれたとき、質問者は物語の
構造ではなく
舞台を聞いている。それが一般的な理解であり、科学は要件としない。
映画であればそれでいい。物語ではなく舞台や雰囲気によってジャンルが定義されるが、小説はそうではない。飽くまでも物語で定義されるべきだ。しかし、昨今ではマルチバース流行りで、これが科学として扱われているせいで、愚かにも「並行宇宙の物語だ」と言えば、あらゆる異世界ものが空想科学小説たり得る。榛央はその取り繕ったような理屈よりも、物語の構造を重要視した。たとえば改造人間を主人公とした物語の場合、『科学の力によって改造されたこと』がSFの要件となるわけではなく、『改造されたことによって明らかになる社会の構造』がその要件となる。
果たしてどこまでの作品をSFと呼ぶべきか。この議論はときに白熱し、グループ内の派閥の形成、分裂とさまざまな結果を生むが、これを『SFとは第四文学である』と示し、本人にしかわからない言葉で再定義すれば、無駄に言い争う必要もない。答えが出ないときは、問を変え、新しい概念を生み出すに限る。また、それが求められているのだ。
第四文学というのは、いまSFと呼ばれているものの枠を拡張し、『社会構造を暴いたもの』を一般化した概念だ。たとえば遭難して雪山に閉じ込められたケースでも、登場人物の心理や行動が描写の中心になれば第三文学、インフラが失われたことで暴かれる常識の転換などが描かれていれば第四文学となる。
小さなきっかけから、いままでの常識をガラガラと崩壊させて見せる。これはアイザック・アシモフが語ったセンス・オブ・ワンダー――価値観の転倒にも通じる。
「つまり厳密に言うと、サルトルの嘔吐は第四文学になるってこと?」
「はあ? めんどくせえこと言うな」
「いや、おまえだって。めんどくせぇこと言ってんの」
しばらく足をかばっていた圭吾の怪我も目立たなくなった頃、高校演劇地区大会の練習が始まった。そのときにはもうタカユキは部長を山下に譲り、名前も貴之に戻っていた。演劇部の部長の交代は一学期を終えてからが恒例だったが、ふと見ると後輩たちには羽根があった。蛹のままもがいていたのは、部長である自分だけじゃないか。練習を見守りながらそう思った。
榛央は榛央で、高校を辞める決意は変わっていなかったが、ややおかしな方へと進み始めていた。
「お母さんにはまだ言ってないんだけど」
と、まず父親に切り出し、高卒認定試験、かつての大学入学資格検定・大検を受けて、合格後は高校を休学して独自に法学を学びたいと告げた。
そう聞かされた俗物は悪い気がしなかった。進路の相談を普段べったりと接している母親にではなく、自分にだけされた。妻に話すと、そちらは榛央がバイトを探していること、すなわち、家庭の事情を気に掛けていることを察しており俄には賛成しなかった。母親のこの態度が息子を萎縮させているのだ。そう見た俗物は息子の肩を持った。高校は進学校だが、自由な校風で知られていた。文化祭では髪を染めたものを目の当たりにして、顔をしかめることがあった。息子がその校風が合わず、独自に進学を考え、母親がそれに難色を示している。父の威厳を示す絶好の機会ではないか。俗物は前のめりに話を聞き、書店でアルバイトを始めたいという息子にも「あまり根を詰めすぎるなよ」と言う程度でしか反対しなかった。
榛央は父親のことは毛嫌いしていたが、性格は呪われたように受け継いでいた。小難しい芸術家気質もそうだ。父が母と言い争うときに愚にもつかぬ理屈でやり込めているのをよく目にしていた。心情的には母の側に立ったが、それでも育てば父親の劣化コピーになった。レジャー好きの父が温泉だけは避けている件も、漫画忌避という形で受け継がれている。祖父が温泉好き、芸者遊びが好きで、榛央の父はそれに嫌悪感があった。
その父に話をどう切り出せば賛成するかわかっていたし、それを戦略として弄したつもりでもいたが、認められると嬉しかった。まだこの家庭は壊れるべきじゃない、自分がバイトで支えなくともまだなんとかできるはずだ、と。
榛央の成績なら高卒認定試験は寝ていても合格できる。実際にもう教科書に書いてあることはすべて頭に入っており、高校はレクレーションのために通っているようなものだった。周りも似たりよったりで、少なくとも榛央の周囲に授業を聞くかどうかが成績にリンクするものはなかった。
当初は一学期が終わる前の自主退学を予定していたが、高卒認定試験の結果が出るまでは動けなくなった。試験は
11月初旬。結果はその一ヵ月後。退学からは後退したものの、決意がつけばすぐにでも担任に休学を伝えるつもりでいた。だが実行すれば無用な波風を立てる。朝食の終わったテーブルに肘を付き、もう焦る必要はないと考え直した。切符は手に入った。なしくずしにアルバイトの許可を取り付けたし、これで学費といくらかの生活費を捻出できる。家で勉強する時間はなくなるが、学校ですればいい。いままで忘れていたが、学校はそのためのものだ。
演目がキャラメルボックスに変わってから、榛央は演劇部に顔を出さなくなった。わかっているのはSFであるということだけ。キャラメルボックスは場面場面のクリップのいくつかしか観たことがなかった。通しで観ればおそらく好きになるだろうことは感じていたが、だけど好きになるにはもっと強くて明確な理由が欲しかった。
中学で読んだカズオ・イシグロに衝撃を受け、それから物語らしきものを書くようになった。それ以上に影響を受ける作品はほかにはないと信じている。キャラメルボックスで脚本を書く成井豊がどんなひとであろうと、その舞台がどんなに感動的であろうと、それはだれかが薦めたものでしかない。それも病の叔母が土手を散歩しながら手にとって渡した花ならまだ違う。己の生きた
17年のどこにも連続しない虚像は、手にとっても枯れるだけだとわかっていた。
成井豊はもう
60を超えている。それでいていまも清しく透明感のある、かつ、深い川底の闇まで見通すような繊細な筆を操る。演劇界のなかでは、平田オリザに並んでもっとも自分たちに寄り添っているひとのように思えた。それでも榛央にとっては、壊すべき権威であることは違いない。もちろん、壊すにしても、壊すもののことをよく知りはしなかったが、突き詰めて考えることは避けた。そも演劇をやりたいわけではない。知る必要もないし、よくよく考えれば壊す必要もない。要は、妬み、嫉みの類があるだけなのかもしれないが、それも認めたくなかった。
では果たして、榛央が権威のすべてを壊すべきと考えているかと言えばそうでもない。そこまでパンクな人間はカズオ・イシグロを読まない、いや、だからこそ読むのかもしれないが、傾倒したりはしない。榛央は第三文学の中心にあるのはサルトルだと主張していたし、同様に第四文学の中心をウェルズだと捉えている。むしろこれだけ聞けば権威主義そのものだ。
その榛央がじつを言うと、中学生の頃はSFにはあまり興味がなかった。『わたしを離さないで』に受けた衝撃も、そのSF的な内容よりは表現に拠るものと言える。そしてまた、仮に榛央が漫画やアニメに染まった中学生だったら、この小説にそれほどのショックは受けていなかった。『わたしを離さないで』という小説は、粗筋を追う限り漫画やアニメではありがちな話だった。貴之などはこれを、「大島弓子の絵で想像しながら読んだ」と評した。
件の小説の醍醐味は、キャシーという主人公の一人称で語られている点にある。その視点を通してのみ登場人物の仕草や表情がわかり、読者はそこから世界を知るしかない。世にネタバレは有りか無しかの論争があるが、それは飽くまでも粗筋を先に知るかどうかという視点だ。榛央はこの『わたしを離さないで』という小説をなんの前情報もなく、SFであるということすら知らず手に取り、おかげでキャシーの視点から、キャシーと同じ体験をするしかなかった。己の感覚と現実との乖離が違和としてわだかまり続けるなか、キャシーが枕を抱いて歌っている場面では、全身に鳥肌が立った。ちょうど世界の全容がぼんやりと浮かび上がってきたあたりだ。
漫画やアニメ、あるいはテレビドラマや映画であれば、登場人物の表情は主人公の目を通すことなく視聴者の目に届く。それは純粋な主人公の視点とは異なる。榛央はこの小説で得た完全なる一人称の体験で、文章の底知れぬ破壊力に触れ、幾度か友人にも語ったが、そのたびにアニメや漫画のどの作品と同じだと返されて辟易していた。そもアニメや漫画を第二文学と定義するに至ったのも、この体験がもとにある。
話題は少しずれるが、榛央のなかではカズオ・イシグロや村上春樹のSFと言われている一部の作品群は厳密にはSFとは違うジャンルに収めていた。SFと言えばアベンジャーズやスターウォーズなどの印象が強く、そちらを『SF』、それ以外のものはなにか違うジャンル、というぼんやりとした印象があったが、それらの狭義の『SF』に『空想科学』を感じることはなかった。その地平線を変えたのがウェルズだった。昨今のSFとの最大の違いは、主人公が、そしておそらく作者までもが、そこに芽生えた新しい視点のひとつひとつに驚愕していることだった。自ら仮定した世界に驚き、そこから現実の不確実性を問うた。その問は、後に続く作品で幾度も繰り返され、ミーム化した。『タイムマシーンで父親を殺すとどうなるか』という問には必ず、『時間が分岐する』という答が添えられる。だがそこにはもうセンス・オブ・ワンダーはない。読む側も往々にして、新しい知識で補いながら古いSFを読むが、そこにあるのは既知の事実だけ。もはやそれはSFではなく、その骸だ。SFに描かれているのは『科学』ではなく、『現実の不条理』ではなかったか。
「村上春樹にノーベル賞をって言ってるヤツ、いるじゃん?」
と尋ねたのは貴之だった。
「いるいる。でも、どうかな」
榛央は答えた。
「どうかなって思うよな」
榛央がカズオ・イシグロを貴之に薦めた一週間ほどあとのことだった。
「――でも、ありなんじゃないかと思うようになった」
一週間、とくになにも反応はなかったが、いずれかの作品を手に取った可能性が高い。その結果の発言なのだろう。いったい何を読んでその言葉を発したのか。
「は? 具体的にはどれが?」
「いや、どれがとかじゃなく。全体的に見て」
「は? 全体的って、どこ?」
「どこって。全体だっつーの」
榛央にとって、村上春樹はしつこい性描写をする下衆な年寄りであり、嫌悪感があった。そこにはどうしても父親が買って部屋に置きっぱなしにする青年漫画が重なった。そんなものが優れているわけがない。だから逆に言えば、大人になって『それ』が日常のルーチンになれば、その評価は変わるのかもしれない。更に逆に言えば、貴之もそれを真に評価できる立場じゃないはずだ。
「浅いよ、おまえは」
榛央も貴之もまだ、正確にものを計るツールを持たない。いや、だれかがそんなツールを持っているわけでもないし、だから多くのひとが何も言わない。言えばその物指がひとの目に晒される。その短い物指で計る村上春樹には、不快感があった。
「お互い様だ」
貴之は言い捨てた。
梅雨明けから間もない7月の半ば、貴之から不可思議なラインが届いた。
――貴之はバイクで事故を起こし、足を追って入院しています。
――代筆・
充季(妹)
足を追って入院など、犬じゃあるまいし。
――どんな具合ですか? 見舞いには行けますか?
そう折り返すと、怪我の具合を記した短い一文と病院名、部屋番号が送られてきた。いらすとやと呪術廻戦コラボの『こんにちは! 役立たずです』のスタンプが付いていたが、元ネタがわからず返答に困った。まぁ、怪我の具合は重くはないということだろうが、これで駆けつけてみたら集中治療室など言われたら、さすがは貴之の妹と感心するしかない。
――すぐに行きます。連絡ありがとう。
帰ってきたスタンプは同じく、『レディの気遣いナメんな』だった。買ったばかりのスタンプを使いたくてしょうがないのだろうと思ったが、貴之のアカウントだ。面白がってスタンプを探ってそこから選んでるのだ。
南武線西国立駅に近い総合病院とあり、定期の範囲外で面倒だと思ったが、地図で見るとなんのことはない立川まんがぱーくの隣だった。その位置にあってわざわざ西国立という駅名を出すのは代筆ならではだ。中学生である妹・充季の生活圏はまだ立川には達していないことを伺わせた。
それにしても、まんがぱーくの向こうにある大きな総合病院が見えてもいなかったとは。些細なきっかけから、いままで見えていなかったものが見えるようになる。そう。人生とは、まさに――ほんの刹那その言葉を胸に弄んで、そんなことは一般化するまでもなくあたりまえの話だと思い直した。通学路にある靴屋も眼科も、興味がなければ目に入らない。病院だから特別な意味があるわけでもない。ものを書いてひとに訴求するうちに、なんにでも物語を探す愚かな癖がついてしまっていた。
「噂をすれば」
病室に入ると、先に駆けつけていた見舞客が言った。
「何を噂してたんだ」
笑って返すと、
「村上春樹を超えると豪語してたって」
足を吊られた貴之が、笑いながら答えた。
「してねぇよ」
病室の見舞客は榛央の他に三人。みな貴之のクラスで、榛央には馴染みがなかった。顔はわかるが、名前が一致しない。ぎりぎり野球部の『送りバントの神様』川相はわかったが、それがあだ名なのか本名なのか、また本当に野球部員なのかなどはわからなかった。
しばらくはその三人の話を聞いていたが、ここにいない別の友人の愚痴が多かった。だれそれは小遣いを月に何万円もらって、バイクのガス代は別にもらっているだの、だれそれの告白をだれそれが先に嗅ぎつけて、向こうにバラしただの。
あまりにもくだらない話だったので、榛央はその場でおかしなポーズを取ったまま固まって見せた。くだらない。おまえたちの話は本当にくだらない。だけど俺はそのくだらない話をさせている呪いとこうやって戦っているんだ。と。
「なにやってんの」
ひとりが榛央のポーズに気がついて噴き出した。
「エンゼル体操」
頭に浮かんだ言葉をそのまま口から捨てた。
その吐き出したゴミを見て、また三人は笑ったが、そのときにはもう三人にとって居心地の良い空間はなくなっていた。
三人が夕焼けのドアを開けて帰ると、貴之は釣り逃した魚のことを話した。
「実際に炎上する高校生 YouTuber を書くとしたら、何を描けば良かったんだと思う?」
と、吊られた点滴の滴る薬液の雫を見ては、しみじみと続けた。
「選択肢は2つだと思うんだよ。榛央が言った通り。『炎上はよくないと思います』っていい子ぶって見せるか、『あいつらにも言い分はある』って援護して見せるか。中間はない。それ以外の視点もない。あったとしても、伝わらずに消える」
あるいは多くのものと同じように、沈黙を通すか。高校生当事者でありながら。
「いい子ぶるのはうんこだよ」
「俺もそう思うよ」
「援護してみせる気もしないし」
「うん」
「黙ってるのもうんこ」
「うんこし過ぎ」
「どっちも正解じゃないのに、なにか言えばそのどちらかになる。何も言わなかったら『無関心な高校生』。なんなんだそれ」
結局は、理解されたか、されなかったか、だ。どんなに複雑な心境を語り、受け取る側も様々な状況を鑑みてギリギリの判断で受け止めたとしても、それで『理解された』という結論を引き出してしまえば、それはただ『いい子ぶった』だけでしかない。世間が用意している椅子はふたつだ。そのどちらかに座るしかない。
「だったら牛乳をこぼしたほうがまだいい」
「だよな」
貴之は点滴の管を少し揺らしてみせた。
「詰んだかもしれない。俺」
「詰んだって、なにが」
「この問題を解決できずに先に進める気がしない」
足を吊られたプラスチックのカイゼル髭の男が言った。
果たしてどんな経緯で事故ったのか。相手は車だったのか、あるいは転倒か。なにも聞いていない。ヤケを起こしたのか、不注意だったのか。目の前にいるのはただ絶望して包帯に巻かれた親友だ。
「蛹みてぇだな」
「なんだそれ」
榛央はまたベッドの横でおかしなポーズを取っていた。親友の羽化への祈りを込めた、人類のなかで榛央が初めて取るであろうポーズを。
「本を読みたい」
「本」
「なんでもいい。おまえのおすすめ」
そう口に出す貴之の姿を見て、改めて榛央は思った。
さすがは貴之の妹。
❡
ちょうどその頃、国分寺の駅ビルにある大手の書店でアルバイトを始めていた。
国分寺を選んだのはクラスメイトの生活圏から少し外れると思ったからだが、実際には国分寺から通う生徒も少なくはなかった。駅前には丁寧なカバー掛けで知られた小さな書店があり、憧れていたが、高校生という点がネックになり断られた。そこでカバーをかけ、荷受け、検品、仕分け、品出し、売れていない本にはPOPを書いてレジに立つ姿を夢見ていたが、バイト先に決まったのはその店を潰しかねない大型店だった。本の流通を少し齧っていると、あまり良い評判は聞こえてこない店だったが、噂は噂でしかない。レジに立ち、POSの扱いをレクチャーされ、荷受け、検品、仕分け、品出しと、憧れた書店でこなすはずだった仕事を覚えたが、POPを書くのはマネージャーだと教えられた。残念。正直、POPが書きたくて選んだ仕事だった。きっかけは――その昔、『ゾッキ本』を主人公にした物語を読んだことだった。小学生の頃だ。そのときに憧れたのが書店のPOP書きだった。
ゾッキ本というのは、書店の店頭で売れ残り、返却され、
天か
地にマジックで線を引かれて叩き売られる新古本のことだ。物語はその本がまだ形になるまえ、小説家の耳元にインスピレーションとして囁かれるところから始まった。小説家は編集者にアイデアを話し、編集長がそれを聞いて、決済が降りると小説家の筆先からスルスルと文字として生み出される。やがて本となって出版され、箱詰めされて、仕分けされ、そのあいだ本は、平積みにされて多くの客の目に触れることを夢に見るが、そのまま棚に立てられ、売れ残り、何週間も売れ残り、やがてPOPを書かれてワゴンに並んだ。POPには意図せぬ謳い文句が書かれ、それでもだれかが買ってくれるならと待ち続け、待ち続け、待ち続けて、それでも売れることはなく、やがて返本されて、ケシタに線を引かれて神田の古本屋に買われていく物語だった。少年城戸榛央にしてみればまさかの体験――まさか本を主人公にした話で泣くとは思っていなかった。せめてその本が意図したPOPを書いてやりたい。少年はそう思った。
榛央は本の陳列、整列をしながら貴之に差し入れる本を選んだ。
店員が立ち読みするわけにも行かず、勢い表紙とタイトルで選ぶしかなかったが、できるだけ売れ残りそうなものを見繕った。何冊かセレクトし、最後にはPOSシステムの情報も見て取次に返却する寸前のものを選んで社販価格で購入、自分でカバーをかけた。ハサミで切り込みを入れて丁寧に掛ける、幼い頃に憧れたスタイルだった。
その日は残業して、大量の ONE PIECE をビニールに包んだ。明日はこれが新刊の棚を占め、レジ横にも置かれる。本を買うひと、読むひとがたくさんいるのは、本好きとしては嬉しかったが、その一方ではそれが本の価値を毀損しているような気もした。本がすべてこの
10倍の値段で、ハードカバーで、だれもがそれを
10回ずつ読み、どの作家もいまの
10分の1しか書かなければ本の価値はもっと高かった。近頃では電子出版も、本の価値を破壊している。
夜の
11時。父が帰宅する。
お帰りなさいの声に続いて、キッチンにパタパタと足音が走る。
父が働くマスコミ関係の仕事で、この時間の帰宅は早い方だった。遅い日は2時3時になる。妹も受験生だったが、もう寝静まる時間だ。そんな時間でもやはり、父が帰るとキッチンにはパタパタと足音が走った。
貴之のために買った本を狭めに開いて読むと、足跡を残さないように忍び込んだ空間で拾い集める文字は、特別なときめきに彩られた。
――選択肢は2つだと思うんだよ
『炎上はよくないと思います』っていい子ぶって見せるか
『あいつらにも言い分はある』って援護して見せるか――
出会いは偶然だ。己に即さぬPOPでも大量のひとの目に触れれば、だれかに届く。POPを書くか、書かないか。
10人が手に取り、ページを開いてくれたら、だれかが買ってくれるかもしれない。売れるためにはもっと奇を衒えばいい。そう考えた挙げ句のPOPも世に少なくない。
榛央少年はその本を読むまで、ゾッキ本の存在を知らなかった。
おそらく多くのものが知らない。
どんな思いでワゴンに並び、返品の箱に入り、版元の倉庫で何を思い、古書店に投げ売られる日の空が、どんな色をしていたのか。
だれも知らない、そんなことは。
だから、タカユキ。これが答えだ。
俺が選んだのは、三日後にケシタに線を引かれる、この本だ。
用意した本をカバンに入れた朝、貴之からの最後のラインが届いた。
――たったいま、旅立ちました。
代筆、充季、妹。
スタンプのない、1行だけのラインだった。
第五文学 羽化
改築を控えた図書室の本はもう半分が仮の図書室へと移されていた。
太陽の上らぬ
40日の夏を終えた九月長月、扇風機が回る冷房の効かない図書室。その隅の陽の届かぬ一番暗い角にタカユキは座り込んでいた。
来るは、十月神無月。
出雲詣でを終えた十一月霜月には高卒検定の試験。
師走、十二月に榛央の高校生生活は終わる。
「第五文学は象徴。肉体を失う」
タカユキは笑いながら語った。
肉体たる現実に束縛されるのは第四文学まで。そこまでは還元論的に現実とリンクするが、それを失う。現実は作家の胸に表象として現れるが、その先に意味を持たない。現実を切り離してようやくここに至る。
「本当に学校辞めるの?」
タカユキが問いかける。
「わからない。おまえのせいで。何が正解かさっぱりわからなくなった」
「俺のせいかよ」
「彼女はお見舞いに来たの?」
「彼女って?」
「コーラス部の」
「知ってたんだ」
「見たらわかるよ。で? 会ったの?」
「いや」
「やるせねえな」
「あのさあ」
「ん」
「高卒試験とかぶって悪いんだけど、演劇部見てやってくれない?」
「俺が?」
高卒試験は今ここでと言われても通る自信があった。
「たのむよ」
だけど演劇部の仕切りは自信がない。
「いや、でも、演劇はよくわかんねぇし」
「城戸榛央に拍手を!」
「やめろよ」
「地区大会、出してやりたい。諦めさせたくない」
「でもさあ……」
「キャラメルボックス、ちゃんと見てくれよ」
「でも……」
「俺が勧めてるんだ。それで見る理由になるだろう?」
その言葉で榛央は泣いた。
あれから何度図書室で泣いたかわからない。
その日の放課後、ずっと避けていた講堂へ足を向けると、相変わらずの剣道部の剣戟とコーラス部のクワイア。演劇部はまだ静かに素読みを行っている頃。榛央はコーラス部に足を向けて、石崎
聖奈を探し、本を渡した。
「あいつには説明無しで渡すつもりだったけど」
と断り、本を選んだ理由、ゾッキ本の物語のこと、それから病室で貴之に語ったことなどを聖奈に話した。貴之には十年か二十年後に話すつもりだった。彼女はまだ二年だ。今年のバレンタインからの短い付き合い。もしかしたら負担になるかもしれないとも思ったが、避けるのも不誠実かと思った。
それから演劇部へ。もらいそこねていた台本を受け取りに行った。
「お久しぶりです。もう大丈夫ですか?」
コーラス部に顔を出したときは気が付かなかったが、気を使われているのは榛央のほうだった。
「うん。大丈夫。それより俺にも台本が欲しい」
部長、山下
一成。
「ようやく読んでくれる気になったんですね」
「うん。あいつに頼まれたから」
「あいつって、部長?」
「部長はおまえだろう」
「そうですけど」
「さっき図書室で会った。改築されるまではいると思うから、会ってくるといいよ」
「ええ。あとでぜひ」
手渡された台本にはカタカナで『タ』の字が記されていた。表紙はカールし、本文には無数の付箋とメモが残る。
いつの間にか小説を読むときに、これは第何文学だろうと考えるようになっていた。
話題になった小説、新しく手にした古典を読んで、あれとこれとは第何文学だったと貴之に話すのが楽しみになる一方、それが自分の理解を狭くしていることにも気がついていた。
ひとのいない図書室。キャラメルボックスの渡された台本を読んでいると、タカユキが隣に腰をおろした。
「もう第何文学とか、そういうのはやめる」
気配を察して、榛央が口にした。
「いや、無理だね。この呪いは一生ついてまわるんだ。第七文学までちゃんと理解しないと抜けられない呪いだ」
その口調は少し芝居がかっていた。
「第五でやめときゃ良かった」
「あと二段階ある」
「おまえは知ってるの? あと二段」
第五文学の話をしたとき、貴之はアルチュール・ランボーの『酔ひどれ船』を例に挙げた。未読だった榛央はよせばよいものを中原中也訳で読み、最初はほとんど内容を解さなかった。そう話すとすぐに貴之がネットで検索した新しい訳を示し、ようやくなるほどと思った。その後、堀口大學訳の詩集を買って読むと、中也訳よりも遥かに読みやすく、『裏切られた心臓』という詩に『酔ひどれ船』と同じ世間への幻滅を感じ、これが榛央のなかでランボーのカラーになった。
それが第五文学。
第五文学で肉体を失う。
それが貴之の主張だった。
ならば第六、第七はどう進化すれば行きつけるというんだ。
「知る、というプロセスでは知れないところにあるかもしれない」
「めんどくせぇ。そういうこと言い出すおまえがめんどくせぇ」
「あそうだ」
「なに?」
「本。あいつに渡してくれてありがとう」
「ああ、うん。どうしてわかった?」
「昨日、来てた」
「ここに?」
「うん」
「進展はあった?」
「ないよ。時間はもう止まってしまった」
「そうか。でも、止まったんじゃないよ。おまえが止めたんだよ。俺も。もしかしたら俺も悪かったのかもしれんけど」
「だよなぁ。だから責任とって舞台はやってもらわないと」
「そこにつながりますか」
「ああ。うん。まあ、ありがとう。あと、ゾッキ本の話も」
「彼女に聞いた?」
「うん」
「あれ、どこかで読んだ気がするんだけど、覚えてなくて」
「じゃあ、調べとくよ」
世界は小さくなったのかもしれない。図書室と講堂、運動場、花壇。ほかにもいろんなものがあった。それがもう、図書室の外になにかがある気がしない。花壇脇にいつも三羽いた雀も二羽になった。
「大丈夫?」
うなだれる榛央に、圭吾が聞いた。
「ああ。みんなに聞かれる。そっちは?」
「相変わらず」
「でも、部活もうやってないんだろう?」
「別に剣道だけやってるわけじゃない」
「そうか」
花壇の冷たいモルタルのうえ、榛央は圭吾の膝にしなだれた。
「タカユキに薦められた台本、読んだよ」
「どうだった?」
「あいつが出てた」
「キャラメルボックスって、どんな劇団なの?」
「そういう劇団」
圭吾に膝枕して、膝の間から雀を眺めた。飛んで、また戻ってくる雀は、はたして同じ雀なのか、別の雀なのか。上手に捌けて、また上手から戻る。タカユキがその雀に声を当てる。
――尼寺へ行け! 尼寺へ!
「彼女作れよ、おまえ」
「いいよ。めんどくせぇ」
――飲むでない、ガートルード!
「面倒ってなにが」
「親父と一緒なんだよ、俺。性格が」
「で?」
「彼女なんか出来たら、同じことしてしまう」
母親へのDVまがいの恫喝。嘲り。その他。あれも、これも。
「そこまでわかってんだったらなんとかしろよ」
「わかってないな、おまえは。呪いを甘く見てる」
――雀一羽落ちるにも、天の理りが働いている――
「2~3年もしたら変わるよ」
「甘いな」
だけどタカユキ、第三文学では物語など否定したじゃないか。
それなのにどうして、僕たちは因果に呪われたままなのか。
「なんで子どもを生む女のほうが体が小さくて、男のガタイはデカいかわかるか?」
「そりゃあ、あれだろ。男は狩りに出たり、家族を守るために戦ったりするから」
ほら。人間は思考なんかしていない、カマキリの腹のなかのハリガネムシのように、呪いが僕たちの思考を奪っている。
「女だってそうだよ。狩りにも出てたし、家族も守った」
「じゃあなんでだよ」
「強いオスが、逃げられない弱いメスを奪いあって、選抜したんだよ。だから子を残しうる最も弱いメスと、メスから生まれうる最大の体格のオスが生き残った」
「はじめて聞いた」
「それを聞いてから、女子をちゃんと見れない」
「なんで」
「俺たちが呪いをかけた姿なんだ。可憐で、美しく、そして弱くあれって」
「思い込みだよ、そういうのは」
「違う。いや、そうかもしれない。その呪われた肉体の物語が第四までの文学。第五文学はそれを超越するんだと」
「貴之が言ってたのか?」
「そう。俺のアタマだと第四がせいぜいだった。でも、あいつはその先にいた」
榛央はまた涙をこぼし始めた。
「みんなこっち見るの避けてんだけど」
圭吾は低い声でぼやいた。
「だろう?」
「だろうってなんだよ」
「いいから。頭撫でろよ」
膝の上で泣きながら言うので、言われるがままに圭吾は頭を撫でた。
「これでよろしいか」
よろしいかと問われても、良い悪いではない。ただこの虚ろな時間を埋め合わせたいだけ。
「にゃあ」
榛央は細い声で洩らした。
立ち稽古の初日。部室に入ると、そこに和んでいた空気は罅隙を生じ、砕けた。
榛央はこの瞬間がたまらなく嫌だった。
同じ光景は去年から目にしていた。放っておけばいつまでも稽古など始まらず、5時半までと決められた部活時間の残り
10分を切った頃にようやく稽古が始まる。上級生がそこにいなければ、「イメトレ終了」などと笑い合って背を伸ばし散開となるが、榛央が部室に入ると部員は何も言わず、黙って腰を上げた。
別に稽古など、したくなければしなければいい。それで恥をかこうが知ったことではない。漫画やドラマに出てくる鬼コーチをやってみたところで、必ずしも結果が伴うわけじゃない。それでも、タカユキに任された舞台だ。
「来週、通しでやる」
演劇経験のない榛央が細かい指示を出せるはずもない。
「来週の何曜日ですか?」
「月曜」
「いや、無理でしょ」
「いつならできる?」
「いつならって……」
「じゃあ、来週半分。月曜までに」
「月曜までって」
「躓いたらあとはアドリブでいい」
「でも、そういう作品じゃ……」
――だったらちゃんとやれよ。
と、言いたいのはやまやまだった。だがそれで自分が困るわけでもない。それにきっと、どこの高校生も似たようなものだ。部長の山下は恐縮しながら、「できるところまでやろう」と部員に声をかけていたが、当の部員たちは部外者に指図されていい気はしなかった。
「みんなそうだ」
山下に向かって、半笑いの口元からこぼした。
「自分へ向けるべき憤りを他人に向ける」
山下もまた口と眉とを複雑に曲げた難易度の高い笑みを返した。
「自分の気持ちくらい、自分でなんとかできるようになれよ。舞台なんかそのずっと先だろ」
ひとはみな、自分が隷属できる人間を探している、というようなことを聞いたことがある。はたしてだれの言葉だったかは忘れた。ひとがひとを値踏みするのは、相手の能力を畏れるからではない。隙あらば犬に成り下がり、煩わしい自由から逃れようとしている。雑談をやめて立ち上がったときのあの目で、主人を探しているのだ。
バイトは一ヶ月以上休んでいた。マネージャーももうあてにはしていないし、今更再開する気もない。バイトを始めた当初残業もいくつかあり、それで疲れたか嫌になったかしたのだろう――父親はそう言って、「それもまた経験のうちだ」と気にも留めなかった。母親は貴之の件を聞き知ってはいたが、その生徒の名前も知らなかったし、まさか息子の親友だなどとは思いもしなかった。
「良い経験も嫌な経験もして、また日常に戻る。そういうもんだよ、学生のうちは」
父が語ったその言葉のうちひとつかふたつが、榛央の部屋に届いた。その間も榛央は、貴之を見舞いに行ったとき、もしかしたらなにかの兆候があったかもしれないと振り返っていた。それを見つけ、すぐに指摘していたら、もしや、と。あるいはあのときベッドの下を覗いたら血が滴り落ちていたかもしれない。ベッドに吊られたカルテを見ればそこにヒントがあったかもしれない。
第三文学でそれは否定したはずだった。ロカンタンが嘔吐を感じるほどに、この世界には意味がない。カルテを見ても、ベッドの下を見ても、何もないのが現実だ。
一方、象徴主義では物語におけるすべての要素が現実の何かを象徴していると言われる。それが第五文学。たとえば見舞いに行った際に、ベッドから滴る血を見逃したというエピソードがあったとしても、そのままの意味だとは限らない。それは「聞き逃した言葉」を現しているかもしれないし、あるいは「主人公の心情」を語ったのかもしれない。
たとえばこんな物語があったとする。
――友人が事故で入院し、主人公が見舞いに行く。主人公は点滴の輸液が止まっているのを目にするが何も言わない。
それは決して文言通りの現実を語っているとは限らない。ただ主人公の友人に対する思い――おそらくは内心での距離感や無関心――を象徴しているのだ。
それはきっと素晴らしい作品に違いない。主人公の機微をよく表していると評価されるだろう。だけど、その物語を読んだものは呪われる。そのエピソードを自分に重ね合わせ、あのとき異変に気がついていれば、体調の変化を感じ取っていればと、とりとめのない妄想で自分を責める。それをどうすれば拭うことができるだろう。タカユキが点滴の管を揺らしたときの不安が、何度も繰り返し胸を過った。
たまに父が早く帰るときも、食事をともにすることはなかった。なにかと理由をつけてずらして、顔を合わせないようにした。いつ壊れるかもしれないガラスの家のなかで、自分の本音を隠すため、受ける気もない共通テストの願書を出した。
雨の日の講堂は窓を閉ざされ、いくつかの運動部のシェルターと化した。昼日中から人工の灯りに浮かんだひとの姿はいくつかの薄い影を曳いて、シューズの擦れる音、ボールの跳ねる音と、聞き慣れぬ掛け声とが、雨音に濡れた壁を叩いては床へと落ちた。わずか数十メートル立法の空間を除いて、町は雨が覆った。前線が迫っていた。雨足が強まるなか、早めの帰宅を促されたが遅きに失し、講堂は棟の突端に雷を受け漂い、部活の喧騒はやがて、船倉のざわめきに変わった。
コーラス部の鳩が方舟を飛び立ち、やがてオリーブの枝をくわえて戻った。
「乾いた大地を見つけた」
その情報は、演劇部部長山下にも伝えられ、コーラス部と演劇部は旧図書室へと場所を移った。
横殴りの雨の渡り廊下。
人影のない暗い洞窟。
佇む扉を開けると、図書室はもう空になった書架をいくつか残すほかはがらんとしていた。コーラス部員はめいめいに声を発し、返す木霊に耳を澄ました。これはもう人間の生態ではない。虫を捕るコウモリか、密林で呼び合う獣。天井をながめ、ポジションを変えてあちこちの壁に声を飛ばして、演劇部もそれを真似て拙い喉で声を響かせた。
女子
14名、男子7名、三年の榛央を覗いて
20人が車座に座った。
コーラス部も演劇部も女子が多く、男子は小さく固まって座った。それぞれ意中の子はいるかもしれないと思うと、それも榛央には微笑ましかった。
「先輩、ここ空いてますよ」
と、コーラス部女子に隣を促されたが、そこが女子の真ん中で躊躇った。
「だれの隣がいいとかありますか?」「あるいは真ん中」と笑い合う女子部員。男子の方を見ると、榛央がだれの隣を選ぶかを見守るようにスクラムを組んでいる。そのなかにあって女子生徒のひとりは目を伏せ、隣の子がそこに座るようにしきりに手招きする。大きく手を振り、榛央の手を掴みそうな勢いで身を乗り出して。窓に雷光が翻った。
気を取られていると、コーラス部のひとりが、短く通る
884ヘルツの声を当てた。
わずか
0.1秒の差もなく、雷鳴が轟く。
ひゅう、と声が上がった。
雷光、再び。
雷鳴と同時に、幾人かのコーラスが鳴り響く。
ひとの喉が紡いだ音色が、また雷神を捉えた。
また。そしてまた。雷光が閃くたびに図書室の壁にコーラスが響き渡った。
雷鳴が消えたあとも柔らかいコーラスが部屋を満たし、光とともにまた声が迎える。
コーラス部の声は、雷鳴と踊った。
そこでは雨の音でさえ、柔らかな色の浮かぶ音色に変わった。
そのなかで演劇部は借りてきた猫――と、榛央は少し肩をすかされた思いだったが、部長山下が立ち上がり、車座の中心に立ち、目に見えぬ風船を膨らまし始めた。
雷光が翻くとまた、コーラスが湧き上がる。続く雷鳴を受けて、山下の顔のすぐ前で風船が破裂した。
山下は驚き、胸を押さえて見せ、また風船を膨らませる。それを伊藤、谷口、岡野に順に渡すとまた雷光が閃く。急いで4つ目の風船を膨らませていると雷鳴、4つの風船が一斉に割れた。
すぐにこんどは巨大な風船を膨らませ始める。
「いや、でかいっす部長!」「そのへんにしておかないと!」「ヤバいっしょ、それ!」
その巨大な風船を伊藤に渡すと、みな耳を覆った。
「なんで俺に
!?」
雷光、コーラスが高鳴る。雷鳴とともに風船は破裂、山下と伊藤を吹き飛ばした。
その動きに紛れてコーラス部のひとりが榛央の手を取って、輪のなかに引き入れた。
榛央はなすがまま、目を伏せた子――おそらく榛央に思いを寄せているだろうことはもう十分に想像できたその子の隣に座らされそうになったが、刹那、立ち止まり踵を返し、石崎聖奈に駆け寄った。タカユキが付き合っていた子。コーラス部員が騒然とする。せっかくのお膳立てが目の前で崩れる。あろうことか小さな恋が壊れる場面を目撃してしまうのか。コーラスが途切れた雨のざわめきのなか、榛央は戸惑う聖奈と隣の女子に声をかけ、その間にひとりぶんのスペースを作った。そして目配せした。
そこはタカユキの席だ。
そして改めて手を引かれて示された自分の場所に戻った。榛央が腰をおろすと、隣の子は手のひらで口元を覆って固くなったまま、頭を下げる素振りを見せた。
聖奈の隣には、タカユキが腰をおろす。山下はそのタカユキの席のまえで一礼、風船を受け取る。部員たちもタカユキに駆け寄って手に手に風船を受け取った。
雷が閃く。
またコーラスが響き渡る。
刹那の間をおいてその雷鳴を受けると、部員たちの手の風船は柔らかく弾けた。
スローモーションで紙吹雪が舞う。
みなその紙吹雪に手を伸ばした。
榛央が手を伸ばすと、隣に座っていた子もゆっくりと手を伸ばした。
触れ合った肩が、互いの体温を伝えた。
図書室の老人が現れたのはそのときだった。
初めて目にする全国の高校生に呪いをかけた老人の姿だった。
老人は入り口から入ってくると、軽く会釈し、「コーラス部?」と尋ねた。
「コーラス部と演劇部、合同です」
「あ、そう。電車はちゃんと動いてるみたいだから、いまのうち出たほうがいいよ」
見るともう窓を打つ雨はない。雷も雨を追うように遠ざかりつつあった。
「いいね、若い人は。あったよ、俺も。そういう時分が」
生徒たちは顔を見合わせる。
小さく閃いた雷光にあわせて、小さなコーラスを奏でると、榛央に寄せた肩からもコーラスの声が響いた。
「思い出をさぁ。なんかこうやって、リアルタイムで見てるっちゅうか」
時計を見る。もう正門は閉まったかもしれない。
「まぁ、わからんか」
バスの時間があえば駅までは
10分。あわなければ歩いて
30分。
「もうここ閉めるんで。ちょっと各々電車確認して、あー。まあ、動いとるはずだけど、ちょっと見て。電車。閉めるんで。ここ」
榛央の目に、笑いながら――真っ赤に目を腫らして立ち上がる聖奈の姿が映った。
第六文学 追憶
十月、神無月。古い神々が出雲へと詣でる頃、黒猫とカボチャとが町を席巻する。その頃になるともうタカユキのことを思い出すのも演劇部員と、親しかったクラスメイトくらい。その演劇部員も地区大会でそれどころではない。そしてそれでいて、相変わらずだらけていた。
ただ、個人の技量は高かった。
たとえば、去年の公演でテグスを首にかけたことが問題視されたが、実はテグスなど使っていなかった。首にかけられた伊藤も、それを引いていたふたりの生徒もすべて演技だった。保護者から問い合わせがあったと、後に呼び出されて校長に聴取されたときも、俄には信じてもらえず、その場でそこだけ実演して見せるしかなかった。脇のふたりが伊藤の首に空想のテグスを掛けて引くと、伊藤の顔は瞬時に紅潮した。
この脚本はそもそも事前に提出し、プログラムにもフェイクだと記していたが、それでも観客は呑まれていった。あるものは、フェイクと書いてあることがフェイクではないかとさえ思った。
そのときの心境をタカユキに訊いたことがあった。
「あのとき、観客が拍手していたらどうなってたと思う?」と。
「怖かった」と、タカユキは答えた。
「それはつまり――」頭のなかに情景を再現しながら、「山下が伊藤を刺したかもしれない、ってこと?」と、榛央は質した。
だけどその答えは予想を裏切った。
「そうじゃない。あの舞台を支配していたのは伊藤だよ。だれも伊藤の目を見れなかった。テグスを引いてるふたりがいつ手を離すか、そうなるとどうなるか山下は怯えてた」
榛央もあの舞台に得体のしれぬ恐怖は感じていたが、言葉にされてなるほどと思った。しかしそう聞いても一方では、しょせん舞台での話だろう? という感覚もあった。本当にそこまで思い詰めるものか。それともこの芝居じみた追想も舞台の一部なのか。
「それに、山下の怒りは俺に向いてた。観客が煽ってたら、刺されたのは俺だったと思う」
榛央の脚本ではあったが、舞台に立つ彼らの気持ちがそれを追い越しているのはわかった。もちろんそこに完全に共感できるわけではないが、いまの彼らの稽古を目の当たりにするにつれ、自分だけ突き放された感覚は大きくなっていった。榛央はもはや口出しすることも躊躇われ、いつしかただロッカーに収められたガラスの仮面を読むだけのひとになっていた。そのうち部員たちも榛央がいても気にしなくなり、おしゃべりばかりして、ほとんど稽古のないままに解散する日もあった。それでも毎週月曜に(なぜか週の終わりではなく、はじめに設定してしまったわけだが)動きを合わせると着々と進歩しているのがわかった。
演劇はそもそも覚えたセリフを順に言う場ではない。その役になり、その場の空気に身を任せるものだ。完璧に覚えたセリフを、そこで初めて聞いたかのように驚き、戸惑い、いま胸に浮かんだように発する。部員をよく見れば、話し込んでいるものの他に、2時間ずっと頭のなかにイメージを整えているものがいたし、不意に立ち上がり位置取りを確かめるものもいた。その必要な時間を経て、十月の半ばからは加速度がついたように仕上がっていった。そして常に、完璧であることを拒絶した。ある意味彼ら、彼女らは、素人の高校生であることを目指していた。
その十月の半ばだった。
タカユキの妹、充季が小さめのダンボール箱を持って部室を訪ねた。
中身はタカユキが買い集めた舞台のDVDとブルーレイ。何冊かの本。
「遅くなりましたけど、一通り見ておきたかったので」と、充季は断って、山下の手に渡した。
パッケージで買ったものもあれば、どこかのサブスクから落としたものもあった。
「南家さん、ピーター・ブルックの真夏の夜の夢を観たがってたんですけど、あるかな?」と、伊藤が尋ねる。妹は首を捻る。「いや、入手したならまっさきに報告してるはずだから」と、山下が答えた。
榛央は後に調べ、それが日本では
73年に公開された伝説的な舞台だと知った。
実際には、タカユキとのいままでの会話のなかで何度か出た言葉だったが、数多聞くタイトルのなかで、それが特段のものだとは思わなかった。それを山下に伝えると、隣で聞いていた部員が「死守せよ、だが軽やかに手放せ」と口にした。それがピーター・ブルックそのひとの言葉らしい。
城戸榛央が第六文学、『何もない空間』に到達した瞬間だった。
「おまえいくら小遣いもらってたんだよ」
昼休み、伽藍堂の図書室で榛央は尋ねた。
「村田より1万円安い」
胸を張ってタカユキが答えた。
「あいつ、月に4万だぞ」
つまりタカユキは3万。
「しかも、バイクのガス代別でな」
月に3万ももらっていれば本もDVDも好きに買えるわけだ。
「俺もそのくらい欲しいわ」
「親父が偏屈で、絶対バイトはするなって」
「そのぶん金は出すって?」
「そう。『俺ならおまえの5倍稼げるが、おまえは俺の5倍学べる。バイトは非効率だ』って」
まあ、合理的な話だ。
「金を出す親、最高だな」
「なんか、雑魚のセリフになってんぞ」
「いい。雑魚でいい。俺がそれもらえないかな」
「頼んでみたら」
「おまえから言ってくれよ」
「まあ、ここに連れてきてくれたら」
「ちなみに5倍って、時給5千円?」
「そのくらいかな。それでも年収にしたら……一千万くらい?」
「年間で二百時間? まあ、そんくらいか」
「親父が若い頃はそんなもんじゃなかったらしいよ」
「ああ。昔はそうだったってな」
「その代わり駐車場代が7万とかしたって」
「ははっ。ご冗談を」
「ビデオはもう観た?」
「今週末見る予定。オススメは?」
「野田地図かな」
「ピーター・ブルックじゃなく?」
「おおっ。なんか覚えたね」
「からかい禁止で」
「ピーター・ブルックだったら野田秀樹も影響受けてるから、観るといいよ」
「わかった。それから観る」
「wowowで録画したやつだから、青いディスクから探して。『桜の森の満開の下』ってやつ」
「坂口安吾の?」
「そう。でもそっち読んでないからわからん。別物かもしれん」
「ラベルは貼って無いの?」
「今週末貼る予定」
「遅っ」
「大学行ったら、演劇部の倉庫とかにこそっとビデオがあるかもしれないと思ってたんだけどね。ピーター・ブルック」
「残念」
「だから、おまえがやれよ。真夏の夜の夢」
「第六文学デビューだ」
「やめるんじゃなかったのかよ、第何文学って」
「やめられないよ。呪いだから」
「だな」
「改築されるまではいるんだろう?」
「そのつもり」
「そのあとは?」
「アレクサンドリア図書館」
まんがぱーく隣のビルで旅立ち、アレクサンドリアへ。
タカユキに似つかわしい旅路だ。
金曜、長い時計の針がようやく太陽を傾かせる頃、充季が持ち込んだダンボール箱からディスク4枚と書籍を2冊カバンに入れた。
わずか一駅だけの中央線。パッと目についた『演劇とその分身』と第された赤い表紙の本を開いて読み始めたが、内容が複雑でほとんど頭に入らなかった。おそらく文章の構造からしておかしい。助詞助動詞副詞を分解、正解に近かろうテキストに適宜並べ替え、先に進んでは戻りと紐解いてみたが、やはり溢れる単語があった。どこぞの狂信者が己を崇拝する信徒に向けて書いたような回りくどい文章。タカユキはまんまとこれに騙されたのだとすら思ったが、数ページも読み進めるうちに不思議と頭に入るようになった。聖徳太子が十人を相手に言葉を合成して返しているような、その文章が。新しい言語を学びながら同時に読み解く感覚に、世界が塗り替えられていった。そして次のページを開くと、アレクサンドリア図書館への言及があった。パピルスで収められた本にも触れられている。
そうか。ここが原点なのかも知れない。
榛央は嬉しくなった。
圭吾にタカユキを紹介された日のことが思い出された。卓球部の新人が体をくねらせた変なギャグをしている脇をすりぬけて講堂に入った。場違いなその場所に疎外感を感じながら、窓から射す陽の光を見上げた。あのときタカユキはもう、この本を読んでいたのだろうか。
日曜日を超え、もう地区大会までそう遠くない月曜。
通し稽古。舞台には箱がいくつか置かれ、その箱が椅子にもなったし、ふたつ重ねて机にもなった。
いつもの時間を少しはみだし、バスの時間を逃し、山下とふたりで駅まで歩きながら、野田地図を2作、それと高校演劇を題材にした映画を1本観たことを話した。
「どうでした?」
「ピーター・ブルック観たくなった」
「ああ。わかります」
『桜の森の満開の下』は役者が舞台上にリボンを張り、それが風になることもあれば、絵画のフレームになることもあった。テレビで観ているせいか、その匂いの全てまではわからなかったが、舞台という表現が小説とも映画とも違うのだということはわかった。
「箱を使うの、舞台セット用意する金がないからかと思った」
「それもありますよ。箱もたしか、どこかでもらってきたやつですし」
「アントナン・アルトーも読んだ」
「すごい。よく読めましたね」
「そういう扱いなんだ」
「最初の1文だけで5回くらい読み直しました」
「俺も」
「わかりました?」
「諦めた」
「諦めたけど、読んだんだ」
「そう。意味は諦めたけど、読むことは諦めなかった」
「それって、何を読んだんですか?」
「意味よりも大切なこと」
「ああ。なるほど。わかります。僕もまたチャレンジしようかな」
ノリで返した言葉に「わかります」と言われ、やや戸惑った。
「映画はどっち観ました? 女子校? 男子校?」
映画のDVDは2本あった。ひとつは女子校演劇部の話。こちらはアイドルものの映画にも見えるが真面目な話。もうひとつは男子高校演劇部。コメディ。
「男子校のほう」
「ああ。あれ、すごいですよね」
この感覚もまた分からなかった。
平田オリザ原作の女子校ものの映画の評価が高いのは知っていたが、男子校のほうはどう観ても色物で、倫理的に問題がある箇所も散見された。舞台経験ほぼゼロの部員たちが演劇の地区大会に出るコメディで、ラストで演じられる舞台も鉄棒にぶら下がりながらの朗読劇、内容的に目を引くものはなかった。
「ほかの高校の演劇部の様子がちらっと見れるけど、凄いよね」
あたりさわりない答えを選んだ。
山下は「あれ、ショックでかいっすねー」と、合いの手を入れ、すぐに「大会で鉄棒にぶら下がってるじゃないですか」と話題を切り替えた。
そっちか。
「あれぜったい、ピーター・ブルック意識してるんですよ」
しまった、と思った。後輩相手だと少しは見栄を張りたいところだが、さっきから無知を晒してばかりだ。ピーター・ブルックを観たくなったと言ったばかりなのに、目のまえを通り過ぎたそれに気が付かなかった。何よりも、そんな有様で第何文学などと語っていた己が恥ずかしかった。
「建て付けはコメディだけど、即興で、ハプニングもあって、観客も笑ったりハラハラして観てるんですよ。あの場であれをやらせるってのは、ただの色物じゃないですね」
山下が言葉を区切る。だけどまだ榛央には完全には飲み込めていない。色物ではないと言われても、果たしてどこを評価すれば良いものか。
「鉄棒にぶら下がってる姿見て、やめてくれって思いましたもん」
「やめてくれ?」
「高校演劇って
30分から
60分じゃないですか。てことは、
30分ぶら下がってるんですよ、彼ら。だれがどのタイミングで落ちるかわからない、落ちてからは地獄のアドリブ。見ていてすごい緊張しました。自分だったら何を言うだろうって」
視点が違っていた。もしかしたらこの山下という男、この映画だけでなく、どんな映画を観ても自分を重ね合わせて観ているのかもしれない。あるいは、演劇部員は皆こうなのか?
「客席は笑ってたよね」
「それが救いです。演劇やってるひとは心臓バックバクですよ」
「でも、きみらも凄いよ。去年の舞台、すごかった」
「ありがとうございます」
榛央には少し気がかりなことがあった。
「ちょっと聞いていい?」
「え? なんですか? ドキドキしますね」
去年の公演に関する、タカユキの意見のことを、直接訊いてみたかった。
「あのときさあ、もし観客が拍手してたら、どうした?」
そう言った途端、山下の表情が曇った。
「あ、ごめん。タカユキとも話したんだけど、自分が刺されるかもしれない、怖かったって言ってたんで」
「ああ」
山下は緊張を剥ぎ取るように笑った。しばしの沈黙の後、ため息が聞こえ、こう続けた。
「最後、役を放棄したんです」
「えっ?」
「舞台袖に走ったとき、もう役をやってませんでした。南家さんも気づいたと思います」
もちろん、榛央は気がついていなかった。
「あのまま劇中の山下を続けてたら、何するかわかんないと思って。だからもしそれで評価が下がったとしたら、ごめんなさい」
「いやいや」
慌てて取り繕った。
「そこまで思い入れるものだと思わなくて」
そしてまた山下は奥歯で言葉を噛み砕いた。
「あの脚本持ってきたとき、南家さん、鬼だと思いました」
山下は南家貴之を示したが、鬼と言われたのは自分ではないか。
「ごめん。鬼は僕かもしれない」
「そんなことないです。南家さんですよ、山下と伊藤って、そのままの名前でやらせたんだから。せめて役名があれば違ってたのに、だれを演じればいいんですか、それ」
地区大会当日。
部員たちは顧問が手配したバンで会場へと向かった。
城戸先輩も、と声はかかったが、そこが自分が入り込める場所ではないことは薄々気がついていた。
「圭吾と行くから」
と、受験勉強中の剣道少年を出汁に使い、西国分寺駅前で待ち合わせた。いつものように改札前。学生服に似つかわしくないバックパックを持って。
「図書室に行くと、いまもタカユキがいるんだ」
定期を改札にかざして、榛央が言った。
「呪いの老人がいるんじゃなかったんだ」
隣の改札を通りながら、圭吾が聞き返した。
「呪いの老人にも会ったよ」
土曜の午前。ひとはまばら。
「他には?」
他。他って。
「興味ないなら、『ああそう』とか『ふーん』で打ち切れよ」
「いや、興味はある。他には?」
他。
「荒俣宏」
「タカユキも連れてくれば良かったのに」
「振ったらフォローしろよ」
微笑むだけで、返事もないままエスカレーターへ。
「タカユキは妹と一緒」
「そうか」
ホームに入ると石崎聖奈とその友人の姿があった。おそらく全員コーラス部。少し離れて立っていると、向こうから手を振ってきた。
「車で行ったと思ってました」
「いや、こいつの面倒見ないといけないんで」
榛央は圭吾を指さした。
「方向音痴なもんで」
圭吾も話を合わせた。
「はじめまして」「こちらは剣道部の……?」「瑞樹です」「はじめまして、よろしくおねがいします」
コーラス部のなかでは、圭吾と榛央の仲が密かに噂されており、まじまじとその顔を覗くものもあったが、
「噂はコイツが勝手に立ててるんで、気にしないで」
と、圭吾本人が榛央を指さして否定した。
「予選、突破しますよね?」
石崎が訊いてきた。
「もちろん」
そう答えはしたが、声は沈んだ。ここ一ヶ月で高校演劇の奥の深さに触れた榛央には、その自信はなかったし、目標でもなくなっていった。
「演劇って、花が咲くかどうかは観客との相互作用だと思うんだよ」
ゆっくりとそう口を開く榛央に、コーラス部は視線を集めた。その頬にはあの日の歌声を含み、柔らかく漏れ聞こえるようでもあった。
「プロの劇団でも公演を重ねて修正して形にするってケースが少なくない。でも高校演劇は一発勝負だから、ほんのちょっと歯車が合わなかっただけで終わる。そうなると演劇のいちばん演劇らしいとこ、観客のリアクションを血肉にするとこを経験しないままに終わる」
「わかります」
もう榛央が語り終えるまえから、その言葉は口に溢れていた。
「わたしたちも一緒だよね」
「同じですよ、やってることは」
「あ、うん」
語り終えると同時に急いで相槌を打ったが、もはや自分が語りたいことを語ったかどうかもわからなかった。もしかしたら話の半分は、彼女らの言葉だったのかもしれない。
「負けたら悔しいけど、それで終わりだとは思ってないです。いままでやってきたことが結果で変わるわけじゃないし」
「だからわかります」
その言葉に榛央は涙をこぼしそうになり、俯いた。
耳にした風の音、鳥の声、顔をあげるとそこはもう地区予選会場のホールだった。
幕が上がる。
静かな静かな滑り出し。
いままで気にしていなかった照明のタイミング、効果音の音量にまで意識が走った。見えもしない裏方の緊張が伝わってくる。演出も兼任するからと主役を張らなかった山下もきっと、細かい演出を意識しながら舞台に立っている。だけどそれを感じさせないほどに伸びやかだった。
山下、伊藤の演技もだが、去年脇でテグスを引いていたふたり、岡野、坂井が群を抜いた。キャラメルボックス成井豊の筆は登場するものすべてを引き立てた。
正直、失敗すると思った。失敗すれば良いとすら思った。なにがキャラメルボックスだ。どの高校も演じる既成の舞台じゃないか。そこで何ができるんだ。だけどその舞台が榛央の胸ぐらを掴んで離さなかった。だれかが飛び降りたりもしないし、首にテグスを掛けたりもしない。これが最初から目指していたもの、『戦争を描かずに正義を描く』、まさにそれだった。大きな話は要らない。部員たちはなにげない小さな言葉のやりとりから、その背景の複雑な感情を顕にして見せた。ずっと講堂に吹き溜まっていた光と音の積層が、形を為し、榛央の胸を通り過ぎた。舞台の上に描かれた無数の物語は、客席に座るものたちの物語も束ねて奔流となった。山下の目に映る伊藤、伊藤の目に映る山下が見えた。それは『わたしを離さないで』でキャシーの目を通して見た世界を、幾重にも織り上げた世界だった。
スポットライトのなか、最後のセリフが決まる。
効果音の余韻が消えると山下以下演者8名が舞台面に並んで頭を下げた。
拍手が湧く。
拍手は彼らを役の呪縛から解き放つ。
高校を出てからも演劇を続けるとしたら、彼ら、彼女らはこのあと、何百、何千と舞台に立つ。その舞台に立って身に受けた呪いを、こうやって拍手で清め落とす。
拍手が呪いを解く。
だれかの呪いを解く術を、だれもが持っている。
舞台を重ねるうちにやがて彼ら、彼女ら自身にかけられた呪いも消える。そしておそらく、彼らを観たものの呪いさえも。時間をかけて、いつか、確実に。
第六文学――それはもしかしたら、生涯をかける長い冒険なのかもしれない。
第七文学 永遠
かつて夕刻の空は太陽が染めていたが、ひとの暮らしを十年も続けると、やがてそれは胸のうちから滲み出すようになる。仄かな疲労と、充足と、いくつかの絡まった追憶とを眺めているうちに空は染まる。人類は因果のすべてを逆に覚えた。現実は、まず影が長く伸びて、それから太陽が傾く。その低い太陽に手をかざして、石崎が山下になにか話している。それもきっと、こうやって手をかざすから太陽が傾くのだろう。顧問がバンのバックドアを下げる音が空に吸い込まれる。コーラス部の張りのある声は腰の高さの低い風に乗って榛央の足元に届いた。テニスボールのように転がって消える声のいくつかは拾い損ねて、手に触れた音と影を動かすひとの動きから、コーラス部と演劇部と、合同でなにかやりたいと話していることを類推すると、小さな人影の影を伸ばして、空には見事な夕焼けが焼き上がっていた。
榛央が後ろ向きにゆっくりと駅を目指すと、山下が気がついて会釈した。両手をあげてそれに応えていると、コーラス部員の何人かも手を振り、同時に駅を目指した。夕方の声は低く地面をバウンドする。その声がゆっくりと足元から疲労となって広がる。
改札。
「瑞樹さんは先に帰られたんですか?」
尋ねてきたのはコーラス部の部長。名前も知らない、圭吾の半分ほどの細い肩。女子の目を見ることも躊躇われ、その細い肩くらいしか目をやる場所がない。
「あいつは薄情だから」
「方向音痴は大丈夫ですかね」
圭吾はノリのいい男だ。今頃、松本の駅で困り果てているだろう。
夕方、中央線の上り列車。榛央と向かいの少し離れたシートに島本釉が座っていた。大雨の日、隣に座ってから意識するようになった。だけどまだ何も知らない。視界の隅に捉えると、隣に座るだれか、前に立ち吊り革を握るだれかと話はしているものの、意識はこちらを向いていることがわかった。おそらく、こちらの意識が向いていることも筒抜けなのだろう。だれか、だれか、だれか、島本釉、だれか。名前だけは覚えた。それがそのシルエットを背景から切り抜くための輪郭になった。
西国分寺から乗り換えて二駅。
駅前のブロック敷きの道を歩いて、街灯のない細い路地に入る。南武線の線路を超えた先の低層マンション。小学生の頃に調布から越してきてもう
10年になる。
国立へ通うようになって2年半。バスも電車も少なく、時刻表もすべて覚えた。ドアを開けると食事が用意されている。妹はよく居間で宿題をしていたが、その日はもう部屋に入り、友達とチャットする声が聞こえた。母親がいた。榛央の姿を見留めるとすぐに台所に立ち、ごはんをよそい、テーブルに置いて、
葉月――つまり妹にはまだ内緒だと釘を刺して、離婚のことを告げた。
葉月はよほどのことがない限り父親が引き取る。自分では、養育費をもらったところで大学へはやれない。
「あなたはどうする?」と聞かれ、答えに迷った。
この日のことはぼんやりと予想していた。
榛央は母親について、働いて生活を支えるつもりだった。
「考えておく」
とだけ答えて、箸を取った。
師走、風が走り、ひとを急がせる。
乾いた図書館の冷たい床に腰をおろした。
もうタカユキの姿は見えなかった。
「二年生のうちふたりが辞めるって」
「ちょうど区切りいいもんな。来年になるとズルズルまた秋までってことになる」
「負けたせいかと思ってヒヤヒヤした」
「でも、そうだったとしても、それが人生だろう?」
「まあ、そうだけど」
「それよりも、おまえをこっちに引きずり込んだことを後悔してる」
「こっちって?」
「演劇」
「べつに、そんなにはまってるわけじゃない」
「じゃあ、ほかにやりたいことは?」
「ないけど」
閉塞感の理由は家庭だった。何を考えてもそこに戻った。
「貧乏なんだよ。うち。
バイトなしじゃ大学にも行けない。
そこでもし演劇にはまったりしたらさ。
どうすんだよって話。
それに俺、演劇の才能ないし……戯曲が書ける気もしない」
幼い頃の『動機』は単純だった。
飛行機がカッコいいというだけで、パイロットを目指せた。少年少女は真っ白な紙。どんな将来だろうがクレヨンででかでかと書けばいい。それが中学、高校と進むに連れ動機を探すのが難しくなる。
「でも、動機がないなんて嘘だ。
動機がないって言うやつ、みんなそう。
ないのは才能であって、動機じゃない。
動機はあるんだよ。身の回りに。
でも、才能がないから、それを受け取らない」
南家貴之の声はもう聞こえなかった。
それでもしばらく、榛央はその声を自分で紡いで語り合った。
高卒試験合格の知らせを受けて、本来ならいよいよ退学届、となるところだが、アルバイトを辞めて久しい。両親がどうなるか、自分と妹がどちらを選ぶかもわからないなかでは決め兼ねた。もう卒業の規定日数も満たしている。明日から全休してアルバイトに明け暮れたところで卒業はできる。その後はアルバイトをしながら大学に行ってもいい。奨学金を利用する手もある。多くの選択肢が胸に浮かぶ。だけど決意は定まっていなかった。大学に行きたいわけではない。ただなんとなく、それが既定路線のような気がしただけで動機がない。だけどそれだってキャラメルボックスを手にしたときのように、手に取ればその先が見えるのかもしれない。
「何をするにも決め手がない」
相談した相手は圭吾だった。
電車のなかでラインで送ると、部屋に帰り着く頃に返事が来た。
「大学行けよ」
剣道少年はどこまでも真っ直ぐだった。
「金がないんだよ。ほんとに」
「父親から養育費は取れないの?」
圭吾には両親の離婚のことも話していた。
「取れるけど、あの親がちゃんと払うかどうか」
「弁護士は?」
「だから金が無いんだって」
「じゃあ、わかった」
「わかったって何が?」
「おまえがなれよ。弁護士」
「なるほど、それで時間を遡って俺自身を弁護に来ればいいんだな?」
「正解。おまえ、頭いいくらいしか才能ないんだから。なれよ。弁護士」
「ありがとう天才少年。こんど剣道教えて」
渾身の嫌味のつもりだったが、その
鋒は虚しく空を切った。
「じゃあ、塾の帰りだから」
榛央が母親に付いて行きバイトをする。ふたりの稼ぎでなんとかやっていく。妹は父親に付いて行き、高校、大学と出て就職する。それがほぼ定まった未来図だった。だが妹は、父よりも母といることを望むだろう。榛央にしても同じ。父親と暮らすことには抵抗があった。
そして、もうひとつ可能性はあった。妹が母について行き、父から養育費を取ること。榛央はもう2年しか養育費がもらえないが、妹なら5年出る。父のもとでなら榛央も大学に通える。バイトもすればバイト代で母を支えることもできる。ただ、動機がない大学で4年を過ごせる自信がない。それに、父とも。
学校を休みがちになり、担任からも話があった。進路指導室で、いつ退学してもいい、迷っていると伝えると、最大限の配慮はする、いまからでも推薦を出せる大学はあると諭された。
演劇部にビデオを返しに行くと、山下が中野の小さな劇場のチケットが余っていると榛央に手渡した。なぜか部室にはコーラス部の島本がいた。
「OBの舞台なんで、穴を開けるわけにいかなくて」
「それを受験のある3年に渡すか?」
「いや、受験しないって聞いたんで。だれか誘って。ぜひ」
なぜか部室にはコーラス部の島本がいた。
「わかった」
榛央が借りていたビデオを山下に手渡すとき、島本と目があった。ちらりとチケットに目を落とし、「外で」と促して部室を出た。中庭に面したモルタル敷きの上の板張りを、ゆっくりと歩いていると背後で部室の扉が開く音がした。振り返ると島本がいた。
「あの」
ふたり同時に口に出した。
「だれと行くんですか?」
島本がそう口に出す前に、
「もしよかったら」
目を泳がせて榛央が言った。
中野の劇場MOMOは定員
100人に満たない小さな劇場だった。
そこで金土日の三日間だけ、OBが所属する劇団の舞台があった。
「舞台はよく観るんですか」
榛央が聞いた。
「いえ、初めてです」
島本釉――釉がこたえた。
いわゆる初デートだった。往きの道はほとんど話さなかった。
小さな椅子に並んで腰掛けて、観劇の間もずっと緊張をたたえ、舞台も終わりキャストに拍手と声援を贈るときにようやく互いの笑顔を覗きあった。拍手という魔法が壁を溶かしたように思えた。
「フランス文学が好きなんです」
中野の駅へ向かう道すがら、釉は語った。
「とくに好きなのはクロード・シモン」
「ノーベル文学賞の?」
「そう! ご存知ですか?」
「いや、読んだことはないけど」
詩的な文体、時間も内容もばらばらの長文が特徴で、はじめは読みにくいと感じるかもしれない。でも慣れてくると情景が浮かぶ。意味を追いかけるというより、音楽を聞いているみたいだと釉は語った。
仏文学と聞いても、サルトルのほかにはカミュ、ゾラ、プルーストと教科書で聞いたような名前しか浮かばない榛央は少し気後れした。ヴェルヌ、サン=テグジュペリ、サガン。
「ランボーは好きかな。ありきたりだけど」
「あ、そんな雰囲気ありますね」
「それってどんな? 愛人から撃たれそうな?」
「うん。瑞樹さんから」
サン=テグジュペリが好きで、中学の頃には辞書を片手に原文を読むようになったと釉は語った。そういえば、雀を見ながら花壇の脇で話していたとき、何度か傍にいた気がする。いままでずっと話したくてウズウズしていたのかもしれない。だけどいまにして思うと、あの頃の自分――と言っても1年も経ってはいない――は痛々しかった。深く愛した作家などいない。知識として読み漁って分類しただけの、世界の文学の
0.1%にも遥かに届かない知識を堂々とひけらかしていた。クロード・シモンも名前は聞いたことがあったが、文体も内容も知らない。作家が望むのはそうやって知識として読み漁られることじゃない。それがわかったいま、もう文学について語る言葉は失ってしまった。おかげでこの日は釉の方から一方的に話した。釉としては「手応えなし」がその正直な感想だっただろう。それが失望に変わるのに、そう時間は要さない。
山下から「MCを頼みたい」との打診を受けたのは暮れも押し迫る師走の半ばだった。
MCとは?
山下に問うと「マイク……コントローラー?」みたいな答えが返ってきたが、そうではない。
「マスター・オブ・セレモニーっしょ。いや、そういうことじゃなくて。どこで何やるの?」
聞けば演劇部とコーラス部とで旧図書室で最後に出し物をする、そのMC、つまり司会を、ということらしかった。演劇部に顔を出す機会も減り、榛央の耳までは届いていなかったが、もう学校にも許可を取り日時も決まっていた。
「どんなことするの?」
「あの、嵐の日にやったようなこと。あれを全校生徒の前でやりたい」
「全校生徒は入らないでしょう」
「じゃあ、一部二部に分けて」
「いや、無理だって。というか、任意じゃないの?」
「任意」
「せいぜい
30人じゃない?」
「みんなそう言います」
中野の劇場MOMO以来、釉と話すことはなかった。
榛央の方からも意識するようにはなっていたが、それ以上はなにもない。まわりはもう十分なお膳立てはした、あとはふたりの問題、何が起きたかも聞かなかった。図書室でリハーサルを兼ねて打ち合わせる間も、お互いの視界にその姿を捉えてはいたが、あれこれと出されるアイデアについて語るとき、このふたりの間にだけ会話がなかった。これはきっともう駄目だと、周囲は感じていた。国立の駐輪場に自転車を停める折、たまたま顔を合わせたときも、また舞台のチケットでもあれば誘えるのにと、ほとんど片思いのような感情が榛央のなかにも芽生えていたが、話しかけることはなかった。
妹の受験の準備が大詰めを迎えるなか、まったく無神経なことに父親から妹に、離婚の話が伝えられた。冷静を装って、「お兄ちゃんは知っていたの?」と問う妹に返す言葉がなかった。どうしてこうも、あの男は。まったく。
翌朝、授業の始まるまえの早い時間に図書室に行くと、釉の姿があった。釉は小さく会釈した。
たまたま?
胸のなかでタカユキに尋ねると、「昨日も来てたよ」の声が返った。
なんのために?
さあ。
「個人練習?」
「ええ。まあ。先輩もですか?」
「うん。というか、相談に来た」
「相談?」
「タカユキがいるんだ。ここには」
「ああ」
普通に聞けば、いま演劇部とコーラス部で準備している物語の話だと思うだろうが、釉にはピンと来た。榛央はずっとここでタカユキに会っていたのだ。釉の目にもまだ本棚に並んだ本が見えていたし、その本棚の向こうにはタカユキもいた。
「わたし、いないほうがいいですか?」
反射的に尋ねたが、釉が聞きたい言葉は「いて欲しい」だった。だけどまだそんな仲ではないのはわかっている。こんな聞き方で良い返事が返るわけがない。榛央にしても同じ。ようやく話す機会ができた。いて欲しいに決まってるが、軽々しくそれを言える性格でもない。恋になるまえのなにか、それが破れるほんの2ミリ手前、榛央は気がついた。そういえば釉が立っているところにはかつて、仏文学の棚があった。
「読んだよ。クロード・シモン」
やっときっかけを見つけた。
「本当ですか? どうでした?」
ぱっと晴れやかな声が返った。
「難しかった」
いくつかの候補から言葉を選ぶと、同じように釉も頬のなかに言葉を選んだ。
「第何文学だと思いました?」
もうやめようと思った言葉遊びだった。ちょっと苦々しい思いをしながら、
「第……二十八?」
上目遣いに答えると、
「出ました! 第二十八文学! 一気に記録更新です!」
あの日のタカユキのように、釉が声をあげた。
クリスマスを直前に控えた土曜日。午後。
旧図書室で演劇部・コーラス部の合同イベントが開催された。
観客は部員たちの知り合いを中心に
40名。ステージにあたる床に丸く貼られたテープの周囲に座り、めいめいに開演を待った。ステージは図書室のほぼ中央に位置し、円形劇場のようでもあった。
開演一分前、ブザーが響いた。
客席のざわめきは息を潜め、時計の針に空間の支配を委ねる。
秒針の足を追って長針が最後の一歩を動くと、五時間目のチャイムの音とともに舞台は幕を開けた。
資料室からオペラ座の怪人を模した城戸榛央が現れ、ステージに立った。
「藤橋高校演劇部コーラス部、第一回合同公演へようこそ」
榛央は手を広げ挨拶し、ぐるりとギャラリーを見渡した。
円形のステージに広がる静けさを均等に胸に吸い込むと、この上ない高揚が押し寄せる。
「南家タカユキを覚えていますか――」
もういちど周囲を見渡す。
「あいつはアレクサンドリア図書館に憧れていました。
アレクサンドリア図書館というのは、古代エジプトにあった巨大な図書館で、その蔵書数は4万から
50万と言われています。
4万というのはみなさんご存知立川まんがぱーくの蔵書数。一方
50万は都立多摩図書館の蔵書数です。西国立のまんがぱーくから、西国分寺の多摩図書館。自転車で
30分。それが僕らの生活圏でした。
あいつはまんがぱーくの隣の病院で旅立ちました。その向こうには、あいつが行くはずだった大学があります。本当に、本当に目と鼻の先でした」
榛央は涙をこらえた。まだ序盤だ。ここからだ。まだ泣くときじゃない。
「あいつが、こう言ってたのを聞いたことがあります。
舞台を観て、感動して、どこが面白かったって言葉にするけど、そのとき言葉に出来なかった想いって、どこに行くんだろうね」
胸の中ではもう泣きじゃくっていた。観客にもそれは伝わり、榛央の代わりに涙を零すものがいた。
「そのとき、どう答えたか覚えていません。
でもきっと、それらは僕らの血肉になったのだと思います。
だからタカユキの想いも、僕と、演劇部のみんなと、それとともにいたコーラス部、それから今日集まって来てくれたみんなの、血肉になるのだと思います」
マイクを持つ手は震えている。
「拍手で迎えてください――」
榛央が手を差し伸べると、図書室入り口の扉が開く。
その扉から演劇部部長、コーラス部部長、ふたりが先導し、タカユキが花道に入る。柔らかで荘厳なクワイア。ゆっくりとライトのなかに浮かび上がる影が、舞台中央に来たとき、榛央は改めてマイクを口に当てた。
「紹介します。
わが校演劇部が誇る不世出の天才、南家タカユキ。
みなさん拍手を」
ゆっくりと沸き起こる拍手にまぎれて、ざわめき、啜り泣く声が聞こえた。
タカユキは軽く手をあげて、四方へと挨拶、用意されたディレクターズ・チェアに座る。
おもむろに、榛央はタカユキから台本を受け取り、ページを開いてめくり始める。
控えていた山下にその台本を渡して、改めて客席を向いた。
「それではお送りいたします! ご覧いただく作品はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト作! フィガロの結婚!」
そう告げるや宮廷風の音楽が流れ朝の爽やかなコーラスが舞台を彩り始めると、演者たちは姿勢をただしスカートを上げて挨拶を交わした。が、すぐに曲が止まる。
止めたのはタカユキ本人。
――それじゃない。
はあ?
タカユキはディレクターズ・チェアを立ち、舞台を横切り、山下の手から台本を奪って榛央に叩きつける。榛央はまた台本を見て、首を捻り、タカユキが椅子に戻るのを確かめて台本をズボンに刺す。
「大変失礼しました。プログラムが間違っていたようで……それでは御覧ください! ジュゼッペ・フォルナリ・ディ・パルマ・ヴェルディ作! 椿姫!」
流れ出した曲が、2秒で止まる。
部員は戸惑い、タカユキはものを投げて怒りだす。
そうじゃない? はあ? なにを言ってるんだ?
訝る榛央にタカユキは堪えきれず、ラジカセまで歩き、自ら曲を掛けた。
観客は何がおきるのかと固唾をのむ。
そこに流れ始めたのは ONE PIECE の主題歌、『ウィーアー!』。
次の瞬間、ステージは大海原の海賊船になった。
もはや榛央はお呼びではない。コーラス部の歌声が風と波とを紡ぐなか、『ひとつなぎの大秘宝』を探す冒険が始まる。
モンキー・D・ルフィとその一味のまえに海賊たちが立ちはだかる。
繰り広げられる戦い。押される仲間たちにタカユキが次々と武器を手渡す。
あるものは刀を受け取り、あるものはパチンコを受け取り、あるものは水の入ったバケツ、あるものは自転車の空気入れを受け取り、戦った。
空気入れでどう戦うの? ――トニートニー・チョッパー山下が戸惑う。
ナミ役の坂井が受け取ったのは、牛乳パックと紙コップ。
ナミは牛乳を一杯飲み干すと、紙コップに牛乳を入れてルフィに、サンジに、ゾロに手渡し、ついには舞台に並べ始める。
紙コップを持ったまま、足元の紙コップを避けながらの殺陣。
牛乳を零すと戦いを一時中断してみんなで掃除した。
仕舞いにはトニートニー・チョッパー山下の頭にも牛乳が入った紙コップが置かれ、やがてその ONE PIECE の世界がフィガロの結婚と交錯、そこからはコーラス部の独壇場。フィガロの結婚のあの有名なアリアからアベ・マリアを経由して、魔笛からパパゲーノ・パパゲーナ、プッチーニ、ラ・ボエームからシミュール・ラ・ジュールのアリアとこちらもやりたい放題で、最後は何が起きたかわからないまま、山下ら演じる麦わらの海賊団は『ひとつなぎの大秘宝』を手に入れた。
からっぽの図書室に拍手が鳴り響いた。
ステージ上の部員たちが、ディレクターズ・チェアのタカユキに拍手を送る。
椅子を立ち、舞台中央まで出るタカユキの姿が観客の目に映った。
演者たちはタカユキからめいめいに風船を受け取り、その風船を観客席に配った。
海賊船も、風船も、牛乳の紙コップも、何も必要なかった。
舞台上で、榛央とタカユキがハグを交わすと、観客たちはしっかりと風船を手にしたまま涙を拭った。
「いままでありがとう」
榛央からタカユキへ。
「短い間だったけど、たくさんの言葉を交わした。
言葉にできない想いは、それ以上だった。
言葉にすればするほど、本当の気持ちから遠ざかっていたように思う。
タカユキ、君もまたそうだと思う。
だけど僕たちは、そうやって言葉にならなかった思いを、永遠に胸に刻む。
だからいつか。いつの日か。また会おう。アレクサンドリア大図書館で」
柔らかなコーラスが包む。
舞台の上には泣き崩れる部員の姿もあった。
「ありがとう。タカユキ」
榛央と手を握り、また固いハグを交わすと、タカユキは客席に向かって軽く手を挙げ、照れた笑みを浮かべて踵を返した。
次の瞬間、観客の一人がステージに上り、タカユキに握手を求めた。
それを見た別のひとり、さらにもうひとりとステージに上がった。
肩をたたくもの、ハイタッチするもの、ハグするものがいた。
挨拶が一巡した頃、改めて榛央が会場に求めた。
「タカユキに拍手を」
湧き上がる拍手。
榛央が指を開くと、その手から風船が空へと舞い上がった。
振り仰ぐと、青い空があった。
部員たちも一斉に空へと風船を舞い上げる。
観客たちもまた手を開いて、風船を空へと還した。
色とりどりの無数の風船が舞い上がった。
いまこの瞬間、この図書室の外はプトレマイオス朝エジプト、アレクサンドリアへと続いている。
第七文学。
それはだれも言葉にできない、今日のこの空の色だった。
中央線沿いだというのに、バスの数は東京とは思えないほど少なく、通学路を少し離れただけで田畑が見えた。中央線で国立駅から通うものの多くは、駅前の駐輪場を借りて自転車で通った。榛央もそうだったし、釉もそうだった。ただなぜかその日はふたりでバス停に並んだ。バスが来るまで
15分あった。いまから学校に引き返し自転車に乗れば、バスを待つ時間で国立の駅につく。
だけどふたりは、時間の使い方を覚えていた。
「歩く?」
榛央から声をかけた。
「うん」
もう歩きかけた榛央を釉は小走りで追いかけた。
駅まで徒歩で
30分。
お互いに話したいことがあった。
そのための時間は、いくらあっても足りなかった。