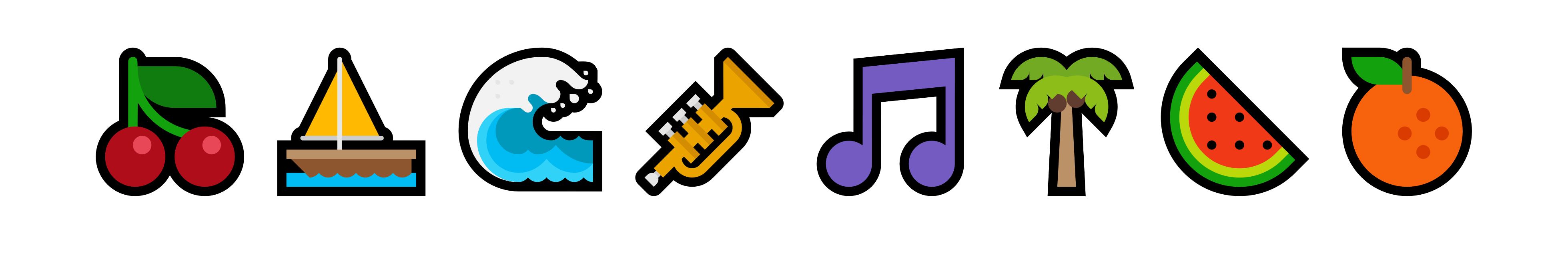- 序
- 第一章 青銅の檻
- 第二章 金の雨
- 第三章 流刑の島
- 第四章 旅立ち
- 第五章 アイギスの盾
- 第六章 翼の靴
- 第七章 古い記憶
- 第八章 見えない妖精たち
- 第九章 炎の生徒会とメデューサの首
- 第十章 白球のアンドロメダ
- 第十一章 オリュンポスの神々
- 第十二章 僕たちは大人になる
- あとがき
序
ある漫画家が言った。
漫画を書いている時、僕はその世界の中にいる。
それは決して、僕だけが住まう小さな世界じゃない。
その世界は僕らの世界のすべてを含み、この世界よりも遥かに大きい。
漫画を描くというのは、小さな箱庭を作ることじゃない。
この世界の壁を壊して、外に出ることなんだ。
だれのどの漫画だったかも覚えていない。友達から借りた漫画の中のどれか、まだ漫画家を目指すなんて考えてもみなかった頃。作者が読者の質問に答えた一頁だったと思う。
――この世界の壁を壊す
異世界から来た化け物が次々と人を襲う――そんなスケールの大きい漫画を描けばいいのかなかと思ったくらいで、本当の意味まではわからなかった。
でも、今の僕なら――
第一章 青銅の檻
高校二年、秋の終わり。
母、
樺島裕美が急逝、その告別の席、喪主には祖父が立った。
通夜には友人の姿も見え、中には小学校、中学校以来の顔も。懐かしさと、場違いな思い出話。後ろに並ぶ焼香客に押され、「また今度、いつか」と、笑顔をこわばらせて、寡黙な黒い列に並ぶ。
受付には父、
高松真雪の姿も見えたけど、祖父、祖母と話しただけで、母方の親戚の人垣の外に立ち尽くしていた。両親が離婚してもう六年。胸の底にはまだ父への嫌悪感が消えない。
父の後ろには姉、
奏絵の姿も。今年から福岡の大学に通っていると聞いた。少しだけ視線が交わると、
「
勇!」
僕の名前を呼ぼうと、一瞬だけ綻んだ顔が見えて、でもすぐに僕は視線を反らしていた。その声も、笑顔の続きも、想像の中。僕は最後の瞬間に見えたその顔を、記憶の中の姉の頁に貼り付けた。
畳の席では叔母がグラスを持ったまま、その背中でずっと父の姿を追っている。美しく波打つ髪を結び、喪に服した黒い服は少し艶やかにも見える。ネイルの指。横目で父の背を見送ると、ケータリングの小さなサンドイッチをつまみ、紅に触れないように口に運ぶ。
叔母の傍らには従兄弟の
樹。僕より三つ下。言葉をかけるきっかけを探しながら、僕の方を覗き見ている。樹は三歳で父を亡くした。もう十年以上も昔。その父、高松
真陽の死因はバイク事故だった。遺体からは薬物が検出されて、叔母はその後すぐに旧姓の古賀に戻した。
まだ六歳だった僕には、樹の苗字が変わったことは奇妙に思えた。だけどその五年後には僕の両親が離婚、僕の苗字も変わった。樹も奇妙に思っただったろうに、そのことには何も言わなかった。幼いなりにいろんなことを考えていた。それは僕も、姉もそう。両親が離婚する前の一ヶ月、父母が交わす言葉を布団の中で耳にしながらよく泣いていた。僕も姉も、寝たふりをして。
父の家を出て、母とふたり、小さなアパートを借りて、隣の校区の小学校に転校すると、新しい友だちは新しい名前で僕を呼んだ。その中でときどき、昔の友だちから昔の僕宛に手紙が届くと、一年ぶり、二年ぶりの僕が起き出して、手紙を読んで、返事を書いた。
公園で前の学校の友達に会うと、奇妙な距離を感じた。それまではコンビニで買う菓子が違っていてもそれだけのことでしかなかったものが、まるで通っている学校の違いがそこに現れているように思えて、だれかが買ってきた菓子に、別のだれかが言った、「それ、美味しかろう」の言葉も、僕の胸に届く少し手前でこぼれていった。
JRの久留米駅に近い
荘島町の、小さなアパートで暮らした十一歳からの六年。最後の一年は、母の闘病生活。膵臓がん。父は古い医院を継いで、六ツ門町で小さな外科・循環器科を開業していたけど、母は最後まで父を頼ることはなかった。
泣いたり、笑ったり、泣いたり、泣いたり……
涙にはいろんな理由があった。いろんな理由で泣いた。今もまだ気持ちがこみ上げてくる。まだまだ涙にはいろんな意味があるんだ。僕はこの先、涙の意味をいくつも知ることになるんだ。
棺には、痩せ細った母の顔がある。髪はかつらで他人のよう。つい先日まで、僕が選んだ帽子をかぶっていたのに。耐えきれずに目を反らすとまた涙が溢れてきた。止まらない。言葉も息も堰き止められて、祖母が僕の肩を抱き寄せる。
どうしてあんなに苦労してきた母が、こんな最後を迎えなければいけないんだろう。安らかな眠りとは程遠い闘病の苦悶を貼り付けたまま、棺に横たわり、僕は母が天に上って花の中を歩く姿さえ思い描くことができなくて、姉がまだ近くにいるかもしれない、姉が僕を見つけて、声をかけてくれるかもしれない、目を反らさなきゃ良かった、父さんのことなんかどうでもいい、話をしたかった。十七歳ってこんなに泣くのか。高校二年生って。こんなに肩を震わせて、自分でも止められないくらいに。
だけど悲しみがどれほどにあふれても、その底にある大きな不安が喉を通ることはなかった。ずっと喉につかえたままの不安。悲しみで消せるものなら消してしまいたかった。
祖母がその背をさする。ハンカチを手渡して、また別のハンカチで、自分の涙をぬぐう。ふと耳に届く音が途切れた気がして顔を上げると、涙で滲んだ視界の中、参列する焼香客に紛れて叔父の姿が見えた。その背中、ペガサスの刺繍が入ったサテンのスカジャンが式場の光を映して浮かび上がる。ずっと昔に死んだはずなのに、その違和のある佇まいに、だれも目をくれない。
叔父の姿が棺の前まで来たとき、棺の中に横たわっていた母がゆっくりと体を起こして、叔父に微笑んだ。
ふわりとした暖かな空気が僕を包む。
「お母さん」
思わず口に漏れる。
天井からは光が降り注いでいる。光の一条一条が弦のように、高低様々の音色を響かせて、母の姿は式場の花に散る光を集めて煌めいている。
今この瞬間、繋がっているんだ。天国と、こことが。
そう言えば、さよならを言ってない。
さよならだけじゃないよ、母さん。まだ話さなきゃいけないことがたくさんあるんだ。
炊事当番の日、台所を片付け忘れたときのこと。洗濯物をたたみ忘れたときのこと。シャンプーの詰替えを忘れて、そのままにしてしまったときのこと……。胸の中には後悔ばかりだ。
今度はちゃんとするけん……怒らんでよかごつするけん……。
手を伸ばすと、ようやく母さんも僕に気がつく。
そして、優しい手を僕に伸ばす。
お母さん……。
僕も行くよ。
もうこんなとこにいたってしょうがないし、父さんとなんか暮らしたくないよ。
生きていたって、辛いことばっかりだよ。
――僕の手が母の手に触れるすんでのところで、叔母に肩を揺すられた。
「どげんしたと?」
おどけて声をかけた叔母が、呆然としている僕に気がついて、笑顔をこわばらせる。僕の視線を追っても、母の棺だけ。蛍光灯のノイズが降る中、叔父の姿もなく、もちろん起き上がった母の姿もない。棺の中には、花に埋もれて母の顔が、痩せこけて、硬直した皺を寄せている。
「いま、ヒロ叔父さんがおったごたっ気がして……」
何をどう言っていいかわからなかった。
「真陽が? 迎えに来よらしたっちゃろか」
叔母の言葉を聞いて、少し気まずさを感じた。これだと死別した夫が、僕の母を迎えに来たことになる。少し戸惑っていると、祖母がしずかに頷く。
「向こうでも知った顔がおったほうが、心細うなかろうたい」
祖母と叔母とが、今は亡きヒロ叔父さんの話を始める。
――僕の父とは仲の良い兄弟だった、優しい弟だった……。
僕にはヒロ叔父さんの記憶はもう微かだった。親戚はみんなお年玉をくれる他人。法事の日のビール臭いトイレが嫌いだった。掃除をしていた母の背中。血の繋がりもない親戚。どんな気持ちで食事を用意して、片付けて、掃除をしていたのか。
叔母と叔父、祖母と叔父。血の繋がりもないのに『親戚』という絆で繋がっていることが、不思議に思えた。
長い通夜の夜。
三時を過ぎた頃に眠りに落ちて、翌日、窓から差す陽の光を見て改めて、僕ひとり置いて行かれたんだと感じた。
眠気の残る体。いくつもの時計がぱたぱたと走り回る。挨拶、読経、焼香と、一通りの葬儀が終わり、徹夜明けの足にも重力の感触が戻るころ、祖父の出棺の挨拶が始まる。
式場の係の人が用意してくれた例文を、たどたどしく読んではつかえ、途中でそれを丸めてポケットに入れて、娘、裕美の人生を、自分の言葉で語り始め、僕を呼び寄せて、肩に手を置いて続けた。
「裕美はこの子――勇を残してくれました。裕美にしてやれんかったぶん、勇には尽くしてやらにゃいかんち言うて、京子とも話しました」
その先は涙声。昨日から式場で係の人と打ち合わせ、ケータリングや装花の手配、その確認で走り回り、弔問客も減った夜になって、ようやく娘と語り合えた、その小さな背中が震えている。
「もう、なんも残っとらんとです。人生に、楽しかこつが、なんも残っとらん。そいばってん、誰かば幸せにしてやらんと、なんで生きとうとか、わからんごつなるけん、勇にはもう、なんでっちゃしてやろうち思うとります」
祖父が深く頭を下げると、出棺を告げる長いクラクションが鳴る。
黒いバンの車体に映した雲が流れる。
職員の靴や、運転手の手袋、柔らかくギヤを入れて、ハンドルを回す所作。シートベルトを締めた僕の隣には、まだ母がいる。その人生の最後は斎場が用意した画一的な処理に接続されて、何百、何千人と見送ったであろう斎場のひとたちに見送られる。その機械的、反射的な悲しみも、きっと本当の悲しみに変わりはないのだろうけど。
火葬は山の麓のほうにある市営の斎場。叔父の火葬のときに来たことがある。あの時は初夏。姉と二人でバッタを追い回していた。
祖父と祖母と、その縁者らしい人。母の知り合いらしい人が幾人か僕に声をかけてくれた。通夜では入れ代わり立ち代わりいろんな人が訪れたけど、ここまで来た人たちが僕の親戚、母の友達なんだと思う。そのひとりひとりと母とがどんな関係だったのか僕は知らない。僕にはもう開かれないだろう物語が、ぽつりぽつりと椅子に座っている。あともう一時間もすれば、この数々の物語が終わる。
そのフィナーレを前にして出番を待つ祖母の目には、安堵にも似た疲れが見えた。
母が入院するようになってからは、ずっと僕の部屋に来てくれていた。
大川という小さな町で呉服屋を営んで、僕のアパートまでは、毎朝、毎晩、祖父が車で送り迎えしていた。祖母を車から下ろすと、祖父は行きつけの弁当屋へ行って、お昼の弁当を買って大川へ戻る。店は老夫婦ふたりで切り盛りしている。町の人口も減って、呉服が売れるようなこともほとんどなくて、「毎日が休みんごたるけん」と、笑っていた。
祖母は、高校の卒業までは、今まで通りに僕の面倒を見させて欲しいと言うけど、県道を通って車で四〇分。毎日毎日その距離を来てもらうのは忍びない。
火葬を終え、母の小さな遺骨を集めて、桐の箱と遺影、葬儀場が用意してくれた仮の位牌を持って、祖父の車でアパートへと戻る。
寺への納骨はまだ先、四十九日の法要の日。父方のお寺にはお盆のお墓参りに行ったことがあるけど、大川のお寺はどんなところかも知らない。だけど母にとってはきっと、幼い頃からお盆が来るたびに花を供えた思い出の場所なのだと思う。母と過ごす最後の七週間。母の位牌も、四十九日を過ぎたら大川の家に戻る。
「そうだ、入院費」
ふと思い出して切り出すけれど、祖母は意外そうな顔で答える。
「勇は心配せんでっちゃよかたい。真雪さんから、葬儀代にちゅうて二百万出してもろうとっと。二百万は使いきらんけん」
父から?
「通夜んときは断ったとばって、そのあと電話ん来て、郵便受けに入れといたーち言うけん、急いでノリさんに取りに行ってもろうたとよ」
ノリさんというのは祖父のことで、名前の
記嗣からそう呼ばれている。
それにしても、最後の最後に父の経済力に支えられるなんて。
「もろうたぶんな、葬式代やら戒名代やら、ぜんぶ合わせたっちゃ少し残るち思うけん、あとはあんたが好きに使うたらよかよ」
祖母にそう言われても、僕はどう答えていいかわからなかった。
大通りから路地へ。車での移動は、通る道も、景色の密度も違っていた。喧騒もガラス越し。自転車に乗った友達は、他人の顔で信号を渡る。
アパートへ着くと、祖母も車から降りようとしたけど、祖父が引き止める。
「それじゃあ、また明日も来るけん、元気出さないかんよ」
そう言い残して、車は走り出した。
走る車の中で、祖母はまた泣いているんだと思う。今度は娘のことではなく、残された僕のことを思って。でも僕は大丈夫だから。きっと。
錆びた郵便受けを開けて、ここ数日封じられてきた息を吐き出した。読みもしないチラシ、読まれるはずだったチラシを束ね、鉄の階段に足音を擦りつけて二階へと上る。何日も留守にしたわけじゃないのに、部屋の扉は懐かしい。隣の部屋の枯れたアロエと、塗料の剥げたガスのメーター。ポケットの鍵を取り出して、ドアに手を掛けると、その向こうにあったいろんな景色が胸の中にあふれてくる。
でも、何もないんだ、このドアを開けても。
「おかえり」の声も、夕食の匂いも。
ドアを開けるときれいに揃えられて、母の靴。その傍には病院から引き上げてきた小さな紙袋が無造作に置かれている。母の靴を汚さないように靴を脱いで、
「ただいま」
静かに口にして部屋に入ると、胸に仕舞ったはずの現実が、そこかしこから覗き返してくる。
母が使ってたタオル。ドレッサー代わりに使っていた小さなチェスト。その上にならぶ化粧水、マニキュア、口紅と、ビーズを編んだマスコット。食器棚の母の湯呑を、柱に掛けられたバッグやマフラーを、ひとつだけ片付け忘れたクリスマスの飾りを、僕はどうすればいいんだろう。
しばらく横になっていると、姉からメッセージが届く。
――話したいことがあるけど、いまいい?
姉と母とはたまにやりとりをしているようだった。三年くらい前だったか、父の家を飛び出してきたことがあって、一晩だけ泊めて、それ以来だと思う。それで僕も姉の連絡先は知ってはいたのだけど。
――いいよ。
まあ、携帯でなら。
――わかった。いまから行く。
えっ? 待って。来るの?
しばらくすると、呼び鈴が鳴る。
携帯でいいのに、本当に来たんだ。
どうしようか戸惑いながら、ソックスハンガーが風に揺れたら、と思って待っていると、また呼び鈴。そして直後、今度は携帯に。
――今どこ? 家じゃなかと?
玄関を開けると、緩いカーディガンを着た姉の姿があった。
「缶コーヒー買うてきたたい。カフェオレがよかとやろ」
姉が手渡してくれたのは、アパートの近くのマイナーなメーカーしか入ってない自販機のコーヒー。
10円安い。カフェオレじゃないと飲めないなんて言ったのは小学生の頃の話。
姉は部屋に上がるとすぐに遺骨の入った桐箱を見つけて、膝を畳んで手をあわせる。桐の箱に並んで、まだ戒名もない白木に名前を書いただけの粗末な位牌。しばらく胸に手を置いて、言葉を選ぶようにして、「残念やったね」と、一言。僕はその言葉の意味を計りかねて、姉も自分の口を突いて出た言葉の意味を追いかけた。何年かぶりに交わした会話は、今まで通りを意識しすぎたのか、少しぎこちなかった。
「あとでマドレーヌ買うてくる」
と、姉は繕う。
ばたばたして考えが回ってなかったけど、そういえばお供え物もなにもない。姉は、母が好きだったものをちゃんと覚えていた。
「マドレーヌは明日焼くけん、他んもんがよか」
たったいま思いついたことを、最初からそのつもりだったように言うと、姉は、「じゃあ何か飲み物ば買うてくる」と笑った。
「と言うかあんた、マドレーヌ焼けると?」
「うん」
まあ、なんとか失敗しないくらいには。
「話って?」
「進路のこと」
姉は缶コーヒーを開ける。促されたような気がして、僕も。
「大学、行くとやろう? 学費はお父さん、出してよかち言うとるけん。それだけ伝えに来たと。一緒に住めとは言わんち言いよらす。こんアパートに住もうごたんなら、その金も出してよかち。高校卒業までと、大学の四年間は面倒みるち言うとらすたい」
矢継ぎ早に投げかける。
「要らない」
「要らないじゃなかろが。要ろうが。あんたの人生には要ると」
姉はやっぱり父さんに似ている。何を言っても僕の話なんか聴かない。それで少し言葉を探してると、姉も僕の言葉を探す。
「大川が支援してくれるとね」
そう聞いて、少しだけ僕の表情を待って続ける。
「じいちゃんばあちゃんもそげん裕福じゃなかよ。苦労するち思う」
「でも、お父さんから支援を受けるちゃ言えんもん。それはあのふたりから、希望ばむしり取るとこになるけん」
自分で自分のことを『希望』と言ったようで、ばつの悪さは感じた。姉は肩を落として視線を泳がせる。そのままゆっくりと滑らせる視線は、壁のハンガー、先月のままになったカレンダー、冷蔵庫に貼られたマグネット、ゆっくりと母の記憶を結んで、柱に掛けられたバッグに停まる。
「お母さんの形見、なんかひとつ貰うてってよかね」
「うん。バッグとかは使わんけん、欲しかとがあったら全部持って行って」
その言い方が気に障ったのか、姉はこれみよがしなため息をひとつ吐いて、立ち上がるとその視線をテーブルの上に留めた。
「これ、結婚式のときに用意せらしゃったカップやろ」
靴下で床を拭うようにして体を寄せて、カップを取る。
「私、このカップば配らっしゃったとき、お母さんのお腹の中におったとよ」
答え合わせを求めるように視線を投げて、僕は「うん」と口の中に呟いて頷いてみせた。当時、その意味はわかっていなかったけど、姉は持ち手が天使の羽根になったカップを、『フライングカップ』と呼んでいた。
「懐かしかー。好いとうたとよ、これ。『二ヶ月フライングして授かったけん、あんたのことよ』ちお母さん言うとらしたけん、
詩香さんには見せられんばって」
詩香さんというのは、いま父の家に同居してる人。姓は
向井。時期を見て入籍するのだと思う。
「大川は形見は要らんと?」
「要らんち。じいちゃんも、ばあちゃんも。実家にはお母さんの部屋が残っとうて、そこにこまか時からん思い出が残っとるち言いよらした」
「そうやね。形見っちゃ思い出の品やけんね。思い出もなしに物だけ貰うたっちゃ、しょんなかもん」
姉は柔らかな瞬きと、軽く触れる指先とで、母の思い出を集める。
「懐かしかね。お母さんの字」
冷蔵庫のメモ、カレンダーにも残る、少し丸みのある母さんの字。でも、そういうものだったら――
「押し入れに姉ちゃんの工作とか絵とか、いろいろ残っとうよ」
「えっ
!? なんで
!?」
「お父さんと別れたとき持ってきたごた。幼稚園の通園バッグやら、給食袋やら入っとう」
押入れの中には引っ越してきて六年間、開けもしなかったダンボールがあった。母が入院する段になってようやく寝間着や身の回りのものがないかと箱を開いた。
「ばって、まるまるふたつが学校関連のガラクタたい」
そう言いながら開けた箱の一番上に、筒状に丸めた画用紙がある。
「ガラクタじゃなかよ。宝物たい、お母さんには」
「そうやね」
姉が幼稚園の頃に描いた、青一色で塗りつぶしただけの「おふろ」。
僕が小学二年生の頃に描いた、「かいじゅうどうぶつえん」。
かいじゅうどうぶつえんには、怪獣の名前が書かれた付箋。そこにも母の文字がある。母が僕に聞いて、名前を書いて、付箋を貼った。その日のことはよく覚えている。
「期待されとうたとよ、あんた」
「そうかな……」
「あんたがちゃんと大学に行って、勉強して、ちゃんと働いて、ちゃんと家庭持ったら、お母さん、喜ぶよ。ぜったい」
「うん。それはわかっとう。ばって今は何も考えられん」
「来年もう受験やろ? 何も考えんで何もしよらんかったら、何もなれんとよ? お母さん死んでショック受けたけん無職になったとーとか言うたら、お母さん泣かっしゃるよ? そげんこつなったら私、お母さんの代わりに殴るよ?」
姉の髪からは高松医院の臭いがした。ときどき鼻先に思い出す、応接の革張りのソファと、壁に染み込んだ消毒液の匂い。木のテーブルの大きな節、大理石の灰皿、据え置きのライターと、
「勇はどげんすっとか」
という、父の言葉。
「あ、これ、覚えとう」
時間の糸のもつれにからまっていると、姉は先に行く。
「ほらこれ」
と見せてきた紙には、頭からミミズがたくさん生えた怒り顔のおじさんの絵。
「なにこれ?」
「覚えとらんと?」
「うん、ぜんぜん」
「大嫌いやった。こればっか描いとったけんね、あんた」
裏を見るとテスト用紙。小学四年生。でもそれ以上はわからない。
「いま、九大の文学部に通うとうと。本当は上智ば受けたかったとばって、まあ、私の成績じゃ難しかったけん。九大やったら哲学も心理学もあるち聞いてくさ……ツイッターもあったとよ、哲学研究会の。そいでホームページでシラバス見て、図書室の蔵書とかも聞いて、そいからやんけん、本気出したとは。去年はめちゃくちゃ勉強しとうた」
小さい頃の姉の成績は、そんなに良くなかったと思う。中学で伸びたのは覚えてるけど、上智なんて言葉を聞くとは思わなかった。
ダンボール箱から出てくる、図画工作や落書きの数々。名札、連絡帳、遠足のしおり。
「これ、お母さんの絵やろ」
姉はPTAの会報を開いて見せる。
「お母さんも、絵は
上手かったけん。描き慣れた人じゃなかとこうは描かんもん」
僕のテスト用紙の裏の落書きを褒めてくれたのはいつも母だった。父は決まって渋い顔をした。落書きの時間があるなら答案を見直せと、何度も言われた。
「お父さんとはうまくやっとうと?」
「できるだけ顔ば合わせんごつしとう。上智も反対されたけん。大学まではこっちにおれち言うて」
「僕もそげんなっとやろうか」
「あんた、東京の大学に行きたかと?」
「そうじゃなかばって、僕と姉ちゃんとで違うとやろかーて」
「そりゃ違おうたい。男親は娘は外に出さんけん。特に九州んもんはそげんち、ネットにも書かれとう」
そう吐き捨てる姉の顔に、寂しさのようなものが見えた。諦め、悔しさ、いくつかの色が混じった名前のない表情。僕は西町高校だし、東京の大学へ行くやつはそんなにいない。でも姉は有数の進学校。周りが上を目指す中で夢を諦めるのは辛かったと思う。
「大学出たら家ば出るけん。あと三年半。お母さんのごつ出口んなかわけじゃなか」
威勢の良い姉の言葉も、少し歩調を緩めた。止まりかけたその言葉の行き先を探していると、姉の手が不意に止まる。小さく折りたたまれた紙切れを広げて、僕の顔を見る。
「どげんしたと?」
姉から渡された紙切れには『借用書』と書かれていた。
「お母さん、借金しとうたと……?」
戸惑った。生活が苦しいのは知っていたけど、人からお金を借りてるなんて思わなかった。サラ金でもなさそうだし、その先には僕の知らない人間関係がある。姉の手が書類を探る中、僕は自分の気持ちの揺れを抑えるだけ。
「お母さん、結婚してから、働かせてもろうとらんやんね。自由に使えるお金がなかったとよ。いくらかあるち言うたっちゃ、自由に習い事したり、コンサートに行ったりするわけじゃなかろう?」
姉はフォローするけど、僕の思考はどこかに巻き取られたまま。
「気にせんでよかよ。こげんとはぜんぶお父さんが悪かつやんけん。お母さん、悪うなかとよ」
「もしかして、お母さんの借金が離婚の原因やったりしたとやろか」
胸に浮かんだ言葉が、思考を通すことなく口を突いて出る。
姉はまた、ひとつため息。
「あんたが庇ってやらんでどげんすっと」
そう言うと、黙々と借用書のカーボンコピーと返済証のペアを作って並べる。
「バイトするち言うたら、反対されたと」
今のもそうだ。何も考えないで言葉だけ出てきた。答えが欲しいわけでもない。姉はもう何も答えない。沈痛な面持ちで、母の過去を占うように、証書を並べて、ただ一枚だけ、返済したとは言い切れない借用書を見つけた。
金額は三万円。
「給料日前にやりくりつかんごつなって借りたとじゃなかと? この直後に入院しとるやんね。それで返せんごつなったっちゃろ」
貸し手は福岡市中央区
警固、カコエオフィス、
加古江郁人。
「かこえいくひと……ち読むとやろか?」
「わからんばってん、返さんでよかとやろか」
独り言のように漏らす姉の言葉に、僕も独り言のように応えると、時計の針は意味のない時の長さを数えはじめる。
「えっ? 何て?」
証書を眺めていた姉が、少し遅れて反応する。
「返すって、どげんして?」
「どげんて、会うしか無かばって……」
「会う
!?」
姉が目を丸くして、僕の顔をのぞき込む。
僕は目をそらして、小さくうなずく。
「うん」
会いたいと思った。
お金を返したいと言うよりは、母にお金を貸した人がどんな人なのか、会って確かめてみたいと。
第二章 金の雨
風にカタカタとソックスハンガーが揺れる。
うちは呼び鈴の代わりにソックスハンガーが鳴る。なぜか。
玄関を開けると、祖母と、メガネをかけた見知らぬおじさん、その奥さんらしき人。
「勇くんね? 大きくなったねえ」
知らないおじさんが顔を綻ばせると、祖母が僕の戸惑いを察する。
「お母さんの従兄弟の
俊彦さんたい。こっちは奥さんの
佳奈さんよ」
紹介されると改めてふたり、頭を下げる。
「裕美さんに、線香ば上げさせてもらおうち思うて」
おじさんが言うとすぐに祖母が割り込んで、
「用意しとらんやったら、持ってきたとがあるけん」
と、手提げ袋から線香の箱を出して見せてくれた。
喪服姿の大柄の男は、不器用に足を上げて靴を脱ぎ、背をかがめるようにして部屋に入った。祖母は僕に線香とマッチと、用意してきた道具を渡してお茶の準備を始め、ガスの火が灯ると、しばらく喪に服していたこの部屋も、ようやく動き出した。
車を停めに行っていた祖父も加わり、おじさんたちの話がしばらく続いて、その間、僕と母は少し外れて聞いていた。だから、
「ばってん……」
と、祖母が切り出したとき、そこまでの話の流れは、よくつかめていなかった。
「アパートの名義ば変更せにゃいかんとよ。不動産屋さんに聞いたら、勇は未成年やけん、契約できんち言わしゃったい。四十九日までは待ってもらうごと頼んどるばってん、そいまでん後見人ば決めないかんと」
まだ母が息を引き取って三日。それなのにもう、世界は別の時間へと移っているようだった。
「後でよかろうもん、四十九日まで待ってもろうとるなら、そんとき決めたらよかよ」
「そげん言うたっちゃ、後見人の手続きにどんくらい時間がかかるか、あんた、わかるとね?」
母が作った銀行口座はふたつ。ひとつは母名義の生活費の口座。もうひとつは僕の名義で、毎月一万円が積み立ててあった。その積立も途切れ途切れ。残高は十八万。生活費の口座には二万。電気代や水道代の引き落としがどうなるのか、父からの養育費は。不安ばかりの四十九日と、その先の暗闇と。
「今じゃのうてよかけん、覚えとかんね」と、祖母。
「ばあちゃんとじいちゃんが養子にしてもよかし、後見人になったっちゃよか。ばってん、決めきらん。勇が真雪さんの方がよかち言うなら、うちらが何か言うたっちゃ、どんこんならん。向こうは医者やけん、お金は向こうのほうが持っとらすたい」
借金の証書を見た時は正直、何のための借金なのかと思ったけど、生きるためなんだと、今更ながら。
金曜、一週間ぶりに出すゴミの呆気ない量の、その隙間に溜め息を詰める。ぽつりぽつりと行き交う人の、互いの胸の内の知り得ぬことの気楽さと、寂しさと。胸につかえるばかりの大きな何かを出しそこねて、太陽はまだ低く、僕の背中の向こう。でも十分な熱を届ける。
ソックスハンガーに靴下を三本吊るすと、その日は矢口がうちに来る。矢口用の靴下の吊るし方は三パターン。中でも一番確率が高い吊るし方を試すと、昼頃にようやくハンガーが揺れて、夕方、予定通りに矢口が来る。
矢口との付き合いは長い。同じ中学を出て、同じ高校へと進んだ。下の名は
慶輔、軽音楽部。もう僕しかいない部屋に、おじゃましますと言いながら、おずおずと入り、母の遺骨を納めた箱を見留めると、指差して、僕の方を見る。
「よかよ、気にせんで。それよか、授業のノートば見たか」
「いや、気にするやろ。あの、あれ。線香とか。なんか、ほら。あるやん」
たどたどしく位牌の前に座り、手を合わせ、線香を上げる。
「もっと落ち込んどうち思うとった」
「落ち込んどうばって、でもなんか、ホッとした。やっと日常が戻って来た」
「ああ。日常、イズ、俺?」
矢口のノートを見て、要点だけ書き写す。
「そげーんは進んどらんごたる」
「そう? 毎日学校行っとるけんわからん。テレビは見とうと?」
いや、テレビは見とらん。ネットばかり。うん、俺もそう。でもたまに見る。ニュースがいちばん面白か。ちゆーか、ニュース以外はネットでよかもん。
矢口とはいろんなことを話せた。このアパートを引き払い、大川の祖父母の家に世話になるかもしれないことも、ぜんぶ話した。
祖父母の家には行ったことがない。母も敷居が高いのか、足を向けることはなかった。祖母に聞いた話では、西鉄の駅から車で十分、自転車でなら二十分ほどの場所。バスは一時間に二~三本。それも二十時には終わる。
「でも、卒業するまで一年ちょっとやん。学校からなら十五キロくらいやけん、チャリでなんとかなるっちゃなかろうか」
「親父さんの家は、六ツ門ち言うとったろ。そこからやったら、学校まで十分くらいしかかからんけん。絶対そっちがよかよ」
「ばってんくさ。母親の実家に世話んなるか、父親に世話んなるか、通学距離で決めんめえたい」
窓の向こうは二層の空。十月にもなると、六時前には日が落ちる。迫りくる冬が夕方の時間をどんどん削って行く。カラスの鳴かない夕焼けを捕まえ損なっていると、いつの間にか冬になる。
「明日、行ってみらん?」
不意に矢口が切り出す。
翌日、十月八日、土曜日。祖母に電話。
友達と二人でチャリで遊びに行くことを伝えると、「泊まって行くとね?」と声が返る。
「いや、日帰り。ちゅーか、休んだらすぐ帰るけん、麦茶だけ飲まして」
「そげんこつ言わんで、泊まっていかんね。裕美の使うとった部屋があるけん」
その電話を矢口が隣で聞いて、あれこれとジェスチャーで示す。
――俺、ばいばい、おまえ、おやすみなさい。
「じゃあ、わかった。友達とふたりで行くばって、僕だけ泊めて。昼過ぎに着くち思うけん、近くまで来たらまた電話するたい」
高校の門の前で自転車にまたがり、十時ぴったりになるのを待って、ペダルを踏み込む。矢口のロードバイクが先行し、その後を追って僕のギアが付いただけの普通のチャリが走り出す。校門からまっすぐ、西町高校前の交差点へと向かい、毎朝通い慣れた県道へ出る。そのいつもと変わらぬ車の流れの、いつもと反対側、南へと向かって、すぐに目の前に現れる踏切を渡る。
「西鉄やろか?」
矢口が振り返って僕にたずねる。
久大線やろ。普通に考えたら。と、思いながら、
「銀河鉄道やろ」
「マジか!」
道路ぎりぎりまで建てられた家と、道に迫ってはまた離れていく塀と、すれ違う車、追い越す車。その頭上を九州新幹線の白い龍が、咆哮を上げて飛び去る。在来線の踏切。降りてくる遮断器。鐘の音とともに、足止めの赤い光。
南下すると視界には田畑が増えてくる。右手に西鉄大牟田線。特急列車が並走すると、クランクシャフトの足がペダルを回す。
「カンパネルラーーーーッ!」
矢口が腰を上げて左右に身体を揺らしながら叫ぶ。
「ジョバンニーーーーッ!」
肩のハッチが開いて水蒸気を上げる。吠える僕ら。右手に小さな駅舎を見つけると、足を浮かせて、慣性のまま滑り込む。その駅を越えて大牟田線を横切り、県道二三号線へ。車の量も増えて、少しチャリには厳しい。さっきまで見なかった大型のトラックとたまにすれ違う。
「富松んげがこのへんにあるたい」
「演劇部の?」
「ラグビー部の方。ちゆうか、両方たい」
三潴を超えると、車は少なくて走りやすい。しばらく命の危険を感じない田舎道が続いて、県道七一〇号線に接続するあたりで道は狭まる。自転車を想定していない田舎道。大型車に押し出されたら田んぼ直行の細い道で、後ろから、前から、車がすれ違い、国道を横切る交差点の信号が、僕らの足を止める。
「今日のスピードで毎日ここ走っとったら、いつか死ぬて」
汗が流れる。まるで季節をいくつか遡ったように。こうして額を汗が伝った日の昼下がり。あのとき、なんのために、何を思って走ったか。脳裏をよぎる蝉の声を追った。
そこからはペースを落とした。今まで見過ごしてきた水路や川を眺めたくて、道路の右へ、左へ、渡りながら。小さな淀んだ水路にゴイサギを見つける。水は目にしただけで疲れを癒やした。
花宗川を越えて少し行くと、矢口が不意に自転車を止めて、「ここ――」と、指差す。
「うちに来よらす看護師さんの出た学校ばい」
見上げると、看護学校の看板がある。
「ラインで送っとこ」と、案内板の前で写真を撮って、携帯を僕に渡して、再度案内板の前でポーズを取る。
「看護師さんとラインしよると?」
「たまに。その人もギター弾きよらすけん」
矢口の家も病院。僕の父の高松医院よりはずっと大きな、入院用のベッドもある内科。矢口の兄が一浪して医大に入ったと聞いたのは、たしか去年。
お前は?
俺はミュージシャンになるけん。
じゃあ、進路は?
いちおう大学は行くばって、勉強せんでよかとこがよか――
「ギターちゆうかベースばってん、学生の頃から弾きよったち言うとらしたけん、ここ通いながら弾いとったとよ」
地図で場所を確かめて、二本目のペットボトルを開け、祖父母の家に電話をかける。
ここからはもう、目と鼻の先。のんびり向かっても十分。最後に時間を確認したときは十一時半だったのに、時計はもう十二時を回っている。自転車を走らせるペースは更に落ちた。
ここが大川のどのあたりなのか。地図ではわかるけど、市街地なのか、はずれなのか。家具屋も金物屋もシャッターが閉まり、そのシャッターにも錆が浮いて、その並びに祖父母の呉服屋がある。
表に出したワゴンに並べられた手ぬぐいや巾着。戸惑いながら引き戸を開けて、こんにちは、おじゃましますの僕の声の終わるのを待たずに、祖母の「いらっしゃい、待っとったとよ」の声がかぶさる。一段上がった畳の間、火鉢があり、奥の壁には作り付けの箪笥。
「冷たかお茶のほうがよかろ?」
と祖母は、わざわざ氷の入った麦茶を用意してくれた。
「横んなってよかよ。疲れとろうたい」
麦茶を飲み干すと、思い出したようにまた汗が吹き出す。古びたデザインの扇風機が静かな唸り声をたてて、柔らかな風を部屋に巡らせる。
「久留米から自転車でどんくらいかかるとね」
老眼鏡を外してケースに仕舞い、祖父がたずねる。
「どんくらいやろか。国道んとこで、一時間五分ち言うとったけん……」
「国道ちゅうと……」
「五叉路んとこやろ。なんとか橋南の」
「ああ。自転車やったら、あすこからでっちゃ、かないかかっとやなかと」
若っかけん、裕美ん子やけん、祖父も祖母もしきりに誉めそやし感心していたけど、正直、これが毎日となると辛い。
祖母はアルバムを何冊か抱えてきて、子供の頃の母の写真を見せてくれた。矢口にしてみたら、見てもしょうがない写真。祖父が撮ったらしい祖母と母の二人の写真が続くなか、矢口は一枚の写真を指差した。
「筑後川昇開橋ですよね」
写真には、昭和の初期に作られた可動式の鉄橋があった。旧国鉄の単線の線路が通り、船と列車の運行に合わせて橋桁の一部が垂直方向に上下する鉄骨の橋。昭和の終わりに廃線になって、今は遊歩道として整備されている。と、祖父の説明で知る。写真には赤い鉄橋の手前、幼い母の姿があった。まだ小学校に上がる前。淀んだ空。しかめっつらの手に、ネコのぬいぐるみ。
「この橋、このへんにあっとですか」
矢口が関心を寄せていると、祖父が更に別のアルバムを持って来る。モノクロの頃からの写真。そこにもまた、若き日の祖母の背景に、筑後川昇開橋の姿がある。まだ母が生まれる前。二両編成の列車が走る。この頃からずっと祖父は写真を撮り、モデルは祖母か、母だった。
矢口が帰ると、途端に静かになった。
しばらくすると、筑後川昇開橋まで足を伸ばして、自撮りした写真が送られてきた。
一枚、また一枚と、スマホが鳴る。
「裕美の部屋ば片付けといたけん、今日はそっちに泊まっていかんね」
祖母の声に振り向くと、細い手にはおろしたてのパジャマがあった。そう言えば、泊まる準備を何もしていない。
「売れ残りで、ずっと箱に入っとったばって、虫に食われたりはしとらんごたる」
表、裏、と返して見せる祖母に礼を述べて、携帯に送られてきた矢口の写真を見せる。パジャマを受け取りながら、写真をスワイプして見せて、僕も祖母もまだ、どのくらい笑っていいのかわからず、浮き輪の空気を少しだけ抜くような笑みをこぼした。
母の部屋は二階にあった。
壁の染み、床の傷に気を取られながら、階段を軋ませて、案内されされるがままに中を覗くと、そこは踏み込むのを躊躇われるような、女の子の部屋だった。
「二十歳の時うちば出て、そん時んままんなっとう」
呆れたような、憂うような声で笑う。クリーニングから戻ったまま吊るされた外套を片そうとするので、「よかですよ、そのままで」というと、「勝手に部屋ば使うと、裕美に怒らるっけん」と、苦笑いした。
僕が知ってる母は、四十代。だけどこの部屋にいたのは違う。壁に残るポスター、本棚、机、そこかしこに染み込んだ、僕と同世代の女子の匂いが、古い木肌の中に息を潜めている。ドレッサー代わりにしたチェスト。三月のままのカレンダー。コルクボードに貼り付けられた雑誌の切り抜き、糊が滲んだシール、メモに残る蛍光ペンのかすれた文字、空の本棚。
その空の本棚に一冊だけ少女漫画誌が置いてある。祖母は僕の視線に気がついて、その本を取って、ページをめくり始める。
「ほら、ここ」と言って止めたのは、読者投稿のページだった。
「裕美の漫画が佳作ばもろうた時の号だけ出しとうと。あとはぜんぶダンボールに入ったまんまなっとう」
母が漫画を?
祖母の言葉の意味を、にわかには理解できなかった。
「専門学校ば出てから、東京に行って、漫画家さんのもとで絵ば描いとらしたとよ。その時、漫画は全部持って行ったとばってん、こっちに戻って来る時、もう漫画は卒業するち言うて、ダンボールに入れてうちに送ってきて、そんままんなっとう。漫画じゃ食べていかれんけん、区切りば付けたかったとやろ」
そう聞いても、僕の中ではまだ情報がつながらない。どのくらい本気だったのか、もしかして家族には隠しておきたい過去だったのか……。でも、東京に行ってたって……。目の前に差し出された本を、母の絵をこぼさないように、静かに受け取る。
「この投稿作ちゃ、どげな漫画やったとですかね」
「いっちょんわからん。わかっとうとは、『風使いの翼』ちゆう題名と、ペンネームの『
流沙ルカ』だけたい」
あとは掲載された一枚の絵、ヒロインがマフラーをたなびかせてビルの屋上に立ち、憂いのある目で腕組みをしている。
デビューした漫画家だったら、どんなに無名でも掲載された雑誌は探しようがある。だけど、投稿作のタイトルしかわからなかったら、その先は追いようがない。
――キャラクターへの愛は感じられるけど、少し思い込みが強いのかも。冷静にキャラの動きを捉え直してみると、もっとストーリーに深みが出ますよ。(美どり)
――絵は少しぎこちない。でも描こうとしてるものははっきりしてるし、デッサン力も構成力もそれに合わせて伸びていくでしょう。(あゆ)
――コマとコマのつながり、展開の単調さには気をつけて。セリフのセンスは抜群、今後の躍進に期待大。(P介)
胸の中で小鳥たちが騒ぎだす。今まで投稿漫画の評価ページなんてまともに読んだことはなかった。まるで自分の漫画が評価されているようなときめき。嬉しさと、気恥ずかしさ。母さんもこの部屋で、このページを読んで、同じ胸の高鳴りを感じたんだ。この瞬間、何かが始まったんだ。母さんの胸の中で。
「あのう……これ……」
僕は母が送りつけたというダンボールを指差した。
「開けてもよかやろうか?」
「よかよ、あたりまえやんね。勇に読んでもろうたほうが裕美も嬉しかろうたい」
祖母はそう言うと、晩ごはんの準備があるからと踵を返す。
「あ、晩ごはんは僕も手伝うけん」
「よかよか。お客さんやけん、ゆっくりしとうたらよかと」
「ばってん……」
「この部屋には、まだ裕美がおるとよ。あんたの姿ば、ちゃんと見せてやって」
涙目でそういうと、祖母は階下へ降りた。
半年ほど前、押し入れのダンボールを開いたのは、母とのお別れが近いことを知らされた頃。母の寝間着になるもの、コップやタオルを探すため――と思ったけど、それも口実でしかなかった。
「お母さんの着替えば探しよったら、こげなもんば見つけた」
そう言って、笑いながら病室に入るきっかけが欲しかった。
ねえ、母さん。
開けてもいいのかな、この箱。
中身は漫画なんだよ。
どこの書店でも手に入るような。
アルバムのように姿が写ってるわけでもないし、文字があるわけでもない。だけどもしかしたら、母のいちばん大事なものかもしれないとも思う。心の震えが伝わったかのように手が震える。喜び、懐かしさ、感激、寂しさ、心のなかでルーレットが回り、僕の顔も多分、パタパタと切り替わっているのだと思う。
手の震えを抑え、《再会の喜び》、でルーレットを止めると、箱の中にはぎっしりとコミックスが詰まっている。
天を上に向けてきれいに並べられた本の、その中の一冊を引き出して見ると、それは僕がぼんやりとしか聞いたことのないタイトル。『天使なんかじゃない』の四巻。生徒会を舞台にした学園もの。これは全部で八巻あった。そのとなり、花より男子、また隣はフルーツバスケット、それから天使禁猟区、動物のお医者さん、ぼくの地球を守って、赤ちゃんと僕と続く。別の箱を開くと、うしおととら、るろうに剣心……この箱は少年漫画が入っている。幽遊白書、みどりのマキバオー、ダイの大冒険、スラムダンク。
中でも一番読み込まれていたのは、どうやら『ぼくの地球を守って』。奥付を見ると、母はまだ小学生か中学生の頃。十四巻以降は初版。きっとその頃に嵌りだして、そこからは発売日に買ったんだ。
祖母と夕食の洗い物を済ませて、お風呂を頂いて、母の部屋へ駆け上がると、もうそこは知らない女の子の部屋じゃない。ベッドに転がりながら、一巻から順にページを捲る。
高校生として地球に転生した異星人たちの話。
二巻、三巻と続けて読んで、中断するタイミングを見失う。
そのまま七巻あたりまで読み進めて、いつの間にか眠りに落ちて、夜、目を覚ますと、部屋には母の姿があった。母は学習机の椅子に座り、僕がベッドに積み上げた本の一冊を開いて目を落としている。
「お母さん? なんばしよると」
「なんばしよるち、見てわかろうもん。漫画ば読んどうたい」
「死んだっちゃなかと?」
「死んだっちゃ、漫画くらい読もうもん」
そうか。
でも、そう言うものなのかなあ。
「成仏しとらんと?」
「そげん、幽霊んごつ言わん」
「ごめん」
「やっぱ、面白かー。中一んとき、友達に薦められて読むごつなって、持っとるけん貸すち言われたばってん、ぜんぶ買うて揃えたもんね」
漫画の話、たまにしたけど、母もそんなに漫画が好きで、ましてや描いていたなんて。
「あのくさ」
「なん?」
「お母さんの描いた漫画くさ、どげな漫画やったと?」
「どげんちゆうか、いろいろ描いとったけん、一言じゃ言いよらんよ」
「投稿作の、佳作の漫画は?」
「ああ……ペルセウス座流星群の話やなかったろうか。流星群に乗って、ゴルゴン軍団の降ってきて、地球ば破壊すっと」
「『風使いの翼』ち、SFやったと?」
「SFじゃなかよ。ラブコメばい」
「お母さんのセンス、どげんかしとっちゃなかと?」
母は僕に目もくれずに漫画を読んでいる。
「お父さんと別るっとき、あんたがどげん言うたっちゃお母さんじゃないといかんち言うたやんね。あれ、嬉しかったとよ。あんたが、『絵ば描きたか』ち言うけん。男の子の育て方はようわからんち思うたばってん、あんときのあんたん顔ば思い出すと、弱音は吐いとられんち思うて……」
「うん。たまに後悔しとったとよ。足枷になっとうとじゃなかろうかち思うて」
「足枷じゃなかよ。生きがいやけん。最初はどげんしゅうかーち思ーて、しばーらく悩んどったばってん、あんたちゃんと育ったやん。お母さんも、お父さんも、よか孫に育ったち言うて笑とらすたい」
この母は幻覚だ。だとしたら、その言葉は僕の言葉で、『よか孫』というのも自分で言っているのかと思うと、気恥ずかしさがあった。
「なんでこげん、ちゃんとした子に育てられたかわかると?」
「急に何? 急に聞かれたっちゃわからん。なんで?」
「あんたん中に、私が読んできた漫画の主人公がぜんぶ転生しとうとよ。あんた、お母さんの作り上げた最強の転生系主人公ばい」
「はあ?」
母は振り向いて、微笑む。
「こげんしてお母さんの姿が見えて、話ばしよっしゃんやんね。それがあんたの力よ」
「うん。わかるばってん。いや、ようわからんよ。なんねそれは。て言うかさ。ねえ、お母さん」
「なんね」
「僕はどげんしたらよかと」
「そうねえ……明日うちに帰ったら、手紙が届いとるけん、そいば読んで、書かれとる通りしたらよかよ。よかち言うか、して。書いとるけん、その通り」
「ああ、うん、よかばって、手紙ち、なん? お母さんが書いたと?」
「未成年後見人ば選ぶとに、司法書士さんに遺書ば預かってもろうとると。その人から今日手紙の行っとるはずやけん、忘れんごつ読んどいて」
「ちょっと待って。後見人ってだれ? 僕の知っとう人?」
「知っとうはずよ。言うたこつあるもん」
母は読んでいた漫画を置いて、大きく伸びをした。
「そろそろ眠なって来たけん」
そう言うと母はベッドに横になって眠った。
幻覚にしては実体がある気がして、顔に本を乗せてみると、乗った。
五冊くらい乗せて、
「お母さん。リアクションの足らんばい」
と言うと、「なんばしよるとね、もう」と言いながら、全部払い落とされた。
これはたぶん、実体のある幻覚だと思う。
時計は朝の六時。階下からは朝食の準備を始める音が聞こえてくる。
母にベッドを占拠されて……いや、もともと母のベッドなのだけど、僕は行き場をなくして、ベッドの端に座って漫画の続きを読んで、やがて階下から朝食の準備ができたと告げられ、朝食を取り、もう一度部屋に戻ると、ようやく母の実体のある幻覚は消えていた。
九日、日曜日。
午前中には大川を発ち、ちょうど十二時を回るころに荘島町のアパートに着く。
郵便受けには母の言った通り、どこかの司書からレターパックが届いていた。
いくつかの書類や、写し。添えられた手紙には未成年後見人の名前と、その人の顧問弁護士の名前、もうすぐ死亡保険が振り込まれるので、そのことを親戚に知られないようにと警告されていた。
未成年後見人の名は
島津国之、住所は東京都練馬区。聞いたことのない人。必要な時は司法書士さんを通して連絡すれば、ほとんどは向こうの弁護士さんのほうで処理すると確認は取れているらしい。その際に必要な経費の請求は僕に来るけど、そこはこちらの司法書士さんも相談に乗ってくれる。成人するまでは親権に関して心配する必要がないように手配されていた。
保険金の額は一二〇〇万。数日内に振り込まれるという。
遺書に添えて、母から僕への手紙もあった。
ガスや電気の払込先、学校や市役所の連絡先、自治会の細かい決まりごとが書かれ、最後は、
――大川の祖父母、私の両親、樺島記嗣と京子のふたりを決して信用しないでください。私はあなたのためだけに財産を残しています。あなたの人生のために使ってください。
と、締められていた。
第三章 流刑の島
高架下に自転車を停めて、西鉄久留米駅の改札へ向かう。
母が借金をしていた加古江という人のオフィスは、福岡の警固というところにあった。
旅らしい旅をまだしたことがない。友人からよく、東京へ行った、バルーンフェスタを見てきたと聞くことはあったけど、僕には縁のない話。友達同士でキャンプに行って、潮騒を背にラジオから流れる曲を聴いた――なんて思い出話を、地元のフードコートで聞いた。僕にとって旅の記憶と言えば幼い頃の、荒尾の潮干狩り、
志賀島の海水浴。
特急に乗って、椅子にも座らずに窓の外を見て、刈り取られた田んぼに馬を走らせる。真っ白い馬。弓を持った乗り手。土手を駆け下りて、川を超える。
薬院駅に停車した時、クラスメイトのことを思い出した。
通っていた小学校の近くの美容院の一人娘、
伊藤芽郁。五年生の終わり、僕が転校するまで同じクラスで、中学でまた同じ学校になったけど、その時はもう垣根が出来ていた。今は薬院にあるモデル事務所に所属していると、共通の友人から聞いた。
「伊藤はアイドルになるつもりでおると?」
矢口に聞かれたことがあるけど、同級生がアイドルというのは奇妙に感じた。とくに伊藤は。あの頃の伊藤は、野球がやりたいと言っていた。
福岡駅についてホームに降りると、その風景にはかすかに見覚えがあった。駅ビルを出て、少し薬院側に戻って、警固公園の向こう、
国体道路を西へ歩く。
小学校の五年の時だ。伊藤のことを好きになったのは。放課後、なんとなく教室に残って宿題をしていたら、伊藤が入ってきて、「勇だったらいいか」と言って体操服に着替えた。今思えば馬鹿にされてたんだと思う。でもなんとなく、それから意識するようになった。
「勇だったらいいか」
伊藤が僕のことを嫌いだって気がついたのはその四年後。四年間ずっと勘違いしたまま、彼女のことが好きだった。今もたぶん好き。だけど、会うのは怖い。このあたりはもう薬院にも近い。もしかしたら歩いてるんじゃないかと、すれ違う人の顔ばかり気になる。
カコエオフィスは通りの突き当り、低層マンションの三階にあった。
一階はリカーショップ。だれとすれ違っても、その人が加古江郁人本人かもしれないと思う。郵便受けを見て、カコエオフィスの名を確認して階段を上る。三階。廊下を少し歩くと、玄関に貼られた小さなネームプレート。
来たんだ。
息を整えて呼び鈴を鳴らす。
自分の心臓の音が聞こえる。
伊藤を誘いに行った時がこうだった。
あのときは恋をしているからだと思ったけど、案外恋って関係ないんだな。
しばらく待っても反応がない。これもあの時と同じ。
振り返ると、広い緑地が広がっている。
どこかコンビニに寄って、パンでも買って食べようと、肩を落として階段を降りる。
エントランスに戻ると、扉を開ける男の姿が見える。白と黒のサテンのスカジャン。男も僕の顔をじっと見つめている。背丈は僕と同じくらい。スカジャンの胸には翼の刺繍。すれ違い、背中を見ると、ペガサスの刺繍が見える。
通夜の夜に見たスカジャン。ヒロ叔父さんじゃなかったんだ。
「加古江さんですか?」
その背中に、声をかけた。
「ああ、もしかして」
相手の男も振り返る。
「樺島さんの……?」
「ええ、息子の勇です」
「道理で見覚えがあると思った。ええっと」
加古江さんは急なことで戸惑っているようだった。
「お母さんのこと、お悔やみ申し上げます。通夜には行ったんだけど、勇くんとは話せなくてごめん。とんぼ返りだったから」
「あ、いえ、わざわざありがとうございます」
「ここじゃ何なんで、飯でも?」
「いや、僕、お金ないんで、どこかでパン食べてまた来るです」
加古江さんは笑った。
「大丈夫。君のお母さんには世話になったから。奢るよ」
通りへ出るまでに、今日の目的――母の借金のことはあらかた伝えたけど、加古江さんは聞いていない素振りで、母の思い出を語った。
繊細な絵を描くひと。妥協を許さないひと。それからちょっと、おっちょこちょい。
うつむいて、つまさきで次の言葉を探すように、ぎこちなく歩いたビルの一階、イタリア料理店のドアを開ける。表に出た黒板には、なんとかのマリネ、なんとかのリゾット、なんとかのなんとかソース。サラダ以外はほとんど千円を超える。
席に通されて、腰に椅子を下ろ、椅子に腰を下ろす。
加古江さんはメニューを僕に向けながら、本題に入る。
「借金はべつに返さんでいいよ。返ってくると思って貸した金でもない」
「ばってん」
「よかよ、あとで。先にメニュー選んで。黒板の方にも書いてあるけん」
加古江さんは、カウンターの方、イラスト付きでメニューが書かれた黒板を指差す。その情報量。書いてある単語の意味の半分はわからない。戸惑っていると、
「わかった。じゃあ、嫌いなものはある? 食べられないものがあったら言って」
と、メニューを取り上げる。
――覚えてる。
メニューがすっと、僕の手を抜けたこの感覚、この瞬間を。昨日のことのように。
ケールのサラダと、桜えびのペペロンチーノ、スズキとそら豆のプレゼ。
あの頃のうちの食費に換算するとたぶん、一週間分――
加古江さんが何か言った気がした。
視線を上げて覗き込んだけど、不審そうな顔をして問い返す。
「ん? どうしたの?」
「いまなんか、言いませんでしたか?」
「言ってないよ」
メニューを戻して、おしぼりで手を拭いて、悪戯な目を向ける。
「きっとそれは、あれだ。言葉が勝手に脳内で再生されるやつ」
そう言うと加古江さんは、塩の容器と胡椒の容器をテーブルに並べてみせた。
「こうやってよく話をさせていたよね、裕美さんも」
容器の頭を指でつつくと、塩と胡椒の容器が、母の声色で話しはじめる。
――料理をおいしくするのがボクたちの使命じゃないの
!?
――おまえはいいよな、気楽で!
加古江さんは加古江さんで、別の物語を描いているのかもしれない。僕と同じように、静かにテーブルに目を落としている。
やがて目の前に運ばれてきたサラダは、公園に生えてる葉っぱのようだった。
――葉っぱ? 公園に生えてる葉っぱ?
――しょうがないよ、この子、そんなに高級なもの、食べたこと無いんだから!
塩と胡椒とに演技をつけながら、ときおり僕の目を覗き込む母が、まだそこにいる気がして、僕は胸の中身をこぼしそうになる口を、葉っぱで塞いだ。
「裕美さんは、僕の先輩。ふたつ上だったかな」
加古江さんは桜えびのパスタを食べながら語り始める。
「道具の使い方を教えてもらったり、細かいテクニック、あとは心得とか、いろいろ」
母はデザインの専門学校を出たあと上京して、有名な漫画さんのアシスタントをしていたらしい。そこにあとから来たのが加古江さん。先生は当時人気実力トップの人で、今はその下で描いていた人たちがメインストリームを席巻していると言う。
「トップチームにいたんだよ。僕も、裕美さんも」
チームと言われても。漫画って個人で描いて、アシスタントっていう手伝いの人がいるものだと思っていた。
「違うよ。チームだって意識がないと作品はできないよ。映画はチームで作るでしょう? たとえば照明の人は、その照明の仕事で自分の人生を支えてるんだよ。そこには仕事への誇りと責任がある。漫画も同じだよ」
加古江さんはずっと視線をそらしたまま。たまに顔を上げて僕の顔を覗く。
「僕はまあ、いろいろあって、漫画はすぐに諦めたけどさ。それからバイトしながら雑誌のカットを描いて、ちゃんと金が回るようになったのはつい最近だね」
そうなんだ。じゃあ、母さんは?
「裕美さんはねえ……」
加古江さんは、そう言って口ごもる。
「本人には聞いてないよね」
「ええ、何も」
「僕に言えることはそんなにないし、間違ってるかもしれない。それでも敢えて言うとね、真面目すぎたんだよ。たぶん」
そう言うとため息をついて、皿の上にそら豆を並べて、遠い過去を覗き込んだ。フォークを持つ手の親指と人差し指の間に、大きな傷の痕が残っている。
「僕も正直、無理だと思ったんだ。裕美さんは。なんていうか、ふんわりしてるって言うか。周りはみんな化け物なんだよ。凄まじいスピードで、とんでもないクオリティの絵を上げる。その中で、彼女はいつまでも一枚の絵に線を入れてるんだよ。もちろん、そこを先生は買っていたと思うんだけど、周りがどんどん独立する、ピンで仕事取ってくる、賞を取る、そういう中で、自分の作品はこれでいいっていう気持ちを維持するのは難しいんだよ」
そう言うと気持ちをごまかすような笑いを一つ挟んで、ひとつ首を傾げて、まばたきを二回して言葉を続けた。
漫画は……漫画だけじゃないかもしれないけどさ。最初はどこまで出来るかという戦い、次に来るのは、いつ身を引くかという戦い。何かのきっかけでヒットする可能性は常にある。決定的に駄目な瞬間なんていつまでも来ない。その中で、どう自分を納得させて、どこに自分の場所を定めるか――
加古江さんは見ていたんだ。大川の母の部屋に残されてたカレンダーの少し先から、九州に戻って父と結婚するまで、一番希望に満ちあふれていた母と、その光を失っていく母を。
「最初に先生に会ったとき、食事に連れて行かれてね。ちょうどほら、今みたいな感じで。その時、裕美さんもいたんだけど、先生はその店の主人を呼んで言ったの。
『彼も元は漫画を描いてたんだ』って。
二十一だよ、その頃。血気盛んな馬鹿だからさ、負け犬に見えるんだよ、夢を諦めて堅気になるような奴は。でも、いつ自分にその瞬間が来るかもわからない、いつか受け入れなきゃいけない日が来る。そう思うと、それだけで不安で仕方がなかった」
フォークを持ったまま、加古江さんの手はときどき止まった。ため息を付いて、思い出の底を見つめる。
「それで。その中で、一番親身になって話を聞いてくれたのが裕美さん」
母を失ったということが、ここ数日、僕の看板のようになっていた。だれもがしげしげとその文字を読んで、お悔やみを述べた。加古江さんは僕の看板を読むまでもなく、自分の看板を背負っていた。ふたつ並んだ寂しい看板。そこにはただ静かに微笑んだ、母の姿があった。
「再婚はせんと?」
中学の頃、母にたずねたことがあった。
父に縁談の話が持ち上がった頃だったと思う。その話をしながら、なんとなく予感していた。母にもだれか、思っている人がいることを。
「勇はどげん思う」
「したっちゃ良かち思うばってん」
「ばってん、何?」
「怖か」
僕がそう言うと母は、自分の涙を誤魔化すように、僕を抱きしめた。もう中学生になった僕を、少し距離を取るようになってきた僕を、戸惑いながら、肩に手を置いて、僕の涙がこぼれると、母も堪えきれずに。
――思い出すとまた、涙がこぼれてきた。
覚えておかなきゃ。今日のこの涙の意味を。
「赤坂によく利用してた画材屋があるから、見ていくといいよ」
加古江さんはたぶん、僕が涙を拭ったのを見て、別の話に誘導したんだと思う。
でも。
「僕はあんまり。その。絵は描かんとです」
「あ、そうか。でも、描くよ、これから」
僕が、絵を?
呆気にとられていたと思う。僕の未来を知っているかのような口ぶりに。
「裕美さんから、勇って名前をもらったんだ、描くよ」
加古江さんは得意げに言うけど、僕は勇という名前は、好きじゃなかった。
いさむ? それとも、ゆう?
そう聞かれるたびに、自分にはない勇ましさを求められてるような気がして。
「名前はたぶん、父がつけたち思う。男らしさとか、勇ましさとか、そげんこつ、母の口からは聞いたこつなかけん」
「そうかな。勇ましさと男らしさは関係ないよ。そのネーミングは絶対に裕美さんだと思う。先生の座右の銘があるんだけど――」
そこで言葉を止めて、そしてひとつ、息を吐いて続ける。
「勇なるかな、勇なるかな、勇にあらずして、何をもって行なわんや」
ゆっくりと暗誦して、勇気が大切、勇気以外の何をもって臨むというのかという意味だと教えてくれた。
「息子の名前が勇だって知って、うれしかったっちゃ。大川に帰った時、すべて諦めたとばかり思ったけど、そうでもなかったんだなって。でも、こんなことになって……」
加古江さんの皿の上には、そら豆がふたつ並んでいる。僕はその顔を直視しちゃいけないような気がして。それからふたり、お互いの顔を見ることなく泣いて、とりとめもない言葉を交わして、少しだけ笑って、だけどまた泣いて、砂糖を二杯入れたコーヒーは、甘くて苦かった。
テーブルで会計を済ませて店を出ると、もうやることはない。食事をするために福岡まで来たわけじゃないのに。加古江さんはオフィスに戻ると言うけど、付いていくわけにもいかない。胸の中にはまだ吐き出せなかった何かが残っている。
「本当は母の借金の話ばしたかったとです」
「じゃあ、用件は終わりだね」
「いや、でも、お昼まで食べさせてもろうて、このままじゃ悪かけん」
「わかった。それじゃあ」
と、加古江さんは前のめりの僕を制するように掌を見せる。
「西町高校だよね?」
「はい。西町の二年です。それも母から?」
「そこの美術室に、もしかしたら僕が描いた漫画が残ってるかもしれないから、あったら写真に撮って送ってもらえる?」
えっ?
「加古江さんも西町校だったとですか?」
「そう。偶然だね」
――いや、たぶん偶然じゃない。
僕は母が作った最強の転生系主人公なのだから、様々な能力が備わっているんだ。死んだ人の姿が見えるし、空だって飛べる。偶然を呼び込む能力だって、きっと。
「帰りはどうする?」
――その言葉を聞いて、胸を圧迫していたものの正体がわかった。もう少し母の話を聞きたかった。もう少し話を聞いてほしかった。僕の胸には、いつの間にか『寂しさ』が居座っていた。
「薬院の方まで歩いて、あとは空を飛んで帰ります」
そんな冗談を言って、泣き腫らした目の下に笑顔を浮かべると、
「ああ、いいね。僕はもう飛ぶ必要はないからね」
加古江さんも同じように冗談で応えた。
冗談だと思った。
加古江さんが不敵に笑って、足を止めた瞬間も、怪しく両手を広げて見せたときも、まだ冗談だと思っていた。
だけどその広げた両手の指先には光の煌めきが見えた。
僕は笑顔をたたえたまま、表情の作り方を忘れる。
加古江さんが静かに息を吸うと、両手のひらから七色の光が溢れだした。粒なす光を大きく宙に巡らせると耳に届く喧騒は途切れ、そこに現れた虹のアーチは空間を歪ませて、奥へ奥へと伸びるトンネルを作り出した。
「それじゃあ、また、いつか」
加古江さんはキザな漫画の登場人物のように、人差し指と中指とでさよならのサインを見せて、光の中へと消えていった。
ぽつんと取り残された僕の目の前、虹色の光の粒がさらさらと消える。
胸の中に広がっていた空気の塊が、寂しさから喜びに変わった。
僕は、能力者と出会ったんだ。
次の日にはもう忌引は明け、高校へ行った。
担任と少し話したあとは、クラスメイトの様子も変わらず、先週の金曜日からの時間の先に今の僕を繋ぎ合わせた。ただやっぱり、心はまだ乱れているのだと思う。人の笑い声を聞くと苛立つ。ときに、耐えられない程に。矢口は向こうから声をかけてくることもなく、ただ目が合うと変顔でリアクションしてくる。
二限目、三限目の終わりは教室にいることが耐えられず、中庭を歩いて、昼休みになってようやく矢口に声をかけることができた。
「写真、見たよ。筑後川昇開橋の」
って。校舎の屋上で。
その屋上の端でコーラス部のハンドクラップ、そしてその声が重なり始めて、リードのヴォーカルの伸びやかな声が空に舞い上がる。
矢口は金網に張り付いて、筑後川昇開橋で自撮りしたポーズと同じポーズを取る。
「ねーよ」
と、矢口。
ねーよ?
何が?
「あいつらが歌ってる歌。
Ne-
Yoってアーティスト。すごか。あの声は出らんばい」
そうなんだ。ぜんぜん知らなかった。
「もうみんな羽ばたけるったい。ここば出たらみんな、自分の道ば行くったい」
「ああ、うん」
「俺は、なんにもなりきらん」
「矢口も軽音楽部やん。ギター弾けようが」
「俺のギターには、人生が貼り付いとらんもん」
矢口は矢口らしくもない寂しい顔を見せる。
でもさ。
「あいつらがずっと音楽ば続けるわけじゃなかやん。大学は普通に進学して、いま歌うとる竹下は先生になるち言いよったし。人生とかそげん重かことは考えとらんよ」
「いかんなあ。おまいはー。ぜんっぜん、いかん」
矢口はそう言って、落胆した顔を見せる。
「なにがさ」
「よう見らんと」
矢口は空を見上げている。
「空ば飛びようとよ」
その視線の先を見ると、コーラス部の四人が空を飛んでいた。いつの間に。屋上の端には四人の譜面だけ残されている。
「これが世界やけん」
僕は自分の小ささを思い知るしかなかった。
空を飛べるかもしれないと思ったのは、昨日のことだった。少し練習して、いつか矢口にも自慢しようと思っていた。だけどそうか。もうみんな、飛べるんだ。
美術部副部長、
篠宮聡に案内されて、僕と、矢口と、美術室に入る。三人の部員がイーゼルに掛けた油絵を前にして談笑している。篠宮の顔を見ると会釈して、カンバスに筆を入れる。
「よかよ、別に。お喋りも大事やけん」
篠宮は笑って、美術室の奥、美術準備室のドアをノック、返事を待たずにドアを開ける。中には美術教師、
里崎結。
「ちょっと部外者を連れてきました」
篠宮が言うと、里崎先生が振り返る。
「勧誘?」
「勧誘じゃなかです。二年やけん、勧誘したっちゃ、すぐおらんごとなる。ていうか、教え子ば覚えとらんとですか」
「顔と名前は一致せん。絵は知っとお。野獣派とパウル・クレーやろ」
「そげん言われたっちゃわからんち思いますよ」
「何の用?」
「先生、加古江郁人っちゅうイラストレーターは聞いたことあるですか?」
僕に言葉をはさませることなく、篠宮は続ける。
「ああ、ここの卒業生っちゅう話やろ。聞いたことはあるばって、もう二十年以上昔の人やろ?」
「その人の描いた漫画が残ってるかもしれんち聞いて、探しに来ました」
「漫画がー? いやあー……」
話しながらロッカーを開ける篠宮に、里崎先生は意外なような、困ったような顔を見せて、机の奥のキャビネットを開く。
「授業で描いた漫画やろ? あたしの代はぜんぶコピーして取っとおばってん、二十ウン年前やろー? あたしん前は中村先生が七年務めとらしたち言うけん、更に前やんね。そぎゃん、だれ先生の教え子かもわからんばい」
キャビネットから出した紙の束には黄ばみがあった。長い年月を超えた紙は端も撚れて、その木端には年輪にも似た縞模様が見えた。
「ここに残っとうかもしれんばって、このへんで八年前やもんね。漫画やったらケント紙に八枚やけん、見てパッとわかろうばってん、それらしかもんは残っとらんよ」
先生と篠宮の手元から古い紙の匂いが漂う。たまにパラパラと絵の具の粉が落ちて、知らないだれかの思い出が、風のなかの微粒子になる。
「加古江先輩ち言うたら、うちの学校唯一のイラストレーターじゃなかですか」
「ぎゃーなこつぁなかよ。こんだけ卒業しとったらおるよ、何人か、確実に」
「でも、ウィキペディアに乗っとるとは加古江先輩ひとりやけん、昔先輩と探したこつがあっとですよ。なんか残っとらんかなちゆうて」
「それで? 見つかったと?」
篠宮は紙の束に指を挟んだまま、先生に顔を向け、肩をすくめて見せる。
「やっぱ先生も加古江郁人に興味あっとですか」
「そりゃあるよ、大先輩やんね」
「ああ、あった」
骨ばった手が、ロッカーから古いノートを引っ張り出す。
「授業で描いた漫画は残っとらんばってん、こいが当時の回し漫画やろうちゅうて、話題になっとった」
『西町美術部・回し漫画・8』
ストレートなタイトルがマジックで殴り書かれている。
篠宮がぱらぱらとページを捲り、
「ここ。ここが多分、加古江先輩」
と指し示すと、決して上手いとは言えない絵がそこにあった。
「この画力から漫画家目指したち、凄かち思わん?」
卒業生に漫画家を目指した人がいると聞いて、少し得意になって持ちかけた話だった。なのにこの絵。僕から見ても、とてもプロで通用する絵じゃない。だけど、里崎先生は篠宮の振りを引き取って、続ける。
「凄かよ。ばってん、こうやけん高校生は教え甲斐があるたい」
加古江先輩のパートは2ページ。その後を捲ると、同じタッチの絵が数ページごとに現れる。そこまでの話をパワーで持っていくタイプの展開。
里崎先生はしきりに感心している。
ここで全身を描く人はいない。自転車に乗る途中のポーズを描いてる。このコマとこのコマで表情を描き分けている。わざわざ両手のアップで紙を破っていてる。里崎先生は細かいところをいくつも指摘する。
「これは、プロになるわ」
わかるんだ。こんな絵から。
正直、加古江という人がどの程度の人なのかは知らない。ウィキペディアは見たけどページは少ししかないし、箸にも棒にもかからなかった人かもしれない。それでも自称――自称でしかないけど――トップチームにいた人の、まだ頭角を表す前の絵だ。
さっきから意味不明の感動が止まらない。
「会いたかー、この人に。ねえ、樺島くん。会いたいんだけど、この人に」
篠宮が言い出す。
篠宮が緻密なSF調の絵を得意としてるのは知ってる。普通の油絵やデザインよりも、漫画やイラストに近いものが彼のカラーなんだと思う。
「この写真送るので、そのときに聞いてみる」
本気で言っているわけでもないのだけど、おそらく篠宮もそうだと思う。
「おっ、やった」
篠宮は小さくガッツポーズをした。
保険金が振り込まれたのは翌日。
気を良くして司法書士に会い、後見人とのやりとりについてたずねた。不動産契約に関しては、電話をもらえたらなんとかする、契約は後見人名義で、保証人が必要ならばそれも手配できると説明を受け、次の週末、姉にも来てもらって部屋を探した。
後見人のこと、保険金のこと、司法書士のこと、これらを話すと姉は、
「出来すぎとう。詐欺じゃなかと?」
と言うけども、実際に一二〇〇万が振り込まれたことを伝えると、しばらく考えた後、
「だからあんたは馬鹿ち言うと」
と、罵られた。
紹介された日吉町のアパート。がらんと開け放たれた押し入れを覗きながら、姉は後ろに立つ不動産屋のひとを目線で示す。たしかに、ひとが聞いているとこで話すことでもない。
「―それに」抑えた声で、「そげんこつは黙っといて、お父さんから養育費も振り込んでもろうたほうがよかよ」と、姉は続ける。
「うん」
「お父さんにはあんたから言わんね。養育費のどげん条件で出とるかも知らんし、なんかあった時に、あんたが生きていくるかどうかわからんけん、あたしじゃ決めきらん」
姉は自分の胸にしまっておくから、大川の実家には言うな、生活費は父が支援してるで押し通せと念を押した。僕にはあのふたりは良い人に思えるんだけど、どうも家族の評価とは食い違う。
「お父さんと、大川のじいちゃんばあちゃんの間でなんがあったと?」
「なんがあったとか、そげんこっちゃなかとよ。どげん良か人でっちゃ、生活が削られたら変わるちゆーとると」
ゆーとると。と言うけど、言ってないような気がする。
「ばってん」
それで何か言い返そうと思ったのだけど、その先に意味のある言葉が出てこない。
「大川の家が貧乏しとうとはわかろう? 葬式代の二百万も、親戚の前じゃ断りよらしたばってん、ちゃんと受け取っとらす。そげんこつよ」
姉は、僕の知らない手札を持っている。僕はそれに戸惑い、驚き、また少し、不快を感じる。
部屋をいくつか見たあと、缶コーヒーを買って、三本松公園のベンチで話の続き。
「店の建て替えのローンがまだ残っとらすもん。店も閑古鳥ばってん、これからも暮らしていかないかんやん。介護とか要るごとなったら、あんた、お金持っとうとに知らんふりできると? うちはできるよ。他人やけん。あんたそうじゃなかろうが。『このお金は僕の学費にするけん』ち言えると?」
姉の言うこともわからなくはない。母が言っていたのも同じことなんだと思う。僕もきっと、そう言うふうに考えないといけないのだとは思う。だけどそれは正解なんだろうか。
姉は続ける。大学に行くとなったら、国立でも卒業までに二〇〇万。私立なら倍。生活費は年に二〇〇万は消える。一二〇〇万は大金じゃない。すぐなくなる。
確実な答えは得られなかったけど、祖父母には父から支援を受けたことにして、父には母方の親戚筋のミツコさんに保証人になってもらったと説明することにした。ミツコさんは鍋島藩ゆかりの有力者。母の離婚調停のときも力になってくれた。
「ミツコさんやったら、本家が出てきたらしょんなかち、お父さんも納得しよらすち思う。高校ば出るまでは養育費ももろうたらよかよ。私もお父さんには『ミツコさんの保証人にならっしゃったごたー』ち、ようわからん感じで通しとくけん」
その嘘をいつまで通さなきゃいけないのか。心細くはあったけど、
「バレた時は、私がそげんしろちゆーたち、堂々と言うてよかよ。あんたば守るための方便ちゆーとは大人やったらわかるけん」
と、姉に言われて、まあ、姉がそうやって守ってくれるのだったらと思った。
引越し先も決まって、荷物を整理していると、母が現れた。
「大川の実家から漫画送っとくばい。ぼくの地球を守ってがまだ途中やろ。他はなんば読むね」
「なんば読むねち言われても……てゆーか、お母さん、そげんこつまでできると?」
「できるっちゃなかと?」
「正直、なんか、なんちゆーとかな。幻覚ち思うけん納得しとうとこがあるたい。お母さんのこと。ばってん、荷物ば送って来られたら、もうわけがわからん。それは生きとるとと、どげん違うと?」
母は少し呆れたように溜息をつく。
「そーゆーとこばい、あんたの悪かとこは」
そうかなあ。
「あ、そうだ。お母さんくさ。加古江さんの携帯の連絡先はわかるね」
「ああ、わかっばい。携帯出さんね。送るけん」
「そげんこつまで出来っと?」
母の幻覚がポケットから携帯を取り出す。
「僕の会話、ほとんど疑問形んなっとう」
「それが?」
「それがち言われたっちゃ困るばってん」
加古江さんのアドレスが僕の携帯に送られてきた。
「すげー」
母は窓を開けて、ソックスハンガーを取って、そのまま身を乗り出す。
「行ってみるばい」
「行ってみるち、どこにさ?」
「ピーターパンのごつ」
「返事んなっとらんよ。お母さん。死んでからそげんこつ多かよ」
母は僕の手を取って、空へと舞い上がる。
空に出ると、上下はあまり関係なくなる。イメージするだけで身体の向きが変わるし、好きな方向に飛べる。星空を見上げたときのときめきの正体に、ようやくたどり着いた。
そしてそのまま、日吉のアパートへ。
「ここやろ。まだ電気のついとらん部屋が、あんたの部屋ばいね」
そう言うと高度を下げて、ベランダにソックスハンガーを吊るす。
「こいでよか」
新しいアパートの屋根から、小さい頃に通った、日吉の小学校が見える。
あの頃の、僕らの声が聞こえる。
廊下を、運動場を走り回り、大笑いする声が。
そしてその少し先に、伊藤の美容院が見える。
「好いとうたと?」
僕の胸に浮かぶ彼女の姿を見透かして、母が聞いてくる。
「うん」
母は少し切なげな顔を見せる。
僕の心の中をどのくらい見通しているんだろう。
――お母さん。こんどお母さんが描いた漫画ば読みたか――
胸の中で聞いてみると、母はほくそ笑んだように見えた。
ならば、と、母は右手を握り、それを目の前でゆっくりと水平に動かしながら、手のひらを開く。するとこそから、無数の光、無数の闇が漏れ出し、僕の体にまとわりつく。
そしてこの星空の天という天、大気あるところすべて、意識及ぶすべての点より光が降り注ぐ。昏昏と眠る、静寂の町に。
第四章 旅立ち
高二の秋も終わろうという頃。美術の授業の最後の課題は漫画だった。
その最初の時間、参考用と思われる一枚のコピーが全員に配られた。
まるで下手の見本のような漫画。ページはまっすぐに6コマに分割され、顔と体がようやく判別できるキャラ、背景も地面や道が分かる程度の線画があるだけ。ストーリー的なものもない、ただ釣りをしているネコのところに、別のネコが来て何かたずねて、二匹でどこかへ行く、それだけ。
みんな同じことを思ったと思う。
「こういうのは描かないでください」
先生はきっと、そう言うんだと。
周囲の生徒たちが配られたページを見てクスクスと笑う中で、先生は教壇で、漫画にはいろんな製図技術、印刷の知識が含まれている、と話し、一通りの前置きを終えたところで、「配られたコピーを見てください」と全員に促す。
「これを描いた人は、漫画ば読んだことがありませんでした」
ああ、なるほど、と思う。
そんな人でもここまで描けた、という話なのかな、と。
「アニメも見とらんち言うてました。そういう人はたまにおるけん、この中にもおるかもしれません。家が厳しくて漫画は読ませてもらえん、ちゆう人が。ちなみに先生もたまに『漫画やら教ゆんな』ちゆーて抗議されます。でも、もし家の人がそぎゃん人やったら、ちゃんと先生に抗議しに来てもろうてよかです。先生が話します。それで説得でくるちゃ限らんばってん、話ばしてもろうたら、その背景ば知るこつが先生の血肉になるけん、喜んで抗議は受けます。
はい、それじゃ、もう一度この漫画を見てください。
先生はこの漫画を見て、この授業ばして、本当によかったち関心したとこがあると」
先生はそう言って少し間を取る。
クスクスと笑っていた生徒たちは真剣な目でコピーを眺め始める。
僕も見てみるけど、先生がどこに感心したのかはわからない。
「3コマ目を見てください」
先生が言うと、みんな3コマ目に注目する。釣りをしていたネコが、歩いてきたネコに話しかけられるコマ。不自然なところは特にない。
「話しかけられたほうのネコから、汗が散っとうでしょう?」
静かに、だけど力強くそれを言うと、また改めてその眼差しを生徒たちに向ける。
「漫画ば読まん人は、この汗の表現はせんとよ。でもこの人は、授業をきっかけに何冊か漫画を読んで、そこからこの表現を覚えて、的確にこの場面で使うとると。手間で言うと一秒もかからん。『ポッチ』よ。ばって、これを描いたらこのネコが話しかけられて焦って返事しとるち伝わるちゆうことを、始めて読んだ漫画から読み取って、実際に読む方にも伝わるごつ描いとうと」
たったひとつのぽつんとした記号の説明に教室がどよめく。
「芸術も文芸も、読む力、受け取る力が必要なのはわかるよね。
で、受け取ったら、それを再構築して、新しいものを作る。
これは芸術に限らず、コミュニケーションすべてがそう。
漫画にはこの、汗のぽっちだけでなくて、様々な記号やお約束が散りばめられとう。
たとえば――」
そう言って先生は、黒板に怒りのマークを描いて、その前に立って話を続ける。
「こぎゃんして話したら、怒っとるごたっ感じのするやろ?
もちろん、こぎゃん記号は使わんでっちゃよかよ。絵で魅せるのも、セリフで言うのも、なんでっちゃよかとが漫画やけん。自由に描いてよか。
絵の
上手か下手かも、考えんでよかです。
自由に描いてもろうたら、あたしがそこから、あなたたちを見つけます」
先生はこんどは黒板に『笑い』を示す記号を描いて、その前に立ち。左手で指差す。
「これだけで伝わります。それが漫画です」
帰宅して、四十九日の法要を前に姉の携帯に電話をかける。
父はともかく、姉だけはその席にいて欲しかった。
姉は快く受けてくれたあと、声を沈ませて、
「ちょっと大事な話があるけん。今から行ってよか?」
と、切り出してきた。
「電話じゃいかんと?」
「いかん。今からアパートに行くけん。新しいアパートの住所ば教えんね」
言い出したら聞かない人だから。
仕方なく姉にメッセを送って、まだ散らかった部屋を少し片付ける。
こちらへ来て母の幻覚は見なくなったけど、引越し前にあれこれ相談できたことで、踏ん切りはついた。
「あんた、下着とかぜんぶ捨てんで持っとくつもりやったとね」
そう問われ、もちろんそんなつもりはないけども、引き出しを開けることすら怖い時期はあった。今残っているのは形見にと思って取っておいたいくつかの雑貨、大川から送られてきた漫画の山、ソックスハンガー。
夕方。
ソックスハンガーが揺れて姉が訪ねてくる。
腰を下ろすとすぐに本題に入った。
「お母さんの保険金の件、黙ってはおられんごつなった。お父さんと詩香さんには話すしかなかばってん、よかろ?」
姉は深刻な顔で迫るけど――
「ちょっと待って」
僕の理解が間に合わない。
遺産のことを言うのは構わない。でも、それを言う、言わないの問題じゃない。そこにどうして詩香さんが割り込んでくるのかがわからなかった。
「お父さんにはわかるばって、詩香さんは関係なかっちゃなかと?」
姉は首を振り、「関係なかこたなかとよ」と、ため息とともに押し出す。
「詩香さん、自分がおるけんあんたが帰って来れんとじゃなかとかち思うとらすと。自分がおらんごとなったら、あんたも六ツ門の家に戻って、大学に通うとじゃなかかち」
「そげんこつなかて。姉ちゃん知っとろうもん」
「そいば詩香さんに説明すっとに、あんたがちゃんとお金ば持っとうち言わんといかんめえが。あんたが高松の家ば頼らんとは自分のせいじゃなかとかち、詩香さん、ずっと自分ば責めよらすたい」
「ばってん、姉ちゃんも保険いくらもろうたか人に言わんがよかち言うとったやん。お父さんに言うなら、じいちゃんばあちゃんに黙っとうわけいかん。じいちゃんばあちゃんば、裏切りとうなかもん。僕が高松の子になったら、あのひとたちはもう、なんもなかとよ。それに姉ちゃんが言うたとよ。話さんほうがよかち」
姉が作った嘘の世界の中で、自分を騙し続けるのはできると思う。高松の家も、大川も、すべてまとめて。姉がそうしたから。姉が庇ってくれるから。でも、父にだけそれを言ったら、僕と姉とで一方的に祖父母を騙すことになる。それに姉はすぐに忘れる、僕に嘘を吐かせたことなんて。そうなったら僕は、一人で大川を騙し続けなきゃいけなくなる。
「言わん方がよかちゃ言うたばってん。じゃあ詩香さんにも言わんで通すと?」
「そげんこつは、僕の勝手やろうもん。そげん誰かに世話してもらわんでよかし、詩香さんもお父さんと結婚したかなら、したらよかだけやん」
「あんた、自分の立場がわかっとうと?」
姉の表情が険しくなる。それはもう言葉を吐くときにはわかっていた。
「放っといたらのたれ死ぬとよ。みんなそいば心配しとるとが、わからんと? なんね『世話してもらわんでよか』ちゃ。お金ば持ったらそげんなっとね。お金ば見たら変わるもんがおるち思うて心配してやったら、変わったとはあんたやったたい」
どう言えばいいんだろう。姉は僕の言葉を叩き潰そうと、口を開くのを待っている。
じゃあ、姉ちゃんは僕のなんがわかると?
僕がのたれ死んでも、姉ちゃんに迷惑かからんめぇが。
言葉を選びあぐねて――
「そげんこつ言うたっちゃ。変わったつもりはなかし、詩香さんは関係なかもん」
そう口にしたけど、これが自分の気持をどれほど表せているのかわからない。
姉はこれ見よがしな大きな溜息を吐いてみせる。
「三十一の時から、四年つきおうとらすとよ、詩香さん。あんたが高校ば出るとば待っとらすと。あんたが詩香さんば良う思うとらんことも知っとらす。そいでもあんたに遠慮して待っとらすとよ。あんたが大学に行くとば、詩香さん、待っとらすと」
そうじゃない。詩香さんだからじゃない。姉は高松の家のことしか考えてない。姉と僕とで世界を手玉に取るような気でさえいたのに。結局騙されるのは祖父母じゃないか。
「待ってくれち、頼んどらんけん」
姉の目を見るのが躊躇われた。大川から送られてきた荷物を整理するふりをして、箱を開いて、ノートを取り出す。
「わかった。じゃあ、バラすけん。あんたが遺産ばもろうたち。お父さんにもまだ言うとらんとやろ。ばってん、しょうがなかたい。あんたが言わんなら、私が言うしかなかけん」
姉は袖口で涙を抑える。
「お父さんには僕から言う」
姉に言いつけられて、ソファに座らされた時のことを思い出した。父なんかもう他人でしかないのに、思い出すと動悸が暴れ出す。
「そしたら詩香さんにも話は行くとやろ。姉ちゃんはなんもせんでよかよ」
「やったらいま電話せんね。あんた口ばっかやろうが。いまおるけん、電話せんね」
「でも……」
「あんた、どんだけ甘える気でおると
!? ぜんぶお父さんのせいにしたらよかけん電話せんね! 詩香さんがうちば出ていったら、あんたどげん責任取ると
!?」
姉はボロボロと涙を流しながら、怒りを顕にする。
僕も泣きたいよ。
姉ちゃんも詩香さんのこと、好かんち言うとったやん。僕の味方になるち思うとったとに、なんでこげな話しになっと。だいたい僕は、詩香さんがどげんひとか知らんもん。姉ちゃんから聞いたこつしか知らんもん。姉ちゃんが好かんち言わんやったら、何の感情も抱いとらんもん。
喉まで出かかる。
六ツ門の家でどんなやりとりがあったかはわからないけど、僕はただ圧倒されて、携帯を取って、何年ぶりかに自宅の番号に電話するしかなかった。指が震える。実質僕は、泣いているんだと思う。
四回のコールのあと、受話器が上がる。
「もしもし、高松です」
女の人の声。詩香さんだ。
「もしもし。勇やけど。お父さんはいますか?」
電話の向こう、詩香さんの動揺が伝わってくる。言葉を探して、たどたどしく、母へのお悔やみの言葉を継いで、すぐに代わるからと、
「真雪さーん」
掌で押さえた受話器越しに、父を呼ぶ声が聞こえる。
「もしもし。勇か。久しぶりたい。なんばしようとか」
少し上ずった父の声。胸のなかに書き留めていたはずの言葉が、ぽろぽろとこぼれていく。電話の向こうからは、母へのお悔やみの言葉を並べる父の声。あとは姉から聞いたのと同じ話。大学の四年間は支援するつもりだと語り始め、僕はその言葉を遮る。
「お母さんの保険金が降りたけん」
あとは、どう言えばいいのだろう。父も電話口の向こうで返事に困っている。
「養育費はもうよかけん。大学も、行くか行かんか決めとらんばってん、自分でなんとかすっけん」
「ああ、そいばってん」
父は話を続けようとするけど、
「いまちょっと、なんか聞いたっちゃ飲み込みきらん」
「ああ、それじゃあ、詳しかこつはまた今度。奏絵ば通したっちゃよか」
「うん。それじゃ」
続く父の声が耳に入らないようにと、急いで電話を切る。
「勇、ごめん」
電話を終えると姉が声をかけてくる。
「ちょっとカッとなったばって、あんた、悪うなかけん」
そう言われると自己嫌悪を感じる。僕が悪くないわけがない。何の罪もないとしたら詩香さんで、その詩香さんが一番割りを食っていることくらいわかってる。でも……だったらあんな人について行かなきゃいいのに。自由になればいいのに。
「再婚したらさあ、弟か妹ができると?」
そうたずねると、姉は呆れる。
「そげんこつは、お父さんと詩香さんの問題やろ」
「そうばってん。また僕とか姉ちゃんに遠慮して決めないかんごつなるやんね。これからずっとばい。詩香さん。僕と姉ちゃんの顔色ば見て人生決めるとばい」
「それがわかっとうなら、仲良うしたらよかだけやんね」
それはそうだけど。
「好かんもん。あの人は」
そう言うと、姉の溜息がまた一つ聞こえた。
手持ち無沙汰に、ダンボールから取り出したノートを開く。母の構想ノート。見開きのページ。いろんなキャラがいて、いろんな事件が勃発するダイアグラム。その事件の数々から矢印が引かれて、その先。
――これらの事件が、すべて劇的に解決する――
の文字があった。
まるで僕らのことを見透かしてこのページを書いたような。
笑いと涙が同時に溢れ出す。
「なにそれ?」
姉がきいてくる。
「お母さんのノート」
きっとこの世界はもう、母さんの世界なんだ。
母さんが描いた漫画を読ませてって言った時から、僕たちは母さんの術中にいるんだ。僕の優柔不断も、進学も、姉と父の関係も、詩香さんのことも、母さんの作劇ですべて解決するんだ。
でも、どうやって。
僕にはどんなスーパー能力がある設定なの、母さんの中では。
四十九日の法要は、祖父の腰痛で一週間伸びた。
祖父は自分のせいで法要が遅れたら裕美に悪いと言い出したけど、どうせ家族だけの法要、慣例で少し前倒しにしているのが、ほんの少し後になるだけだからと諭して、その週は月曜から木曜まで学校を休んで祖母とともに祖父の身の回りの世話をした。
母の遺骨はその一週間、祖父母の呉服屋に置くことになった。母の幻覚のおかげで、僕の中では遺骨の意味付けが薄らいでいたけど、祖父母の家に置いて改めてお供え物などを飾ると、いままでの感覚がいろいろとおかしかったんだと気がつく。最初からこうしておけばよかったのに、僕のわがままで母を手元に置いていたようで。
祖母はまだ元気ではあったけど、風呂掃除や布団の上げ下ろしは辛そうだった。祖父が車を出せないと買い出しもままならない。近くにもスーパーはあるからと、二人で二十分ほど歩いて、不慣れな店で、鰹節、たまご、ひとつひとつ売り場を確かめて、セルフレジも使い慣れたものとは違う。僕と祖母とで、どこにお札を入れるか戸惑った。
もし大川に世話になるとしたら、これが僕の日常になる。母のおかげで僕はその苦役から逃れられるのだけど、でもだからといって、この現実がなくなることはない。
僕が休んだ四日間、水曜日の勤労感謝の日を飛ばして三日、矢口から毎日、ノートの写真が送られてきた。授業の要点までしっかりと記録され、写真に添えたテキストには「樺島ば卒業さすとが俺のクエスト」とあった。
木曜日あたりになるとノートもこなれてきて、まとめのテキストには先生の口調の変化まで記されている。矢口はそう言うところは少し偏執的でおかしい。
大川にいる間は、母の部屋に寝泊まりしたのだけど、漫画はぜんぶ僕の部屋に送られていたから、夜は退屈。七時になると町の灯も落ちる。
土曜日の四十九日の法要には、姉も出席した。
授業の漫画が完成したのは翌年一月の後半。
僕は、英雄ペルセウスがメデューサに恋をするギャグマンガを描いた。
二ヶ月以上かけて完成させたたった8ページの漫画の出来は拙かった。それでもクラスの連中は面白いと言ってくれたし、それまで話したことのなかったラグビー部の富松なんかも話しかけてきたりした。冒頭を読んで、「ゼウスがペルセウスの母ちゃんば孕ませた金の雨ちゃ、やっぱあれのことね」と、高校生男子が言いそうな凡庸な下ネタに振る。ほかのだれかがその話題を拾って、べつのひとがまた笑って。たった8ページの漫画で、僕の世界はあきらかに広がっていた。
そして、篠宮は加古江さんのことを忘れていなかった。
美術部副部長が仕上げた漫画は緻密だった。
二隻の巨大宇宙船がすれ違うだけの漫画。そのほんの短い間に交わされるコミュニケーション。タイトルは『種子』。
宇宙空間で航路が重なり、不意に接近する二隻の巨大宇宙船。互いの種族、航路を確認し、偵察機を飛ばし、一触即発の緊張。お互いに引き返せないギリギリの戦闘態勢を取った中で、ひとりのパイロットが相手宇宙船の窓に花に水をあげる子の姿を見留め、そこから全戦闘機に戦闘中止の連絡が飛ぶ。宇宙船は何事もなくすれ違っていく。漫画の中に使われているのは二種類の架空の文字。最後は遠くから、すれ違った二隻の宇宙船がとても小さく描かれている。ふたつの種子が星間を漂うように。
感動して言葉が出なかった。
彼が加古江さんに会いたいと言ったときは生返事だった。ハイハイと言っておけば、いずれは忘れるし、きっと彼だって本気じゃないと思った。でも実際に彼が描いた漫画を読むと、逆に僕のほうが会わせたくなった。もちろん、そんなことをしたら僕が霞む。第一線を見てきた加古江さんを唸らせたいという気持ちは満たせなくなる。でも、それでもいい。そもそも僕の漫画なんかで唸らない。篠宮が僕に見せたのは、僕なんかが絵を描いているのは間違いなんだと思える傑作だった。
一月の最後の日曜日、ダウンのジャケットを着て、警固を目指した。
僕と矢口と篠宮。
カコエオフィスは天神へ出て乗り換えて薬院大通駅からが近かったけども、薬院駅からの差は四〇〇メートル。「ばってん、運動場一周の距離やん」と、地下鉄に乗るのも躊躇われて薬院から歩くことにした。
西鉄電車に乗って、薬院駅で降りると、「薬院ち言うたらくさ」と、矢口が口を開く。
「伊藤ちおったやん。あいつがこのへんのモデル事務所に登録しとるち聞いたこつんある。中学のとき一緒やった。樺島は知っとろう?」
もちろん。知っているもなにも。
篠宮にとっては、顔も見たことのない相手。
「可愛かと?」
「普通。でも、普通やけんよかっちゃなかと?」
矢口と篠宮のそんな会話は、空気の壁を一枚通した向こうにあった。
篠宮は少し斜に構えて受ける。
「そげんとは上の世代から見た意見やろ。歳取ったら、若かったら誰でっちゃよかごつなるけん。ばってん俺たちにとって普通やったら、普通ばい」
知り合いの子がそんな風に見られるのは嫌な気がした。伊藤に片思いしていた僕の意見としても、伊藤は普通だけど、伊藤は伊藤だし。というか、心の中では芽郁って呼んでたし、伊藤って言われると別人のよう。実際に面と向かって「芽郁」なんて、呼んだことないけど。
「樺島も知っとう子? どげん思う?」
「樺島は小学校から一緒やったけん、俺より知っとうやろ」
「ああ、うん」
そんなに美人じゃない。一方的に片思いはしてたけど。それをどう言っていいかわからないし、あんまり話題にもしたくない。可愛いから好きになったわけでもないし、そんなに可愛かったら自分にチャンスなんか感じてない。
「おお? なにその思わせぶりな表情は?」
いや、表情って?
「なんかあったと?」
「いやいやいやいや。そげな表情しとらんやろ。だいたい嫌われとったけん、あんまり考えとうなかたい」
「嫌われるち、なんばしたと?」
「いやらしかー。なんばしたとやろかー」
「いやいやいや」
「このへんおるとやったら、偶然会うかもしらんね」
「そげん偶然はなかよ。漫画じゃなかけん」
「偶然じゃなかったら、必然たい。ここで会うたとしたら、運命ばい」
「いやいやいや」
話していると、時間はすぐに過ぎ去る。目の前にはもう目的地のビル。直前でメッセだけ送って、三階のドアの呼び鈴を鳴らす。以前ここへ来たのは十月。あれから三ヶ月半。加古江さんはドアを開けて、僕らを中へ通す。
奥はデザイン事務所らしく、資料やパソコン、製図台のようなものが見えるけど、僕らはその前の小さな応接室に通され、加古江さんは缶ジュースの入ったバスケットを持ってくる。
「謎ジュースコレクション。いろんなとこで買い集めた。飲んだことなかとも混じっとるばってん、遠慮せんで飲んで」
バスケットの中にはハングルやタイ語らしき文字、あるいは筆の書き文字が踊る缶や瓶が詰まっていた。
「おひょー」と、奇声を上げて僕とバスケットを交互に見る矢口と、硬直する僕。
「デザイナーらしかですね」と、フォローする篠宮が大人に見えた。
三人はそれぞれにジュースを手に取る。
篠宮は「それじゃあ、無難に」と言いながら、ペプシに良く似た缶を選んだ。
「コカ・コーラばいこれ。後ろにロゴのある」
篠宮はそう言って手にとった缶の裏を指差す。デザインはペプシっぽいのに、ロゴはコカ・コーラ。だけど状況から察するに、どうやら篠宮はアタリを引いたらしい。
次に矢口が「俺も無難に」と言いながら『うなぎコーラ』を、僕は正解がわかるはずもなくハングル文字の書かれた黄色い缶を取る。直後、篠宮から「湿布の味のする」と聞こえる。矢口はどう見ても蒲焼のタレにしか見えないものを飲んでいるが、味覚が壊れているのか、「普通のコーラばい」と言う。ちなみに僕が飲んだのは加古江さん曰く『ライスジュース』で、味は藁をまぶしたお粥のようだった。
僕は、このタイミングで出して良いものかどうか、と思いながら、
「今日は、僕たちの描いた漫画を見てもらおうと思って来たとです」
と、カバンからケント紙を取り出した。
加古江さんは、うん、と頷いて、飲んでいた缶をおろして、ソファカバーで両手を拭いた。とっさにハンカチを渡そうとする篠宮に、笑顔だけ返して、加古江さんは原稿用紙に目を落とした。
緊張する僕の隣で、篠宮がスタンバイする。
篠宮が本命で、僕は前座。
そう思って感想を待っていると、
「これが探してくれって頼んでた漫画かあ。懐かしいなあ。こんなだったかなあ」
と、加古江さん。
「加古江さんの漫画じゃなか! 樺島が描いとーと!」
すかさず矢口がツッコミを入れると、原稿を手にした篠宮は苦笑いを浮かべる。
加古江さんは目を通し終えると、また最初のページに戻って、見直しながら語りだす。
「さすがだね。漫画のお約束をよく知ってると思うよ。『エスタブリッシング・ショット』ってわかる?」
「いいえ、わからんです。なんですか?」
「映画とかの場面の最初とかに入る、引きの画面。そこでキャラクターの関係性を見せておくと、観客が頭の中で位置関係を構築できる。この漫画だと、最初のコマ。ここでバー全体を見せてるから、ここ、この『横に飛ぶ』って動きで、椅子の後ろに隠れたことが伝わる。そういうところを丁寧に織り込んである」
「あー、別に、考えてそうしたわけじゃなかとですけどね」
「じゃあ、才能だ」
才能……今まで自分の才能のことを言われたことがなかった。
「絵は下手だけどね。そこはなんとかなるよ」
おおう。痛いところを。
続けて、篠宮と矢口が顔を見合わせて、矢口が漫画を差し出す。
自分をモデルにしたような、高校生アマチュアバンドの成り上がり物語。
それを読んだ加古江さんは、「うーん」と、額を押さえる。
「駄目とですか?」
「誤魔化してると思う。やるべきことを」
どういうこと? 矢口も篠宮も疑問の表情を浮かべる。
「僕から見たら、このコマの隅っこに描いてある、この子。この子が言ってる『でも失敗するよね』が本音だよ。君の。でも最後、なんとなく成功してる。描きながら成功するなんて信じてないでしょう? 信じてるんだったらいいんだよ。うおーって最後は盛り上がれると思う。でもこのラストは、オチとして最初から決まってるから、サクセスストーリーだから、っていう理由で付け足したものでしかない」
「やっぱ、わかるですかー」
手痛いところを突かれたように、矢口が背を伸ばす。
「でも、そげん考えで描いたら、高校生がプロを負かすお話は描けんごつなりませんか?」
苦笑いしている矢口の隣から、篠宮がたずねる。
「勝たせるんだよ。それでも。その可能性は、数千、数万の中のひとつかもしれないけど、それを探して見せるのが漫画家の仕事だよ。絶望しかない。そこを認めるところから始めて、見つけるんだよ。光を」
その話を聞いて、矢口は顔を伏せる。
「鍵を握っている人がどこかにいるかもしれない。助けてくれる人がいるかもしれない。助けてくれる人はどんな理由があって? 勝たなきゃいけないのはどうして? いったい何の勝負なのか。相手は何を賭けているのか。全部考えて、たとえ血を吐いてでもその答えは見つけなきゃいけない」
矢口も篠宮も、そして僕も、何をどう言えば良いのかわからなくなる。
「現実だと、この『でも失敗するよね』が答え。読んでる方もみんなそう思ってる。でも、超えるのが絶対の使命。そのために何をすればいいか。考えてみて。考えるだけでゲロ吐きそうになるから。でもそのゲロの海で、最後に立ち上がれるやつだけが、漫画を完成させる」
そんな話を聞いてハラハラしていると、
「ありがとうございます!」
そう言って矢口が立ち上がる。
「握手をお願いします!」
と、両手を差し出し、加古江さんも苦笑いしながらそれに応じる。
「僕もこのレベルのことを言われるかもしれんと?」
そう言って笑いながら、篠宮が加古江さんに作品を差し出す。
少し手が震えているのがわかる。矢口は漫画家志望でもないし、絵だって描いたことがない。正直、何を言われても凹まないと思っていた。でも篠宮は美術部の副部長でプライドもある。将来は絵で食べていくかもしれないし、その可能性を摘まれるようなことを言われたら――
でもそれは杞憂だった。
「めちゃくちゃいいね、これ!」
篠宮の表情から緊張が抜ける。
「絵もすごくいいし、発想もいい。異文明の言葉が通じない中での緊張感も出てるし、シチュエーションも練り込まれてると思う。このままどこかに出せば確実にファンは付くと思う。問題は、漫画としてこれを求める人がそんなにはいないってことくらい」
「ああ……」と、篠宮は残念な顔で、「それはなんとなく自分でもわかります」
「この技術を活かせるのは漫画じゃないかもしれない。ファインアートかもしれないし、もしかしたら映画の美術かもしれないし、絵本かもしれない。だから、運良くぴったりとはまる道に進んだら、奇跡が起きる。でも、その奇跡が起きる可能性は……さっき言った話じゃないけど、万にひとつかもしれない」
「褒められてるのは嬉しいけど、微妙だよねえ」
篠宮は戸惑いながら、僕の顔を見やる。
「アシスタントだったら、すぐにでも来てくれって漫画家はいっぱいいると思う。でも、それで逆につぶれる人も少なくないんだよ。アニメとかゲームだと、背景だけ、世界観設定だけでも名前は出るんだよ。でも漫画はアシスタントのひとりでしかなくなる。もちろん、それでいいんだよ、考え方としては。名前を出さずに名作を支える。でも、自分が納得できない人と組んだら、病む」
「病む?」
加古江さんの言葉の末尾にぶら下がった、『病む』という言葉を、篠宮が復唱した。それは僕たちにとっては、笑いを誘いたいときのミームでしかなかった。だれそれが病んだ、あいつは病んでるからどうの。だけど加古江さんの表情は、そのときのものとは違っていた。なにか冗談でも挟もうと思っていた矢口の口が、子音だけの音を漏らして、愛想笑いに固まっている。
「合う、合わないってのはあるんだよ。どこにだって。良い作家と良い技師が出会ったからって、それで自動的に良い漫画が生まれるわけじゃない。ほんと、つまんない理由でいなくなるんだよ、優秀な人材が」
そうやっていなくなったひとは、二度と物語には登場しない――と、加古江さんは続ける。「そう言えば、こういうのがいたよね」ってだけの話になって、どこで何をしてるか振り返られることもない、と。下手だから、失敗したから消えるんでもなんでもなく、理由にもならないようなつまらない理由で消える。
「上手い下手、天才か凡才かなんか、一切関係なし。事件事故が起きる、変なサークルが流行る、妬み、嫉み、なんでもありの世界だよ」
そう言うと、やるせなく顔を覆った。
質問を重ねたら、もしかしたらもっとえげつない業界の裏話も聞けるのかもしれない。ただ、いまの僕たちはその深淵を覗いて、戸惑うことしかできなかった。その雰囲気を察したのか、
「そういうなかで、島田巽ってひとには、魂を預けることができたんだよ、みんな」
と、加古江さんは取り繕った。
「君の本質はここに込められているハート」
篠宮へ向けた、柔和な声が戻ってくる。
「そのハートを預けられる人、お互いに納得しあえる人に出会えるかどうかって、大きいと思うよ。それは編集の人かもしれないし、漫画家の先生かもしれないし、仲間かもしれない。その受け皿になる環境次第。君がどんな理想のためになら、自らの魂を預けることができるか」
加古江さんの長い話が、最後だけはなんとか、明るいトーンで締めくくられると、
「俺が駄目なのはわかるけど、巧すぎても駄目かー」
矢口は少し的外れな感想を述べながら、どんよりと降りていた空気を両手で押し上げた。
「でもまあ、運だよ。こういうのは。たまたま編集が探していたタイプと一致した、みたいな感じでデビューする人だっているわけだし」
「じゃあ、俺にもチャンスが?」
さっきから篠宮は黙って考え込んで、受け答えは矢口がしている。
逆にそこまでのことを言ってもらってない僕が不安になる。
しかも、「絵が下手」って言葉にされたのは僕だけ。
「ありがとうございます! 来てよかったです!」
篠宮が立ち上がって、矢口と同じように両手を差し出した。
カコエオフィスを後にして、三人の足取りは踊っていた。
「ココロのピヨピヨ言うとる」
小さな羽根を羽ばたかせながら矢口が言う。
「どうすっと? 漫画家になると?」
矢口が僕と篠宮の顔を交互に眺める。
「わからん。挑戦はしたか。ばってん、怖か」
僕よりも遥かに描ける篠宮が怖いと言ってる。
僕は? 僕はどうすればいい?
樺島裕美の子だって言ったって、絵の才能は遺伝しないだろうし、技術を受け継いだわけでもない。
だけど。
「投稿用の漫画ば、ちゃんと描いてみようち思う」
雰囲気に乗せられただけかもしれない。つい口にしていた。
母の縁もあって知り合った人だし、僕にはきっと、その夢を引き継ぐ使命がある。今日ここに来るために僕はもう数知れ……ぬ……偶然……を?
「あっ」
ふと、目の前から歩いてくる女性に目が留まる。
僕の足が止まると、向こうの足も止まる。
それを見た矢口と篠宮の足も、同じように。
「えっ? だれ? もしかして?」
篠宮が僕にたずねる。
そう、その予感通り。正面から歩いて来たのは伊藤だった。
中学の頃とイメージはすっかり変わっているけど、はっきりとわかった。それにひと目見て芸能人だとわかるアイドルのオーラがある。
矢口も気がついて、声にならない声を発しようとしている。
伊藤も明らかに僕だと気がついているけど目線を反らして、また歩き始める。
――ここで会ったら、それは偶然ではなく、必然。
矢口が言っていた言葉が思い出される。
すれ違う間際、矢口が声を掛ける。
「伊藤さんですか?」
伊藤の肩がびくっと跳ね上がる。
「矢口と樺島」
矢口は僕の袖をひっぱって、ふたりの鼻を交互に指差す。
「中学で一緒やった。それから……」
矢口が篠宮の鼻を指差すと同時に、伊藤は走り出した。
突然のことで、リアクションに困る。
伊藤はそのまま振り返ることなく通りの向こうへと走り、角を曲がって姿を消した。
走り出す肩から、ふわっと離れたコロンの匂いのなか、僕たちの時間は止まった。
「絵に描いたように嫌われとう」
「おまい、伊藤になんばしたとや?」
なんかしたかなあ。そこまで嫌われなきゃいけないようなこと。
第五章 アイギスの盾
英雄ペルセウスは、王の命で醜き怪物メデューサを倒すこととなった。
しかしペルセウスには、顔の良し悪しがわからぬ。
メデューサを見分ける自信もなかったが、ひとまずは女神アテナの協力を仰いだ。
知の女神アテナ。たしかに女神ともなると、その顔は美しい。
「メデューサの醜い顔を直接見た者は石になる。この盾に映して見るが良い」
「ありがたく頂戴いたします。それにしても、女神のお顔はお美しい」
「ところでペルセウス、おまえがさっきから見ているのは、わたしの膝だ」
「おお、膝でありましたか。どうりで目鼻立ちがはっきりせんと思いました」
――中略――
こうしてペルセウスは、メデューサがくだを巻いていると言われるバーを目指す。
見ると一人の女を除いてみな石になっている。その女の頭には無数のヘビ。
「おい、そこの爬虫類好きの女」
「おまえ、私がただの爬虫類好きの女に見えるのか?」
「違うのか?」
「勝手にネズミを食わすな!」
「いかんと
!?」
「こっちは好きで飼ってんじゃねえんだよ! 髪の毛なんだよ!」
「なにぃっ! では、貴様がメデューサ!
しかし……聞いたほど醜くもない……どういうことだ?」
「お前が見てるのは私の膝だっ!」
「どうりで石にならんと思うた」
「なれよ! 目ぇ合ってんだろ、さっきから!」
――と、僕が描いたのは、篠宮が描いたものに比べると、落ち着きのない漫画ではあったけども、美術の授業と言うこともあってか、思い切ったギャグを描くものも少なく、提出作品の中では異彩を放っていた。
タイトルは、『ペルセウスがメデューサに恋をした七つの理由』。
『アテナが強引すぎた』から始まり、『ヘビが気持ちよかった』、『恋愛観が近かった』、『はじめて人から殴られた』、『ヘビたちが応援してくれた』、『石化も慣れると気持ちいい』と続き、最後はメデューサとともに悪い王を石化させて母を取り戻し、『石化能力、最高!』で締める筋書きだった。
ギャグマンガだからストーリーものよりは簡単だと思ったのだけど、僕のデッサン力は絶望的に低かった。最初のペルセウスが跪いている絵が描けなくて挫けそうになった。バーに入ってくる場面を斜め上から描いたら、想像以上の難関だった。ヘビにネズミを食べさせる場面、ヘビをヌンチャクにする場面、盾に映して剣を振る場面は何度描き直したかわからない。出来上がった漫画には、消しゴムで消しても消えない下書きの痕ばかり。
やっぱり僕には才能がない。何度も思った。母が残したノートの絵と見比べると、足元にも及ばない。完成したのが奇跡だと思う。
絵ばかりじゃない。内容も。現実世界での顔の良し悪しを言えば、僕は良い方ではない。見た者を石化させてもおかしくない。だけど見ただけで石化するとしたら、勝手に石になるやつのほうが悪い。そう考えると、ペルセウスが恋をしたメデューサは、僕を投影した僕自身。何も考えずにメデューサに会いに行く馬鹿なペルセウスも僕。僕が描いたのは、僕が僕に恋をする漫画だった。
「どうしてペルセウスは石にならんと?」
とは良く聞かれたけど、『見たものが石になるほど醜い』のなら、顔の美醜がわからなければ石にもならないんだと思う。
高校三年になって、まだ少し肌寒い四月の始め。小学校近くの喫茶店、ふるむーんで姉と待ち合わせる。詩香さんが会いたいと言うので、せっかくだからケーキでもと、姉がその店を選んだ。
少し早めに来たはずなのに、店の前にはもう姉と詩香さんの姿があった。
「改めて、はじめまして。向井詩香です」
自己紹介されるまでもなく、名前は知ってるのだけど。でも、知ってても名乗るのが一般常識なのかなと思って、
「樺島勇です。はじめまして」
そう口にすると、
「知ってる」
と言って、姉は笑う。
釈然とせず睨み返していると、「はいはい、ごめんごめん、怒らんでよかけん、入るばい」と、カウベルの下がった扉を開ける。そういえば小学校の頃からこういう性格だった。だけどここで機嫌を損ねたら、詩香さんに悪い。
店に入ると、リザーブのサインが置かれたテーブルに通され、「勇は奥がいい? じゃあ、詩香さんはこっちで」と、姉の仕切りで席が決まる。
メニューを眺めて、姉はラズベリーのタルト、詩香さんはレモンケーキ、僕は苺のショートケーキ。姉と詩香さんは紅茶の茶葉まで告げてオーダーして、おかげで僕は紅茶を頼みにくくなる。
「カフェオレをください」
そう言うと姉は何も言わずニコニコと頷いている。
――勇はずっとカフェオレだよね――と、思って聞いてるんだ、きっと。
もういちど改めて自己紹介から、趣味や特技の話へ。ここではじめて、詩香さんの趣味がボクシングで、職業がボクササイズのインストラクターだと言うことを知る。
「大手町にスタジオのあるけん、よかったら見学に来てください」
福岡教育大学出身、小学校教諭免許あり、ボクシングの他に、剣道、合気道が有段、学生時代は水泳の県大会記録保持者だったという。
姉が三年前に父の家を飛び出してきたのは、おそらく再婚の話が原因。あの日の姉は遅くまで「詩香さんは好かん」と母に訴えていた。その姉がこの前は詩香さんのために涙を流して、今はこうして仲良くケーキを食べている。三年前のあの日にずっと取り残されていた僕。姉に寄り添ってきたつもりでいたのに。
「勇はなんか、タブーってあると?」
姉があっけらかんと聞いてくる。ここで聞くものでもないだろうに。
「恋愛とか、進路とか、聞いちゃいかんもんがあったら最初に言うて。避けるけん」
タブーだらけだと思う。僕はともかく、お母さんの話は詩香さんも避けたいだろう。
「恋愛はあんまり。しよらんけんわからん」
姉とそんな話になるとは思わないけど、一応。
「ああ。それじゃあ、恋愛の中でも、特に聞いちゃいかんこつとかある?」
なんだ、この姉。
「初恋の子がいまどこでなんばしようかとか、最近会うたかとか」
答える僕も僕だけど。
「あー、聞きとうなかねー。どげん子やろかー。どこで会うたとやろかー」
詩香さんは置物のようにニコニコ笑っている。
「姉はどげん。なんか聞いちゃいかんこととかあると?」
「失恋のことだけは聞いたらいかん。場所とか、ぜったいやけん。こいばっかしは」
「じゃあ聞かんけん、場所とか聞かん。いつ頃か、とかも」
「二週間前たい。大濠公園で。デートしよって、ソフトクリームば買いに行って戻ってきたら、彼氏が他の女と話しよらしたけん、少し離れて見とうたと。そしたら、両手ん持ったソフトクリームのだらだら溶けてくるわ、鳩は集まってくるわ――記念写真ば撮るとはよかばって、あたしの入らんごとしてー、あたしごとSNSに上げんでーち、こげーんこげーんしよったら、そのうち女ん人がおらんごつなったと。そいで、やっと行かしゃったち思うて、溶けたソフトクリーム持って戻って『だれやったと?』ち聞いたら、そこで別れ話たい。信じらるっと?」
それはちょっと、哀れだけど笑いが止まらない。
「笑うちゃ悪かばい」
と言う詩香さんも、腹を抑えてる。
「そげんして待っとるけんフラれたっちゃなかと。割り込んでよかとよ」
詩香さんが笑いながら言うと、姉は涙を拭ってみせる。そして僕に
「勇はどげんしてフラれたと?」
見えないソフトクリームを両手に持ったまま聞いてくる。
「勇くんはフラれたとは言うとらんよ」
詩香さんはフォローしてくれるけど、でも、今なら笑い話にできる。
「薬院でばったり出会うたとばってん、走って逃げ出された」
「フラれとうばい! 絵に描いたごつフラれとう!」
ちょっと、カチンと来た。
「詩香さんはなんか、聞いたらいかんことあると?」
姉が問うと、詩香さんは少し考えて、
「三本松公園で痴漢に遭うた件」
「うわー。聞こうごつなかー」
「二人組やったけん、一人はケリば入れて、そのまま身体を返して、もうひとりば肘打ち。で、体勢こげんからの、裏拳。つい顔のあったけん、入るっちゃなかろかーち思うて手ぇ伸ばしたら入ったと」
「こげん人よ。私も護身術は教えてもろうたばってん、真似しきらんたい」
詩香さんに比べると母さんは内向的なひとだったと、こんなときでも母のことは思い出してしまう。亡くなった人に遠慮して、せっかくの楽しい会話から身を引く必要なんてないんだけど、でも少し乗り切れない。
「ごめんね勇くん、勝手に盛り上がって」
僕が少し沈んだのを察したのか、詩香さんが済まなそうな顔を見せる。
「いや、別に。楽しんどうですよ」
こうやって遠慮されるのも、本当は辛い。
姉もそう。おどけて笑いを絶やさないようにしているけど、僕を伺いながら、ちゃんと切り上げるタイミングを計っている。僕と詩香さんを馴染ませる計画の第一段階は終わった。紅茶ももうあと一口。姉がその最後の一口を飲めば、それが解散のきっかけになる。予定された通りの笑いと、予定された通りの幕引き。半年前ならそれで終わってた。でもそれでは終わったことにならないんだ。何かを引きずって歩く、長い階段に登りかけただけで。
「あのさあ。姉ちゃん」
「なん? なんかあると?」
「姉ちゃん、ペルセウスの話て知っとう?」
僕はペルセウスの漫画を描きながら疑問に思ったことをいくつかたずねた。姉は「先行研究があるはずやけん、それば見てからじゃないと」と、断りながらも、あれこれと感じることを話してくれて、最後に、
「端的に言うと、メデューサちゃ、なんち思う?」
そう聞くと、姉はしばし悩んだ末に、
「性欲」
と、答えた。
処女神アテナと対をなし、アテナが恥として内面化したもの。絶世の美女に科せられた呪い。クロノス、すなわち時の神の鎌によって刈り取られるもの。社会がそれを認めず、不浄とされ、英雄に利用、略奪され、晒されるもの。すなわち性欲。とくにこの場合は、女性の。
「でもこれ、今の思いつきやけん。もしあんたがメデューサで漫画ば描くつもりやったら、あんたが答えば出したほうがよか」
うん。それはもちろん。
「あの、もうちょっとよか?」
僕はカバンから、美術の課題で書いた漫画を取り出す。
「私も見てよかと?」
詩香さんがたずねる。
「もちろん。感想ばもらえるとうれしか」
それから三十分ほど、僕の漫画を読んで、改めて話し合った。
母さん、僕はもういいのかな。この人たちと、こうやって仲よくなって。
翌日、新しいアパートから自転車で一〇分。市立図書館へ。広い公園の中の大きなレンガのビル。大通り側から入り、先へと進むと、吹き抜けのガラス窓の向こうには緑の公園が広がっている。
ギリシャ神話は古典過ぎて、脚色の入ったものが多い。原典に近いものを読んでおきたいのだけど、それがどれなのかもわからない。研究書が多いし、古臭くて文体も硬くて読みにくいものばかり。それでも何冊か手に取って読んでみる。
ペルセウスの話はこう。
――ある日、アルゴスの王は、孫が自分を殺すという神託を受けて、娘ダナエを青銅の部屋に閉じ込める。しかし、そのダナエの元に、神々の長ゼウスが金の雨になって忍び込み、彼女を孕ませる。
やがてダナエはペルセウスを生み、それを知ったアルゴスの王は娘を殺すわけにもいかず、生まれた子ともども、彼女を島流しにする。
島流しにされたペルセウスとダナエは、地元の漁師に育てられるが、やがてダナエは島の王に見初められる。王はペルセウスの存在を疎ましく思い、不死の怪物、メデューサの討伐を命じる――
最初はその話を聞いて、不幸なペルセウスが怪物を倒して、最後はアンドロメダという美しい妻を娶る、不幸から幸福への大逆転の話だと思った。ダナエは僕の母、僕がペルセウスなんだ、と。
だけど一方で、メデューサはもとを辿れば人間で、その美貌故に海神ポセイドンから、こともあろうかアテナの神殿で陵辱され、それを理由に怪物に変えられた――
僕は、アテナに会った時に思った。
僕がアテナに会えたのは、父、ゼウスがいたから。ゼウスの子でもだれでもない島の漁師の子だったら、僕はアテナに会えていなかったんだ、と。
自由に生きたメデューサへの恋心というのは、僕の本心でもあった。そのメデューサの首を刈り取れるのか。何度も自問した。僕の漫画、『ペルセウスがメデューサに恋をした七つの理由』を読んで、クラスメイトは笑っていたけど、描きながらどれほど泣いたかわからない。
だけど、ペルセウスは顔の良し悪しがわからぬと書いたときの気持ちは、いまでは自信がない。
顔なんか関係ない。僕は芽郁でいい。いや、あの素朴で味のあるとぼけた顔をした芽郁がいいんだ。なんて思っていたのに、薬院ですれ違った芽郁の――いや、伊藤の顔を思い出すと、胸がときめく。
小学生の頃、友だちから「だれば好いとうとや」と聞かれたとき、伊藤だって言えずに、違う名前を答えた。
――川原? 川原は違う?
じゃあ、立野?
立野でもないなら、高口? 三原?
……そうやって名前を挙げられて、伊藤の名前が出たのは七番目か八番目。それまで恋愛なんか興味はなかったけど、伊藤という名前を聞いて、その時だけ目の前がぱっと明るくなった。
なのに、
「違う」
その場にいるのが嫌で、無難そうな三番、四番人気あたりの名前を出して逃げ出した。
でも現実は違う。彼女のことを連続で二週間、ずっと夢に見た。
あいつが着替えている夢、身体に触れてくる夢を見て、起きると何故か下着が濡れていて、何が起きたのかわからなかった。
そうやって身体が大人になっていく中で、引きずられるように恋をして、それから少し、伊藤とも話すようになって、たとえば東町公園で、たとえば校舎の屋上で、たとえば昼休みの理科実験室で。キャッチボールして、愚痴を聞いて、昨日のテレビの話、髪についた虫を取って取ってと僕の元に走ってくるようになって、いつの間にか僕は運命的な恋をしているような気持ちになっていた。
ペルセウスは顔の良し悪しがわからぬ。
そう書いた時と今とで変わったことはない。でも、薬院で見た伊藤は可愛いと思った。その駆け出した後ろ姿、揺れる髪も、その残り香も。
ふと見ると、目の前に司書のひとが立っていた。
「そちらの本、電子版がありますよ」
電子版?
ずいぶん古い本なのに、電子版なんかあるんだ。
「ご案内します」
司書の人は数歩先に進んで振り返り、改めて
「こちらです」
と指し示す。
僕は促されるまま、断れもせず、司書の人の後を追って、廊下、角を曲がり、階段を降りる。冷たい壁にふたりの足音が響く。電子とは程遠い、深海の静寂、冷ややかな湿り気の中、階段は下って行く。
踊り場の扉に鍵を挿すと、シリンダーを回す音が薄暗い階段に響き渡る。
脇の通路へ入り、その先は石の階段。水音が聞こえる。公園の地下だから、池の下に当たるのかもしれない。壁はしっとりと湿っている。木々の間を流れてきた水の匂い。裏返しになって流れる死んだ魚の、瀬に差し掛かり、するりと通り過ぎる時の。
どれほど下っただろう、階段が途切れると列柱の並ぶ広間へと出る。
司書のひとが歩くと燭台に火が灯っていく。
足元は大理石。
――神殿だ。
一番奥にはアテナの像、その足元には一枚の盾が安置されている。
「あなたは……もしかして、アテナ?」
「いいえ。私は
錠崎まどか。先生の命で、参りました」
「錠崎まどか? 漫画家の?」
「ご存知でしたか。光栄です」
「いや、ちょっと待って。これって、なんですか?」
錠崎と名乗った人がタクトのようなもので指し示すと、盾はぼんやりと輝いて宙に浮き、僕の手元に来る。
「知恵の象徴、アイギスの盾です」
「いや、そげん言われたっちゃわからん。ちゆーか、盾は見てわかるです」
「メデューサとの戦いでは、この盾に姿を映して見るようにしてください。また、あなたに必要な知識はすべてここに現れます。携帯を出してください」
メデューサとの? 何? 携帯? 携帯を?
僕は戸惑いながらも携帯を差し出す。
「インストールします」
「インストールって……」
アイギスの盾から光の濁流が僕の携帯に流れ込む。
「ちょっと待って、どげんなっとうと?」
光の最後の粒が流れ込むと、僕の携帯は光り輝いて、その盾にあった紋章が浮き出す。
それと同時に、地面が揺れ始める。
「さすがに向こうも気がついたようですね」
司書のひと、いや、錠崎先生は顔を上げて天井を見上げる。
「ちょっと待って、気がついたって何? 向こうってだれ?」
揺れが激しくなり、石の破片がぱらぱらと降ってくる。
錠崎先生は手にしていたタクトを僕に示す。
Gペン。漫画を描く時に使う、ペン先を使い捨てるタイプの付けペン。
それを空中にかざすとピアノとコントラバスが描画され、実体化する。
「乗ってください」
乗る? 乗るってどうやって?
戸惑っているとコントラバスのほうから僕の下をくぐり、すくい上げる。
先生はピアノの上に直立、三六〇度ゆっくりと回転するピアノの上でGペンを振るうと、無数の楽器がそこに現れ、調律のA音が重なって行く。
弾き手のいない楽器が音を重ねる中、天井の岩盤が開き、そこに湛えられた水はゆっくりと舞い落ち、光が差し込む。天井から降りる光の斜線。その中に、池の水が幾筋もの小さな滝を作る。
「ジュゼッペ・ヴェルディ……」
先生がペンをあげると、調律の音が止む。
静寂。
「レクイエム」
ペンが振り下ろされて、音楽が始まる。
楽器は、重厚な音を放ち舞い上がる。天上の青に水の雫が舞う。その煌めき、地下の闇を照らし出す陽の光の中、音楽の螺旋、巨大な石のホールに繰り返し叩きつけられる旋律が、地上へと上昇する。
久留米市諏訪野町の上空に、何十、何百という楽器が舞い上がる。コントラバス、バイオリン、オーボエ、フルート、ティンパニ……その上空には厚い乱雲が垂れ込め、青白き雷光が閃く。
僕を乗せたコントラバスは風の音を曳いて上昇、弦楽器の編隊とともに乱雲に突入する。左右を駆け抜ける雷光を躱し、雲の深部へと迫ると、前方に闇色の飛翔体を発見する。それは巨体をうねらせて、禍々しい不協和音を響かせている。吐き出される闇。それは苦悶を浮かべる人の顔のようにも見えて、濁った煙に変容して消える。
閃く雷光が楽器を殴打すると、錠崎先生のタクトで、楽器陣による反撃が始まる。連弾。数千の音の弾丸が敵を襲う。先生を乗せたピアノは上空へ、それを追って怪物も雲の海の上に姿を現す。怪物は、青暗い光の筋を脈動させ、その全身に空いた無数の穴には、体液に濡れた内腑が露呈する。
「ゴルゴン本体捕捉。迎撃します」
先生のタクト。展開した楽器群が音を放つ。溢れ出す音は光の奔流となり、その先端が化け物の表皮を走る。焼けたゴムの異臭と煤煙、金属質の奇声。化け物はのたうち、無数のタールの血を噴き出す。
反撃。数百、数千の爆発。火球が空を覆い、迎撃の網を漏れた闇の弾丸が地表へと落ちる。轟音とともに巻き上がる爆炎。直後、衝撃波が駆け抜け、そこを中心に周囲数キロの雲が消滅する。
先生は更に数十の楽器を描画、輝きを失ったペン先を捨て、新しいペン先に変える。
「コンサートホールへ誘導する!」
「なんで市街地に
!?」
楽器の攻撃を受けた怪物は高度を下げ、肉体を崩壊させながらも紫光の雷で地表を穿つ。すかさず先生はペンを振り、ヴィオラ隊を下降させる。市民の頭上で、怪物と弦楽器隊の攻防。怪物は西鉄駅、デパート最上階を崩壊させて更に侵攻、市街地へ。その先にはJR久留米駅、熊本方面より九州新幹線がホームに入ろうとしている。新幹線の乗客の一人が、上空に浮かぶ怪物の姿に気がつく。明治通りを行く車に怪物の影が落ち、瘴気を放つ半物質状の体液が撒き散らされる。
市民の防衛に手数を取られ、先生の楽器群が押されている。楽器はつぎつぎと撃墜され、残る数台が市民への攻撃をぎりぎり防いでいる。先生が更に数台の楽器を描くと、Gペンの輝きが消える。予備のペン先はもうない。
最後か。
その時、六ツ門の真新しいビルより、白き一条の光が立ち上がる。
シティプラザ・コンサートホールの天井がゆっくりと開くと、中には三〇〇のコーラス隊。舞台がせり上がる。天上からのスポットライト。白き衣、天使たちの歌声。前奏が終わり、先生の高く高く振り上げたタクトが楽隊の呼吸を一つに集める。
光を。もっと光を。細胞は光だ。家族から、友から与えられた光、その全て、肉体の記憶、胸の中の思いを全て、喜びへと変えて。
先生のタクトが下がる。
全身全霊を委ねたクワイアが、全ての光、全ての音をかき消して立ち上がる。幾重にも重ねられる歓喜の咆哮、それは巨大な光の柱となり、天上の光がそれに呼応する。
歌は闇を払う。崩壊する冥闇の肉体は呻き声を轟かせながら、小さく、更に小さく、光の中にその質量を失う。
天駆ける幾筋もの歌声が、そこに散る闇の全てを捕らえ、噛み砕き、消滅させて行く。
投稿漫画の、最初の四ページを書き上げたのは、ゴールデンウイークに入るほんの少し前。漫画を描いて投稿すると高らかに宣言した日から、二ヶ月ほどが過ぎていた。構想でつまづいてなかなか最初の一歩を踏み出すことができなかった。歩きだしてからも苦難の連続。絵もまだ拙く安定しない。
それを見た矢口は言った。
「賞は取れんち思うばってん、俺は好いとう」
正直に言われて凹みはしたけど、
「じゃあ、おまいんために描くけん、おまいが賞ばくれ」
と、口に出してみると、実際にもうそれだけでいいとも思えた。
「篠宮から見てどげん?」
矢口がたずねると、篠宮は少し考えて、
「樺島さあ、里崎先生が最初に見せてくれた漫画、覚えとう? ネコが釣りしてて、連れ立ってどこかに行くやつ」
と、ストレートに言い難かったのか、話題を変えた。
「忘るっわけんなか。あれが僕の原点になっとうけん」
そう言うと、篠宮は淀んだ笑みを口に含ませて、
「あれやけどさあ」
そう切り出して、少しだけ言葉を探した。
「先生、あの漫画の汗の記号ばすごい評価しとうたばってん、あのくらいは漫画読んどらんでっちゃ、ポスターとかでも見かけるやんね。あれ書いた人も、見たことあるち思うったい」
「えっ? そうなん?」
矢口が言葉を割り込ませる。篠宮は僕が描いた漫画を手にしたまま、また続きの言葉を探す。
「そいけん最初聞いた時、大げさやーん、ち思うたとよ」
「篠宮、そげん思うとったと?」
矢口が意外そうな顔をするけど、僕も、実を言うと。
「うん、最初は感動したばって、いろいろ考えると違うったいね。先生が言いたかったのは、たぶん違う」
「そう。あれもっと、深い物語よ」
篠宮の言葉には、少し大人びた苦味があった。
「なんそれー。そげーんして置いていかんでっちゃよかろうがー」
矢口は苦くなりがちな話題にミルクを注ぐ。
「先生、なんも言わんけど、たぶんあの漫画が、俺らと同じ十七年の月日ば生きてきただれかの、全てを表した『ぽっち』と思うと。あの漫画が、その人の人生ば変えたとよ。そいけん先生は、あの漫画ばお守りのごつ持っとうし、そいがあの人の力になっとうと」
なんでもない漫画だった。
ただの下手くそな漫画だった。
だけどあの、コピーされた一枚の紙には、質量があった。
先生はきっと、その重さを僕らに問うたのだと、いまになって気がついた。
何度も何度も消しゴムをかけて、描き直して、ようやく一本の線を拾い上げて、その満足の行かない線を自分に納得させて、それでやっと見えてきたものがある。たった一本の線にかけた時間は、線を引いた一秒じゃないし、下書きを含めた一時間でもない。僕の人生の長さ、その全てだ。
篠宮の話を、僕が引き取る。
「先生くさ。『芸術も文芸も、読む力、受け取る力』ち言うたやんね。そいば読めるかどうかちゆうとが、あの最初に見せられた漫画の課題ち思うたい。それを僕はまだ読めとらん。そげん考えたらくさ、僕らの課題はまだ終わっとらんとよ。一生続くとよ」
僕らが読み取るべきもの。
それがあの漫画を描いた生徒の家庭環境なのか、その人自身の肉体、あるいは精神の問題なのか、そんなことはわからない。案外考えすぎてるだけなのかもしれないし、あるいは逆に、先生はずっと、十字架のように背負っているのかもしれない。
「先生は、あの漫画にも成績付けないかんやったとよ。ばってん、よか成績は付けられん。最低の点ばつけたかもしれん。奇跡のごたる成長ば目にしながら、そいでっちゃ先生やけん、評価はせないかんやん。駄目なものは駄目、ち。先生が、そん時どげん気持ちやったか考えるとさ、僕らが越えて行かないかんこつは、並大抵じゃなかち思うと」
恥ずかしながら、自分でそう言いながら泣きそうになった。胸の中にはまだ口にしていない思いがある。無数にある。だけどうまく言えそうもない。
「やけん僕は、諦めん。この漫画が、どげな評価されたっちゃ、絶対に諦めん」
僕が言葉を結ぶと、矢口も篠宮も、フッと口から漏れる笑いだけで返した。
新しく描き始めたペルセウスの物語はまだ、アイギスの盾を手に入れて旅だったばかり。何箇所ペンを滑らせて失敗したかわからない。それでも僕は、諦めない。
「樺島さ」
「なんね」
「俺が樺島に、魂ば捧げたかち言うたら、どげん思う?」
「はあ? 篠宮の? なんで僕が?」
「俺がなんか賭けて、失敗したっちゃよかち思えるとが、おまいしかおらんけん」
「そげんこつ言われたら、照れくさかろうが」
「俺もよ」
第六章 翼の靴
「樺島さあ、もう気がついとうかもしれんけど、実は俺、二十五年後の樺島なんよー。未来から来とうちゃー」
カコエオフィスに来たのは二回目。母と加古江さんが師事していた島田という人の新作のアニメが公開されるからと呼び出された。先生と呼ばれるそのひとの下の名は
巽。女子サッカー漫画で一斉を風靡したあと身体を壊して休載がちになり、いつの間にか消えていった。今では知る人も少ない過去の人。僕もSNSに貼られるネタ用のコマでしか見たことがない。その人の漫画を原作にした何年かぶりの新作アニメが二ヶ月前に東京で封切られ、ミニシアターを中心に、少しずつ全国へと広がっている。
目の前には謎ジュース。アルファベットで、チチャモラーダとあるのが読める。甘くて酸味があって、複雑な風味。ラベルの絵は一瞬ブドウのように見えたけど、紫のトウモロコシらしい。加古江さんはインカコーラという黄色い液体を飲んで、さっきからおかしなことを言い出している。
「僕の名前、『加古江郁人』、これは別の読みかたで、
過・去・へ、
行・く・ひ・と、
とも取れるやろう? これがヒントやったっちゃー」
どうしよう。乗ってあげたほうがいいのかな。
「樺島はいま漫画ば描こうとしとーばって、あと何年かしたら漫画を諦めて、定職にもつかずにフラフラすることになるちゃ。そいば二十五年後の世界から警告に来とるちゃ」
「僕、明日、死ぬのかな」
「はい?」
「加古江さんの言うとるこつが仮に真実だったとして、なんでいま言うとですか? そげんこつは、クライマックスでばらさんですか?」
「なかなか鋭いじゃないか、過去の僕は」
加古江さんはインカコーラを掲げて乾杯を求めてくる。
大丈夫なんだろうか、この人は。
「加古江さん、小学校の頃好いとうた子の名前、覚えてます?」
「覚えとらんよ、そげんことは」
「いや、ありえんばい。あんだけ好いとうたとに。偽モンやけん知らんとたい」
「樺島は今もその子ば好いとーかもしれんばってん、すぐ忘るるよ」
「それは、母に会うけんですか?」
そう聞くと加古江さんは苦笑いしたまま黙った。
この人はやっぱり好きだったんだと思う、母のことを。
母もそうかもしれないし、その後の母を思うと、このふたりが一緒になってたほうが良かったのかもしれない。だけど、そうなると僕は生まれてない。僕はなんなのだろう。母の幸せな物語の結末にはいない存在。母の人生を犠牲にしてこの世に生を受けて、それなのに僕にはなんの取り柄もない。
映画が上映されるキャナルシティは西鉄福岡駅とJR博多駅の間にある。しかも、周りのどの駅からもほどよく遠い。カコエオフィスも同様にどの駅からもほどよく遠いので、最寄りの赤坂駅から祇園駅まで地下鉄に乗るとしても、歩く距離は一・五キロ、地下鉄に乗らずそのまま歩いて行くと二・二キロ。
加古江さんは、
「こういうときこそ能力を使うんだよ」
と、空間に歪みを発生させて、その中へ入る。
僕も手招きされて、踏み込んでみると、虹のような、あるいはシャボン玉のような七色の光が揺らめくトンネルが先の方まで続いていた。
「ここを歩くんよ。直線だから二キロくらいかな」
普通に歩くのに対して二〇〇メートルしか縮まってない。
「空間を越えたりはせんとですか?」
「その能力を持ってるのはチル」
「チルって、ギャグ漫画家の
枯葉チル? あの人も島田先生のアシスタントやったとですか?」
「そうよ。ナンセンスギャグの使い手やけん、なんでもありよ」
読んだことはあるけど、あのひとの漫画だったら、ショートカットさせてくれなんてうっかり頼んだら火星に送られかねない。
「この前、錠崎まどか先生に会いました」
「ああ、音楽漫画の」
「凄かったです」
「うん、あの人の漫画は凄いよ」
七色の虹のトンネルの末端は、キャナルシティの映画館のスタッフルームまで通じていた。その揺らめく光の壁越しに、初老の紳士が映画館のスタッフと談笑している姿が見える。
虹色のトンネルから出ると、紳士もこちらに気がつく。
「先生、裕美さんの息子さんをお連れしました」
先生?
わけもわからず僕は前へと促される。
「あなたが勇くんですか。はじめまして。島田です。今日は映画を見に来てくれたんですか?」
状況からすぐに目の前にいる人が島田先生だということはわかった。だけど頭の中のその単語がまだ収まるべき場所に収まらない。
「こちら、僕と裕美さんの師匠、島田巽先生」
加古江さんの紹介の声でようやく、頭の中の『島田巽』の名前が腰を下ろす。
僕は慌てて自己紹介し、挨拶し、そしてまた言葉を選び損ねて自己紹介をする。とっさのことで手札に二枚しかカードがない。
島田先生は新作の舞台挨拶のためにこちらへ来たらしい。それと僕の母、樺島裕美にお別れを言うために。今日は昼と夜二回の舞台挨拶があり、明日、大川の母の実家を訪ね、お線香を上げたい、と。
それから、
「弁護士まかせにはなっていたけど、一応は私が後見人ということになっているので、裕美さんのご両親にも挨拶したいと思っていました」
不意にそんな言葉を聞いて、僕が絶やさないように浮かべていた笑顔のいくつかが、宛先をなくしてこぼれた。
この人が、僕の後見人?
「いやあ、すみません。書類は本名の島津国之で作ってあるから、気づかないのも無理はないでしょう。挨拶は遅れたけど、今後ともよろしくお願いします」
「いえ、こちらこそ――」
その先は事態の把握ができなさすぎて、およそ意味のある言葉は紡げていなかった。実家の方には僕から連絡を入れておきます、と慌ててつくろったのだけど、母がアシスタントをしていた頃に連絡を取ったことがあって、今回はもう連絡は済んでいるという。
劇場のスタッフの人が来て、上映開始の時間を伝える。
作品は、先生が女子サッカー漫画でブレイクする前の短編をアニメ化したもの。今回アニメ化に漕ぎつけたのは、熱烈なファンのクラウドファンディングと、同じくこの作品を愛する編集者の尽力によるものだった。
――江戸時代中期。素浪人が食い詰めて、用心棒に身をやつし、一宿一飯の恩義を果たすために自らの師匠を斬りに行く話。
師を超えることは主人公の積年の願いだったが、彼は門下生の中では落ちこぼれだった。一門を離れて十年が過ぎた今も、無類の技を誇る師に勝てるとは思えなかった。師を斬るよう依頼され、浪人は己の人生の最後を予感する。それでも、恩義ゆえに降りることはできない。母への手紙をしたため、義理の弟に託し、そこに仕事の前金にともらった金を添える。
名乗りを上げ、師の道場へ乗り込む。死を覚悟しての師との斬り合い。たが、師の腕は衰えていた。勝負は一瞬。軍配は浪人に上がる。だがそこに師を越えた喜びはない。直後、その弟子三人に囲まれ、これを斬り伏せ、道場を後にし、浪人は手負いのまま姿を消す。
義弟は、故郷で待つ義兄の母に金を届ける。義兄が念願であった師匠超えを果たし、ついに本邦随一の
士となったことを伝えると、母は涙を流した。
最後に母は、受け取った金を弟に差し出し、「この金で私を斬ってくれ」と頼む。
――陰鬱な作品。師とまみえるまでの浪人の機微が、その視線、目にする景色で淡々と描かれ、最後に母が死を望んだ理由、義弟が母を斬ったか否かは語られていない。この結末の受け取り方は、今もファンの間で議論となる。
舞台挨拶から、質疑応答。
ひとりのファンが、ラストシーンの母の言葉の意味をたずねる。最後に母が感じたのは、喜びだったのか、それとも息子への憤りだったのか。
「ごめんなさい、僕はそれをちゃんと作品中に描いたつもりだったんだけど、伝わってないとしたら僕のいたらなさが原因なので、もう一度、新しい作品でそれを語らせてください。いつになるかわかりませんが、待っていてください」
正直、その質問が野暮だと言うのは僕にもわかった。こうやって躱す以外に答えようはない。質問した方は苦笑いして、ありがとうございました、と、席に座る。
進行役の人が、他に質問はありませんか? と促し、ふと気がつくと、僕はうっかり自分の手を挙げてしまっていた。最前列は関係者席。そこからの挙手に進行役の人が戸惑う。
先生は笑いながら水を向ける。
「関係者席から手が挙がりましたが、受けたいと思います。では、質問を」
受け取ったマイクが少しハウリングを起こす。
「最後に弟が母を斬るか斬らないか、作品中では描かれていませんが、もし先生が弟だったら、斬りますか?」
野暮な質問だ。
会場で聞いている人たちも、そう思っただろう。答えようがない、と。
だけど先生は、
「斬りますね」
と、一言。
「兄が生業としてきた仕事を見てきたわけですよ、この弟くんは。その世界で生きてきて、その世界のルールに倣わないと生きていけないことは誰よりも知ってる。兄のことも母のことも知ってる。この金をどう使えばいいか、兄が何をどう考えているか、すべてわかってる。その上で、僕だったら斬ります」
会場がどよめく。
「この作品は、僕が二十代の頃に描いたもので、ここに描かれた世界というのは、その時に僕がこの作品の中に描けた限界でもあるんですよ。だけどそれからもう、二十年、三十年経ってる。僕もいろんな人に教えているし、みんな僕を超えて成長している。だから、弟子たちだったら、『斬りません』とはっきりと言える作品を描けるはずです。僕が閉ざした、すべての道をこじあけて、彼を救うたったひとつ、小さな可能性を探し出して、それを描くことができるはずです」
先生は僕の顔を見ることなく、会場を見渡したまま話し、最後に僕を見て、
「――これで大丈夫かな?」
と、締める。
僕は立ち上がり、両手でマイクを返し、深々と頭を垂れた。
その後キャナルシティのカフェでお茶を飲んだ。
先生と、加古江さんと、僕。
「加古江はよく怒られてたから、裕美さんに」
先生は舞台挨拶の緊張から開放されて、表情も和らいでいる。
「いや、無茶なんですよ、裕美さんが」
「そうそう。――どうしてこのクオリティでOK出したんですか。呼び戻してください――って、夜中に言われるんだぞ? いや、もう締め切りなんだからこれで出すしか無いから、っつったら、――だったら加古江くんじゃ間に合いません。私が描き直します。キャラだけ先生が入れてください――って」
「そこまで言ったんですか、彼女」
先生は眉をひそめて頷く。
「それで、直したんですか?」
と、僕。
「直したよー朝までかかってー」
漫画を描いていた頃の母のことを聞いても違和は感じなかった。どんな逸話を聞いても、母ならそうすると思えた。しばらく三人で話した後、先生は次の上映の舞台挨拶があるからと、三人分の支払いを済ませて、劇場へと戻る。
その背中を見送りながら、加古江さんと僕とで深く頭を下げる。
「それじゃあ、明日、迎えにあがりますんで、また連絡します!」
先生の姿が消えると、加古江さんの顔からふっと緊張が抜ける。
「いちばん親身になって教えてくれたのが裕美さん。いちばん厳しかったのも裕美さん。それと、僕が先生のオフィスに行った初日にカッターナイフ持ったまま転んで怪我させたのも裕美さん」
と、左手に残る真っ直ぐな傷跡を見せる。
「じゃあ、もうすぐ僕もその怪我をするんですね?」
「するよ。上京した初日に。覚えといて」
加古江さんは、しみじみと手の傷を眺めながら、当時のことを語ってくれた。
――地元の専門学校に三年通って、上京したのは二十一の時。
高校の頃に描き始めた絵は、上達したとは言っても、他の連中にはまだ遠く及ばなかった。だけど、それでも僕は、諦めたくなかった。
専門学校を卒業するまで、漫画を投稿して、何度か賞をもらって、担当の編集者もついていた。それで学校を卒業する頃に、編集さんから電話がかかってきて、すぐに上京できるか、できるんだったらアシスタントの席が一つ空いたんで頼みたいって言われて……まあ、いろいろと片付けなきゃいけないことはあったけど、大急ぎで終わらせて、最低限の荷物だけ持って上京して、それから部屋を探した。
あの頃先生のアシスタントはたしか、リードが小野田さんで、カズサさんが僕の少し先輩でスクリーントーン職人、裕美さんがまとめ役、修羅場の時に
思妤がヘルプに来るって感じで動いてて、僕の仕事はひたすらベタ塗りだったね。今考えるとレジェンドメンバーだよ。僕以外は。
裕美さんは、あの時点でアシスタントはもう二~三年やってたんだよ。リードの小野田さんは一年くらいで、彼も裕美さんが育てたの。樺島裕美は島田先生の相棒と言っていいポジションだったと思うよ。
それで、新人にあれこれ教えるのは裕美さんの役目。それまであんまり女子と話す機会がなかったから、最初はやっぱり緊張したよ。裕美さんはそういうのはあんまり気にしないタイプだったから、教えてくれる時の距離感が近いんだよ、妙に。
で、僕が入って半年くらいで小野田さんがデビューして抜けて、エミルが臨時で入ってくるんだけど――森エミル。今じゃあもう押しも押されぬ大作家――もう化け物みたいにうまくて。しかも裕美さんと同じ少女漫画系だから、本人すごく劣等感を覚えたみたい。その頃なんだよ、「このクオリティでいいんですか」って先生に詰め寄ったの。
それでエミルもすぐデビューして、連載持ちながらアシスタントにも来て、向こうでもアシスタント抱えて、交流するようになって、表面上は楽しくワイワイやってたけど、裕美さんはもう、ピリピリして見てられなかった。
それで彼女、一ヶ月くらいかな? 体を壊して休んで、そのあと精神的に外に出られなくなって、でも収入ないと生きていけないからって、先生が仕事を都合してあげたの。漫画プレスの特別読み切りのネーム。キャラだけ空けて下書きまで。漫画ってかける時間の半分以上ネームだけど、キャラだけ先生が入れたら、先生の漫画っぽくなるから。先方ともそれで合意して、で、それを完成させて、当然『島田巽』の名前で発表されるわけよ。もちろん、裕美さん本人もそれは承知の上で。
で、その漫画が好評で、『続編をお願いします』って来たの。漫画プレスから。
当然、今度も裕美さんにネームを、ってなるわけじゃない。
だけど彼女は、これを受けずに、実家に帰った。
エミルに差をつけられて、自分の名前は出せないで辛いんだろうなって思ったよ。
あるいはそうやって、おこぼれみたいに仕事をもらうのも嫌なんだろうな、って。
僕、彼女の部屋に行ったんだよ。二回目の仕事断った時。
仕事受けたほうがいい、生活どうするんだ、このままだと実家帰るしかなくなる、先生はその漫画をきっかけに、裕美さんをデビューさせる気じゃないのか、って。
そしたら彼女、『怖い』って。
先生の名前で描いて、読者の期待に応えられる自信が無いって。
僕から見たら杞憂だよ、そんなのは。できるんだよ彼女だったら、そのくらい。
なのに彼女、震えて、泣き出して……
先生に、裕美さんを実家に帰るように諭してほしいって言ったの、僕なんだよ。
さっき先生が言ってたし、僕もよく言うんだけど、『万に一つの可能性を探せ』って。あらゆる希望が断たれた絶望の暗闇から、たった一つの可能性を示してみせるのが漫画だ、って。でもそれは漫画だからなんだよ。
答えなんかないよ、現実には。
あの時の裕美さんに何を言っても、彼女を漫画にとどまらせることはできなかったんじゃないかな。だれにも――
「彼女が結婚したって聞いた時は、寂しい気もしたけど、嬉しかったっちゃ。もうよか、こいでよか、最悪の結果だけは避けたち思うて」
加古江さんは息継ぎをするように、わずかに残ったコーヒーで口を湿らせる。
「さっきから僕ばっかり話しよるばってん、逆に、よ。逆に聞くけど、樺島やったら何かしてやれたち思う? あの時の裕美さんに」
「僕が、加古江さんの立場だったら、ですか?」
「そう。さっき先生にかなり無茶な質問してたよね。『先生だったらどうしますか?』って。今度は樺島が答える番」
加古江さんは、僕にマイクを渡す。
「さあ、どうぞ。樺島裕美は自信がない、描けないと泣いてます。どう声をかけますか?」
僕は……
加古江さんの差し出したマイクを静かに受け取る。
「僕が描きます」
「はあ?」
「僕は下手です。先生みたいには描けません。でも、母さんが……樺島裕美がそばで見てくれているなら、僕が描きます。母は絶対僕を見捨てないし、僕も見捨てません」
僕がそう言った途端、加古江さんは崩れ落ちた。
やっぱりこの人は好きだったんだ。母さんのことを。
――裕美さんが大川の実家に戻ってすぐ、僕も先生の元を離れた。
自分の作品に集中します、とは言ったけど、心の支えを失ったんだと思う。
何を描こうとしても、ぜんぜん手につかなくて。
それから一年ほどして、先生から連絡があった。
漫画プレス用の読み切りを手伝って欲しい、って。
裕美さんが受けてた仕事。
たぶん先生は僕が食うや食わずの生活をしてるのを知ってて、仕事をまわしてくれてるんだ。そう思うと素直に受けることもできなくて。
それに僕は裕美さんみたいに器用じゃなかったし、正直、パワーで押すタイプ。絵も上手いとは言えない。それを先生の名前で描くなんて。
僕が失敗して恥をかくのならいい。だけど恥をかくのは先生で、そうなったら僕は失った信頼をどうやって取り戻せばいいのかわからない。
エミルだったら描ける。あるいは小野田さんでも。でも、僕には無理だ。
裕美さんが言った『怖い』の意味が、身を持ってわかった――
「おまえさあ」
加古江さんが目を赤くして言う。
「おまえが言うとーとは、おまえ自身が生まれない世界線に行くパターンやぞ」
この人は本当に未来の僕のつもりでいるんだろうか。
「だいたい人に回った仕事を『俺がやる』って言うの、タブーやぞ。お前は裕美さんの最愛の息子やけんそれで通じようばってん、普通はそげんはいかんと」
母の青春時代。聞いたこともなかったことが、次々と知らされる。母は加古江さんのことどころか、東京に行ってた話すらしてくれなかった。祖母からその話を聞いたときは、夢が破れたショックが大きくて、話せなかったんだと思った。だけどいま、なんとなくわかった。家族にその話をしなかった理由が。
「母も加古江さんのことば好いとうたち思いますよ。そうじゃなかったら、東京にいたときのことを一言も家族に言わんち、考えられんけん」
そう言うとまた、加古江さんは顔を覆った。
「過去の自分から言われるのは堪えるわ」
加古江さんは呻いているけど、加古江さんが本当に未来の僕だとしたら、僕はもうすぐ自分を生んだ人に出会うことになる。でも、あるわけがない。そんな話。
「伊藤って子、知ってます?」
知らないでしょう。他人なんだから。
「知ってるよ」
加古江さんが顔を上げる。
「美容院の子やろ? 薬院のモデル事務所に登録しとう」
記憶のノートのページを捲る。この人がそれを知っている可能性。それが、どこにあるのか。だけどページは捲られるだけ。何も目に留まらない。
「忘れるよすぐ。正直に言うよ。僕は裕美さんが好きだったよ。今のお前の、芽郁への思いなんかとは比べ物にならんくらい」
翌、日曜日。
柳川駅で先生と待ち合わせる。
祖父のバンに乗って、大川の呉服屋まで。中古車販売店、ディスカウントストア、背景に描かれた稲の絨毯、スクリーントーンを削った雲。柔らかく回したハンドルが、緩めた手の中をするすると戻る。
沖端川を渡り、狭い県道へ。春の鳥の名前、土地の歴史、幾重にも言葉を交わして、方向指示器のかちかちと言う音で、車を停めて、切り欠いた歩道にドアを開く。
祖父のあとに続いて先生が暖簾をくぐる。高い背を屈めて「おじゃまします」の声を響かせると、慌てて出てきた祖母が膝を畳んで、先生も恐縮して腰を曲げる。背の高い先生の視点を通して見る母の実家は、小さかった。
仏間には、祖父母の父母らしきひと、よく知らない親戚、小さな子どもの白黒写真が掲げられ、それに並んでカラー写真の母の遺影がある。その写真の中の匂いを知っている。
先生と加古江さんは、東京にいた頃に母が好きだった店のマドレーヌと、一番好きだった紅茶の缶を供えて、線香に火を灯し、鐘を鳴らして、手を合わせる。
「今日はわざわざ裕美のためにありがとうございます」
「いえいえ、こちらこそ挨拶が遅れまして。後見人の件でも、今の今になるまで」
祖母が来て、お茶が入りますからと居間へ促すと、加古江さんが、これ、と、マドレーヌの箱を指し示す。
「裕美さんが好きだった、川端康成も通ったと言われる店のマドレーヌで――」と、切り出して、次に紅茶を指し示す。「紅茶はこの『カレル・チャペック』がお気に入りで、カレル・チャペックと言うのは、『ロボット』という言葉を作ったチェコの小説家の名前と同じとです。だから裕美さん、紅茶はこれ一択しかなかち力説しとうたとですよ」
「ああ、それじゃあどうしましょう」
と、祖母が戸惑う。
「僕が淹れるけん。お母さんの使うとったティーポットのあったごたる気がする」
ありがとう、と、加古江さんは紅茶の缶を手渡して、言葉を続ける。
「裕美さん、マドレーヌを紅茶に浸して食べてませんでした?」
ああ、と僕は思い当たる。子供の頃は真似して食べていた。中学に入る頃からみっともないと思い始めたけど、東京でもずっとやってたんだ。
「あれ、プルーストの『失われた時を求めて』っていう小説の冒頭なんですよ。主人公がその匂いを嗅いだら、幼かった頃の記憶が思い出されてくる、お話に入る最初のきっかけなんです」
言葉は僕の目の前に、パッと道を示してくれることも、それをかき消すこともあった。今の僕の目の前には、道の見えない入り口だけ。でもその先には、不思議なときめきがある。
「あとで詳しく聞かせてください」
祖母と僕とで台所に立つ。
揃いのカップがなくて、母が結婚式の引き出物に用意したカップが残っていたからと戸棚の下の開き戸を開ける。十二月の結婚式、クリスマスにちなんで持ち手が天使の翼になったカップ。お気に入りだからと僕の部屋でも使っていた。
湯が湧き出し、茶葉を蒸らし始めた頃に祖母はおろしたてのカップを洗い終えて、テーブルに並べる。祖父と先生がどんな話をしているのか、はっきりとは聞き取れなかったけれど、台所から顔を出して覗くと祖父が涙を拭っている姿が見えた。
母の分まで含めて、紅茶を六杯。マドレーヌを木の器に盛る。母の仏前に座り、母と六人でマドレーヌを紅茶に浸した。
確かに幼い頃に食べた味。おそらくは加古江さんも食べたことがあるのだと思う。カップの中の波紋が静かに、母の部屋とこことを繋いでいる。
「ああ、わかりますね。始めてなのに懐かしい味がします」
先生は胸いっぱいにその匂いを吸い込む。
その香りで時間が巻き戻っていく。
古い写真の色は褪せるけど、本当の過去は陽の光を蒸発させた濃厚な色と、胸の中から呼び戻される匂い。
ふと見ると祖父の姿がない。
そこにはネコのぬいぐるみがある。
以前写真で見た、母が抱えていたぬいぐるみ。
眺めていると、そのネコが立ち上がる。
「ノリさんは筑後川昇開橋に行ったにゃあ」
と、両腕を使って一方を指し示す。
祖母が慌てて立ち上がり、
「ひといで行かしゃったと?」
と、たずねると、ネコの人形は背伸びをして、んん、と力を込め、ぽんと弾けて人間の姿になる。
大きなワッペンのあるジップパーカー。タイダイのTシャツ。蛍光ピンクのラインが入った黒いボトム。
「チル! なんでおまえまで!」
その姿を見て、加古江さんが呆れたように声を上げる。
「おもしろそうなことやってるのに、なんで私には連絡くれないんですかー」
ベビーバングのシャギーのショート。チルという名前ですぐに思い当たった。枯葉チル。青年誌にナンセンスギャグの連載を持つ漫画家。顔は初めて見る。
「おまえ、いつもめちゃくちゃにするじゃん」
「そんなことないですよ。怖いなあ、イクトせんぱいはー」
チルさんは悪戯に笑って、フードを被る。
「もうすぐペルセウス流星群ですよー」
「ああ。わかってるよ」
「ことしの流星群は三万年に一度の大流星群。はじまりますよー、ゴルゴンたちとのラグナロクがー」
戸惑う祖母に、先生は声をかける。
「私たちも行きましょう。筑後川昇開橋に」
祖母がうなずくと、加古江さんは次元の扉を開く。それを横目に、
「それじゃあ、わたしはおさきに~」
チルさんはネコのぬいぐるみに戻って、両腕を引いてタメを作って猛スピードで部屋を飛び出していった。
残された四人、祖母と、先生と、加古江さんと僕、虹色の次元の穴へ入り、
「履物をお持ちしました」
と、祖母が持ってきた靴を履く。
「僕らはここを歩きです」
「やっぱ中途半端だよな、おまえは」
「凹むからやめてください」
靴の紐を締め直して、さあ、歩こう。と、立ち上がったとき、かかとに翼があることに気がつく。
「先生、これ」
見ると先生の靴にも、加古江さん、祖母の靴にも。
筑後川昇開橋。
今は遊歩道となった鉄橋。
でもどこか違う。柔らかな音。止まった空気。足元には、佐賀線のレールがある。
レールの先へと視線を移すと、橋の上に幼い母と、カメラを向ける若き祖父の姿がある。昇降するブリッジの手前、左手にはプレハブの二階建て。ガタがきて傾いだドアにはカギが掛かる。
よどんだ空。上流にふった雨で、かさを増した水面。防火用水の赤いドラム缶。昇降部のブリッジはくさりで締め切られている。
若き日の祖父、ノリツグは、腰を低くして一眼レフのカメラを構えている。
「ひろみー。もっと笑ってー。はい、チーズ!」
幼い母、ひろみは眉をしかめ、口を結んで、その手にはネコのぬいぐるみがある。
「もうしゃしんはよかーっ」
ノリツグが苦笑いして、灰色の空を見上げると、風はアンテナを揺らして、絹を裂く長い音を響かせる。雲の奥深くには、雷鳴が響いている。
週に一度の店休日、あいにくの曇り空。雨になる前に、ひろみの笑顔をフィルムに収めたかった。ぎゅっとぬいぐるみを握ったしかめっつらに、一枚だけシャッターを切ると、ため息がこぼれた。
フィルムを巻き上げながら、
「そろそろ雨の降ろうたい」
そう口に漏れたとき、ひろみの手に抱かれたネコの目が光った。
「アメ、ガ、フル……?」
ぬいぐるみの口から、かすかな声が聞こえた。
「えっ?」
ひろみの口にもかすかな疑問の音が浮かんで、手のなかのネコにまさかの目を向ける。
まさかこの子が?
――口のなかにふくれだす言葉が、静かな吐息になって漏れると、赤いサンダルの足元に、どこかからアメ玉がころがり落ちてくる。
「アメ?」
ひろみがネコにたずねると、ネコもゆっくりとひろみの顔を見上げる。
目をあわせたふたりの足元、いっこ、またいっこと、アメ玉が落ちてくる。
おとうさん! ――息をのんで、その言葉を口にしようとしたそのとき、
「あめがふりだすぞー!」
岸のほうから声が聞こえた。
はっとしてふり向くと、線路の先に人形の駅員の姿が見える。
人形はふたり、息を切らして駆けてきて、プレハブ小屋の前まで来ると、がちゃん、とカギをあけて、ひとりはそのまま中へ入り、がちゃん、もうひとりが線路のくさりをはずした。
がたん、がたん、ごとん。
足もとの床がゆれて、長い長い笛が鳴りはじめると、プレハブ小屋のまどから駅員のひとりが顔を出して、旗をふる。
「あんぜんかくにーん! ブリッジをあげろー!」
「あんぜんかくにーん! ブリッジをあげるぞー!」
その声を合図に、ひろみの目のまえの、大きな鉄のブリッジがあがっていく。
ノリツグはとまどい、あたりをキョロキョロと見わたしているが、ひろみの表情は少しずつ笑顔へとかわっていく。
ごとん、ごとん、とのぼっていったブリッジが、てっぺんにとどいて、
がしーん!
大きな音をたてて橋をゆらすと、川の下流を見つめていた信号が、赤から、青へと変わった――つぎのしゅんかん、水の中からカラフルなウロコをまとったオモチャの潜水艦が浮かびあがる。
ひろみの目もと、口もとに、笑顔がほころぶ。
くもり空のした、川面を見つめる親子のまえを、ぐりぐり目玉の潜水艦が横切る。
「おとうさん!」
なんどか言いかけてのみこんだ言葉が、やっと口に出る。
背伸びするひろみの手をとって、ノリツグがかたぐるますると、遠くには三本マストの大きな帆船が見える。えんとつを立てた外国の客船が見える。紙ふぶきの大砲を撃つ海賊船が見える。
潜水艦が大きな目玉からサーチライトを照らすと、灰色の空が割れて、青い光が降り注ぐ。川面がその青に染まる。
「いろがもどってきた!」
ひろみがゆびさす先には、色とりどりの魚が泳ぐ。右にも、左にも、魚が群れなし、そのきらめく水面を大きな波が分けて、パステルカラーのクジラが姿を見せる。
クジラは、おおきく、おおきく、空中にはねて、
おおきな、おおきな、波をあげて、
おおきな、おおきな、せなかから、
おおきな、おおきな、潮をふきあげて、
その水滴はキャンディーになってふりそそぐ。
「あめだー! あめがふってきたー!」
船に乗ったひとたちが窓から手を出して、それを受け止める。
空にはストロベリーキャンディの大きな月。モコモコのくもにはクレヨンのラクガキ、オレンジ、さくらんぼ、りんご……そのラクガキが飛び出して踊りだす。
空をとぶネコ、ニコニコ顔のアヒル、キラキラとウロコを光らせたドラゴンと、白い貝をかざったマーメイド。
どこまでもどこまでも広い大河に、船と生き物とがひしめきあう。
そのとき、警笛が聞こえてきた。
ひろみが振り向くと、オモチャの汽車が線路を走ってくる。
「あぶない!」
「予定んなかった汽車のきよるっ!」
駅員さんはパタパタとあわただしくなるけど、せまりくる汽車は、ひろみが「まて」と手のひらを見せると、そのまえで止まる。
おどろいたのは、オモチャの駅員さん。
「すごか!」
「この子はなんばしたと!」
駅員さんも、ぬいぐるみのネコも目を丸くする。
もじもじするひろみにかわって、ノリツグがこたえる。
「この汽車はひろみが走らせとうとばい。そうやろう、ひろみ」
父にたずねられと、ひろみはとくいそうにうなずく。
川面から魚がはねる。つぎからつぎへと、見たこともない魚がはねる。
その見たこともない魚をノリツグがゆびさすと、ひろみはその場でなまえをつける。
ぷかぷかはぽぉー。
べたーんげれろ。
もももりもー。
祖父はひとつひとつ頷いて、また他の魚を見つけてゆびさす。
母はなまえをつける。いつまでも。
まだだれも口にしたことのないなまえが、母の口から、あふれつづける。
第七章 古い記憶
先生に会ってからも、ずっと迷っていた。
本当に僕は進路として漫画を選んで良いのだろうか。
真面目に考えてくれる人なら、漫画はひとまず置いておけと言う。おそらく、だれに聞いても。自分でもそれはわかっている。
ネットで質問箱的なところを見たら、『まずは賞を取れ』と書いてあった。
――賞を取れなかった場合、どうすればいいですか?
――諦めろ。毎月何人が賞を取ってるか数えろ。
僕は賞どころか、年内に完成するかすら怪しい。受験は嫌でもやってくるのに、天秤にかけるほうがどうかしている。
このところずっと神話のことや民俗学なんてものを調べているので、もう少し準備の時間があったら、社会学部、文学部などを狙っていたんだと思う。だけどもうすぐ高校三年の一学期も終わる。もう高望みは出来ないし、今から出来るのは、自分の成績に合わせた進路を選ぶくらい。だけど経済学部にしても、工学部にしても、それを学びたい人が行くのだと思う。
じゃあ、漫画は?
篠宮は――あいつは、九州大学の機械航空工学科を受けると言う。
「絵を描くためにも、航空機や機械工学の中身のことを知っておきたい」と。
あれだけの絵を描ける篠宮がそれを即断して、僕が漫画の投稿にこだわっているのは、傍からは滑稽に見えるだろう。
篠宮が僕の漫画を気に入っているのも、時々よくわからなくなる。下手なりに変な自信はあっても、評価されると戸惑う。
執筆の手が止まって一週間。
僕の目の前には、たくあんコーラとうめぼしコーラが並んでいた。
「どっちがいい?」
たくあんコーラを手に取って飲んでみるけど、正直、味のことはあんまり頭に入ってこなかった。
「僕は、どげんしたらよかとやろか」
膝の上、両手を組んで握った、たくあんコーラの瓶。その雫が僕の手に伝う。
「どげん、と言うと?」
今までに思っていたこと、不安、進学のこと、とりとめもなく加古江さんに話した。
僕は――
「僕は、漫画家になれるとやろうか」
加古江さんはソファに深く座り直す。
「なれるよ」
簡単に言う。自分は諦めたくせに。
「ベレー帽をかぶって、Gペンを持てば、それだけで漫画家だよ。なれるよ」
そうじゃない。漫画家はどうせ自称に過ぎないって言いたいのかもしれないけど、僕が相談してるのはそうじゃない。もっと深刻な悩み。母からの遺産、社会に出るまでの時間を本当にそれに費やしていいのかどうか。
そういうと加古江さんは、
「わかってないのは君の方だよ」
と、深い嘆息を漏らして見せる。
「君がなりたがっている漫画家ってのはただ、ベレー帽をかぶってGペンを持ってる人だよ。なりたけばなればいい。今すぐになれる」
何を言われたのか、すぐには飲み込めなかった。戸惑いは加古江さんにもわかってるはずなのに、何かを気づかせたいのか、少し間をおいて言葉をつなぐ。
「昔、先生に聞かれた質問があるんだけど、それをしてもいい?」
「先生って、島田巽先生?」
「そう」
僕がうなずくと、加古江さんは続ける。
「貧乏は、どんな顔をしていると思う?」
貧乏の顔――
漫画でよく描かれているのは、ツギハギの汚れた服を着て、顔もみすぼらしくて、ボロ家に住んでて、貧相な食事をしていて……それから最後に、でも、夢は持ってる、と付け足すと、加古江さんは首を振る。
「じゃあ、君の回りにはいたかい? そういう貧乏な子が」
そう返されて、咄嗟に浮かんだ言葉は「いるわけがない」だった。
「枯葉チル、このまえ会っただろう? 彼女、貧乏だと思った?」
加古江さんは質問を重ねる。
「漫画が当たる前はすごい貧乏だったんだよ。でも見た目は今と変わらない。美容院に行く頻度とかは変わってると思うよ。でも、変わらないんだよ。彼女からよく貧乏エピソードを聞いたんだよ。『土を食べようとした』とか。こんど彼女の漫画を読む時、思い出してみたらいいよ。何が彼女の漫画を作ってるかわかるから」
へえーとか、そうかーとか、そんな言葉しか浮かばなくて小さく頷くと、それを見留めて加古江さんは続ける。
「貧乏に顔はないんだよ。そこいら中にいる普通の人が貧乏かもしれない。あるいは着飾って贅沢に見える人がそうかもしれない。貧乏っていうのを描く時に、ありきたりの他の漫画のイメージを持ってきて、服にツギハギを描いて、割れた窓にテープを貼って、これが貧乏ですってやっても、それで貧乏を描いたことにはならないんだよ」
里崎先生が言っていたことと反対だった。里崎先生は記号一つで表現できると言ったけど、そのことを言うと加古江さんは、
「その先生が言ったことも真実だよ。その話は一限目。僕の話が二限目」
と、指を一本、二本と開いて見せて、続けてたずねる。
「じゃあ、漫画家はどんな顔をしていると思う?」
ここでやっと話がつながった。だけど僕はまだ周回遅れ。
「漫画家って言葉を使わずに、自分がなりたいものを説明できる? あるいはお金持ちになりたいとしてもそうだよ。お金持ちって言葉を使わずになりたいものを説明してみて。芸能人も、芸能人って言葉を使わず。で、あらためて聞くけど、君がなりたいものは? ベレー帽をかぶってGペンを持った人? それは違うって言ったよね」
「わからない……」
言葉の足がもつれる。
自分から振り出した話、僕の悩みに答えてくれた話なのに、言葉はどこか遠くを走っている。他人ごとならいいのに。もうひとりの僕が手を引かれて遠くを走っていて、僕はそれを追いかけるしかない。
「何になりたかかはわからんちゆうか、それがわからんけん相談しよるちゆうか」
少しパニックになりかけたんだと思う。加古江さんは、わかったわかった、落ち着いて、と、僕の言葉を止める。
「じゃあさあ、友達にミュージシャンに憧れてた子がいたでしょう?」
「矢口?」
「そう、矢口くん」
うめぼしコーラを飲んで、炭酸の息を吐いて、続ける。
「彼がミュージシャンになる物語を考えてみて。妄想でいいから、なんでも。君の考えたストーリーで、彼をミュージシャンにしてみて」
「えっ……? 今ここでですか?」
「早く答えが欲しいんだったら、今がいい。急がないんだったら宿題でもいいよ」
答えを急ぐわけじゃないけど、でも。
「矢口は――」
まずは切り出すだけ切り出して、頭のなかに矢口のファイルを用意する。
「矢口はああ見えて凝り性で、一度嵌りだすと集中するけん、きっかけさえあれば伸びるタイプち思う。楽器はギターやけん、バンド仲間ば探すっちゃなかろか」
たどたどしく物語を紡ぐと、
「でも、みんな受験勉強中だよね? 相手にしてくれる?」
加古江さんが細かい質問を投げてくる。
「受験が落ち着くまでは、そげなムードじゃなかけん。受験はするち思う」
顔色を伺いながら話すと、うめぼしコーラを持ったままの手で先を促される。
「――来年の春から、福岡の大学に通い始めて、軽音楽部に入って、ライブハウスにもちょくちょく行くようになる。バンドも組むち思う。仲間と。軽音楽部には刺激んなる同期や先輩んおって、ライブに出とう連中は滅茶苦茶に腕が良くて、改めて自分の短所ば目の当たりにして、それがきっかけで練習して……」
「練習して? その時間は?」
時間。いつもそこにあって、僕たちがつかまえそこねているもの。加古江さんはその流れに言葉を浮かべる。
「学校の単位もあるし、卒業はどうするの?」
言葉は僕の目の前を流れ、とっさに手を伸ばして、
「――学校の単位は、矢口は『勉強せんでよかとこがよか』ち言うとったけん、大学はレベルを落として……」
そうすれば、時間は生まれると思う――そう出かかった言葉を飲み込んだ。
そこに生まれる時間。それは何もない、空虚な時間だ。
矢口の顔が思い出された。中学からのいろんな表情がスライドショーの映像で流れる。付き合いも長く、お互いのことはよく知っている。時間なんか、ずっと持て余してきた。
「じゃあ……」
加古江さんは話を区切って、
「もし矢口くんが、ミュージシャンになるために、学校のレベルを落とすって言い出したら、賛成する?」
と、水を向ける。
わからない。それでうまくいくとは思えない。
それにたぶん、あいつはそんな選択はしない。あいつは――矢口は、スイッチが入らなきゃ何も出来ないやつだから、何かやるとしたら、手を抜くんじゃなくて、走り始めると思う。
そう説明すると、加古江さんは背中をソファに預けて、うめぼしコーラの息を右手で押さえた。
「じゃあ、いままでの話はやりなおし。矢口くんの物語を考えて」
また最初から。
ため息を漏らすと、加古江さんは言葉を継いだ。
「漫画のお話を考えるのも同じなんだよ。可能性なんかいつもゼロなんだ。そこに道筋を見つけるのが漫画だよ」
取り繕ったのかもしれないけど、ただ――可能性なんかゼロ――という言葉が、胸に刺さった。可能性なんかゼロだから、僕も矢口も夢なんか持ってない。退屈な高校生活を送るだけ。言葉にしなくても、最初からわかってた。あいつが言うミュージシャンだって、本気じゃない。それは僕の漫画だって同じ。
「でも、失敗するよね」
矢口だけじゃない。僕も同じように感じていた。
みんなそうなんだよ。失敗するよ。可能性なんかゼロだよ。真剣にやってるやつなんか、笑いのたねだよ。その事実を僕は、現実のみならず、創作ですら変えることができないんだ。わかってたんだ、最初から。漫画家なんて、無理だ。
泣きそうになる。
逃げ出してしまいたい。
でも――
母さんだったらどんな物語を描くんだろう。
そう思うと、母のノートが胸に浮かぶ。
――これらの事件が、すべて劇的に解決する――
でも、ありえないよ、母さん。
そんなできすぎた物語、あるわけがない。
思わず両手で顔をおさえると、
――そうかな?
母の声が聞こえた。
――私はそうは思わないよ。
でもそれは、母さんだからだよ。
――お母さんが特別なんだよ。僕には才能なんてないんだ。
――才能なんか要らないよ。大切なのは才能じゃない。才能なんかより、ずっと大事なものがある。さて、それはなんでしょう?
――才能より……?
――才能で描いてるひとなんていないよ。それでも描くんだよ。そこには、理由がある。才能なんかじゃない。それがわかんないなら、漫画なんか描かなくていい。
――いやだ。僕は描きたい。理由は、描きたいから。やっと、はじめて僕が、言葉をちゃんと表現できるようになったんだから。
――そうだよ、言葉だよ。じゃあ、矢口くんにどんな言葉をかける? そこになにかの才能が必要? 才能がなければ言葉さえかけられない? 違うでしょう?
そうやって母と話しながら、頭のなかでダイアグラムを追ううちに、矢口の取ったノートが思い出された。
――そう、それ。
――これ?
母がそのノートを指差す。
――そう。ちゃんと見て。
――ちゃんとって、何を?
――ことば。
鉛筆と、赤、青の線でびっしりと書かれたノートには、母の構想メモにも似た高揚感があった。机にしがみつくようにして、シャーペンの他に二色のボールペンを同時に持って、教壇と、黒板と、教科書を追いながら、ペンを走らせる矢口の姿が見えた。
「うひょ」「いやいやいや」口のなかに含ませた独り言が漏れ聞こえる。
僕はその傍らに立って、かけるべき言葉を探す。
――なあ、矢口さあ。
声をかけると矢口は、僕に一瞥を投げて、それでもペンは止まらない。
――ミュージシャンになるち、本気で言うとうと?
何度かたずねてきた問いを、改めてその横顔に問うと、
――そんくらい、わかろうもん。
矢口はやるせない笑顔を向ける。
わかる?
わかるって、何が?
親友だからって、口にしないことまではわからないよ。
――それで樺島、お前は?
――僕?
教壇の坂田先生の声が裏返ると、矢口は「うひょ」と笑って、青いペンに持ち替えて下線を引いた。教科書、
48ページ。赤い文字で記したあと、教科書にもライナーを引く。
そして、ふと――
「あいつ、一年浪人して音大目指すかもしれん」
胸の中に生まれた言葉が、口から羽ばたいた。
加古江さんはすぐにその言葉をつかまえて、質問の足枷をくくりつける。
「音大はレベル高いよ。一年浪人したくらいで行けるかな?」
だけど僕自身どうしてそう思ったのか、まだ理解できていない。
ただ、幼い頃にピアノを習ってたのは聞いてる。演奏は聞いたことないけど、基礎は出来てると思う。だからきっと……親に頭を下げて、塾に通って、レッスンも受けさせてもらって……
その動機は? どうしてミュージシャンじゃなきゃ駄目なの? 高卒で就職してもいいし、普通に進学してもいいよね?
言葉が苦手なんだ、あいつは。自分の気持を説明できずにいる姿を、何度も目にした。言葉だけじゃなくて、生きるのが下手なんだと思う。
でも、それで親を説得できる?
それは親もうすうす知ってる。だから彼には医者の道を勧めなかった。このまえ漫画を批判されてからだと思う、あれから矢口は、授業も集中して聞くようになった。あいつは努力なんかできる質じゃないけど、凝りだしたことからは逃げられないやつだから。あいつはただ、楽しいんだと思う。ノートを取るのが。
ミュージシャンは諦めて、まずは進学をと考えたのかもしれないよ?
そうかもしれない。でも違うと思う。先のことなんか考えてないよ、きっと。だったら考えることはもう、いまここに留まることしかない。
それが音楽ってこと?
そう、矢口にとっては。
音大を目指すにしても親は? ミュージシャンで食っていけるの? って聞くよね。
夢なんか、口にしちゃいけないんだと思ってた。笑われるから。傷つくから。でも――
ミュージシャンが無理でも、基礎的な技術や知識があれば食べていける。でも、食うとか食わないとかは関係ない。可能性なんか考えたら、限りなくゼロだよ。だけど、どこを目指すでもなくなれば、最後には音楽しかなくなる。音楽が全てだから。音楽の中にしか見つけることのできないものを探すために。生きるために、音楽という酸素を求めて――
音楽家になるんじゃない。音楽をやるんだよ。
――僕のその説明がどれほど加古江さんに伝わったかはわからない。それに、求められた答えでもなかった気がする。そう言うと加古江さんは、
「うん。それでいい」
と頷いて、うめぼしコーラを飲み干した。
「答えなんか、どこにもないよ。自分で作るんだよ」
僕の手のひらで温まったた瓶の口からは、ほのかにたくあんの香りがする。生ぬるいたくあんコーラを口に含むと、ねっとりとした甘みの上に消えかけた炭酸が思い出したように弾けた。
――決めた
――決めたって、何を?
――漫画家になる
――うひょ
*
国道二〇八号線、大川橋と諸富橋、ふたつの白い鉄骨の橋を渡って佐賀市街地方面へ。地元の馴染みの店で買った海苔を積んで、「こげんして、海苔ば買うて持ってくるけんノリさんちゆうとやろち、本家ん人たちは笑いよらっしゃる」と、市街地を抜けた少し先にある母方の本家、ミツコさんの家を目指す。
ミツコさんの相良家は、祖父の母方のいとこにあたる。母方の親戚は柳川にも多いが、祖父の生家が相良家の近くにあるため、こちらとの付き合いのほうが深い。両親の離婚調停のときには、「有馬藩の好きにはさせん」と、火のような剣幕で乗り込んで来た。
大正時代に建てられたという屋敷には、広い居間があった。障子を開け放った風の通る建屋、窓が作る影、風鈴の音、そこには何かしら、郷愁のようなものを感じた。柔らかく足を受け止める畳、柱の穴に木を切り欠いて詰めた修理跡。
麦茶を頂いて、母の初盆の話。
今年はだれそれの十七回忌、お盆には母の従兄弟たちも集まるので、そこで母の法事も、と祖父は勧められている。
「裕美は最後まで不義理ばしとうたけん」
祖父は低姿勢に断りを入れて、
「なんば言いよらっしゃっとね、そぎゃんこたなかよ」
ミツコさんは笑いながら呆れる。
ここから徒歩圏に相良家の分家が三つある。海苔を持ってたずねると、玉ねぎ、きゅうり、なすなど、出荷用のダンボールで分けてもらえる。
もうちょっと早う来たら、桃があったとに。
勇くんな、琵琶は食べたことがあるとね。
これからはノリさんに世話になるとね。
苦笑いする祖父の傍らには五歳の裕美。話が長引くと、その袖を引く。
初盆の法要は八月十二日の土曜日。家族だけでしめやかに執り行われた。
その夜。
ベランダで星空を見上げていると、祖父が枝豆の入ったボウルとビールを持ってやってくる。
「一緒によかね」
「ああ、どうぞ」
ベランダには、日に焼けたビーチチェアがふたつ並んでいる。
樺島呉服店は、表の呉服店とその裏の別棟の住宅とが繋がった形をしていた。呉服店の通りとは反対側にベランダがあって、そこから日曜大工で作ったような頼りない足場を介して、別棟の屋根の物干し台に繋がっている。物干し台は母の部屋のすぐ外。母の部屋の窓からも出ることが出来た。
祖父はビールを飲みながら、
「裕美が東京から帰ってきたときは、どんくらい嬉しかったかわからん」
と、話し始める。
「久留米に部屋ば借りて、こっちには帰って来んやったばってん、近くにおるち思うだけで気持ちは違うけん。あんまりベタベタしよったら、もうお父さんなしぇからしかーち、また東京に行くかもしらんち、電話もせんでおった。こげーん早う逝くちわかっとうたら、もう少し話しばしとけば良かったち、今んなって思うとう。
大川にはなんもなかけん。東京から戻ってきた裕美には退屈やろうち。久留米やったらボウリング場もあるし、映画館もあるけん、そっちで羽ば伸ばしたらよかち思うとったとよ。
ばってん、あればい。真雪さんに会うてからは、真雪さんが電話してくるっごつなったけん。もー、よかったー思うた。こいでひとりで野垂れ死なれんで済む。なんかあったらちゃんと連絡の来るち」
出会って半年で結婚式を挙げたという話は聞いたことがある。
それを聞いた時はなんとも思わなかった。
だけど、
「お父さんと知り合うたとは、東京から戻ってどんくらいの頃やったとですか?」
と聞いて、
「知りおうたとは、すぐよ。こっち帰ってきてすぐ」
と即答されて、加古江さんのことが少し哀れに思えた。
「春頃にこっちん戻って来て三日目やったろうか。久留米の津福町にある大っか病院に入院して、そんとき顔ば合わせとう。そんときは真雪さんな研修医やったけん、患者との恋愛はご法度たい。だいたい名門のお医者さんの御曹司やけん、裕美には興味もなかったち思うと。あのへんはよかお嬢さんの住んどらすとこやけん。
裕美は二週間くらい入院しとって、真雪さんなちょうどそん途中で高松医院に移らっしゃったけん、一週間くらいしか顔は合わせとらんはずよ。
付きおうたとは、その後たい。夏頃んなって、どっかで偶然会うたち、披露宴の時に再現ドラマんごたっとば見せるやんね、あれで見て知ったたい」
祖父は思い出に浸りながらビールを飲んで、枝豆をつまむ。しばらく言葉をなくして、
「ちゃんと花嫁修業ばさせとうたら、離縁もされんで済んだかもしれんし、病気も早う見つけてもろうたかもしれん……」
視線を下げて、深い溜め息を漏らす。母が実家へ帰るのを嫌っていた理由はなんとなくわかっていた。それを今更伝えたところで、とも思うけど。
「そうかもしれんばってん、お母さんば悪う言わんで。お母さんは僕ばちゃんと一人で育てたけん、十分よ。それでなんか足りんち言うとやったら、お母さんのせいじゃなかよ。高松の問題よ」
祖父は言葉なく、空になったビールをもう一度口へ運ぶ。
流れ星が流れる。
ひとつ。またひとつ。
チルさんは、今年は三万年ぶりの大流星群、ゴルゴンたちとのラグナロクがはじまると言ったけど、本当にそんなものが降ってくるんだろうか。
「来るばい。あんたも覚悟しとかんね」
ふと見ると、母の姿がある。祖父にも見えているのかと思って、祖父の方を見ると居眠りしていた。
「お母さん、ひさしぶりやね。どげんしとったと」
「四十九日過ぎたらあの世に行かないかんとよ。今日はお盆やけん帰ってきたと」
ああ、そうか。ちゃんと理由があったんだ。
「そっちはどう? 悩みとかあるなら、今のうちに言うたら聞くよ」
「悩みは……加古江さんに話して、なんとなく解決したちゆうか、踏ん切りのついたけん、お母さん、成仏してよかよ」
母は僕を見て静かに笑った。
「あ、そうだ。お母さんくさ」
「なんね」
「お母さん、お父さんのこと、ストーカーしたとやろ?」
「はあ? お母さんがストーカー? なんでそげんこつせにゃいかんと?」
「今じゃなかよ。東京から戻ってきて、退院した後。探して待ち伏せたりしたとやろ」
「あっ。だれに聞いたと?」
「やっぱり。さっき、じいちゃんと話しとって、お母さんとお父さんが偶然会ってどうのこうのち言うとって、そいば聞いた時、ぴーんと来たと。お母さん、ストーキングしとう、ち」
「いや、それは、ストーキングち言うほどのことはしとらんよ? 住んどう場所調べて、なんちゆうか、再会の演出んごたっこつはしたばってん、それはストーキングとは言わんもん。だいたい、そげんして再会できたけん、あんたが生まれたとやろうが」
「うん。責めようとじゃなかと。良かったち思う。今まで、お父さんとお母さん、喧嘩しとるとこしか覚えとらんやったけん。幸せなときもあったちわかって、安心した」
「夫としては最悪やったけどねー。研修医の頃はキラッキラしとらしたけん。映画とかでよう『余命何日のなんちゃら』んごたっとあるやん? あれの逆概念よ。『フェロー修了一週間前の研修医』。もう、夢にあふれて、キラッキラしとう。『僕はもう来れなくなるけど、裕美さんだったら大丈夫』って、実質プロポーズやろ、その言葉は」
「ストーカーよ、その発想は」
「そげんゆうばってあんた、こっち、パジャマばい。ベッドに横になっとう。向こう、白衣。聴診器持っとう。もう、無理やけん」
通りに背を向けた母の背後に、凄まじい数に登る流星群が煌めく。
「来たね、いよいよ」
母は背中越しに、自信と高揚に満ちた声を僕に向ける。次の瞬間――前方の空より呉服店の屋根を貫いてベランダに降る影、家全体が激しい衝撃に揺れる。振り返り見ると、スリムな赤い西洋鎧姿の少女の姿がある。鎧、あるいは、宇宙服かもしれない。
「これがゴルゴン?」
家の壁を背に、赤い鎧と母の顔を交互に見る。鎧は大気との摩擦で灼熱し、煙をたなびかせている。鎧は金属か、あるいはセラミック、硬質でありながら身体の動きに合わせて可動するなめらかな繋ぎ目、繊細に加工された文様、膝をついたその四肢が、ゆっくりと立ち上がる。
「これ、今川くんのキャラクターやろ」
「今川くんの?」
「
今川功敬、宇宙の騎士・シバルリック・ゲイト・シリーズのアテナじゃなかと?」
「あー、読んだことあるばって、それがなんで?」
僕と母とが話していると、
「来る。伏せて」
と、アテナ。
肩のハッチが開いて、金属のグリップがポップアップ。右手をグリップにかけ引き抜くと、全長四〇センチほどの銃が姿を現す。
アテナは空の一点を見据え、持ち上げたセラミック質の銃身に赤い光が走る。長く延した腕の先、その指が静かに引き金を引くと、衝撃が僕の身体を揺らした。
轟音のあとに残る耳鳴りと、焼き付いた閃光。次の瞬間には赤い光球が夜空に広がり、そこに浮游する巨大な構造物の姿を浮かび上がらせる。背後の星の煌めきを覆う巨大な闇。その躯体に炸裂した音のない閃光は、しばし静寂の間をおいて、衝撃となって地表を舐める。夜の町に重低音の衝撃が広がる。街路樹が揺れ、屋根瓦が吹き飛ぶ。電線が切れ、街灯の灯り、家々の灯が落ちる。
同時に、ペルセウス流星群が弾丸となって降り注ぐ。家々を破壊し、大地を穿ち、水面に落ちたものは高い水柱を上げる。どこからともなく警報が響き、サーチライトが立ち上がる。町のいたるところで火の手が上がる。闇の中に無数の航空機が見える。地表へとばらまかれる爆弾、連続する爆音。
「大丈夫なの、これ……」
アテナはかかとに光る装置の光圧で滞空、その視線を僕に投げる。
「行くぞ、ペルセウス」
「ペルセウスって、僕?」
「行ってらっしゃい! 勇! がんばって!」
「がんばってって……なんばしたらよかと?」
言っているそばから僕の身体を金属質の鎧が覆う。コンパクトに畳まれた鎧が、いつの間にか背負った背中のパックからかたかたと音を立てて全身に広がり、バイザーが降りる。一瞬の暗闇。次の瞬間にはバイザーのディスプレイに外の映像とともにコンピュータからの情報表示が現れる。
モニターを通して見ると、アテナが撃った敵の姿がはっきりと見えた。
巨大な宇宙船。複数の筒状の躯体が連結し、多数の砲門、大小様々な突起物、四方に張り出した艦橋、独立したブロックと、それらを繋ぐ橋梁、推進部らしき巨大な構造。
眼前のディスプレイに赤い点が表示され、アラートが鳴る。戦闘機らしき機影。宇宙船の側部ハッチが次々と開いていくのがわかる。続けて赤い点が、ひとつ、ふたつと増え、アラートが重なっていく。アラート、またアラート、ディスプレイが真っ赤な点で埋め尽くされていく。
「雑魚は気にしないで」
アテナは光圧を上げて上昇、身体を翻しながら迫りくる機影を次々と砲撃、吹き上がる炎、機影は煤煙を引いて地上へと落ちていく。
僕も空に上がるけど、アテナの砲撃を見守るだけ。その機動はあまりにも激しく、意表を付き、すぐに見失う。引き金を引いた時の赤い閃光がその位置を教え、その光に横切るシルエットがその動きを教える。僕の左右を戦闘機が飛び抜け、硬直していると背後で爆発音が聞こえ、衝撃波が背中を押す。戦闘機と、それを追う赤い光の矢。その攻防。撃墜された機影はもう三〇を数える。その残骸は市街地へ、筑後川の水面へ、あるいは遠く有明海まで飛来し、その一端を水面に取られて転がり、崩壊し爆発、その爆炎が干潟の浅い海を白く浮かび上がらせる。
鎧――鎧状のスーツは僕の意識に感応している。飛びたいと思った方向に飛ぶ。
夜の町に宇宙船が放った影が飛び交う。
樺島呉服店のベランダでは、祖父が和服に着替えて能を舞っている。
影は白い鎌状の光線を放ち、地表を攻撃、そこにある構造物を大地ごと砕いて瓦礫を巻き上げる。攻撃された地表には白く燐光する跡が残る。アテナの攻撃だけでは防ぎきれない。大地を汚す這いずるような白い傷跡、そこに青白い炎が上がる。
「そちらのスーツにも
中性粒子砲が装備されている。音声コマンドでポップアップする」
音声コマンド……口で言えばいいのかな……?
「中性粒子砲を」
そう言うと、アテナが銃を取り出したときと同じように右肩に銃把が飛び出してくる。これだと銃身は僕の身体の中にあることになるのだけど、どうなっているんだ。銃把を握って引き抜こうとして、まっすぐ引き抜けずにたじろいでいると、目の前から戦闘機の直撃を受ける。戦闘機に見えたものは、昆虫のような装甲を持った生物質の何か、具体的にそれが何かはわからない。凄まじい速度で僕に激突してそのまま飛行し、触手で僕の身体に触れて確認している。このままだと地面に激突する。そう思っているとアテナが放った赤い閃光が虫を撃ち貫いて、僕はそのまま地面に叩きつけられて転がる。
凄まじい衝撃を受けたはずなのに痛みはなかった。
アテナが降りてくる。
「ダイラタント流体を用いたリキッドアーマーだ。次元多重化してある」
アテナはスーツの防御性能のことを説明してくれるけど、なんのことやら。
空に赤い閃光が連続して炸裂する。
不安げに見上げると、そこに飛び交うアテナ同様のスーツの影が見える。
「ヘルメス隊、ヘパイトス隊だ。ここはまかせて、私たちはコアへ」
「コア?」
「フォローを」
「フォロー?」
アテナが急加速で飛び立つと、引きずられるように僕のスーツも飛び立つ。どうやら事情もわからないまま、フォローコマンドを入れてしまったらしい。
虫の突進、不意に炸裂する赤い閃光を避けながら、宇宙船本体に取り付く。
その表皮は昆虫の外殻、あるいは甲殻類のようにも見え、ところどころに触手もあり、アテナは左手に持った別の銃で触手を焼きながら艦上を走る。
船体にはいたるところに虫が埋め込まれ、あたかも虫で補修したかにも見える。
「この宇宙船は?」
「
老魁。数億年前に滅びたゴルゴン文明が残した宇宙船だ。その中のグライアイ群と呼ばれる群体で、ペンプレド、エニュオ、デイノーの三隻が融合している。老魁は自己補修機能を持ち、永久に宇宙を彷徨い、保守用の素材を収集するが、搭乗員は何億年も昔に滅んでいる」
「滅んでる……いったいどうして?」
「搭乗員はこの宇宙船自体の補修材として利用されるようになった」
「ということは、あの虫がこの宇宙船の……?」
「そう。二軸神経系を持つ超文明だったが、宇宙船自身が、制御装置の暴走でコールドスリープ中の乗員を補修材として利用することを覚え、やがては船自らがそれを飼育、品種改良するようになった。以来、老魁はこの宇宙を漂い、文明を攻撃し続けている」
「じゃあ、こげな宇宙船、すぐに破壊せんと!」
「いや。それはもう無理だ。この宇宙船は、生物としての意志を持ち始めている。我々はそれとのコンタクトを試みている。成功したら彼女らの数十億年の記憶を取り出すことができる」
「コンタクトって……乗組員とじゃなくて、宇宙船自体と……?」
「この宇宙船は、宇宙の暗黒領域……虚数空間を航行する能力を持っている。私たちが辿り着くことのない、その先の記憶。その情報にアクセスできなければ、いずれにしても私たちは何十億年後かの宇宙の終焉の時に滅びる」
「何十億年後か……?」
「地球ではまだ人の寿命は数十年というところだろうが、私たちの星ではもう寿命は数万年を越えている。科学の発達で、いずれ寿命はなくなる。その時に必要となる情報を知っているんだ、彼女たちが」
難しいことはよくわからなかった。
アテナたち、宇宙の騎士たちはまだ老魁とのコミュニケーションには成功していないという。だが、老魁には数多くのロストテクノロジーが搭載されている。それを防衛システムを掻い潜りながら利用して共存する。時に、文明に牙を剥く老魁と、死闘を繰り返しながら。
今回のミッションの目的は、ペルセウス流星群を追って実体化したグライアイ群から、惑星メデューサを停止させるための情報を得ること。
「惑星メデューサの原子変換炉が異常を来し、石化性重粒子線を放出するようになった。それを止めるために、彼女たちの知識が必要だ。さっき、老魁には自動補修機能があると言っただろう? だが、深深度次元レーダーと、重粒子変換器だけは補修ができないらしく、これが壊れると他の機体に取り憑いて共用するようになる。グライアイ群はこの双方を一つずつしか持たず、三体でこれを共有している。だからこの切替のタイミングで制御を奪って、幻星ニュンペーを探す」
「幻星というのは?」
「三・五次元世界にある高次元惑星。惑星メデューサの石化性重粒子線源を隔離するためのキビシス元素と、粒子線を遮蔽するためのヘルム・オブ・ダークネスがある」
アテナの会話はすべてペルセウス神話をなぞらえている。だけど、僕が書こうとしているものとはまるで違う。
「深深度次元レーダーからの入力が止まると、次元ジャイロが機能を停止、アンチ重力フィールドが失われ、落下を始める。この高度だと地表接触まで三〇秒。その間に機能を回復すれば、浮力回復とともに接触回避マニューバが働き、自動で虚数空間にワープインする。ワープインにかかる時間が推定八秒。その間に中性粒子砲で躯体に穴を開けて脱出する。ワープインに巻き込まれたら、私たちはこの宇宙の外側にはじき出される」
アテナは目の前に現れたハッチの上にセンサーをかざす。
「ここだ。潜入する」
内部は宇宙船と言うよりは、生物胎内。巨大な昆虫が徘徊し、その吐いた糸が壁を覆う。様々な昆虫が壁に貼り付いて宇宙船の機能を代替している。アテナは要所要所で壁を破壊して先へと進むが、すぐにそこに無数の昆虫が集まり、糸を吐いて補修する。
厚い隔壁を超えると、学校の教室ほどの空間にバランスボールほどの球体が浮かぶ部屋に出る。球体は眼球のよう。いくつもの細い糸に支えられて浮かんでいる。その眼球の一点に三方の壁から伸びた触手が接触している。眼球は定期的に向きを変え、そのたびに接触する触手が変わる。
「僕は、何をすれば……?」
「私の操作が終わったら、脱出路の確保を。モニターにターゲットマークが表示されるので、私が指示したらそこを、最高出力で砲撃」
アテナは手の甲に操作パネルを呼び出す。宙に浮かび、バックパックから肩越しにアームを伸ばし、眼球の動きを見守る。そして触手の切り替えのタイミングでアームの先端のプラグを差し込む。船体が大きく傾いだのがわかった。
壁の一面の照明が消える。
「ペンプレド機能停止、降下開始。残時間、三〇秒」
僕のバイザー内のモニターにカウントダウンが表示される。
残り時間表示二四秒で、壁のもう一面の照明が消える。
「エニュオ停止」
残り十八秒、部屋の明かりが全て消え、手の甲のモニターの光だけがアテナの姿を浮かび上がらせる。
「デイノー停止、グライアイ群、全機能停止」
巨大な眼球から壁面へ映像が映し出されている。
三つの影。ゆっくりと像を結ぶ。
まだ人で賑わう頃の久留米一番街。そこには幼い母の手を引いた祖父と祖母の姿がある。母は左右を見渡し、指差した先に映画館。子供向けのアニメを上映している。
アテナはカウントダウン残り八秒で操作を終える。
「残時間八秒、幻星ニュンペー座標確認完了、ペルセウス」
アテナが僕に目配せする。
「深深度次元レーダーの制御を開放する。同時に脱出路確保。タイムカウントゼロで実行する」
僕は頷いて、中性粒子砲をモニターに表示されるターゲットマークへ向ける。照準が重なり、ロックオンのシグナル。
「出力を最大に」
言われた通り、
「中性粒子砲、最大出力」
音声コマンドを送ると、モニターに銃の出力レベルが表示され、それを示すバーが伸びる。対衝撃アラートが流れ、自動的に僕とアテナのスーツの追加装甲が閉じていく。
タイムカウント、3、2、1……0。
アテナが眼球からプラグを抜くと同時に、僕は中性粒子砲の引き金を引く。
巨大な閃光と爆風とが壁面に坑を開け、タイムカウントは8に再セットされる。
「急いで!」
アテナは僕を先に促し、僕は坑へと飛び込むが、その時……
――アテナ――
どこかから声が聞こえる。
「この声は?」
――ギャラクシー・ゲイト、太陽系方面指揮官アテナ――
「グライアイ群……まさか、コンタクトを……?」
残り4秒。巻き込まれる!
「アテナさん! 早く!」
僕は目玉の部屋に戻り、アテナを抱え脱出坑へ飛び込む。
「全力加速! 推進機、全力で!」
残り2秒、僕だけだと加速が足りない。空間が歪み始める。アラートが高鳴る。モニター全面が真紅に染まっていく。
「アテナさん!」
残り1秒、アテナが我に帰る。
「緊急離脱マニューバ」
爆発的な加速。
僕とアテナは消えていく宇宙船からぎりぎりのタイミングで放り出され、そのまま有明海の干潟に転がった。
ペルセウス座流星群が降り注ぐ。
地中奥深くに、悪意を持った闇の群れが身を沈めて行く。
その数は数千、数万、いや、もっとか。
僕が戦っている間、祖父はベランダで能を舞っていた。
演目、殺生石。非業の死の果てに石となった妖狐が、その先もなお人を苦しめる話。
今日、この空に物語を描いたのは、祖父だったのかもしれない。
荒尾干潟を二〇分ほど歩いて陸に上がると、ポケットの中の携帯が震える。
矢口からメッセージが送られてきた。
――一年浪人することにした
理由の見当はついたけど、
――えっ! なんで
!?
スタンプ付きで送り返した。
――決めた
――決めたって、何を?
――ミュージシャンになる
――うひょ
第八章 見えない妖精たち
……より、ご案内いたします。
《第八章・見えない妖精たち》には、グロテスクな表現が含まれています。
小さなお子様をお連れの方は、目次をご確認の上、次の《第九章・炎の生徒会とメデューサの首》までページを進めてください。第九章冒頭に、ささやかながら、第八章のダイジェストをご用意させて頂いております。
繰り返しお伝えします。
《第八章・見えない妖精たち》には、グロテスクな表現が含まれています。
小さなお子様をお連れの方は……
新合川町のショッピングモール。
流れてくる店内放送が、聞くともなく耳に入る。そこに割り込んで――
「先輩!」
僕の背中で、はりのある甘い声がはじける。
その声が耳元を通り過ぎた先、スポーツショップから雑貨屋へと視線を移すけど、その声に振り向く顔はいない。
そこにもう一度、少し沈んだトーンで「先輩?」と聞こえる。
まさかと思って振り向くと、見覚えのない女子の顔がふたつ、僕のほうを眺めていた。「高松先輩……じゃ、なかったですか?」
――僕の旧姓を知っている?
声をかけた子はおずおずとたずね直す。隣の子は「ひと違いやろ、行くばい」と小声で伝え、肘でつついて、声を掛けた子の方も、肩をすくめる。ショッピングモールで女子二人組に「先輩」と声を掛けられるなんて、あまりにも漫画然とした展開。戸惑いながらも、
「高松は昔の名前やけど、君たちは?」
たずね返すと、彼女たちの表情がぱっと綻ぶ。
「小谷です!」
旧姓で声をかけてきたと言うことは、五年生よりも前。クラスメイト全員の名前を覚えてるかどうかも怪しいのに、下級生の名前。
「久保田です。マジで高松さんですか?」
「うん。今は樺島だけど」
隣の子も僕を知っているらしい。
「小谷と久保田、覚えとらんとですか?」
やばいな。ひとの名前って、そんなに簡単に忘れるものかな。
「昔、川南さんと四人で遊んどった」
「ああ!」
川南の名前を聞いて思い出した。
「タコとモチ」
そうだった。そう言えばあのときも、今のようにコロコロといろんな表情を見せてくれた。「いえーい」と、グータッチを求めてくる。
「ちゅーか、なんで名前ば覚えとらんと?」
「ごめんごめん、マジでタコとモチしか覚えとらんやった。雰囲気も全然ちがうけん」
五年生。まだ両親が離婚する前、日吉の小学校にいた頃。親友の川南と、下級生の子ふたり、四人でよく遊んだ。
「あたしたちも本当は先輩のこつ、『チワワ』ち呼んどったとですよ。似とるけん」
「先輩の今の名字は、お母さんの名字ば名乗っとーと?」
「そうよ。名乗るちゅーか、正式にそげんて。僕の親が離婚したちゆうとは聞いたと?」
改めて自己紹介を交わす。話しかけてきたほうが小谷
流那、隣りが久保田
絵美、小谷のことは反対読みのニタコからタコ、久保田のことはボタモチからモチと呼ぶようになって、名前のことなんて忘れてしまっていた。
「あたしたちここでバイトしとうと。フードコートの……あとで紹介するけん、食べに来て欲しかです。久保田も――」久保田の顔を見て、頷いたのを見て続ける。「一階のグルメストリートでバイトしよっと。そこの和食店。先輩はここにはよう来るとですか?」
「うん。たまに来るけど」
でも、どう説明すればいいのか。
「昨日、ペルセウス流星群の極大日やったやん」
「ああ、見た! でも二時には寝たけん、一番すごかったとこは見逃したと」
そう。その頃僕は大川市上空でグライアイ群体と戦っとって、それで今日は、その艦内で見せられた映像を頼りに一番街の映画館に行ったと。ばってん、その映画館が閉館しとって、それでアイギスの盾をインストールした携帯で調べたら、映像の中で母が指差しとうた映画と同じシリーズが、このへんの映画館で上映されとって……それで詳しゅう調べたら、ちょうど漫画家の
小野田幸秀さんと、
八敷カズサさんがサイン会ば開いとるち書いてあって、ふたりとも島田先生のアシスタント経験者やけん、それでもう、こればい。これに違いなか……と。
――そんなことを言えるはずもなく。
「それで今日は、本屋に行きとうなって、ここに」
とだけ。
「すごいメルヘンじゃなかですか。いっちょん意味のつながっとらん」
意味がつながっていないことが、すなわちメルヘン?
「そっちもつながっとらんけん」
ふたりとも短いパンツに、プリントのTシャツ。厚底のサンダル。首には細い革紐のペンダント。小谷のTシャツには枯葉チルのキャラが大きくプリントされている。
このふたりじゃなかったら、肌の露出に戸惑ったと思う。女の子は苦手な方だけど、知ってる子だと案外気にならないものだな、と思う。でもあの頃、小学四年生だった頃の彼女らとは違う。少し化粧もして、髪も染めている。ときめき、と同時に、可笑しさを感じる。
「タコツボとボタモチがお洒落しとう」と笑うと、「今日はぜんぜん普段着でおしゃれじゃなかけん」と、照れながら両手でシャツを隠す。枯葉チルのクマが描かれたシャツが胸元に皺を寄せる。
「枯葉チル、好いとうと?」
「ああ、これ? 好いとう。なんか、描いてるひと、あたしたちに似とると思う」
「アタマおかしいよね、あの漫画」
ふたりが笑うので、僕もつい。
「そう。おかしかよね。ばってん、すごいよか人ち思う」
「そう! わかる!」
しばらく枯葉チルの漫画のことを話して、そのうち久保田が時計を見て、
「じゃあ、シフトの時間やけん」
小走りに奥へと向い、僕と小谷がベンチに残される。
彼女たちと僕らとは中学でも同じ学校だったはずだけど、ほとんど意識したことがなかった。小谷の方では時々僕の姿は見ていたという。そう話しながら、小谷は行き交う人の群れに視線を移す。
「どげんしたと?」
「あたしたち、何回目のデートんごつ見えとるとやろか」
思わず眉をしかめて小谷の顔を見返す。
「じゃあ、そろそろ本屋に行くけん」
「先輩冷たかー。いっちょん変わっとらん」
立ち上がって歩きだしても、小谷は付いてくる。
「胸のドキドキすると。先輩に恋しとるとかもしれん」
小谷は冗談めかして胸の真ん中のあたりを示してみせる。だけど、
「それ、たぶん不整脈やけん。ひどかったら病院行ったほうがよかよ」
ペルセウスは顔の良し悪しがわからぬ。だから小谷が可愛いかどうかもわからない。
「サイン会目当て?」
壁に貼られたサイン会の案内を見て、小谷が聞く。
うん、と頷いて、小野田先生はミリタリー系の漫画、八敷先生は昔は暴走族漫画を描いていて、ブレイクしたのは医療漫画、どっちも島田巽っていう凄い漫画家のアシスタント、そう説明しても小谷は相槌をひとつ打って、そんなことより、と遮る。出会ったきっかけが何だったか、最初に会ったのがどこだったか、記憶を追いかけながらとりとめのない話が始まる。そんな中で、
「先輩に会うた頃、いじめられとったと」
目をそらして、少し曇った笑顔を床に捨てる。
「なしていじめられとったと」
「ようわからん。よそもんやけんかもしれんし、親が水商売やったからかもしれん。だれもうちらと遊ばんし、無視しよったけん」
分かれ道に戸惑っていると、
「エスカレーター、あっち」
小谷が指差す。
「伊藤ち覚えとう?」
「伊藤? 美容院の?」
「そう。大嫌いやった」
予想外の言葉に戸惑いながらエスカレーターに乗る。一階のフロアがゆっくりと僕の足元に沈んで、二階の廊下、そこに居並ぶ店が降りてくる。書店のそばにはもうサイン会用のブースがある。
「あっちだ」
こんどは僕が指差すと、小谷が僕の手を握ってついてくる。
漫画で読んだことがある展開。後輩の女の子が、きっかけを見つけて、憧れていた先輩の手を握る。「先輩に恋しとるとかもしれん」という言葉が頭の中で繰り返される。冗談で言っただけのセリフの続きのセリフを探して、書きかけた下書きに消しゴムをかけて、現実と漫画とは違うのだけど、それでも、と思う。もしかして小谷は僕のことを好きなのかもしれない、と。でも、仮に万が一、僕が小谷から告白されたら、どう返せばいいんだろう。
以前から、可愛らしいアイドルが失恋の歌を歌うのに違和感があった。あんな子が失恋なんかするわけがない、と。
いや、ペルセウスは人の顔の良し悪しなんかわからない。
僕には小谷が可愛いかどうかなんて、わからないのだけど。
「死ねばよかち思うとった。伊藤」
小谷は話を続ける。僕の想像しなかった方へ向かって。
「伊藤がなんかしたと?」
小谷の、僕と繋いだ手に力が入る。
「教室まで来て、呼び出されて、『なんで上級生と遊んどると』ちゆうて、肩ばこげーん。こげんして押されて」
握った手と反対の手で、肩を押す仕草。
「伊藤に?」
汗ばんだ手は、強く僕の手を握る。その手を振りながら、胸に詰まった言葉を口に登らせる。小さな喉から、押し出すように。
「あのひといま、芸能科のある学校に行きよらすと。知っとうた? ダンス部の先輩に聞いたとばってん、伊藤、あの顔でアイドルば目指しよるち。アイドルグループのテストば受けて落ちて、まだ諦めとらんち。先輩と一緒に大笑いたい」
そう言って嘲笑う顔は、僕が描いた下手な絵だった。消しゴムで消した無数の線が隠れた、主線を拾いそこねた絵。嘲りでも、悲しみでも、怒りでもない、表情を作りそこねた崩れた絵。
サイン会に並ぶ人の列の中で、僕たちは異質だったと思う。何回目のデートであったとしても、こんなにも固く、まるで命綱でも握りしめるかのように手を握ったりはしない。でもそれを痛いとも言えず。小谷は口よりも、その手で語る。
「ばってっん、ちょっと感謝しとると」
「感謝って、伊藤に?」
「うん。二回目に教室に来た時、馬乗りになって泣かしてやったら、そいからいじめられんごつなったけん。それは伊藤のおかげやけん」
答えに窮する。
列は少しずつ前へと流れる。
小谷は落ち着いたのか、考えているのか、言葉はもう途切れた。
「小谷、手ん痛か」
そう言うと小谷は握った手を掲げて、笑う。手をほどいて、指の跡がくっきりと白くなった僕の手を両手でほぐして、ふーふーと息を吹きかける。
「おまえさあ」
小谷が僕の顔を振り仰ぐ。
ペルセウスは顔の良し悪しがわからぬ。だから小谷のこの、少し唇が緩んだ柔らかい笑顔だって、可愛いかどうかはわからない。
「いま吐き出したもん、もう飲み込まんでよかけん」
よかけん……そのあとの言葉をどう選べば良いのかわからない。小谷は口角を上げてコクコクと頷く。どう言えば気持ちが伝わるか、いや、自分の気持が本当はどこにあるのか、何もわからないまま、サインの順番が来る。前の人がはけて、一歩前に出ると、目の前には小野田さんと八敷さん。顔は初めて見る。
小谷がまた手を握ってくるけど、もう気にしない。いや、気にしないってのとは違う。気を許したとかじゃない。ないと思う。
「お名前は?」
黒縁メガネに天然の緩い癖毛、口ひげを蓄えた小野田さんがたずねる。
――樺島裕美の息子、勇です。母は去年の十月に他界して、今は島田先生に後見人になってもらってます。漫画も描いてるんです。というか、描き始めたところなんです。加古江さんの事務所へも何度か行きました。
胸の中に、話したいことがいくらでも湧き上がる。でも、一言だけ。
「樺島です」
そう告げると、隣に座っていた頬のこけた八敷さんが、銀縁のメガネのブリッジを指で上げて視線を向ける。
ほぼ同時に、地面を突き上げるような大きな衝撃。
ショッピングモールの建物が揺れ、商品が棚から落ちる。それに続けて地震とは違う細かい揺れ、その振動は収まらない。警報が鳴る。何の警報かはわからない。各エリアの警報が次々と重なって行く。
フロアの遠くで窓の割れる音、悲鳴。破壊音はフロアのあちこちで続き、またそれを追う悲鳴。ここからはまだ遠い。ひとりがその声と反対方向に駆け出すと、群衆はそれに引きずられる。
次の瞬間、天井を破って斜めに落下する影が見える。破壊された天井が瓦礫となって降る中、影は床を貫き一階まで貫通する。同様に、ふたつ、みっつ、闇を曳航する影が落ちてくる。翼が見えた。一階では悲鳴が広がっていく。何体が降り立ったのかはわからない。
次の一体がエスカレーターを破壊して二階フロアでとどまる。その姿を数店舗先に見留める。翼を広げ、身体を起こすと、その上背は人の倍、いや、それ以上、両手に鎌を持った翼のある闇色の化け物。これがゴルゴン? 僕が知っている怪物で言えば、ガーゴイル。振り向いただけで翼は店内の什器をなぎ倒す。
小谷が僕の腕を握って震えている。
「大丈夫。すべて幻覚だから」
外から回転翼機の重いローター音が聞こえる。
小野田さんの深海機工兵団が来たんだ。
すぐに近代的な武装で固めた兵が北側階段を登ってくる。先頭を切るのはクリップボードを持った背広姿の男。そのうしろから、長身の銃や各種機材を手にした兵が上がってくる。兵は駆けつけると同時に目の前のガーゴイルを砲撃。足止めしたところで、小銃による一斉掃射、赤外線で装甲の破損をモニターしながら照準点を移動させ、最終段階、ロングバレルの銃で炸裂弾を打ち込む。ガーゴイルは炎を吐いて応戦、その炎の熱気は2ブロックも離れたここにまで届く。が、兵たちは距離を取りながら着実にその四肢を破壊していく。
小谷を支えて立ち上がると、そこに小野田先生の姿がある。
先生はペン先を向けた壁の更に向こうに、兵士たちの姿を次々と描き、ショッピングモールに突入させる。その向こうには装甲車部隊、気密式機工スーツ部隊まで待機しているのがわかる。
「侵入した敵性個体は四十三体と報告されている。一階の客を避難させたら機甲部隊を入れる。彼女と屋上に避難してるといい。すぐにヘリを回す」
「ありがとうございます、小野田先生」
先生は部隊を描画しながら、横目で僕を見る。僕もさっき言いそびれたことをと、喉の中に紡ぐと、
「知ってるよ。裕美さんの息子だろう? でもここは僕らにまかせて」
と、柔らかく頷く。
深々と頭を下げて、階段へ向かおうとすると、「ああ、そうだ」と、呼び止められる。
「これ、持って行くといいよ」
小野田さんは僕にGペンを手渡す。
「それがあれば、多少の危機は乗り越えられる」
僕が、このGペンで?
「Gペンの先に、君の漫画をイメージするだけでいい」
自信はないけど、使わずに済むことを祈りながら階段へと向かうが、階下から様子を伺うガーゴイルの姿が見える。
「こっち」
小谷が僕の手を引いて通路を案内する。
書店の奥を抜けて食品館の階段へ。フードコートの前で立ち止まると、小谷は携帯を取り出して電話をかける。留守電の案内。メッセージの終了を待って、
「絵美? すぐ助けに行く! こっちでも探すばって、もし場所がわかったらメッセして!」
早口で告げると、電話を切ってポーチにしまう。
まさか、助けに行く気か。
「絵美はグルメストリートだから、たぶん一階」
ここはまかせておいたほうが――そうは思うものの、小谷の決意が、僕を圧倒する。
「どうすれば会える?」
小谷は頭の中の地図をたどる。
「屋上からウエストコート階段」
答えを聞いてもまだ迷いがある。屋上に出たらそこで待機したらいい。すぐに小野田さんのヘリが来る。久保田の方にだってそう伝えればいい。だけど、小谷は唇を噛んで涙を堪え、僕の顔を見て、拳を伸ばす。
「わかった」
僕は、Gペンをもらったんだ、小野田さんから。小谷の拳に自分の拳を当てて、屋上へと向かう。
屋上にはガーゴイルが突入した穴が多数空いている。梁が折れ、床は大きく陥没し、駐車場の車のいくつかは炎を上げ、怪我をした者たち、穴に巻き込まれた車、泣いている子供と、その手を引く若い両親。上空には軍のヘリコプターが見える。だれの作風かわからない。小野田さんじゃない、現実の自衛隊も動いているのかもしれない。
ショッピングセンターの外にも多数のガーゴイルの姿が見える。激しい銃撃戦。装甲車から機銃が撃ち込まれている。上空からは次々と、新たなガーゴイルが舞い降りる。
瓦礫と穴だらけになり火の手の上がる屋上を、対角線に横切ってウエストコート階段へ。小谷は携帯を確認する。
「返事は?」
首を振る。
サンダル履きの小谷の手を引いて建屋に入ると、風圧が肩にかかる。階下に燃え盛る火が、血の匂いの気流を作る。階段の壁に靴の音を響かせて二階に降りると、一面の血の海。駆け下りた足が最後の一歩を躊躇う。
小谷が両手で肩にしがみつく。呼吸が不規則で早い。このままだと呼吸困難を起こす。
とっさにその頭を胸に抱える。
「深呼吸して。僕の呼吸に合わせて」
ぎゅっと抱きしめたまま、ふたつ、みっつ、呼吸を整えて、
「座って。ゆっくり。落ち着こう。ゆっくり。呼吸は僕に合わせて」
彼女を抱えたまま階段に腰を下ろす。
「呼吸はゆっくり」
僕は彼女の頭を、肩に受け止めて、とんとんと背中を叩きながら歌った。
「あーきの ゆーうーひーにー てーるーやーまーもーみーじー
こーいも うーすーいーもー かーずーあーるーなーかーにー」
歌っているとようやく彼女の息が整う。
「携帯ば見て。久保田からの連絡があるかもしれんけん。助けに行くばい。よかね」
小谷は小さく頷く。
「メッセんきとう。携帯ショップの奥ち」
「場所はわかる?」
窓から見ると、ヘリの姿が増えている。報道ヘリ。遠くに消防車のサイレンが聞こえる。市街地にも危機が広がっている。主戦場はもう、ここじゃないのかもしれない。
一階に降りる。階段付近、視界内に敵の姿はない。
東のエリアからは逃げ惑う人の悲鳴と、ガーゴイルの発する奇声、銃声、砲撃音。敵の不在を確認すると小谷は背を屈めて歩き出す。その背中を追って、グルメストリートへ。ふと左手の通路を見るとフロアは真っ赤に血に染まっている。肉塊が見える。半分になった人の姿、その腕、脚。目眩を覚えていると後から小谷が僕の襟首を引っ張る。
無表情な小谷の目から涙だけがこぼれている。
震えながら、静かにその唇が動く。
「行こう」
頷いて、目的地まで目と鼻の先、手前の角を曲がると、通路の奥にガーゴイルの姿が見えた。
小谷の足が止まる。
脚の力が抜けて崩れる小谷を受け止める。
呼吸が速い。
「深呼吸を、小谷。意識をしっかり。久保田ば助けるとやろう
!?」
抱き留めるけどパニックは収まらない。体は過剰な酸素を拒絶し喉を堰き止め、恐怖は肉体に抗って空気を求める。
「小谷、呼吸が早い。落ち着いて。僕の呼吸に合わせて」
ガーゴイルは炎を吐き、近くのポスターが熱で発火する。ショップ内から悲鳴が聞こえる。その悲鳴と熱が小谷を更に怯えさせる。体が細かく震えだす。痙攣。どうすればいいんだ。
僕は、小谷の肩越しに小野田さんから受けとったGペンをかざす。
だけどイメージが沸かない。あいつと戦える、戦車も、騎士も、僕には描けない。
僕の手の中で、小谷の全身から力が抜ける。
頭を打たないように腕を潜り込ませて、そのまま抱きかかえるようにして、ともに崩れ落ちる。
もう、駄目かもしれない。
――まだ両親が離婚の話を始める前。
だけど、今思うとあの頃からその話は出ていたんだと思う。僕が家に帰ると、両親は何か話をしていたけど、母はそのまま奥へと消えて、僕は居間のソファに座らせられた。
ランドセルを降ろして、また成績のことかと思った。
「……という子は知っとるか」
知り合って三ヶ月くらい。その時ですら『小谷』という名前にピンと来なかった。僕は首をひねったと思う。それを見て父は説明を続けた。
「生協の通りに、第一アパートちあるやろ。知らんか。そこに春頃引っ越してきた、おまえの一個下の子。母子家庭ち言われとうばってん、男は出入りしとるごたる。旦那かどうかはわからん。そこの子。知っとうか」
そのあたりで、タコのことだって思った。
――あたし、お父さんがだれかわからんけん。
そう言っていたのを覚えている。
「娘の方は看たことがある。母親に連れられて来たとば覚えとう。ばってん――
蟹副さんはわかるやろう? あん人が、あの
母娘は好かんちいうて良か顔ばせんたい。うちは医者やけん来たものは拒まん、怪我やったら治すとが仕事ばいち言うたっちゃ聞かっしゃらん。穢れとるだの、追い返せだの。そげん言われたっちゃ、追い返しはせんたい」
父の話は要領を得なかった。
カニゾエさんが、タコの家族を嫌っている。
そこまではわかっても、それを僕が聞かされる理由がわからなかった。
「母親は夜の仕事ばしよるし、アパートもどげな男が出入りしとうかわからん。言いたかなかばってん、真陽んごたっとが出入りしとうたい。いつどげん事故が起きるかもわからん。トラブルに巻き込まれんごつ、仕事以外の付き合いは控えたほうがよかち、裕美とも話しおうた」
父はヒロ叔父さんの名前を出した。「真陽のごつなるな」は父の口癖だった。ニュースで芸能人の薬物依存が報道されるたびに聞いた。「あげんなっちゃいかんぞ」と、時に症例の写真を見せながら。それに、母とも話したんだったら、僕はもう口を挟めない。でも、僕にどうしろと言う話なのか。
「娘も暴力事件ば起こしたち、問題になっとう」
そこまで聞いて僕はやっと驚いたのだと思う。タコが暴力事件。
「親も親なら、子も子たい。クラスに友達は作らんで、上級生とばっかりつるんどるち言われとう。子は親ば見て育つけん、娘も同じごつなるよ、いずれ」
上級生の男と聞いて、六年生か、あるいは中学生の男を思い浮かべた。「アバズレ」「アバズレの娘」父が繰り返す言葉を聞いて、僕は騙されてたんだと思った。小谷がつるんでた上級生が僕のことだとも気づかず、素直に小谷は酷いやつだと思った。
それからは小谷と遊ぶこともなくなったし、記憶にさえ留めていなかった。
言い訳かもしれないけど、父の話す小谷のイメージと、僕の知っているタコのイメージが違いすぎて。裏の顔がある、僕は騙されてる、そういう理解でしか自分を納得させることが出来なかった。
だけど、いまにして思うと、それも違う。
怖かったんだ。父が。
小谷の顔に耳を寄せても、もう呼吸がなく、手首に脈拍もない。
携帯ショップの前のガーゴイルが、ゆっくりと僕の方を向く。
「小谷――」
これが僕の――、僕たちの、最後の時間かもしれない。
「おまえ、自分の父ちゃんがだれかわからんち言うとったやんか。
でも、わかったよ。いまわかった。
おまえの父ちゃん、ギリシャ神話のゼウスばい。
おまえの母ちゃんとこに、金の雨になって救いの手ば差し伸べに来たとよ。
わかったよ、小谷。ペルセウスは僕じゃない。
おまえがペルセウスやけん、ヒーローやけん、絶対に助かるて」
すでに意識のない小谷にGペンをもたせる。
「絶対に」
その手を握りしめるとプリントのTシャツが光り出す。まばゆい光が立ち上がる中、枯葉チルのイラストが実体化する。
「ねーこーくーまーとーじょー!」
そこに現れた左右の目に違うボタンを付けたツギハギのクマが雄叫びを上げる。
身の丈三メートルを超える。
ネコクマと名乗ったチルのキャラはそのままガーゴイルへ突進、体当りして押し倒し、背負投げ、ジャイアントスイングで壁に叩きつけ、最後は謎の光線で仕留めてフィニッシュした。
小谷に呼びかけてみるけど返事がない。もういちど脈を取るが、それも。
胸の中を虚無が跳ね回る。認めたくもない一文字が胸の中にこびりついたまま離れない。違う。落ち着け。脈が無いんじゃない、取れないだけ。近くにAEDがある。僕にはできる。目の前のショップの中にAEDの機械を見つけると僕の脚はもう走り出している。
「ごめん、小谷」
ペルセウスは……いや、ペルセウスは君だ。僕じゃない。
僕は――僕は、今まで、何もわからなかった。何も見えていなかった。
でも、これからは。
僕は小谷の胸にAEDをセットして、スイッチを入れる。
*
秋の夕日に 照る山もみじ
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦は
山のふもとの 裾模様
母が歌ってるのを聞いて、『ふもと』と『すそ』は同じじゃないかって感じていた。きっとその時に聞いていたら、裾模様の意味を教えてくれたんだと思う。小谷の手を握って歌っていると、横になったまま彼女も僕の歌の後をおいかける。
ネコクマと名乗った生き物はどうやらまだどこかで暴れているらしく、ときどきその奇声が聞こえる。その後に続けて小銃の音。枯葉チルのキャラだから、おそらく敵味方関係なくなぎ払ってるんだと思う。
携帯ショップにいた八敷さんが僕たちを見留めて、
「そこで待ってろ、動くな」
そう言ってショップ内に戻る。
八敷さんが担架を持って駆けつけて、もう歩けるからという小谷を担架に寝かせて、携帯ショップへとかつぎ込む。そこは野戦病院だった。腕章を付けた久保田の姿も見えて、こちらに気がつくと駆け寄ってくる。
「人工呼吸と心臓マッサージはできるか?」
八敷さんがたずねる。
「ええ、実家が医者だったので、小さい頃習いました」
「じゃあ、腕章を」
八敷さんは白い腕章を手渡してくれる。
「包帯や消毒液、ガーゼ、気管チューブ、いろいろかき集めたが、医療スタッフが足りない。別棟にクリニックもあると聞いたが、向こうはここ以上の惨状だ。動ける患者から隙を見て外へ出していたんだが、国道、バイパスともに寸断されている。もう何体のバケモンが降りたのかすら見当がつかない」
八敷さんが説明している間にもけが人が運び込まれてくる。ガーゴイルの炎によるものか、熱傷が酷い。二人がかりで気管チューブを挿管している姿がある。先生はすぐに気がついて傍に駆け寄る。
「貸して」
先生は小さなライトで患者の喉の奥を照らす。腕章の男に指示して、顔の向きを固定、気管チューブを挿管する。
「ありがとうございます。先生の漫画を見て看護師になりました」
そう語りかける男に、手のひらを見せて、次の患者を、そう促して、心臓マッサージを続ける別の腕章に声をかけて、手技を代わる。
「何分経った?」
「十二分です。熱傷で気道が塞がって、もう挿管ができんけん。心臓が動いても呼吸が……」
先生の手が停まる。もっと生存の可能性が高い患者がいる。
腕章がもう一度、手技を代わる。
僕は思わず、
「気道切開を。そこから空気を送れば――」
先生に訴える。
「それができる医師は二階で別の患者を見てる。そちらも手が離せない」
また患者が運び込まれる。
「気持ちはわかるが、俺たちは医者じゃない。自分にできることを着実にやるしかない」
先生は新たに運び込まれた患者へと向かう。久保田が立ち上がり、机の上の包帯を取る。僕は――僕は携帯ショップを出て、樺島の姓になって二度目の電話を高松医院にかける。電話を取ったのは父。
「気管切開がいる! 人工呼吸器も! 医者もぜんぜん足りとらん!」
向こうの声も聞かないうちにまくしたてる。
「落ち着け、勇か。いまどこにおると」
新合川のショッピングモール。三号線と櫛原バイパスは寸断されている。父の話では、六ツ門にも大量のガーゴイルが降り立ち、父も医院から動けないらしい。その様子が僕の頭の中に描き出される。寸断された国道、パニックに陥る町の様子。小野田さんの部隊が対応しているが、ぜんぜん間に合っていない。でも、まだルートはある。抜け道はある。
「車ば出そうにも、どんこんならんたい」
「寺町のルートが活きとう!」
僕の意識の中に、はっきりとそれが描き出されている。
「郵便局んとこから、鳥類センターの裏ん抜けて、公園ばつっきったら行かるる!」
それを父に言ったところで……!
携帯を握りしめる僕の目の前の空中に、改造スカイラインが描き出される。
竹ヤリ、シャコタン、ボディ両サイドに描かれた炎の文様。
八敷カズサ先生の公道レース漫画アーミージェイルブレイク、主人公の
闇龍祐一が駆るジェイルブレイカー。描画を終えるとともに床面へと落下。たった今生を受けた野獣が、落下のその衝撃を糧とするように体を沈ませる。
ドアが開き、祐一が顎で搭乗を促す。
ショップの中の八敷先生が立ち上がる。
「心拍が戻った! 急いで医者を!」
頷いて、ドアを閉めると、ジェイルブレイカーの咆哮、吐き出す排気音、燃え残るガソリンの匂い。アクセルを踏むと、亜光速のタイヤの回転が煙を上げてフロアを削る。唸る車体をブレーキで抑え込んだまま、その鼻先をグルメストリートへ向けて、いま、
深紫のハイウェイスターが駆け出す。
急加速。シートに沈み込む背中。グルメストリートを抜けて、ショッピングモール北西のゲートを突破。ドリフトして車体を立て直す刹那、ショッピングモールの屋上に、腕組みして立つ少女の影が見えた。長いマフラーをたなびかせている。母の投稿作、風使いの翼で見た構図。
次の瞬間、野獣は瓦礫を踏み越えて体を浮かせ、そのまま激しい衝撃とともに河川敷に降り立つ。筑後川沿いを西へ、荒れた路面、暴れる車体を抑え込んで、支流に架かる小さな橋を渡り、
V6ツインターボエンジンを唸らせて一気に土手を駆け上がる。目前にガーゴイルが迫るが、ガトリングガンの掃射、そこに生まれた一瞬の隙に車体をねじ込む。
空中でのドリフト、直角ターン、陸上競技場脇を駆け抜け、駐車スペースの背後の茂みに飛び込み鳥類センター裏へ。公園をショートカット、路地を抜けて、西鉄大牟田線の踏切で一時停止。
祐一の運転は技術だけではなかった。完璧な交通ルール遵守が見るものを虜にした。日本全国の走り屋に安全運転の精神を伝えた、あの漫画で見た涼しい目をした祐一がそこにいる。バックミラーには迫りくるガーゴイル、祐一は余裕の笑みを見せる。車体背後のハッチを開いて水平に並ぶ四本のラムジェットエンジンが火を噴く。
時速は瞬時に一四〇キロまで上昇。交通ルールの権化である祐一にはジェットエンジンはもはや合法。車検が通ればそれがすべて。この速度で路地の左右にならぶ鉢植え、自転車を巧みに避けながら、ガーゴイルを振り切る。その速度を緩めることなく、深海機工兵団のメカが戦う国道三号線を舞うように越えると小さな祠を目印に左折、そこへの一礼も忘れない、その先の小路をぐんぐんと加速、一八〇、二五〇、三四〇……祐一にとって音速は子守唄、思い出される夏の日。音速が速度を下げて祐一に屈服し、風となったあの日。真白きヴェイパーコーン、音速突破。昭和通りを越えて、一つ目の角を右折、姉と詩香さんと三人で話した喫茶店、次の信号を左折するとそこからはもう直進。その時、信号を横切るおばあちゃんの影が。しかし、祐一の動体視力は、はるか前方でそれを捕らえている。祐一はおばあちゃんに不安を感じさせることなく車体を止める。信号待ち。
ふとバックミラーを見ると、西鉄久留米駅方面に巨大なチルのクマが暴れているのが見える。自衛隊機とカラフルなおもちゃのUFOとが戦っている。それを見て祐一は、フッと笑みを浮かべる。その意味はすぐにはわからなかった。だけど。改めて見上げると、自衛隊のヘリを掴んでデパートを破壊しているのは、巨大化した小谷だった。
そして、信号が青になると同時に、ジェイルブレイカー号はまた深紫の野獣へと変わる。
父と看護師ひとりを乗せてショッピングモールへと戻ると、混乱はより一層広まっていた。父はすぐに患者へと向い、その場で気管切開、チューブを入れて、そこにいる者たちに指示を与える。
すれ違いざま、八敷さんが僕に告げる。
「メデューサが降臨した。ゴルゴンたちの統治者だ。俺たちだけではもう抑えきれない」
怪我人が次々に運び込まれ、八敷さんは腕章のついた人たちに檄を飛ばす。
そんな中、ショッピングモール館内にお知らせのジングルが響く。
メンデルスゾーン、『
雲雀の歌』を二小節。
続けて、アナウンスが流れる。
生徒会よりご案内いたします。
緊急生徒会総会を行います。
各部部長、及び、クラス委員の方は、生徒会室へお越しください。
繰り返しお伝えます。
緊急生徒会総会を行います。
各部部長、及び、クラス委員の方は、生徒会室へお越しください。
第九章 炎の生徒会とメデューサの首
ここまでのあらすじ。
母の初盆の法要を終えた勇は、母の足跡を辿るべく市内を散策。そんな中、ショッピングモールにて、幼い頃によく遊んでいた下級生、
小西流奈と
久保田絵美に出会う。だが、再会の喜びもつかの間、ショッピングモールはガーゴイル軍団の襲撃を受け戦場と化す。勇は幾度かの危機に陥りながらも、母の同僚だった漫画家小野田幸秀の描く深海機工兵団に救われ難を逃れる。
小西と勇は、ガーゴイルの襲撃で野戦病院と化した携帯ショップに保護されるが、勇はそこに運び込まれる怪我人を見かね、八敷カズサのレース漫画の主人公である
闇龍祐一の協力を得て、父を連れて戻る。
そうしている間にゴルゴンの統治者メデューサが降臨。ガーゴイルと機工兵士部隊の死闘が続く中、店内には緊急生徒会総会開催のアナウンスが流れる。
「今のは?」
「おそらく、森エミル『炎の生徒会』だ」
炎の生徒会と言えば、
私立聖歌学園生徒会に織りなされる演劇漫画……だけど、小野田さんの兵団が苦戦しているような状況で生徒会?
「樺島くんも早く」
八敷さんに促されて、スタッフルームの奥、生徒会室へと向かう。
扉の前に立つと、テノールの歌声、ドイツ語で歌うメンデルスゾーンの《
雲雀の歌》が聞こえる。
ノックをして中へ。
最奥には生徒会長の机。その斜め前、制服の男が腕を後ろに組んで、歌を歌っている。表でも聞こえていた歌声。
「相変わらずの美声だな、
副島」
「お褒めいただきありがとうございます」
「その歌声のために、貴様を副会長に据えている。その立場、その喉にかかっていると心得るがいい」
会長席に座っている女性がおそらく生徒会長。僕の姿を見留め、声をかける。
「漫画部部長、樺島勇。転校生だったな。貴様が一番乗りだ」
「お初にお目にかかります」
「知っていると思うが古式に則って自己紹介しよう。私立聖歌学園生徒会長、
長嶺菫。この学園内では、私の指導に従ってもらう。心得るように」
長嶺菫……一見可憐な名前。だけど、菫にはトリカブトという読みもある。漫画の中では長嶺の名前にだけルビが振られていないことが話題になっていた。
「そしてこちらが生徒会副会長」
「副島だ。以後、長嶺会長への用件は私が取り次ぐ」
「揃ったようだな」
気がつくとうしろに各部の部長、クラス委員らが勢揃いしている。
副島が腕を背に組み、胸を張って委員に向かう。
「それではこれより、私立聖歌学園生徒会、臨時総会を始める!
式次第一! 《
雲雀の歌》斉唱!」
ピアノの伴奏。短い前奏に続けて、混声四部の合唱が生徒会室に響く。
おお
雲雀 高くまた
軽く 何をか歌う
天の恵 地の
栄
そを称えて 歌う
そを
寿ぎ 歌う
同じフレーズを五回繰り返し、最後は伸びやかに、ゆるやかに歌い上げ、余韻を引いて終える。
「式次第二! 議題提示!」
副島が宣言すると同時に、委員席から声が上がる。
「待ってください、小鳥部が混じっています」
声の聞こえたところに小さな人影が紛れている。運動部の大きながたいの影にいるが、会長が視線を投げるとその人垣が割れる。
「小鳥部部長、
砂場日代子。小鳥部を部として認可した覚えはない。つまみ出せ」
会長の声に、すぐに小さい影が応える。
「校長先生から認可は頂いています!」
「校長の認可など関係ない。ここは生徒会室。ふさわしい人間かどうかは私が決める」
小鳥部部長・日代子は、手に持った小鳥の藁巣をかばいながら、むくつけき運動部員たちに部屋から押し出された。
「おまえなんか二時間おきにぴーぴー鳴いてる文鳥に挿し餌してりゃいいんだよ!」
「せいぜい
素嚢をぱんぱんにしてやるんだな!」
小鳥部を追い出した者たちの心無い声。藁巣の中から聞こえていたまだ青白く羽根も生えていない文鳥の、挿し餌を求める声が耳に残る。
「小鳥部が……何をしたというんだ……」
パーカーのフードを被った、ひとりの委員が小さく漏らす。
「貴様、いまなんと言った?」
会長はそれを聞き漏らさない。
「いいえ、何も」
「なぜ顔を隠している。きさま何部の代表だ」
「私は……風使い部部長、風乃翼」
風乃翼……?
その名前には聞き覚えがあった。大川の実家で見た母の漫画のタイトルが……確か……。
「あら、風乃先輩」
長嶺の声が慇懃な音色に変わる。
「先輩はもう転校されたとばかり思っていましたわ。今回はお手柔らかにお願いしますわ、風乃先輩」
長嶺は風乃に含みのある笑みを向け、その笑顔を吐き捨てる。
「副島! 議題をっ!」
「ハッ! 議題、その一っ! ゴルゴンの統治者メデューサ侵入の件! 以上一件!」
「ということだ。我々はこの学園の治安を守るべく、全力をもってこれを討伐する。異議のある者は!」
委員席からの異議の声は上がらず、賛成の声だけが上がる。その中で、風使い部部長だけは歯噛みして声を殺している。
「それではこれより、演劇部部長・
草石成夫の脚本に沿って、メデューサを討伐する! 副島! 準備を」
「ハッ!」
生徒会長の言葉を合図に、委員全員が舞台袖へとはける。
ひとり舞台中央に残った長嶺菫が、客席に向けて宣言する。
「それでは、私立聖歌学園演劇部第一〇三回公演、
《炎の生徒会とメデューサの首》、
開演いたします!」
菫は右手を舞台中央に差し向けたまま上手へとはける。
ベルが鳴り、客電が落ちる。
下手に板付で司書・
書関宛奈、スポットライト。
彼女のモノローグから、舞台は始まる。
「かつてこの学園には、不世出の美少女と呼ばれた、
芽戸遊沙という生徒がいた。この学園を出てモデルになった者、アイドルになった者は少なくない。だけど遊沙の可憐さはその中でも群を抜いていた。
そんな彼女に水泳部顧問、
保瀬井曇が恋をした。遊沙は保瀬井の求愛を断り続けたが、ある日、よりにもよってこの図書室で、保瀬井は力ずくで遊沙をものにした。
図書室を預かる私には、それが許せなかった。悪いのは保瀬井だ。そんなことはわかりきっている。だけど相手はこの学園の教師。私は司書の職を得たばかりの派遣社員。私は、遊沙を責めるしかなかった。
それで職が安定するんだ。生きる糧を得られるんだ。いつか私は、それを正義だと信じ、気がつくと、彼女に呪いをかけていた。
醜く歪んだ彼女の顔を見た時、私の手は震えた。
それでも、私を責める者がいたら、私は言った。
彼女が、保瀬井先生を、誘惑したのだ、と。
以来、怪物となってしまったメデューサは、人のいない旧校舎に潜み、私への――この学園への復讐を目論んでいる。
彼女の醜さは、私の心の醜さだ。
どうかペルセウス、彼女に、死の自由を与えて、その醜さを、私に返して欲しい」
宛奈、下手へはけてボーダーライト点灯、舞台に光が入る。
場所は、聖歌学園玄関ホール。
「と、そういうわけだ、ペルセウス」
「あなたは?」
「この学校の校医を務める、
辺瑠眼寿。この『辺瑠眼寿』という字ヅラのせいで練馬に住んでいた頃はよく暴走族と間違えられた。それはともかく。君にはこれから、怪物メデューサを倒してもらう。グライアイ、ニュンペーと会った君の手にはすでに、メデューサの首を入れるキビシス、逃走時に姿を隠すための闇の帽子、そして、メデューサの首を刈れる唯一の武器、時の神クロノスの鎌があるはずだ」
「いや、アイギスの盾と、ヘルメスの靴らしきものは手に入れたけど、他は何も……」
戸惑う僕の台詞を遮るように――
「人選を間違えていませんこと、ヘルメス先生」
下手より、取り巻き四人を従えて、生徒会長、長嶺菫が登場する。
「そんな新入生に頼らなくても、この私になら、ラグビー部の肉盾! 将棋部の戦略! 生物部の分析力! そして、理事会のお金がありますわよ!」
「わがラグビー部、スミレ様のためなら喜んでこの肉体を捧げる覚悟でございます」
「そのラグビー部を、私たち将棋部が立てた戦略で動かしてご覧に入れましょう」
「我ら生物部ではすでにゴルゴンの体細胞を分析し、無敵のコーティング剤を開発し終えたところです。視線で石化など、もはや昔話」
「そして極めつけ、スミレ様の武器は我ら理事会が米国軍需産業関係者と連絡を取り合い、最高のものをご用意しております」
ひとつひとつ頷いて聞いていたヘルメス先生が僕に振り返る。
「そういうわけだ、ペルセウス。仕事を打診して間もないが、君よりも適材が見つかった。君を評価していないわけではないが、これも時の運。幸い君とはまだ契約を交わす前、お互い自由の身、ここまでの納品物は、君のポートフォリオとして、こちらで引き取らせてもらう。機会があったら、またどこかで!」
そう言うと、ヘルメス先生と長嶺会長、その取り巻きは、談笑しながら理事室へと姿を消した。僕は――僕には正直、荷が重いと思った仕事ではあったけど、夕焼けを背負って歩く帰り道、それでも僕の目からは涙が零れてきた。
道すがら小鳥部の部長と、生徒会副会長が話している姿を見かけた。
「本当にやるんですか、副島様」
「ああそうだ。長嶺が思い上がって、有頂天になったところで梯子を外す」
「でも、そんなことをしたらスミレ様が……」
「気にすることはない。当然の報いだ。たったひとつの部を除いて、部長たちはすべて打倒長嶺菫に協力すると言ってくれている」
「たったひとつを除いて?」
「風使い部だ。あの部だけはどうにも読めん。他の誰よりも長嶺会長を憎んでいて良いはずだが、俺たちの計画には乗れないそうだ」
その言葉を聞いた小鳥部の部長の顔が少しだけ綻びを見せる。
「わかる気がします……騙し討は私も……」
「自由のため、みなそれぞれの夢を叶えるためだ」
「私の夢はただ、文鳥の雛にごはんを上げて、素嚢をぱんぱんにすること……」
「そんな夢は5分で終わるぞ、日代子」
手に持った藁巣の文鳥が鳴き始め、給餌を始める日代子。
慈しむようにそれを眺める副島。
旧校舎。彫像が並ぶ廊下。
上手より、各部の部長たちと改造されたラグビー部員六名を引き連れて長嶺が舞台に出る。長嶺は右手には剣、左手には銃を持ち、ヒーローらしくマントを羽織っている。
引き連れた生徒たちは、そこに並ぶ彫像を見て各々口を開く。
「このへんの彫像はすべて、かつて在籍していた生徒ですね」
「おいおい、もっと丁寧に扱え。メデューサの顔を見て石になった、哀れな先輩方だ」
「でも私たちにはもう石化は通じない。この生物部が開発したコーティングのおかげで!」
長嶺、剣と銃を使って彫像に対して型を披露、舞台中央へ。
「長年この学園の評判を落とし続けた怪物メデューサ……。
まさか私みずからが倒す日が来るとはな」
長嶺、薄笑みを浮かべる。
下手よりラグビー部員がひとり走ってくる。
「来ました、スミレ様! ゴルゴン軍団です!」
「わかった! 者ども、迎え撃てい!」
その合図とともに、ダンスシーンへ。
長嶺を中心に七人が舞台に立ち、他はまわりに腰を下ろす。
単純なリズムから、動きは少しずつ大きく、複雑になる。
どうバランスを取っているのかもつかめない不思議な動き、非同期の動きが次の瞬間には一つの溶け合った動きに変わる。そしてその抽象的な動きも、追っていると物語を描き出す。
先程見たガーゴイルのような衣装をつけたゴルゴン役が入ると、それを別の四人が囲んで、せめぎ合い、また別のゴルゴンには別の四人が、こんどは全く違ったダンスを見せる。そこには戦いの勇猛さばかりではなく、恐れや、怒り、迷いまでもが表されている。
中でも長嶺のダンスは美しかった。その細い足は美しい弧を描き高く上がる。そのまま身体を翻し、体を沈めてからのジャンプ、リフトへと繋ぐ。身体を委ねることへの恐れのない堂々とした動き。ウエスト、脇、太腿の内、それが男子の手に触れることに物怖じもない。王者の風格。
ダンスはクライマックスへ。長嶺がダンサーたちの力を集めて、放つと、ゴルゴンがもがき、動きを止める。長嶺はゴルゴンたちを次々と仕留めていく。ダンスは激しさを増し、最後のゴルゴンが倒れると、舞台上のボーダーライトが消え、クロスするサスペンションライト、吹き上がるスモーク、メデューサが登場する。
メデューサ役は弓道部部長、
鏑真弓。晒しの上半身をはだけさせた和装。真っ白なライトが、その美しく隆起した広背筋を浮かび上がらせる。
「来たなメデューサ! ものども、準備はいいか!」
長嶺が号令をかけ、攻撃の一歩を踏み出すが、取り巻きはもう反応しない。
ひとり、またひとりと動きを止め、長嶺の前にメデューサが近づいてくる。
「どうしたんだ、おまえたち
!?」
メデューサの攻撃。その一撃で、長嶺の身体は倒れる。口の血を拭う。
「なぜ石になる
!? 生物部のコーティング剤はどうなった
!?」
メデューサは長嶺にすくい上げるような蹴りを入れる。体が浮き上がる。次の攻撃を躱してメデューサの体を崩すが、同時に長嶺の手から武器がこぼれる。
上手より、副会長の副島が登場する。
「無残だな、長嶺菫」
「副島
!? これはいったいどういうことだ
!?」
「聞いてどうなる。おまえはここで死ぬんだ」
「なんだと
!?」
「みんな、おまえの独裁にはうんざりしていたんだよ! ここにいる生徒全員がおまえの死を望んでいる! なぶられ、恐怖に震えながら、死んでいくのを!」
「貴様ッ!」
立ち上がる長嶺をメデューサが襲う。
長嶺は落とした武器を拾い上げ応戦するが、一切のダメージが入らない。
まわりにいる生徒たちが、石のように目を伏せてうつむく中で、長嶺ひとりメデューサの攻撃を受けてボロボロにされていく。
「痛いか、長嶺ェ! それがおまえが今まで俺たちにしてきた仕打ちだ! おおっと、まだ死ぬんじゃないぞ……俺たちが受けた痛みはそんなもんじゃない。そうだろう、みんな!」
副島は雄叫び、そこにいる者たちの顔を覗くが、凡夫の群れは身じろぎもせず、静かに、ああ、と頷き、目を伏せる。
下手より、ゆっくりと日代子が舞台に出る。
メデューサによる容赦ない攻撃、それが入るたび、日代子は小さく肩をすくめる。
「あんまりです……」
日代子は肩を震わせて息を飲む。
メデューサは長嶺の頭を掴んで、岩肌に叩きつける。額が割れ、血が流れる。
「これが酬いか……ひとりとして、学園に友を作らなかった……私への」
長嶺の口から弱音が漏れ、メデューサの次の攻撃が迫る。
日代子は小さく首を振る。
「そんなことないです、スミレ様……」
周りの誰も、目を伏せたまま動かない。
次の攻撃。吹き出す血が、赤い弧を描く。
その血しぶきの下、日代子はか細い声で歌い始める。
「おおー ひーばーりー たかーくまたー」
再度長嶺にメデューサの攻撃。日代子は思わず息を飲むが、それでも歌を続ける。
「かろーく なにーをか うーとうー……」
メデューサは長嶺を両手で抱え、地面に叩きつける。
日代子の目から涙がこぼれ始める。
「てんのー めぐみー ちのー さかえー……」
血に染まった地面を見て、息が詰まる。声が出ない。もう歌えない。そう思ったその時、ラグビー部のひとりが続きを歌った。
「そーをー たたえーて うとーうー」
副島は顔を険しくするが、ラグビー部員は目をそらしたまま歌を続ける。
「そーをー ことほーぎ うとーうー」
またべつのだれかの輪唱の声が追いかけて、細い細い歌声が紡がれる。
日代子もまた、歌を続ける。
「おおー ひーばーりー たかーくまたー」
ワンコーラスを歌い終えると、輪唱の輪はまたひとつ広がる。
「かろーく なにーをか うーとうー」
メデューサの執拗な攻撃が続く中、歌声は確実に大きな流れを作り出していく。
「てんのー めぐみー ちのー さかえー そーをー たたえーて うとーうー」
副島が怒鳴り始める。
「おまえたち、何を歌っているんだ! 横暴な生徒会長の最後だ!
笑え! 嘲れ! 罵れ!」
だけど歌は止まらない。副島のその目に、声を上げ続ける日代子の姿が映る。
「やめるんだ日代子! この女に何をされたか忘れたのか
!?」
「忘れない……忘れるわけがない……でも、だからこそ時間が必要なんです! スミレ様と私たちとが、わかりあうための時間が!」
輪唱の和は広がる。
「おおー ひーばーりー たかーくまたー かろーく なにーをか うーとうー」
やがてその歌声は混声四部の大合唱となり、力強く空間を満たす。
長嶺の持っていた武器が輝き始める。メデューサの攻撃を間一髪で躱し、光り輝く武器を手にして立ち上がった時、その歌声はついに、副委員長、副島の口からも静かに漏れ出していた。
メデューサの攻撃に合わせて、長嶺のカウンターが決まる。
メデューサがよろめき、後ずさる。
おおひばりの大合唱の中、最後の一撃……
と、その時、
「まーてーこーらー!」
どこからともなく声が聞こえる。
「だれだ?」
「まーーてーーこーーらーー
!!」
「これから感動のエンディングを迎えようと言うのに、いったいだれ?」
「まーーーてーーーこーーーらーーー
!!!」
花道を走って、風乃翼が登場し、駆けてきた勢いそのままで長嶺にフライングクロスチョップを浴びせる。
「大向うで聞いていたら、なんだこの寸劇は! ふざけんなこら、歌ったぐらいで感動してんじゃねえ! こんな茶番で貴様の罪が赦されると思ったら大間違いだ! このまま貴様がヒーローになるくらいなら、私が貴様の息の根を止める!」
風乃は手に持ったモップで長嶺に襲いかかる。
やばい人が来た。
まさかと思って顔を見てみると、母だった。
「こんなお涙頂戴の猿芝居、てめえらも歌って感動したらそれで忘れんのか
!? こいつがやったことがチャラになんのか
!? みんなで仲良くお歌歌ってめでたしめでたしって、群れなきゃ何も出来ねえ雑魚どもが、どいつもこいつも似たような顔してんじゃねえよ!」
「先輩……」
長嶺が衣装の埃を払い、風乃に向き合う。
「そういうことを言うんだったら、先輩が倒せばいいじゃないですか、メデューサを」
「そういう問題じゃない。あんたのやり方が気に要らない」
長嶺はひとつ溜息をついて続ける。
「先輩、去年の文化祭の舞台劇、私が作ったセットをまるまる作り直したでしょう?」
「クオリティが低かったんだから、当たり前だ。まさか、根に持ってるのか?」
「根に持ってはいないけど、次の日、顧問の先生、授業に穴を開けたしょう?」
「ああ、あれ、あの時だっけ?」
「しらじらしい。先輩はいつも無茶ばっかり。この学園を受けたのも、中退すると大騒ぎしたのも、ぜんぶ後先考えずに感情的に行動した結果でしょう? 私、その子にすべて話してもいいのよ?」
長嶺会長は僕を指差す。
「あいつは関係ない。メデューサを倒すのは、私の使命だ」
「はいはい。それじゃあどうぞ。メデューサは譲りますから、勝手に倒してくれば?」
「言われなくてもそのつもりだ!
てめえらは学園に帰ってまた甘ったるい恋の話でもしてろ!」
母は……風乃翼はそのままメデューサが去って行った方へ姿を消す。
ゴルゴンとの戦いで転がされていた彫像を立て、生徒会メンバーが両袖にはける。
効果音、風。
月に照らされる荒野。
「お母さん。どこに行ったと……」
上手より、走り去った母の姿を追って僕、樺島勇が舞台に出る。
周囲には石化した生徒たちの姿がある。中にはついさっき、生徒会室で見た者の姿も。
「もうメデューサは倒さっしゃったとやろうか……」
歩いていると、目の前にヘビの髪を持った女の後ろ姿を見留める。
さっき長嶺会長が戦っていたメデューサとは違う、おどろおどろしい髪、すぐにそれが劇の中の作り物のメデューサではない本当のメデューサだとわかり、僕は思わず、アイギスの盾をインストールした携帯のカメラ越しにその姿を見る。
メデューサがゆっくりと振り返ると、その口から、
「なんで……?」
か細い声が漏れる。
「なんでついて来たと」
アイギスの盾に映し出されたメデューサの顔は、母の顔だった。
「お母さん? お母さんね?」
「なんね、携帯ばっかり見て。お母さんの目ば見て話さんね」
「ばってん、お母さんじゃなかったら……メデューサやったら、見たら石になるけん」
「そげんこつ疑うたっちゃしょうがなかよ」
「お母さんがメデューサやったら、僕はお母さんの首ば切らんといかんと。ばってん、お母さんがメデューサかどうかわからん」
「やったら、直接見たらよかろうもん」
「ばってん……」
「あんたが五年生のとき、親戚が集まってカレーば作って食べたことのあるやんね。覚えとるね?」
「覚えとるよ。ちょっと辛さの足らんち、おじさんたちの言うとらしたけん」
「あれね、お母さんと離婚する口実ば作るとに、お父さんが親戚ば集めらっしゃったと」
「嘘……」
「親戚ん集まるけん、こまか子もおるやんね。そいけん、肉も野菜も小そう切って、辛さも抑えて、シチューのルーば足して作ったら、みんななんち言うたと思う?」
「覚えとうよ。具の小まか、味の足らん、ごはんなこげん柔らこう炊かんでよか」
「あのクソどもが、私の目の前で、笑いながら、真雪はよか医者になったばってん、嫁だけは失敗した、ち言うて、あの人は私んこつば庇いもせんでヘラヘラ笑うとったとよ。お母さんが、どげん気持ちやったと思う?」
「気持ちはわかるばってん。わかるばってん……」
「よかよ。あんたも石になるとやろ。私の顔ば見たら、石になるとやろ。ばってん、あんたまで石にする気はなかけん。もう帰らんね」
「そげんこつ、言うたらいかんよ」
「やったら、携帯ばしもうて、顔ば見らんね。あんたん目で、直接!」
母の言葉は、少しずつ語気を荒げ、感情をむき出しにする。
「見たらよかろうが! どうせあんたも石になるっちゃろうが!」
僕は、信じるしかなかった。
僕だけは、母の顔を見ても、決して石にはならないと。
顔を上げると僕は、新合川町のショッピングモールにいた。
大勢の怪我人がいる。
自衛隊や救急医、外からは緊急車両のサイレン。
父はそこにいる多くの看護師たちに指示を出し、腕章をつけた久保田もその下で包帯や消毒液を運ぶ。父はそこで、多くの命を救い、多くの人に安心を与え、信頼を集めている。その信頼の元で、この緊急時の現場が回っている。
だけど僕は嫌だ。
こんな世界は嫌だ。
なんであの男が世間の信頼を集めて、母が苦労しなきゃいけなかったんだ。
わけがわからなくなって、僕はただ叫び声を上げた。何を叫ぶでもない。それで気持ちが晴れるでもない。体が勝手に吠える。流れる涙の理由もわからない。
すぐにふたりの看護師が来て、僕の背中を擦って、背を屈ませる。
僕になんか構わなくていいのに、こうしている間にも弱って行く人はいるのに。僕が今吸っている空気は、声を出せない人の生命だ。僕は泣きながら、それがわかっていながら、その生命をすするしかない。
その姿を見て小西が駆けつけて、看護師の一人に代わって僕を抱きとめる。
「吐き出して良かけん。吐き出してよかよ」
小西が僕の耳元に囁く。
「吐き出したらもう、飲み込まんでよかけん。吐き出して。ぜんぶ」
アイギスの盾を下ろし、顔を上げると、ヘビの髪をたなびかせる母の姿があった。
もし僕が、石にならなかったらかけようと思っていた言葉を、喉から絞り出す。
「お母さん、もうよかよ、そげなこつは。終わりでよか。僕は石にはならん。石になるとは、その後ろにある物語ば見らんごつしとるだけよ。僕は全部見る。どげん苦しか物語の中からでっちゃ、真実ば見つくる。絶対に、この先どげな物語に触れても、どげな現実に触れても、僕の身体は、僕の心は、絶対に石にはならん」
母は大粒の涙をこぼし始める。
そして右腕を己の左胸に突き刺し、心臓を取り出した。
心臓は空っぽになったインクのボトルだった。
「あの世には、インクが売っとらんけん、これでもう、続きは描けんたい」
母は僕に、空になったインク瓶を手渡す。
「お母さん、成仏するけん。首ば切り落として」
「そげんこと言われたっちゃ困るばい。それで本当に成仏できると?」
「首ば落として天国に行くるとなら、体だけでも天国に送ってやりたか。あんたば生んだ、あんたば育てた体やけん。地獄に行ったら、あんたに申し訳んなかもん」
「ばってん……無理よ。クロノスの鎌も貰うとらんもん」
「そげんこつなかよ。小野田くんから貰うとったろうが」
小野田さんからもらったもの……? Gペン……?
僕はGペンを取り出して、母の首にかざす。
クロノスは時の神、クロノスの鎌は、時間を切り取る、時間の鎌だ。
ならば――ならば僕はこのGペンで、母の時間を、僕の時間に接ぎ木する。
時間を示す真っ直ぐな直線を、母のメデューサの首にゆっくりと引くと、メデューサの頭は地に落ちて、その首の上に晴れやかに綻ぶ母の顔が戻った。
ここまでは、母の物語。
そしてここから描くのが、僕の物語だ。
あーきの ゆーうーひーにー てーるーやーまーもーみーじー
こーいも うーすーいーもー かーずーあーるーなーかーにー
どこかから歌声が聞こえている。
全身に疲労感がある。手足は痺れて動かない。
左手には点滴の針が刺さっている。
ふと見上げると、チルさんのシャツを着た小西が見えた。
時計を見ながら、目を腫らして、口ずさみながら僕の脈を計っている。
まーつを いーろーどーるー かーえーでーやー つーたーはー
僕が歌を合わせると、小西は顔を上げて、その歌声は涙に堰き止められた。
やーまの ふーもーとーのー すーそーもーよーおー
第十章 白球のアンドロメダ
「伊藤さんち知っとう?」
「知っとうばってん、何?」
「あんたの連絡先ば教えてち言われたとばってん、教えてよかね」
「よかばってん、なんで?」
「そげんこつ、向こうから電話がかかってきたら聞かんね」
姉からの電話だった。
高松医院の番号だったら、電話帳にも載ってるし、看板にも出てる。それを見て電話して、詩香さんか父が受けて、それで姉が僕に連絡をよこしてきた。だけど、どうして伊藤が僕に。
次の日には電話がかかってくる。
どこかで会いたい、できれば母の仏前に何か供えさせて欲しい、と言うので、大川の家に近い西鉄柳川駅で待ち合わせることにした。祖父は車を出すと言ってくれたけど、でも少し話す時間が欲しかった。
西鉄柳川駅の改札前。福岡からの特急が入り、人波の中に彼女の姿を見つける。笑いながら手を降る彼女は、場違いなほどに輝いていた。ひとこと、ふたことの挨拶。ぎこちなく言葉を交わして、西口の三番バス停へ。
「嫌われとるち思うとった」
「嘘、逆よ。私のほうが嫌われとるちばかり思うとったとよ」
バスを待ちながら、とぎれとぎれに会話を進める。
「お母さんの実家は遠いと?」
「二十分くらいバス。バス停からは僕で五分くらい」
「バス、好いとうけん、ちょっと楽しみ」
「お母さんが死んだとは、どこで知ったと?」
「うちのお父さんに聞いた。お父さんはじいちゃんから。あのね、樺島くん」
伊藤は少し息を飲んで続ける。
「ごめんなさい」
深々と頭を下げられるけど、僕はなんのことかわからない。
「どげんしたと」
「お父さんがスーパーの店長しとったとき、樺島くんのお母さんばクビにしたと。じいちゃんが、高松さんが離婚した時、跡取りば盗って行ったち言うてめちゃくちゃ怒っとって、うちとはぜんぶ縁ば切るち言うて、無理やり辞めさせたと」
彼女の家は母親が美容院、父親が祖父がオーナーの小さなスーパーで店長をしていた。
「伊藤が謝らんでよかよ。顔上げて。泣かんでよかけん」
彼女が言うには、その後僕の母は二ヶ月職がなくて、僕は自分の家のことなのにそんなことは知らなかった。その二ヶ月、母がどんな気持ちだったかと思うとやりきれなくはあったけど、でもそれは伊藤のせいじゃない。
バスが来て、ふたり掛けのシートに座る。
「ありがとう。わざわざ伝えてくれて」
まずはそれだけ言って、言うだけは言って、言葉を探した。
「僕たちは、大人になるとよ、これから」
何を話せばいいのか、筋道も見えないまま。
「大人がいて、僕たちがいた世界が、もうすぐ終わって、大人になると。今までいろいろ、わからんこつはあったばってん、その喜びとか、怒りとか、悲しみとか、ぜんぶ食べて大人になって、どげん大人になったかだけが答えやけん。そいけん、よかよ」
自分で言った言葉の意味を、自分でも探りながら、繰り返した。
「大人になるとよ、僕らは」
中原高木病院前にバスが止まる。そこから徒歩五分。
「なんか、オーラのあるけん。最初、芸能人が来たかち思うた」
「可愛かろ、私。自分でも、顔は可愛かち思うと。道具やけん、手入れ次第でなんとかでくるばってん、ちゃんと自分の武器ば見つけるまで、これしか取り柄んなか」
そう言って伊藤は口を尖らせる。
ついこないだも舞台のオーディションに落ちた。自分が出ていたCMがいつの間にか終わっていた。アイドルグループのオーディションは一度受けて落ちて、それで踏ん切りは付いている。ダンスは絶賛上達中。でも、本当に自分が何をしたいのかはわからない。
五分の道のりを十分かけて歩いた。
伊藤は、母の位牌にも、祖父母にも、深々と頭を下げた。
九月に入り、一周忌までもう一月もない。
僕の進路はまだ決まっていない。
投稿用に描いていた漫画はようやくメデューサを倒し、残りはケトゥスという化け物を倒してアンドロメダを助け、メデューサの姉ふたりを倒して結婚式をあげるのみとなった。ページ数にしてあと8ページ。
「樺島くんは?」
「僕は、漫画ば描こうかち思うとるばってん、諦めて進学しようか迷うとると」
「私と同じ系の悩みよ、それ」
篠宮が進学すると言いだしてなかったら、たぶん僕は突っ走ってたと思う。そういう意味では彼に感謝しなければいけないんだけど、将来のこと、漫画のことを熱く語ったのはなんだったんだろうという気持ちもなくはない。
次の土曜日、伊藤に誘われて、薬院の近くの公園に来ていた。
「野球のコーチばしよると」
そう言って少年野球チームのメンバーを紹介してくれた。全部で十五人。そのうち女子が三人。その中のひとりはレギュラーでファーストを守っているという。
「なんで伊藤が?」
「幼馴染んくせして、知らんと?」
そう言うと伊藤は、キャッチャーを座らせて投球を見せてくれた。
その球速を見て少年たちが沸き立つ。
「すごか!」
「魔球ハリケーン!」
歓声をあげる少年たちに、伊藤は声をあげる。
「魔球は漫画の中だけやけん!」
伊藤は言う。ファーストの子、唯一の女子レギュラー、
飯島楓の姉と知り合いで、それで少しだけ教えるようになった。それがきっかけで、仕事で忙しい監督に代わって練習を見るようになって、今は三十日に開催される試合に向けて調整中だと。その試合のことをたずねると、伊藤は呆れたように、「それがもう」と、大きく息を吐く。
「滅茶苦茶よ。もう。相手はプロの二軍」
「はあ
!?」
「に、おった男が率いる社会人チーム。うちのエースの
里中樹莉くんが、ちょっとその人とトラブったとよ。『ボクだったら二軍から上がれなかったらその時点で野球やめます』ち言うて」
「それ、絶対言うちゃいかんやつ」
「それで、じゃあ野球で勝負だー、一点とったら許してやるー、ちゅう感じで」
「面白かばってん、嘘よ。できすぎとう。漫画でっちゃそげな話はなかよ」
「ナンパ目的よ。向こうは試合はどげんでっちゃよかと。向こうから絡んで来たとば、里中くんが庇うてくれたとよ」
「それやったら辞めたがよかよ、球団か会社に言うて、なんとかしてもらえんと?」
「ばってん、プロ山も根っからの悪人じゃなかけん」
「プロ山?」
「里中が名前で呼ばんで、ずっとプロ山プロ山言うけん」
「ああ」
「子供たちにもちゃんと点ば取らせて、活躍の場ば作るけん、打ち合わせばしようち言うて来たと。ばってん、ズルはしとうなかやん。それに、監督のおらん時ば狙うて話に来たけん、ムカッ腹ん立って。プロやったらこの子らば0点に抑えてみらんね、ナンパはその後やろうが、このクズが!……ち言うてやった」
「馬鹿なの?」
「別に、0点に抑えたら身体ば許すとか言うとらんもん」
「相手はそのつもりよ、0点に抑えたらデートOKくらいに思うとるよ、絶対」
「一応、学校にもストーカー対策の窓口はあるけん、相談はしとう。そっちにも止められはしたばってん、あとは自己責任たい」
「そげん悠長に言わん。僕も、試合当日は行くけん」
「ありがとう。今月末、三十日正午、場所はここ」
母の一周忌の日だ。午前中の法要を終えて、それからでも間に合う。
「隣におって、彼氏のふりばしてくれると?」
法要のことを考えていて、少し返事が遅れた。
「やっぱよか。彼女さんに悪かもん」
「いや、そげん風に言わんで。まだ付きおうとる人はおらんけん」
そのあとふたりで、『答え合わせ』をした。僕たちはお互いのことが好きだった。でもそんなことを言う必要はないと、お互いに思っていた。なんとなくわかっていたことを言葉にして、お互いいつ頃、どんなきっかけで好きになって、いつ頃まで好きでいたかを話した。それでどうやら彼女のほうがわずかに早く僕のことを好きになって、そしてお互いに、今も好きなままでいることがわかった。
だけど僕たちはまず、大人になるって決めた。
それもお互いにもう、わかっていることだった。
家に帰ると、ネットで注文していた漫画プレスの島田組特集回のバックナンバーが届いていた。テレビを付けて、届いた包を開けていると、たまたま流れていたテレビのニュースが、成層圏に巨大なクジラの化け物が発生したと伝える。
全長二キロ、幅四〇〇メートル。場所はフィリピン海沖。米軍がスクランブルをかけたがダメージは与えられず、化け物に追随して飛行する小型の飛翔物によって全機撃墜された。現在化け物は太平洋上をゆっくりと日本へと向けて移動中。テレビ画面には、その予報円が示される。
日本上陸は今月末。予報円の中心は、九月三十日、僕たちの試合が予定されている、平和中央公園に差し掛かる。
おそらくこれがケトゥス。アンドロメダを襲う怪物。
今まで、怪物が現れると決まって、島田先生の教え子さんたちに助けられていた。
音楽漫画の錠崎まどか先生にはじまり、ナンセンスギャグの枯葉チル先生、宇宙の騎士シリーズの今川功敬先生、民営ミリタリー漫画の小野田幸秀先生、レース漫画の八敷カズサ先生、メデューサの時は炎の生徒会の森エミル先生と、ついでに僕の母、樺島裕美。
ここまでに登場したのは七人。あと見ていないのは、野球漫画の
石泉シュウ先生、動物漫画の思妤先生、ガールズヒーロー
三銃姫の
星乃望先生。それと、加古江さんと島田先生。これで十二人。
漫画プレスに、島田先生の仕事部屋の写真があった。若い日の母と、加古江さんらしき人、島田先生らしき人がいるのがわかる。その背景に、
――勇なるかな、勇なるかな、勇にあらずして、何をもって行なわんや――
の、額装があった。
ケトゥス襲来の一週間前、高松医院に行った。
校医を担当している学校からの帰りが遅れているからと、応接室へと通される。詩香さんが選んだ紅茶と、お茶菓子。しばらく待っていると、若い男が部屋に入ってくる。
「おまえが勇か。詩香と親父が話してるのを聞いたことがある」
歳は二十代半ばだろうか。涼しげな顔。はじめて会う。なのに図々しい。
「紅茶、マズいだろう? よく飲めるよな、それ。熱いし」
「あのう、あなたは?」
「銀。詩香の保護者みたいなもん」
そうは言うけども、詩香さんより上の歳には見えない。そもそも保護者がどうして?
「今日は、どうしてこちらへ?」
「どうしてって、ここに住んでるから。詩香の部屋があるだろう? そこに俺のベッドも用意されてるし、たまに詩香とも寝るし。今日はお前が来るって聞いて、顔くらい見とこうと思ってな」
いったいこの家で何が起きているのか。「ああ、はあ」としか言えない。
「ここに来る前に相談されたんだよ、詩香に。もう四~五年前じゃないかな。『不安だ』って。あいつ馬鹿だから、この家に来るには俺と別れなきゃいけないと思ってたらしく、それで悩んでたんだと。でも、ちゃんと話したら俺も一緒でいいって話になって、あとはとんとん拍子よ。おまえ、あの親父の息子なんだろう?」
「ああ、はあ」
「そう思ったよ。似てるし」
「そうですか。僕はよく母親似だと言われてました」
「まあ、そっちは知らねえからな。ちょっとそっち行ってもいいか?」
と、銀さんは言うと、返事を待たずに僕の方へ来て、膝の上に横になった。
「背中、揉んでくれよ」
なんで? と思いながらも、銀さんの背中には揉まざるを得ない気持ちにさせる魔力があった。揉んでいると腰を上げて、伸びをする。
「奏絵は避けてるみたいだけど、悪いやつじゃねえよ、あの親父も。よくコロコロでそのへん掃除してるし、俺のウンコも処理してくれる」
なんでも母任せ、看護師頼みだった父が、コロコロはともかく、他人のウンコ?――の世話をするのは、少し意外だった。それにしてもこの、銀と言うひと。膝の上でくつろぐ無防備な姿態に釣られて、無意識に脇の下に手を入れてみると「シャーッ!」と言って手を叩かれた。
「わきまえろよ、おまえ。触っていいとこといけないとこがあるんだから」
「すみません。このシチュエーションが始めてだったもので」
話をしていると父が戻ってきた。入れ違いに銀さんが席を立ち、外で待っている詩香さんに抱きとめられて部屋を出る。
ソファに腰を下ろすと、すぐに父は口を開いた。
「大学は決まったとか」
最初に出た言葉がそれ。わかってはいたけど、あらためて落胆する。
「僕は大学は無理と思う」
「西町高校で、成績は真ん中くらいやろう? それやったらまだなんかあるよ」
「専門学校に行こうと思う」
「そうか……」
父は少し言いよどむ。
「大学に行くならうちで支援する。一年やったら浪人したっちゃよか。医大に行けとまでは言わん。今更やけん。ばってん専門学校は、俺は賛成せん。小学校んときは成績は悪うなかったとぞ。国立ば狙うだけ狙うてみらんか」
「今日はそげんか話ばしに来たっちゃなかけん。詩香さんのことたい。もう一週間で一周忌やけん、それ過ぎたら、再婚してち言おうと思うて」
父は苦笑いする。
「こげん歳になって、子供にそげんこつば言わるっとは、恥ずかしかつぞ」
父も昔に比べたら随分穏やかになった。でも、だからと言って。
「離縁したとは、しょんなか面もあったたい。お互いにもう、修復できんとこまで来とったけん。そうばってん、離婚しとらんやったら、せめておまいば手元に置いとったら、この医院ば継がせてやることはできたけん、それだけは後悔しとう」
「そげんとこじゃなかと、お母さんが嫌うとったとは。詩香さんのことば話しとうときに、僕の話になったら、僕も良か気がせんもん」
「よかやんか、何年ぶりにゆっくり話しとうとやけん」
自分の話したいことしか話さないのは相変わらず。
「大学に行ったがよか。後悔するとはおまえぞ」
小学校の頃、家に帰ってきて、今日と同じこのソファに座ったときと同じように、シートの縫い目に指を添わせる。空白の時間があったはずなのに、僕と父とは、あの日の続き。
「部屋も日吉に借りたとやろ。そげんして自由に生きたっちゃよかばってん、家賃も電気代もかかろうたい。メシも自分で作るとやろう。その金と時間で、なんがでくるとかちゃんと考えとうとか。俺も親は嫌うとったばってん、俺がおまいやったら、親が金ば出すち言うなら断らん。そいが自分のためやけん。一年浪人して、大学に行って、知識ば身につけながら、そん中で夢ば叶ゆるたい」
僕は恵まれているのだと思う。
たとえば小西にこんな環境が与えられるかと言えば、それはない。
浪人の一年まで含めて五年間の猶予が僕に与えられようとしている。
断る理由がない。
「要は自分が、なんばしたかか、よ。なんばして世の中に貢献するか、なんばして世の中に居場所ば見つくるか。社会で求められる人間になるために学ぶとぞ。自分のため、生きるためだけやのうて、人の役に立って、助けるために学ぶとぞ」
ずっと言われてきたことの繰り返しだった。どんな夢があるか、何をしたいか、幼い頃から何度も問われてきた。だけど、ないんだよ、そんなものは。ただ、するべきことがあって、たとえばそれは食事や排泄もそうかもしれないし、目の前で困ってる人がいたら、助けるのがそうかもしれないし、だけどそんなことはだれも言わない。目の前のどこにもない『やりたいこと』をさがせ、と。そればかり。探すものじゃないんだよ、それは。胸の中になければ、ないんだよ。
「なんばしたかか、じゃなかよ。なんばせにゃいかんか、よ」
「それが勉強やろうもん。勉強はせにゃあいかんばい。ばってん、漫画ば描かにゃいかん理由はどこにもなか」
「お父さんは自分の見栄のために、僕ば大学に入れたかだけよ。お母さんの教育が間違うとった、正しかとは自分やったち信じたかだけよ。でもそれは、お父さんの慰みになったっちゃ、お母さんが報われたりはせんけん」
「見栄じゃなか。おまえと裕美のために言いよると。おまえが裕美についていって、養育費はぜんぶ生活費に消えた、塾にも通わせてやれん、成績はだだ下がり、大学にも受からんやった、もうなんもできんけん漫画家になりますち言うたら、裕美の恥になるとぞ」
父はもしかしたら、本気でそう思っているのかもしれないけど、そうやって母を利用されたくなかった。
「じゃあたとえば僕が、四年制大学の看護学科ば受けるち言うたら、どげんすると」
そう聞くと、父は黙り込んだ。
きっともう推薦枠は埋まってる。願書が間に合うかどうかも知らない。でも、今の成績で不可能じゃないし、父の言う条件をすべて満たしている。
「ばってん、看護師ちゆうとは、一生の仕事じゃなかぞ」
予想した範囲で言葉が返ってくる。呆れると同時に、僕は自分の正しさを確信した。
「いいよ、それでも」
「なんがよかろうか」
父は、乗り出していた背中を背もたれに預けて、嘲るように笑う。言葉を重ねようとする父に、僕はカバンから、メデューサの首を取り出して見せた。
「もういい。これでおしまい」
メデューサの首は闇を放つ――
「うわーっ、それは見た者が石になるちゆうメデューサの首! なんでそげんかもんば見せると! そいば見たらお父さん、石になろうが!」
父は石になった。
部屋の外で聞き耳を立てていた姉と詩香さんがすぐに中へ入ってきた。
「お父さん、石にならっしゃった!」
「真雪さんの石になっとう!」
僕はメデューサの首をカバンに戻して席を立つ。
部屋を出ようとすると、銀さんが入ってくる。
「おう、もう帰るのか。いまこれを獲って来たんだ」
そう言うと銀は、ヒヨドリの雛を僕の目の前の床に置く。
「銀! どこで獲って来たと!」
詩香さんが驚く。
「もう帰んの? 食う時間ない? じゃあ、持って帰るか?」
キラキラした目で僕を見る銀さんを裏切れなくて、それにこのままにしていたらこの子は死んでしまう。僕はヒヨドリの雛をポケットに入れた。
「勇!」
去りゆく僕に銀さんが声をかける。
「あんまり考えすぎるなよ! 好きに生きればいいから!」
頷いて、日吉のアパートへ、途中、ペットショップが目に入る。
こんなところにペットショップが?
昔ながらの小鳥の匂いをいっぱいに湛えたペットショップ。僕は駆け込んで、ポケットの中の雛を掌に乗せる。
「この子に食べさせる餌ばください。この子の素嚢ばぱんぱんにしてやりたかとです」
「なんがよかね。なんでっちゃ食べるばい、その子は。あんたが与えるもんは、なんも見らんで食べて、じぶんがなんば食べたかもわからんで大きゅうなるたい。なんば食べさせるとが正解か、だれも知らんと。ただ、自分が正しいと思う餌ば食べさせとうだけよ、みんな」
店の棚にはたくさんの本が並んでいた。漫画もあったし、小説も、歴史書も。旧い映写機と8ミリのフィルム、空き缶と、ゲーム、映画のディスク。
かごに入れて、支払いを済ませて店を出ると、掌に乗せていたヒヨドリはいつのまにか大きくなっていて、空へと羽ばたいていった。
九月三〇日、朝九時から母の一周忌の法要。
祖父母と、佐賀から母方の親戚が来て、お寺でお経を上げたあとは、本家、ミツコさんのお屋敷で食事をするという。
伊藤たちの少年野球団のプレイボールは正午。
食事の準備を手伝うくらいの時間はあるからと、ミツコさん宅を目指す祖父母の車に乗った。
「この一年で、二回もぶつけとらすとよ。物損でよかったばってん」
「免許ば返上せい返上せい言わるるばってん、免許んなかと生活できんもん」
国道二〇八号線。大川橋を渡り、佐賀県に入る頃に、僕は切り出す。
「あのくさ。僕、じいちゃんばあちゃんに、嘘ば吐いとったと」
「なんば急に言いよらすと」
「嘘くらいだれでっちゃ吐くけん、改まらんでよかよ」
「お母さんの生命保険が降りとると。久留米のアパートの家賃は自分で出しとう。高松の家には世話になっとらんと。金額ば言うとトラブルになるこつがあるけんち言われて、今まで黙っとった」
祖父母は返すべき言葉を探す。
「言わんでよかよ。裕美が勇に残したつやけん、じいちゃんばあちゃんな関係なかもん」
「うん。ばってん、関係あるとよ。僕、大川の学校に通おうち思うとるけん、お母さんの部屋に三年間下宿させてほしかと。下宿代は払うけん」
「下宿代やらいらんよー。一緒に住んだらそいでよかたい。家族やなかね、水くさか」
「いや、でも、いかん。そこだけは僕の無理ば聞いて。お母さんにもろうたお金やけん、さっきお寺さんでお母さんとも相談して決めたけん」
「そげんこつ言われたら……」
うしろの席の祖母が言葉を詰まらせる。
「どこの学校さ行くと。漫画は諦むっとか」
「看護学校に行く。漫画は諦めん。お母さんの使うとった部屋で続くる」
この三年間で、僕の人生を決める。
どちらに進んでも後悔はない。
ミツコさんの家で、お昼の準備を手伝って、煮物をつまんで、親戚が集まってくる頃にはもう十一時五十分をまわる。
「十二時から薬院ち言うとったばってん、間に合うと?」
親戚の叔父さんが心配していると、祖父が一言、
「裕美の子やけん」
僕は、それではこれで、と頭を下げて、空間の歪み、七色の虹の道を作り出す。
かかとには翼がある。
親戚一同のどよめきの中、一路、平和中央公園を目指す。
佐賀から薬院まで四〇キロ弱、翼の靴でものの二分とかからなかった。
厚い雲の隙間、上空はるか高く、薬院方面へ接近するケトゥスの姿が見える。
携帯でニュースを確認すると、今川さんと錠崎さんのキャラが戦っているのがわかる。それと星乃さんの三銃姫らしき姿も。
グラウンドを見れば、ユニフォーム姿の子供たちにも不安の表情が見える。
相手チームには少なくとも三人の元プロ選手がいる。それがピッチャーとセカンドとショートという重要なポジションを押さえている。その中のセカンドが伊藤が言っていた『プロ山』だと思われる。日焼けして、筋肉質で、茶髪。
こちらは最年長で十二歳。ピッチャーができるのは里中だけ。端から勝てるわけのない試合。一点をもぎ取ることを目標としているけれど、時速一二〇キロを超えるボールをバッターボックスで見たことのある子はいない。
伊藤が声をかけてくる。
「今日は練習の成果ば出すだけばってん、応援してやって」
「うん、でも、化け物の動き次第では、そっちに行くかもしれん」
「よかよ。それも応援よ。みんなが頑張っとう時、別の場所で頑張るとも応援のうちよ」
ルールは特別ルール。イニングは七回。各回
10点を越えたら攻撃終了、コールドはなし。お互いに手を抜かないこと。それと、子供たちが0点に抑えられたら、伊藤はプロ山のナンパに晒されても文句は言えない。でもそれを言うと伊藤は、そげなことのために戦うとじゃなか、と言う。
十二時。
プレイボール。
相手チームも最初はレクレーションのような雰囲気だった。だけどプロ山の、「手を抜いても子どもたちのためにはならん」の言葉を飲み込んで、黙々と、試合に臨んだ。
一回表、プロの攻撃は打順を一巡して全員ホームベースを踏み、ルールによって
10点で攻守交代。少年たちは全員がバント狙い。一四〇キロのボールにバットを当てたところでコントロールはできない。それで塁に出たところで、後が続くはずもない。
試合前は不安の中にも、プロと試合することに胸をときめかせていた子もいた。この数週間の練習、みんな生き生きしていた。最初のイニングを終える頃、その希望はすべて絶望に変わっていた。
その時。煙を噴きながら空を斜めに落ちてくる影があった。
プロペラ付きのジェットパックを背負っている。片肺のジェットパックで器用にバランスをとってグラウンドへの激突を回避し、バックネットに突き刺さり、落下する。
騒然とする。近くに寄って確かめると、加古江さんだった。グラウンドにいる者は皆、空を仰ぐ。どんよりと垂れ込めた空に巨大なクジラの化け物と、それと戦う無数の戦士たちの姿がある。
「なんばしよるとですか?」
聞くまでもないけど、加古江さんに聞いてみる。
「なんばって、ケトゥスと戦いよるちゃ」
加古江さんのその言葉に、子供たちが振り返る。
「ばってんもう無理ー。腰ば打ったごたー」
試合は? このまま続行するのか? 大人たちの顔にはそんな表情が浮かぶが、
「試合は続けます! この、樺島勇が、ケトゥスば倒します!」
伊藤が僕の右手を持って高々と上げる。
子供たちは固唾をのみ、真剣な目を向ける。
「わかった」
僕にも魔法のGペンと、ヘルメスの靴がある。行ってこよう。
そう決意したところに、加古江さんが携帯をよこす。
「これでメカを呼び出すといい」
メカを?
受けとった携帯を操作しようとするが、アイコンが無い。
「二十五年後の携帯だ。脳波と音声コマンドで操作する」
加古江さんはまだそんなことを言ってる。でも――万が一それが事実だとすると、本当に加古江さんは二十五年後の僕と言うことになる。
「音声コマンドち言うたっちゃ、コマンドがわからん……」
「なんでもいいよ。言えば相棒がぜんぶやってくれる」
「相棒?」
「君がイメージするメカを、君の言葉で伝えたらいい。あとはあいつが設計してくれる」
「あいつって?」
「時間がない! 早く!」
「じゃあ、私たちは試合の続きを!」
加古江さんがグラウンドからはけて、第二イニングが始まる。
僕は――僕はわけもわからず、携帯に言葉を伝える。
「全長一〇〇メートルの巨大ロボット!
飛行形態に変形可能で、武装は可能な限り、すべて!」
そう告げると、ピピッと、小さな効果音を鳴らして、携帯の画面が光る。
数秒のローディングののち、携帯から光が溢れだし、その光の先にパーツが実体化する。何千、何万というパーツがワイヤーやシャフトを介して目の前で組み上げられていく。その一部が巨大な機械の手となって、足元から僕をすくい上げる。ロボットは部位ごとに完成していき、僕を乗せた手も高く高く上がっていく。各部の装甲が噛み合わさる。始めて見るロボットだけど、僕はこれを知ってる。
美術室で見た漫画の宇宙船、篠宮が描いてるメカだ。
二十五年後の篠宮が描いてるんだ。
ロボットの組み立てが完了し、バックパックのリアクターに火が入る。
「篠宮っ!」
大声で呼んでみても、その声はロボットのエンジン音がかき消す。
「篠宮っ! 飛べるか、空を!」
ロボットは上空、ケトゥスの姿を見上げ、次の瞬間にはバックパックと脚部にジェット気流、その巨体は空に舞い上がる。
それを見留めたケトゥスの体表に無数のハッチが開き、小型の飛翔体を一斉発射、白煙を引きながらこちらへ迫る。僕はロボットの手の上で風に煽られながら指示を出す。
「迎撃!」
ロボット左右の腕のハッチが開き、大量の小型ミサイルがばらまかれる。直後、推進剤に点火、敵の飛翔体を追尾、撃破。続けて第二波、第三波の攻撃、迎撃が間に合わない、
「防御を!」
バックパックより数百のデコイ射出、その間に張り巡らされた細い樹脂繊維が敵飛翔体を絡め取る。
「武器のリストを見せて!」
目の前の空中にウインドウが開いて武器のリストが表示される。その中から、
「熱投射レーザー!」
両掌から熱線が放射される。繊維に絡められた飛翔体はその熱で次々と爆発、その爆煙の中で飛行形態に変形、腕のパーツは細かくスライドして、翼となり、僕の身体はコクピットの中に取り込まれる。脚部は複数のジェットエンジン群により躯体を浮上させたまま、双胴のボディへと変容、そのまま二門の主翼上部砲身から荷電粒子ビーム照射、流束を一点に浴びせながらケトゥスに突っ込む。装甲破壊を確認。変形しながらの急制動、再度人型で腹部機銃より徹甲弾連射。脚部より大型レールガン二丁を取り出し、至近距離から重粒子砲を浴びせる。離脱。
ケトゥスの左鰭が破壊されて千切れ飛ぶ。分離した肉塊は変形し、小さなケトゥスとなって襲ってくる。次の攻撃を、と武装リストを開くが、どれも赤字で表示されている。
ペン先寿命アラート。
そう言えば小野田さんからGペンはもらったけど、換えのペン先がない。
まだ緑で表示されているフレキシブルアームを選択、八本の多関節の腕で迫りくる分体を破砕、そのままケトゥス本体へ向けて伸ばす。鉤爪を本体に打ち込み、収縮させてその躯体に取り付く。
ケトゥスはまるで、浮遊する大陸だった。その上で星乃望先生のガールズヒーローたちが戦っている。ケトゥスの体皮から次々と化け物が生み出される。その化け物を三人の銃使いが華麗な技で迎撃するが、終わりのない戦い、ただペン先だけが消費されていく。
赤いスーツを着たアテナが僕のもとへやってくる。
「ケトゥスはまっすぐ平和中央公園を目指している。約七分後に接触。少年たちを避難させて」
公園ではまだ試合が続いているかもしれない。
僕はひとつ頷いて、
「緊急離脱! 脱出機を!」
ロボットの一部が切り離され、小型の飛行機に変形する。
それを駆り、グラウンドへと向かう。
グラウンドへ戻ると試合は最終回七回裏。点数は
70対0。2アウト。
あとひとりで試合は終わる。
時計を確認すると、ケトゥス接触まであと五分強。
「伊藤!」
「ケトゥスはどげん
!? 倒せたと
!?」
「いや、ケトゥスはまだ……」
「だったら来んでよか! 倒してきて!」
バッターボックスにはこのチーム唯一の女の子、楓が立ってる。
子供たちの目はもうどんよりと曇っている。
「最後のひとりだ! さっさと打ち取るぞ!」
「打たせてやれ、打たせてやれ! ご褒美くらいくれてやれよ、大人なんだから」
相手チームには苛立ちと疲れが見える。彼らにも迫りくるケトゥスの姿が見えている。
子供相手とは言え、手を抜かずに戦えと指示されていたピッチャーには相応の疲れが見える。それでも球速は速い。2ストライクからの三球目。必死に食らいついてバントで当てるも、ボールはセカンド、プロ山の目の前へ。
楓の目に涙が浮かぶ。
「走れ、楓ーっ! アウトがコールされるまで諦めるなーっ!」
伊藤の激が飛び、楓は走り出すが、プロ山の気を抜かない華麗なフィールディング、ボールはファーストへと送られる。どんな間違いがあっても間に合うタイミングじゃない。
それでも、
「走れーっ!」
伊藤は叫ぶ。
そしてなぜか、ファーストの男はベースに置いた足を外してボールを受ける。
楓の顔にほのかな希望が浮かぶ。
プロ山は肩を落とした。ここまで来たんだ。最後に花を持たせてもいい。そう思ったのかもしれない。
だけどファーストの男は迫ってくる楓の顔を見ながら、その目の前でベースを踏む。
「残念だったね、お嬢ちゃん。がんばって走ったのに」
楓は泣いて崩れ落ちる。
一瞬の戸惑いのあと、伊藤がベンチを飛び出す。
続けて子供たちも。
泣きじゃくる楓の前、プロ山はファーストの男に駆け寄り――その顔を殴った。
ボールがこぼれる。
球場は騒然となる。
「走ってー! まだアウトはコールされとらーん!」
ベンチにいた他の女子選手が叫ぶと、楓は顔を上げる。
転がるボールを追うプロ山に伊藤がタックルする。子供たちが覆いかぶさる。
「走れーっ! ボールは抑えるから、ホームインしろーっ!」
上空にはもうすぐそこにケトゥスの姿が見える。
大人たちはただ呆然としている。
楓は控えの女子選手ふたりに並走されながらホームイン、審判のコールにより、一点が認められる。
プロ山に覆いかぶさっている子供たちが歓声を上げる。
脚にしがみついていた伊藤が立ち上がると、エースの里中が力なく倒れたプロ山の手からボールを奪い取り、そのボールを伊藤に手渡す。
子どもたちの雄叫びに沸き立つグラウンド。
だけどもう一分を待たずしてここにはケトゥスが激突する。
野球なんかやってる場合じゃない。
墜落の衝撃に供え、三銃姫も、宇宙の騎士も、機工兵も、楽器隊も離れていく。
僕は急いで虹の空間を開く。
「ここから逃げるんだ! 早く!」
だけど伊藤は、僕にボールを見せて笑った。
「これが、私たちの手でもぎ取った一点だ!――」
そして改めて、少年たちに向い、ボールを掲げる。
「――このボールには、私たちのすべてが詰まっている!」
「はいっ!」
大きな返事が返ってくる。
「これから何か辛いこと、苦しいことがあったときは、このボールを思い出せ!」
「はいっ!」
子供たちは涙を流している。
だけどそんなことより、ケトゥスが……!
そんな僕の心配などよそに、伊藤は弩声を上げる。
「目に焼き付けろおおおおおおおおおおっ!」
白球を大きく振りかぶる。
「これが!
魔球!
ハリケーンだあああああああああああああああああああああっ!」
伊藤の投げたボールは嵐をまとった光の一筋となってケトゥスを貫き、全長2キロのその巨体は、轟音を轟かせ、光となって消滅した。
第十一章 オリュンポスの神々
野球の試合を終えてファミレスでふたり、食事を取った。
「なして看護学校にしたと?」
伊藤にそう聞かれて、
――なんとなく。
そう答えれば良かったのかもしれない。
「芽郁」
「なん?」
うっかり下の名で呼んでしまったけど、戻すのも躊躇われて。
「芽郁より好きな子がおる」
芽衣はため息をひとつ吐いて椅子に座り直し、話の続きを促す。
「ショッピングモールでその子が倒れて、僕が応急処置して、その時から、僕にできることは何やろうかち考えるごつなって、僕は……自分の漫画の中で人ば助けようとしとうとに、目の前の人ば助けられんとは違うち思うて。医者の息子やけん、こまかときから親のしてきたことは見てきとうと。今から医者になるちゆうとは無理ばってん、それでなんもせんちゆうとはなかけん」
芽郁は目をそらして、少し早い瞬き、ハンカチで涙を抑えて、
「嘘よ。ぜったい嘘。私が迷わんでよかごつ、嘘ついとーとよ。こげん可愛か子ばふる男はおらんもん」
涙を抑えながら笑うので、僕もなんとなく笑った。同じように、涙を拭きながら。
「勇」
「なん?」
「私たち、お互いに片思いしとうたやんね。ずっと」
「うん」
「約束して。あの頃の私のことは、好いとうままでおるち」
「うん」
以前から、可愛らしいアイドルが失恋の歌を歌うのに違和感があった。その物語の裏に、どんな背景があるかも思い至らず、ただ、可愛いから失恋なんかするはずはないって、勝手に。
投稿漫画の締め切りは一ヶ月後、十月の末。
完成させたページは二十八。あと四ページ。メデューサの姉ふたりを撃破すれば終わる。
その後は、僕の身の回りのこと。看護学校に願書を出して、十二月の頭に試験。結果は一週間後。投稿漫画の結果の発表はおそらく、その少し後。
あとはもう走るだけ。でもそう思って自分の漫画を読み直してみると、自己嫌悪に陥る。描いた時は最高の展開だと思ったところや、自分でもうっかり感動してしまったところも、読み返してみると凡庸で、稚拙。
他方、四年制の大学は諦めたものの、専門学校の試験日は迫る。担任は問題ないと言ってくれるけど、何の準備もできていないし、三年に入ってからの僕のノートは漫画のアイデアメモと化している。
二週間後、韓国はソウル西方の海上に二体の巨大モンスターの影が確認される。
先日薬院へ現れた怪物、その前は久留米のショッピングモールで起きた惨劇、また同じ惨劇が繰り返させるのか、こんどは、韓国で。学校へ行くと朝からその話題で持ちきりだった。
ヘリからの映像が中継される。携帯で見る限りそれは人型。水上を浮遊している。その首がカメラを向くと次の瞬間、画像が赤く光り中継の画像が切れる。映像はスタジオへと戻り、「どうやら中継機器のトラブルのようです」と伝えるが、僕らの間では「撃墜された」という声を否定できるものはなかった。
四限目の授業を終える頃、二体の影は朝鮮半島を横切り釜山に達していた。
テレビの報道はスタジオから軍事専門家のコメントを流すばかりだが、ネットでは一般人が撮った各地からの映像がアップされる。大邸駅上空、旅客機をかすめる怪物の姿、同、釜山、ビルの向こう、あるいは頭上、さまざまなアングルで撮られた怪物の姿がアップされ、想像図が描かれる。それは僕がショッピングモールで見たメデューサの姿だった。いや、それよりもさらに外殻は厚く、黄金の翼を持ち、肩や背中には棘状の突起が見られる。
浜松より早期警戒管制機、宮崎より第三〇五飛行隊の離陸が伝えられ、日本各地から上空を通過する戦闘機の映像がアップされる。ニュースでは民間航空機の運行中止ばかりが伝えられるが、市民の手で自衛隊、米軍の動きが事細かに報告される。やがてネットでは、二体の怪物を総称してゴルゴン、それぞれの個体はメデューサの姉の名前であるステンノー、エウリュアレと呼ばるようになる。
昼休み、ステンノー先行、三分差でエウリュアレ、二体とも対馬上空を通過。校内放送が午後の授業の中止、交通機関停止のため下校の際は教員の指示を仰ぐようにと伝える。そしてそのアナウンス終了の頃に、壱岐島周辺海域にゴルゴン到達。博多方面から飛翔したコントラバスの一軍がこれと接触、先行する一体を足止めする。
攻撃を回避したエウリュアレ個体は速度を維持したまま長崎県松浦市へ、その北方海上で上空からの荷電粒子砲による砲撃を受ける。外気圏外にある宇宙戦艦からの連続した攻撃。湾内に立ち上がる高い水柱、それらの映像が市民のドローンに捉えられてネットにアップされる。荷電粒子砲の熱で海水は蒸気立つ。砲撃のうちの数発がエウリュアレにヒット。水柱に囲まれる蒸気の中に無数の赤い光線の閃きが見留められる。映像を切り替えると、エウリュアレと戦う人影が見える。すぐに新しい映像がアップされる。シバルリック・ゲイトのアテナが戦っている。蒸気でエウリュアレ本体の姿は見えないが、時折水しぶきを上げて巨大な砲撃が発せられている。別のチャンネルを見ていたグループが、コントラバス隊全機喪失を伝える。
「どこば目指しとるとやろか」
「ここに来たらどげんする」
生徒たちの顔は曇り、泣き出している者もいる。携帯に家族から電話が来る者、必死に家族にメッセージを打つ者、ただそこを歩き回るだけの者、ずっと祈りを捧げている者。
そこに教室のドアが激しく開く。
「おったおった」
矢口と篠宮。僕の姿を見留め、教室に入ってくる。
「いよいよクライマックスばい!」
「美術室ば要塞化したけん、そこで描きあげるばい! 漫画ば!」
促されるままに美術室へと移動、携帯を見ていると、シバルリック・ゲイトの砲撃が止み、アテナの離脱が伝えられる。
「どげんしたと?」
「Gペンの消耗ち思う」
要塞化された美術室へ。
机が並べられ、その周囲にはギリシャ神話を始め、美術、ミリタリー、哲学、歴史、様々な資料が積み上げられ、里崎先生はノートパソコンでゴルゴンの動きを追っている。
「二匹とも福岡に向かっとうち」
「東に向こうとるちことですか」
「わからんばって、米軍機のいま撃墜されたとこ。市街地に落ちたごたる」
「描こう、樺島! この物語の結末を!」
「そいがよか。あんたん腕にかかっとう。Gペンもインクも腐るごつあるけん!」
用意された椅子に座ると、両脇の机に矢口と篠宮が座る。
今川さんと錠崎さんがリタイア、このまま市街地に入られたら市民に犠牲が出る。
ネットの情報でゴルゴンの居場所はリアルタイムで推定できた。その映像もほぼリアルタイムで入ってくる。どうやらゴルゴンは、糸島で地上へと降りたらしい。ステンノーは糸島半島中程の九州大学付近、エウリュアレは西九州自動車道、
前原インターチェンジの東2キロ地点に降り立つ。
校舎からの映像、車載カメラからの映像、ネットには怪物の映像が次々とアップされるが、そのコメントの中に
――魏志倭人伝のルート?
――邪馬台国目指してるwww
の書き込みが見られる。
確かにかつての帯方郡、ソウル近辺から対馬、壱岐を経て、松浦、糸島へ……つまりゴルゴンたちの行き先は……!
――近畿逃げてー!
――邪馬台国は九州! 吉野ヶ里遺跡へようこそ!
ネットでは邪馬台国論争が始まっている!
「なにこの展開……」
「よかと! 勢いで描いたらそれでよかと!」
九州大学キャンパスには星乃望、三銃姫、西九州自動車道には小野田幸秀、深海機工兵団が立ち向かう。
九州大学、伊都キャンパス。センター一号館近辺。
馬に引かれた隊商が疾駆している。
隊商に紛れて大陸を彷徨う、カトレイシア・トライバルと銃の乙女たち、総勢十二人。
「すべての男子による火器の使用は、これを禁ずる」
大陸法に書かれた、実質的に『人』の意味として用いられてきた『男子』という言葉の解釈を変え、すべての男子に与えられた権利、架せられたあらゆる制限を捨て、禁じられた火器、魔法銃を武器に帝政に立ち向かう者たち。
キャンパスセンター前、石敷きの道に蹄鉄と車輪の音を響かせ、その音の止むところ、馬の背に上がる汗の蒸気の影から三つの小さな影が飛び出す。
「カトレイシアが退路を塞ぐから、ジュディは囮になって私の射程に引きずり出して」
「空を飛べるぜ、あいつら」
「真空弾を使うわ。空気がなければ、翼なんてただのお飾りでしょう?」
三人はキャンパスの奥にステンノーを確認、ロングバレルの銃を持ったバレッタ・アッシュコートはビルにチェーンを掛け屋上へと舞い上がる。同時に大型のリボルバーを携えたジュディ・ブラウンは物陰に隠れながらステンノーに接近、魔法銃を持ったカトレイシアは銃の乙女たちに指示を飛ばし、左右に展開しターゲットを囲む。
囮役、ジュディの合図で戦闘開始。物陰から不意に姿を見せたジュディが至近距離から銃撃を浴びせ、バレッタの射程に誘導する。ステンノーが飛び立とうとする刹那、それを取り囲む銃の乙女たちの魔法弾が炸裂。ステンノー周辺に渦巻く炎とともに真空状態を作り出す。ジュディは全力で炎を逃れ、マンホールへと飛び込む。ステンノーの羽ばたきはただ空を切る。その翼を狙ってバレッタの炸裂弾。翼の付け根に穴を穿つ。
バレッタが姿を隠すとともに銃の乙女たちの攻撃がやみ、空気が戻る。その空気を掴み、身体を浮かさんとするステンノーの翼が、その負荷に耐えられず折れる。
「バレッタ! とどめは!」
マンホールの穴からジュディが叫ぶ。
「もうこっちチームはインク切れ! あとは他にまかせていいわ!」
一方、西九州自動車道、エウリュアレ。
鷹取マリン工業株式会社、特殊運用部部長、田中幸治。
異星からの侵略に見舞われた二〇四二年、各国の軍が崩壊する中で、深海用作業スーツの開発に長けた鷹取マリン工業は私軍を構えて立ち上がった。別名を深海機工兵団。全高二十五メートルの主力機、気密式機工スーツうみゆりを始めとする数多くの軍事転用可能な重機を操る。
「粒子砲は?」
「最大出力下で8%の運動量低下が認められます」
「そんなものか……ショッピングモールのやつとは比較にならんな。出力は?」
「排出熱量と筋組織の稼働率からの推測で七八〇〇万馬力。ラプター三〇機相当です」
「となると問題は、こちらの出力か……」
「電源車十八台。いま準備できるのはこれですべてです」
「しょうがない。九州電力さんの電気を貸してもらおう」
「しかし、そんなことをしたら、また」
「かまわん、稟議書を上げろ」
大型の輸送ヘリから、気密式機工スーツうみゆりが高速道路に投下される。
対向車線に置かれたクレーンがうみゆりの背中に巨大な電源プラグを接続する。
その周辺には巨大なウインチを装備した重機が多数並べられている。
「稟議、上がりました!」
田中は稟議書に目を通し、部下へ戻す。
「承認」
田中の声を合図に、エウリュアレを取り囲むウインチ車から次々と銛が打ち出される。銛はエウリュアレに絡みつく。銛には電流が流れ、それが触れた部分は痙攣しているが、動きを制するには至らない。一台、もう一台、エウリュアレの抵抗により倒される中、うみゆりがローラーダッシュでエウリュアレに取り付く。エウリュアレの体高は推定二〇メートル。うみゆりの肩に取り付けられた高出力レーザーが暴れるエウリュアレの翼に照準を合わせ固定される。照射。まばゆい光が漏れる。電源車は唸りを上げる。
「出力
70%、周波数低下しています! このままではブラックアウトが発生します!」
「損害額想定は?」
「九州全域全電源喪失、推定七〇〇億円!」
「やれ。社長には私から電話しておく」
「ハッ! 出力最大! 焼き切れぇっ!」
エウリュアレはその熱に苦しみ、咆哮を上げ、目から閃光を放つ。気密式機工スーツうみゆりは大破、アンカー車はすべてなぎ倒されるが、その土埃が晴れたとき、そこに立つ怪物の両肩には翼がなかった。
かくして翼を失ったエウリュアレは天神方面へと逃走。
ネットの噂通り邪馬台国を目指しているとしたら、次は
奴国、
儺県、博多。このままでは福岡から博多まで目抜き通りが蹂躙される。
天神へ差し掛かる直前、枯葉チルがこれを捕捉。逃げ惑う人々をシャボン玉に包んで空へと舞い上げる。
空には無数のキャンディが描き出されている。
足元の地面が歪み、街はカラフルなポップカラーで塗り替えられ、西鉄の特急電車がロボットになって立ち上がる。顔も電車、腕も胴体も、脚も電車。体高四〇メートルはエウリュアレの倍、その体格差を活かして数発のパンチを食らわせるが、動きを読まれ、背後を取られる。
「西鉄ロボが危ない! 助けてラプリッティマーン!」
チルが叫ぶとどこからともなくラブリーでプリティなラプリッティマンが現れ、ラブリーなダンスを披露する。それを見た渡辺通りに取り残されていた群衆からハートが飛び出す。ラプリッティマンがフィニッシュを決めると、そのハートがエウリュアレに向かって打ち出されるが、全弾弾き返されてそのひとつがラプリッティマンに刺さる。
――ラプリッティマンは痛い痛い!
――それを見る群衆は悔しい悔しい!
「ラブリーフラフープー!」
今度はラプリッティマンがフラフープを回し始める。群衆もみなフラフープを回す。ラプリッティマンがフィニッシュを決めると、そのフラフープがエウリュアレに向かって打ち出されるが、全弾弾き返されてそのひとつがラプリッティマンに当たる。
――ラプリッティマンは痛い痛い!
――それを見る群衆は悔しい悔しい!
こうなったら、と、チルはクレーン付きのUFOを召喚、
「連れ去れ! 宇宙の果までーっ!」
チルが叫ぶと、UFOはラプリッティマンを連れ去る。
その一連の行動に気を取られ、油断したエウリュアレを西鉄ロボがぶん殴る。エウリュアレは天神ソラリアビルへと向かって飛ばされる。ソラリアビルには多くの市民が残っている。このままでは市民が危ない。
「ソラリアビル! 十六文キックだ!」
チルが命じるとソラリアビルは十六文キックを放ち、エウリュアレの体はどこまでも遠くへと飛んでいった。
平和中央公園。
里中とプロ山はキャッチボールをしている。
「よか肩しとう」
里中は視線を外して何も言わない。
そこからクイックモーションでボールを投げる。
ひょう、とおかしな声を出して、プロ山がボールを受けて、
「おまい、卑怯かぞ!」
と笑う。
遠くではゴルゴンが暴れている。
「逃げんでよかとか?」
「よか。僕が魔球ば投げるけん」
里中はあの日、伊藤が投げる魔球を見ていた。あのあとひとりで練習することがあったが、まだ自分で投げるには至っていなかった。
「女コーチは最近どげんしとう」
「あんたには教えん」
「好いとうたとやろ」
プロ山に図星を疲れた里中は、顔をうつむかせる。
「彼氏おって残念やったな」
「彼氏じゃなかち言うとった」
「じゃあ、まだチャンスはあるたい」
「ばってん、六こ下やもん。子どもとしか見られとらん」
「俺に挑んで来たやんか。大人でもそうはおらんぞ」
「それが人生で最大の失敗!」
そう言うと里中は渾身の力でプロ山にボールを投げる。
だけどボールは大きく逸れて、その大暴投をプロ山が追いかける。
プロ山が戻ると、里中は座り込んで泣いている。
「東京に行くち言いよらす」
プロ山は隣に腰を下ろす。
「俺、今年もう三十四ぞ」
里中の顔を見ることもなく、遠くを見たまま、プロ山は続ける。
「来年の春、宮崎の実家に帰る。最後によか思い出ばもろうて、踏ん切りのついた。アホんごたる。こげん歳まで自分の道ばみつけられんで。この十年後悔ばっかりしとうた。ばってん、最後に、最高の試合のできた」
その丸めた背中には、寂しさがあった。
「おまいが大人になって、自分の役割がはっきりできたとき、コーチもちゃんとした大人になっとう。そんときに、どげん顔ばして会うか考えたらよか。おまいはこれからやけん」
プロ山は立ち上がり、去りながら振り向いて、後ろ歩きしながらボールをよこす。そして踵を返して駅の方へと歩いていくその上空には、大牟田方面へと飛ばされていくエウリュアレの姿が見えた。
その頃、翼を失ったステンノーは九州大学を徘徊していた。
教室内に残された学生たちの悲鳴。そこに低い唸り声を轟かせて闇龍祐一の改造スカイライン、ジェイルブレイカーが飛び込んでくる。ジェイルブレイカーはステンノーに突進、その巨体を持ち上げたままエンジンを吹かす。ボンネットから突き出すスーパーチャージャーが翼の跡に食い込み、ステンノーはその巨体を引きずられる。
ステンノーは思わず大地に鉤爪を立て、ジェイルブレイカーの車体はスピンする。だが祐一はこれをハンドル操作で立て直すと、ステンノーの身体を引きずり、前輪を浮かせたまま学園通りへ躍り出る。ステアリングは浮いているが祐一にはそんなことは関係ない。
「ハンドルは、タイヤを動かすためのものじゃない。この車を操るためのものだ!」
肥後線の高架をくぐり、ラムジェットエンジンに点火、車体はぐんぐん加速して、前輪を浮かしたその車体は空へと舞い上がる。ステンノーを背負ったまま西九州自動車道へ上がり、その着地の衝撃でジェイルブレイカーは大破する。
しかし、そこは計算通り、そこに乗り捨てられた十八輪大型トラックに乗り換え、荷室の扉を開けたままバックで突進、ステンノーをその中に閉じ込める。
トラック無線に別チームの動向が入る。エウリュアレは有明海に向けて弾道軌道を飛翔中。そこで私立聖歌学園の生徒会が待ち受けているという。
――有明海……人のいない場所を決戦の場に選んだということか。
祐一がいる場所から、仲間たちがいる有明海まで約八〇キロ。高速には乗り捨てられた車が多数、それを荷室で暴れる怪物を乗せたまま走るのは至難の業。荷室が破壊されれば命の保証はない。もし道が寸断されていたら……それでも俺なら、とシフトレバーを見ると、なんとそれは十八段の超多段ギア。祐一にとってトップ以外のギアは迷い。このままでは走れない。
その時、トラック無線に聞き覚えのある声が入る。
「祐一、ヘリの映像で見てたぞ。有明海を目指すんだって?」
かつて関東ナンバーワンを競った
白樹矢洸の声だ。
「いまこっちで運送屋をやってる。有明海までの道、俺たちで掃除しておく。てめえはブレーキなんか踏まねえで、かっ飛ばせ」
「アイツ……」
祐一の口元に笑みが漏れる。
エンジンを吹かして、ギアをトップに叩き込む。ロー、セカンド、サード……そんなギアを使うのは車を知らない素人。祐一はバックとトップしか使ったことがない。十八輪トラックの鋼鉄の心臓に祐一の気迫が血流となって流れ込む。輝く巨体に稲妻が走り、その刺激が鋼の肉体を目覚めさせる。
「ガスが尽きたら俺の魂を喰らうがいい。地獄を見せてやる」
ロケットスタート。そこに転がる車両をなぎ払い、鉄の化け物が走り出す。
一方、福岡市動植物園。
飼育員のアール氏は市民からの電話を取る。
「動物が暴れて逃げ出したらどうするんだ。動物たちを即刻処分しろ」
しかし、そう言われたところでアール氏にはその権限もないし、何よりも動物への愛がある。それでも市民からの電話を受けてしまった以上、上司に報告しないわけにはいかない。やるせない気持ちを抑えて報告したところ、「では、いちばん危険な生き物から処分することにしよう」と上司は言った。
いちばん危険な生き物。さすがは上司だ、機転が利く。いちばん危険な生き物はライオンやゴリラではなく、意外な生き物だということをアール氏は知っている。もう一度電話が来たら、「もっとも危険な生き物から処分中です」と言えばいい。
しかし待てよ、とアール氏は思い当たる。この上司は案外馬鹿かもしれない。ライオンとかゴリラとか雰囲気で言い出す可能性がある。
アール氏は上司に提案する。
「あなたの考えには賛成しますが、ふたりの考える『いちばん危険な生き物』が違っているかもしれません。ふたりで『いちばん危険だと思う生き物』を紙に書いて、せーので見せっこしませんか?」
それは良い考えだ、と上司も賛成し、ふたりは紙に『いちばん危険だと思う生き物』を書いて、せーので見せあった。
アール氏の紙には『蚊』と書いてあった。蚊は伝染病を媒介し、学術的なデータでも最も人を殺す生き物だということが確定している。そう説明して、次に上司のメモを見ると『らいおん』と書かれている。案の定馬鹿だった。でもさっきの説明でさすがにわかっただろうと思っていると、
「ならば今からライオンが十頭入った檻と、蚊が十匹入った檻を用意するので、君はライオンの檻、私は蚊の檻に入って試してみよう」
と提案してくる。
蚊の危険性を熱弁したアール氏は、引くに引けなかった。
かくしてアール氏はライオンの檻に、上司は蚊の檻に入った。だが、死を覚悟したアール氏のもとに、動物漫画で有名な漫画家の思妤が現れた。
「大丈夫。ライオンは猫なので、みんな素直な子ばかりです」
そう言うと思妤はライオンをじゃらし始め、隣の檻を見ると上司がボコボコに蚊に刺されて死んでいた。
「来る」
私立聖歌学園生徒会長、長嶺菫の肌にはそれがわかった。
生徒会長以下、私立聖歌学園生徒全員、総勢一二〇〇人が、有明海にほど近い、筑後川とその支流、早津江川の間のデルタ地帯でエウリュアレの到着を待った。
「会長! この先の干潟には貴重な生態系が!」
「わかっている。ここで止める」
周りのたんぼは刈り入れの後、破壊されても園芸部員による原状回復は可能だ。
エウリュアレの軌道から落下地点が予測され、そこには近隣住民が飛ばした撮影用のドローンが舞う。そしてそのカメラが中継する映像を、数百……いや、数千万の瞳が見守っている。
落下してくる怪物の姿が目視にて確認されると、
「まずは俺が出よう」
剣道部主将、
豪剣剛が立ち上がる。
下段の構え。
面前をまっすぐに降りてくるエウリュアレを見据える。
人を畏怖させる異形の肉塊がその頭上を越えんとしたそのとき、豪剣の身体は舞う。
ゆうに三十メートルはあろうかという跳躍、勢いにしなる竹の刀を両の腕で叩きつけ、怪物を大地へと叩き落とす。落下したエウリュアレには、ラグビー部のタックル、弓道部の弓、科学部によるテスラコイル放電、次々と攻撃が加えられる。
手応えがある。押している。
「次は俺だ」
と、前に出たのはボクシング部主将、
鬼界カルデラ。
ゆうに十倍の上背があろうエウリュアレに正面からの打ち合いを挑む。正々堂々、私立聖歌学園の校訓に則った古式ゆかしい戦い。そして、個人戦の間のインターバルに、部員たちによる総攻撃。
中堅、ワンダーフォーゲル部主将、
小山田登。弱ったエウリュアレにハーケンを打ち込んで登る。そのあとに副将、忍術部頭領、
苦無忍、ここで帰宅部と三年生は家に帰って、大将、弓道部主将、鏑真弓と続く。
エウリュアレに打ち込まれたハーケンから濃碧色の体液が流れる。
勝てる。
そう思った次の瞬間、祐一の乗ったトラックが到着、その荷室を破壊してもう一体のゴルゴン、ステンノーが姿を現す。敵が二体となり、動揺する生徒たち。
「大丈夫! おちついて! まずはエウリュアレを!」
しかし、そこに隙が生まれた。
ステンノーはエウリュアレの身体を取り込み、ゴルゴン本来の姿へと変容、その姿が現れるや衝撃波が放たれ、小山田が頭上から振り落とされる。
そこに現れたのは下半身が馬、頭から多数のミミズを生やした男神。身体は更に巨大化し、その巨体が駆け回るだけで、生徒たちはなぎ倒される。
ゴルゴンはその右腕に青銅の剣を実体化させる。その攻撃が長嶺菫に振り下ろされようとしたとき、ゴルゴンの巨体を祐一のトラックが弾き飛ばす。手から離れ空を舞う巨大な剣。その下には長嶺生徒会長の姿が。運転席を飛び出した祐一が長嶺の身体を抱いて飛び退く。
「奴をあんな姿にしてしまったのは俺の責任だ。あんたを死なせるわけにはいかない」
「うぬぼれないで。この結果は、私たちの隙が招いたもの」
祐一と長嶺の視線に火花が散ると、そこにゴルゴンの巨大な拳が振り降ろされる。が、これは西鉄ロボが受ける。更にはそこにシバルリック・ゲイトのアテナ、輸送機で運ばれてきた気密式機工スーツうみゆり、コントラバス部隊、三銃姫の姿もある。
立ち上がったゴルゴンを、全員の力を合わせてなぎ倒す。
――が、二体合体して真の姿となったゴルゴンは、すぐに体勢を立て直す。
「Gペンは?」
「私のが一ケース残ってるけど、インクがもう……」
「じゃあもう、大技は無理」
「あとは体術でいくしかない。この身ひとつの勝負だ」
決意を新たにしてみるが、有効な手はない。起き上がったゴルゴンは、頭に生えたミミズを振るって無残にも彼らをなぎ倒していく。シバルリック・ゲイトのアテナが、気密式機工スーツうみゆりが、そして長嶺菫率いる生徒会の精鋭たちが次々に倒れていく。最後まで粘ったのは枯葉チルの西鉄ロボだったが、それが倒れたとき、ネットを介して見守る市民の胸に灯る火も、ひとつずつ消えていった。
ゴルゴンは両手に鞭を実体化させる。
終わった。
ネット越しに嘆息の声が聞こえる。
だけどその中の幾人かの胸に、幼い日に読んだ、ひとつの漫画が思い出された。どんなピンチでも、あきらめなかったイレブン……
「島田先生ならきっと……」
誰かがそうネットに書き込んだ次の瞬間、どこからか飛んできたサッカーボールが、ゴルゴンの頬を打つ。
「これは……」
島田巽先生の女子サッカー漫画『ラズベリーシュート』のボールが、長嶺の足元に転がる。
最終編となったユース編、その最後の試合で、東京の国立スタジアムから福岡ドームまで飛ばしたパスがあまりにも荒唐無稽だと笑われ幕を閉じた伝説の漫画。そのユース編のダブルヒロイン、
空音ベルノと、
涼白沙也加が降臨する。
師匠のキャラの登場に、そこに横たわる者たちの瞳に、希望の光が戻る。島田巽のアシスタント樺島裕美と、島田巽本人をモデルにしたとも言われるこのふたり。彼女たちがいれば勝てる。
センターサークルにボールを置いて、試合開始のホイッスルが鳴る。
ネット越しに見守る市民の心に、連載時の胸に踊る期待、ページを捲るときのあの喜びが蘇る。今週の島田はどんな感動を与えてくれるのか、百円玉を握りしめてコンビニのレジに走ったときの、あの胸の高鳴りが、ネットの網の目を励起させる。
パスを交換してゴルゴンへと攻め上がるベルノと沙也加。ゴルゴンの攻撃をフットワークで躱し、ベルノのセンタリング。
幾度も目にしたシチュエーション。県大会で、全国大会で、このセンタリングが幾度もミラクルを起こしてきた。そのボールが沙也加の足元に落ち、シュートを決める。
――が、このシュートはあまりにも凡庸。
ゴルゴンには何のダメージも与えていない。
そしてまた、希望は絶望へと変わる。
先生はもう現役を離れて久しいし、絵柄も古い。
――老い――
だれもがその二文字を胸に感じずにはいられなかった。
「なんだ、こんなもんか」
SNSには、そんな書き込みが投稿された。
「昔の漫画家だからな」
「今はもう通じないよ。しょせんは思い出補正ってやつでしょう」
だが、空音ベルノは動じない。
「今川くん。集中線。あなたの仕事でしょう」
その声は母のものだった。
アテナははっとして、今川功敬の顔になる。そこにゴルゴンの攻撃。両手に持った鞭が左右から襲う。一同はこれを躱して、次のシュートを狙う。
ボールは祐一から沙也加へ、ベルノへのセンタリング。
今川が手にしたGペンをかざすと、走るベルノと沙也加のまわりに集中線が現れる。
こんどはベルノが決める。
さっきよりボールの勢いが上がっている。
こぼれるボールを祐一が拾って、いや祐一のコスチュームを纏った八敷カズサが拾って、後方の小野田幸秀へ。そして八敷もその手に持ったGペンをかざす。
小野田を起点として次の攻撃。
シュートの瞬間、描き文字の『ドッ!』が見えた。
ダメージは遥かに上がっている。
「まだまだ」ベルノは呆れる。「こんなもんじゃないはずよ、私たちの実力は」
SNSの評価は揺れている。だけどそのなかに、「それでも僕は」の文字が見える。
次のシュート。ゴルゴンの足元がぐらつく。
「島田先生、あなたの漫画が大好きでした」
その書き込みが島田巽そのひとに届いたかどうかはわからない、でも――
次のシュート。ついに足元を崩し、ゴルゴンの巨体は倒れ、大地に手をつく。
「あなたに勇気づけられて、僕は学校へ行けるようになりました」
ベルノと沙也加の動きのすべて、振り向きひとつにさえ流線と効果音が見える。
「最終話を読んだあと、友だちと朝まで語り合いました」
宛先のない書き込みがSNSに溢れ始める。
「留学先で、先生のファンというひとと知り合いました」
「受験に失敗したとき、なんども先生の言葉を噛み締めました」
気がつくと、スタジアムには無数のファンが描かれ、旗を振り、歓声が広がっている。
「先生がいつも僕を導いてくれました。勇気をありがとうございます」
ベルノはゆっくりと、右の拳を挙げる。
「子どもが漫画を読めるようになりました。もちろん最初に読ませたのは先生の漫画です」
それは、勝利へのビクトリーサイン。
「拝啓、島田先生。小学校の頃ずっと、学校になんか行きたくないと思っていました。だけどある日、クラスメイトのひとりが先生の漫画が好きだと知って、その日からだと思います。私の世界がひらけたのは。あの頃は何も知らずに、登場人物のセリフを真似て、ごっこ遊びにふけっていただけでしたけど、いまあらためて、その言葉の深い意味を噛み締めています。去年、学校の先生になりました。いまでは先生から受け取った言葉を、生徒たちに伝えています」
高く突き上げられた拳は、場の緊張を一気に高める。
自信ではない。言葉を紡ぎ、人に伝える責任がそうさせるのだ。宛先のない言葉たちすべてに向けて、己の決意を示すために。
全員が息を呑む。
次の攻撃。小野田、錠崎と繋がったボールが最前線へ放り込まれる。ベルノが胸で落とし、沙也加へと戻すと、目のアップ、トラップする足、背中に敵をひきつけて、一瞬の隙を付くクイックモーション、そこに乱れ舞う極致なるエフェクト、最高の緊張と恍惚が沙也加の胸を満たし、ファイナルステージに立つベルノへとボールは送られる。師から弟子へ、熱き魂のアーチがふたりを繋ぐ。
このボールは人類の希望。
ドローンが中継するネットの映像に世界中の人たちが祈りを捧げる。
思い出を映すストップモーション。長い長い物語のすべてを力に変えて、フィニッシュは空音ベルノの秒速
80メートルのシュート、その熱き魂をゴルゴンへと叩き込む――
散れよインク!
折れろよペン!
敵を貫くのは力でも技でもない、その魂だ!
割れろよ机! この筆圧で!
その衝撃は地球を貫通してブラジルに断層を築くがいい!
空に舞い踊るベタフラッシュは未知の新元素を生み出し、カミオカンデに捉えられるがいい!
時を閉じ込めた、永遠の瞬間。力に満ちた静寂の中に、勝利の予感が広がっていく。
――が、ボールの勢いはみるみる消えていく。
ネットで見守る世界中の人の心に動揺が生まれる。
「インクが切れた……」
まさかこんな時に……
これでもう万策尽きたかに見えたそのとき、
「長嶺様! われわれ私立聖歌学園化学部、紙に描かれたインクを液化還元する装置を開発しました!」
化学部の部長が生徒会長に――いや、生徒会漫画で名を馳せて今や大スターとなった森エミルに進言し、小さなインク瓶を差し出す。
「でかしたぞ、化学部!」
「待て! 何をする気だ!」
小野田が振り返り、エミルに糺す。
「私は私にできることを。あとはおまかせします、小野田先輩」
森エミルがインク瓶に触れると、その身体はどんどんインクに還元されていく。
「それじゃあ、小野田さん! あとはよろしくですー」
こんどはチルが!
「リード、がんばってください」
八敷が!
「負けないでくださいね」
錠崎さん!
レジェンドたちが次々とインクに還元され、ボールに勢いが戻る。集中線に圧されてぐいぐいとゴルゴンの肉体に食い込んでいく。最後は小野田自身もインクとなって姿を消して、残っているのはベルノと沙也加とボールのみ。
だがそこに残されたボールは、今やレジェンドとなった島田ファミリー全員の力を合わせた絶対無二の一球。まばゆき炎を噴いてゴルゴンの分厚い装甲を突き破る。
「貫けええええええええええええええええええええええええええっ!」
勝利を確信したベルノの全身全霊を込めた雄叫び。ベルノのキックの圧力は凄まじかったが、それを受けるゴルゴンの力も極限に達する。両者拮抗する中――
だけど私は思いました。
私はこの勝利に、どのくらい貢献できただろう。
この勝利はみんなの勝利。
でも、私はいつか、ひとりぼっちで負ける。
レジェンドチームにいたから勝てただけ、
実力はたいしたことなかった、と笑われて。
だったらこの勝利を、だれも手にすることなく
いま、負けてしまったほうが、ずっといい。
――気がつくとベルノの身体はボールごと吹き飛ばされていた。
残されたのはついに沙也加ひとり。
ベルノは? ベルノの姿は?
すぐにインターネット解析班が動く。
押し返された時の速度や角度から、ベルノが月にいることが導かれる。
「月に
!?」
もうおしまいだ。月にいたのでは何も出来ない。
一台だけ巻き込まれて、月へと飛ばされたドローンがベルノの姿を探した――
たった四年のうちに、故郷の街は変わっていました。
私が知らない時間が流れて、
友だちは私が知らないカフェでお茶を飲んでいました。
東京で過ごした四年、必死に埋めてきたパズルのピースは、
すべて崩れて、空白になりました。
だれよりも幸せになってやると、息巻いて始めた新生活も、
いつかガラガラと、音を立てて、崩れて。
私が欲しかったのは、栄光。
費やしたのは、時間。
得られたものは、何もない。
何も。
でも、本当にそうでしょうか。
まだ胸の中に燃え残る思いがあります。
暖めたまま、伝えそこねた思いがあります。
決して綺麗な思いではありません。
恨み持つ悪霊の胸の内のように、渦巻く怒りと、嫉妬と、憎しみと。
私は、愚かでした。
自らの闇を恐れるばかりで、
その中の自分に、気が付かなかった。
虚空は果てしなき闇。
だけど私は、そこに光る、小さな星。
私にはまだ、できることがある。
だれかがこの小さな光を、見つけてくれると信じて。
――すぐにドローンは、月面に立つベルノの姿を捉える。
ベルノは月の大地にボールをセットする。
腰を落とし、気を練り上げ、
「いーーなーーずーーまーー……」
ボールの五キロ手前からの助走。
「はーーりーーけーーん……」
全身を撓らせ、鋼の脚は多段ロケットで加速するかのようにマッハを超える。
「キーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーック!」
ベルノが蹴り出したボールは月を飛び出し、地球へと爆進する。
「轟け、白球! おまえは、私が愛した主人公たちの全てだ!」
ボールにはみんなの魂が宿っていた。
ベルノの想いを受け取ったボールは、どんどん速度を増して行く。
その速度は亜光速、光の速さの99・999999999……%まで加速、相対性理論が示すローレンツ収縮により、地球到達までの一・三秒でボール表面では二十一年と半年の月日が流れる。
ほぼ光速にまで加速したボールがいま、地球でパスを待つ沙也加へと迫る。
そのエネルギー量は八十二恒河沙ジュール。
沙也加はグラウンドに立ち、ベルノのパスを信じて天の一点を見つめる。
「この生命を賭けてでも、トラップする」
ほぼ光速のボールは、その姿を捉えた次の瞬間には接触する。チャンスは一瞬。しかも仮にトラップできたとしても、八十二恒河沙ジュールのエネルギーが開放されれば、その衝撃波で地殻は破壊され、地殻津波が地球を三百周する。
しかし、沙也加の決意に迷いはない。
この虚空に現れる一点の光、ベルノのボールを必ずや見つける。
次の瞬間、ほぼ光速のボールが現れ、沙也加は全身のバネでそれをトラップ、亜光速のスピードを抑え、胸の前に浮かせる。
だがそこに、予想された衝撃波はない。
水を打ったように静かだ。
いったいボールの運動エネルギーはどこに……?
「ベルノが届けてくれた力……一滴たりとも……無駄にするかああああああっ!」
沙也加は全身でその力を飲み込んでいた。受け止めた運動エネルギーをわずかも漏らすことなく自らの肉体に吸収し、八十二恒河沙ジュールの運動エネルギーは八十二恒河沙度の熱量となり、それを飲み込んだ沙也加の身体はいま、太陽質量を超えた。
その太陽の力は胸から腹を伝い、脚へと降りていく。
それにあわせてボールはゆっくりと、柔らかく、静かにその高度を下げていく。
狙いを定め、沙也加はその右足を振り抜く。光速で振り抜かれた足がボールを捉えると、その運動エネルギーのすべてがボールに乗り移る。ボールは再び光速へ、いや光速を越えて加速される。宇宙の歴史ではじめて、サッカーボールがチェレンコフ光を放った。もしこの世界に神がいたら言うだろう。こんな物理現象は想定外だと。島田巽とその弟子たちの想いを込めたボールは宇宙の法則も常識も切り裂きゴルゴンの心臓へ突き刺さる。
そこに発した音は、原稿用紙いっぱいに描いても描ききれないほどの『ドッ!』。
それはタクラマカン砂漠一面に描いた『ドッ!』を縦に百万枚、横にも百万枚並べて作った『ドッ!』の文字を、百万回同時に鳴らしたほどの巨大な音となって鳴り響いた。
そしてゴルゴンの身体は光となって、素粒子レベルでこの宇宙から消滅する。
しかし、島田の全盛期を知る弟子たちは語った。その巨大な『ドッ!』の音ですら、島田巽がデビュー作のひとコマに描いた『ドッ!』に比べれば蚊の鳴き声のようなものだった、と。
かくして、ゴルゴンは討ち取られ、僕の漫画は完成した。
すべてを出し尽くした。
これが僕のすべてだ。
第十二章 僕たちは大人になる
朝起きると、芽郁からメッセージが届いていた。
「鳥は初めて見た動くものを、親だと信じると言うけど、そうじゃない。
鳥は初めて見た動くものを、自分だと信じるんだよ。
今まで、ありがとう」
たぶんこれが、芽郁の別れの挨拶なんだと思う。
小学校の頃からずっと続いてきた何かが、そこで終わった。
投稿した漫画は、努力賞だった。僕はその発表された号を母の部屋で読んだ。母と同じように。レビュワーの評価のひとつひとつを、繰り返し、胸に刻むように。
高校を卒業すると矢口は音大を目指すためにと、予備校へ通った。父親に頭を下げてピアノの家庭教師を頼んだと、笑いながら話した。
篠宮は九州大学の機械航空工学科へ。漫画を描いている中で僕は、加古江と名乗る未来から来た男に会ったけど、その男の言うことが事実かどうか僕にはわからない。それどころか、この一年で起きたことのどれほどが現実だったのかすらわからない。
高校を出た後、三年間、僕は大川の母の実家から看護学校へ通った。
大川の家には毎月五万円を入れた。家賃と光熱費、生活費諸々と考えると決して十分な金額ではないと思ったけども、祖父母が恐縮して、それ以上は受けとってもらえなかった。母の遺言には背くかもしれない。でも、母の残したお金を、母が望んだ通り、僕のために使うのだから。
学校で看護の知識や手技を学ぶと、それがみるみる自分の血肉になっていくことが実感できた。だれがどんなところで事故に合い、病気になり、そのとき何が起きるのか。怪我や病気のことばかりではなく、社会の構造や、いま起きていること。多くのことを考えたし、考えることは僕の力になった。
漫画も描き続けた。何作か投稿して、編集の人から電話が来たこともあった。
看護学校の三年が終わりに近づく頃、芽郁が東京から戻ってきた。
僕の母のように、夢破れて戻ってきたのだとしたらと連絡を取ると、諏訪野町に借りた小さなスタジオを、待ち合わせにと指定された。スタジオを訪ねるとその上空、空を見て立つ芽郁の姿があった。その視線の先には、あの日、彼女が晴らした青い空があった。
ここで子どもたちにダンスを教える。もうスタッフにも声をかけてある。
そう聞いて、僕は嬉しくなった。
僕はまだ就職を決めきれない。
三年の学生生活を終えて、僕の手元にはまだ三百万円が残っていた。
これなら、上京しようと思えば上京できるし、あるいは芽郁のように地元で何か始めてもいい。
三年間漫画を投稿して、今は担当の編集者もいる。ネームを送って相談したりもしている。上京すればアシスタントの口も紹介できると言ってもらえてるし、糊口は凌げる。僕の夢はまだこれから。
そう思っていた矢先、その十二月、祖父が他界する。
風呂を洗っている最中の心不全だった。
祖父の葬儀はしめやかに行われた。
若い頃にローンで建て替えた家の借金が、あと五年残っている。
「戒名やら要らんばい、お金はかけんでっちゃよかよ」
と、祖母は言ったけども、戒名は見栄のためにつけるんじゃない。お寺に納めるお金でお寺は立派になって、それが地域の文化を守っていく。僕たちは地域の中で支え合っている。祖父が地に足をつけてきたことの証、残されたものが先立ったものへ交わせる数少ない約束のひとつだからと、僕の貯金から二百万円を支出した。
母さん、ごめんなさい。
遺言を破りました。
祖父と祖母のために、遺産を使ってしまいました。
手元の貯金はもうすぐ百万円を割り込む。
祖母は涙を流して感謝を述べるけど、いいんだ、そういうことは。
それから一週間ほどして、先生から電話がある。
春から大きな連載が始まるのでアシスタントを探しているとのことだった。
先生が僕のことを思って電話してくれたんだ。樺島裕美へのはなむけにと。そうでもなければわざわざ僕のような素人を九州から呼び寄せる理由なんかない。それに、祖母を置いて上京することはできない。
「僕はこちらで看護の仕事を探します」
迷いはあったけども、その電話でもう、僕は自分の思いを断ち切った。
母がどんな気持ちで夢を諦めたのか知りたい、その轍を踏みたくない、ずっと思ってきたけど、おそらく今のような、こんな気持で。
篠宮、ごめん。
僕はお前の魂を受け入れてやることなんかできない。
午後、市役所に陳情へ。
この三年僕は、地域の活性化のためにバス路線の拡充や、一人暮らしのお年寄りの支援を訴えて、仲間たちとたびたび市役所を訪れていた。
反応は鈍い。
その後ファミレスで、西鉄さんはどうやろか、バスが無理やったら買い出しの支援は頼めんやろうか、いろんな話が出てくる。とりあえずひとつでも前に進めたい。
家に帰ると、玄関先で祖母が深々と頭を下げる。
「もうよかよ、勇」
「どげんしたと、具合が悪かと?」
祖母はその場に座り、畳に頭をつける。
「東京に行ってください。これ以上頼ったら、裕美とノリさんがおるとこに行かれんけん」
涙声で訴える。
「裕美はこまかときから世話してやっとるけん、歳ば取ったら世話してもろうたっちゃ、悪かち思わんやったろうばってん、勇に世話してもろうたら、返しようのなか。世話になるばっかしで、なんもできんとがどんだけしゅるしかかわかんね。裕美の夢ば叶えてやれんで、あんたの夢まで摘まな生きていけんなら、もう生きろごつなかよ」
その苦しさは、僕にも伝わってくる。
「そげんこつ言うたっちゃ、家族やけん。ばあちゃんば残して、東京に行ったっちゃ、後悔するだけやもん」
加古江さんならきっと、ここからスーパーまで、直線でトンネルを作れる。
僕にもできたはずなのに、玄関先で何度手を動かしても、虹のトンネルは現れない。
それさえあれば、祖母は安全にスーパーへ通えるのに、現実の僕は無力だ。
出先から学校へと向かう道すがら、チャリを止めて僕を呼び止める男がいる。
ラグビー部の富松。
酒屋のデリバリーチャリ。
「なんばしとうと、こげんとこで」
「これから学校。この通り、まっすぐ行ったとこの」
「ああ、あそこ。看護学校に通うとったとね。樺島は絵の仕事につくち思うとった」
「そっちは、バイト?」
「これ、実家の店やけん、正社員たい。ちょっとお茶でもしていかん? 学校は忙しかと?」
もう学校は卒業した。今日は事務手続きに顔を出すだけ。富松は店に電話して、戻りが遅れるとの連絡を入れる。
近くのファミレス。
母のこと、自分のこと、祖父母のことなど。
「うちの店は三潴やけん、大川までやったらデリバリーでくるばい。今日はバイクが出払っとうけん、チャリで周りよるばってん」
「でも、酒だけやろう?」
「そいがいま、酒だけじゃのうて、肉とか野菜とかも届けらるるごつ、いくつかの店で連携して話しば進めとうたい。で、酒はみんな馬鹿んごつ飲むけんよかばってん、豆腐とか野菜とかじゃ元が取れんと。それでいま、市にかけおうて、補助金ば出してもらうごつしとっと」
その場で担当を聞き出すと、「紹介してやるけん」と富松とともに、市役所の三潴支所へと向かうことに。担当に話を聞いてみるが、市をまたぐことは想定していない、大川は範囲に含まれないと告げられる。
「ごめんね、期待持たせて。俺たちも補助金が頼りやけん。市がいかんち言うたら、無視するわけいかんたい」
「ありがとう。でも、僕は諦めん。これから大川の市役所に行く。いつも話ば聞いてもろうとる人のおるけん、相談してみる」
「しょんなかねえ」
「よかよ、富松くんは。仕事があるとやろ」
「なんば言いよると、これも仕事よ」
久留米市役所三潴支所の玄関前に、僕と富松のチャリを並べる。
目の前には、矢口とはじめて大川を目指した日に通った道。
先行してペダルを漕ぎ出す僕を、ラグビーで鍛えた富松の足が追いかける。
あの日と同じように、車も少なく走りやすい田舎道が続き、県道七一〇号線に接続するあたりで道は狭まり、背中からトラックが追い越していく。
自転車を想定していない田舎道。大型車に押し出されたら田んぼ直行の細い道で、後ろから、前から、車がすれ違う。急ぐ道でもないのに、気持ちが止まらない。まだ午前中の雲雀の鳴く道を、改造スカイラインに追い越されてペダルを漕いだ。あの日僕らの足を止めた国道の信号が、目の前で青に変わる。
祐一のスカイラインを追い越す。
全速力で僕を追う元ラグビー部の富松。
母を病から救うことはできなかった。
でも、今の僕なら――母と、母と同じ苦しみと、同じ寂しさを湛える人へ、差し伸べることのできなかった手を、差し伸べることができる。
大川の市役所についた頃に、太陽は正中する。
二月の終わり。
肌を切る風の中、シャツは湿り、額に汗が流れる。
ボトルホルダーからボトルを取って、イオン飲料を喉に流し込む。
富松に渡すと、「しゃっす」と受けとって、日差しに目を細めながら、喉を潤す。
息を整えて、富松が口を開く。
「顔だけつないでもろうたら、あとは俺たちでやるけん、樺島くんは上京して」
僕はシャツに籠もった汗を襟口から追い出し、まだ弾む息に言葉を詰まらせる。
「地元んこつは地元にまかせてよかよ。樺島くんは俺たちば楽しませて。それが樺島くんの仕事やけん。俺たちも樺島くんが不安になるごたる仕事はせんよ」
――ありがとう、富松くん。
僕のその声は震えて、最後まで出ることはなかった。
「十年後、二十年後、ぜったいにこの町はよか町になっとう。地元に残った俺たちが責任持つよ。もしそれが信じられんなら、ここに残らんね。よかよ、残って。ばってん、そうじゃなかったら、もし俺たちば信じるなら、樺島くんは東京に行って、漫画ば描いて」
額に汗が流れ、首に巻いていたタオルで拭い、富松は言った。
樺島くんの漫画ば読んで、ゼウスの金の雨ちゃなんやろかち言うたやんね。
覚えとう?
そう言えば、そんな話をした気がする。
その意味がわかったごたっ気がする。
ああ。
うん。僕にもようやく、わかった気がする。
それは――
いま僕たちが流しているもの。
僕たちは大人になる。
口を開けて、餌を求めて、
詰め込まれる餌の、それが何かもわからないまま。
あとがき
この小説には、現実を超えたものがいろいろと出てきますが、基本的には『自伝的小説』にあたると思います。人生で漫画家を目指したことが3度ほどありまして、その最初が高校を卒業する前後のことでした。このお話にもある通り、美術の授業で8ページの漫画の課題が出たのがきっかけで、そのとき描いたものは、友人をモデルにしたキャラが、ちょうど授業で習った酒天童子の怨霊と戦うというギャグ漫画でした。
振り返れば少年時代より、ノートの端っこによく絵を描いていたものですが、所詮は落書きでしかありませんでした。中学に入るとまわりは宇宙戦艦ヤマトや宇宙空母ブルーノア、更に高校へと進むと機動戦士ガンダムなど精緻なものを描くようになって、とても僕などと思って絵を描くこともなくなっていきました。ところがその高校2年の三学期の授業で描いた漫画が、友人に妙に受けてしまって、もしかして僕には才能なんてものがあるのではないかしらと考えるようになってしまったのです。まあ、漫画家を目指されたみなさんなら、きっと通られた道かと思います。このお話の主人公と同じで、絵は完全な素人、それでもたったひとつ見つかった取り柄らしい取り柄だったので、とりあえず人並みの画力を手に入れたいとアニメの専門学校に通いはじめ、そこから人生が変わっていきました。
よく夢に見たものです。アニメの学校に通いながら漫画家としてデビューして、実家の自分の部屋をアトリエにして友達にアシスタントに来てもらって連載を続ける……
しかし、アニメの学校に入ってみると周りには自分より上手いのがゴロゴロいて、最初の夢はその頃にしぼんでいきました。
それが1度め。いったん2度めは飛ばして、3度めは、
10年勤めたスクウェアというゲーム会社を辞めるとき、
30代なかばの頃でした。『就職口が見つからなかったら、しょうがないので漫画を描こう』と思っていました。なんと不遜なことでしょう。普通は、漫画家を目指して、それがダメだったら就職、だと思うのです。だけど僕はその不遜さと無謀さがあったからこそここまでやってこれたのだと思います。ゲームという世界で勝負して鍛えたのだ、漫画では勝負ができないと言うのなら、それはゲームを愛する皆様にも失礼ではないか。と、本気で思っていました。が、このときもまた、たまたまゲームの働き口があったので、ここでも漫画家にはならず終いでした。
で、さきほどすっ飛ばした2度めなのですが、これは
20歳で上京して、1年間アニメーターをやってそれを辞めた頃のことでした。アニメを辞めた理由はいろいろとありますが、自分では通用しないという絶望感を抱えていたことだけは間違いありません。動画を描いて月7万円ほどしか稼げなくて、映画も見れないし、資料も買えない、テレビを見る暇もないという苦境の中、失望してアニメを辞めて、一ヶ月ほど福岡へ帰り、友達の家に居候していました。九州へ帰るのなら実家に戻れば良いのにと思われるかもしれませんが、実家に戻ったら、それこそ本気で夢破れたことを思い知るじゃないですか。それで、博多駅の隣、吉塚駅近くの友人宅に身を寄せていたのですが、そこに、当時ヤングサンデーで連載を始めたアニメ学校時代の友人、G氏が訪ねてきたのです。曰く、「漫画の仕上げを手伝ってほしい」と。それがきっかけで、ベタ塗りやトーン貼りを3日ほどお手伝いさせてもらって、そこで始めてちゃんとした漫画の作業に触れました。
その時に、漫画を投稿するように進められたんです。
彼はニュースで流れる『客にウンコを投げつけるゴリラ』を見ながら、「ゴリラを主人公にした漫画を描きなよ」と言うのですが、「ゴリラはちょっと……」「どんな動物が好き?」「象かな」「じゃあ、ぞうさんで」と、主人公が決まり、続いて流れてきた『下関のフグの競り』のニュースを見て『フグが好物』ということが決まりました。
なんじゃそりゃ? というような設定ではありますが、ジャングルに住んでるぞうさんが、フグが好物となると、まあ物語は連想でとんとんと浮かびまして、描き上げた
32ページの漫画は週刊少年ジャンプのホップ・ステップ賞で佳作などをいただきました。
さすがは俺、と思いましたね。
鼻高々でした。
それで、意気揚々と編集部に行ったのですが、そこで高くそびえ立った鼻をへし折られてしまいました。編集部内では何人かの編集の人が
10点満点で評価していたのですが、それによると僕の評価は、副編集長は3点、編集長に至ってはただ『?』とだけ書いてありました。ここちょっと、よく覚えておいてくださいね。3点と『?』ですよ。ただ、ゲスト審査員の新沢基栄先生だけが
10点満点という高評価をくれたおかげで、なんとか佳作に引っかかって、その後もめげずに執筆できましたが、滑り出しはこんなものでした。このときの審査員が新沢先生じゃなかったら、僕の人生は変わっていました。本当に偶然ってすごいものだと思うし、自分が今の仕事してられるのも、偶然が重なった結果でしかないんだって思います。
で、ここからが面白いのです。
アニメーターをやっていたのはたった1年ですが、その間にけっこう知り合いができていたんですね。そのひとたちが、僕の佳作のニュースを聞いて「あ、こいつ、漫画も描くんだ」とばかりに連絡を取ってきて、「俺の友達がアシスタントを探してる」だの「同人誌を作ってるんでなにか描いてくれ」だの「担当は誰になった? ○○? 新人じゃねえか、俺が編集長にかけあって変えさせてやる」だのという話がまわりに流れてくるようになりました。そうやって僕は漫画のアシスタントという職をみつけはしたのですが、同じ頃、ゲームにはまってしまいまして、結局はゲームの方へ行ってしまいました。だけど、世の中ってきっかけひとつで変わるものなんだな、と、つくづく思ったものです。アシスタントをさせていただいた、たかつき勇先生、ともながひでき先生、有賀照人先生には、この場を借りて感謝の気持ちを表したいと思いまます。
ちなみに今回の小説の主人公の名前の『勇』は、劇中にあるとおり、細井平洲という人の言葉から取ったのですが、これは同時に久留米にいた儒学者で平洲の門下生である樺島石梁の通称、勇七にもかかっているし、G氏のペンネームの『たかつき勇』、ともながひでき先生の『ストライカー!勇気』の主人公の名前にも通じているという、因縁の深い名前です。
あとそれから、この作品の中のオリュンポス
12柱のモチーフとなったひとたちのことを書き添えさせてください。
アニメーターになるべく上京した頃、実はとてもとても幸運なことに、上京してすぐ、小山高生というアジア最大の脚本家と知り合っていたのです。作中に出てくる島田先生は、小山先生がモチーフになっており、とくにキャナルシティや大川実家での加古江さんとのやりとりは小山先生の口調をイメージしながら書きました。作中の島田先生と同じように、数多くの脚本家を育てた人です。
知り合ってすぐ、先生はシナリオ教室を始めて、当時アニメーターだった僕はお金も時間もないし、そこには通えなかったものですが、カバン持ちとして同行していた友人を経由して、どんな課題が出た、どんな作品にどんな評価がついていた、というお話を聞いておりました。門前の小僧の実家の子犬くらいの位置にはいたのだと、野良犬仲間のうちではよく話させていただいています。
それと最後の紹介になりますが、僕が脚本家の中で最も敬愛する故・島田満先生。作中の島田巽の名前のモデルとなったひとです。直接会ったことはありませんが、ツイッターで幾度か言葉を交わさせていただきました。本当に子どもたちのことを思い、友情や思いやりを強く訴え、またそれを自ら信じている作家さんでした。この小説は島田先生に捧げたものといっても過言ではありません。ラストのゴルゴンとの戦いは島田先生の作風を意識して書かせていただきました。島田満先生の思いは、責任をもって次の世代に引き継がねばならないと思っています。
上京後はほんとうに、いろんな人に支えられてきたと思います。今はもう、その恩を返すべく、次の世代の人たちを育てる立場にいるはずなのですが、いまだ自分のことで手一杯という状況が続いています。
でもなんというか、今回のこの作品には、僕が諸先生方から受け継いできたすべてを込めたつもりです。僕にとっては、この小さな作品が、作中でベルノが月から蹴った白球なのです。亜光速までの球速はさすがに出ませんが、無事に地球まで届くようにと、祈りを込めてリリースさせて頂いています。
最後になりましたが、このたびは作品を手に取っていただき、ありがとうございました。これからもまだまだ、作品を書いていきたいと思いますので、よろしくおねがいします。
©sayonaraoyasumi novels
この作品の著作権は井上信行が有しています。著作権者の許可なく複製、配布、改変することを禁じます。
This work is copyright 2023 Nobuyuki Inoue. It may not be reproduced, distributed, or modified without permission of the copyright holder.
| 著者 |
井上信行 |
| 表紙 |
ともながひでき |
| 出版 |
さよならおやすみかぶしきがいしゃ |
| 出版日 |
2021年 8月 25日 |
| 使用ツール |
でんでんコンバーター, VSCode, PowerPoint, PhotoShop |
| HOME PAGE |
https://sonovels.com/ |