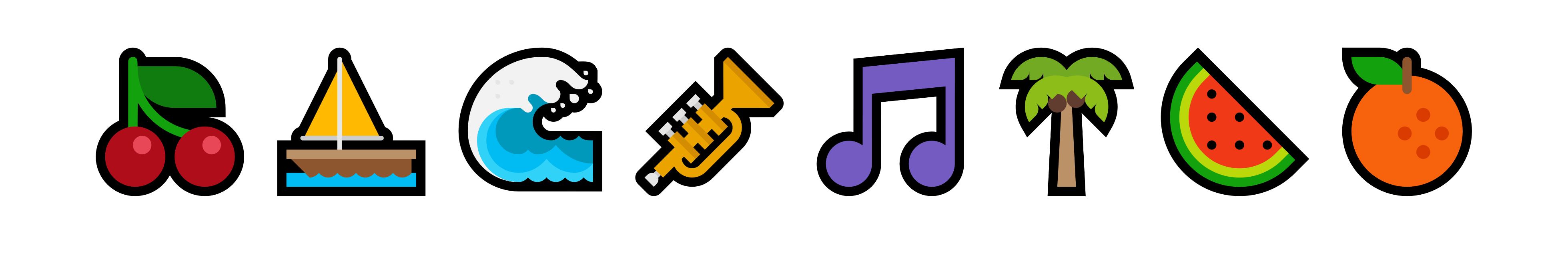- 第一部・クロスロード伝説
- 一・冒険者の酒場がある通学路
- 二・生活向上委員会還元教団
- 三・勇者ギルデンスターン
- 四・冒険の門出
- 五・はじめてのダンジョン
- 六・ヤマカガシ
- 七・オープンキャンパス
- 八・水天宮裏河童伝説
- 九・憧れの竹下さんに捧げる冒険
- 第二部・河童に魂を売った男
- 十・失われた古代史
- 十一・祇園山古墳
- 十二・ワールドシフト
- 十三・メロンソーダ
- 十四・遠い世界に
- 十五・賢者・ローゼンクランツ
- 十六・ファタ・モルガーナ
- 十七・水槽検体
- 十八・大魔王降臨
- 十九・側近ディストメア
- 二十・大魔王城決戦
- 第三部・オクターブユニゾン
- 二十一・憧れの古澤くんに捧げる冒険
- ボーナストラック
- カーテンコール
- あとがき
第一部・クロスロード伝説
一・冒険者の酒場がある通学路
高校へ通う道の途中に、冒険者の酒場があった。 ガソリンスタンドの五叉路を斜めに入って二つ目の信号、落雷で折れた欅が目印の小さな雑居ビルの一階。その小さなカフェに世界各地から冒険者が集まって、仲間を募っている。彼らは酒場を拠点に、どこかの洞窟の奥に潜んでいる魔王を倒しに行くらしい。 だけどその魔王がどこにいるのか。 冒険者たちに聞いても、 「それがまだ、わからないんだ」 「はっきりしているのは、このままではこの世界は魔王の手中に落ちてしまうということだけ」 のような答えしか返ってこなかった。 友人の田村は、 「魔王なんかいねえっしょ」 と笑って言い放ったが、友人の僕からみてもそれは雑魚町人のセリフに思えた。 僕の名は、古澤幹夫。 澤の字は難しいほうの字だけど、郵便物は古沢でも届く。 というか、友人から届く年賀状はほぼ古沢で、古澤で届くのはほぼ父方の親戚筋からの年賀状。 『古澤』って書かれると大切にされてる気がするって、姉に言ったことがあるけど、返ってきた返事は「どっちもダサい」だった。 「どーーーーせ」 と、うんざりした口調で 「結婚したら名字なんか変わるから」 とか言い出すので、 「じゃあ、ジョナサンあたりに嫁げば」 と、言ってやったら、 「ジョナサンはファーストネームじゃない?」 と、返ってきた。 「じゃあデニーズにしとけよ」 「おまえがロイヤルホストに婿入りしろ」 みたいな言い合いが始まって、それから姉は僕のことをデイリーヤマザキ・幹夫と呼ぶようになった。僕は根っからのセブンイレブンっ子だったけど、デイリーヤマザキも悪くないと思った。つまりはまあ、古澤って名字は僕的にもしっくり来ていなかった。 ちなみに高校二年。趣味はギター。軽音楽部。 バンドの真似事もやって、ギターも弾けるし、高校に入ったらほぼ自動的に彼女ができるんじゃないかと思っていたけど、いまのところ彼女はいない。 同じクラスの竹下さんのことが気になってはいるけど、でもさ。つきあうとしてもさ。 「上京してバンドマンになるから、いっしょに阿佐ヶ谷のアパートに住もう!」 みたいには言いにくいわけでさ。 でも、まあ。それでも悶々と考えたりはする。僕の演奏の動画の再生回数がすごいことになって、金なんかもうがっぽがっぽで、駅前の藤井フミヤや鳩山邦夫が所有してるって噂のマンションで暮らすようになって、竹下さんが赤ん坊を抱いて僕の帰りを待ってるような未来を……考えたりはするんだ。 高校の二年ともなるともう進路の話ばっかりで、親とも担任ともよくその話をするんだけども、先生―― 「どうした。進路は決まったか?」 と、ことあるごとに聞いてくる。 「それなんですけど、九州の大学を出てグラミー賞を取ったミュージシャンっていないんですよ」 「まあ、そうだろうな」 「逆にいうと、九州の大学に行ったら、その時点でグラミー賞は諦めるって意味なんですよ」 「そこは同意できんが」 「僕まだ高二なんですよ」 「わかっとるよ」 「高二で夢を諦めたくない」 と、このやりとりで、進路指導に関しては先手を取ってやったぞって気持ちでいたのだけども、 「じゃあ、夢に向かって何をやるべきか、先生に教えてくれないか?」 と返されて言葉を失った。 「古澤幹夫という人間は、何をすべきだと思う?」 古澤幹夫が、何をすべきか。 だけどグラミー賞を獲る男がそんなことで悩んでもしょうがない。 「僕はただ、生きていけたらいいんです」 僕の夢。ただ生きていく。 グラミー賞? わざわざ努力して獲るものでもない。 いつかクロスロードで出会った悪魔に魂を売って、超絶技巧を手に入れるんだ。 「カート・コバーンになりたいんですよ」 知らない名前を出して相手をひるませるのが教師の専売特許だと思ったら大間違いだ。僕の生活圏には、先生の知らないことが腐るほどある。 「そうか」 そうだ。 「寿司は好きか?」 寿司? はあ? 「好きです」 「毎日食ってるか?」 「食ってないです」 「おまえの親父さん、毎日働いて、息子に好きな食い物さえ食わしてやれんことをどう思う?」 なんなんだ、この話。 父親のことはそんなに好きではなかったけども、担任から父親の稼ぎを揶揄されるってのは、めちゃくちゃ不愉快なもんだな。 「寿司、食いたいよな」 ああ、うん。食いたいよなって聞かれりゃあ、それは。 「畳屋なんだよな、親父さん」 「畳がなんか関係ありますか?」 それから先生は、金を稼ぐのはたいへんなんだぞ、生きていくだけでもみんな大変な苦労をしているんだと続けて、僕はうっかりしんみりと聞いてしまった。 食いたいさ。そりゃあ。日本人だもの。お寿司だもの。 「だからグラミー賞を獲って……」 「妄想のグラミー賞で食えるのは、妄想の寿司だけだぞ」 そう言って先生は、妄想の寿司をつまんで口に放り込む。 俺も寿司を食いてぇ。 駅前の藤井フミヤや鳩山邦夫が持ってるマンションに住んで、竹下さんが僕の赤ん坊をあやしてる部屋で、サビの効いた寿司を食いてぇ。 もともと洋楽からだと思う。 Aメロ・Bメロ・サビという構成で二回繰り返して、最後にもう一回サビを歌うの。 音楽の田中先生の話では、昔は三回繰り返していたらしく、だいたいの歌謡曲には三番があったらしい。 「なんで二回半になっちゃったんですかね?」 と、聞いたら、 「Aメロ・Bメロなんかなんども聞いたってしょうがないじゃない」 と、買ってきたばかりの楽譜をペラペラめくりながら教えてくれた。 「僕の人生ってまだAメロあたりですよね」 ――そんな高校生活、どんな意味があるんですかね――という思いを込めたんだけども、田中先生はすべてわかってますとばかりに溜息を吐き出すと、 「エリック・サティのヴェクサシオンって曲は知ってる?」 と尋ねてきた。 音楽を志してますもの。エリック・サティは知らないわけじゃない。 だけど、ヴェクサシオンに関しては―― 「いえ、知りません」 「同じフレーズを八四〇回繰り返すの」 はあ? ぜんぶ演奏しようとすると丸二四時間かかるとかなんとか、買ってきたばかりの楽譜を反対からめくりながら教えてくれた。 先生はその――ヴァース・ブリッジ・コーラスで構成されていた洋楽が、最近ではその形は失われてきているし、前奏もどんどん短くなっていると口先にこぼして、ばらばらばらっと、ページをめくった。 そう言えば、ギザギザハートの子守唄ってABABABABだ。 まるで永遠に続く学生生活。 「暗譜した」 先生は楽譜を閉じて、ピアノの前に座り、音を奏でた。 「古澤くんも」 そう促されて、スーパーのBGMでしか聞いたことのない曲の、どこがギターパートだかもわからない曲の演奏に加わる。 「どう弾けばいいかわからない」 「グラミー賞獲るんでしょう? カート・コバーンだったらどう弾くかやってみて」 ギター叩き壊せばいいのかな。二・生活向上委員会還元教団
そしてこの高二の、わりと人生の重要な時期に友人の田村が失恋する。 漫画とか読む限りにおいて、高校生は失恋しがちだと思う。 社会人はひととおりの恋をして失恋するけど、高校生はアタックして砕ける。更にこれが田村の場合、アタックする前に砕けた。 「わかんないそれ。いったいなんでよ」 「岡本と一緒に下校してた」 「それだけ?」 このレベルの話になるともう失恋と呼べるかどうかさえわからなかったが―― 「ところで、相手はだれ?」 「寺島さん」 ――寺島さんの受ける大学と、岡本が受ける大学が同じで、ふたりは小学校からずっと一緒で、漫画でいうと達也と南の関係で云々、と。 でもやっぱり、 「それは失恋じゃないよ」 と、少しは慰めようとして言ってやったのに、あいつが生活向上委員会還元教団に入信したのはその直後だった。 だれよりも早く失恋情報を嗅ぎつけて勧誘に来る、別名、失恋教団。例の冒険者の酒場にもたくさんの僧侶を派遣する老舗の新興宗教。 「略して生向委」 「俺たちは『還元教』って略すことが多いかな」 それからの田村は、 「おまえ、勇者になれよ。魔王倒しに行こうぜ」 と、僕に絡むようになった。 あの「魔王なんかいねえっしょ」と言ってた田村が、である。 田村は親友でもあったし、バイトの金が入るといつも不二家のパフェをおごってくれた。見逃したアニメはお互いにテープを貸しあった仲で、 「教団に入る必要はないから、冒険者の酒場にだけは登録しておこうよ」 と、言われると、断る理由もなかった。 「でも、高校生が酒場って、法的にどうなの?」 「17時までは酒も出してないし、普通のカフェと変わらないよ」 「プロントみたいなもんか」 「プロントもそうなの?」 だけど受験とかいろいろ考えると、やっぱ、ないなぁって感じ。そもそも喫茶店なんて、ドトールしか入ったことがない。 「冒険とか行って、怪我したらどうするの」 「それを俺が治癒するんだよ」 要らないよ、おまえの治癒なんて。 それでまあ、冒険の話は適当にいなしてたんだけども、パフェ食べながら「還元教団のパーティがあるから」とか言われて、「食い物で釣るなんて卑怯だぞ」と、冗談めかして言ったものの、だんだん誤魔化しきれなくもなっていた。 田村の目からは『今日断ったら、俺たちの仲はもう最後だからな』っていう覚悟が読み取れて、僕としてもまあ、田村が完全にあっちの世界に行ってしまうのもなんだったんで、パーティにだけは行くことにした。 これでもし、僕があっち方面に行くことになったら、いつか聞かれると思うんだ。 「古澤さんがグラミーを諦めて、魔王退治の道へ入ったきっかけはなんですか?」 って。 だって親友がさあ、絶交を厭わずって覚悟で誘ってきて、断ったらたぶん田村はもう、向こうの世界に行ったまま縁が切れちゃうわけだろう? そりゃあ、考えるよ。 還元教団の支部は市役所通りにあったけど、パーティは市街地の会場を貸し切って開かれていた。 支部長さんの挨拶があって、どの冒険に何人のメンバーを派遣した、どのクエストでどんな成果を治めたって発表があって、 「魔王を倒す日まで、冒険者を支えていきましょう!」 という締めの言葉のあとに、教団歌を歌った。 ああー わーれらー かんげんーきょーうだーん 会場にはフリーのドリンクが用意されていて、驚いたのは、生徒会長に立候補して破れた吉田くんや、図書委員の藤島さんもいたことで、知らない一面を見たっていうか、向こうも僕の顔をまじまじと見ながら、学校では聞いたことのない声のトーンで話しかけてきた。 彼らは親の代からの教団員で、受験が終わったら冒険者の酒場に登録するんだって、握手なんか求められて、 「いや、僕はまだグラミー賞を諦めたわけでは」 と、言うと、 「僕だって総理の椅子を諦めてはいない」 「私がノーベル文学賞を獲るのは運命なの」 と、わけのわからない返事が返ってきて、総じて僕ら気持ちのいい馬鹿だなって思った。 その還元教団の支部長の戸田さんは、かつて不死身の魔王を倒した勇者硯葉さんとともに戦ったひと。 総理大臣を目指す吉田くんが、「あの話、お願いしますよ」と水を向けると、 「いやその魔王がさあ、たいして強くないのよ」 と、照れ笑いしながら話してくれた。 「でも不死身なんですよね? なんども生き返るんでしょう?」 「そう。でも攻撃受けると、痛いことは痛いらしいのよ」 「あ、痛いんだ」 「そう、三回くらい殺したときかな? こいつ、けっこう痛がってるなーって気がついて、次に生き返るまでの間に、勇者硯葉さんと『つぎ、どんな痛がらせ方しようか』って話してたもん」 「ひどいw」 「それで、どうなったんですか? 不死身の魔王」 「生き返るたびに、だんだんしおらしくなってって……」 「そうなんだw」 「最初は、 『ふははははは! なんどやられようが、俺様は不死身だ!』 って言ってたのが、五回目くらいで、 『なんで無駄に殺すんですか』 って」 「敬語になってる!」 「――死なないって言ってるのに、ひどいじゃないですかー! あなたらがやってることはただ相手を痛がらせるだけで、なんの解決にもなってないんですよー!? ――って」 「魔王www」 「で、それでどうしたんですか?」 「硯葉さんが 『では、生き返らねば良いのだぐわははは!』 って言ってグサリ」 「遊んでますよね、完璧に」 「生き返る前に足を切り離して隠したり、いろいろやったよ」 「ひどいw」 「――僕の足、どこに隠したんですか! ――ってw」 戸田さんを囲んだ不死身の魔王談義は盛り上がっていたけど、僕は不安になった。 その様子を気取った戸田さん。 「どうしました? あまり好きじゃなかったかな、こういう話は」 不意にこちらへと集まる目線に射られて、思わず―― 「もしかして、勇者側も斬られたら痛いんですか?」 と聞くと、まわりはキョトンとした顔を僕に見せた。 「そりゃそうでしょう」 いや、そりゃそうでしょうじゃなくて。 「あの、戦いの最中、治癒魔法とか蘇生魔法とかで蘇るじゃないですか? あれって、ダメージ受けたときって、痛いんですか?」 わずかに間をおいて、図書委員が吹き出すと、吉田くんも目を細める。 「なに言ってんだおまえ、剣で切られるんだぞ!? 痛いに決まってんだろう!」 その日いちばん盛り上がったのは、この話だった。 「僕らヒーラーだから、あんまり攻撃は受けないけど、戦士とかたいへんだよね」 という戸田さんの言葉に、 「ラスボス戦で戦士が体験する痛みは、タンスのカドに足の小指をぶつけたときの三千回ぶんって統計がありますよね」 図書委員の藤島さんが笑いながら添えた。 笑い話にすることなのかな。 「古澤くんの冒険の物語も、今日からはじまりだね」 ――って吉田くん。 いや、勝手に始めないで。 「これで僧侶と吟遊詩人が揃った」 と、翌日の始業前に田村に言われて、「なぜ僕が」と問い返すべきところを、「吟遊詩人ってなに?」という質問が先に飛び出してしまった。 「あ、いや、まだ僕が冒険するとは限らないんだけど」 あわてて取り繕ったものの、田村は、 「おっ、フラグだね」 とあしらって、残るメンツをクラスの中から見繕い始めた。 「やっぱ、戦士ほしいよな。物理アタッカー」 クラスを見渡すと、ラグビー部の富松、柔道部の坂井と、それっぽい連中はいるにはいるのだが、 「そういうのを紹介してくれるのが冒険者の酒場じゃないの?」 と、尋ねると、 「酒場で集めると金がかかるから」 と、にべもない返事が返ってきた。 ちなみに、にべもないなんて言葉はいま生まれてはじめて使った。まさか使うとも思ってなかったので意味もよく知らない。おそらくこのタイミングで使う言葉だと思う。 「ていうか吟遊詩人って、何するの?」 「それはおまえ、あれだよ。冒険の盛り上げ役。歌って踊って、敵にダメージを与える」 「歌って踊ってダメージを受ける敵ってなに?」 「わかんねw」 そうか。仮に僕がラグビー部の富松、柔道部の坂井、凡人田村とで冒険に出たとしたら、僕の歌で盛り上がった富松と坂井が敵に襲いかかって、傷ついたふたりを田村が癒やすんだな。 その光景は少しおかしくもあったけど、でも―― 「戦士、竹下さんじゃだめかな」 あ、しまった。いまのはうっかり口走っただけでぇ―― 「おっ、いいねぇ」 いや、よくなくてぇ―― 「あの、でもほら、ラスボス戦で体験する痛みって、タンスに足の小指をぶつけたときの三千回ぶんだっけ?」 「らしいね」 いや、らしいねじゃなくてぇ。 「竹下さんをそんな目に合わせるわけにいかないよ」 「じゃあ、どうするよ?」 「まぁ、坂井でいいよ」 「うひょ!」 うひょってなんだよ。 「攻撃を受けた坂井の柔道着がはだけて胸があらわに!」 って、田村ぁ。おまえさぁ。三・勇者ギルデンスターン
で、その日の放課後、冒険者の酒場に行ったんだ、田村と。 「扉を開けると、むさくるしい男たちがこっちをギロリと睨んできてぇ」 「睨んできてぇ」 「おそるおそるカウンターに近づくとぉ」 「近づくとぉ」 ――見ない顔だね。何を飲むんだい。 ――ミルクを……。 「……って言うと、後ろでポーカーしてたやつが大笑いするんだよ」 なんてことを話しながら店に入ったけど、店の雰囲気は野中町のカードショップと大差なかった。カードショップというか、システムは漫画喫茶かな。 入り口にカウンターがあって、学生証を見せて、五百円払うと、『ジョブカード』をもらえる。 田村はヒーラーなので青いカード、僕は吟遊詩人でサポート役なので緑色のカードを首から下げて、飲み物はフリードリンク。僕たちのカードにはでかでかと『1』と書かれている。 「レベル1かい。新人だね」 すぐに口ひげの怪しい男が話しかけてくる。 「おまえたち、ギルドには入ってんのか?」 「いえ、ぼくたちは今日はじめてここに……」 そう答えるとすぐに男はギルドに誘ってきた。 ギルド……ゲームではよく聞く言葉だけど、いまいちピンと来てなかったのだけど、その男が実に端的に説明してくれた。 「ギルドってのは、ラインのグループだ」 「ラインのグループ……」 とりあえず誘われるままにギルドに入ると、年齢不詳の冒険者たちのチャットがずらっと並んでいた。 ――◯◯討伐メンバー募集! だの、 ――◯◯地方に◯◯出現! だの、リアルだかファンタジーだかわからない文字が流れる。 苦笑いを浮かべて画面をスクロールさせていると、「まあ、じきに慣れるよ」とひげの男は口角を釣り上げてみせて、僕らが加入したことをチャットで流した。 僕らも急いで挨拶文を打ち込むと、 ――ようこそ! 肉桂文鳥団へ! の文字とスタンプが踊る。 「にくけい文鳥団?」 「ギルド名だ」 「なんでにくけい文鳥団?」 「リーダーが文鳥好きだから」 冒険者が文鳥好きって。 「ちなみに肉桂と書いて『シナモン』な」 さいですか。 「――こいつがリーダーの『たゆたう』だ」 と、指し示してくれたリーダーのプロフの写真はシナモン文鳥だった。 結局その日はひげのおっさんにギルドに誘われただけで終わった。 おっさんはギルデンスターンと名乗っただけで、本名はわからなかった。 その帰り道。 「ライン来た」 ギルデンスターンからだった。 ――受験を第一に考えるんだぞ。冒険はそのあとだ。 「そのあとだって」 「偉そうに言える立場か?」 「俺ら、このおっさんと知り合うために五百円払ったん?」 「それな」 翌日。 ――レベル1冒険者にぴったりのクエストがあるので、週末にどうですか? とのラインが来る。 テンションが普通の人だ。昨日の口調はキャラだったんだ。 まあ、それはともかく。田村が飛び上がって喜んだのは言うまでもない。 ちょうど昼休みで、目の前には竹下さんがいて、キュリオスな瞳でこちらを見ている。 誘いたい。 漫画だったら向こうから、「どうしたの?」って声をかけてくるシチュエーション。だけど現実はそうじゃない。たぶん僕はこうやって竹下さんに憧れたまま学生時代を終えて、卒業して、就職して、グラミー賞を獲って死んでいくんだと思う。 ――なんて夢想していたら、 「どうしたの?」 と、竹下さんから聞いてきた。 漫画かよ。 盛り上がった田村はギルデーンスターンさんとの冒険のことを、ツバを飛ばして説明しはじめるが、竹下さんは引いている。 だけど、告白するならいまがチャンス! 告白? いやいや、告白じゃないよな、誘うんだよ。とか思ってたら―― 「その冒険、私も行っていい?」 竹下さんから告白来たーっ! いやいやいや、告白じゃないだろ。落ち着け。落ち着け俺。 「念のためギルデンスターンさんに聞いてみる」 あ、余計なことを田村。 田村の落ち着いた応対に、竹下さんは少し顔を曇らせる。 「もしだめだったら、私はべつにいいから」 下唇をきゅっとあげて、眉をしかめる。 可愛い。 加納のやつはブスだとか言ってたけど、天使じゃん。 もしだめだったらって、だめなわけがない。ここで無用なものはむしろギルデンスターンだ。僕と田村と竹下さん、そこにラグビー部の富松か柔道部の坂井を誘えば四人パーティの出来上がりじゃないか。ヒゲのおっさんに頼る必要がどこにある。 と、熱弁をふるいたい気持ちはやまやま、去年の春に同じクラスになってから憧れ続けたひとと初めてかわす言葉だ。そうそうがっついたセリフは吐けなくて―― だめなものか。 カンペ風に画用紙に書いて、目つきだけ雄弁にキラキラさせていると、 「ギルデンスターンさん、OKだって!」 田村がスマホを見せてきた。 「よっしゃあっ!」 とっさに出たセリフがこれだ。 我ながらびっくりというか、竹下さんがちょっと引いている。 「ジョブは何やりたい? って聞いてる。ギルデンスターンさん、8ジョブカンストしてて、なんでも出せるって」 カンストってのはカウンターストップ、レベルが上限の99になってるってこと。ジョブってのは冒険中の役割みたいなもので、8ジョブもカンストしてるってのは、働きもせずに冒険ばっかりやってる人間のクズってことだ。 慌てて解説を入れると、 「ジョブって何があるの?」 と、竹下さん。 「ええっと、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、吟遊詩人、侍、賢者……」 「私、戦士やりたい!」 竹下さんが跳ねるようにして手を挙げる。 竹下さんが跳ねる。竹下さん……ああ……。 あ、でも、戦士は……痛いよ…… そう言わなきゃいけないんだろうけど、やっと竹下さんが乗ってきたんだ。正式にジョブを決めるときに言えばいいか。 このところ洋楽しか聴いていなかった。 洋楽のCDは包装も雑で、近くのリズムレコードだとずいぶん安く売ってたから、高校生の僕でもジャケ買いできた。 uruseiyatsura や that dog Alice in Chains。メジャーどこだと NIRVANA だとか Red Hot Chili Peppers sonic youth NOFX……。 邦楽では Hi-Standard Blanky Jet City あたりなら聴ける。 つまりどういうことかと言うと、クラスで話があうやつがいなかった。 でも話があったからって、クラスの連中と Lemonheads や Dinosour Jr. の話をしたいかと言えば御免こうむるわけで、竹下さんにだって、ずっと僕の空想の中の彼女でいてほしいって気持ちはなきにしもあらずだった。 土曜日。明日の冒険の準備を進めていると竹下さんからの電話。 生まれてはじめてと言ってもいいクラスの女子からの電話。姉にからかわれたらどうしようなんて思って握りしめた受話器から、鈴の声の音。 曰く―― 「ごめんなさい」 ――って。 「お父さんが、素性のはっきりしないひとと冒険に行っちゃだめだって」 「あ、うん」 会話の中身が漏れないように、受話器を耳に押し当てた。 「そうだね」 僕もあのおっさんのことはギルデンスターンってハンドル名しかしらない。 「古澤くんも気をつけたほうがいいよ」 「うん」 途切れそうになる言葉を、彼女は受話器に添えた掌に受ける。 「ちゃんとした冒険者は、国家資格があって登録されてるはずだから、聞いてみたほうがいいって」 「うん」 「ごめんね、約束したのに」 「いや、べつに、僕もそんなに本気じゃなかったし」 竹下さんへの思いは本気だけど、冒険なんてべつに。そんなものどうだっていいから、気にしないで。声に出せずにまた、胸の中だけで紡いだ。 「よかった」 「そうだね」 よかった―― それって、どういう意味だろう。 僕が本気じゃないことが――よかった――? いくつか言葉を拾いそこねて、 「だから、ごめんね」 やっと届いた彼女の言葉。 未来の僕は、今日のことをどう振り返るのだろう。 長い物語の最初のエピソードとして? あるいは、憧れたひとと交わした最初で最後の電話として? 「映画館とか石橋文化センターとかだったら、お父さんもだめだって言わないと思う」 「うん」四・冒険の門出
Vの字斬りを日本でメジャーにしたのは、勇者山本さんだった。 一九七七年、魔王デスボルケイノ戦で山本さんがフィニッシュに使った技がVの字斬りであったため、日本国内では長らく『山本斬り』と呼ばれてきたが、この技はもともとはデンマーク王家に仕える騎士団が発祥で、そちらでは単に『Vの字斬り』とだけ呼ばれていた。勇者山本の名とともに注目さたのは事実だったが、世界的には『Vの字斬り』が主流、やがて日本でもそれで定着した。そしてそのVの字斬りが重宝されたのは、実戦的な対モンスター戦よりはむしろ、模擬戦、対人戦闘においてであった。 上から斬り下ろし、一歩詰めて下から上へと斬り返すという動きが相手の虚を突き、八〇年代初頭の御前試合の半分はこの技でフィニッシュされた。 ところがこれも八◯年代なかばになると、流れが変わる。 剣を斬り返すという性格上、剣速は期待できず、北米勇者大会においてオーストラリア出身のウィリアム・ハドソンがすれ違いざまの一撃でこれを破ってからは、大会におけるVの字斬りの使用者は一気に数を減らしていった。 ところが歴史とは面白いもので、デスボルケイノ撃破十年を祝う武道大会の席で、山本の弟子、勇者八重樫さんが旋風斬りの構えからVの字斬りへとつなぐという神技で優勝杯を手にした。旋風斬りに対してアクセル・スラッシュ――その後、ウィリアム・ハドソンのフォロワーによって命名されたすれ違い斬り――は分が悪かった。旋風斬りで左右への変化を狙われれば対応のしようがない。半歩下がっての上段の構えが定石とされたが、攻めを中心に組み立てる上位の戦いにおいて、そのわずか半歩の組み立ての遅れは時として勝敗を分けた。 勇者八重樫さんが用いた大旋風キャンセルVの字斬りは、師の名を関して『真・山本斬り』と呼ばれ、この語は世界標準語となった。 いま、経済学者がV字回復などの折れ線グラフを見て、 「ヤマモトですねぇ」 と解説するのは、これが所以である。 学校の勉強はさっぱりだったが、勇者伝説は面白かった。 僕が知りたいのはポンディシェリ連邦直轄領の話やシャンデルナゴルの戦いの話ではなく、勇者山本さん、勇者八重樫さんの話だった。 そんな話に耳を傾けた冒険者のたまり場。田村とふたり、レンタル装備を借りた。 レンタル衣装といえば、七五三のときが多分そうだった。次に衣装を借りるのは結婚式になるだろうと考えると、初めての冒険ってのも人生の節目なのかもしれない。 「みんなレンタルなのかな?」 田村が低い声でつぶやいて店内を見渡す。 時計はまだ午前。酒場にいる冒険者は僕らの他には三人しかいない。 「みんな首から冒険者カードをぶら下げてるし、僕らと一緒だよ」 と、自分のカードをぶらぶらさせて見せた。 「ギルデンスターンもそうだけどさ、上級者はカードなんかぶら下げてないよ」 言われて気がついたのか、田村は「あっ」と言葉を詰まらせた。 着替えを終えて、冒険者の酒場の前でギルデンスターンを待った。 折れた街路樹に、黄色と黒のテープが巻かれている。 「ギルデンスターンがどれほどの冒険者か知らんけど、ただのくたびれたおっさんだよ」 メイン回復役をまかされる田村は、その緊張をほぐすようにギルデンスターンの陰口をならべた。朽ちかけた幹は足を掛けると、ぽろぽろと崩れる。 僕はと言えば、竹下さんからお断りの電話をもらって、緊張はどこかに吹っ飛んでいた。七五三、結婚式に並ぶ重要な通過儀礼だってのに。 「あのおっさんのGパン、ダサいし」 無精髭でやぼったいパーカーをかぶったギルデンスターンを待ちながら、僕のなかには変な喪失感があった。そのせいか―― 「コロンの匂いきついし」 コロン。いい匂い。竹下さん。 「モテなさそう」 モテる。女子。竹下さん。 何を聞いても3ステップ以内に竹下さんにつながった。 「タバコ臭いし」 タバコ。大人の階段。竹下さん。 やがて僕らの前に停車したのは、赤いアルファロメオだった。 雑誌の広告のようにサングラスを決めたギルデンスターンが、助手席の窓を開けて乗れよと促す。その席には髪の長い女の人の姿があった。 僕はとっさに―― 真っ赤なスポーツカーに乗ったってダサいものはダサいんだよ―― と、胸の中に用意したけど、田村のニヤけて固まった表情を見ると唇を動かせなかった。 「ハルノです。春夏秋冬の春と、乃木坂の乃」 長髪の女の人は名乗った。 真っ黒な髪。4つ上の大学生の従兄弟と髪の長さは同じだけど、あっちは伸ばしただけ、こっちはなんか、綺麗。同じ髪とは思えない艶と膨らみがある。春乃という名前が本名なのかキャラ名なのかわからなかった。 田村もなぜか、「ウィレムです」とキャラ名で挨拶したので、キャラ名をきめてなかった僕はウケを取りに行くしかなかった。 「デイリーヤマザキ古澤です」 「えっ?」と、表情が固まる春乃さん。 そこに田村が、 「ちなみに俺は、ウィレム・サンチェーン。さんちゃんと呼んでくれ」 と被せてくるものだから、笑いは田村に持っていかれた。 「よろしく、さんちゃん」 春乃さんは改めて挨拶してくれてるけど、田村はそれで良いのだろうか。 「じゃあさんちゃん、回復よろ」 「おまえはウィレムと呼べ、タタミ屋」 「なんでよ」 「デイリーヤマザキのことはデイリーでいい?」 いいけど―― 「ああ、はい」 まあ、いいや。 アルファロメオのエンジン音は、父の乗る日産セレナとは違った。 地面の振動も足元の近くに感じる。 小頭町公園の角を曲がって、バイパスへ出ると、日産セレナより、ふだんのチャリよりも低い視点で街の景色が流れ去る。 「パーラー櫛原の向こうにダンジョンがある」 「パーラー櫛原?」 「むかしはトップレーンってボーリング場だった。いまはパチンコ屋だけどな」 いや、パーラー櫛原のことはわかる。 でもその向こうにダンジョンなんてあったかなと思って。 フロントガラスの向こうは空ばかりで、座り直して覗いてようやく見慣れた建物が見えた。 「ここ、姉ちゃんが結婚式挙げたとこ」 田村が指差すと、ギルデンスターンもちらりとそのビルを見上げる。 ――要らないなぁ、その情報。 「ここと夫さんの地元の長崎と、二回披露宴やった」 ――うん、要らないよ、その情報。 この街は変わった。 小学校のころと比べても、あちこちが新しくなっている。 ずっとここに住んでいる大人たちは、もっと大きな変化を過ごして来たんだと思う。 「不思議だと思わんか?」 ハンドルを掌でするすると滑らせて、ギルデンスターンが聞いてくる。 「パチンコ屋とダンジョンとが隣接してんだぞ。なんか不思議だよな」 うん。いままでダンジョンのことなんて目に入ってなかったけど。 「ダンジョンって、たくさんあるんですか?」 「そりゃあもう。パチンコ屋の向こう、市民会館裏、リバーサイドホテル横……奇妙な景色だよ」 アルファロメオがウインカーを上げる。 「パチンコ屋なんかないほうがしっくりくる」 パチンコ屋の駐車場に車を停めて、武器を持って外へ出ると、『ダンジョン利用者の駐車は禁止します』の貼り紙があった。 僕が指差すと、 「魔王の手下が貼ったものだ。惑わされるな」 と、ギルデンスターンはその貼り紙を破って捨てた。 脳内のインタビュアーが僕にマイクを向ける。 ――古澤さんが、冒険を始められて、『これはやばいなぁ』、と感じた最初のシチュエーションって、どんなときですか? どんなときって、いまだよ。いま。いまいま。いま。 田村も戸惑っている。 春乃さんは左手に松明を持って、右手の剣を素振りしている。 大丈夫なのか、僕ら。 「貼り紙破って怒られませんか?」 おそるおそる尋ねる田村に、 「理屈もなく怒るとしたら、自分が悪党だと自己紹介しているようなもんだ」 と言い放ち、ずんずん進んでいくギルデンスターン。&春乃さん。 いやいや、怒るでしょう。僕らパチンコ屋の敷地に勝手に車を停めて、こともあろうか貼り紙を破いて、しかも武器まで携帯している。 田村もそそくさと彼らのあとに続いて目配せするので、僕だけ残るわけにもいかず、犯行現場から逃げるようにしてダンジョンの入口へと走った。 ダンジョンの入り口は――なんというか――ダンジョンの入り口だった。 ――古澤さんがはじめてダンジョンに行かれた時の第一印象は? ――ダンジョンの入り口がなんか、ダンジョンの入口っぽいなぁ、って。 ――具体的には? ――ダンジョン来たー。これかー。みたいな。 こんもりと丘のようなものが盛り上がって、そこにぽっかりと穴が空いている。 僕はその、なんていうかな。 冒険者のことについて深く考えたことってなかったわけ。 酒場に集まって冒険に行って、敵を倒したりしてるんだなぁくらいに思ってた。 だけどよくよく考えたら、これってなんなの? 田村がはまっちゃった宗教にしても、隣んちの婆さんが毎日お経をあげてるアレだってことは知ってたけど、中身は知らなかったわけじゃん。 だけどここまで来てそれを聞くのも今更じゃない? だから、 「ここのボスって、なにが出るんでしたっけ?」 などと、遠回りな質問から切り込むことにした。 「盗賊ウサギのラヴィ・ヴァニィ。そんなに無茶な攻撃はしてこないけど、念のため前に出ないように気をつけてね」 そう教えてくれたのは春乃さん。 うん。僕ら新米が前に出ると危ないからね。 でもちょっと待って。察して。僕が聞きたいのは、「この冒険ってなに?」ってこと。 「今回は春乃がメインアタッカー、サンチェーンがヒーラー、デイリーがバフ役でいく」 ギルデンスターンは察するどころか、どんどん先に行く。 ヒーラーもバフも専門用語だよ。知ってる前提で話すの良くないよ。 「ギルデンスターンさんは?」 「背後の警戒と指揮、及び、クラウドコントロール」 また専門用語。 「それって、どういうこと?」 「戦闘は一体ずつ確実に仕留める必要がある。複数の敵が来ても一対一の戦いに持ち込めば、ヒーラーとバフを有したこちらが有利になる」 ヒーラーとバフ、すなわち、回復役と強化役。 「群れで襲ってきた敵はギルデンスターンが寝かせるから、私たちはマシーンのように敵を倒すの」 ふたりの解説にはまるでこれからガチの戦闘が始まるかのような緊迫感があった。 ギルデンスターンと春乃さんは更に細かい打ち合わせをしている。 「低レベルのダンジョンだと聞いたんですけど」 迷子の子猫のような目で田村が聞くと、 「今回のミッションは、おまえたちに怪我をさせずに帰すことだ。だから、念には念を入れる」 との返事をもらって少しホッとするけど、 「フラグですね」 フラグじゃねぇよ、田村ぁ。 「高良山で遭難するものだっている。原因は登山道が崩れていたり、道に迷ったり様々だ。山道ですらそうだ。俺たちは自然の洞窟に入るんだ。なにが起きるかわからん」 いや、それにしても。 「でも、さすがに大げさですよね」 春乃さんはさらさらの黒い髪をピンで留めてヘルメットを被る。 「ダンジョンレベルは冒険者の酒場で格付けしたものでしょう? もしかしたら昨日の夜に手強いモンスターが中に入り込んだ可能性だってあるじゃない?」 「フラグですね」 フラグじゃねぇよ、田村ぁ!五・はじめてのダンジョン
洞窟の中は真の闇だった。 四人それぞれ松明を携えて中に入り、オレンジの明暗の中で道を探した。 「ていうか、こんなに真っ暗だとは聞いてないです」 「明るいはずがないだろ。自然の洞窟なんだから」 「敵が出たらどうやって戦うんですか?」 「片手に松明持ったまま戦うしかない」 「でも敵と言っても蛇かムカデだから、避けられるなら避けて」 ここまで聞いた感じ、冒険というより探検だ。でもその先が違った。 「ゴブリンが潜んでいたら、ぜったいに手を出すな。まず勝ち目はない」 ゴブリンに勝ち目がない? それは僕らがレベル1だから? 「あいつら、夜目が効く。物陰から吹き矢を打ってくる」 「しかも猛毒が塗ってあるわ。解毒しないと二時間で死ぬ。あいつらはそれを待ってから私たちの肉を食べるの」 田村がそんなまさかって顔をする。たぶん、僕もそう。 「吹き矢でなくとも、暗闇で松明を叩き落されたら、死が確定する」 「待って。ゴブリンって、そんなに凶悪なの?」 「向こうも野生動物じゃない。戦っているうちに知恵をつけた」 「明るいところでならこちらが有利なんだけどね。洞窟だと不利よねー」 「潜んでたらどうすればいいんですか?」 「まずは向こうから警告音を出してくるから、それを察知したら食い物を置いて去る」 「戦わないんですか?」 「だから言っただろう? 勝ち目がないって」 足元は凸凹していた。普通に歩いているだけでも転びそうになる。 「水にはできるだけ入るな。住血吸虫がいる」 そう聞いたときには、バランスを崩して片足は水たまりの中にあった。 「まあ、住血吸虫にやられるかどうかは運だ」 「運って……」 「レベル1でこの難易度……?」 田村がまた子猫の目で訊ねる。 暗闇のなか、どこかにある壁がその声にエコーを被せる。 「このダンジョンのレベルは1じゃないよ? 15だよ」 春乃さんの声の響き。水の滴りと、風の音。 「えっ?」 静けさのなかに、耳鳴りだけが消え残る。 「私のレベルが28、ギルデンスターンが99。ここで死ぬことはないと思う」 ギルデンスターンの話では、高良山遊歩道と筑後川サイクリングコースがレベル1らしい。 「敵はカエルとワタリガラス」 「最初の冒険はそっちにしたかったです」 「ああ。初心者にはピッタリのコースなんだが……」 「何か問題があるんですか?」 「たまに一般人から通報される。警察に」 くそー一般人めー。なに考えてんだもー。 「止まって」 春乃さんが僕らを制すると同時に、暗闇から高速で打ち出された何かが春乃さんのアーマーを叩く。 「大丈夫ですか?」 「大丈夫。見て」 春乃さんが指差した先に、巨大なカエルが照らし出される。 「ジャイアント・トード。あれなら仕留められる」 ゲコゲコ鳴いてる。 「キラキラした動くものに反応して舌を伸ばしてくる」 ――カエルそのものだ……。 「デイリー、《戦いの歌》だ。攻撃力を上げて一撃で仕留める」 何なんだこの展開。 回復はギルデンスターンにもできたが、戦闘中の回復はサンチェーン田村に花を持たせてくれた。回復魔法は『ケペペス』。 「昔はホイミとかケアルとかキュアとか、ギルドによっていろんな名前があったんだが、4年くらい前に統一された」 ケペペスに。 ケペペスの回復量は低かったが、《気持ちを込める》ことで回復量はアップした。気持ちを込めるコツ……ギルデンスターンによると…… 「呪文を使用する際に ――天空を舞う清らかな風よ! ――我に集い、その力を与え給え! みたいなのを唱えるんだ」 ということだった。 田村は還元教団で教えられた基礎詠唱集を暗記していたが、どんな言葉で気持ちが込もるかは個人差があった。 実戦の中で田村は、好きなアイドルの曲や偉人のセリフなどいろいろと試してみたが、いちばん回復量が増えたのは「あなたは僕の太陽だ」だった。 カエルのボヨヨンアタックでダメージを負った春乃さんに、 「あなたは僕の太陽だー! ケペペス!」 の、サンチェーン田村の回復魔法が飛ぶ。 「好きな人に使うと、回復量あがるの、この魔法」 「えっ? そうなの?」 「それで結ばれたカップル、何組か知ってる」 マジか! カエル、カエル、大ムカデ、コウモリ。 コウモリと戦い終える頃にレベルアップした。 どこからともなくファンファーレが響いて、力がみなぎってきた。 「これは……?」 「おめでとう、レベルアップだ」 「人生初レベルアップね」 レベルアップって、こういう風にするんだ。 田村は「おおお」とか言って感動してるけど、なんか釈然としないというか、 「レベルアップってなに?」 「レベルアップはレベルアップだ」 小学校中学校で9年? 高校で1年ちょっと? ずっと勉強とか習字とか水泳とかやってきて、レベルは上がってるはずなんだ。だけど、 「いや、なんていうか、こういう形でレベルアップしたのって初めてで」 「初々しいなぁ、そのリアクション」 いや、初々しがられても困る。 「吟遊詩人だから、ヒットポイントが3上がってるはずだ」 うん、なんか力がみなぎった感覚はあったけど…… 「ヒットポイントってなに?」 「ヒットポイントはヒットポイントだ」 「そのうち慣れるよ」 レベル3になると、《守りの歌》を覚えた。 「こういうのって、レベルがあがると自動で覚えるんですね」 「不思議だろう?」 「不思議だって感覚はあるんだ」 「もう慣れたけどな」 僧侶の田村が覚えたのは《コルプレ》。 「《コルプレ》覚えたんですけど、これ、なんの魔法なんです?」 自分ではわかんないんだ……。 「《コルプレ》は覚醒の魔法。眠らされた味方を起こすことができるのよ」 眠らされた味方を起こす……なるほど……でも。 「それって耳元でフライパンをガンガン叩くのとどう違うんです?」 「火事だーっ! 起きろーっ!」 田村が無駄に乗ってきてうるさい。 「フライパンが無くても起こせる」 「いや、そうじゃなくて」 「真面目な話、麻酔で眠らされたものをフライパンでは起こせんだろう?」 「あ、そうか」 戦闘中の睡眠効果のある魔法って、麻酔みたいなもんだったのか。 「逆に言うと、《コルプレ》で手術中の患者を起こせる」 ひどいことを思いつくなぁ。 「フラグですね」 回収しきれねえよ。 僧侶はレベル12で蘇生呪文《ピンチョミンチョ》を覚える。それまでは、死んだら還元教団に死体を担ぎ込んで、お金を払って蘇生してもらうしかないらしい。 でも、蘇生? 死者を蘇らせる? 「それって、交通事故で死んだひとも生き返らせることができるのでは?」 「いや、そっちは医師会が反対してるから無理なんだ」 「医師会が反対って? なんで?」 「医者による厳密な施術で蘇生させなければ、医療事故につながるんだと」 「でも、死んでるんですよね? 医療事故ってなに?」 「わからん」 「利権を守りたいだけよ。みんな高い金つっこんで医大出て、贅沢して暮らしてるでしょ? その暮らしを守りたいんじゃない?」 春乃さんは意外にもリアリストだった。 「でも、蘇生の手段があるのに放置するしかないって、おかしくないですか?」 このところ完全に還元教団のひとになった田村が訴える。 「そうよねー。ちなみに交通事故で死んだひとを、死亡診断出される前にダンジョンに担ぎ込んで、そこで死んだことにすれば生き返らせることができるみたい」 「いや、原理的には可能だが、それをやった県議が医師会に吊るし上げられて辞任しただろう?」 「世知辛いなあ」 田村はふてくされて、春乃さんは笑った。 僕らは出会って二時間ほどしか経っていない。なのにクラスの連中より親しげに言葉を交わしている。もしかしたら春乃さんとの会話が、竹下さんと交わした言葉の総量を超えたかもしれない。四人でいるとたまにふっといい匂いが鼻をかすめる。これが春乃さんの香りだったらいいのに、ギルデンスターンなのが悔しい。 「さんちゃんは、私が交通事故で死んだら、そうやって蘇生させてくれるよね?」 「はい! もちろん! まだ蘇生魔法は使えませんけど、還元教団で蘇生させます!」 「あー、それだったらパス」 「ええっ? どうして?」 洞窟を奥へと。 「還元教の蘇生基金って、教祖の陵墓建築に使われるのよ? 死んだほうがまだましだわ」 足元の石は一歩ごとに揺れる。 「そんなこと言わないでくださいよー。教祖様、いいひとなんですよー」 「あーもう、これだから。還元教団のひとは」 田村は、還元教団の教祖は末端の信者には許されていない《両手ケペペス》ができるのだと、スマホに保存した写真を見せた。 「で?」 「この写真をこうやって体に当てるだけで癒やされます」 スマホを体のあちこちに押し当てて恍惚の表情を見せる田村を、 「馬鹿じゃないの?」 春乃さんは切り捨てた。六・ヤマカガシ
――それで、ダンジョンの奥にいたのが……? ――そう。例の悪魔なんです。 ――古澤さんにギターの超絶テクニックを教えてくれたという! ――ええ、あの出会いがなかったら、僕のグラミー賞はなかったでしょうね。 なんてこともなく、ボス戦はあっけなかった。 最初のボス戦だから、そいつが残した謎がラスボス戦で回収されたり、実はそいつは過去から来た僕自身だったり、なにかしら仕掛けがあるんじゃないかと田村と盛り上がったけど、奥にいたのはただのヘビだった。 「ウサギの盗賊は?」 「外出中じゃないかな」 「ダンジョンのボスが外出?」 ファンタジー要素も何もない1メートル前後のヘビ。田村は松明で照らしてヤマカガシだと教えてくれた。 ここまで回収されたフラグ、ゼロ。 いつか僕の前にも、白馬に乗った悪魔様がやってきて、超絶技巧を授けてくれる……そんな妄想をあっさりとかき消したのだから、ボスとしては優秀だと思う。 どんなに強くて野心的なボスよりも、弱くて無価値で夢を砕くボスのほうが辛い。 夢破れもしない。打ち砕かれもしない。 「なにもありませんでした」 それで、おしまい。僕の人生そのものかもしれない。 竹下さんとの仲が深まるわけでもないし、田村が変な宗教から帰ってくるわけでもない。 宝箱は九十九島せんぺいの缶。 棒でヤマカガシをどかして、宝箱を開けると、中にはコリスのフエガムと学研の雑誌の付録とが入っていた。 「これ、だれかが埋めたタイムカプセルだ」 天井を見上げると、少し光が差し込んでいる。 地上のどこかで埋められたものが、ここに落ちてきたんだ。 田村は身をかがめて箱の中を確かめる。 海岸で拾ったらしいガラス石に、見覚えのある牛乳瓶の蓋……ギターのピック……そう言えば最初に弾いたのは4才のときだった。このへんでなんとなく、僕が埋めたんじゃないかって気がしはじめたけど言い出せなかった。 「エッチな漫画のページがある!」 ああ、そう言えば。たしかに埋めた。言わないけど。 「うひょ!」 うひょじゃねーよもう。うっせぇなあ。 パーラー櫛原の入り口からずいぶんと歩いたから、このあたりは僕の家の庭の下かもしれない。ずっと昔に埋めた缶が落ちてきたんだ。 でも、だとしたらこの穴はいつできたんだ。 「ヘビは知恵の木の実をくれるもんだと思ってた」 と、田村が言った。 「だったらあの九十九島せんぺいの缶が知恵の木の実だな」 「《かしこさ》が1~5ポイントアップするやつ」 ――あの話を最初に知ったのは、まだ小学生の頃だ。 「かしこさ99で使うと0に戻るやつな」 4つ上の従兄弟から聞いた。 「違うよ、文字化けするんだよ」 クロスロードで悪魔に出会い、悪魔に魂を売り渡して、その引き換えに超絶なギターテクニックを身につけたという、伝説のアーティストの話。 rockin’onだったか、BURRN!だったかを見せられながら、どんなアーティストかも知らずに逸話だけを聞いて、僕はアメリカの片田舎の風景に、エルヴィス・プレスリーみたいなリーゼント頭を思い浮かべていた。 その逸話の主人公、ロバート・ジョンソンを知ったのは、何年か後。 彼は黒人だった。 エルヴィス・プレスリーとは似ても似つかない。 そのとき、僕は思った。 神様はきっと残酷な差別主義者だ。 彼は黒人だから、白人の神や天使は手を差し伸べてくれなくて、悪魔が助けてくれたんだ――と。 だったら――僕を助けてくれるのも神様じゃない。 悪魔か……あるいは水天宮の河童が手を差し伸べてくれるんだ。 その日だけでレベルは4つあがって、レベル5になった。 田村は《ヘパモンチン》の呪文を覚えたというが、本人曰く、 「効果はよくわからない」 僕は《毒消しワルツ》を覚えた。こちらはギルデンスターン曰く、 「二日酔いにも効く」 らしい。 春乃さんは「また誘ってね」と言ってくれたけど、僕はやっぱり竹下さんと冒険がしたい。 「冒険の人数なんですけど、五人になってはだめですか?」 「いや、別に何十人でもかまわないよ」 「ま、今日行ったとこだったら、五人だと何かあったときに逃げ出せないから、場所によるかな」 「そのときは俺が離れて背後を守るよ」 「そうね。外で救護班として待機してもらうのもありだから、人数は何人でもいいかな」 そうなんだ。 僕はてっきり冒険ってのは人数が決まってて、その人数みんなで洞窟に入るんだと思っていた。 「昔はそうだったよ。パーティは四人、みんなで洞窟に入って、一緒に行動してボスを倒した」 「昔のことを言うんだったら、ゴブリンはもっとアタマが悪かったし、洞窟ももっと明るかった気がする」 「そうなんだよな。変わったんだよ、他にもいろんなところが」 「いろんなとこって?」 「宝箱はぜんぶ同じ形をしていて、洞窟の同じ場所にあった。モンスターは決まりきった動きしかしてなかったし、戦闘はもっと楽だった」 「なんかリアルになったよね、いろんなことが」 リアルになった? 僕は――おそらく田村も、その意味を飲み込めなかった。 「冒険人数を聞くってことは、ほかに誘いたい子でもいるの?」 春乃さんが図星を突いてきた。 「ええ、クラスの女子なんですけど……」 「ガールフレンド?」 「いや、そんなのでは」 「誘えばいいじゃない。連れて来なよ、こんど」 「でも彼女のお父さんが、身元不明のひとと冒険はしちゃいけないって」 「あー、なるほど。じゃあギルデンスターンは放っといて三人で冒険すればいいんじゃない?」 「そうですね」 ギルデンスターンに国家資格のIDを聞けたらそれでいいんだけど、切り出せなかった。 「リバーサイドコースだったら余裕だし、三人で挑戦してみるといい」 冒険者の酒場に寄って、春乃さんと僕と田村と三人、メロンソーダを飲んで、チャリを押して家路についた。 「いま、卒業旅行中で、駅近くの旅館に滞在してるの」 「ああ、だから訛りがあるんだ」 「やっぱりわかる?」 「どこ出身なんですか?」 「尾道ってわかる?」 「ああ! 映画の舞台になってるとこ!」 「そう。私の住んでる家もちらっと写ってるんだよ」 なんて話を、本当は竹下さんとしたい。 「デイリーはどうしたの?」 「あいつまた、竹下のこと考えてるだけだから」 図星だけど。 「うるさい。バカ」 そう言えば、竹下さんとラインの交換をしていない。 電話は古澤畳店のほうにかかってきたので、電話帳で調べたのだと思う。 小さい頃から《タタミ屋》って呼ばれて、あんまり良い思い出はなかったけど、竹下さんから電話が来たのはそのあだ名のおかげだ。 て言うか、僕はさあ。リバーサイドコースに三人で冒険に行くよりは、普通にサイクリングしたいんだよ、竹下さんと。田村なんか抜きで。七・オープンキャンパス
「魔王って、どこにいるかわかんないって言うじゃん?」 「うん。言うね」 「どこにいるかわかんない魔王って、倒す意味あるの?」 いつもの通学路。チャリを押す田村。 「うーん。倒したらなんか良くなるんだよ、世界が」 「たとえば?」 「消費税が5%になるとか」 追い越す車。 「あ、それ、倒すわ」 「すげぇモテモテになるとか」 「倒す倒す」 信号で足を止める。 「遺産を三千万残すとか」 「倒すわー……って、倒しちゃいかんだろ。だれよ、それ」 「正解。うちの爺ちゃんだ、それ」 いつの間にか青になった信号を見留めて―― 「て言うか、モテモテになるって理由で倒すのはどうなの?」 急いで歩き始める。 「じゃあ王様が褒美をくれるからって倒すのはどうなんだよ」 「あー、だめだねそれ」 前から来るチャリを避けて歩道に降りる。 「姫を嫁に取らせるとか」 「そういうのだめだよ。その王様が悪人だと思う」 街路樹を挟んで、変圧器の陰。 「あー、わかった。わかりました」 田村が手を挙げる。 「はい、田村くん」 「魔王が悪いことしてるから倒すんだよ」 得意げに僕に人差し指を向けるけど、それってあたりまえじゃん? 「まあそうだろうけどさ。でも、悪いことって法律で裁かない?」 「そうだけど、毎日何百人もの市民を殺してるとしたら?」 田村はチャリにまたがって、低速でよろよろと漕ぎ始める。 「法律で裁くんじゃない?」 僕の家も近い。 「いや、正論だけどさ。じゃあ、冒険者って何を倒すんだよ」 「わかんねw」 古澤畳店は、大通りから一本入ったところにあった。 そこに生まれた僕は、生まれた落ちた瞬間に、畳屋を継ぐ未来が7割くらいは決まっていたのだと思う。 畳屋の売上が落ちたいまですら、3割くらいはそうだ。 ちゃんと泳いでないとブクブクと畳屋の淵に沈んでいく。 でも、それもいいかなって気はする。 好きな曲をガンガンに鳴らしながら畳を仕上げる。 夜は仲間と文化街のバーで歌って。 ――いやいや、これからじゃないか、古澤幹夫の可能性は無限大だ、って言われるかもしれないけどさ。宝くじが当たる可能性も隕石に当たって死んでしまう可能性もゼロじゃないさ。 ねえ、先生。 先生は大学の卒論で何を書きました? その研究を進めて、まとまったものを出版して、世界を変えることだってできましたよね。今からでもできますよ。常識を覆すような偉業を成し遂げることが。 これからじゃないかって、僕にだけ言うの、ずるくないですか? 未来の総理大臣からダブルデートのようなものを持ちかけられたのは、僕の吟遊詩人レベルが8になったころ。 「僕と藤島さんと竹下さんで神籠石大学のオープンキャンパスに行くんだけど、古澤くんもどう?」 って言われたら、断る理由がないよね。 でも少しもったいつけて、 「あー、それっていつ? 今週末?」 なんて言ってみるけど、今週末だろうが来週末だろうが、なんなら今すぐだろうが行く。 「今週末だけど、もしかして予定ある?」 「あ、いや、ない。僕も行っていいの?」 「もちろん!」 吉田くんの分厚い唇が力強く動くと、 「でも古澤くんって、進学しないで独学で音楽に打ち込むって言ってたよね?」 と、藤島さん。 言ったっけ? そんなこと? 吉田くんは、「いいよ、そんなことはどうでも」と藤島さんに囁いて、振り返り、 「竹下さーん。古澤くんも行くってー」 教室の隅の竹下さんに声を送ると、竹下さんのはにかむような笑顔が、ふわっと教室にひろがった。 それで僕と吉田くん、藤島さん、竹下さんで神籠石大学のオープンキャンパスに出かけることになったのだけど、この絶妙な仕掛けに田村の影を感じずにはいられなかった。 あいつが僕と竹下さんとがくっつくように糸を引いているんだ、きっと。 その証拠に、キャンパスへ入るとすぐに吉田くんが提案してくる。 「僕ら薬学部だから、ここらで別行動にしない?」 ほらね。この流れ。この流れは偶然じゃないよ。 田村め。田村のくせに。失恋したくせに。こんなことまでお膳立てしやがって。 「そっちは医学部志望だよね?」 医学部? 竹下さん、医学部志望だったの? 「うん。私はそう」 「じゃあ、決まりだ」 「あ、でも、古澤くんの意見を聞かないと……」 竹下さんは気遣ってくれるけど、いや、僕はその、とくに志望とかはないんです。というか、そこまでしてもらわなくても、あ、ええっと、医学部? 「ええっと」 どう言えばいいんだ? 戸惑いながら少し考えていると、藤島さんと吉田くんとが手をつないでいることに気がついた。言葉の続きを継ごうとしてうた竹下さんも、 「古澤くんは……」 ――と言いかけて、気がついた。 藤島さんが右手指を鼻の下にあてて、照れ笑いする。 「それじゃ、これで! 帰りは流れ解散で!」 力強く声にする吉田くん。その後姿は、藤島さんの手を引いてキャンパスに消えていった。 これも田村の仕込み? いや、違うか。僕ら、出汁にされたんだ。 吉田くんたちの背中をしばらく見送って、竹下さんが口を開いた。 「まだ内緒にしといたほうがいいよね」 あのふたりが付き合ってるってこと―― 「あ、うん」 「ふたりきりで気まずかったらごめん」 ふたりきりになるとすぐに会話は途切れた。 「大丈夫。いつもと一緒だから」 いつもと一緒? まあ、そうだね。いつも同じ教室にいるのに言葉なんか交わさないしね。 「そうだね」 でもせっかくだから。 「あ、そうだ。ライン交換してもらえるかな」 「ライン?」 「ええっと、スマホの」 「ごめんなさい、よくわかんなくて」 待って。ラインはともかく、もしかしてスマホを知らない? 「メールは?」 「手紙は好き」 「手紙じゃなくて」 「ごめんなさい。あの。メールって?」 メールって―― 正直、戸惑いはしたけど……でもきっと、これが竹下さんなんだ。 「聞き返されると、よくわからなくなるよね。手紙かな?」 「だよね。びっくりした。こんど手紙書いてもいい?」 「うん。もちろん」 竹下さんからどこに行こうとも言ってくれなくて、徒然に歩いていると、ギターケースを持つひとの姿ばかり目に留まった。 やがてそのギターが音を奏でだす。 「リッケンバッカー」 「なに?」 「ギターの種類。あれ。たぶん」 ギターケースの形とかじゃなくて、持ってる人のイメージが呼び起こすのだと思う。勝手に推測するだけだから、当たったかどうかなんてわからないけど。でも。今日の出会いは違った。そのギターケースを持ったおっさんがこちらへ向かってきた。 「あたりだ。きみは?」 あれ? 「リッケンバッカー。あたりだよ」 「僕、声に出しましたっけ?」 「出したよ。けっこう大きい声で」 「でもすごい。なんでわかるの?」 隣で竹下さんが驚いているけど、ていうか、 「偶然?」 ええっと―― 「オープンキャンパスに来ました。古澤です」 僕が会釈すると、あわてて竹下さんも自己紹介。 「同じく、竹下です」 おっさんはふたりの顔を見渡す。 吉田くんたちみたいに手はつないでないけど、傍から見たらつきあってるように見えるかもしれない。 ――恋人かい? なんて聞かれたらどんなに幸せだろう。 「いいねえ」 おっさんはそう口にして薄笑みを浮かべた。 いいねえってなんだ。 恋人に見えたかどうか言ってくれ。 おっさんは蟹副と名乗った。精神医学部門の主任の教授らしい。 「ギターには詳しいの?」 「まあ、クラスの中では。バンドやってますから」 「へえ、それはいいね。どんな音楽を?」 「グランジ系ですね」 「ああ。流行りの。NIRVANAから入ったクチか」 「いや、僕の場合PIXIESから。教授はどんな音楽を?」 「私は自分では弾かんのだよ。軽音楽部の顧問をやってて、たまにこうして小間使いをやらされるくらいで」 音楽の話で盛り上がる横で竹下さんはにこにこしている。 退屈させちゃまずいなと思うけど、教授は構わずに続けた。 「Ramones Talking Headsあたりは聞いていたけど、最近はさっぱりだ」 呆れた表情をして見せて、 「お嬢さんは?」 と、竹下さんに水を向ける。 「私はぜんぜんわかんないです。さっき挙がった名前もさっぱり」 「そうか。これは失礼した」 うん。三人いるんだから、三人がわかる話のほうがいい。 「邦楽だと、スカパラダイスオーケストラとかユニコーンとかいいですよね」 一気に舵を切ってみた。 「私はA-JARI押しだな。ナイト・ホークスもいい」 知らん。なんだそのバンド。聞いたこともない。空気読めおっさん。 「私はその……」 竹下さんが遠慮がちに口を開く。 「さだまさしとか……安全地帯とか……」 そうだ! さだまさしだ! そのままこっちのペースに持ち込むんだ! 「おお! その年でさだまさしか!」 あ、なんで教授のテンションまで上がってるんだ。 「それじゃあ、はしだのりひこや、井上陽水は?」 おっさん、そっちも押さえてるのか! 「大好きです! 五つの赤い風船はご存知ですか?」 僕らは教授に招かれて、『楽屋』と呼ばれている軽音楽部の部室を訪ねた。 クロスロード伝説に憧れていることを話すと、 「古澤くん、それは違うよ」 と、教授は言った。 「ロバート・ジョンソンだって努力はしたと思うんだよ。だけどその努力をだれからも評価されず、『悪魔と契約したから上達した』と言われて蔑まれたんだよ」 「えっ、でも、悪魔と取引するなんて、カッコよくないですか?」 そう訊くと教授は眉をしかめた。 「僕も専門じゃないので詳しくはわからんけど、第二次大戦前だろう? 敬虔なキリスト教国で『悪魔と取引した』が、そんなに良い意味だったとは、僕には思えないな」 突然訪れた社会科の時間。大戦前のアメリカ。 「だから古澤くんも、本当にグラミー賞が欲しいなら、悪魔に期待しちゃいけない」 当時の音楽シーンはメタルやグランジに慣らされたいまの感覚とは違うはずだ。悪魔がカッコいいなんて感覚はないのかもしれない。でも、具体的な景色は思い描けない。 「じゃあ僕は、己の才能でグラミー賞を獲るしかないですね」 たいして考えたセリフでもなくて、僕はただ頭の中をひらひらと舞う黒い蝶を追いかけるだけだった。 「ああそうだ。その意気だ」 ノリだかマジだかわからない返事。教授は続ける。 「そして君がグラミー賞を獲った時、まわりの連中は言うだろう。 ――あいつが超絶技巧を身に着けてグラミー賞を獲ったのは、水天宮で出会った河童に魂を売り渡したからだ。 ――ってね」 一拍置いて、 「どう思う?」 改めて言葉を継いだ。 「悔しいですね。そう言われるのは」 「そうだろう? もういちど、ロバート・ジョンソンのことを話せるかい?」 蟹副さんは僕の目をまっすぐに覗き込んだ。 「彼は悪魔と契約したのだ、だから超絶技巧を身に着けたのだ……と」 自販機でパックのドリンクを買って、講堂の階段に座った。 「カドを持つんだよ。そうやって持つと中身出るから」 竹下さんの口から、ふと何気ない日常会話。 僕の脳裏に、小さい子どもにパックの牛乳にストローをさしてみせる竹下さんの姿が思い描かれた。 でもちょっとまって。 この、駅前の藤井フミヤや鳩山邦夫が持ってるマンションに住んで、子煩悩に世話をしながら僕の帰りを待つ竹下さんって、医者なの? 「医大志望だって、はじめて知った」 「うん。高望みだけどね。挑戦はしておきたい。古澤くんは?」 「僕は……」 この流れでもう、悪魔と契約してグラミー賞だなんてことは言えない。 「歌って踊れる畳屋かな」 医者と畳屋かあ。 「いいねそれ」 「いいかなぁ」 畳屋かあ。 「いいよ。手に職があるんだよ?」 「まだないけどね」 「じゃあ、私といっしょだ。今の私には、なにもない」八・水天宮裏河童伝説
「ギルデンスターンって本名じゃないよね?」 「うん」 オープンキャンパスの帰り道。 「本名は聞いてないの?」 「うん」 吟遊詩人のレベルは8だけど、僕と竹下さんの間はどのくらいのレベルなのだろう。 「聞いたほうがいいよ。何か起きてからじゃ遅いから」 「わかった。こんど聞いてみる」 あと、冒険者の登録番号もあるからそれも、と、竹下さんは念を押した。 ともに白髪が生える頃をレベル99だとすると、肉体的な結びつきが20くらい? お友だちが1で、一緒に歩いたら2、デート3、手をつないで4、キスは5くらい? ということは、いまレベル2か3。 今日のことをデートって呼べるかどうかだ。 言葉が途切れて、 「私も冒険に行きたい」 竹下さんは視線を外したまま呟いた。 「でも、高校卒業してからじゃないと無理」 「うん」 門を出るとすぐにバス停がある。 「いまレベルいくつだっけ?」 「吟遊詩人で8レベル」 「じゃあ、卒業する頃には20くらいにはなってるんだ」 時刻表を見て、僕は55番、竹下さんは23番のバス、それぞれの時間を調べて、どっちも30分以上待つねって笑って、 「駅からだともっと出てるんじゃない?」 って、目の前に来た01番のバスに乗った。 ふたりがけの小さな椅子に、お互いの腕が触れないように固く座って、 「今日はありがとう」 竹下さんが言うから、 「いや、ありがとうはこちらのセリフだよ」 あわてて繕った。 「デートみたいで楽しかった」 「えっ? ああ、うん。僕も」 『デートみたい』ってのは、あくまでも『みたいなこと』であって、デートじゃないよって念を押されたんだって思った。 「今週末も冒険?」 「うん」 僕と竹下さんの関係のレベルは2。 「そう。レベル上げ、がんばってね」 ――私とのレベルはもう2でお終い。 「うん」 ――あとは冒険でがんばって。 そう言われたような気がした。 水天宮は僕のココロの故郷だった。 僕だけじゃない。京町小学校の出身者のココロには遍く河童が住んでいる。 水天宮の脇から川べりへ出て、大分の山奥に端を発し有明海にそそぐ筑後川を見るとココロが洗われた。 有明海の向こうは東シナ海。更に南下すれば親潮に合流し、太平洋をぐるっとまわってカリフォルニア海流につながる。そこははるか遠い、ロックの故郷。 水は音楽のようだ。いや、逆かな。音楽は水のようだ。 実のところ、ロバート・ジョンソンの曲なんて聞いたことがない。海流になって流れてきた水の一滴。それがクロスロードの伝説だった。 そんなの、彼がヒーローだったって証じゃないか。僕はずっとそう信じてきた。それを得意になって田村に話したからって、それで引け目を感じなきゃいけないような話じゃない。 どのみち大昔に死んだひとだ。 それなのに、夕焼けは卑怯だ。 僕はただ憧れていただけなんだよ。 いつか僕の前にも悪魔が現われて、契約を迫ることに。 夕日が山並に触れると、意味もなく涙がこぼれてきた。 逢魔が時の帰り道。 川べりに、ギターケースを忘れてきた。 取りに戻ると、川べりには河童の姿が見えた。 空のオレンジが溶け落ちる時間。それに水天宮裏の筑後川沿いだ。そりゃあ河童も見るだろう。 立ち尽くしていたら、向こうから話しかけてきた。 「おまえが忘れていったギターはこの、カート・コバーンがステージでブチ壊したギターカパ? それともこっちの、ジミ・ヘンドリックスがステージで燃やしたギターカパ?」 このパターンで来たか。 「語尾のカパはなんとかならんか?」 「語尾はどうでもいいカパ。答えるカパ」 悪魔や河童から誘惑されても乗らないと決めた矢先にこれだ。 「いいえ、僕が忘れていったのは従兄弟のバンド仲間から八千円で譲ってもらったボロっちぃギターです」 「なるほどカパ。正直者のおまえには特別に、オレが壊したおまえのボロっちぃギターをやるカパ」 「おまえっ!!」 「どうだ。うれしいカパ?」 「うれしくねえよ。おまえが壊したのか?」 コクコクコク。 「なんてことしてくれんだよ……」 「壊れたものはしょうがないカパ」 「壊れたって、おまえが壊したんだよな?」 コクコクコク。 「ギターを壊したお詫びに、グラミー賞を獲れるような超絶技巧をあげるカパ」 「要らん」 「じゃあ、殺すカパ」 「なんでそうなる」 「じゃあ、竹下さんのココロを自由に操る技巧をあげるカパ」 「えっ?」 「フラれてもフラれても蘇る熱い思いを、テクニックに昇華させるカパ!」 「フラれるの前提で話すのやめろ」 「それがあると、竹下さんのココロやブラウスやその他もろもろパックリパカッと開かせることができるカパ~」 「おまえ、中身おっさんだろ?」 「おっさんじゃないカパ! カパは女の子だカパ! ここだけの話……昔話に出てくる金と銀の斧の女神……あれもじつは河童だったカパ~」 ぜってぇ嘘だろ。 「とりあえず、壊れたギターはおまえにやるカパ~」 「ああ、それはどうも……って、オレのだけどな!」 「カパは川のなかのおうちに帰るカパ~」 「ああ、帰れ帰れ」 「そうしたらここでカパと会った記憶はなくなるカパ! 代わりにここで人生が嫌になって自分でギターを叩き壊した記憶にすり変わるカパ~」 「えっ?」 「さらばだカパ!」 河童は帰って行った。 記憶がすり替わる……いったいどういうことだろう……と、しばらく呆然としていたが、記憶がすり替わることはなかった。 僕は河童に壊されたギターを持って家に帰った。九・憧れの竹下さんに捧げる冒険
こんにちは、古澤くん。 手紙を書くと言ったこと、覚えていますか? 覚えていなかったらごめんなさい。まさか本当に手紙が来るなんて、思ってもみなかったかもしれませんね。 今朝、庭の木の洞にミツバチの巣を見つけました。よくわからないけど、ニホンミツバチだと思います。どこかから花の蜜を集めて来ているのだと思うのだけど、ミツバチって私たちが知らない花のことも、きっとたくさん知っているんですね。 それで突然だけど、ひとつだけ言わなければいけないことがあります。 じつは古澤くん。あなたは、勇者山本さんに封印された世界の中にいます。 あなたが手紙を受け取ると言ってくれたから、私は外の世界から、この手紙を届けることができました。 封印された世界のなかで、古澤くんは輝いています。外の世界はあなたにとって退屈で、呪われていて、夢も希望もないかもしれません。だけど、外の世界も悪くないです。それだけ伝えたくて、ペンを取りました。 こんどいつか、ちゃんと会ってお話をしたいです。 その日を待っています。 時節柄、風邪など引かぬよう、くれぐれもご自愛くださいませ。 追伸 ロシア軍がクリミア半島のシンフェローポリ国際空港を占拠しました。あなたの世界からは、見えていますか? ――魔王が出た ラインに入ったのは金曜日の昼休みだった。 低レベルでも倒せる魔王ということで、僕と田村も参加することになった。 「でも、ちょっとまって」 「どうした?」 「魔王ってたくさんいるの?」 「それな」 それなじゃわからないよギルデンスターン。問い詰めると、 「結構たくさんいる」 との答えが帰ってくるけど、本当に聞きたかったのは、それはなぜなの? って話なんだよ。察してよ。ほんとに。 ギルデンスターンによれば、かなり極悪な世界クラスの魔王から、地方で庶民の生活を脅かすローカル魔王までわんさかいると言うけど―― 「ドラゴンがたくさんいるのは理解できるんだ。種だから。でも魔王はやや納得がいかない。なんでたくさんいるの?」 「いたほうが楽しいだろう?」 って、それは問題発言でしょ。 更に問い詰めると、 「いずれわかるさ」 と、三角関数の意義を問われた大人のような答弁で躱された。 土曜日の午後、冒険者の酒場に来たけども雰囲気はいつもと変わらず。生ぬるいココアのような気だるさがあった。 今回現われた魔王はディストメア。スマホで調べると、攻略法も確定しているし旨味もない『いちばん過疎ってる魔王』と書かれている。 まだそんな本格的な魔王が倒せるとも思えないけど、でもだからって過疎ってる魔王じゃしょうがない。ほっとしたり、がっかりしたり。 それでも酒場のひとに聞くと、 「ディストメアはこの土地で多くの子どもたちの命を奪った。許しがたい存在だ」 「三百年前、有馬藩の家老、有馬吾保友によって封印されたが、その封印の効力が切れたんだろうな」 と、それらしい物語を語ってくれた。 ここではちゃんと役になりきって話すのが暗黙のルール。 そのなかで、国家資格の有無を聞くのは野暮に思えた。彼らは本名すら聞いてこない。ある意味気楽だった。僕と彼らは高校生と大人の関係じゃない。新米の冒険者とベテランの冒険者だ。僕の進路のことなんてだれも気にしない。逆に僕からしても、彼らがリアルでどんなひとなのかわからない。大金持ちもいるかもしれないし、大泥棒がいるかもしれない。 そのルールに触れない範囲でと思って、 「冒険に行かない日はなにをしてるんですか?」 ギルデンスターンに聞いてみると、 「映画見たり、家で寝てたりかな」 と、わりとリアル人生寄りの答えが返ってきた。 「何年くらい冒険者やってます?」 「あれ? 何年だったかな。20年は超えてるよ」 「20年?」 この酒場ができてまだ10年くらいだったと思う。 「あの頃は、このあたりは何もない荒野だった」 「このあたりが荒野?」 「ああ。今で言う吉野ヶ里遺跡のあたりと、御井町のあたりに大きな集落があって、北野、田主丸、神埼の集落が冒険の拠点になっていた」 なんだろう。 この人はもうリアルと冒険がごっちゃになって、おかしくなってるのかもしれない。 17時を過ぎるとメニューが変わって、フリードリンク組は店を追い出される。 コーヒー一杯五百円は辛い。 「家で飲んだらタダだし」 「タダっていうか、親が買ってんだよ、あれ」 そうなんだよな。 おやつの丸ボウロがよく台所に転がってるけど、あれもだれか買ってるんだよ。 「うちはしるこサンドだな」 「なにそれ」 「竹下さん、どうだった?」 チャリを押しながら田村が聞いてくる。 なんかよくわからない手紙は来たけど―― 「どうだったって、なにが?」 「告白」 「しないよ、告白なんて。そんなつもりじゃなかったんだし」 お膳立てしてもらって申し訳ないんだけど。 「いや、おまえがじゃないよ。向こうが」 「えっ?」 「えっ?」 「えっ?」 いま、すれ違ったおじさんまで「えっ?」って。 「だめだ、おまえ。鈍すぎる」 「あ、でも。えっ?」 「おまえ、無駄に壁作ったんじゃないだろうな?」 「えっ?」 田村はそれ以上教えてくれなかった。 僕も訊くのはためらわれた。 ほんの少し変な期待が生まれて、その芽が摘まれるのが怖かった。 レベル8。日曜。昼下がり。 篠山城の奥、深く立木に覆われた先に祠があった。 ディストメアはそこに封印されているという。 「こんな感じでいろんな魔王が封印されてて、それが都合よく蘇るんですね」 田村のやや失礼な聞き方に、ギルデンスターンは悪党っぽい笑みを返す。 「知ってるか? ディストメアの悪行」 「ええっと、子どもをたくさん殺したとしか」 「そう。問題はその殺し方だ」 殺し方。 「あいつは、子どもの臍から毒の水を注入して殺したと言われている」 「臍から……」 「えげつねぇ……」 「それでディストメアに殺された子どもたちは成仏できずに、怨霊となって筑後川沿いに留まり、近づく子どもたちを殺すんだそうだ。自分たちがされたように、臍から毒水を注入して……」 「うわー、トラウマになるわー」 「だろう? でもなんのことはない。住血吸虫の症状だ。おそらくそれが大流行した頃に、ディストメアが創作されたんだ。そして子どもたちが川に近づかないように、物語として綴られた」 「あ、そうか。だからか。だからこんな感じで土地土地に魔王がいるんだ」 「そう。それぞれの魔王にそれぞれの土地の物語がある。どの魔王が強い、どの魔王が弱いって話じゃない」 正直、冒険はもう最後にしようと思っていた。受験のことも考えなきゃいけないし。でもこうして話を聞いていると、こちらの方が大きな経験をしているようにも思えてくる。 「死んだものは無念だったろう。身内を失ったものもしかり。百の犠牲者があれば、そこには千の悲劇がある。ここに封じられているのは、そういった悲しい物語だよ」 それに耳を傾けることが弔いになると、ギルデンスターンは続けた。 いままで魔王の背景なんて考えたことがなかった。リアルな高校生の僕らにとって、魔王は魔王でしかなかった。どの魔王が強い、どの魔王が弱い、それすらもなかった。 「おまたせー!」 遠くから春乃さんの声。砂利道を小走りに登場すると空気も少し華やいだ。 息を切らして、ペットボトルの蓋をとって喉に流し込む。 「ディストメア倒したら、レベル10超えるね」 上気した声。 田村はおどけて 「いえーい」 と返す。 僕は―― 「うん」 ギルデンスターンさんの話を聞いて、まだ考えを整理している途中だった。 「どうした、デイリー。元気がないぞっ」 「うん」 ここにはリアルな僕が忘れていた、草の匂いがある。 「でも、いいのかなって」 「いいのかなって、なにが?」 いや、冒険を抜きにしたってリアルな世界であることは変わらないんだ。 「竹下さんも高校出たら冒険したいって言ってたのに、僕だけレベル上がっていいのかな、って」 事情を知らない春乃さんも察したと思う。ちらりと田村の顔を見て、話の続きを待った。 「高校出たらおまえがリードしてやればいいじゃん」 「いっしょに歩むんじゃなくて?」 「それ、無理でしょ」 「リードするの?」 「そうだよ。向こうは医者だぞ? どうせリアルでリードされるんだから、冒険くらいリードしてやれよ」 「うん」 リアルでうまくいくなんてもう、到底思えないけど。 「もしかして、デイリーの意中のひとってお医者さん志望なの?」 春乃さんに訊ねられて、答えに窮していると、 「行くぞ」 ギルデンスターンの声に救われた。 魔王ディストメアが封印された祠、その内部は広くて複雑だった。 とは言え、ダンジョンはこれで4つ目。 最初の頃に感じていた、こんな広大な迷宮がどこにあったんだろうっていう感覚もなくなっていた。でも、 「祠って、なんなの?」 こんなんだっけ? 「知らん。こういうとこのことだろう?」 「こういうの、社殿とか言わない?」 まあ、本当の祠がどうかは知らないけど、ここは洞窟と違って自然の明かりがある。 「これ、祠じゃないよね」 だよね。ずっと疑問だったんだ。 敵を倒すのももう慣れたもので、最奥のボスまでは雑談しながら進んだ。 今日はギルデンスターンはレベル99の騎士、春乃さんは僧侶83。いつもは僧侶をやっている田村がレベル1の戦士をやっている。この構成だと田村の耐久力に不安があるけど、いざとなったらギルデンスターンひとりでも魔王を倒せるし、あらゆる状態異常は春乃さんが治せる。 それでも、ボス部屋の前に来ると胸は高鳴った。 注連縄があって、御札が貼られている。 「絵に書いたような」 田村が言うと、ギルデンスターンは苦笑いした。 部屋のなかは薄暗く、壁じゅういたるところに梵字が書かれていた。 「注連縄のなかは梵字って」 「節操ないね」 火の消えた燭台、四体の羅漢像に囲まれて鎖のかかった禍々しい椅子があり、魔王ディストメアらしき影はその前にうずくまっていた。 「どうする?」 ギルデンスターンが訊ねる。 「どうするって、なにを?」 「ボスの前口上。聞いて倒す? それともこのまま殺っちゃう?」 春乃さんが補足してくれるけど、ギルデンスターンから魔王の由来について聞いたばかりだ。せめて話は聞いてみたいと思った。 「聞いてみます」 「OK」 そう言うとギルデンスターンは僕に目配せする。 「僕が聞くんですか?」 思わず田村の方を見やるけど、俺と、おまえ、ふたりで、言う、みたいなジェスチャーを見せる。よくわかんなかったけど、まあ、やってみるか。 「魔王ディストメア!」 まずは魔王に呼びかけてみる。が、反応はない。田村が引き取る。 「おまえの悪事はすべて見通している! これまでだ!」 田村はヒーローっぽく魔王を指差す。 だけど魔王は何も言わない。ただ低くうなり声を上げる。 少し不安になってギルデンスターンの顔を見るけど、肩をすくめて見せるだけ。 戸惑いながらも、 「おまえを成敗に来た! 覚悟しろ!」 田村が剣を構えると、 「……けて」 魔王は小さな子ども、あるいは河童のようにも見えた。 「聞こえねぇ!」 田村のがなり声が祠に響く。 「たす……けて……」 ようやく魔王のかすかな声が耳に入った。 「待って! 助けてって聞こえた!」 「はあ?」 魔王は力なく続ける。 「なに……も……して……ない……」 「なにもしてないって、おまえ、魔王じゃん! やったんだよ、何か!」 「ちょ、ちょい待て、田村。そんな理由で倒していいのか?」 「倒していいのかって、おま……」 田村は呆れて剣をおろして、改めてディストメアに訊いた。 「三百年前! 子どもをいっぱい殺して! 有馬吾保友に封印された! 魔王ディストメア! 間違いないな!」 「そう……」 「ほらあ! 魔王本人じゃん!」 「本人であってもだよ! 魔王、助けてって!」 ヒートアップしているところに、春乃さんが割り込む。 「統計的に3割の魔王は命乞いします」 そんなこと言ったって! 「どうするかはおまえたちで決めろ、デイリー、サンチェ」 「ここで魔王に背を向けると、9割方背後から刺されます。統計的には」 どうしよう。どうすればいいんだろう。わからないよ。 「ギルデンスターンさんだったらどうします?」 「俺? 俺だったら話なんか聞かない」 「えっ?」 ひどくないか? あまりにもひどくないか? 「すべて調べつくして覚悟決めて乗り込んで来たんだ。たとえ冤罪でも、生き延びて帰るには倒すしかない。話なんか聞いても迷うだけだ」 クソのような理屈だ。 「まあ、魔王の話が嘘か本当かなんて裏のとりようがないよね」 と、春乃さんも援護する。 「古澤、俺は死にたくない。蘇生呪文があるったって、痛いのは嫌だ。俺はやる」 「わかるけど……わかるけど、それは正しいのか?」 「生きて帰れるかどうかってときに、正しいも間違いもないだろう!?」 「それを言うんだったら、僕ら好き好んで乗り込んで来たんだよ! こんなとこに来なかったらそんな究極の選択だってないんだよ!」 思わず声を荒げる。 「大丈夫だよ。魔王は不死身だから」 「ええーっ?」 僕を気遣ってか、春乃さんがフォローしてくれるけど、 「端的に言えば弱体化して封印するだけだからな。そこまで揉める話じゃない」 そうなの? 本当にそれでいいの? 「覚悟決めろ。デイリー」 覚悟ったって! 「魔王ってのは、クソみたいな社会が生み出した澱だ。100%の悪かといえばそうじゃないなんてことは、よくある話だ」 ギルデンスターンは20年以上のベテランだ。僕より多くを知っている。 「癌になったら、病巣だけじゃなくて、まわりの健康なところも切り取るでしょう? それと同じだよ。たとえ魔王に3割、4割の良心があっても、倒すしかないのよ」 春乃さんだって、高レベルのジョブがある。 だけど3割、4割の良心があっても倒す? 「だったらそれが5割だったら? 6割だったら?」 「それはひとそれぞれだけど」 「春乃さんだったら?」 「殺す」 10割でも? 最後の問いを口には出せなかった。 なのに、春乃さんは静かにうなずいて見せた。 春乃さんが言うんだったら。 覚悟は決まったけど、なぜか涙がだらだらと流れた。 「冒険者って、みんなそうなんですか?」 「そうだよ。英雄なんかじゃない。半分は悪党だ」 ギルデンスターン……。 「デイリーみたいな子はいっぱいいた。優しい子。でも、みんな死んだ。死んだら家族も恋人も守れないでしょう?」 春乃さんまで! 「で?」 田村が聞いてくる。 僕はうなずいて……うなずくしかなくて、戦仗を構えた。 悪魔に魂を売るって決めていたんだ。 その瞬間が来ただけじゃないか。 ――そのとき。 「あいや待たれい!」 「待たれよ勇者方!」 芝居臭いセリフとともに、黒ずくめの者たちが乱入してきた。 「何者!?」 「チッ」 ギルデンスターンが舌打ちする。 「我ら、魔王弁護連盟!」 「その魔王の弁護、我らが引き受ける!」 「なんなのそれ……」 体中の緊張が抜ける。 「名乗ったとおり。魔王の弁護をしてまわってる暇な連中だ」 ギルデンスターンも春乃さんも呆れて見遣っている。初めてじゃないんだ。 「おおお、魔王ディストメア……こんなにも怯えて……」 「このまま戦わせるわけにはいきませんね!」 「いや、待って。なんなの、この展開」 田村は混乱しすぎて半べそになってる。 「あいつらは……」 と、言いかけた春乃さんを制して、黒ずくめが躍り出る。 「ときに魔王をその場で弁護し!」 「ときに魔王を連れ帰り、弁論術を学ばせる!」 「われら!」 「魔王弁護連盟!」 田村はすでに放心状態。 「どうするの?」 「さっさと連れて帰れ!」 「目障りなんだよ、バーカ!」 春乃さん……春乃さんが、バーカって……。 「バカと言いましたね!? 魔王にバカと!?」 「魔王に言ってんじゃねえ! てめえに言ってんだ、バーカ!」 「良いでしょう。その愚弄、情状酌量の論拠とさせていただきましょう!」 「話聞けよ! 魔王に言ってんじゃねーよ! てめえに言ってんだ、このターコ!」 「では! さらば!」 「またお会いしましょう!」 「待てこらーっ! ざけんじゃねーぞっ!」 魔王は連れて行かれた。 結局レベルは8のままだった。 「で、どうなったんですか?」 緊張と弛緩とで体にもう力が入らない。 「知らない。どこかで教化して返ってくるんじゃない?」 「強化?」 「教えるのほうの教化ね」 「魔王としての弁論術を身につけさせるんだ」 「『助けて』で動揺するデイリーなんか、勝ち目なくなると思う」 そういうものなの? 祠の入り口へと引き返しながら話した。 魔王の周りには、魔王のカリスマで回っている世界があって、経済があって、それが破綻したら多くの魔物が露頭に迷う。そうならないように、さまざまな対策が施されているのだと。 ギルデンスターンに駅まで送ってもらって、田村とふたり、バスを待った。 「ごめんな。さっきは」 田村が頭を下げる。 「僕の方こそ。怒鳴ったりして」 「いいよ。これからはもっと増えるよ。ああいう究極の選択が」 これからも、か。続けるのかな。これからも。 「少し考えたい」 「うん。それもいいね。竹下のこともあるしね」 「うん。でも、それなんだけど」 田村は来ましたとばかりに目を輝かせる。でも、決めたんだ。 「なんかもう、諦めようと思う」 僕には、リアルか冒険かの二択だった。 「諦めるって?」 「竹下さんのこと」 彼女はリアル側にいる。 「なんでよ! 脈あるって! あるっていうか、それ以上だって!」 「でもさ。竹下さんが将来医者になって、どんな人生でも自由に選べるようになってさ、僕を選ぶ理由ってなんだと思う?」 僕はリアルでは、負け犬になる。 「知らねぇよ! 好きだー! 愛してるー! ちゅー! でいいんだよ!」 「そうかなぁ」 もう、決めたことなんだ。 「そうだよ!」 僕は冒険者になる。 「おまえもう、冒険はいいよ。告れ! いますぐ告れ! 竹下に!」 「無茶言うなよ」 無数にいる魔王、その物語を目に焼き付けるのが、僕の冒険。冒険というか、人生だ。 いつか自伝を出そうと思う。 タイトルは『憧れの竹下さんに捧げる冒険』。 その本は、藤井フミヤや鳩山邦夫が持ってるマンションに僕じゃない誰かと暮らす竹下さんの本棚に飾られて、いつか彼女の子どもが大きくなったとき、はじめてひとの目に触れるんだ。第二部・河童に魂を売った男
十・失われた古代史
勇者側に魔王経済圏に関する資料は少なかった。 しかしそれでも、歴戦の冒険者の話を切り貼りすると、うっすらとその全容は浮かび上がった。それは―― 「それは――っていうよね」 「映画の予告編とか、それは――って」 それは――大魔王の下、無数の魔王たちに統率された世界―― 「でもさ」 「なんだよ」 「魔王フォロワーとか魔王親衛隊はわかるんだよ」 「ああ、いそうだね」 「魔王弁護連盟って、なに?」 「なにって、魔王を弁護するんだよ。勇者の言いがかりに対して」 「弁護団に守られた魔王なんて聞いたことがない」 魔王に用意された特権は弁護連盟だけではなかった。 まずは魔王保険。 勇者に破れた魔王が、再起のために受け取る軍資金。これにより敗北後も失職せずに現場復職できた魔王が無数にいる。 「なんだそれ」 「ちゃんと先のこと考えてるよね、魔王」 魔王健康保険組合。 勇者との戦いで負った傷の治療代が出るほか、糖尿、高血圧、高脂血症、ありとあらゆる魔王習慣病をケアする、略して魔王健保。 「健康にこだわるのかよ」 「健康、だいじよ」 魔王影武者派遣組合。 命を狙われがちな魔王に代わって、魔王の椅子に座し、身代わりとなる者を派遣する。 「派遣かー」 「辛そうだなぁー」 魔王年金。 毎月百人を殺す魔王が、更に十人余計に殺して積立を行うと、引退後も自動的に毎月三十人を殺してくれる。 「あ、ちょっとまって。それってなんの意味があるの?」 「知らないよ。魔王じゃないんだから」 魔王出版。 魔王の伝説をまとめあげ、本にして出版する。 「あ、いいなぁ、それ」 「ちょっと羨ましい」 そして、それらを統合したのが、魔界で話題の魔王総合保障サービス。 「そんなものまであるんだ」 「いま、だいたいの魔王がこの総合保障最王手、魔王ライフに加盟していて……」 「魔王ライフ」 「そこのトップが死んだら魔界の経済は破綻するって言われてる」 「おっ? フラグだねぇ」 「でも不死身だそうよ、そこのトップの魔王も」 「あららー」 中間考査も近い週末。 冒険者の酒場前には規制線が張られていた。 ――なんか、酒場が規制されてるんだけど ギルドチャットに質問を流すと、 ――魔王タマタールが復活した すぐにリプライ。 ――タマタール? ――タマタールに挑戦した連中がみんな返り討ちにあった ――傷だらけで運び込まれて ビルの住人に通報されて警察が来た どうしてこう冒険者の酒場って、社会の常識から外れちゃってるのか。 ――警察も住人もクソばかりだよな そっちがクソなのかよ。 ――ロイホで作戦会議だ すぐに来い ギルデンスターンは相変わらず。 「おっ! 行かなきゃ!」 って、田村。それ、僕らも行かなきゃいけないの? ロイホでギルデンスターンの姿を探すと、その傍らには春乃さんの姿もあった。 テーブルには資料が広げられている。 ギルデンスターン曰く、 「タマタールは由来のわからない魔王。もとは高良山の山頂の神社に祀られていた神だが、いつの頃からか魔王となった」 「由来、わかってるじゃん」 「いや、わかっていないのは神だった頃の話だ」 神だった頃の……? タマタールは神だった頃、神の中では唯一、出雲大社に呼ばれていなかったという。 「出雲大社に呼ばれるというのは?」 「神無月というのを知っているか?」 聞いたことはあるけど、知っているかと問われると首をひねる。 「旧暦の十月、日本中の神様が出雲大社に集まり、出雲以外の土地から神々がいなくなる。それが神無月」 ああ、そういうことか。そうか。出雲に行ってたのか。 「その集まりにタマタールだけ呼ばれていない?」 「そう。神だったころの名は、玉垂命」 「たまたれのみこと?」 「そうだ」 ギルデンスターンは僕らの胸の内を探るように、声のトーンを落とした。 「あまり知られた名ではないが、俺はこの玉垂命が、隋書にある『阿毎多利思北孤』だと思っている」 あまの、たりし、ひこ。 たま、たれの、みこと。 遠くはないけど、初耳の単語ってのは、どうしても右の耳から左の耳へ抜けていく。 「隋書と言うと、ええっと……」 「中国の隋王朝の歴史書だ。阿毎多利思北孤による第一回遣隋使の記録が残されている。が、日本の歴史ではこの阿毎多利思北孤は登場しない」 頭の中でまだ整理が追いつかないけど―― 「それが俺らの地元に祀られてる神様!?」 そう問うと、ギルデンスターンは深く頷いた。 「そう」 「つまり……?」 「邪馬台国は、久留米にあった」 ええっと。 邪馬台国の話がどこから結びついたのだろう……。 「すごいですね。でも、あんまり説得力感じない」 「そうか?」 「テレビでやってたら納得する」 ギルデンスターンは何も言わず人差し指を立てる。 「あと、YouTube」 もういちど何か言いたげに、人差し指を立てる。 なんの意味があるんだろう。何か言いたいなら言葉にすればいいのに。 「お前らはバカだ」 ああ、はい。 「とにかく、来週末討伐に行く。準備しておけ」 「来週って、中間考査の前日なんだけど」 「気にするな」 しろよ。 「でもそんな日本神話でも特別扱いされてる魔王に、勝ち目あるのかなあ」 「勝ち目など関係ない」 「いや、あるでしょ」 「おまえはグラミー賞を獲ると口にした時、勝ち目があると感じたか?」 「それは……」 「タマタール討伐も同じ。生き様だ」 喋らせろよ。 「紀元六〇〇年、第一回遣隋使。俺はこれを派遣したのは高良玉垂だと思っている。第二回は六〇七年、小野妹子だ。知っての通り、小野妹子は這這のていで追い返されている。何故かわかるか?」 さっきからスマホでウィキペディアを調べている田村が口を開く。 「携えた書簡に『日没する処の天子』と書いてあって、それを見た隋の煬帝が激怒したって……」 「違う」 「違うって。見たんですかあなたは」 「派遣したのが玉垂ではなかったからだ。第一回遣隋使と第二回遣隋使、この七年の間に日本国は激変したんだ」 ギルデンスターンはテーブルの上の資料をいくつか指差して説明を続ける。 「玉垂が多利思比孤だというのが俺の勘違いだろうがかまわん。俺は、玉垂の言葉を聞いてみたいんだ。直接」 「でも……酒場のひとたちがことごとく返り討ちに……」 「それだったら大丈夫」 やっと春乃さんが口を開く。 「魔剣七支刀を持ってる。その刀に宿る御霊を開放すれば、ワンチャン勝ち目がある」 なんだそれ。初めて聞いた。 「そんなすごい武器をどこで?」 「ガチャで当てたの」 ガチャで…… 「一万六千分の一を引くんだから、たいしたもんだ」 ガチャで当てた七支刀で魔王タマタールを倒して、日本古代史の真実を暴く? 僕の胸に浮かんだ言葉。 それは―― バカはおまえらじゃないの? 言わないけど。十一・祇園山古墳
冒険に行くからって、竹下さんのことをきれいさっぱり忘れられるわけでもなく、ことあるごとに顔が浮かんだ。 顔。顔もだけど、肩かな。いちばん脳裏に浮かんだのは。ストラップが透けた細い肩。 「そんなの気にせず竹下誘ってダンジョンに行けばいいんだよ」 と、田村は言うけど。 「いや、だから卒業までは冒険はしないって」 「じゃあダンジョンじゃなくていいから。映画とか、美術館とか」 「ハードル高っ」 「ダンジョンのほうが高いだろ」 夏になって制服がブラウスになると、背中が透けて見えるようになって、妙にドキドキした。肩までの長い髪。細い腕。できるだけ目を合わせないようにと思って焼き付けた姿は、後ろ姿ばかりだった。 その竹下さんが、将来は医者になるという。 休み時間。5分の喧騒。 魔王タマタールが潜むダンジョンは、御井町の祇園山古墳にあるらしかった。 「古墳とか、奈良とかにあるやつやろ?」 「うん。でも、八女にもあるらしいよ」 八女までだったら車で10キロ。八女にあるのなら久留米にあっても不思議ではない。 「歩いても10キロだよ」 そこ、突っ込むんだ。 「一説によれば、邪馬台国の女王卑弥呼の墓だとも言われてるって」 「言われてるって、なにが?」 「祇園山古墳」 「その古墳が?」 「卑弥呼の墓だって」 初耳すぎて、頭に入ってこない。ちょうど通りかかった御井小出身の松原くんに聞いてみたけど「なにそれ」って返事だった。 ギルデンスターンから聞いた情報も込みで説明して聞かせたけど、 「日本全国に卑弥呼の墓なんてゴマンとあるんじゃないの?」 との返事。 地元の子でさえこれだよ? 「古墳なんて、そのへんの丘と変わんないよ」 と、その話をとなりで聞いていた古賀くん。 「いやいやいや」 「逆に言うと、そのへんの丘が古墳かもしれんとも言えるわけじゃん」 「そうだよ」 「いやいやいや」 土曜日早朝。 ――いますぐ祇園山古墳に来い 田村からのラインが入った。 ――もしかして、魔王? ――そう。ギルデンスターンが俺たち抜きで突入するらしい いや、当然でしょう。僕らレベル10にも達してないぺーぺーだよ? そう言ってなだめてはみるものの、「後方待機組ででも参加したい」と鼻息を荒くするものだから致し方なく祇園山古墳に出向くことにした。 ――だって、邪馬台国だぞ!? ああ、うん、それが? ――いまどこ? ――自宅 ――じゃあ、九大前の改札で待ち合わせ ――時間は? ――5分後 無茶言うなよ。 魔王ダンジョンへは、ギルデンスターンがリーダー、春乃さんと酒場の有志二名を加えた四人で突入するらしい。 「なんでついてきた?」 と突き放すギルデンスターンに田村は、 「後方待機でかまわないんで」 とすがりついた。 ギルデンスターンのジョブは装備からみて騎士か戦士、春乃さんは僧侶にも見えるけど、魔法使いかもしれない。残りは武闘家と、もうひとりは…… 「レンジャーかな?」 「弓装備だろう? だったら賢者かもしれない」 「賢者だ。今回は春乃と俺の二枚ヒーラーで臨む」 なるほど。 「ギルデンスターンが正面で攻撃を受けて、カーズが背面に回り込む」 カーズってのは武闘家のひとだと思う。チャットでは見たことがある。この賢者だってひとがだれかはわからないけど、自己紹介されたところでどうせ覚えない。ピリピリした四人の中で、このひとだけがにこやかに語ってくれた。 「《インジェクション・ライト》を張る。短期決戦だ」 というギルデンスターンの声。 春乃さんの七支刀の《御霊開放》を軸に、インジェクションと呼ばれる技をいくつか重ねる。作戦の概要は聞こえてくるけど、わからない単語ばかり。 「インジェクションってなに?」 田村が聞いてくるが、僕にわかるはずもなかった。 そういえば田村は、昔から邪馬台国九州説を説いていた。 祇園山古墳が卑弥呼の墓だという噂を知ってからは、ことあるごとに 「やっぱり俺が言ってた通りだろう?」 と、自慢してきた。 「でも、いままでこの古墳のことも知らなかったんだよな?」 「うん。知らん。御井小の連中が知らんのに、俺が知ってるわけがない」 「邪馬台国九州説を信じてるくせに?」 「そりゃそうだけど、まさかこんな地元にあるって」 「春乃さんはどう思います?」 準備で忙しそうな春乃さんに田村が無神経に訊ねる。 「古代史ならギルデンスターンが詳しいわ」 ほうら。邪険にされた。 ギルデンスターンだって暇じゃない。 それでも、鞄の中の道具を確認しながら、教えてくれた。 「邪馬台国はおそらく国号じゃない。朝鮮半島南岸から九州地方に無数にあった邑を統べるのが倭、その首都が邪馬台、すなわちヤマトだ」 「えっ、待って」 「ユウって何?」 「そっち?」 「自治権を持った集落。都市国家だと思えばいい」 「都市国家!? 日本に!?」 都市国家と言われて僕らが想像したのは、ギリシャやイタリアの城塞都市だった。見たことないけど。 「ああ。古代日本にもあったんだよ。田主丸、白木原、前原など、マルやバルが地名に残っているとこがあるだろう? あれが都市国家。古代の邑だ」 「それを統一していたのがヤマト!?」 「じゃあ、畿内にあるヤマト王権の大和は?」 ギルデンスターンは溜息をひとつ漏らした。 「生きて帰って来たら話してやる」 「フラグですね」 冗談めかして口にはしたが、あたりの空気は針の嵐。いままで田村がフラグだって言って回収されたことは一度もない。それだけが救いだった。 『祇園山古墳』と書かれた小さな標識は草に覆われ、その文字もかすれていた。その丘の頂、小さな石の棺のようなものから四人は侵入した。 僕たちは後方待機という名の居残り組。危ないから離れていろと言われて丘の下までは降りたけど、はたして意味があるのか。 ギルデンスターンたちは音声チャンネルを開いて、スマホからその声が聞こえる。 『《インジェクション・ライト》、《インジェクション・サンクチュアリ》、詠唱完了』 『先行する。背後はまかせた』 その会話に加わってよいものかと、固唾を飲んだ。 『さんちゃん、デイリー、危なくなったらすぐに逃げてね』 春乃さんのアイコンにスピークマークが閃く。 「危なくなるってどういうことですか?」 『なにか察したらすぐに逃げろ』 ギルデンスターン。 「ちなみにインジェクションって何?」 田村が質問を投げるが、スマホの向こうはもう緊迫感を伝えるだけ。 「ギルドで聞いてみる」 「だれに?」 「だれか。いる奴」 田村が言い出して両手親指で文字を打った。 ――インジェクションって何? 「もっと丁寧な聞き方ってないの?」 「いいんだよ、チャットなんだから」 答えはすぐに返ってきた。 ――一言で言うと禁呪 その『禁呪』の二文字を見て田村が目を輝かせる。 「こっち見るな」 「禁呪って!」 禁呪で盛り上がる気持ちはわかるけど、抑えろよ。 ――ギルデンスターンが使うの? 田村が返事を打っている間にもいくつかチャットが流れる。 同時に音声通信は緊迫したギルデンスターンたちの声を伝える。 ――ログが残るとやばい 『こっちに足あと』 ――俺も行こうかな ――禁呪って、使うと何が起きるんですか? 『痕跡は罠だ。囚われるな』 ――それが実はよくわかんないんだよねー ――わからない? ギルドメン曰く、インジェクションは宇宙の法則を書き換える魔法。 この宇宙には外側の世界があって、インジェクションを介して外の宇宙にアクセスすることで、この宇宙では起き得ない事象を起こすことができる。 ――マジで!? 『酸素濃度アラート』 ――宇宙には修復力が働いているから 下手すると術者本人が宇宙からはじき出される ――それに宇宙の法則が未来永劫書き換わっちゃうこともあるらしい 『仕掛けてきた。来るぞ』 ――それってどういうこと? ――この世界で起きてるなんでもないことってあるじゃん? 常識として誰も疑ってないようなこと ――竹下さんが可愛いとか? 「あ、まて。なんてこと書きやがんだ」 『周囲警戒して』 ――そういうのが実はもうインジェクションによって書き換えられたあとの状態だって可能性がある いや、待って、竹下さんのことはともかく、 ――宇宙が変わると記憶はどうなるんですか? ――記憶も変わるよ だから元の竹下さんのこと覚えてるひとなんか どこにもいなくなる ちょっとまって! 竹下さんを例にしないで! 直後、鈍い打撃音に続いてギルデンスターンの声。 『春乃!』 春乃さんのアイコンが赤く変わった。これはいったい? 「何かあったんですか?」 田村が声を張るが、返事はない。 『蘇生を!』 『フリーズを重ねる!』 ただパニックに陥った現場の声が返ってくる。 「ギルデンスターン!」 田村はただ呼びかける。 『タマタールの足を止めろ!』 『無理だ、向こうも――』 「何が起きてるんですか!」 『田村、古澤!』 本名で呼ばれた……? 『離れろ、できるだけ遠くへ! 1分待つ』 「離れろって?」 『インジェクション、7つ目を重ねる! 早く!』 ――7つ目? ――すでに6つも使ってんの!? 音声チャンネルをモニターしていたギルドメンに動揺が走る。 ――祈るしかない 『逃げろ、早くっ! 早くっ!』 ――えっ!? 冗談じゃないの!? ――さらばだ、来世で会おう 「なにが起きるの?」 「俺に聞くなよ……」 田村はそう言いながら立ち上がると、すぐに走り出した。 僕も田村に続いて走り出し、高速道路の高架を超えて市街地へと駆け込んだ。 その背後、巨大な夕焼けが広がったような気がした。十二・ワールドシフト
グラウンドで歓声が上がった。 傾いた太陽はビルの縁をなめて、銀杏の影を長く延ばす。 校庭の人垣の中心にいるのは生徒会長の吉田。得意げに目からレーザーを放って、空き缶を撃っている。 うっすらと夕焼けの色を重ね始めた景色に、黄色い歓声が響く。 「そりゃあ、目からレーザー出たら生徒会長にもなれるし女子にもモテるよなー」 恨めしそうに田村が言う。 「そうかあ? そういうもんかあ?」 30メートルほど離れたところに置いた空き缶を仕留めると、レーザーが走った空間は灼熱し、爆音を轟かせる。 「前々から不思議だったんだけど、あれ、自分の目はやられないのかな?」 「なんか、眼球の前方2センチくらいのところから出るんだってよ」 「そうなの?」 「ちょうどこのへんかな? このへん」 田村は自分の顔でその場所を指し示す。 「マイクロブラックホールを生成して、シュヴァルツシルト面に生じる相転移のエネルギーを射出するんだと。だから本人には、ブラックホールに遮られてレーザー光は見えないって、600こちら情報部で餌取先生が言ってた」 「それって、僕らでも練習すればできるの?」 「いや、ひとによるんだって。三千人にひとりくらいらしいよ」 「そうかー」 文化祭での出し物が『冒険者の酒場』に決まって、僕らは放課後もその準備に追われた。本物の冒険者の酒場に入り浸っている僕と田村は、当然のように委員に祭り上げられ、料理班のリーダーには竹下さんが収まった。竹下さんの実家は小料理屋。彼女の料理の腕前はクラス全員が舌を巻くレベルだという。 「まさにサラブレッド!」 そう言って囃す田村に、竹下さんは眉をしかめた。 「こういうのは血統じゃないよ。竹下さんだって努力したんだよ」 こんなに近くにいても、竹下さんの目を見つめることができなくて、視界の端っこに、小さく頷いている顔をとらえた。 田村は僕に肘打ちしてくる。 口には出さないけど、またどうせ「告白しろ」って意味なんだろう。 冒険者の酒場は、三本松公園の向かいの道を入った寺と寺の間にあった。 通学路のはずれ。 なんでこんな遠回りをして酒場に通うようになったのか。 「こないだ、ギルデンスターンがタマタール倒しに行ったよな?」 「ああ、うん。そうなんだよねー。行ったのは覚えてるんだけどねー」 「ああ、やっぱそうだよなー。でもなにが起きたか覚えてないんだよねー」 冒険者の酒場上空には今日も飛空艇が停泊していた。 「あれ、いつになったら乗れるようになるの?」 「レベル20でクエストを受けて、パスをもらったら乗れる」 「クエストって?」 「ダンジョン3つ回って、キーアイテム集めるんだって」 「めんどくさそーっ」 「ギルデンスターンが手伝ってくれるよ」 「あー、ギルデンスターンと言えばー」 「言えばー」 そう言えば、邪馬台国の話を教えてもらうんだった。 酒場の奥、中二階の下の薄暗いテーブルが僕らのたまり場になっていた。 「神武東征の話は知っているだろう?」 ギルデンスターンの邪馬台国の話はそこから始まった。 「聞いたことくらいは」 歴史だったら僕より田村のほうが詳しい。と、田村のリアクションを待つと、 「神武天皇が、東に行った話ですよね?」 ――と、どうやら僕と大差ない知性を晒した。 神武というのは日本神話に出てくる最初の天皇。九州の宮崎を出て、船で大阪、奈良に向かって、近畿で王朝を開いたひと。ひと? 神様かな? 「その神武がどうしたんです?」 「どうして神武は宮崎から畿内を目指したんだと思う?」 いきなりどうしてと言われても。 「いや、ごめんなさい。詳しいことは」 「まあ、話してやるが、あとで調べておけよ」 ギルデンスターンは少し呆れ顔を見せる。 「あの、お手柔らかにお願いします」 「ちょっとトイレ」 このタイミングで!? 「その神武東征だが、神武が九州のどこを起点にしたのかは謎とされている」 いや、待って、田村抜きで話し始める? 「えっとそれ、宮崎だと思ってた」 「そう。宮崎から出発した説は有力だ。宮崎と畿内に同じ地名が残っているという話もあるしな。だがそれだと――」 それだと? 「関門海峡を二回通ることになる。いったいなんのために?」 それはただ、なんとなくとかじゃなく? 「じゃあ、神武はどこから出発したんですか?」 「それだ」 と、ギルデンスターンは顎の前に指を組む。 「神武はおそらく倭国の者ではない」 「と言うと?」 「魏の敗残兵だ」 はあ? 「三国時代末期、西暦二八〇年頃だ。戦に破れ大陸を追われた神武は九州北岸にたどり着いた。だが朝鮮半島南岸と九州一帯は倭の支配地域だ。簡単には入植できずに、舳先を畿内へと向けるしかなかった」 いいのかな、これ。まわりで右翼が聞き耳を立ててたらやばいことになるんじゃないかな……。と思ってたら田村戻ってきた。 「うひょ」 うひょってなに。 「当時の畿内には、黄巾の乱で発生した後漢の難民が国を築いていた」 それも断言していい話なの? 「そこに魏から逃れてきた敗残兵、神武が流れ着き、魏と交流のあった倭の名を笠に着て侵略戦争を仕掛けてきた」 「いやいや待って待って、日本神話の始まりが、魏の敗残兵?」 ろくに話を聞いてなかった田村が、それでも絡んでいく。 「おかしいか? 舞台が大陸だとしたら、ありがちな話だ」 ありがちかなぁ。 「ちゅうかさーっ」 田村の悲痛な叫び声。 「なんていうかもう、俺のロマンを返せーっ、みたいな?」 「っつーかおまえ、しばらく聞いてろ」 「九州を統べていたのは朝鮮半島とゆかりの深い国、倭国。近畿にあったのは大陸由来の国。当時は文化も軍事も中心は九州にあった。神武は魏の出身でありながら、畿内の田舎者を平定するために、優秀な倭民族の名を語った。そのために絶大なカリスマを持っていた卑弥呼を主神、天照大神として仰いだ」 そう言えば。 素人が語る日本古代史において、とても重要な要素があることを思い出した。 「ギルデンスターンさんって、出身どこですか?」 古代史論と出身地の間には密接な関係があると、なんかの漫画で読んだことがある。 「岩手県、花巻市」 微妙だなぁ。逆に言うとその立ち位置だから好き勝手言えるのかなぁ。 「主神が女神という神話体系は世界でも珍しい。それが成立しているのも、神武が倭国の威を利用したためだ」 「待って待って。つまり日本神話にあるような、神武が九州から出発したってのは嘘だったってこと?」 「そう。畿内を制圧するために作り出した偽の歴史。つまり――」 「つまり?」 「史上初の『歴史戦』があったんだ」 歴史戦と来たかーっ。 卑弥呼の死が西暦二四八年、神武東征は二八〇年――ギルデンスターンが簡単な年表を記す。辻褄が合わない話でもない。 でも、 「だったらどうして――」 これだけは聞かないと納得できない。 「――どうして今も倭国と大和とは分裂してるんです?」 「そうそう、神武が倭国から出て大和を平定したんだったら、そこで日本は統一されていても良いはずなのに、なんで今の日本は出雲・尾道ラインで倭国と大和に分断されてんの?」 ギルデンスターンは座り直し、椅子の背もたれに背中を預けた。 「そのきっかけが西暦六〇四年、高良玉垂の乱だ」 高良玉垂の乱―― 「なんだっけ?」 「高校で習っているはずだぞ、このあたりは」 「習ったっけ?」 あ、いや―― 言われてみれば、習った気がしてきた。 そしていつものように17時がきて、店を追い出される。 「あのさあ」 「なんだよ」 「なんか、このまえのタマタール戦からだと思うんだけど、記憶がぼんやりしていて」 「うん。俺もだけどさ。もう慣れたっていうか」 「なんかさあ」 「うん」 「夢みたいだよな」 「夢? いやそれどういう意味で?」 「たとえば朝、電話が鳴るだろう? そうすると夢の中でも電話が鳴って、それを取るじゃん。夢と現実がちゃんとシンクロするの」 「それはあれだよ。耳はちゃんと起きてるから、その刺激で夢も変わるんだよ」 「でも、あれだよ。ちゃんと電話を待ってる夢を見てるんだよ。電話が鳴る前から。そわそわしながら待ってるの。そうしたら電話が鳴って、実際にも電話が鳴ってる」 「ああ、たしかにあるね、そういうこと。予知能力なのかな」 「あれさあ」 「うん?」 「予知能力じゃなくてさぁ。過去が書き換わってるんだと思う」 「過去が?」 「電話が鳴って、それを聞いた瞬間に、過去の記憶が作られてるんだと思う」 「ああ、なるほど」 いまもそんな感じ。 知らなかった過去が、いつの間にか記憶の中に芽生えてる。 家に帰ると高級そうな寿司が取ってあった。 親父は上機嫌だった。どこかのホテルの宴会場の畳を一括で請けてきたと、寿司をつまむ。しかも藺草のグレードは最上級で実入りも大きいと。 「後藤畳店が店を畳んだだろう? そこに行ってた仕事がぜんぶうちに来る」 親父は売上の見込みをチラシ裏に書いてみせた。とんとんと指で叩いて得意げに顎をあげる。 「これなら毎日寿司が食えるね」 と、うっかり漏らした笑顔を、 「なんであんたが調子にのるの?」 と、姉が叩き落とした。 畳屋もまだ捨てたものじゃないのかもしれない。 寿司をつまみながら不意に、先生の言葉を思い出した。 ――妄想のグラミー賞で食えるのは、妄想の寿司だけ 姉は手づかみで中トロを取って醤油をつける。 「記憶と現実が食い違っている気がする」 次の日、田村の開口一番。 「たとえば?」 「たとえばと言われてもわかんないけど、冒険者の酒場の前には折れた欅があった気がする」 「あ……」 「それに、最初に冒険に行ったとこ」 「パチンコ屋の駐車場な」 「そこって、どこ?」 「トップレーンっていう……櫛原町の……あれ?」 「ボーリング場だろう?」 ただ、そうは思っても話しているうちに記憶は修正されて、いつの間にか僕らはボーリング場裏で冒険をしたような気持ちになっていた。 「それに吉田」 「吉田な」 「目からレーザー出してたか?」 「いや……出してた気がする……生徒会長選挙のときもデモンストレーションしてたよ、確か」 とりあえず、仮説を立てた。 「僕らの記憶は毎日差し替わっていってる」 「記憶っていうか、現実世界が変わっていってる。記憶は後追いでつじつま合わせてる」 「そう。それを検証したい」 「わかった。じゃあとりあえず」 僕らは教室の後ろの黒板に 『高橋浩介は歌が下手』 とデカデカと書いておいた。 「これで例えば、明日になって高橋の音痴が治ってたら、矛盾が起きるわけだよ」 「黒板に書いたことと現実がズレてる! って」 「ああ、なるほど。それが記憶が差し替わってる証明になる、と」 「我ながらグッドアイデア」 「でも、そうそうピンポイントでそんなことが起きるか?」 「そうだけど、でもそうやって絞っていくしかない」 翌日、黒板を見ると、 『アパラチャノモゲータ』 と、デカデカと書かれていた。 「アパラチャノモゲータ?」 「これ、昨日書いたっけ?」 「いや、書いてないよ」 「すげぇ! やっぱこれ、あれじゃん? 世界線が変わるやつ!」 「おおー」 とは言ったものの。 なんだそれ? 「でもなんか、だんだん書いた気がしてきた」 いい加減だなぁ、田村は。まあ、乗っておくけど。 「もしかして!? 記憶が差し替わってるーっ!?」 「つまりー?」 「仮説は正しかったーっ!」 なんて話をしてたら、藤島さんに消された。 消しながらなんか、ずっとこっち見てる。 「バカじゃないの? って思われてる」 藤島さんの口元が緩む。 「言ってもいいんだぞー。俺たちバカなんだからー」 藤島さん、ちょっと噴いた。よかった。ちょっと報われた。 でも、僕らのカンは外れていなかった。 ――WS発生してるっぽい 田村がギルドチャットを指し示した。 ――WSって? ――ワールドシフト 世界線がどんどんずれていく 「なんか、俺たちのデタラメに世界があわせてる的な」 「すまんなぁ、世界」 「迷惑かけちまって~」 ――ずれていくとどうなるんです? ――何も変わらないよ 普通は ――うん 普通はずれても気が付かないけど 今回のは規模が大きい ――記憶の書き換えが現実の変化に追いついていない 「つまり、バカは俺たちじゃなくて、この世界ってことか」 「でも、ワールドシフトが起きてるなんて言ったら、僕らのほうがバカに見えるわけで」 「まあ、そうだけど、実際にさあ」 と、田村が指差した黒板には 『岩田浩は絵が下手』 とデカデカと書かれていた。 実際にと言われても…… 「昨日、なんて書いたっけ?」 「さあ」 よくわからないけど、失われていく現実をひとつでも留め置きたいと思った。 「他のひとのことも書いておこう。ワールドシフトが起きても覚えていられるように」 そうして僕らは黒板いっぱいに友だちの特徴を書いた。 『池田泰弘は剣道部主将』 『小沢紗友里、水泳県大会出場、準優勝』 そして竹下さん……竹下智子は…… 『……医大志望』 そう書くと田村が、変な顔で睨んだ。 なんだよもう。大好きですとでも書けばいいのかよ。 でもなんか、不思議な優越感があった。 「だれも僕たちがしてることの意味なんてわかんない」 「俺もー」 おまえもかよ。 冒険者の酒場に行くと、ギルデンスターンの傍らに髪の長い女のひとがいた。 声をかけるのを躊躇っていると、 「春乃だ。覚えているか?」 ギルデンスターンの方から声をかけてきた。 「ハルノ?」 「東西南北の春と、乃木坂の乃です」 東西南北に春はないな。うん。 「あのう……もしかしてデイリーヤマザキくん?」 「ああ、はい。デイリーヤマザキ古澤です」 そう言えば、そう名乗ったことがあった気がする。でも……どこで……? 「どちら様でしたっけ?」 「それが、なにも」 聞くと、住んでる場所もわからず、昨日は冒険者の酒場で仮眠をとっただけという。 「俺の部屋に連れて帰るわけにもいかんし、駅前の旅館でも借りてやろうと思う」 「そんなことまでしてもらわなくても!」 春乃さんは恐縮して声を裏返らせた。 「いや、今回のワールドシフトは、おそらく俺のせいなんだ」 確かに、いままでの話を総合的に考えるとそういうことになる。ギルデンスターンがタマタール戦で使ったインジェクションってのが原因で世界線がずれているんだ。 でもそこから先はわからない。 何が起きたのか、これから何が起きるのか。 「ワールドシフトで、ひとが消えてしまうこともあるんですか?」 田村が不安げに訊ねる。 それはすなわち、この眼の前にいる春乃と名乗ったひとが、いつか不意に消えてしまう可能性を訊ねていた。 家に帰ると、古澤畳店の納屋には張替え待ちの畳が積み上がっていた。 おそらくこれもワールドシフトのおかげだ。 つまりどうやらここは、僕は竹下さんのこともグラミー賞のことも諦めて、畳屋になる世界線のようだ。 鞄を放り出すと、机の上に紙切れがあった。 加納の奴がクラス編成のときに書いたメモ。 女子生徒全員の名前と寸評が書いてある。 なんでこんなものが回ってきて、しかも捨てずに取っておいたのか。 そう思いながらもリストに目を落とし、竹下智子の名前を探すと、そこにあったのは―― 『竹下智子 いっけん可愛いけど、よく見るとブス』 ひどいことを書く……。 竹下さんは天使だぞ。 ――そう訝りながらも、なんかもう自分の感覚に自信がない。十三・メロンソーダ
たいがいメロンソーダだな。 田村も僕も、なぜかフリードリンクでメロンソーダを選んでしまう。 「だって、コーラは骨が溶けるっていうし」 「それも」 田村が指差してみせる。 「あ、これもワールドシフト?」 「ワールドシフト前の俺たちはたぶん、十六茶ばっかり飲んでたと思う」 春乃さんが、 「映画の中に、私の家が出てきたのを覚えている」 と言うので、そのビデオを借りてきて、酒場で上映会をした。 瀬戸内海、海沿いの港町。主人公が坂を登る場面で、 「ここ」 と、春乃さんが指差した瓦屋根の家。 だけどそこは、架空の町だった。 エンディングクレジットには、撮影協力に尾道市と書かれているけど、そんな市は存在しない。出雲から尾道にあるのは倭国と大和を分かつ万里の長城。尾道はその終点。巨大な砦があるほかは、原野が広がっている。 おそらくこの映画を撮った監督は、倭国と大和の戦争の象徴である尾道に架空の都市を想定することで、平和を訴えたかったのだと思う。 ビデオを見ている間、ギルデンスターンはスマホのログに目を落としていた。 エンディングクレジットが終わる頃、静かに口を開く。 「タマタール戦では、初手でひとりやられた」 映画の余韻は、ぷっつりと断ち切れた。 タマタール戦に乗り込んだのは四人。生還者三人。ひとり足りない。そこまでは戦闘のログからも明らかだった。でもひとり足りないのが誰なのか、どうなってしまったのか、だれにもわからなかった。 「それが春乃だったかもしれない」 ギルデンスターンは喉の奥から絞り出したが、そのことはもう、だれもがうっすらと感じていた。 だとしたら、この春乃さんという存在はなんなのだろう。 「うん。そうだと思う」 春乃さんは自分に言い含めるように、静かに口にした。 「タマタールのインジェクションが想定外だった」 そうか。魔王側も使えるんだ……。 「《インジェクション・腐食》と呼ばれる時間コントロールの術を使ってきた。こちらは短期決戦のつもりですでにインジェクションをふたつ重ねていた。そこにタマタール側も3つ。おかげで躊躇って対応が遅れた。最後は《インジェクション・ロケート》でなんとか逃げ出したが、限界を示す青い光が見えた。今の世界はもうずいぶんと変わってしまったんだと思う」 ギルデンスターンはなにかを思い出そうと額を押さえるが、その顔を歪ませるだけ。 「可能性でしかないが」 そう言うとまた少し考え、 「もしかしたらあのとき、タマタールの手に七支刀が渡ったのかもしれない」 と、絞り出す。 「どういうこと?」 「高良玉垂命は西暦六〇四年、隋の文帝と組んで大和を制圧し、九州王朝を拓いた」 「知ってます、そのくらい」 「その歴史がインジェクションのせいでつくられてしまったものかもしれん」 まさか……。 「古代史ではずっと謎とされてきただろう? 大和にあるはずの七支刀を玉垂が手にしていたことが」 「そう言えば聞いたことがある」 歴史が苦手な僕がそう答えるくらいには有名な話だった。 「もしそうだとしたら、倭国の首都が博多にあることも、瑞穂の国が倭国と大和とで分断されていることも、ニセの歴史かもしれんということだ」 「出雲尾道間の万里の長城も?」 「ああ。本来の世界線では存在してないのかもしれない」 「じゃあ、尾道市も本当なら実在する!?」 「あくまでも仮定の話だ」 それはそうだけど。 「タマタールによって世界線が変わってしまったのが事実なら、第一回遣隋使以降の歴史がすべて虚構である可能性が高い」 「つまり……?」 「九州王朝は存在しない」 「九州王朝が存在しないって……」 「この瑞穂の国……日本列島は、大和というひとつの国であった可能性が高い……」 古代、たしかに九州諸国は力を持っていたが、玉垂の時代には実権はほぼ大和へと移っていた。神功皇后の三韓征伐で軍事協力した頃は、半島との交渉においては先導的な役割を果たしてきたが、筑紫君磐井の治世に袂を分かって以来、歴史の表舞台に出ることはなかった。 そんななかで大陸に生まれた新たなる大国、隋と組み、瑞穂の覇権に手を掛けたのが高良玉垂命だった。大国の威光を借りての進軍。対する大和には百済の後ろ盾があるとされていたが、挙兵した玉垂の手には、百済が倭に送ったとされる七支刀が握られていた。 「その七支刀が、こないだの戦闘で魔王に渡ったもので、そのせいで歴史が変わった?」 「そういうことになる」 「しかし、いったいどうやって七支刀を手に入れたんだ……」 「ちょっとYouTubeにチャンネル作ってくる!」 「おまえら、YouTubeをなんだと思ってるんだ」 すべてはギルデンスターンの推論に過ぎなかった。 だけどもしそれが的を射ているとするならば、この世界はもう魔王タマタールの妄想の中。 郵便受けを開けると、神籠石大からの封筒があった。 差出人は蟹副教授。 オープンカレッジの案内。 精神医学学会の研究発表…… 少し前の僕だったら、1ミリも興味を持っていなかったと思うけど、なぜか惹かれた。 それにこの手紙、竹下さんのところにも届いたはずだ。 行けば、会えるかもしれない。 車に照り返す夕焼けの色は、メランコリックな甘い風。 「竹下、第一志望は大和の大学だって」 チャリを押しながら田村が言った。 つまり竹下さんにとって、こっちの大学は滑り止めってことか。 「医学部志望だろう? だったら倭国より大和に行ったほうがいいよ」 「でも、医学部だったら伯済にもあるし。大和なんか行かなくても」 「大和は近代国家だよ。倭国はほんの半世紀前まで呪術国家って言われてたんだ」 それに京畿の大学も大和の大学も、距離にしたら大差ない。国境はあるが、地続きだ。でも―― 「大和語を喋る竹下さんって、あんまり見たくないよね」 「文法は一緒だよ。もとは同じ国だったんだし」 わかってるよ、そのくらい。 大和語のイントネーションは中国語に似ている。 大陸から渡来したひとたちだから、そりゃあそうなんだけど。 「なんかさあ! 見返したいよなあ、大和の連中を!」 19世紀、米国より渡来した黒船に大和はあっさりと国を開いた。対する僕らの倭国は全海軍力を上げて接岸を阻止。それが仇となって今の凋落があるのだろうが後の祭り。それに、当時としてはそれで正しかったのだと思う。 「なあ、古澤」 「どうした」 「ここの欅、折れてたよな?」 「そうだっけ?」 通学路のガソリンスタンドの五叉路を斜めに入って二つ目の信号。雑居ビルの床屋の前の欅の木を見て田村が言った。 「それもワールドシフトだよ」 「なんでもかんでもワールドシフトのせいにするよな、俺たち」 「サビから入る曲の元祖ってなんですかねぇ」 クラッシック畑の田中先生に訊くのも変だとは思ったけど、 「さあ、わからないけど、ミュージカルからじゃない? ミュージカルだと、しょっぱなでテンション上げなきゃいけないこととかあるじゃない」 と、畑違いならではの答えが返ってきた。 「たとえば?」 「詳しくはないんだけど……たとえば『どんな偉い大将も、最初は二等兵~』みたいな曲あるじゃない?」 「いや、知らないけど」 「あれって確か、戦前だと思うんだよね」 そうか。でもミュージカルの話になるとさっぱりだ。 「じゃあサビしかない曲もありそうですね」 「ああ、あるある。サビだらけの曲とか」 「あるんですか?」 「山本リンダの『狙い撃ち』とか」 「どんなですか?」 「サビサビ大サビサビ サビサビ大サビサビ」 「それ普通にAABA AABAって言いません?」 「山本リンダがヘソ出して踊ってんだよ? そんなのぜんぶサビでしょ」 一番街リズムレコードで、五つの赤い風船のレコードを買ってきた。 楽譜はざっとさがしても見当たらなかったし、フォークソングだったら耳コピしたほうが早い。 もしオープンカレッジで竹下さんに会って、もしギターを弾く機会があったら、彼女が好きだと言った五つの赤い風船を披露したい。 それから幾度か、春乃さんとは冒険にでかけた。 レベル83の僧侶。 ケペペスの詠唱。 はっきりとは覚えていなかったけど、でもどこか懐かしい気持ちがした。 冒険者の酒場に戻ったら、必ず三人でメロンソーダを飲んだ。 そんな折だった。 ――春乃がいない ギルドチャットにギルデンスターンの書き込みがあった いないったって、恋人同士でもないだろうし。 あれ? もしかして恋人だったんだっけ? ――たぶんワールドシフトだ このままだとすべての記憶が書き換えられる ――マジですか!? そうか……。もし春乃さんの出身が本当に尾道だったとしたら、尾道市が存在しないこの世界では……。 ――春乃さーん! いませんかーっ! 田村の書き込みも流れてくる。 ギルデンスターンは今までの冒険の記録をチャットにコピペし始めたが、それらは貼られると同時に消えていった。 春乃さんの記憶、記録がみるみるうちに消えていく。 ――これって、春乃さんはもう消えたってこと!? ――クソがっ! ――どうすれば覚えたままでいられるんですか? ――不可能だ 宇宙の修正力が働いてるから? ――魔王を倒す! ――ぜったい倒す! ギルデンスターンが連投する。 ――協力します! 魔王を倒しましょう! 僕もすぐに書き込んだが、どうして魔王を倒すのか、その理由もきっとすぐに忘れてしまうだろう。 ――嘘だ! 消えるわけがない! ワールドシフトなんか嘘だ! 俺は忘れない! 田村は少しパニック気味にチャットに書き続けた。十四・遠い世界に
勇者八重樫さんは、数多くの勇者とともに冒険したあとは、酒場勇者の道を歩んだ。 酒場勇者――スタジオヒーローとも呼ばれ、自分でパーティを組むことも、積極的に魔王を探し、倒しに行くこともない。ただ、依頼を受けて、パーティの穴埋めで日銭を稼ぐだけの存在。その話を聞いて―― 「堕落してると思う」 と、ギルデンスターンに言うと、 「たとえ勇者だろうと、食っていくのが第一だ」 と、そっけない返事が返ってきた。 勇者八重樫さんの実力は群を抜いていたという。 何年か前の御前試合、ゲストとして引っ張り出されて、そのショートソード部門で優勝を攫った。 もう何年も実戦には出ていないスタジオヒーロー。英雄の化石、職業冒険者、ディナーショー勇者。そう揶揄する人は無数にいた。他方、対戦者には数多の魔王戦をかいくぐった猛者たちが名を連ねる。 勇者八重樫さんがエントリーしたクラスは、ショートソード部門。でも現実には刃渡りの制限があるだけ、ロングソード級に柄を伸ばした得物を持ち込むものもいる。より実戦に近い状況を再現するためと、含み針、仕込み靴、毒霧、レギュレーションはなんでもあり。その試合に勇者八重樫さんは、ショートソード一本で挑んだ。 下馬評では、勇者八重樫さんの一回戦敗退。 しかし蓋を開けてみると一転。試合はどれも勇者八重樫さんペース。華麗、かつ、精緻な展開で勇者たちを圧倒した。 百戦錬磨の勇者の猛攻をショートソード一本で器用に躱し、小さな革盾で攻撃を受けて相手の懐に潜り込む。 一介のスタジオヒーローがなぜ? 多くの観衆がそう思ったはずだ。 「その試合、見てました?」 「録画したのは見たよ」 「ギルデンスターンから見て、勇者八重樫さんはどうでした?」 「まだまだかな」 「まだまだ……というと?」 「まだまだ隙だらけだ。試合で勝ったのもなんかの偶然だろう」 「そう言うんだったら、自分も出てみればよかったのに」 「賞金次第では考えなくもない」 ギルデンスターンは笑った。 「わざわざ手の内を晒すんだ。それなりのメリットがないとやらねぇよ」 右手を振って店内を指し示す。勇者八重樫さん程度のひとはざらにいる、特別じゃないと。 「そういう連中を集めたほうが強いパーティが組める。だけど勇者たちは決してそうはしない。自分の友だちやツテでパーティを組んで、戦いに挑もうとする」 まったく、若造はみんな愚かだ……と結ぶかと思ったら、 「だが、それが大切だ」 と、顔を緩めた。 「そうなのかなあ」 「自分じゃないだれかが勝てばいいんだったら、だれも冒険になんか行かねぇよ」 「つまり、魔王を倒すことよりも、自分が勝つことに意味があるってこと?」 「そう。虚栄心以外の動機で勇者になるやつはいない。だが、虚栄心では魔王は倒せない」 これを一般的には、《勇者の矛盾》と言うらしい。 虚栄心ってのは、いわゆるあれだな。 勇者になって金をがっぽがっぽ稼いで、駅前の藤井フミヤや鳩山邦夫が所有してるマンションで竹下さんと暮らす妄想みたいなことを言うんだな。 でも僕にはもう、そんな野心もない。 「僕もスタジオヒーロー目指しますよ。ギルデンスターンさんみたいに」 「だめだ」 「なんでですか」 「俺たちは、真の勇者の出現を待っているんだ。それになれ」 「真の勇者って?」 「真の魔王を倒すものだ」 「真の魔王って?」 「それをおまえが探すんだ」 神籠石大学。 二回目のキャンパス。 場違いなギターケースを抱えて、案内のチラシを見ながら公開講義の部屋を探した。 僕のギターは河童に壊されてしまったから、軽音楽部に置きっぱなしになってる象さんギター。 階段を上り、廊下の真ん中。想像したよりもずっと小さな教室。 案内の学生に促されて席について、あたりを見渡すけど、竹下さんはいなかった。 急に不安になる。 竹下さんが、この瞬間に消えてしまっていたらどうしようって。 遮光カーテンを閉じて、スライドが映される。 講義はなぜか視神経の話から始まった。 曰く、人間の視細胞の数はいくつで、これに対して視神経の数は異様に少ない、と。 これは、視細胞の情報が脳に一対一で送られるわけではなく、情報的には圧縮されたデータが送られることを意味するという。 「つまりこれは、脳と眼の間に、どのように情報を交換するかのプロトコルが存在し、脳は眼というデバイスに対して、どの情報を送れ、という命令を出している可能性を示唆するものです」 医学の話だと思っていたのに、内容はコンピューターサイエンスのようだった。 「これがどういうことか――たとえばみなさん、水槽脳をご存知ですか?」 と、唐突に話はSFに変わる。 水槽脳というのは、脳を体から取り出して培養液のようなものに浸けて、肉体の情報はコンピューターから与えて、ニセの現実を見せるというものだ。 先生も僕よりは少し洗練された言葉を使って、そう説明する。 「こうやって、ニセの情報を教えられた脳というのは、それがニセモノの世界だということは理解できないんですね。だからもしこの世界が水槽脳の世界……実際には存在せずにコンピューターで見せられている世界だったとしても、我々にはそれを識別することはできないんです」 まあ、それは、はい。漫画やアニメが好きでたくさん見てたらわかってますよ。そのくらい。 「じゃあ、この水槽脳を見破る方法がまったくないか? と問われると、実はまったくないわけでもないのではないかということが、私たちの最新の研究でわかってきました」 は? 「眼球と脳の間にプロトコルがあるという話はしましたよね?」 あ、はい。いま聞きました。 「水槽脳の場合、脳は自分のものですが、視神経はコンピューターに接続されて、映像はコンピュータが作った情報として与えられます」 それは知ってる。 「この、眼球デバイスに対して、脳は常にメッセージを送っているんですね。どの情報をよこせ、次はどこを見ろ、どのへんの解像度を上げろ、と」 そこは初耳。 「要はそこに、想定外のコマンドを送れば良いのです」 はい? 「眼球デバイスが通常は処理できないコードを送り、眼球アプリの外部に実行させればいい」 実行させればいいって、どうやって? 「で、この操作のことを、われわれは《インジェクション》と呼んでいます」 インジェクション…… 講義が終わってすぐに先生のもとへ走った。 ――インジェクションのこと、知ってます。 ――この世界はインジェクションで書き換わったんです。 そう伝えようと思ったけど、すんでのところで留まった。 僕のいうインジェクションと、先生のいうインジェクションはたぶん違う。 というか、僕が冒険者の酒場で経験してることがなんなのか、自分でもわからない。 言葉にできずに、先生と目があって会釈して、 「あの、ご招待ありがとうございました」 「ああ、軽音楽部の」 「古澤です」 改めて名乗ると、 「彼女とふたりで来てくれたんですね」 と、教授は僕の背後に視線を送った。 彼女? 教授の視線を追って振り返ると、竹下さんの姿があった。 「こんにちは。あの。声をかけるタイミングを見計らってました」 小首をかしげて笑う。僕の彼女。 キャンパスを歩いて、また自販機でパックのドリンクを買って、講堂の階段に座った。 僕の口から出たのは、 「いまも、五つの赤い風船が好き?」 だった。 竹下さんは少し噴いたような気がした。 「好きだけど、どうして?」 昨日と今日とがずっと地続きであることを信じられなくなっていた。 「いや、あの、ええっと。覚えてきたから、聞いてくれるかな、って」 「本当に? どの曲?」 「遠い世界に」 「あれって、オートハープじゃない?」 オートハープ? あの変な音色の楽器? 「あれ、オートハープっていうんだ。櫛でギター鳴らしてるのかと思って真似してみたけど、できなくて……そうか。謎が解けた」 竹下さんはくすくすと笑っている。 「でも、ギターのコードでちゃんと弾けるよ」 「本当に? 私、歌詞ちゃんと覚えてるかな」 あ、待って。歌ってくれるの? 竹下さんは頭の中で歌詞を追いかける。 「大丈夫。歌えそう」 えっ? マジで? 夢じゃなくて? 「じゃあ、前奏から行くけど、タイミングわかる?」 「うん。もちろん」 神籠石大学のキャンパス。木漏れ日の降る講堂の階段でふたり歌った。 竹下さんは僕の予想のオクターブ上。ふたりでオクターブ違いの主旋律を歌った。 田村の顔が思い出される。 ――フラグだね ……って。 なんのフラグなんだろう。 おまえが言うフラグって、いつ回収されるんだよ。 とめどない涙が流れてきた。十五・賢者・ローゼンクランツ
「河童の里へと降りて以来、声をなくした友がいるんだ」 と、ギルデンスターンが言い出して、僕はもう、 「はあ」 としか言えなかった。 そう言えば僕もかつて、水天宮近くで河童に会ってギターを叩き壊された記憶がある。あれはワールドシフトの前だったか、後だったか。 「魔王はおそらく不死身だ」 「はあ」 ゲームで必要なフラグが立ったあとのセリフをAボタン連打で送っているときの表情でギルデンスターンの話を聞いた。 「倒しても死なないから、封印するしかない。その方法を、その友が知っているはずだ」 「はあ」 「名は、ローゼンクランツ」 Aボタン連打以外のどんなリアクションができよう。 ただまあ。 「河童の里の話は興味があります」 ということで、僕もそのひとに会いに行くことになった。 「サンチェーンは?」 と、田村のことも誘ってくれたのに、田村は沈んだ様子で、 「俺はいい」 とだけ。 僕らには何か喪失感があった。それは僕よりも田村の方に、より大きな胸の空白を与えているようだった。 ローゼンクランツは、鳥飼小学校近くの病院に入院していた。 面会時間ぎりぎりの夕刻、夕焼けの裾に紛れて部屋に滑り込むと、ローゼンクランツはベッドに体を起こし、ただ窓の外を見ていた。 「吟遊詩人をひとり連れてきた」 吟遊詩人と紹介されるのも違和感がある。 「まだレベル12ですけど」 挨拶も完全しかとされて、ちょっとバカみたいだ。 「タマタールを封印する。師匠の力を貸してほしい」 師匠? 年齢はそう離れているようには見えないけど、ギルデンスターンの師匠。 病室の隅にはギターケース。 刹那、僕にはそのケースの中のギターが折れていることがわかった。 ――だから言葉を話せないんだ。 「もしかして、河童にギターを壊されたんですか?」 静かに問いかけると、やっとローゼンクランツに僕の声が届いた。 ゆっくりと振り向いて、深い瞳が僕の顔を覗き込む。 その瞳から、彼の音楽が流れ込んできた。 ハードロック系の曲。大昔に聞いたことがあるような。ギターはB.C.Rich Mockingbird? 違う。なんだろう、この形。 ローゼンクランツはなにも言わない。 「タマタールを封印しないと、この世界はどんどん壊れていく。頼むよ」 ギルデンスターンは呼びかけ続けたが、ついにその唇が動くことはなかった。 翌日。 「好きな人がいた気がする」 と、田村。 僕は急に竹下さんのことが気にかかり、竹下さんの姿を胸に浮かべる。 大丈夫だ。彼女はまだ消えていない。 でも田村が好きだったひとのことはわからない。 「だれ? クラスの子?」 クラスの子だったら、加納が作ったメモがある。その中に名前があるかもしれない。でも――そのリストもワールドシフトで書き換わってる可能性が高い――だったらもう残っているのは喪失感だけ。 「覚えていない」 いったいだれを失って、そのひととの間にどんな思い出があったのかさえわからない。 「そうか」 田村は涙をこぼした。だれのための涙かもわからない涙を。 「大丈夫だよ」 「大丈夫ってなにが?」 「すぐに――」 ――忘れるよ。と言いかけた言葉を僕は飲み込んだ。 「すぐに――魔王を倒して、元の世界線に戻すから」 その日はギターを持って病室へ行った。 ローゼンクランツに波長を合わせて、胸に流れ込んでくるフレーズをそのまま音にした。エアロスミス系のポップなハードロック。ときに重厚に。ブレイクを挟んで。また立ち上がる。ドラマチックなコード展開。 何曲か奏でると、ローゼンクランツはよろよろと立ち上がり、ギターケースからギターを取り出して見せた。 Mockingbirdに似た破壊されたギター。 「あなたも、河童にギターを壊されたんですね?」 そう訊ねると、男はかむりを振った。 「違う。俺が壊したんだ」 自分で? 「そう。河童に壊されたと信じていたが……俺が壊したんだ」 ロビーの自販機で缶コーヒーを買った。 夕刻の浅い陽が深い影を作る。 久しぶりに病室を出たというローゼンクランツ。ギルデンスターンは目を細め、プルタブを引いた。 「河童の里に降りたのは、魔王を封印する術を探るためだった」 ローゼンクランツはゆっくりと、喉の奥から押し出した。 「あのときはすまん。忙しくて、一緒に行けなかった」 「かまわんよ。おまえを犠牲にせずに済んだ」 言葉と言葉の間には感情の波が揺れた。ギルデンスターンは渋い表情を浮かべて、言葉を飲み込む。おそらくその脳裏に、犠牲になった仲間の顔が浮かんだのだと思う。 「魔王の封印ってのは、基本的には『生き返っても即死ぬ装置』でやるんだ」 年老いた勇者はうつむいたまま語った。 「聖水を入れた壺、トゲだらけの箱、そんなものに封じていれば、生き返ってもだいたいは即死ぬ。だが、たまに『そもそも死なない魔王』がいる。それを封じる方法を知りたかった」 「それを、河童が知っていた、と」 「そう。河童の里へ向かったのは四人。俺たちは各自アーモンドグリコ1箱を持って、河童の里に降りた」 アーモンドグリコ。 「ところが、河童の里への旅程は思ったより遠く、すぐに食料は底を尽きた」 食料、アーモンドグリコ。 「そして、各自アーモンドグリコが残り1個となったとき、俺たちは決断するしかなかった。全員で1日だけ生き延びるか、ひとりがこれを食べて4日生き延びるか……」 「それでどうしたんですか?」 「ひとりが4日生きる道を選んだ」 「そのひとりがあなただったんですね?」 「そう。翌日、仲間は飢えて死んだ」 ローゼンクランツがアーモンドグリコに例えたもの。 「その直後だった。河童の里にたどり着いたのは……」 それはストレートに食料だったのかもしれないし、 「それで、不死の魔王を封じる方法はわかったのか?」 命だったのかもしれない。 「ああ。わかったよ」 「その方法は?」 ギルデンスターンが訊くと、ローゼンクランツは深く息を吐いた。 「魔王自身が執着しているものに閉ざすんだよ」 それはつまり――タマタールだったら、日本国統一とか? ほどなくしてタマタール討伐隊が編成された。 冒険者の酒場で精鋭18人が集められ、まずは魔王の情報を得るべくその行方を追った。 タマタールはやや南下し、八女市吉田の岩戸山古墳に潜んでいることがわかった。 18人の討伐隊は3つのグループに編成され、連絡を取り合って古墳内へと侵入。 僕と田村は前回と同じように、音声チャンネルで彼らの動向を聞いていたが、そこに聞こえた声は意外なものだった。 『いない』 『抜け殻だ』 抜け殻? 『《インジェクション・脱皮》』 脱皮。 『新たな肉体を獲得したってわけか……』 『いったい何のために?』 『おそらくは、より強い肉体を得るため』十六・ファタ・モルガーナ
――島がひとつ消えている ギルドチャットに書き込まれた。 ――島とは? ――博多湾にあったはずだ もう名前を思い出せない ――ああ! あった! 能古島だろう? ――そうそれ! ――マジで消えてる…… たしか、倭の遺跡があったはずだ。それがなんらかの矛盾で消えたんだ。 チャットに流れる情報は多岐にわたった。他のギルドの情報も次々と転載される。日本中、いや、世界中の現実が書き換わっているらしい。しかも、書き換わって数時間も経てば、あらゆる記録、あらゆる記憶がそれに追従して書き換わる。 冒険者の酒場もにわかに慌ただしい。 「結果だけを見ればなにも問題はないんだけどな」 「たしかにそうだけど、こうして話している次の瞬間には僕が消えてるかもしれないってことでしょう?」 「まあ、そういうことなんだが、それだって過ぎてしまえば問題じゃない」 「そうかもしれないけど――」 僕は嫌だ。 「今までずっとクラスのだれかのことを思ってきて――」 それは取りも直さず竹下さんのことだけど―― 「――その記憶が急になくなるのは嫌だよ」 「その子を思ってきたって事実だって、昨日もそうだったとは限らないんじゃないか?」 そうだけど。 「昨日まで別のだれかのことが好きで、今日そのひとはいなくなって、記憶が書き換わったのかもしれない」 たしかにそうなんだけど。 翌日、井上陽水消失。 ――井上陽水って能古島出身だっけ? ――いや、能古島の片想いって曲があるけど、本人は……。 ――歌っただけで!? 家に帰ると、居間にいた姉と母はそそくさと台所に姿を消し、親父から一言、 「座れ」 と、促された。 テレビはちょうど夕方の時代劇の再放送を終えた。 親父は対面に座り、少し間をおいて話し始める。 「冒険者の酒場には毎日行ってるのか」 「毎日じゃないけど、うん」 「かどの田中さんとは会うことがあるか?」 田中さん? 「いや、会わないけど、どうして?」 「あそこの息子が冒険者の酒場に登録して、七百万の鎧を買って、借金漬けになっとる」 田中さんの息子ってたしか、大学生だ。 あの店に来てたんだ。 「それで毎日のように借金取りが来て、利子も払えんと家を売るしかなくなると言って、商売道具の軽トラを手放すことになった」 ふーん。と、相槌を打ちそうになるけど、そうか。親父は僕も同じようになることを心配しているんだ。それで意見を挟もうとしたけど、親父の言葉は途切れずに流れた。 「姉は姉で、還元教に入信して、盆の墓参りも還元教の教えに逆らうから行かんと言うとるそうだ。今日も田中さんの奥さんが来て泣いて訴えとった」 似たような話は、田村家の話としてうっすらと知っている。 「僕は還元教には入らないよ」 鎧も買わない。 「田中さんの娘も、最初はそう言うとった」 「僕は田中さんじゃないし」 そこにちょうどニュースが流れ始める。 ――勇者硯葉さんがパーティメンバーを募集しているそうです。 ――硯葉さんというと、あの伝説の魔王を倒した!? ついに硯葉さんも動き出した。 ――そうなんです。ちょうど硯葉事務所にカメラが行っております。 硯葉さんは「例えばの話ですけど」と前置きして、 「魔王を放置しておくと、ある日突然、人類が昆虫人間になるかもしれないんです」 と説明した。 ――昆虫人間! それは怖いですねぇ! インタビュアーは大げさに驚いて見せて、硯葉さんも渋い顔を繕う。 わずか2分足らずのコーナー。 みなさんも気をつけてこの週末お過ごしください! それではスタジオさーん、お返ししまーす。 テレビが不安な時間に区切りをつけると、父は一言。 「どうせ騒ぎを大きくして、なんか売りつけようとしているだけだ」 顔に不機嫌な皺を寄せた。 僕の父にとって、いや、世界中のだれにとっても、ワールドシフトはどうでも良い問題だった。 「僕たちが気が付かない間に、僕たちの世界が変わるかもしれないんだよ」 ――と、訴えたところで、だれも気が付かないのであればなにも起きてないのと同じ。 「田中さんの息子も、そう言って鎧を買わされたんだ」 で、終わってしまう。 「買わされたんじゃなくて、自分の意志で買ったんでしょう?」 「自分の意志で買ったように仕向けるのが、連中の手口だろうが」 話してもらちがあかない。 ワールドシフトでなにが起きるかわからないんだよ? とつぜん僕や姉ちゃんが消えてしまうかもしれないんだよ? それでもいいの? ――と訴えたところで、これじゃただの狂信者だ。 昆虫人間にたとえて説明した硯葉さんはさすがだ。父の説得で僕の考えが変わることはなかったけど、父の前では折れてみせるしかなかった。 翌日。昨日の今日で冒険者の酒場に行くわけにもいかず、三本松公園のベンチでギルドチャットに参加した。 ――4ギルド連合して討伐隊を結成する との簡単な説明ののち、ファタ・モルガーナという参加者三百人を擁する別のチャットチャンネルに誘われた。参加するギルドは僕ら肉桂文鳥団のほか、クラッシュ・クラン、ライト・ボックス、平成麦茶会。 ――ライト・ボックスは大和のギルドだ ――はじめまして! ――酒場が勇者様だらけwww 活気づくチャットチャンネルに、田村も発言するが―― ――うわー見てぇー ← 田村 その書き込みは一瞬でウインドウの外へとスクロールしていった。 「おまえはひとりで行ってもいいんだぞ」 「そんなことしたら、おまえのお守りはだれがするんだよ」 「僕のお守りだったのかよ」 ギルドチャットに酒場の写真がアップされると、居並ぶ戦士たちの姿が見えた。 「この中に、勇者山本さんや、勇者八重樫さんもいるのかな」 「伝説の勇者が!」 「あとでギルデンスターンに聞いてみる」 「いたら滾るwww」 冒険者たちで知恵を出し合って、ワールドシフトの状況をモニターする方法が確立されていった。ネットワークでの情報差分から検出するらしい。ファタ・モルガーナにはIT関連の技術者もいたし、現役の大学教授も名を連ねていた。 そこで出た結論は、出雲尾道間の万里の長城が存在しないのが本来の歴史ではないかということだった。 ――でもまさか…… ――私、修学旅行で行ったんだよ、万里の長城 ――だからその記憶も偽の記憶なんだよ 偽の記憶――とは言え、実際に万里の長城は存在する。それが原因で矛盾として存在できなくなったひとが、次々と姿を消しているらしいが、それもすぐに修復される。そちらのほうが正しい現実なんだ。 それでもこの事態を解決すべきか、という点には疑問が向けられた。 この世界は万里の長城ありで回っている。そこから万里の長城が消えたら、また新たな矛盾が生まれ、世界は変わってしまう。 それでも僕たちが意志を一つにできたのは、魔王タマタールが元凶であることが明らかだったからだ。魔王を倒して解決するのなら、その解決した世界が正しいと。それにみんな、魔王と聞いたら倒さざるを得ない性分をしていた。 タマタールは第二形態に変態したと目され、その候補は全国に12体ほどが確認された。 「こいつらを一気に倒す」 というのが、ファタ・モルガーナの作戦だった。 親から言われたこともあって、僕はもう深入りはやめようと思っていたのだけども、ギルデンスターンたちが担当する魔王が神籠石大学裏のダンジョンにいると聞いて、最後にそこだけは覗いてみようと思った。 「レベル17ですが、かまいませんか?」 「わかった。俺が掛け合う」 その週の週末、ファタ・モルガーナはついに硯葉さんのギルドとも連帯、総勢八百を超える冒険者連合が倭国・大和の国境を超えて組織された。十七・水槽検体
小料理屋葵は両替町にあった。 自転車で通りかかり、脇の玄関の郵便受けを見ると、上から六番目に竹下智子の名があった。一番上は祖父母だろうか。続いて両親、兄、そして竹下さん。 今日も消えていない。 そんなことで胸をなでおろした。 神籠石大のダンジョンは、キャンパスからは離れたところにあった。 駐車場代わりの広場には小さな森もあって、小川の流れ、その土手に隠れるように小さな洞穴が空を仰いでいた。 今日、全国12箇所で同時に魔王討伐隊が行動する。 神籠石大チームは六十名。 突入は六人編成の四組、このほかに通信員、補給員、記録員などがダンジョンに入り、半数が外で待機する。 「前回おまえたちを連れて行かなかったのは失敗だった」 ギルデンスターンは語った。 「おかげで記憶も記録も何も残っていない」 「でもそれは、僕らが行ったところで」 「今回は何があろうとも、インジェクションはおまえたちを逃がす一回しか使わない。俺たちの突入が無駄に終わっても、次の時代に可能性をつなぎたい」 「でも……」 僕は固唾をのんだ。 「そんな大役、務まるわけがない」 溜息。僕とギルデンスターンと同時に、それぞれ別の意味の。 「グラミー賞を獲ると豪語したのは嘘だったのか?」 ギルデンスターンは悪戯に笑うけど、それで緊張がほぐれるはずもない。 僕と田村は同じチーム。あとはギルデンスターン、ローゼンクランツのふたりが吟遊詩人。後衛は回復役僧侶とクラウドコントロール役の魔法使い。 「前衛は?」 「曲でバフをかけて防御力・攻撃力を確保する。今回はそれで押す」 「封印、できますかね……」 「汎用の封印壺は持ってきた。それでうまくいくかどうかは運次第」 照明隊が先に入った。各自でライトは携帯していたが、トップレーン洞窟のような不便さはない。自然の洞窟を抜けるとすぐに石積みの水路のようなところに出る。地図を見ながら先へと進んだ。 古い淀んだ水の匂いがする。カエルを泳がせた水槽の匂い。水路の脇の小路を歩くが、たまに途切れ、水のなかを歩いた。水に入るとメタンの匂いが浮き上がる。粘度のある水面が小さく泡立つ。 細い脇道へ入り、その突き当りのはしごを登ると、古い研究室に出た。ナトリウム灯らしき黄色い光。曇った水槽が並び、緑色の液体がコポコポと音を立てる。 「ここは?」 「この大学の医学部の研究室だ」 「医学部の?」 「水槽の中を見てもいいが、気を失うなよ」 そう聞いた次の瞬間、田村の悲鳴が反響した。 「これは……!?」 田村は水槽を指差す。そこには、緑色の液体に浸かった人間らしき顔があった。 「河童だと言われている」 「河童!?」 たしかに頭頂部は皿状の素材で覆われて、髪の毛もない。だけど体格は人間と変わらない。老若男女、いろんな河童がいる。ホルマリン漬け? いや、違う。河童は生きているように見える。田村はその場でリバースし始める。 「しーっ」 ギルデンスターンとローゼンクランツがギターを構える。 かつん、かつん、と足音が響く。 反響してその源はわからない。 「来てしまいましたか――」 館内に響いた。 前方に影がゆらぎ、後衛のふたりが距離をとって展開する。 「――古澤くん」 その声とともに、男が姿を見せた。 「蟹副教授!?」 思わず口に漏らすと、 「知り合い?」 田村が不安げに僕の顔を覗く。 「ファタ・モルガーナと名乗る武装集団が、日本各地で蜂起したとは聞きましたが、ここにも来ましたか」 「魔王・カニゾエだな」 「私が魔王!? これは異なことを」 ギルデンスターンがギターのネックを両手で握ると、ボディから刃が飛び出し斧になった。ローゼンクランツも同じように、大剣に変形させたギターを構える。その後ろ、僕が構えるギターは象さん。小さい刃をぴょこんと立てた。 「そういきりたちなさんな。良いものを見せてあげよう」 蟹副教授が背を向け歩きはじめると、田村が携帯を見せてくる。 ギルドチャットで各隊に指示が出ている。 ――挟撃 魔王・カニゾエ出現の報が伝えられ、別働隊が背後へと回り込んでいる。こちらの体制が整うまでしばらく蟹副教授のペースに合わせるということか。 「古澤くんは、私の水槽脳の講義を聞いて、どう思いました?」 歩きながら問いかけてくる蟹副教授。 ギルデンスターンの顔を見上げると、会話を続けるよう顎をしゃくる。 「この世界が水槽脳の中かどうか、見極める方法があるという話ですか?」 「そうです。優秀じゃないですか。ちゃんと覚えていてくれるとは」 「見極める方法があったとして、見極めてどうするんですか?」 「学問ってのは、そう単純なものじゃないよ。私はただ、見極めるだけだよ。それをどうするかはまた別の学者の仕事だ」 「それじゃあ、人類がどこへ向かうかはわからないじゃないですか」 「ああ、そうだよ。我々が目指す先など、だれにもわからない」 「その道が誤りだったらどうするんですか?」 「そんなことを言い出したら、内燃機関だって、原子力だって誤りだったかもしれないじゃないか」 失笑した。言うに事欠いて。そんな、まさか。 「笑いましたね。古澤くん。事実私たち人類はあと百年もすれば滅びますよ。戦争、飢餓、異常気象、いずれかの理由で。それはなぜですか? 科学を発達させたからじゃないんですか? それをだれか誤りだと指摘しましたか?」 教授はひとつの水槽の前で足を止めた。 「御覧ください」 水槽脇のスイッチを押すと、ぶーんという小さな唸りとともに水槽に泡が満ちた。 「この検体はまだ、脳を取り出す前だ」 「脳を取り出す?」 水槽のくもりが晴れ、無数の泡の軌跡が見える。 「他の検体は頭蓋骨に蓋があっただろう?」 蓋――? 「彼らの脳にインジェクション信号を与え、返ってくる信号を調べ、この世界の外側にある世界を探っているんです」 彼らは……河童じゃなかったのか……? 水槽の細かい泡が消えると、液体に広がった長い髪が見えた。 柔らかなシルエット。 それは――一糸まとわぬ竹下さんの姿だった。 動悸が胸を貫く。発散しかかる意識を胸の中に拾い集めるが、思考は四散したまま。呼吸も、鼓動も、僕の肉体の外へと走り出す。 水槽のなかの竹下さんが僕に気がつく。視線が交わると、胸を隠した。 「竹下さんに何をしたぁっ!」 自分で発した声が、他人の絶叫のよう。 「何を?」 蟹副教授は慇懃な甘い声を漏らす。 「私の仮説に興味を持ってくれたんで、協力を仰いだんです」 刹那、投光器のライトが四方から蟹副教授を照らした。 同時に無数の勇者たちが躍り出て、教授を取り囲んだ。 僕はただ涙がこぼれてくる。 「見ないで……竹下さんを見ないで……」 竹下さんはこの男に脱がされたんだろうか、自分で脱いだんだろうか、ここに入る時ちゃんとバスタオルで隠したんだろうか、変なことはされていないだろうか、着替えはちゃんと畳んで保管されているんだろうか、どうでも良いことばかり脳裏をかすめる。 10人以上の歴戦の勇者たちに囲まれ、蟹副教授は高らかな笑い声をあげる。 「大脳を取り出されたものたちも全員生きています。私を倒せば、彼らは死を迎えるしかありませんよ?」 記録員が蟹副さんにカメラを向けている。その後ろには全裸の竹下さんがいる。 撮るな―― 訴えたいのはやまやま、この地球の存亡の危機だ。体を動かしてその射線を遮ってみるけど、記録員はすぐに立ち位置を変える。 撮らないで。竹下さんの裸を撮らないで。だれも竹下さんを見ないで。 ローゼンクランツが大剣をギターに戻し水平に構え、ピックを高く掲げた。 総攻撃を示す合図。 一瞬の静寂。振り下ろされたストロークで、決戦の火蓋が切られた。 勝負は一瞬。 魔王・カニゾエに反撃の隙も与えず、時間にしてわずか数秒の後、その身はリノリュームの床を赤く染めた。そしてすぐに女性スタッフが竹下さんを保護した。 断末魔さえない最後。 「封印は?」 「ああ。念の為に死体を集めて封じておく」 僕は――力の抜けた足を床の上に立て、バランスを失う上体をギターで支えた。 竹下さんの裸を見ないで。だれも。十八・大魔王降臨
竹下さんの体にはバスタオルがかけられた。 「デイリーさん、彼女があなたのそばがいいと言ってるんで」 ギルドのひとに促されて、すぐに彼女の肩を支えた。 バスタオルの下は薄い肌色のレオタード。全裸じゃなかったんだと少しほっとした。 でも、服はどうしたんだろう。レオタードは本人が着たんだろうか。このままの姿で帰ったらご家族はなんというだろう。もし制服をどこかで脱いでるとしたら取りに行かないと、明日から着る服に困る。 とめどなく脳裏を駆け巡る。 そんなこと、ワールドシフトで人類が昆虫になってしまうことに比べたらなんでもないことなのに。 ダンジョンを出ると、大学がなくなっていた。 小川の土手を上がると見えたはずの一号館の大きなビルもない。 それに、このあたりは駐車場だったはずだ。 またワールドシフトが起きたのかもしれない。 竹下さんは不安からか、ずっと僕の腕に抱きついて震えている。 「どうしたの? 寒いの?」 唇が青い。 救護班からエマージェンシーシートを受け取って、竹下さんに掛けると、 「古澤くんも」 震える唇が動いて、ふたりで頭からシートをかぶって、冷めた体を温めた。 手元のスマホには、各地から魔王撃破の情報が集まってくる。 そこに安堵の声はない。ただただ緊張が高まっていく。 ――ギルデンスターン 気をつけろ 駆け足のタイムライン。 ――神籠石大付近でワールドシフトが急激に進んでいる 魔王がいる この近くじゃないか。 にわかに緊張が走る。 不安げにスマホを覗く竹下さんに、 「大丈夫。僕たちはもう大丈夫だよ」 そう伝えると、 「その光る板はなに?」 と、問い返された。 「これはライン。ギルドって実はラインのグループなんだよ」 「これがラインなの?」 「違う。これはスマホ」 ちょっとまって。スマホを知らない? そう言えば、竹下さんからスマホに電話がかかってきたことはない。電話はいつも古澤畳店の黒電話にかかってきていた。でもいまはそんなことを考えてる場合じゃない。竹下さんの唇は寒さにガチガチと震えている。 「大丈夫?」 「うん。でもちょっと寒い。古澤くん。寒い」 水に濡れた黒髪。濡れたブラウスから透ける素肌。 「待って」 水に濡れてるはずがない。ちゃんとバスタオルで拭いたはずだ。それに、さっきはレオタードだった。どうして制服を? 「温めて。古澤くん」 僕の腕を取る――だけど―― エマージェンシーシートの外でアラートが響いている。 「ワールドシフトが起きてる」 緊迫する声が聞こえる。 「歪がある、この近くだ」 交差する足音。 「インジェクションでカウンターを当てる」 竹下さんが僕の手をとって、肌へと沿わせる。 ――幻覚だ。この竹下さんは僕の幻覚だ。 車の音。ドアが開いて足音が響く。 「魔王がいる。警戒しろ」 ギルデンスターンの声。 ギターを斧に変形させる鈍い金属音が響く。 ここに魔王がいるとしたら――それは竹下さんだ―― だれかの手が僕らを覆ったシートに掛かる。 「守ってあげる」 竹下さんの目が赤く光った。 ギルデンスターンがエマージェンシーシートを剥がすと同時に、竹下さんの目からレーザービームが走った。 光線はギルデンスターンの肩を焼き、その先端は町へと抜け、遠くに悲鳴が聞こえる。 サイレンが響く。 「魔王出現。神籠石ダンジョンポイントA」 通信班の声。 「勇者各位、集結願います。繰り返します、勇者各位、集結願います」 勇者たちがこちらに向き直る。 竹下さんは立ち上がり、レーザーでその影を焼き払う。 「《インジェクション・ミラールーム》!」 ギルデンスターンの声と同時に、あたりの空間が歪む。 竹下さんが放ったレーザーは無数のプリズムに屈折し、空へと走り抜けた。 「チッ」 竹下さんが舌打ちする。その背中から四本の触手が伸びる。 ローゼンクランツの攻撃。これを竹下さんは左手で受けて、触手を叩き込む。 「今までかばってくれてありがとう、古澤くん」 「どうしたの、これ?」 「私が魔王。こんな世界、破壊してあげる」 どうして!? どうしてそうなるの!? 竹下さんは無類の力で勇者たちを薙ぎ払ったが多勢に無勢、四方から攻撃が浴びせられる。 竹下さんの悲鳴。 「古澤! 離れろ! グランド・クロスを叩き込む!」 ギルデンスターン! その後方から光の矢が放たれ、竹下さんの肩にヒットする。 ――ラスボス戦で戦士が体験する痛みは、タンスのカドに足の小指をぶつけたときの三千回ぶん――いつか聞いた言葉が思い出される。 「攻撃をやめろーっ!」 僕は思わず竹下さんの前に躍り出る。 「それはどっちに言ってるんだ、古澤っ!」 「ファタ・モルガーナ! おまえらに言っている! 攻撃をやめろーっ!」 「ふざけるな古澤! 目を覚ませ!」 背後に気を取られた隙にギルデンスターンの斧が竹下さんにクリーンヒット。肋骨に刃がめり込み、血が吹き出す。 「目をさますのはお前らだ」 両手でギターを構えると、そのボディから漆黒の刃が飛び出した。 が、攻撃に出る前に脇腹に矢が刺さった。 いてぇっ! こんな矢くらい……。 鉛筆くらいの太さの棒が脇腹に刺さってる。何センチ刺さってるんだ、これ。 いてぇっ…… ゲームでいうとダメージ値はダイス一個ぶんくらいだろう? こんなもんで……息できないんだけど……。 「おまえでは俺たちには勝てない、古澤。レベル差を考えろ」 ギルデンスターンがギターアックスを僕に向ける。 「うるさい……僕は……竹下さんを守るんだ……」 声の半分は脇腹の痛みに持っていかれる。内出血か。矢が刺さった周りの皮膚が赤黒く変色している。 「古澤っ! よく見ろ! おまえが庇ってるのは竹下じゃない!」 田村の声。 なんだって? 痛みをこらえ振り返ると、竹下さんの影はしゅうしゅうと黒い瘴気を放っている。 「実体じゃない。影だ」 影!? 何の!? 瘴気は僕の腕にまとわりついて実体を取り戻す。 気がつくと僕の象さんギターは、いつの間にか水色のフェンダー・ムスタングに変わっていた。 これは……NIRVANAのカート・コバーンが、ステージで叩き壊したギター…… そしていつの間にか、左手にももう一本のギターがあった。 ジミ・ヘンドリックスがステージで燃やしたハンドペイントのストラトキャスター! どういうことだ!? 両手に持ったギターから、闇の触手が伸びる。 もしかして……僕が……魔王なのか……? 朦朧とする意識のなか、河童の声が思い出される。 ――おまえが忘れていったギターはこの、カート・コバーンがステージでブチ壊したギターカパ? それともこっちの、ジミ・ヘンドリックスがステージで燃やしたギターカパ? あのときの契約? それにしても…… いてぇっ…… 矢鴨なんか矢が刺さったまま普通に生きてたのに。 矢鴨以下か、僕は。 「古澤。すまんな。おまえには期待したんだが、仕方がない」 ギルデンスターンが僕に詰め寄る。 思わず両手のギターを振り回すが、脇腹の痛みで手が上がらない。 「僕は……」 僕は河童に騙されたんだ。 ギルデンスターンは斧を構える。 「でも……それだけ……」 たしかに僕は河童と、契約してしまったのかもしれない。 「さらばだ、幹夫」 だけどそれは! 死をもって償わなきゃいけないほどの罪なのか!? 息ができない―― 吸っても吸っても酸素が足りない―― どうして僕はあえぐばかりで何も言えないんだ! 目の前、大上段に掲げられる銀の刃。 ――そのとき。 「あいや待たれい!」 「待たれよ勇者方!」 芝居臭いセリフとともに、黒ずくめの者たちが乱入してきた。 「またお前らか!?」 田村が素っ頓狂な声を上げる。 「チッ」 ギルデンスターンが舌打ちする。 「我ら、魔王弁護連盟!」 「わずか17レベルの魔王を10人のカンスト勇者で囲むなど言語道断!」 そうだった……僕まだレベル17なんだ…… 「そのアマチュア魔王の弁護、我らが引き受ける!」 なんなんだこの展開……十九・側近ディストメア
気がつくと僕は、薄暗いビルの一室にいた。 「ここは?」 「ここは元トップレーンのバックヤード」 「トップレーンの?」 たしかに周りを見渡すと、ボーリングのピンや大会景品のトロフィーが無造作に散らばっていた。 「そう。閉鎖されたボーリング場。ヤクザ映画ではよくヤクザの隠れ家として利用され、連れてきた一般市民をリンチしてる場所です」 その情報、必要なのかなあ。 「三池崇史、愛と誠。白石和彌、凪待ち。原田眞人、RETURN」 それ聞いて意味あるのかなあ。 「僕は、どうなるんですか?」 「あなたにはこれから、勇者たちと戦っていただきます」 「戦うったって……」 「レベルは99に上げておきました。次は対等に戦えるはずです」 「そんなことできるんだ」 「それと、不死身にしておきました」 「不死身……」 「死んでもだいたい、3分で蘇ります」 「あ、待って」 「なんでしょう?」 「痛みはあるんだよね?」 「ああ、はい。普通に痛いです」 普通に痛いんだ。 「あと、死んでる間に片足を切り離されて隠されたりしたらどうなるの?」 「探してください」 自分で探すんだ。 「でもあなたは、魔王タマタールの生まれ変わりなので、かなり強いですよ。切り離された手足くらい、普通にコントロールできるはずです」 そうか……。良かった……。 ……って、いいのかな。 「次に魔王様に、側近を紹介いたします」 側近? 「こちらになります。これからは手足のように使ってください」 紹介された側近は河童だった。 「河童ではありません。魔王ディストメア様です」 「魔王ディストメアっていうと……」 「祇園山古墳であなたがたに倒されそうになった」 「あのときの!」 あのとき確か僕は魔王を討つことを躊躇って、そうこうしている間にこの人たちが現われて身柄を拐われたんだ。 「大魔王デイリーヤマザキ」 いいのかな、その呼び方。 「魔王とは箱です。覚えておいてください」 魔王弁護連盟のひとは語った。 「魔王とは何か。それは封印された箱そのものなのです」 「箱が魔王?」 「違います。魔王が箱です」 「同じじゃないのか?」 「同じです」 めんどくせ。 「封印される前のディストメアは、ただの少年でした」 「しかし、集落に謎の疫病が広まり、働き手が失われるるほどに人は不安になり、希望を求めました」 「希望って?」 「すなわち、魔王を封じれば災いは過ぎ去るのだという間違った希望! その有り得ぬ希望にすがったのです」 「じゃ、じゃあ、ディストメアは何も悪くないのに封じられた?」 「そう。無類のキュウリ好きだった彼は、大人たちから『お前こそが魔王なのだ。魔王だからキュウリが好きなのだ』と責められ、自分でもそれを信じるようになり、封じられたのです」 「魔王が封じられると、人々の争いは収まりました」 ていうか、河童じゃないんだ。 「罪なき子どもひとりを犠牲にしたのです。自らの手を汚した以上、怒りを抑え、手を携えるしかありません」 まあ、いいか。 「そうして犠牲になったのが魔王」 「そう。魔王というのは、ただの箱。魔王の名を記し、吊るし上げるための。その中に閉ざされるは、罪なき人間なのです!」 「それじゃあ僕も?」 「そう! この世界にワールドシフトをもたらした世紀の大魔王もただの箱!」 「ワールドシフトが起きていた証拠などない! このままでは人類は昆虫人間になってしまうという不確かな恐怖心に煽られ、魔王という箱をでっちあげ、そこに罪なきものを閉ざした! それがあなたなのです!」 「待って! だったら話せばいい! ギルデンスターンともローゼンクランツとも話して、本当のことをわかってもらったらいい!」 「ようござんしょう!」 ようござんしょうって。 「大魔王としていかに振る舞うかは、大魔王ご自身が決めること!」 「我々魔王弁護連盟は大魔王に居城を用意いたしました」 なんと根回しの良い。 「大魔王温泉、大魔王リラクゼーションルームから大魔王史編纂室まで取り揃えた最高のラグジュアリーを、大魔王様のために!」 うわーい、大魔王史編纂室だぁ。 「そちらで襲い来る勇者たちを迎え、説得に励まれるとよろしかろうと存じます!」 やったるでー。 「それでは! 魔王ディストメア様! 大魔王デイリーヤマザキ様のご案内を!」 「おうっ! まかせておくカパーッ!」 語尾に聞き覚えがあるー。 魔王ディストメアの目から闇の渦が放たれると足元に重力の波が駆け抜け、次の瞬間、僕の体は薄暗い城の一室にあった。 そこには新鮮な藺草の匂いが立ち込める。 「ここは?」 「タタミ城カパ」 「タタミ城?」 「久留米市大石町の畳屋が一夜にして築き上げたカパ」 僕の父親じゃないか。 「息子に寿司を食わせるため、俺様に魂を売り、同業他社の仕事を奪ったカパ」 「ちょっと待てこら」 「ここは元は駅前のひなびたラブホだったカパ。駅前再開発事業の貸付金を不正に引き出し、全フロア総畳張りのタタミ城へと改装したカパ」 「不正に引き出しって、もしかしておまえの力でやったのか?」 コクコクコク。 このリアクションを知っている気がする。 「畳職人はこの城のタタミを張り替えると同時に絶命したカパ」 「えっ?」 「しょうがないから寿司は俺様が食ったカパ」 「食っちまったのか?」 コクコクコク。二十・大魔王城決戦
魔王一日目、訪れたのはギルド・クラッシュ・クランの主力メンバーだった。 「大魔王デイリーヤマザキ!」 ちょっとまて。せめてデイリーと略してくれ。 「まさか肉桂文鳥団に紛れ込んでいるとはな」 「だが貴様の命運もここまでだ!」 「貴様を倒して、真の歴史を回復する!」 「待て! 俺様の話を聞けっ!」 俺様……大魔王とおだてられると一人称も自然と変わるのか。 にわかに自信が湧いてきた。 「魔王というのは箱だ」 俺は訴えた。 「はあ?」 「つまりその、魔王というのは、おまえたち庶民が作り上げた幻想!」 「ふざけるなっ!」 「魔王のくせに何言ってんだ!」 「俺様を倒せばそれでおまえたちは安堵し、猜疑心から逃れられるだろう。だが逆に言えば、おまえたちはその安心のために俺を倒したいだけだ。仮に俺様が倒されたとしても、第二第三の魔王が生まれるだろう!」 「そうなったらその第二第三の魔王も倒すまで!」 「だから、そうじゃない! 魔王ってのは、おまえたちが求め、でっちあげてるんだ! 第四も第五も際限なく作り上げるんだよ、おまえらが!」 「第四だろうが第五だろうが、魔王ある限り私たちは戦う!」 「だからそうじゃないんだって! 魔王は、おまえ、なんていうか、ほら! わかんないかなあ! もう!」 「切れた! 説明できずに切れた!」 「やっぱ魔王だわ! 論理的なこと言おうとしてるけど破綻してるわ!」 もういい。 とりあえず、このパーティはめんどくさいので殲滅させた。 「さすがは大魔王様カパ。全体攻撃一発でクラッシュ・クランを壊滅させたカパ」 「さっきの技は……?」 「大魔王様の必殺技、大魔王ブレイクカパ」 大魔王ブレイク……。 「次はもうちょっと手加減して、瀕死にさせたところで説得を試みたい」 魔王二日目、勇者硯葉さんパーティ。 両脇を固めるのは戸田さん、永田さん? もうひとりは妙に若い……少年? 硯葉さんは司会者のような仕草で場を仕切った。 「ここで魔王が口上を述べるので、一応聞いておきましょう」 なんだその扱い。 勇者硯葉さんの声に若手が頷き、ぎゅっと剣を構える。 「俺様は大魔王だ――」 勇者硯葉さんは「ああ、はいはい」って感じで腕組みをして、若い勇者候補生が真剣な眼差しを僕に向ける。初々しい。僕も本当はああやって勇者になるはずだった。 「――だがその存在は貴様ら愚かな人間の手によって作られたものだ。俺様がいったい何をした? すべてはこの社会の歪がそうさせているだけじゃないのか?」 どうやら新人勇者の胸には響いているように見える。 が、硯葉の野郎。 「大魔王はみんなそう言うんですよ」 性根が腐ってやがる。 「苦笑しか出ませんよね」 永田さん! 「なんかもっと面白いこと言うかと思った」 戸田さん! 勇者硯葉さんは若い勇者に返答を促す。 少年は僕をにらみつける。 「大魔王デイリーヤマザキ!」 震える声を制し、通る声を響かせた。 「おまえの言うことにも一理あるかもしれない!」 おお! わかってくれるか! 「だが、お前が重ねてきた悪行の数々は、決して許すことができない!」 「だから俺様がどんな悪行を重ねたかって聞いてんだ! 何もやってねえんだよ!」 ビビりあがる新人。 「くっ……らちがあかない……」 「らちがあかねぇのはこっちだよ! 俺の話を少しは聞けっつってんだよ!」 戸惑い、目を泳がせる。 「前々から疑問だったんですけど」 永田さんがのんきに口を開く。 「魔王って、なんでこうやって無駄に自分語りするんですかねぇ」 む、無駄に自分語りぃ……? 「安っぽいですよねぇ」 や、安っぽい……? もういい。 とりあえず殺した。 「勇者硯葉さんもたいしたことなかったカパ」 「ああ。いつの間にか俺様は恐ろしい力を手に入れたらしい」 魔王三日目、ついにギルデンスターン登場。 田村と竹下さんも一緒だ。 ローゼンクランツの姿はなく、モブのおっさんが混じっている。 「どうしたんだよおまえ」 って、田村が聞いてくるけど、こっちが聞きたいよ。 「俺様は、自分が悪いとは思っていない」 「そうか」 ギルデンスターンはうなずいて、 「殺しはしない。だが、封印させてくれ」 と、アルミの水筒を見せた。 聖水が入った水筒――昔だったら壺かなんか出してた場面。 そこに封印されたら僕は3分ごとに生き返っては死ぬ――それを永遠に繰り返す。 「僕の話を聞く気はないですか」 そう訊ねると、田村が割りこむ。 「統計的に3割の魔王は命乞いするって」 「そりゃそうだろう。魔王だって死にたくはないんだよ」 「古澤くん。もとに戻って」 涙目で竹下さんが訴える。 戻れるなら戻りたいよ。 ていうか、なんで竹下さんまで連れてきたんだよ。 「ギルデンスターン」 呼びかけても物憂げに見返すだけ。返事はない。 「あなたが僕をこの道に誘ったんです」 僕だけじゃない。田村もそう。竹下さんだって、あなたがいなかったら、今日ここを訪ねたりはしていないだろう。 「だから、責任をとってもらいますよ」 緊張が走る。 「あなたに僕を封印するに相応しい力があるかどうか、試させてください」 それが宣戦布告。 間髪を入れずにダブルギターで斬りかかるが躱される。が、想定の範囲内、振り返りざまに大魔王ブレイクを叩き込む。 終わった。 とっさの判断。竹下さんまで巻き込むことになったが、だけどもうこの世界は僕の思うがまま。竹下さんだけ生き返らせて、僕の妻にすればいい。 が、しかし、ギルデンスターンも田村も竹下さんも無事だった。 「魔王、古澤。貴様の攻撃は闇属性。闇耐性100%の装備で固めた俺たちには通らない」 ならば―― 再度ダブルギターで斬りかかるが、脚を射られる。 背後に控えるモブのおっさんが射た矢が右足に食い込む。痛い。 続けてギルデンスターンが踏み込み、ギターアックスが肩に食い込む。痛い。 痛いどころじゃない。タンスのカド30回分はゆうに超える痛みが体中を走り回る。 「待って」 痛みを抱えてうずくまり、もう命乞いの言葉すら出ない。呼吸すら止まりそうな全身の震え。ギルデンスターンは、水筒を僕に向ける。 「ここまでだ、魔王・古澤。貴様を封印する」 ――最後か…… 白い光の粒子が轟々と渦巻く。肉体が分解され小さな水筒に吸い込まれていくと、目の前の景色はガラスのように砕ける。すべてが闇に飲まれていく…… が、次の瞬間、すべての痛みが消え、目の前に光が戻った。 「なにが起きた?」 「ふわはははは! 大魔王様は不死身カパ!」 側近のディストメアが高笑いしている。 もしかして、あの一瞬で3分経って蘇ったのか? 「封印の水筒が……」 竹下さんの声が震えている。 見ると足元に破裂した水筒が転がっている。 うしろのおっさんが矢をつがえるのが見えた。 俺は咄嗟にカート・コバーンのフェンダーを投げる。 クリーンヒット。おっさんは一撃で死んだ。 田村が蘇生を試みるが、無駄だ。やらせるわけがない。ジミヘンのストラトキャスターでその脳天を打ち砕く。 竹下さんが息を飲むが、しょうがないだろう、もう。 「俺を殺す気だったんだろう? だったら覚悟はできてるよな」 ギルデンスターンと対峙。奴の一撃は俺の腹を裂き気を遠のかせるが、絶命と同時に俺は蘇る。 「竹下さんをここから逃がせ。おまえだけを仕留める。ギルデンスターン」 一進一退の攻防、七回の死、七回の復活、俺は、蘇生するたびに体力が回復した。 ギルデンスターンの体力はもう限界。俺の痛みはもはや、快感に変わった。 ――そのとき 「あったぞ、ギルデンスターン!」 背後よりローゼンクランツが躍り出た。 ギルデンスターンがほくそ笑む。 「おまえの負けだ、魔王、古澤」 はあ? 瀕死のくせに、何を言ってるんだ? 「貴様を封印する!」 ローゼンクランツが声を張り上げ、何かを高らかに掲げた。 その手に握られていたもの―― それは―― 『憧れの竹下さんに捧げる冒険』 「あ、待って」 それは書きかけの自分史。ひとに読まれるのは恥ずかしい。 「不死なる魔王を封じる手段はただひとつ! 魔王が最も執着するものに閉ざすのだ!」 閉ざすのだじゃねぇよ、クソがっ! 「……高校へ通う道の途中に、冒険者の酒場があった」 読むなーっ! 「……ガソリンスタンドの五叉路を斜めに入って二つ目の信号、落雷で折れた欅が目印の小さな雑居ビルの一階……」 音読するなーっ! ギルデンスターンとローゼンクランツが印を結ぶと、『憧れの竹下さんに捧げる冒険』から光と闇とが同時に渦巻いて噴き出した。 「竹下さんっ!」 渦は俺の体を包む。 駆け巡る走馬灯―― 竹下さんっ……、竹下さんっ……、竹下さんっ……。 竹下さんの姿を初めて見かけた入学式―― 音楽室で隣り合って――固くなって過ごした1時間―― オープンキャンパスの――帰りのバス―― 一緒に飾り付けた――文化祭―― 声を合わせて歌った――遠い世界に―― 体はどんどん分解され、本の中に吸い込まれていく…… 助けて…… 竹下さんの困惑の表情…… 「よく聞け古澤――」 「ギルデンスターン……」 「おまえを、おまえのいちばん良い時代に閉ざす――」 「うるさいよもう……」 「おまえにとっていまは不自由な時間かもしれんが――」 「かもしれないじゃないよ……」 「おまえのいちばん輝いた時間だ」 「輝いてなんかいない……」 「おまえはそのなかで、苦しんで、毒を吐き続けるがいい」 「僕が…… 僕がなんの罪を犯したって言うんだ! なんで僕が、大魔王になんなきゃいけないんだ!」 「おまえにはわからないさ……幹夫」 「なんで僕が未来永劫に封印されなきゃいけないんだ!」 「わかるわけがない……」 「ああ、わからないよ!」 「ひとはだれも、自分の物語のなかで、自分の罪は見えないんだ」 「罪?」 「おまえはギターを壊した……」 「それが……?」 「八千円であのギターが買えるか……?」 「そんなことが……?」 「元の持ち主がどんな思いで買って、どんな曲を弾いて、それをどんな気持ちでおまえに譲ったか……」 「たかがギターで……?」 「おまえの物語に、1ミリでも出てきたか!」 「たかがそんなことが……僕の罪だって……?」 「たかがって言うな!」 「!!」 「そんなことさえ見えない奴に世界が見えてたまるか!」 「世界…… そうかもしれないけど…… それが魔王になるほどのことなの……?」 「魔王じゃない。幹夫。おまえが魔王じゃないことなんかわかってるさ」 「だったらどうして?」 「おまえがそう描いたんだ」 「僕が?」 「おまえが囚われてるのは、おまえが描いた物語だ!」 「僕が描いた?」 「いつまでもそこに留まりたいか、幹夫!」 「物語……」 「そこから抜け出せ!」 「抜け出せって……」 「這い上がってこい!」 「どうやって……」 「そこから抜け出したければ、あらゆる常識から自由になれ! すべての感覚を疑え! すべての経験、すべての知識を疑え! そうすれば、音楽が生まれる! おまえのなかから、おまえも知らない、音楽が生まれる! その音を掴め! 幹夫! それが! おまえをインジェクションする!」 「インジェクション……?」 「おまえは俺の弟子だ、幹夫!」 「弟子……」 「這い上がれ!」 ギルデンスターンが…… 「約束だぞ! 幹夫!」 僕のことを…… 「待ってるからな!」 弟子……第三部・オクターブユニゾン
二十一・憧れの古澤くんに捧げる冒険
高校へ通う道の途中に、冒険者の酒場があった。 ガソリンスタンドの五叉路を斜めに入って二つ目の信号、落雷で折れた欅が目印の小さな雑居ビルの一階。その小さなカフェに世界各地から冒険者が集まって、仲間を募っている。彼らは酒場を拠点に、どこかの洞窟の奥に潜んでいる魔王を倒しに行くらしい。 だけどその魔王がどこにいるのか。 冒険者たちに聞いても、 「それがまだ、わからないんだ」 「はっきりしているのは、このままではこの世界は魔王の手中に落ちてしまうということだけ」 のような答えしか返ってこなかった。 友人の田村は、 「魔王なんかいねえっしょ」 と笑って言い放ったが、友人の僕からみてもそれは雑魚町人のセリフに思えた。 一冊の本になった僕は、福岡市の南の外れ、小高い丘の白いビルに封印された。 そしてそこで、何年かの月日を過ごした。 ギルデンスターンが一度、田村が一度、僕のもとを訪ねてくれた。 ギルデンスターンはローゼンクランツとユニットを組んで、新しい冒険の旅に出ると語り、田村は還元教団をやめて映像の専門学校へ通い、この春、彼女ができたと教えてくれた。 そんな春の日、竹下さんから手紙が届いた。 手紙には二度、受験に失敗したと綴られていた。 私が憧れたひと。古澤くん。 お元気ですか? 一年ぶりの手紙になります。去年の手紙は、もしかして読まれずに捨てられたのかもしれません。 唐突でごめんなさい。私ごとで恐縮ですが、この春、二回目の受験に失敗しました。 医学部はやっぱりハードルが高いです。 覚えていますか? 私が医学部志望だったこと。 高校の頃の古澤くんは、グラミー賞を獲るんだと言ってオリジナルの曲を作ってはCDに焼いてクラスで配っていましたね。 私もじつは、吉田くんがもらったものを聞かせてもらいました。 曲は今でも覚えています。 私はその曲を聞いて、自分の夢のことを思い出したんです。 小学生になったばっかりの頃、盲腸の手術をしました。そのとき、先生や看護師さんにいっぱい励まされて、将来はお医者さんになろうと思っていたんです。 私は単純だから、古澤くんは将来有名になって、大きなステージに立って演奏するのだと思っていました。だって、クラスにもたくさんあなたのファンがいたから。そのくらい簡単に叶えるものだとばかり。そんな古澤くんに近づくために、私は、夢を諦めちゃいけないんじゃないかって思ったんです。 ステージに立つあなたに声を届けるには、私はぜったいに医者にならないといけない。医者になったらやっとあなたに追いつけると信じて、いままでがんばって来ました。 だけどもう挫けそうです。 兄はこの春大学を出て、オーストリアに行ってしまいました。 幸か不幸か、小料理屋葵の跡継ぎが私に回ってきました。 でも、それもいいかなって思う。 古澤くん。あなたは一廉の人物になるひとです。 封印が解けたら、あなたの曲は売れに売れて、将来は藤井フミヤや鳩山邦夫が持っているという駅前のマンションに住んで、私の知らないひとと温かい家庭を築くんだと思います。 そのとき、私の店、小料理屋葵のデリバリーを頼んでもらえるとしたら、それだけでもう十分なんじゃないかって気がしています。 だって私が憧れたのは、医者じゃなくて、古澤くん、あなただったのだから。 ごめんなさい。 なんだか告白のようになってしまいましたが、あまり真に受けないでください。 好きな人もいるんです。というか、いました。 いまはただ、いろんなことに踏ん切りをつけたいだけというか。 お返事は別に、いいです。 ただ、こんな感じで、高校時代にもお話がしたかったなあって、そう思ってペンを取りました。 春とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。 お体に気をつけてお過ごしください。 僕の憧れ、竹下智子さん。 お手紙ありがとうございます。 最初の手紙も読みました。 でもあのときは随分混乱していて、ちゃんと返事ができませんでした。 医大への挑戦、どうかもう一度がんばってみてください。 無理にとは言いませんが、このところ入試の不正の問題なども耳にします。今だったら行けるかもしれません。どうかもう一度だけがんばってみてください。 手紙には、竹下さんの憧れは医者ではなく僕だったと書いてありましたけど、僕は違うと思います。いや、言葉はありがたく受け取ってはいるのですが、「医者になりたい」って気持ちの底にあるのは、もっと大きなことだと思います。 竹下さんはだれかを助けたいんです。医者はその手段に過ぎません。竹下さんだったら、仮に医者になれなかったとしても、多くの人を救って、多くの人を笑顔にすることができるはずです。もちろん、それが小料理屋葵なのかもしれませんし、それは僕にはわかりません。 高校の頃はグラミー賞のことばかり言っていました。そのことはよく覚えています。 でもそれもたぶん、本当の夢じゃなかったんだと思います。 本当の夢はそんなことじゃないはずなのに、ひとに豪語するうちに自分でもわからなくなっていました。 ステージでギターを壊すアーティストに憧れていたのは事実です。 ピート・タウンゼント、リッチー・ブラックモア、ジミ・ヘンドリックス、カート・コバーン。 でもそれに憧れたのも本当は、彼らが感じてきた不条理や閉塞感に共感したからだと思うんです。 グラミー賞なんか本当はどうだっていい。もしかしたら彼らだってそんな肩書に辟易していたかもしれない。あの頃だって知っていたはずなんです。 一緒に大学のオープンキャンパスに行ったことがありましたよね。 あの日僕は、ギターを叩き壊しました。 八千円で譲ってもらったギター。 それが元の持ち主、従兄弟の友人の手元でどんな音を奏でていたか、それをどんな気持ちで譲ったか、何も考え至らず、ただ怒りをぶつけて、破壊してしまいました。 あなたが、僕の手の届かない遠くへ行ってしまう気がして。それになにも知らない自分が悔しくて。 憧れの竹下さん。可能ならば医者になってください。 そして万が一医者になれなくても、同じだけの笑顔を人に届けてください。本当の幸せっていうのは、自分のほんとうの気持ちがわかって、はじめて手に入るのだと思います。 僕も曲を書き続けます。 いつか少年の頃の僕に会ったら、言ってやりたいんです。 おまえが憧れた賞より、はるかに大きなものを手に入れた、って。 彼はきっと、その意味をわかってくれるはずだから。 お返事遅れて申し訳ありません。 季節もだいぶ過ごしやすくなってきました。どうか心身ともに癒やし、これからの季節に備えてお過ごしください。 それからまた何年か経って、風の便りに竹下さんが医者になったと聞いた。 ギルデンスターンとローゼンクランツは山崎春乃というヴォーカルを迎えて、新しいバンドで活動を始めた。ファーストアルバムをネット配信。その表題曲『インジェクション』。それが僕を救った魔法の言葉だった。 封印が解けた僕は紆余曲折を経て、実家の畳屋のあとを継いだ。 仕事は少なかったが、毎週月曜から水曜までは大川の家具工場に出稼ぎに出て、木曜と金曜だけ畳屋を開けた。 PIXIESとNIRVANAを大音量で流しながら、畳表を縫った。 週末は仲間と文化街のバーで歌った。 そして、一人前に家庭を築いた。 妻に迎えたのは、 「まさかあんたがあれほどのひとを射止めるとは思わなかった」 と、姉も母も口を揃えるほどの出来すぎたひと。 古澤畳店のガタが来た引き戸を器用に開ける細い肩。その技は、僕らの息子と娘にも受け継がれていった。 春の入学式。 夏の海水浴と、秋の運動会。 クリスマス。お正月。 かつて送った人生を、親として二回繰り返した。 僕と姉の成長を、父と母も、こうやって手をつないで見守っていたのだと思う。 僕は今日も畳を仕上げる。 月に一度、ふたりの子に寿司を食わせるために。 「ごめん、今日は遅くなる。晩ごはんをお願い」 ファックス付きの電話を入れたいまも、彼女からの連絡は古澤畳店の黒電話に掛かってくる。カーテンコール
本日はさよならおやすみノベルズ第6回公演、『憧れの竹下さんに捧げる冒険』ご観覧いただきありがとうございました! エンディング曲は、五つの赤い風船・遠い世界に。 どうか皆さん、YouTubeで探して鳴らしながらカーテンコールにお付き合いください。 それじゃあ、いかれたメンバーを紹介するぜぇ~っ!! まずはヒロイン、竹下智子~! ヒロイン役の竹下智子です! 今日はどうもありがとうございました! お次はローゼンクランツ役、Vの字斬りの勇者、山本さ~ん! みなさん本日はどうもありがとうございましたー! そしてお隣、河童、アンド、伝説の勇者役、硯葉さ~ん! 物販の方もやっているので、よろしかったら見ていってくださーい。 そしてお隣は、もうひとりのヒロイン、春乃役、山崎春乃~! 山崎春乃です! パン祭りやってま~す! そして親友、凡人・田村~! あなたは僕の太陽だ~! ケペペス! そしてお隣は、勇者戸田さんと勇者永田さ~ん! 今日はみなさんありがとうございました~! またのお越しをお待ちしてまーす! 吉田くん、藤島さ~ん またどこかでお会いしましょ~! 生徒会長ビーム! それから、音楽の田中先生~! はーい、今日はみなさんありがとうございました~! お父さん&お姉ちゃん、それから冒険者の酒場のみなさ~ん! ありがとう! 野菜も食べなよ~! イエ~イ! 魔王弁護連盟~! さらば、みなの衆! また会う日まで! 神籠石大学教授、アンド、魔王タマタール役、蟹副さ~ん! みなさまとの出会いに感謝いたします! また会う日まで! そしてしんがりに控えしは~ ギルデンスターン、アンド、伝説のショートソード使い役、八重樫さ~ん! 本日は最後までご声援お送りいただき、誠にありがとうございました~! これからももっともっと精進を重ねて、面白い作品をお届けしたいと思います! そして最後は僕のほうから紹介いたします。 我が弟子、主人公、若き吟遊詩人を演じたー…… 古澤幹夫~! みなさん今日は本当にありがとうございました~! このひとときをみなさんと過ごせたこと、これからもずっと大切にしたいと思います! 公演のほう、今日のソワレもチケット残っていますし、平日のほうはまだまだ余裕があります。ぜひぜひチケットセンターの方にお問い合わせください。 それと土日も若干ながら当日券をご用意させて頂いてますので、そちらのほうもご利用いただけたら幸いです。 家族やお友達と観たらまた違った発見もあると思いますので、ぜひお誘い合わせの上、二度三度、四度五度、何度でも足を運んでいただけたらと、メンバー全員心待ちにしております。 ホームページのほうには、今までの作品も紹介していますので、ぜひ『さよならおやすみノベルズ』で検索してご利用ください。 過去作もですが、次の作品、また次の作品と、どんどん面白いものをリリースしていく予定ですので、ぜひぜひお見知りおきのほうお願いいたします。 それでは最後までお付き合いいただき、まことにありがとうございました~! またどこかでお会いしましょう! 本日はどうもありがとうございました~!あとがき
今作は古澤幹夫シリーズ第二弾です。 古澤幹夫といういのは僕の中学時代の友人の名前で、前作『昭和58年の宇宙移民』の主人公でもありましたが、内容的にはいっさい繋がりがありません。 またヒロインの竹下智子さんも高校時代の友人の名から取っておりますが、内容はほぼほぼフィクションとなっております。いやでも、こうやって名前を使うってことは本当に憧れとかなんとかあったんだろうと邪推されるかもしれませんが、まあ、憧れていたのは事実ですね。ほとんど話したことはありませんけど。 モデルになってしまった古澤くんと竹下さんには、ぜひぜひこの作品を読んでほしいのですが、実はこのふたりには接点がありません。架空のお話の中で接点のある同士っていうのもまた不思議な感じがしますね。 あとは、ギルデンスターンという名前が、とある有名なゲームクリエイターの某ゲームでのキャラ名だったりもするのですが、こちらは名前を借りているだけでモデルにしたというようなことは一切ありません。というか、たいがい名前を借りているだけですね。 『あの名前はあれなんじゃないか』ってのは数々あると思いますが、現実のひととはリンクしていません。一例を出すと、肉桂文鳥団は、僕がドラクエXで持っていたギルド名から来ていますし、そのリーダー名は僕がよく使うキャラクター名です。 その他、いくつかミュージシャンや政治家の名前が出ています。もしかしてちょっと問題があるかとも思ったんですけど、自分で調べた限り法的には問題なさそうです。 このノベルは書き始めた当初『母ちゃん、俺、魔王倒したよ』というタイトルでした。勇者となった高校生とその母で書こうとしていたのですが、書いているうちにヒロイン要素が強くなって、母ちゃんにはご退場願いました。勇者と母のお話はまた別の機会でもあれば書いてみたいと思っています。 本作品はさよならおやすみノベルズの第6弾ということになりまして、内容も今までの集大成的な感じになっています。『うさぎがとつぜん私になってこまった100のこと』の短い章構成、『チャットワークス』のセリフ偏重、『昭和58年の宇宙移民』の出鱈目さ、『浮遊大陸でもういちど』の屁理屈感、『勇!! なるかな』の舞台などなど、いろんなものを混ぜ込んで、すべて出し尽くしちゃった感があります。 ちなみに、このいっこ前が『うみねこまりな』ですが、こちらは現時点(二〇二二年二月)でまだ完結していません。 そちらは、小説も書き慣れて、いろんなことをやろうとして、結果文体がとてつもなく重くなってしまいました。ウェブで公開しているのですが、普通にウェブで読んでもらえるのって三千文字が限度かなと思うのです。にもかかわらす『うみねこまりな』は一章あたり一万文字を超えます。プロモーション用にと思って書いているのに、これじゃあプロモーションになりません。今作ではその点を反省して、一章あたりは三千文字程度にして、適宜空行をはさみつつ読みやすくしてみました。 しかし、『読みやすくした』というのが曲者でして、『それは自分が書きたいものとは違うってことなの?』という自問がずっとついて回ってました。自分で書きたいものを書いたのであれば、多少読みにくくても「書きたくて書いてんだからしゃーないやん」と言えますが、「読みやすくしました」と言っちゃったら、「読みにくい!」「つまらない!」どちらにも言い訳ができないじゃないですか。 ……まあ、そういうのを常に正面から引き受けてるプロはすごいですねって話なのですが、どんな神経してりゃプロの物書きなんかできるんだろうと思います。いや、僕もゲームのシナリオなど書いているプロのはしくれではあるのですが。 あとはこの作品って、筆者(僕ですが)の特徴がとても色濃く出ていると思うのです。結果として、好きな人は好き、嫌いな人は嫌い、という、読むひとを選ぶ作品になっていると思います。 他の作品を書くときは、こんなに急に話題が飛んでもいいのかなと思ったり(思うだけで直しませんが)、急に河童が出てきてついてきてもらえるかなと思ったりしますが(これも同じく直しませんが)、今作では割と気にせずぶん回しています。素で書くとこうなってしまいますという見本のような仕上がりです。 でもおかげさまで、だいぶ自分のスタイルが確立されました。 いままでいろいろ書いて、「じゃあ、おまえに仕事を頼むとして、普通に上ってくるのはどれなの?」と聞かれても、これだ! と答えられるものがなかったのですが、これからは本作品を代表作として示そうと思います。あまり万人向けの作品だとは思いませんが、まあ、そこも含めて僕の個性なのだと思います。 それでは、カーテンコールのあとにあとがきまで重ねて、本当に往生際が悪いことこのうえないのですが、このへんでペンを置きたいと思います。 それぞれの季節、それぞれの喜び、それぞれの悩みなどあると思いますが、健康に気をつけ、また休めるときには十分に癒やし、皆様それぞれ健やかにお過ごしください。 またどこかでお会いしましょう。⚪
🐹
🐰
🐻
⬜