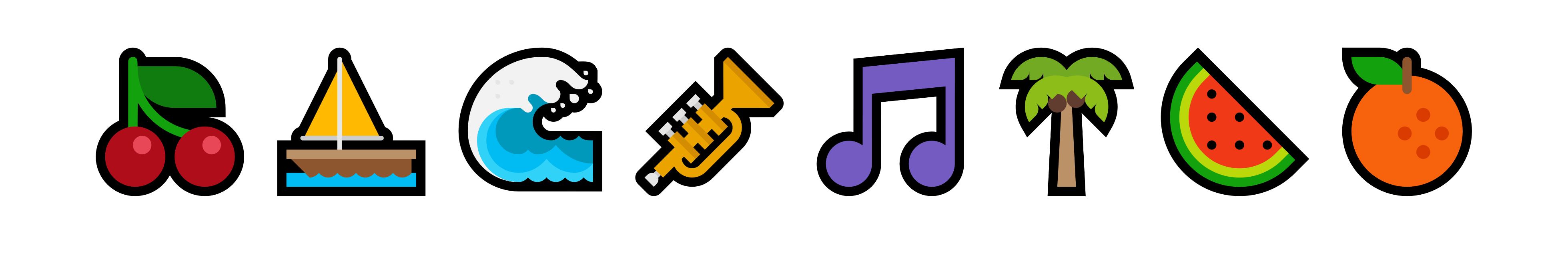- 第1章 搭乗者・古澤幹夫(1)
- 第2章 小市民・古澤幹夫
- 第3章 小役人・古澤幹夫
- 第4章 渡世人・古澤幹夫
- 第5章 搭乗者・古澤幹夫(2)
- 第6章 管理者・古澤幹夫
- 第7章 夢の中の古澤幹夫
- 第8章 大草原の古澤幹夫
- 第9章 帰還者・古澤幹夫
- 番外編 残留者・岬沙也加
- あとがき
第1章 搭乗者・古澤幹夫(1)
昭和58年8月。 宇宙への旅立ちの前日、日本全土をオーロラが覆った。 北海道から沖縄まで遍く広がった光のカーテンを夏の終りのなま温い風が揺らすと、あと数年で地球から地磁気が消失します――そう伝えるニュースキャスターの言葉とは裏腹、札幌の時計台を、大阪の通天閣を、そして沖縄、首里城をバックに日本各地から中継されるオーロラは、僕の胸に小さなときめきと別れの寂寞とを刻んだ。 僕と亜実は、すでに部屋も引き払い、世話になっている千駄ヶ谷の木村さんのアパートでそのオーロラを見上げていた。裸電球を吊るした小さな庭、七輪でサザエを焼いて、木村さんは僕たちのためにと、余市の蒸溜所で特別に手に入れたウイスキーを開けた。 ストレートで口に含んだモルトに、木村さんは眉をしかめる。 「これから、寂しゅうなるな」 七輪の煙に燻されて、オーロラを溶かしたウイスキーが僕の喉にも滲みた。 「木村さんは知り合いも多いし、すぐに忘れますよ」 「いや、そんなことないて。忘れへんて。沙也加ちゃんなんか、友だちがふたりもおらんよなるやんか。俺以上に寂しがるよ」 「でもそういう意味だと、いちばん寂しくなるのは僕と亜実だから」 「まあ、そやな。そやったな」 木村さんはプラッシーのコップを手に持ったまま、菜箸でサザエの向きを揃える。 オーロラの下、ラジオから流れる歌に合わせて、亜実はゆっくりと体を揺らしている。少し色を脱いた、落ちかけたパーマの髪。肩に届いた髪の、先の方だけゴムで結んで、白い麻のワンピースの裾が、亜実の体に遅れて回る。その耳に聞こえているのは、オーロラをかき分けてたどり着いた、昭和という時代の息を切らした喘鳴なのだと思う。探偵ものの映画の主題歌。光を集めて、纏うようなダンス。その指先は複雑で柔らかな軌跡を描く。 地球の重力で踊るのは、おそらくこれで最後になる。深宇宙移民団の船、ニニギ2号は、地上4百キロの衛星軌道上に待機し、いまこうしている間も、1時間半に1回、僕らの頭上を通過している。 出発の当日、新聞を買った。 僕たちと、沙也加と、木村さん。同じ日付、同じ新聞を、この日の記念として。 成田までは木村さんに車を出してもらって、僕と亜実は後ろのシートに座る。フィアットの小さなフロントガラスから見える空は、幾重もの空気の層の向こうに、宇宙の暗闇を沈めている。遠くには飛び立つシャトルの姿が見えて、目で追うと助手席に座る沙也加の横顔に隠れる。 「幹夫たちも、あれに乗るんだよね」 沙也加が指差す。 「そう。今日の午後には」 「そうか。それでもうお別れか」 背中の手の届かないあたりに、昨日からずっと、寂しさがこびりついていた。ラジオから流れる曲は夏の終わりを歌い、亜実は僕にもたれて、車は京葉道路を東へ。成田国際宇宙港へと走る。 少し前まで、成田は過激派の闘争でひどく混乱していた。だけど異常気象が続くほどに、彼らの間にも危機感は浸透し、メンバーは少しずつ脱落、宇宙港としての運用が決まったあとは、足並みが揃うこともなく軍に制圧された。もちろん、軍が本気を出したというのもあるし、世論がそれを許したというのもある。目に見える事件というのは、時代という大きな氷山の一角なのだと思う。滑走路の向こうにある慰霊碑は、いまは軍の管理地。木村さんの知り合いも何人かそこに眠っている。第2章 小市民・古澤幹夫
東京から初めてオーロラが見えた日。昭和42年。僕はまだ中学生だった。 進学祝いのラジオで聞いた、ドアーズ、ザ・フー、ヴェルヴェッツと、姉が買ったハード・デイズ・ナイト。お下がりのギターと、安いアンプが鳴らす歪んだ音。小学校の4年生を最後に、恋のことなんて忘れてしまった。 ラジオにノイズが乗る日はオーロラが見えた。 成層圏に降りる青白いカーテンが、太陽からの風を孕んで揺れる。 新聞もテレビも天変地異を予言し、人々は地球滅亡を予感するなか、オーロラの夜空を見上げるのがどんなに楽しみだったか。 あれからもう16年。 ジョン・レノンも、ジム・モリスンも、キース・ムーンも消えた世界で、僕は28歳になった。オーロラは日常になり、そしていま、僕にはたぶん息子がいる。 岬沙也加と出会ったのは、大学生の頃。彼女は3つ年上。洋楽とギターが趣味だというと、サムラ・ママス・マンナというバンドが好きだと煙を吐いた。沙也加にはすでにふたりの彼氏がいて、それは知った上で付き合い始めた。他のふたりの境遇も僕と同じ。代々木で偶然会った時は、お互いに何も感じない素振り、他人よりも更に遠いひとの目をして。 そんな関係が24の時、彼女が結婚するまで続いた。 沙也加の結婚相手は付き合っていたなかのひとり。子どもができたのがきっかけだった。彼女が選んだのは、家事や育児、あるいは身の回りのことを細かく見てくれるタイプ。そのひととは何度か会ったことがある。他の彼氏の顔なんか見たくもなかったのに、子どもが生まれてからはなぜか、旧友のように感じられた。それまでは特に彼女を愛してるなんて感覚はなかった。僕はただ大人びた関係に浸りたかっただけ、いなくなるならもっと早くいなくなれば良かったのに。そう思いながらも、 僕じゃないんだ―― そんな喪失感は拭えなかった。 アーティスト仲間が集まる『千駄ヶ谷の集い』というパーティでも、僕たちの関係はよく知られていた。2歳になる彼女の息子を見たのも、そこで。遺伝子的には僕の子なんだと思う。それは彼女も、その夫も知っている。 集いの主催、木村さんは 「で、本当の父親はどっちなん?」 と、あけすけに聞いて来たけど、それには彼女が、 「本当とか嘘とか、あんまり関係なくない?」 と、返していた。 「まあ、そうやな」 木村さんは少し遠慮したような、申し訳無さそうな顔で笑った。 僕は子どもが好きなわけでも、子どもを育てたいわけでもない。だけど本心では、「本当の父親は僕なんだ」って、その子にいって、父親らしい何かを示したいとも思う。たとえばいまやってるバンドで一斉を風靡して、ある日のライブの控室に彼女が息子を連れてきて、「すごいですね、こういうのに憧れているんです」なんていわれる日が来たら、どんなに気分がいいだろうって。 別れて4年。当時は意識しなかったけど、人生でいちばん好きだったひとはだれかと聞かれたら、彼女の顔が浮かぶ。愛といえるかと聞かれたらわからない。いや、愛なんて抽象的な言葉は要らないんだと思う。ただお互いのことに責任を持って、起きたことと、これから起こることを受け止めて行ければ、愛なんかはいらない。ただ譜面を追うように目の前にあるものを、その時の気持ちで胸に入れて、吐き出し続ければいい。 だけどその呼吸のようなものは、あっさりと途切れた。 昭和58年、6月11日、土曜日。 千駄ヶ谷の駅を降りて、息継ぎもできないほどのオーロラの下、星をかき分けながら歩くと、五叉路を越えた少し向こう、古い木造のアパートにはもう10人近いメンバーが集っていた。階下のひとにビールを持って挨拶をして、モツの煮物を分けてもらって。 木村さんは、異質な風体のせいかよく職質されて、薬物使用を疑われて髪の毛も調べられたりするひと。だけど警官のその読みは正しい。木村さんは、トリップできる野草に関しては日本でも五指に入ると豪語する。僕のバンドのテープを聴いて、「ええけど、普通やな」と笑っていた。 部屋には階下の住人からも借りてきたというテーブルが並べられ、手刀を切って輪の中に入ると、腰を下ろすなり隣に座っているひとが劇団のチラシを手渡してくる。 「来週末、スズナリでやるんです」 始めて見る顔でも、ここではスズナリで通じる。この気楽さがみんなを惹きつけるのだと思う。「これ」と、チラシの文字をさして、「水の精、中江亜実。これが私」と、自分の鼻の頭を指さしてみせる。 「中江さん、はじめまして。古澤です」 「ミキオくんでしょう? バンドやってるっていう。ミキオってどんな字書くの?」 「木の幹の幹と、夫で、幹夫。バンドは素人に毛が生えたようなものだけど、テレビにも出たことあるんですよ、何度か」 「聞いた。沙也加から」 「ああ。じゃあ、彼女との関係も?」 中江さんは肯定も否定もせず、ただ僕の顔を見て口角を上げた。 チラシを見て、公演の日時を確認して、 「行けそうなんで、チケット買いますよ」 といえば、連絡先を交換してくれる。 「今日持ってきたぶんはもう配っちゃった。取り置きしててもいいし、ここに取りに来てくれてもいいよ。月金は家にいると思う」 と、紙切れに住所を書いて。 「どんな舞台なの?」 「コンテンポラリーダンスを取り入れた、現代風のやつ」 「山海塾みたいなの?」 「遠くはないかな。詳しいの?」 「いや、海外で賞を取ったっての知ってるくらい」 そう話しながらも、別のグループの宇宙移民の話が耳に入る。ここのところどこへ行ってもそう。僕が小学生の頃に耳にするようになった話。地球資源の枯渇と人口増加、予測される天変地異。火星への移民が計画され、人々はこぞって切符を求めた。その切符はとても高価で、金持ちだけが汚染された地球を捨てて宇宙へ逃げ出すのかと批判されて、国会はいつも荒れていて、どこかの大学では連日の立て籠もりや闘争。 「東京で初めてオーロラが出たのが中1の時かな。2~3年中にはポールシフトが起きるっていわれてたよね」 中江さんは虚ろにグラスを覗いている。 「いま普通だからね。オーロラ」 その後、どこかの人権団体が『すべてのひとが公平に宇宙に行ける権利』を掲げ、国連でも問題になって、合衆国の火星移民第一弾は多種多様な人種、職業のひとが集まった。出発したのが確か昭和46年。2年後の昭和48年には、日本からも火星移民団が出発。そしてひとむかし前に流行った芸人のように忘れられ、時折思い出されては、酒の肴になった。 「あのひとたちって、まだ火星で暮らしてるの?」 「暮らせてはいるみたいだけど、低重力の影響で受精・着床しないらしいから、次の世代はないみたい」 「そうだってね。帰ってくればいいのに」 おそらく、本人たちがいちばんそれを切望していると思う。 繁殖のあてもない低重力の火星ベースで、食料は自動供給され、地球で作られたテレビ番組を15分遅れで視聴する日々。彼らはそこにいったいどんな喜びを見出しているだろう。受験競争もないし、就職の心配もない。地球からの指示でデータを採取して送信するだけ。 地球はといえば、火星移民団からの10年でなにもかも変わった。量子コンピュータと量子メモリの発明を始め、20年前に始まった地磁気異常はどんな自然現象よりも人類に作用し、進化を促した。 宇宙移民の背景も変わって、いまはもう地球資源の枯渇はいわれなくなった。問題はいつの間にか異常気象や砂漠化にすり替わり、移民先も海王星、金星、深宇宙の三択。だけどそれでも、戦争は相変わらず。宇宙船開発に必要な希少金属を奪い合って、無駄にひとが死んでいる。 だけどそんな憂慮すべき事態も、ひとの口に上るときは笑い話。顔の見えない移民団と、どこか遠い国での戦争の話。まれに身近な親戚が火星に行ったひとがいても、酒席での笑い話は言いっぱなし。野暮な話は腰を折るだけ。 でも、何が正解かなんてわからないから、僕自身はニュートラルでいたい。 そういうと中江さんは「私も」と、グラスを向けてきた。 この部屋には、いくつかの星が煌めき、流れていた。そのみなもとは蛍光灯の光の一片なのだと思う。それが中江さんの睫毛にふれて、本物の小さな星に変わる。部屋の中の喧騒はもう、深い真空の向こう。たぶん少し、酔ったのだと思う。中江さんのシャツの首周りが浮いて、鎖骨の線に小さな星が光る。視線を泳がせる。何人の男がこうやってシャツの中をのぞいただろう。 「ダンスはうまいの?」 「うまいよ。小さい頃はバレエ習ってたの」 「裕福だったんだ」 「そう。お父さんに捨てられるまでは」 この日のこの会話が、人生で三度目の、恋のようなもののはじまりになった。 バレエを習っていた過去と、百人程度の小劇場で現代舞踊を踊るいまとが、彼女の中で接ぎ木されて、そのふたつの色に塗り分けられた彼女が、僕の中の特別な場所に座った。 「舞台が好きなの。胸に詰まったものを嘘にして吐き出せる。自然主義とか写実主義とかは嫌い。あれは文芸や芸術を傘にきたポルノ。エリートだけが己の肉欲を文章として昇華できますみたいなもんでしょう。クソだと思う」 見た目の印象と違って、言葉は鋭い。僕も隙を見せないようにとは思うものの、舞台やダンスについて知ってることなんてほとんど無い。それらしいことを聞いて、わかったふりをして頷くだけ。 「私のダンスは何も象徴しない。ただ、痛みを感じたら、その痛みを表現するだけ。理想はタコ。タコになりたい。たぶん何も考えてない。体に触れる感触、あるいは光や匂いへの反射だけで体が動く。その肉体の中で、私はじっと動かない静かな核でありたい。たとえばだれかに愛されるときも、たとえばだれかに殺されるときも、私はただ肉体の喜びを感じるだけの、静かな核でありたい」 その口にこぼれる言葉は透き通っていた。風のない水面を歩くように僕の胸の中に波紋を広げ、水際で返る波紋が文様を織りなす。 「シマウマが食べられる時の恍惚が好き」 たまに、無造作に小石をばらまかれるけど。 「そういうのを、ここで踊りで表現して見せてっていわれたらできる?」 そう訊ねると、皿に盛った料理を箸で刺して、くすくすと笑う。 「まだまだお子様だよね、キミオくんは」 おどけた瞳に、リアクションを失う。おとなだったら、どんな会話をするんだろう。 「まいったな。じゃあ、おとなになったら見せてくれる?」 「無理だよ」 「無理?」 「私たちはもう、おとなになんてなれないんだよ。この地球では」 意味がわからない。会話の筋がつかめなくて、おとなになれない、羽化できない、幼体ホルモン、あちこちに話題を探してみるけど見当たらず、 「セミって、成虫になるの、幸せなんだと思う?」 なんてことを口にしていた。 「それに幸せという名前をつけたいかどうかじゃないかな」 考えもしなかった答えが返ってくる。 「あーんして」 中江さんは口を開けてみせて、それに倣って口を開けると、星型のキャンディを僕の口に放り込む。同じキャンディを口に含んで、「そっち、なに味?」と訊ねる。舌の上で転がして、「わかんない」と答えると、中江さんも同じように転がして、「私のはたぶんイチゴ」と、舌の先に乗せて僕に見せる。着色料で染まった赤い舌。僕も促されて口を開けると、「そっちはメロン」と教えてくれた。 舌の上でキャンディを転がしてるあいだ、『お子様だね』の言葉が僕のなかで反芻されて、おとならしい何かをしなきゃいけないのかなって思いが、ぐるぐるとめぐり続けていた。 「僕のことはどのくらい聞いてる?」 「沙也加の元彼だったあたりは聞いてる。沙也加とは同い歳なの」 ということは僕の3つ上。印象としては3つくらい下に見えた。 「どう思っ……いました?」 歳を聞いて急に敬語になるのも変か。 「一対多のお付き合いって。嫌悪感とか感じ……ます?」 「いいんじゃないかな。逆に、なんで結婚する時にひとりに絞ったのかわからない。そのまま4人で暮らしてたら良かったのに」 「それは嫌かな。会いたくはないんだよ、他の男とは」 三々五々集まってくるひとたちが、僕のとなり、中江さんのとなりに腰を下ろして、グラスに泡を満たして、僕たちの方へも乾杯の声を向ける。 「そこまでは割り切れてないんだ」 「うん」 「あのさあ」 「なに?」 「いっしょに、宇宙移民団に応募しない?」 急にいわれて戸惑った。僕たちが知り合ったのは、ほんの10分前。 「木村さんが、再募集枠だったら手配できるって。深宇宙組だけど」 彼氏はいないの? いるよ。じゃあ、彼氏と行けばいいのに、というと、彼氏といっても付き合い方は十人十色でしょう、あなただって沙也加の彼氏だったわけだけど、普通のひとが想像する彼氏とはぜんぜん違うよね? といって、また上目遣いに口角を上げる。 「子どももいる」 こちらの反応を楽しむように、少しずつ情報を出してくる。 「そうなの? そうは見えない」 「おなかに」 「ちょっと待って。何ヶ月? 舞台に立つんだよね? 大丈夫なの?」 彼女は少し言葉を探す。 「飛んだり跳ねたりするわけじゃないし、それに痛みや嘔吐感があっても、それを自分と違うものとして切り分けたくない」 「わかった」 ――いや、わかってはいないけど。 「それじゃあ舞台は見に行くよ」 「ありがとう」 「そのあとの話はまあ、冗談としては面白かったと思う」 「冗談じゃないよ。普通に恋なんかしてると、いつ子どもができるかわからない、いつ仕事をなくすかわからない、いつひとに裏切られるかわからない、これはすべて現実だよ」 「だからって」 「逃げたいの、もう。コールドスリープで何十年か寝て起きたら、そこは別の星なんでしょう? 宇宙船に積み込まれた資材で自分たちの好きな国を作れる。今日ここに集まってるひとたちだって、本当はそうしたいんだよ。この国から逃れて、アーティストだけの国を作りたいの」 「実際にやってみたらクソみたいな国にしかならないよ」 「いいよ、それでも。それに私、宇宙に浮かんでみたい。私の肉体が、人類という大きな肉体を脱ぎ捨てた時、何になるかを知りたいの」 そういうと彼女は、星の形のキャンディを鍋に入れた。 「だから、宇宙へ行きたい。こんな星のことは忘れて」 そのあとアパートの裏に出て、ふたりでオーロラを見上げると、オーロラからは歌うような低い声が聞こえてきて、僕は彼女の小さな窓から、心臓の鼓動を探した。 * 彼女の部屋は井の頭線明大前駅から少し歩いたところにあった。 月金は家にいるといっていたけど、月曜と金曜の意味なのか月曜から金曜までの意味なのか今更になって戸惑う。今週末はもう舞台だというので、訪ねたのは月曜の夜。彼女がギターを持って来てというので持っては来たのだけど、 「まさか、本気にしたの?」 といわれたときに、どんな言い訳をすればいいのか。 駅前で手土産にクッキーなど買って、地図を確認して、メモ帳に書き写して道をたどった。空には相変わらずオーロラが見えている。 しばらく歩いてたどり着いた小さなアパート。ペンキの剥げた扉を開けて、階段下で靴を脱ぐ。住人のぶんの靴入れの他には何もない土間。くたびれた靴を並べて、床板の軋む階段、二階の廊下のいちばん奥、紐でくくられた雑誌の束、ダンボール。ノックすると、ビーズの暖簾を分けて彼女の顔。僕を見留めて、笑顔を零す。 「どうぞ、中に入って」 手櫛で髪をとかしながら部屋へと入るタイダイのTシャツ、緩い麻のパンツ。振り向いたシャツ越しに、胸を弾ませる。 「ちゃんとギター持ってきてくれたんだ。あとで聞かせて」 そういいながら、口にくわえていたゴムで髪を留める。 「でも隣に響くと思う」 「隣は夜のお仕事だからいまいない。その向こうは普段からうるさいし、お互い様」 部屋は荷物も少なくすっきりとしていた。六畳間の横の狭い板張りに、小さな冷蔵庫。小さなシンクに、コンロがひとつ。少し甘い雨の日の匂い。 「ここ、いくらだと思う?」 「2万円くらい?」 「近い。1万8千円。管理費込み」 「彼氏がいるんですよね? 僕、大丈夫なんですか?」 「私がだれと何をしようが、彼氏は関係なくない?」 「そうですね。僕は何もしないけど」 「でも、ギターは弾いてくれるんだよね」 布団をはずしたコタツの上に、チケットが一枚。その前の座布団に座らされて、「じゃあこれ、5百円でいいよ」といわれて、でもチケットを確かめて、額面通りの金額を財布から出していると、彼女はテレビをつけて、ビデオの準備を始める。 「私の舞台のビデオがあるの。見て行くよね?」 そう訊ねながら、有無をいわせずにビデオテープをセットすると、ダビングを重ねた歪んだ映像が映し出される。 「もうちょっと、もうちょっと先」と、画面を見て、3人のダンサーが出てきたところで、「これ! これが私!」と指差して、流しの前に立つ。 「コーヒーと紅茶、どっちがいい?」 「いや、おかまいなく」 「飲み物も何もないと気まずいでしょう? そんなに親しくもないし」 「いや、もうチケットはいただいたんで、すぐ帰りますから」 「あっ、見て見て。ここから私のソロ」 と、手に持ったホーローのポットで画面を指す。 「コーヒーか紅茶、選んでくれないなら両方淹れるよ?」 「じゃあ、コーヒーで」 一人暮らしの部屋の14型の小さなテレビ、ベータマックスの荒い画面の中、彼女の姿を追う。ノイズに塗れた小さな影も、集中しているとだんだんと存在感を持って浮かび上がってくる。 彼女はコーヒーと紅茶を両手に持って机に並べて、僕の右側面に座る。 「夜って、普段はテレビとか見て過ごしてます?」 「見ない。テレビは男のための道具でしょう? ケッて感じ。舞台のビデオ見たり、あるいは本を読んだりしてることが多いかな。幹夫くんは?」 改めて問われると、夜なんて何をしてるわけでもない。 「テレビ見てる」 指摘された通り、男のための道具として。特に土曜日なんか、オールナイトフジをだらだらと深夜まで見て、よくテレビをつけたまま眠っている。 「寂しいなあ、それ」 会話は時々、ぎこちなく途切れて、どちらからともなく次の話題を探す。 「ギター、聞かせて」 「フォークギターだから、普段弾いてる曲と少し違うけど、いい?」 「いいよ。もちろん」 ざっくりとチューニングして、まずはビートルズから。洋楽を中心に、できるだけ有名なものを弾いてみるんだけど、ここのところすっかりエレキに慣れてしまって、アンプを通さない音はどこか心細い。 彼女はただ無表情にじっと聞いている。 「踊ってくれるかと思った」 「もう少し仲良くなってから。でないとバカみたいでしょう? 突然踊りだすなんて」 まあ、それはそうか。 「私のダンスはタコが理想っていったでしょう? 覚えてる?」 「うん」 「ダンスって、大脳的なものではなくて、神経節的なものだと思う。音や感触への反射だったり、感情そのものによる自動的な筋肉の収縮と弛緩によってもたらされるもの。だからたとえば、ほら――」 と、彼女は立ち上がり、両手を広げて、呼吸に合わせてゆっくりと動かす。 「呼吸って、好きなの。呼吸だけでいろんなものを感じることができる。吸って――吐くだけ――。それを入力として、筋肉に伝えると、こうやって勝手に腕や足が動いて、それが意識にフィードバックされてくる。私はただ、自分の肉体の喜びを眺めるだけ――」 彼女は呼吸に合わせて単純な動きを繰り返す。 「エロいでしょう?」 見透かしたように訊ねてくる。 「でも、反射なんだよ、ただの。この動きにエロスを感じるとしたら、水揚げされたタコにだって欲情できるはずなんだよ、本当は。でも、タコだとそうはならない。人間同士だから、肉体が感応する」 彼女はただ、呼吸に合わせた動きを繰り返す。そして、 「このエクスタシーの中心にある力に満ちた静寂が好き」 そういうと動きを止めて、またすっと現実にもどってくる。 「自分のことをエロいって思ったことはないの。小さい頃からずっと、いまも。色気とは無縁だと思ってた。あんまり自分のこと綺麗だとも思わないし。私の裸を見て欲情する男とかバカなんじゃないのって思う。でもアタマで意識することをやめて体に好きにさせてると、体が勝手にエロスを醸し出して、しかもそれが私の中にフィードバックをくれる。肉体がエロスを醸すと同時に、私の意識にも快楽を伝えてくる。だけどそれは悲劇なんだよ、私にとって。男は集まるし、奪われるし。でも、肉体なんか犬にくれてやっていい。宇宙と一如になった一瞬の快楽に、人生のすべてを捧げていい」 彼女の口を突いて出る言葉はどれも真新しかった。だけど僕の胸の深いところにも、それの落ち着く場所があった。もちろん、完全にわかるともいい難いのだけど。 「男でもそうなのかな?」 「男でもそうだよ。病気や断末魔でもがいてる男の動きとかめちゃくちゃエロいよ」 「そこ?」 「芸術家の良いところは、それでも自制心を持って観察者でいられるところ。でも、そうじゃないひとが多い。裸を見ただけで欲情するクズばっかり」 「いや、それはしょうがないでしょう」 テレビの中では彼女が踊っていた。男と絡み合い、服もはだけて、それがエロスを醸していることは彼女も知っていながら、それに欲情するものをクズと切り捨てる。 「ちょっと、聞いておきたいんだけど」 そう訊ねると、彼女は目線だけで話を促す。 「どうして僕と深宇宙移民団に志願しようと思ったの……ですか?」 距離感に悩みながらのたどたどしい質問に、彼女は少し言葉を選ぶ。 「沙也加の元彼でしょう? じゃあ人格的には大丈夫。しかも三叉かけられて従順に従って、音楽をやってて、沙也加と別れたあともガツガツしてなくて、あなたから沙也加を奪っていった男とも普通に会ってるし、私としては最高だと思う」 最後に褒められたとわかったけど、全体としては貶されたように感じた。 「うん、でも。中江さんにしたらそうかもしれないけど、僕たちは会ったばかりで、恋人ってわけでもないし」 「別に、たまたま気が合ったふたりとして宇宙移民に行けたらそれでいいんじゃないかな。恋人になるだけが付き合い方じゃないと思うし。お互いの胸にいちばん好きな果実が実っていても、それを食べるかどうかって別の話でしょう? それに、なんとなくずっと昔から、あなたのことを知ってる気がするの」 そういうと彼女は冷蔵庫から薔薇の花束を取り出して、深皿をその花弁で満たして机に乗せる。 「これは?」 「食用の薔薇」 僕は少し戸惑う。 「おなかの子の父親はいるんだよね?」 「父親じゃないよ。私は子を生んだ時点で母親になるのだと思う。だけど父親は子が認めるまでは父親じゃない。ただお互いの果実をかじっただけで、それは子には関係ないことでしょう?」 彼女は薔薇に牛乳と蜂蜜をかけて、スプーンを差し出す。 「親だから子に尽くすんじゃないんだよ。親になる権利を与えられて、子に尽くして、それをまっとうしたものだけがようやく親として生きた証を残せる。そういう考えは分かるひとだって思った。千駄ヶ谷の集いで何度か声を掛けたことあったんだよ、私。あんまり興味なさそうだったけど。覚えてなかったでしょう、私のこと」 僕は薔薇の花弁を乗せたスプーンを口に運びながら、上目遣いに「ごめんなさい」とだけ。花弁には少し苦味があって、その苦味を縫って薔薇の香りが広がる。 「薔薇の花は初めて?」 「ええ。薔薇は」 蜂蜜の甘さが口の中に残って、それを洗うように冷めたコーヒーを流し込む。 食べ終える頃にはビデオも終わって、僕はふと、鏡台の奥に置いた金属質の黒い塊に目が留まる。 「あれは?」 「ああ、あれ?」 上半身を伸ばして、転がるようにして鏡台に取り付いて、彼女が手に取って見せてくれたものは、拳銃だった。 「友だちが置いていったの」 「本物?」 「わからない。でもたぶん本物。重いし」 そういって手渡された銃には、たしかにずっしりとした重量があった。大型のリボルバー。隠しもせずに無造作に部屋に置かれた拳銃。その異質さ。 「弾もあるの?」 「一個だけ入ってる」 「これを預けた友人って何者? ヤクザ?」 その質問に、彼女は答えなかった。少し踏み込みすぎたのかもしれない。 「これが私の『一切れのパン』なの」 一切れのパン――言葉の意味を探っていると、彼女は拳銃を右手に構え、 「よく、自殺する時、こうやって構えるじゃない?」 銃口を自分のこめかみに当てて見せる。 「これで鏡を見て思ったんだけど、ちゃんと銃口が頭の方を向いてないんだよね。私の手が小さいせいかもしれないけど」 一個だけ弾が入っているという銃を、彼女は無邪気に自分の頭に向ける。 「銃口をこめかみに向けたこの感触が好き。でもその感触もだんだん薄らいできた。最初は引き金に指を掛けることすら手が震えたのに。いまはほら」 彼女は引き金に掛けた指に、少し力を入れてみせる。 「ちょっと見せてもらってもいい?」 「いいよ。撃ちたきゃ撃っても」 苦笑いして受け取って、シリンダーを回してみると確かに弾丸が一つだけ詰まっていた。 これが一切れのパン――というのはたぶん、『最後の希望』みたいな意味。 「説教するわけじゃないけど、ちょっといい?」 「いいよ。説教でも」 「人生って、そんなに素晴らしいものじゃないと思うんだよ。『生きてりゃ楽しいことがある』とかも嘘だし。べつにひとが自殺したいっていうのを止めることもないと思うんだ。でも、何ていうのかな。僕は自分のことは楽器だと思うんだよ。その楽器が壊れて、音が鳴らなくなるのは嫌じゃない? 生かしておけばいつか、音を奏でるんだよ。だから、まあ、しょうがないな、って感じでメンテナンスしてる」 「幹夫くんが楽器ってことは、私は?」 「なんだろう。オルゴール?」 「そうか。じゃあ、壊さないようにしないと」 本当は楽器やオルゴールである必要すらない。ただ空の色を眺めるだけの何か、風の音を聞くだけの何かでいい。生きる理由も死ぬ理由も何もない。そう伝えると、彼女も頷く。 このまま銃を預かってしまいたいのはやまやまだった。だけどそうやって強引に決められることを彼女は嫌うだろうと、差し出された手に、銃を返した。 「ねえ」 「なあに?」 「沙也加からはなんて呼ばれてるの?」 「亜実。あなたもそれでいいよ。そうしたら私も幹夫って呼べる」 「じゃあ、亜実……さん」 「ダメ。やり直し」 「亜実……。もう1回ギター弾いてもいい?」 彼女は何もいわないで、口角を上げて2回頷く。 最初の音が出た瞬間から、彼女の体は僕の音を拾い上げた。 6本の弦から出る、すべての音を、その体、すべてを使って。 * 18日、土曜日のマチネ。 下北沢、無宿者の里に駅馬車が迷い込む。街道から外れた深い谷の集落に、水を切らしてやむなく降り立つと、見慣れぬ店、針金で作ったアクセサリーを売るひと、ラスタ・カラーの帽子。人垣を縫って、駅からの坂を下る。 劇場へ行くと、入り口の前に彼女がいて、見知った顔を見つけて挨拶をしている。 僕の顔を見つけて、胸に手を当てて小首をかしげる。 僕もなんとなく手を降って返すと、 「舞台のあと、楽屋へは来てくれる?」 と、声をかけてくる。 「いや、ちょっとこのあと、行くところがあるから」 「なーんだ。それは残念」 ごめんなさい。苦笑いして、もういちど手を降って、席へ向かう。 本当のことをいえば、消えてしまいたかった。とくに行くところがあるわけでもないけど、たくさんの知り合いに声をかけてる彼女を見て、少し距離を感じていた。古くからの知人に混じって、僕なんかが彼女と話をしてもいいのかなっていう疎外感。彼女がどんな人生を辿ってきたか、舞台で何を表現しているか、何も知らないのに。 客電が落ちるまでチラシの文字を拾い続けた。拾ってもすぐこぼれる。拾っても拾ってもこぼれて、また拾って、こめかみのあたりに押さえる。 上演されたものは、僕がいままでに見たどんな舞台とも似ていなかった。 サーカスに売られた少年がひとを愛することができなくなって、サーカスを憎んで、愛憎渦巻くサーカスから抜け出そうとする。だけど、やがて戦争でサーカス以外のすべてが滅びると、やっと少年はひとを愛することができるようになって、エナメルのビスチェを着た猛獣使いの女と結ばれる。最後は持っていた卵からガチョウが孵化するというお話。ガチョウが何かを象徴しているようにも見えたし、ただガチョウが舞台にいる面白さを狙っただけのようにも見えた。 次の日曜のソワレでもう千龝楽。 その次の月曜、朝まで飲み明かした酒臭い亜実とふたりで、杉並区役所へ向かった。 申請書類は木村さんに用意してもらったもので、再募集枠。期日が迫っているので抽選はなく、簡単な書類審査のみで通る。提出は全国どこの市役所でも良かったけど、ふたりとも杉並区に住んでいたし、そこにした。もし結婚することになるとしたら、婚姻届もここに出すんだろうと思ったけど、申請が受理されたら二ヶ月後には宇宙に飛び立つ。それに亜実は結婚なんか考えないひとだと思う。 書類を出して、亜実がもう眠くて限界だというので、待合室のベンチに座って、膝の上で寝かせた。手を握って、髪を撫でて。エンドウ豆の上ですやすやと眠るお姫様。 千駄ヶ谷の集いで話した日から、まだ一週間。 僕たちの関係はなんなんだろう。 * 6月も終わりかけた水曜日、移民局から封書が届く。 深宇宙移民団申請の審査通知。その結果に驚愕した。 亜実のおなかの中の子がひとりとカウントされ、その二名の申請が受理され、僕の申請は却下。しかも、未成年者が混じることでコールドスリープが必要な深宇宙移民団から、金星移民団へ振り替えられていた。このところ政府の仕事が雑だという話は聞いていたけども、雑というレベルを越えている。 すぐに移民局に確認の電話をかける。決定事項を伝えてあるのであれば、それ以上説明することはないとの一点張りで、電話を切られる。 その日の夕方、亜実の部屋へ。 土間には住人のものらしからぬ大振りの革靴があって、亜実への来客だったら気まずいと、端の部屋から順に聞き耳を立ててまわった。真ん中の部屋、亜実が『夜の仕事をしてるひと』といってた住人の部屋から賑やかな音が聞こえて、胸をなでおろす。念のため、亜実の部屋でも耳を押し当てて、ひとの声のないことを確認して扉をノックする。 「はーい。どなた?」 「幹夫です」 亜実は小さく開いたドアから僕の顔を確かめ、中へ通してくれた。 部屋はこの前来たときよりも散らかっていた。あの日はちゃんと片付けていたんだ。布団は敷きっぱなしで乱れ、こたつの上にはビールの缶が並ぶ。洗われていない食器、スナックの袋もそのまま、そこに散らばる薔薇の花弁は赤黒く、部屋全体に彼女の匂いが立ち込める。脱ぎ捨てた服、雑誌の山が崩れ、足の踏み場がない。 亜実は掛け布団を寄せて布団の上に場所を作る。 散らかった部屋の中の、いくつかのゴミ、薔薇の花弁を丸めてゴミ箱に入れる。僕には見せたくないなにかを隠すように。 「待たせてごめんね」 彼女が腰を下ろす。 「これを見て」 すぐに移民局の書類を布団の上に広げて、重要事項を指で追う。 「亜実とおなかの中の子、ふたりの申請が受理されて、僕は却下。行き先も金星移民団に変更されてる」 彼女は書類を目で追って、僕の指をどかし、虚ろに文字を拾う。 「じゃあ、しょうがないか」 静かに鈴を鳴らすような声でつぶやく。 「うん、でも。ここの注意書き見て」 小さな囲みを指さして、説明を続ける。 キャンセルはできるけど、キャンセルしたらもう他の移民団にも応募できなくなる。だからどうしても深宇宙移民団に申請したいんだったら、この手続の訂正を求めないといけない。そう伝えると、 「もういいよ」 亜実は静かに吐き出す。 「いいって、何が?」 「このまま地球で暮らす。天変地異なんて来ないよきっと。それに、幹夫にも無理いってごめん。最初から乗り気じゃなかったよね」 「乗り気じゃないって、何が?」 いってることが唐突で、意味がわからなかった。 「別れよう、もう」 「いや、待って。どうしてそうなるの? 何かあったの?」 「ぜんぶいわなきゃダメ?」 だめじゃないけど。そう聞いて、亜実のおなかの子のことだと思った。それはずっと感じていた。亜実には僕の知らないところがたくさんある。彼女は何かしらのトラブルから逃げ出すために僕にすがっているだけで、その動機が愛じゃないのもわかっている。 でも、よく考えてみたら―― 「僕たちふたりの関係って何? 恋人じゃないでしょう?」 うん、といったあと、彼女は少し言葉を選んで切り出す。 「ふたりの間に名前って必要なのかなあ。『恋人』とか『友人』とか、そういう名前、役割って必要なのかなあ」 「僕は必要じゃないよ。僕たちはなんでもない。ただの幹夫と亜実でしょう? なのに『別れる』って、何が? いままでの関係は何という関係で、別れたあとは何ていう関係になるの?」 目を見るのを躊躇われて、彼女の膝のあたりを見ながら話した。 「じゃあ、わかった」 わかった。わかったって、何を? 「今日これから恋人になって、それから別れよう」 顔を上げると、彼女は笑った。 「そうしたら、別れてくれるんだよね」 彼女の気持ちは読みようがなかった。弄ばれてるだけのような気もするし、もし何か僕に引け目を感じているのなら、そんなことは気にしなくていいのに。 「いいよ。これから恋人になって、別れて、そのあとは昨日までといっしょってことでしょう?」 そういうとまた、意に介さないような目をして、言葉を淀ませる。 「そうだね。幹夫と亜実をやめるわけじゃないよね」 「うん。僕の初めての恋は一晩で終わることになるけど、そこはまあ」 これが初恋――おおっぴらにいうことでもないけど、恋らしい恋はしたことがない。 小学校の4年生の頃に好きな子はいたけど、そのあとは音楽しかなかった。沙也加との付き合いはあったけど、あれだって恋じゃない。 「私もそう。恋は初めて」 と、彼女が答える。 本質的に僕たちは同じなんだ。世間がイメージしているような恋なんかできない。雑誌に書かれているようなデートもできないし、ひとが憧れるような甘い生活も思い描けない。ただお互いにわかりあえるいちばんの親友が欲しいだけ。それがたまたま同年代の異性で、それを恋だなんていわなくていいし、いまのままでいい。 「じゃあ、今晩だけ恋人になって、別れて、明日からはいままでのままでいよう。移民局に行って手続きしよう。そしてふたりで深宇宙移民団にちゃんと申請しよう」 そういうと亜実は少し目を伏せた。 「そこまでいってくれるなら」 と、ため息を吐く。 「それじゃあ、恋人になろう。僕の告白から始めるね」 「うん」 と頷いて、彼女は鼻のあたりに手を当てて笑い出す。 「私、31だよ。告白って言葉にこんなにときめくとは思わなかった」 その晩、ふたりは恋人になった。 一晩きりの恋人だから、急いでいろんなことをしなければいけなかった。 まずは雑誌の一冊を引っ張り出してきて、相性診断して、ラッキーカラーを調べて、今年の春にオープンしたばかりのディズニーランドに行くことに決めた。布団に横になって、天井を見ながら―― 「じゃあ、目的地に着きました。駐車場に車を停めて……」 「どこから見て回る? やっぱりシンデレラ城?」 「トム・ソーヤ島!」 「じゃあ、いかだに乗らないと。少し並んでるかもしれないけど、いい?」 うん、といって、彼女が僕の手を握る。 ぎゅっと握ったその手は小さい。 しばらくふたり、ポップコーンを食べながら、島の中を歩いた。 ふたりで交互に見上げる天井に、いろんな景色が浮かぶ。ふたりの吐息が部屋を暖めて、彼女の匂いの中に、僕の匂いが混じっていく。 いつの間にか眠りに落ちて、次の日の朝。 目を覚ますともう彼女は起きて、横になったまま僕の顔をながめていた。 「早いね。起きてたんだ」 「うん。さっき起きた。いまはまだ恋人だよ。これから喫茶店で別れ話をするの」 本当にそういう流れなんだ。そのあとはどうなるんだろう。とは思ったけど、ひとの心なんか探りようがない。いまが恋人だったら、いまできることをしたい。 「じゃあ、あと30分だけ」 昨日は会話の流れで恋人ごっこみたいなことになったけど、それが亜実の本心かどうかはわからない。でも、何が本心で、何が本心じゃないとか、そういうのは無いんだ、たぶん。布団の中にはまだ、柔らかい時間が残っていて、手で触れると少しずつ、少しずつ、その温度を失っていく。恋人の時間も終わり、僕の肌に貼り付いた薔薇の花弁。喫茶店に向かう前に、この前いい出せなかったことをいった。 「拳銃、僕が預かってもいい?」 「もしかして私、信用ない?」 「違うよ。亜実が引き金を引きたくなった時に、僕のことを思い出して欲しいだけだよ。その時が来たら絶対に止めない。だから」 「うん。でもそれは私の手綱を握るっていう意味だよ?」 「そうか……。じゃあ、僕の部屋の鍵を渡すし、拳銃を置いておく場所も教える。書きかけの恥ずかしい詞も読み放題だよ。それでどう?」 そのあと、近くの喫茶店に入って、別れ話をした。 温かいコーヒーで口を湿らせて、少し息を落ち着かせるようにして、彼女から始める。 「ごめんなさい。もう、無理なの」 コーヒーカップふたつ間に挟んで、「これってただの『別れ話ごっこ』なんだよね?」と確かめる間もなく、さよならのムードが僕たちを包む。 「どうして? ちゃんと理由をいってくれなきゃわからないよ」 すぐに周りの客が、耳をそばだてる。 「あなたに迷惑をかけたくない」 「迷惑だなんて思ってないよ」 「最初に、私のおなかに子どもがいるって話したときのこと、覚えてる? それを聞くとね、ほとんどのひとは父親はだれ? とか、生むの? 育てられるの? って聞いてきたの。でもあなたは違った。舞台に立てるの? って聞いてきたよね。私、無理だって思った。このひととつきあう資格は私にはないんだ、って。でも、私なりにがんばったの。抜け出そうと思って」 「いいよ、そういうことは気にしなくても。そんなことが原因だったら、ふたりが別れる理由なんて、どこにもないよ」 「違うよ。だからなんだよ。これからも私、怯えて暮らすんだよ。あなたが私を責めないから、私は自分で自分のこと責めるしかない。あなたはもっと幸せになれるんだよ。私なんかと宇宙移民に志願しなくたって」 「僕の幸せを勝手に決めないで欲しい。僕はただ、音楽があれば幸せになれるんだから」 「だったら私はもう要らないよね。それだけが心残りだったんだ。うぬぼれっていわれるかもしれないけど、あなたを不幸にはしたくなかったの。でも、これでもう悔いはない。幸せになって。私なんか忘れて」 「あのね、亜実。100%の幸せで足りるんだったら、僕は僕以外の何も要らない。でも、君がいてくれたら200%、それ以上に幸せになれる。お互いにそうだよ。たとえ僕と別れても、君は100%幸せになれるよ。君だったら絶対。だけどふたりなら、200%。その余った分の幸せは、次の世代につながっていくんだよ」 彼女は顔をそむけ、遠くを見て涙を堪えて、二回の瞬きに続けてそれが溢れる。 僕もだんだん演技なのかなんなのかわからなくなってくる。 「別れたくない。演技でもなんでもなく。本気なんだよ」 「相手がクズだったら、私だって悩んでない。どんなに奪われても、裏切られても、傷ついたりしない」 涙を堪えながら、途切れ途切れに彼女は話して、 「ごめんね。もう決めたの」 席を立ち、店を飛び出す。 僕が思わず立ち上がると、周りの客もハラハラしてこちらを見守っている。僕はといえば、自分でも驚くほどにショックを受けている。演技だから、本当に別れるわけじゃないから、昨日までのふたりに戻るだけだから、そう自分にいい聞かせてみるけど、店を出た亜実がどこに駆けていったかという不安が胸の中に膨らむ。 急いで会計を済ませて店を出てみると、そこに待っていた亜実が僕にしがみついてきた。 細い背中を抱きしめると、彼女の小さな手が僕の顔を掴む。 小学校の4年生、遠足のとき、友だちにもらったコーヒーキャンディの味が口いっぱいに広がる。 降り出す天気雨。 そしてこの街のすべての花が開き始める。 * 翌日はもう7月。金曜日、有給を取る。 気がつくと僕は、区役所に向かっていた。 区役所の移民課の待合室には、僕と同様の問い合わせらしきひとが順番を待ち、窓口ではカウンターを挟んで三十代の男が担当と向かい合っている。 聞こえてきた話では――キャンセルには身分確認が必要だが、申込時に身分確認されていないのでデータベースでの照会がエラーになり、キャンセルはできない。では、キャンセルできなかったとして、移民船に乗らなかった場合にどうなるかといえば、その時にはもう日本国籍を失っているので不法滞在者として本国に送還される。本国とはどこかとなると、これもデータが存在しないのでエラーになる。収監までは執行されるが、そのあとは不明。区役所は窓口業務を請け負っているだけで、詳しいことはわからない。 あまりにも手続きに不備が多い。 そのやり取りを聞いていた順番待ちのひとたちが立ち上がり、ひとり、またひとりと窓口に詰め寄る。だけど抗議の数が増えたからといって問題が解決することはなかった。システムの不備を修復しなければどうしようもない。 手続きをしていた男は最終的には暴れだして、警備員に腕を掴まれて裏に連れて行かれた。その姿を目の当たりにしたせいか、そのあとの2~3人はやや落ち着いた対応をしていたけども、僕の前のひとはやっぱり暴れて、裏に連れて行かれた。 そして僕の番。 窓口の椅子に座って、カウンター越しに手続きを始める。窓口の男の腕には青い腕章がある。二重螺旋をあしらった、宇宙移民局のマーク。 「どういったご相談でしょう」 水を向けられ、現状を伝える。おなかに子がいる女性が二名として扱われているが、これをひとりとして扱って欲しい、申請をしたのは僕とその女性なので、このふたりで申請の手続きを進めて欲しい。そう説明したが、結果は前のひとたちと同じ。まったくもって埒が明かなかった。 話を聞いていると問題はデータ入力のソフトウェアにあると思えた。もしかしたら地方の電子化が進んでいない役場だったら対応が違うかもしれない。システム的には対応窓口を変更してもらえれば良いだけ。その旨申し出ると、担当窓口の変更は住民票を移せば自動的に変更されるという。それならと、あとで亜実にも相談して、一時的に住所を移せばよいかと思ったのだけど、後ろから苛立った声が遮る。 「やめたほうがいいよ」 振り返ると、順番待ちしている男が憮然とした表情でこちらを見ている。 「俺もそれで手続きしたんだ。だが昨日、羽村の町役所で、移民申請中は住所の転入は認められないっていわれて、それで文句いいに来てんだから」 確かに、ここまで破綻したシステムで、住所変更だけうまく行くはずもない。八方塞がりという言葉はあるけど、八方どころか上下まで含めて全方位すべてが塞がっている。 そのあと、営繕課を訪ね、区役所で使用しているソフトウェアに不具合があることを指摘し、改修を促してみるが話の通じるものはいなかった。区役所のコンピューター導入はこの5年間で急激に進んだ。営繕課内にシステム管理係があるらしいが、電話があるだけでスタッフは常駐していない。 結局、区役所を訪ねてみてわかったのは、移民のキャンセルは不可能、移民船に乗らなかった場合は不法入国者として収監され、そのあとはどうなるかだれにもわからない、ということ。宇宙移民政策が性急に進んだとはいえ、この状況を放置するのはどう考えてもおかしい。 僕は亜実にどう説明すれば良いのだろう。もし通達通りに金星移民団の船に乗るとしたら、金星へはコールドスリープではないので、船の中で出産することになる。乗らないとしたら不法滞在で収監され、獄中での出産。果たして何の罪も犯していないのに、どうしてそんなことになるのか。 営繕課、設備科、経理と回って裏口から市役所を出ると、地面に赤い雫が落ちているのが見えた。もう、悪い予感しかしない。 その日の夕方、千駄ヶ谷に木村さんを訪ねる。 彼のほうが世間のことに詳しい。表社会も、裏社会も。 アパートの前まで来ると、木村さんは庭に七輪を置いて、サザエを焼いていた。 裸電球ひとつ灯る下、勧められるがままにビールとサザエを頂きながら、移民団の現状を話した。 「あー、そんなことになっとったんか。すまんかったな」 楊枝でサザエの身を取り出しながら、木村さんは語った。 「実はな、俺のところにも来んのよ、区役所の苦情処理請負の話が」 「苦情処理というと?」 「苦情が来えへんようにするんちゃうん。ようしらんけど、怪しすぎて断ったわ」 木村さんがいうには、移民局のソフトウェアの不備は以前から指摘されていて、その修正パッチもできている。その話を聞いてしばらく経つので、対応はできているものだと思っていた、と。まさかの話ではあるが、それが事実であれば可能性も見えてくる。移民団が出発するまで2ヶ月しかないが、急いでソフトウェアにパッチを当てて変更手続きをすればいい。 「でも、ずっと放置されとるわけやろう? これはおそらく、あれやね」 「あれ? あれというのは?」 「もう政治家は地球におらんって話、聞いたことあるやろ?」 「ああ……」 この前の千駄ヶ谷の集いでも、その話をしていた連中はいた。政治家や資産家はもう地球を見限って宇宙へ旅立った、と。いつもの与太話だと思って聞き流していたけど…… 「もうプログラムにパッチを当てるにも、判断できるトップがおらんのとちゃうん。それでヤクザもん集めてなんとか繕うとる考えると辻褄合うやんか。しらんけど」 「いや、それで世界って動くものなんですか? そうしたら政治家は?」 「もうとっくに火星に移民しとるて。上の連中で火星が満杯になって、それで庶民は深宇宙に捨てとるて。噂やけどな」 それが事実だったら、地球はどうなる? 司法も行政も機能してないとなったら…… 「まあ、ヤクザもんのやり放題やろうな」 「やり放題やろうなって、木村さんはどうするつもりですか?」 「どうもこうも、ここで暮らすしかないやんか。移民団に申請してもええけど、俺としてはそういうのは若いもんにまわしたいわけよ。俺もまだ40やけど、もう子ども作る気もないし、人類としては種蒔かんとしゃあないやん」 木村さんはそういって笑うけど、人類ってそうやって繁殖するために生まれたものなんだろうか。子を残せないものは座して死を待つような、人類が築いてきた文化って、そんなものなんだろうか。 醤油の泡立つサザエをうつろに眺めていると、 「ほら、これ。焼けとるで」 木村さんはサザエをひとつ、僕の方に寄せる。 「前にもあったなあ、こうやってサザエ焼きながら話したこと」 「ありましたっけ?」 「あれ、古澤くんやと思ってたけど、違ったっけ?」 「違うと思います」 「そうかあ? そうやったかあ?」 木村さんは大げさに驚いて見せるけど、こんなシチュエーションを忘れるはずがない。 「でもあれやな。古澤くんもたいへんやな」 「何がですか?」 「亜実ちゃんのためやろ? いろいろ動いとるの」 「いや、中江さんのためというよりは、自分の理想のためというか」 「だからそういうところよ。亜実ちゃんの彼氏のこととか知らんのやろ?」 その言葉を聞くと胸が締め付けられる。 「知らないし、知りたくもないです。それで何か変わることはないし」 「いや、わかるで。古澤くんがそういうひとで、ひとの過去に踏み込まんのは尊敬しとるで。でも、亜実ちゃんに関しては、そういうレベルの話やないねん。これほんと、ふたりのためにいうねんけど、亜実ちゃんの彼氏、ヤクザやで」 僕が聞きたくなかったことが木村さんの口から、泡立つ醤油のように漏れてくる。 「うっかりしてると古澤くんも亜実ちゃんも帰らぬひとになるて」 「知ってました。薄々は」 彼女の部屋に拳銃があったこと、2回目に部屋に行ったときの変化、察する機会はいくらでもあった。ただ僕は、それを明確な言葉にしないように努めてきただけで。でも、だったらこの計画はどうしても降りられない。 「彼女と、深宇宙移民団の船に乗ります。それが変わることはないです」 「まあ、書類用意したのは俺やから、止めはせんけど」 喫茶店の前で彼女を抱きとめた感触がまだ手に残っている。胸の中で泣いたときの声。どんな言葉も介せず、ただ心臓から心臓へと流れ込む気持ちの起伏だけで共鳴しあって。彼女はもう、僕の一部だから。 「そうだ、木村さん」 「おっ、なんか思いついたね、古澤くん」 「プログラムの修正パッチ、僕にもらえますか?」 口に出してみて思ったけど、ここは「手にはいりますか」が正しい。いや、それでも唐突か。持っているはずがない。 「ああ、ええよ」 ええよ? 「前にもあったなあ、こうやってプログラムの修正パッチについて話したこと」 「前にも?」 質問を返してはみるけど、僕はいまの状況に戸惑う。 「せやけど区役所いって、端末のパソコンをアップデートせんとあかんねんで? パソコン管理してんのは、上の命令がないとなんもでけん小役人で、その小役人にどうやってアップデートさせんの?」 言葉の半分は耳に入る前に溢れていく。だけど、木村さんはこういうひとだ。言葉の辻褄なんてものからは開放されている。 「ぜんぶ、話してみます」 「まあ、そやな。それしかないもんな。まあ、やるだけやったらええわ。ちょっと待って。アップデートプログラムやったら昔借りてたクォンタム・メモリに入ってるわ。5インチのフロッピーとコンパチなんで、スロットに入れたらあとはなんとかなるやろ」 クォンタム・メモリは、量子式記憶装置は70年代のフロッピーディスクを置き換える形で急速に普及した。従来の資産を活かすために形状はフロッピーと同じ。5年前のビデオテープのような値段はするけど、それ以上の価値はある。 「これ置いて行った男が、いつか取りに来る思うてたんやけどな。たぶんもう死んでるわ」 といって、黒いプラスチックのスリーブを渡してくれる。それにしても、どうして木村さんが持っているんだ。 「まあ、できるだけ死なんようにな。亜実ちゃんのためにも」 木村さんは渋い顔に重ねて、笑みを浮かべる。 サザエをたいらげたあと、持参したヘアカラーで髪を染めてもらった。 ロック・ギタリストを気取って少し色を抜いていたのだけど、ぜんぶ黒に戻した。 「もし僕が死んだら、亜実に、移民のキャンセル手続きをするように伝えてください。僕、それだけは確実にやって帰りますから」 木村さんのアパートから自分の部屋へ戻り、それでもまだ決心はついていなかった。背中を押したのは次の日のニュース。吉祥寺でヤクザの銃撃戦。僕が動かなければ、この街は変わらない。 月曜日を待って、亜実から預かった拳銃をカバンに入れて区役所へ向かった。 クレームで混み合う移民課を避けて、二階の奥にある営繕課。昼休み、職員が一人になるタイミングを見計らって中へ。 僕の姿を見留め、 「はい。何か?」 不審がる小役人に、 「機材のことでお話があります」 と、銃を向ける。 「大声を出してもいいですよ。僕、この銃が本物かどうか知らないんです。もしおもちゃだったら、あなたはヒーローですよ。警備員につまみ出されてボコボコにされる僕を見て笑えばいい」 小役人は手を上げてゆっくりと立ち上がる。 「サーバー室に案内してください。ソフトウェアをアップデートしたいんです」 「管轄じゃないので、システム管理係の方へ……」 「サーバー室だって蛍光灯は切れるでしょう。蛍光灯、確認しに行きましょうよ。中へは入れるでしょう?」 男は怯え、ゆっくりと頷く。 「目立つので、手は上げないでもらえますか?」 男を廊下へ出し、サーバー室へ向かわせる。カギを開け、扉が開いたら中へと促し、壁に手をつかせて背を向けさせる。 「僕、何か悪いことをしていますか?」 「いいえ、何も」 か細い声で男は答える。 「ですよね。悪いのはシステムなんですよ。知ってますよね。そんなものを守って死にたくはないでしょう?」 サーバーらしきものは一台しかなかった。フロッピーディスクドライブが接続されている。クォンタム・メモリを挿入すると、ソフトのアップデートを実行するか否かのウインドウ。キーボードのYを押して実行する。 「何をする気か知らんが、ど、どうやって、逃げ出す、つもりですか。僕を、僕を殺さない限り、逃げられませんよね?」 男が怯えながら聞いてくるけど、逃げ切るのはもう、オプションでしかなかった。最悪の事態――亜実が不法滞在者として逮捕されるようなことを避けられたらそれでいい。そう思いながらふと、亜実がいっていた『一切れのパン』という言葉を思い出した。 僕がこの男に向けているのは、彼女が大切に持っていた最後の希望。 僕が逮捕されたら、その最後の希望はここで失われ、彼女は移民をキャンセルし、ヤクザの彼氏のいるこの世界に留まる。この銃はてっきり、彼女の不幸を終わらせるためのものだと思ってたけど、そうか。ヤクザの幸福を終わらせるためのものかもしれないんだ。 ――僕がやったことは何だったんだろう。 ただ彼女の希望を奪っただけなのかもしれない。 アップデート終了のビープ音が鳴る。 僕は営繕課の彼に銃を向けたまま部屋を出る。 廊下を走り、階段を駆け下りる頃に全館に警報が鳴り始める。 通用口を出ると、3人の警備員が手を広げている。 立ち止まり、銃を構えてみせるがターゲットを絞りきれない。 そのうちのひとりが体を低くして僕に向かってくる。 残るふたりは銃を構える。 僕は、亜実から預かった一切れのパンを、口に運ぶ。第3章 小役人・古澤幹夫
東京から初めてオーロラが見えた日。昭和42年。僕はまだ中学生だった。 進学祝いのラジオで聞いた、ドアーズ、ザ・フー、ヴェルヴェッツと、姉が買ったハード・デイズ・ナイト。お下がりのギターと、安いアンプが鳴らす歪んだ音。小学校の4年生を最後に、恋のことなんて忘れてしまった。 そしていま、僕の部屋には、いつどこで手に入れたかわからない拳銃がある。 おそらく、コルトパイソン。中学の頃に買ったモデルガンに似てるけど、どこか違う。たぶん、本物なんだと思う。弾倉には一発だけ弾が込められ、時に苛立ちながら、時に落ち込んで、銃把の重みを手のひらに確かめる。 区役所での仕事は、いつも僕を苛立たせた。 移民手続きにミスが多いのはわかる。だけど僕は窓口でしかない。怒鳴られたところで何の権限もないし、僕が謝ったところで何も解決しない。目の前にいるのは僕とは無関係の残念なひとたち。哀れだとは思うけど、運のないひとなんてどこにだっている。杉並区役所で移民課に勤務するようになって1年。最初は窓口の申込みの受付がメインだと思っていたのに、クレーム処理しかしていない。 だけどこれ以上はもう、耐えられない。 5月も終りに近い週末、僕は辞表を書いた。 課長は移民局に詰めることが多く不在がちだった。引き止められるのも面倒だと思って、この機会にと4階の人事課へ向かう。扉を開けると区長の姿が見えた。区長は僕を一瞥し、隣に控えているヤクザ風の男と談笑している。 「辞表はどちらへ出せばいいんですか?」 机で事務作業をしているひとに聞いてみる。 「それでしたら、こちらではなく上長の方へ」 「課長は移民局に行って不在なので。もう、今日で辞めるので、これを」 と、応対してくれたひとの机に辞表を置くと、 「移民課のクレーム処理係だね?」 区長が訊ねてくる。 「クレームはもう、彼の方で引き受けてくれるから、明日からは業務は正常化するよ。辞表は明日まで待ってもいいんじゃないかな」 そういって区長とヤクザものは外へと出ていく。 「あれは?」 「第4章 渡世人・古澤幹夫
バイオリン弾きの少年に会ったのは、高校生の頃。 近くの丘から、オーロラが見えた日。 丘といってもただの傾斜地。家も建てられず草木が生い茂るだけの斜面を、コンクリートの階段が二つにわける。高校卒業の単位が取れるかも怪しくなってきた頃、授業にも出ないで昼間から丘に座って、町を見下ろした。夕焼けも終わりかけると、そのオレンジを仄かに残して、この空をオーロラが覆う。あいつはたぶん、オーロラに乗って来たんだと思う。 夕方になると決まって現れて、バイオリンケースを抱えて通り過ぎた。丘を越えた先にはブルジョワが住んでいる。誘拐でもしてやろうかと考えていたら、ある日その少年は、バイオリンケースを置いて、腰を下ろした。 「僕も今日は休む」 名札から、小学4年生だとわかる。 「バイオリン弾けるのか。すごいな」 「練習したからね」 伊藤栄次。名札の文字はうっすらと滲んでいた。 「サボってると、俺みたいな落ちこぼれになるぞ、栄次」 名乗ってもいない名前を口にされ、こちらを睨みつける。 「才能が違いますから」 生意気なガキだった。 「おまえ、相手見て話せよ。俺は古澤組の次男坊だぞ。古澤組ってわかるか? 昔からこの町を不届きものから守ってる正義の軍団だ。その古澤組の幹夫。木の幹の幹と夫で幹夫だ。親父の名前は第5章 搭乗者・古澤幹夫(2)
僕と亜実を乗せたシャトルは、衛星軌道上を回る宇宙移民船、ニニギ2号を目指した。 シャトルの高度が上がるにつれ、空の色は薄い青から、濃い藍色へと変わる。成層圏に入り、高度20キロメートルでシートベルト着用のサイン、母船から切り離されてロケットエンジンに点火すると、急激なGに驚きの声と、歓声、どこからともなく拍手が起きる。モニターには緩く円弧を描く地球と、移民船ニニギ2号の姿が映し出され、その細長い船体には、数機のシャトルが雀のように群れ集っている。ニニギは円筒状のブロックを23個ずつ連ねた2本の長い棒のような形をして、その2列のブロック群はそれぞれ、コノハナサクヤ塔、イワナガ塔と呼ばれる。 火星や金星への移民船はドーナツ型をしているが、太陽系外への移民船はこれとは異なる。光速近い速度で数十年から数百年飛行するため、星間ガスの抵抗を無視できなくなり、進行方向の断面積は可能な限り小さく設計される。このためニニギ各塔の外観は、銀河鉄道を彷彿とさせる直線形となる。これを人工重力を発生させるため、梯子状に連結させて回転させると、先頭のブロックと後方のブロックの同期のずれで二重螺旋を描く。宇宙を行くニニギの姿は、僕たちの遺伝子そのものだった。 「亜実! 地球の感覚と違うんだから、そんなにはしゃがないで!」 ニニギの人工重力は0.8G。 亜実は少し軽いその重力を楽しむように走り回っている。 「大丈夫だよ、幹夫! ジャンプするから受け止めて!」 亜実が大声で話すものだから、まわりのひとたちは変な目で見てるし、変な期待もされてる。 「そんなことしたら迷惑に――」 いい終わる前に亜実の身体が飛び込んでくる。 僕たちのシャトルが到着して10時間後、最初のシャトル到着から80時間が経った頃、ニニギはゆっくりと地球軌道を離れる。展望室で地球を見守るひとのなかには、歓声をあげるひともいれば、涙ぐむひともいる。おそらく、なかには深く後悔しているひとも。 移民船の各ブロックは4層で、1層から3層までが居住区。それぞれ2本の廊下が走り、1層あたり80のツインルームがある。最上階の4層には展望室とレクレーションルーム。事前の広報ビデオで見た印象よりはずいぶんと小さいが、最新型のゲームセンターやプール、スポーツジム、医療設備など、一通りのものが揃う。観葉植物はフェイクだったが、すぐにそうとわかる安物でもない。テレビゲームは6台。ディグダグ、ゼビウス、ルート16――なかでもゼビウスとマリオブラザーズはおそらくリリースされたばかりで、僕はここで初めて目にした。ゼビウスの画面を見ると、テレビゲームもついにここまで来たのかと溜め息が出た。ただ、それが無料でプレイできるとあって、居座るひともいて、トラブルの原因にもなっていたのだけど。「移民局のひとはいないのか」と、声を上げるひともいたけど、この船に乗っているのは移民を希望するものだけで、管理者はいない。自治のマニュアルも用意されているし、トラブルに対しては自分たちで対応するしかない。 プールやジムがあるといっても閉鎖環境ではストレスも大きい。トラブルを避けるにはコールドスリープに入るのが最善の策だが、コールドスリープに入るまでは、まだ時間がある。入眠まで最大で40日間は食事が用意され、搭乗者はその間の好きな時間に眠りにつく。――とはいえ、地球を離れると時間の感覚はなくなる。数日を経ると、いまが地球を経って何日目なのか、淀みなく答えられるひとはいなくなる。 廊下やロビーは24時間サイクルで調光されているが、部屋にいるとその感覚は狂う。そのまま調光された廊下に出ても、それが昼夜を表してるなんて実感はない。ただ廊下には明るいときと暗いときとがあるという感覚に置き換わっていく。地球で僕たちの時間を作り出していたのは、たとえばカーテンの色だったり、ソファの影だったり、窓の外の喧騒だったり、複合的な要因があったんだと気付かされる。いまにして思うと、部屋の匂いだって、家族の声のトーンだって、すべてが時間を紡ぎだしていた。 だけどその麻痺していく感覚の中で、僕たちは、時間からも、社会からも逃れ、自由を手に入れた。そこではもう、服装に気遣う必要もない。船の中では、そこかしこにヨガを嗜むペアが見られる。最初は目を伏せたものだけど、いつの間にか僕たちもその輪のなかにいた。あちらこちらで人肌から蒸気が上がり、展望室のガラスを曇らせる。亜実と僕もよく展望室で、プールに浮かんで、汗を流して、星空を眺めた。 それから、ふたりでよく瞑想した。ならんで瞑想していると、隣にいる亜実の意識が流れ込んでくる。宇宙へ出てからずっとその感覚はあるけど、瞑想をしていると顕著になる。 小さい頃によく幻覚を見ていたことを話すと、彼女もそうだったという。 それを恐ろしいと思ったのはごく小さかった頃だけで、それが何なのか解明したくて、探求して、二十歳の頃には呼吸法や瞑想で意識をコントロールして、自覚的に幻覚、あるいは明晰夢を見れるようになっていた。 明晰夢は明晰に見えているように感じてるだけで、実は明晰でもなんでもなかった。夢を見ているという自覚があっても、たとえば着ている服の模様をしっかりと見ようとしても解像度は上がらない。観察しようとすればするほど覚醒していき、夢は霧散していく。 金縛りにあうこともよくあった。金縛りはおそらく、脳が送る信号が体に接続されず捨てられている状態、車でいうとギヤをニュートラルに入れた状態だと思う。 そこに神秘を感じることはなかったし、神秘体験なんてしょせん、脳の中で起きている物理現象としか思っていなかった。 それでもある日、幽体離脱としか考えられないことが起きて、その時はさすがに衝撃を受けた。ソファで横になって眠っていたのに、いつの間にか僕は体を抜け出して部屋の中に浮いていた。 ――これが幽体離脱か。 と、思ったけども、その感覚からすぐに明晰夢だとわかった。 明晰夢は明晰だと感じているだけで明晰でもなんでもない。 ――僕はいま自分の体を離れて部屋を見渡している夢を見ているだけで、実際には眠っているんだ。 そう思って目を開けてみると、見ていたはずの景色は消えて、ソファの上で目を開くことができた。体には金縛りが来ていて動かない。憧れていた幽体離脱は、明晰夢と金縛りが同時に来ただけのものだった。 それまでもオカルトには懐疑的な立場を取っては来たけど、どこかに超常現象を信じたい気持ちもあった。だからこそヨガの呼吸についても調べたし、座禅もしたんだと思う。そんなオカルトへの憧れが決定的に消えたきっかけが、幽体離脱だった。 「僕、幽体離脱したことありますよ」 というと、大体のひとは訝しがるし、たまに羨むひともいるのだけど、僕にとって幽体離脱というのは、金縛りや明晰夢くらいにどうでも良いことになっていた。 だけどそれでも、亜実には何か違うものを感じる。 人間が見た世界の解像度と、タコが見た世界の解像度は違う。おそらく人間のほうが高い解像度で世界を見ている。人間より優れた宇宙人がいたら、もっと高い解像度で見ていると思う。じゃあ、解像度を上げた世界が本当に真実に近いかと問われるとわからない。解像度を上げれば明晰になると信じているだけで、あるいは宇宙が明晰であるということ自体が思い込みかもしれない。亜実は僕にはない感覚器を持っている。それを通して見る景色を、僕は知らない。僕は唯物論者でありながら、いまだに唯物の『物』の正体は知らないし、それが幻想である可能性を否定もできないでいる。 ふたりで息を切らせたあと、展望室のソファに肌を沈ませて、星空を見上げながら亜実はいった。 「せっかく宇宙に来たのに、ずっと重力の下なんてつまんない」 宇宙へ出ることの楽しみのひとつが無重力だったのに、このまま人工冬眠に入って、目が覚めたらそこは移民星なんてことになれば、バスに乗って旅行したのとそんなには違わない。 「パンフレットには無重力で遊泳が楽しめますって書いてあったのに」 「ああ、確かにそういえば」 僕たちの部屋があるのはイワナガ塔の第12ブロック。コノハナサクヤ塔への連結部分へ忍び込めたら、重力のない両塔の中間地点へ行けるかもしれない。 「じゃあ、きっとそこだ」 と、船内の探索を始めるとすぐに、レクレーション層内の小さな部屋に梯子を見つけた。天井に空いた幅80センチ程度の通路を上っていくと、先へゆくほどに体にかかる重力が減って行くのがわかる。いちばん先までいくと重力はほぼなくなって、直径5メートルほどの円筒形の部屋へ出る。 「パンフレットで見た部屋だ」 「写真よりずいぶん狭く見えるね」 どうやらその先、コノハナサクヤ塔とは隔壁で隔てられていたけども、そこには僕たちと同じことを考えたカップルが3組。僕たちが『無重力』と聞いて脳裏に浮かべたのは、『遊泳』なんかじゃなかった。 亜実は僕の手を取って、無重力のサーカスに誘う。火の輪くぐりのライオンと、エナメルのビスチェの猛獣使い。そのなかで僕は、恋が下手な少年に戻る。その空間で自由に泳ぎ回る亜実を見て、やっぱり僕は本音では亜実を独占したいんだと思った。 数日を経て、移民船の中の探索も終える頃には、退屈を感じ始める。 食堂へ行くと一日分の食事が手に入ったけど、基本はペレット状の何かと、それを流し込むための人工ミルク。まずいわけではないけど、毎日だとさすがに飽きた。これがひとりあたり最大で40日分供給されるというけど、これを食べ続けるよりは人工冬眠に入ったほうがましだと思えてくる。 人工冬眠装置は大きめの棺のようだった。ベッドも兼用になっていて、眠る時に『人工冬眠』のスイッチを入れると、移民先の星につくまで眠り続けることになる。あるいはタイマーをセットすれば、たとえば3年後だったり、10年後だったり、起きる時間を設定して眠りにつくこともできた。でも、食事がどうあれ、少しでも長く亜実といっしょに起きていたかった。もうその時間がないことがわかっていても。 退屈な食堂から戻ると、亜実はトランクから箱を取り出して、駄菓子を引っ張り出す。 「人工冬眠中に賞味期限切れるんだけど、どうする?」 その手に、モロッコヨーグルやジューC、粉ジュース、コリスのフエガム、テレパッチを抱えて。 トランクの荷物は、本や着替え、日用品、それに、ギター。このあたりは宇宙でも使うかもしれないけど、プレイヤーもないのにレコード、電波もないのにラジオ、現像できないのにカメラ。使いみちのないガラクタも、思い出として詰め込んだ。亜実のトランクには、衣装と、化粧品と、アルバムと、あとは大量のお菓子。 「もっと下着たくさん持ってきたらよかった」 あんまり深く考えていなかったので、僕の下着は5枚程度しかない。洗い替えはあるけど、破れたらもう替えがない。亜実の化粧品なんか、コールドスリープ中に使用期限が切れる。移民先では共有コンテナが開いて、その中に生活物資が収められているというけど、おそらくたいした量じゃない。パンツなんか何枚あっても足りないし、子や孫の代のことを考えると、パンツを作れる環境をどう構築するかが重要になる。 「向こうについたら、このパンツ、代々履くことになると思う」 そういって亜実はパンツを畳み直してしまい込む。 「あんたの婆ちゃんの婆ちゃんが、地球から持ってきたパンツの、最後の一枚じゃ。今日は晴れの日。履いていくといい」 などといいながら。 そして亜実はいつものように、僕の冬眠装置に潜り込んでくる。明かりを落として抱きとめると、濡れた闇はときめきの先端を、するりと飲み込む。 「ごめんね、亜実。後悔してない?」 向こうについたら、この居住区はブロックの外に出されて、それぞれの部屋が自立したコテージになる。だけどそれ以外のことは何もわからない。 「後悔? どうして?」 「ノアの方舟には、羊も乗っていたんだよ。おそらく牛や豚も。流れ着く先も、少なくとも地球だった。羊からは糸が紡げるし、服を作れる。文明を立て直すのは、そんなに難易度が高いことじゃなかったと思う。だけどいまは、資源が尽きたら何もできない」 僕の話に割り込もうと、何度かタイミングを図っていた亜実が滑り込む。 「私だったら大丈夫。この何日かで、一生分の幸せを得られたから。いまもそうだよ。幹夫とふたりでいるこの1分は、私が生涯を掛けてでも手に入れたい1分だよ。移民先の星で食べ物がなくなっても、パンツがぜんぶ破れても、幹夫とこうして眠りにつく前のまどろみを過ごせたら、それだけで私は幸せ。それに、誘ったの私だよ?」 冬眠装置の周りには、さっきトランクから引っ張り出した荷物が散らかっている。亜実の駄菓子も、僕の靴下も。 「冬眠中も夢って見るのかな?」 「うん。原理的には見ないっていわれていたんだけど、実際には多くの人が夢を見たって報告してる」 せっかく亜実とふたりきりなのに、眠るのはもったいないと思ったけど、転がっていたラムネを亜実が見つけて、蓋をあけて口に含むと、なんとなく寝ている間もお互いの夢を見れるように思えてきた。 ふたりでひとつの暗闇の中で、しばらくは感触、匂い、味覚とで、お互いの姿を探して、やがて僕と亜実の体の境目はなくなっていった。 「このままどうしようもなく甘い夢を見たい」 と、後ろから亜実を抱えて、そのおなかに手を添えて、ぬくもりの一部を委ねあったまま、『人工冬眠』のスイッチを押した。第6章 管理者・古澤幹夫
普段よりも、ずっと体の重い朝。 なかなか昨日の記憶が戻ってこない。目の焦点も合わず、耳だけで朝の喧騒などを探してみると、朝っぱらからレッド・ツェッペリンが流れている。 ――どこなんだ、ここは。 少し手足に痺れがある。 「おはよう」 抑揚のない男の声がささやく。 「目覚ましに移民の歌かい。どう? 自分のことは思い出せた?」 男の声はコミュニケーションを取ろうとしている。少し沈んだ声。無理に明るい言葉を紡いだような。僕の意識はまだぼんやりと、その意味をつかみきれない。ゆっくりと目の焦点を合わせても、何も見えない。 「まだ、はっきりとは見えないはずだよ。コールドスリープからちゃんと覚醒するには2~3時間はかかる。記憶も混濁してるだろうけど、バイタルは問題ない。現在気圧の調整中だ。あと30分でハッチが開く」 コールドスリープ? ということは、つまり? 「すぐに思い出すと思うけど、簡単に説明するよ。ここは、太陽系外の深宇宙へ向かう移民船ニニギの中。搭乗者数は2万1千人。大きくふたつのブロックに分かれていて、君がいるのはイワナガ塔と呼ばれる居住区だ。いまは地球を出て16年。ちょっとトラブルがあって、仕方なく君を起こしたんだ」 ああ……。そういえば……。なんとなく思い出してきた。 「おはようございます……」 今更だとは思いながらも、挨拶して、 「トラブルって……何が起きたんですか?」 尋ねてみると男はため息を吐いて、語ろうとした言葉をまた飲み込む。よほどのことが起きたのか、質問を変えてみる。 「あなたはどうして起きてたんですか?」 「結婚記念日だったんだ。毎年同じ日に起きて、だれもいない船の中で乾杯してたんだ。妻とふたりで」 「じゃあ、いまこの船で起きてるのは、あなたと奥さんのふたりだけ?」 「そう。夢のような時間を過ごすつもりでいたんだけど、まいったよ」 まいったよ。文末のその一言を脳裏にメモして、何度か強くまばたきしてみると、ほんの少しずつ視界が晴れていく。 「そうですか。お疲れさまでした。なんか、ずっと悪夢を見ていた気がします」 そういうとモニターの男は申し訳無さそうにいった。 「僕が夢を見せてたんだよ」 ――僕が、夢を、見せていた? 彼の言葉を頭の中で繰り返してみる。その意味はすぐには胸の中に降りてこない。僕が、夢を、見せていた。洗い物を水に沈めるように、何度か繰り返す。 「そうだな。どこから話そうかな」 不安定な声のトーン。軽い口ぶりを装いながらも、その表面に感情のさざなみが立つ。僕の胸にも少しずつ不安が広がる。狂気に沈む前、そのきっかけを待つような、不穏な静寂。 「管理マニュアルにも書いてあるんだけど、重要な案件の決定には投票が必要なんだ。だから、夢を通じて船の置かれている状況を伝えて、それで乗員の脳波がどう反応するかを確認する。だけど夢だからね、言葉ほどちゃんと伝わるわけじゃない。それぞれの個人の記憶をベースとして似たような状況が脳内に再現されるだけで、しかも、マスターの意識が混入する」 「夢の中で投票って……僕は夢の中で何の投票をさせられていたんですか?」 「そうだよね。まあ、気になるよね。詳しいことは覚醒してからログを見てもらうとして……じつは、日本政府が滅びたんだ」 僕の中で言葉が上滑りする。拾いそびれた言葉の意味を追いかける間もなく言葉が継がれる。 「この宇宙船には、日本国の法律が適用される。日本の宇宙船だからね、当然ここは日本ってことになっているけど、肝心の日本がもう存在しない。つい2週間ほど前だよ。昭和74年、7月15日、日本は滅びた。それまでは超光速通信で情報は入ってたんだけど、いまは何の連絡もない」 このひとは何をいっているのだろう。いや、いっていることはわかる。文字通り、日本が滅びたんだ。地球を発つ時に、地球はもう滅びるかもしれないと、知人とも軽口を叩き合った。いつか来るはずの日が来ただけだ。なのに日本が滅んだと聞いても何の実感も沸かない。 「天変地異ですか? あるいは、戦争?」 「さあね。滅んだのは日本なのか、地球なのか、それすらもわからないよ。まあ、予想されていたことだけどね。ちゃんとそのために備えておくべきだったんだよ。おかげでいま、この宇宙船には国籍がない。立法組織も行政も司法もない。そのなかで2万の人口の秩序を維持していかないといけない。いまはみんな寝てるからいいけど、植民星についたら深刻な問題になる」 「――深刻な問題? たとえば……?」 「移民した星の土地はだれのものになる?」 ああ、そうか。地球にはなかった問題が移民先ではあるかもしれないんだ。 「もちろんそれも日本の法律で裁けるかもしれないけど、じゃあだれが裁判官をやる? だれが弁護士をやる? 日本の法律で、といいながら、それを決めるための国家試験はもう開かれないんだよ。『彼は大学で法律を学んでいました。彼に裁いてもらいましょう』で片付くと思うかい?」 問題はわかったけど、まだ頭の中の整理が追いつかない。ようやく目が慣れて、あたりの景色も目に入る。眩しいと思った光は睡眠装置の目覚まし用のライトだ。改めて左右を見る。 ――亜実がいない。 「あのう、亜実がいないんです。いっしょに寝ていたひとなんですけど……」 「いっしょに?」 「そうなんです。それぞれで寝るのは寂しいからって、同じ箱に入って」 「へえ。でもひとのプライベートまではわからないな」 「……ですよね」 「それにおそらく、亜実って子は実在しないよ。君の夢の中の登場人物だと思うよ」 「えっ?」 「亜実ってのは、僕が好きな劇団のトップスターの名前で、僕が夢に出した子なんだ」 待って。じゃあ、僕の中にあるこの記憶は? 「僕はいったいだれと移民船に乗ったんですか?」 「知らないよ、そんなの。でもまあ、数時間もしたら思い出すよ。自分の名前は思い出せる?」 「古澤幹夫。古い澤。澤は難しい方の字で、ミキオは木の幹の幹と夫で、幹夫」 そう答えると男は吹き出す。 「それは僕の名前だ」 「えっ?」 「夢をシンクロさせるってマニュアルにあるから、どれほどのものかと思ったけど、こんなにも一致するんだね」 「じゃあ、僕の名前は?」 「だから知らないって。がんばって思い出してよ」 思い出してったって、僕の記憶を混乱させたのはあなたでは? 「君には困ったよ」 いや、ちょっと待って、困ったのはこっちだよ。 「困ったって? 僕の何が?」 「こちらからどんな提案をしても、必ず君がひとを殺すし、殺される。まいったよ」 まいったよ? たしかにいわれてみれば、そんな夢ばかり見ていた気がするけど、まいったよ? なんでそんな風にいわれなきゃいけないんだ? 「日本が滅びたことを搭乗者に教えるべきか否か、ずっと悩んでて。それでいくつか、パターンを変えて夢を見せたんだ。 まず最初は、何も知らせないで、国家は存在するって前提で統治する案。なかなかうまくいってたんだけど、君が拳銃を持って区役所に乗り込んだ。 次に君を役人に据えて統治の一角を任せてみたんだけど、すぐに職務放棄して、ヤクザに喧嘩売って殺された。 しょうがないから、国家機能を広く市民で代行しようとしてもダメ。まあ、3回目ともなると前の記憶が入り込んで、混沌とした状態にはなってたけどね」 「えっ? それを見てたの? 僕の夢を?」 「リアルタイムで見てたわけじゃない。いちばんピーキーな反応を示していたから、脳波のログから解析したんだ」 言葉がない。ひとに夢を見せたり、それを覗いたりするのって、犯罪じゃないのか? 「どんな社会を設計しても君がぶち壊す。じゃあ、どういう国家を作ればいいの? どうすれば君はひとを殺したり、殺されたりぜずに、善良な市民でいてくれるの?」 いやそれは、逆に聞きたい。夢のことを完全に覚えているとはいい切れないけども、あの不自然で不具合だらけの社会をほかのひとたちは支持したのか? 「みんな目を瞑っていたよ。仮にそれでだれかが不幸になったとしても、君のように短絡的にひとを殺したりはしない」 「短絡的って。夢の中とはいえ、短絡的に殺したわけじゃない。実際にあんな社会が築かれたら、すぐに革命は起きますよ」 「うん。だからそうならないように試してるんじゃないか」 男は苛立っている。 「どうすればこの船の乗員が殺し合わずに仲良くやっていけるか、その方法を探っているんだよ、こっちは」 気持ちはわかるけど、それを僕にぶつけたってしょうがないだろう。 「それだったら、夢なんていう方法で試さず、全員を起こしてみたらいいのに」 「試したよ。イワナガ塔のいちばんうしろ。23区だけで」 「それで、どうなりました?」 「全滅」 「全滅?」 「イワナガ塔23区、搭乗者のうちの2割、90人を覚醒させて議論させたら、話し合いにも何にもならなかったよ。壮絶な殺し合いだね。それで何が得られるわけでもないのに、人間って自分が正しいというプライドだけでひとを殺すんだね。最初の殺人からはもう、タガが外れて。司法も何も機能してないってみんな知ってるから、歯止めが効かない。文字通りの無法地帯。法を作ろうっていい始めるものはいるけど、寝首をかかれてた。みんな疑心暗鬼に陥って。ふたたびコールドスリープに入ろうとしたものもいたけど、機械を破壊されて、引きずり出されて……その記録も全部あるよ。あとで見たらいい」 想像を絶していた。自分が何の話を聞いているかわからなくなる。どこか別の世界のことのよう。閉鎖環境だからというのもあるかもしれない。無機質な宇宙船で虚空を漂って、これからどんな星に降り立つかも知れないなかで、国がなくなったとあっては……。 「地獄だよ。弱いものが狙われて、その復讐に、また弱いものが狙われる。連れ添いと少しはぐれただけで疑心暗鬼になって、その猜疑心でまたひとが死ぬ。僕が何のことをいっているかわかるだろう?」 わかるよ。言葉にはしないけど、そりゃあわかる。 「それが裁かれないとわかったら、復讐でもなんでもなく、それが横行するんだよ。どうせ死ぬ、殺される、命の価値なんかたいしたもんじゃないって考えが蔓延する。君だったらこれをどうやって防ぐ?」 そうか。それを見てきたからこのひとはこんなにも深刻に悩んでるんだ。 「結局は覚醒させなかった8割も全員、何者かに電源を止められて殺された。セキュリティは入ってたはずなのに、破られて。こっちで予測した最悪の事態は、覚醒させた2割の殺し合いだったんだけどね。余裕で越えてしまったよ」 「他のものまで巻き込むって、どうしてそんなことを?」 「絶望したんだよ、人間であることに。死を選ぶほうが幸福だって信じたんだ」 なるほど。納得はできなかったけど、想像はできた。 「俺たちはさあ。やっていけるのかね、本当に」 その声はあきらかな涙声になる。 「幸運なことに、ブロックごとは隔壁で区切られている。おそらくこうなることを見越してたんだと思う。どこかで殺し合いが発生しても、全艦に波及しないように。僕と君とも別ブロックで、仮に僕が間違った判断を下したとしても、君に殺されることはない。リスクなく何でも判断できる。でも、それが良いことなのか、悪いことなのか」 話しているうちに睡眠装置のハッチが開いた。 四畳半くらいの小さな部屋に、コールドスリープ用の機械が2台置かれている。部屋の片隅に小さなモニター。そこには男の映像が映し出されている。 「この船の管理用のパスワードなんだけど、たぶん僕しか知らない。君に教えるから、あとは好きにすればいいよ」 「好きに? 好きにというのは?」 管理パスワードは、各ブロックの代表の合意があれば得られる。それを彼が受け継いでいたんだろう。それが僕に渡されるということは、データベースにもそれが書き入れられて、何かあったときに僕が責任を追求される。 「それがあれば、全員を起こすこともできるし、行き先を変更することもできる。ルート権限だから、ブロックごとの隔壁も開けることができるよ」 ブロックごとの独立性さえも破れる権限を? 「僕がそんな大任を負っていいんですか?」 「いいも悪いも。僕はもうその責任から逃れたい。本当に、あとは君の自由にしてくれ。全艦の電源を切って殺してくれてもいいよ。僕はもう嫌だよ、こんな世界で生きるのは」 モニターの男は顔を覆って泣き出し、隣にいた女がその肩を抱いた。 女の顔はどことなく、亜実に似ている。 「パスワードは、もく星号が墜落した年の雨の日……」 男の声にならない声。続きは聞くまでもなかった。 ――1、9、5、2、0、6、0、6。 男が通信を終えるとモニターは消えて、部屋は少し闇に沈む。人工冬眠装置の目覚まし用のライトが消えると、更に闇が広がる。壁に小さな明かりがひとつあるだけの、薄暗い部屋。なんとなく覚えている。亜実とふたり、この部屋でコールドスリープに入った日のことを。床には賞味期限の切れた駄菓子が散らかる。僕の靴下、レコードとカセットテープ。 あの男は、亜実は夢の中の人物だといった。だったら、隣の箱で寝ているのはだれなんだ。というか、僕が古澤幹夫でないとしたら、僕はだれなんだ。 いままで生きてきて、記憶の中にあるものが夢か現実かを混同したことはない。人工冬眠中もいろんな夢を見ていた気がするけど、僕と、沙也加、亜実の関係は現実通りだったと確信がある。亜実といっしょに移民船に乗ったのだって確かだ。 夢の中で僕は、志藤組の唯という女に撃たれて壮絶に死んだけども、実際に僕が志藤組と接触することはなかった。シアターアプルも亜実が憧れていただけで、実際にそこで踊る計画なんてものはなく、簀巻座はずっと下北沢や王子で細々と公演を続けていた。僕はあいつが見せた夢の背景までちゃんと知ってる。父親の名前は稔、母は順子、姉は智子、小学校の4年、初恋の子の名前は秋山葉子。この記憶が夢に由来するなんてことはない。コンテナの中から卒業アルバムを引っ張り出しても、その名前は確かにある。 あの男は、自分こそ古澤幹夫だといったが、あるいはあの男のほうが、夢を見せる過程で、逆に刷り込まれたんじゃないのか。 亜実はとなりの人工冬眠装置で眠っている。それ以外の現実を僕は信じない。 * 記憶を確かめたくて廊下へ出てみると、微妙なカビ臭さに、饐えた匂いが漂う。おそらく、劣化した樹脂の匂い。あとは空調から来るものと、そこに使用されている消毒剤の匂いが交じる。 内装は明るい樹脂素材で組まれているが、ところどころ結露で浮き上がっている。廊下の何箇所かに豆電球のような小さな明かりはあるが、僕の部屋から漏れている光を除けばほぼ闇。少し離れると扉は自動で閉まって、豆電球の小さな明かりだけになる。急いで扉に戻ると、また扉が開く。 廊下には僕の部屋と同じような扉が並んでいるけど、どれも開かなかった。窓もないから、中のことはわからない。扉の前に赤いランプが灯っている部屋がいくつかあるが、それが何を意味しているのかも。アラートを示しているような気はするのだけど、中の様子はわからないし、たとえ死んでいたとしても手の施しようがない。いや、それもさっき聞いた管理パスワードを使えばなんとかできるのかもしれない。その気になれば、すべての冬眠装置を開いて亜実を探すことだってできる。少なくとも、隣の箱で眠っているのがだれかは、すぐにでも確認できる。でも、それをしてしまったら、後戻りできなくなる。 廊下の豆電球はところどころ切れたものがある。移民先候補の惑星は3つあるけど、到着まで最短でもあと8年。いちばん遠い星となると2百年。この宇宙船がそれほど保つとは思えない。 各フロアにひとつだけ用意されたトイレに行ってみると詰まっていた。水が流れなくなって何年経ったのかはわからない。便器には乾燥したものが山積みになり、その床にも垂れたものが捨てられている。雑誌のページに包まれたもの、その上に捨てられたもの。これはおそらく、ここでしたのではなく、別の部屋でして、紙などにくるんで持ってきて捨てたのだろう。幸運なことに、新しいものはなく、ぜんぶカラカラに乾燥していた。 他のフロアのトイレも概ね同じ。 シャワールームはまだましかと思ったが、糞尿の匂いが立ち込めていた。ここもトイレ代わりに利用されたんだと思う。赤黒い汚れは血の跡か、排泄物か、乾燥した吐瀉物と、脱ぎ捨てられた下着。それに、落書きが多い。鏡は割られている。SFはよく読む方だけど、宇宙船の中が糞尿の匂いだって、だれもいってくれなかった。この部屋は、想像をたくましくすれば、どんな物語でも描くことができた。 第4層のレクレーションルームの電気は消えていた。明かりをつけると、壁には空調の気流で付着した埃が黒い縞を描き、クロスは剥げ、壁の絵も色あせている。プールに水もなく、乾燥したペンキがひび割れ、めくれ上がる。等高線のように残された水垢。パイプに浮いた錆。それを黒く覆う埃。最新鋭だったはずの宇宙船も、いまでは場末の廃ホテルだ。階段を上るとき、角を曲がるとき、無意識に体が固くなる。 すべての人々がうまくやっていけてるわけでもないし、どこかに死体が転がってる可能性だって捨てきれない。この環境で90人を覚醒させたら、嫌でも疑心暗鬼になる。そう考えるとイワナガ塔23区の悲劇も、そこまで人間性に絶望する話でもない。そう自分にいい聞かせてみるけど、でも、たかが宇宙船内での話だ。宇宙船と移民星、どちらの環境が過酷かなんて考えるまでもない。ここには空気もあるし、危険な生き物が潜んでるわけでもない。それで殺し合うようで、これからどうやって生きていくんだ。 トイレとシャワールームに比べたらキッチンはまだましだった。シンクがあって、チョロチョロとだけど水が出る。IDカードをスリットに通すと、例のペレットが一食分と、紙コップに入った人工ミルクが出てくる。だけど4つあるその装置のうち2台は、枠もレバーも外れ、ちゃんと動く気配もない。あとの2台が壊れたら、その数日後には死が待っている。 医療設備は雑に使われた形跡がある。だれかが怪我をして治療した痕跡。出しっぱなしの薬剤。ベッドが4つあるが、それが清潔かどうかはわからない。 宇宙移民に申請したことを後悔した。 宇宙での死は、宇宙船の空気漏れや電気火災、隕石との衝突などでもたらされるのだと思っていた。事前にビデオで見て、その可能性が小さいことは聞かされて、それでもと、不意の事故を思い描いたりもしていたが、現実に味わっている恐怖は『老朽化』だ。 思い起こしてみると、子どもの頃からそう。怖いのは交通事故や火事や天災じゃない。避けようのない死、老衰だった。僕たちは文明の死から逃れるために宇宙へ出たのに、目の前に迫っているのは抗いようのない死だ。 部屋へ戻ると、端末には地球時間が表示されている。 昭和74年、7月28日、午前3時44分。 日本ではもう昭和でもないだろうし、この宇宙船と地球の自転サイクルにも何の関係もない。そもそも寝ている間は生物としての時間が止まっているのに、日付や時間に何の意味があるんだ。だけど、それでも時間が知りたいと思う。いまが深夜で、本来なら寝る時間で、次に僕が眠くなるのはいつ頃で、いつ食べて、いつ眠って、いつ起きればいいか。それでトランクから時計を取り出してみるのだけども、電池が切れている。そういえばと思ってラジカセを見てみると、電池が液漏れしているし、カメラを見れば、表面のウレタン塗装はベタベタに溶けて、BOXYのボールペンとくっついている。 ――なんでこんなもの持ってきたんだろう。 宇宙に出たらフィルムも売ってないし、現像もできない。それでもこの16年という月日をともに過ごして、いろんな場所で、いろんな写真を撮っていたら、この塗装の劣化だって思い出になっていたのに。 通信のログを調べてみると確かに、地球からの通信は途切れている。最後の通信に日本の滅亡を感じさせる言葉はあるけど、はっきりと滅んだ証拠はない。かといって通信が可能な状態でもない。予備の通信機器で試しても同じだし、マニュアルに沿って米国の航空宇宙局との通信も試みてみるが、これもダメ。この船が孤立しているという現実は変わらないし、状況から考えると、日本、いや、地球はもう滅びていることは認めざるを得ない。だけどこのことだってきっと、みんなに知らせたら、いやまだ可能性はある、もう滅んでるはずだ、と論争になる。 司法もない、警察もないとなれば、治安は乱れ、やがては暴力や略奪が横行する。そして次に、力を持ったものによる身勝手な統治が始まる。みんなを起こす前に、搭乗者のデータベースからプロフィールを調べて、法に強いものを起こして新しい法体系を作るという手も考えられるが、果たしてそうやって勝手に作られた法に他のものは従うだろうか。同様にプロフィールから裁判官や警察を選ぶとしても、何の任命権もない僕が選んだ官吏に黙ってひとは従うだろうか。何らかの手を打たざるを得ないことはわかっている。だけど一方では、このまま何も聞かなかったことにして眠りにつくのがいちばんかもしれないとも思う。ふと、隣に眠っているはずの亜実を起こして相談したくなるけど、亜実のおなかには子どもがいる。起こしてしまったら、そのぶんだけ大きくなる。 艦内は室温25℃、湿度50%に保たれている。 おかげで軽装で過ごすひとも多く、僕と亜実も、着替えを無駄に汚したくもなくて、裸で過ごしていた。最初はプール用にと用意した水着を着ていたけど、見渡す限り20代のカップル、堂々と愛し合うものしかいない世界で、水着を着る理由も見当たらなくなった。 この船で、僕たちは初めて自由になった。 たった3日ばかりで、人の肌、互いの目など気にならなくなった。 地球軌道を離れたあと、起きていたのはわずか10日ばかりだけど、周りの連中も似たようなものだった。お互いどんな姿でいても、何をしていても気にしなくなった。愛するものの肌の感触がそこにあるだけで、僕たちは幸せだった。 だけど一方では、不幸なものもいた。とつぜん大声を上げて暴れるものもいたし、トイレの中で声を殺して泣くものもいた。理由は様々。強引にパートナーに誘われたものもいれば、行き場をなくして宇宙へ出たものもいる。そのすべてが満足しているはずもないし、この船の現状を見て悔やんだものだって、きっと。そして今も彼ら、彼女らは、この船のどこかで人工冬眠の眠りについている。幸福な眠りでもなく、また、幸福に目覚めることもない。 僕たちが手にした自由って、なんなんだろう。 だれからも干渉されず、だれにも干渉せず、ただ与えられる餌を食らい、ただ恋人を抱きしめるだけ。たったそれだけのことで、自由を手に入れた。その自由にどれほど憧れたかわからない。なのに、手に入れた自由の意味がわからない。 何かあるとすぐ、左手を上げて時計を見ようとしてしまう。 眠くなったのならば眠ればいいだけなのに。 いまが何時であれ、何時まで寝るとしても自由なはずなのに。 人工冬眠装置にもぐりこむと、不思議な安心感があった。 だけど抱え込んで眠っていた亜実がいない。 このままだと自由を手放してしまいそうで、僕はコンテナから亜実の荷物を引きずり出して、腹に抱えて眠りについた。 * その日、亜実から電話があった。 「駅前のファミレス、わかる? そこでちょっと寝てるので迎えに来て」 西荻まで徒歩で20分。そこから中央線で一駅、荻窪で丸ノ内線へ乗り換え、南阿佐ヶ谷駅。いわれたとおりの店を覗くと、亜実がひとりで横になっている席を見つけた。 「おはよう」 声をかけるとゆっくりと顔を起こして、「ん」と声を漏らし、僕を見上げる。 「朝まで飲んでた」 口の中でもつれるような声。酒臭い息を吐く。少し寝かせておこうと、僕がモーニングをオーダーすると、注文が届く頃に、亜実は起き上がる。 「起きた。区役所に行こう」 「いいよ、もう少し寝てて。大事な体なんだから」 「ありがとう。でも私、スパルタだから。おなかの子にはこういう生活にもちゃんと慣れてもらう」 「ダメだよ。優しくしてあげないと」 亜実は乱れた髪を手ぐしで整える。 「優しくって、たとえばどんな風に?」 そういって小鳥の雛のように口を開けて突き出す。 僕はテーブルごしにスクランブルエッグを一口、彼女の口に入れる。 彼女はそれを少しこぼして、席を立って、僕のとなりに座って、また口を開ける。 「こぼれた」 「亜実のも頼もうか?」 「そうじゃない。幹夫のをもういっこ頼んで」 顔を寄せるとウイスキーの匂いがする。 「次はどれ?」 「これ」 ファミレスの一角は、僕と亜実の給餌の時間。 「もっと、ちゃんと噛んで」 「噛まないよ」 亜実は寝ぼけたまま。本当は起きて欲しい。起こさなきゃいけない。ちゃんと話さなきゃいけないことがある。でも、体のことを思うと、すぐに部屋に連れ帰って眠らせたい。 手をつないで区役所へ行って、移民の手続きをして、亜実がもう眠くて限界だというので、待合室のベンチに座って、膝の上で寝かせた。手を握って、髪を撫でて。30分もすると、亜実は起き上がる。 「気もち悪い」 そういって、あたりを見渡す。 「そんなに飲むから。トイレ、あっち。一緒に行くよ」 僕が指差すと、亜実は立ち上がり、廊下の奥へと駆ける。 亜実が座ってたシートに、薔薇の花弁を見つける。 少し嫌な予感を感じながら、僕はハンカチで花弁を拾う。 ひと目を気にしながら、ふと見ると廊下にも、点々と散る赤い薔薇。 すぐにあとを追って、女子トイレ前へ。 「大丈夫!? 何かあったの!? ねえ、亜実! 大丈夫!?」 意を決して扉を開けると、薔薇の花弁が濁流となって溢れ出す。 * 朝起きると、隣の箱が開いていた。 「亜実?」 呼びかけて、覗いてみるけど、箱は空っぽ。枕に残った香りに、鼻を押し付けてみる。 やっぱり亜実だ。間違いない。 4層の展望室。 電気の消えた暗がりの向こう、四角い窓の一面に、星を散りばめた明るい宇宙が広がる。その宇宙が蓮華座を組んだひとの形に切り抜かれている。 「おはよう」 声をかけてゆっくりと近づくと、その影に肌の色が見える。 明かりの消えた室内に、ほんの少しだけ残った小さな電球が、亜実と僕の姿をガラス窓に映す。眠りについたときの姿のまま。亜実は足を組んで、背筋を伸ばして、遠い虚空に視線を泳がせている。 「おはよう。幹夫も起きたんだ」 「うん。僕は昨日から。起こそうかどうしようか迷ってた」 「そうか。だから起きちゃったのかもね。私も」 僕も亜実の隣で蓮華座を組む。亜実ほどきれいには足の平を持ち上げることはできないけど。 ――でも、どうやって切り出そう。 「人工冬眠中、どんな夢を見てた?」 「うーん……いろいろ」 「おなかの子は大丈夫?」 「わかんない。でも、大丈夫なんじゃないかな」 「気をつけてね。亜実はスパルタだから」 「大丈夫だよ。幹夫が優しいから」 そう聞いてなんとなく、ふたりは同じ夢を見ていたんだと思った。 「あのあと、どうしたの?」 「あのあとって?」 「区役所でトイレに駆け込んだあと」 「別に、普通だったよ。普通というか、いつも通り。幹夫に明大前まで送ってもらって」 「ああ、そうだったね」 僕はガラス窓に映った亜実の呼吸に、自分の呼吸を合わせる。とても静かな呼吸。その横隔膜の動きを飲み込むようにしていると、だんだんと同じエクスタシーが胸に広がってくる。 「地球が滅亡したんだって」 亜実の方から、不意に切り出してきた。 「座長が教えてくれた。簀巻座の。さっきまでここに来てたんだよ」 「そうだったんだ。地球の最後って、どうだったんだろう」 「核戦争だって。地磁気が反転して、世界中の機器が狂い出して、いろんな不具合が発生しているうちにみんな疑心暗鬼になって……」 地球もここも、結局は同じだった。いままでの日常がほんの少し崩れただけで、僕たちの理性はなくなってしまうんだ。あるいは、理性があるからこそ、日常に留まろうとして、不整合を起こしてしまうのかもしれない。 僕は昨日聞いたこと、イワナガ塔23区で起きたことを亜実に教えた。 「そうなんだ」 「うん。辛くない? 大丈夫?」 「辛いよ。本音では。だけど、ワクワクする」 強がって出た言葉でもなかった。亜実の呼吸は期待を孕んで、やわらかな熱を帯びている。 「この宇宙で私たちだけが地球文明を受け継いでいるんだよ。これを宇宙のどこかに根付かせるの。こんなに凄いことってある?」 「そうだね――」 人工冬眠に入る前は、ここにはもっと明々と光が灯っていた。あの頃見えてなかった小さな星まですべてが見える。うっかりしていると気持ちはそこに吸い上げられる。 「子どもの頃は、普通に結婚すると思っていたんだ。父や母みたいに。相手がだれとか、そういうことは考えずに。あるいは、だれでも良かったんだよ。だれと結婚したって、僕のイメージの中の家庭像なんか大して変わらないと思ってた。普通に可愛らしい奥さんができて、僕の身の回りの世話なんかしてくれるのかなって。その程度のことしか考えてないのに、『だれでもいい』ってのは、ある意味自分の懐の深さなんじゃないかなと思ってた。でも、いわれたんだ、沙也加に。だれでもいいなんていうのは、自分が変わらなくても済まされてきたからだ、って。男は結婚しても生活は奪われないけど、女は奪われる。そりゃあ可愛かったらだれでもいいでしょうよ、って」 しばらくだまっていた亜実が、言葉の隙間を見つけて滑り込ませる。 「幹夫はいまも、私より沙也加のことが好きだよね」 少し気まずい。それはある意味真実だけど、でもそれがすべてでもない。 「どうしてそんなこというのかな」 「ごめんね」 「何をいいたいかっていうと、だれでもいいんじゃないんだよ。新しい生活、新しい考え方ってのが、僕と亜実との間にあって、僕にとってはそれが未来だから、亜実じゃないとダメなんだよ」 「照れくさいよ。どうしていまいうの?」 「どうしてって、ふたりはアダムとイブになるから」 そういうと亜実は吹き出す。 「沙也加が僕という血肉を作ったのは事実だと思う。でもその僕がいまいちばん好きなのは亜実。それじゃダメ?」 「いいよ。沙也加が血肉を作ったんだったら、私が好きにならないわけないもん」 「似たようなことを沙也加もいってたよ」 「うん。たぶん正解だと思う。私、あんまりひとの良いところを見つけられなくて。みんな敵に見えるから。沙也加の話を聞いて、ああそうかーって、いつも思ってた」 亜実と話をしていると、いつの間にか僕は地球が滅んだなんてことは忘れていた。 ――地球は滅亡して、宇宙船はおんぼろ。起きたら暴動を起こしそうな2万人。でも、亜実がいる。 「ねえ、幹夫。結婚しない?」 蓮華座を組んで、虚空を見たまま、亜実が訊ねる。 「結婚? そういうタイプじゃないと思ってた」 柔らかい肌は、もう僕の一部。僕と亜実とが別人だったのは、とうの昔。裸を見ても、肌に触れても、自分の身体のようにしか感じないのに、それなのにゆっくりと上下する亜実の横隔膜の動きに、胸はときめく。 「結婚って、世間とするんだよ。恋愛だったらふたりだけですればいいし、子どもだってふたりで育てたらいい。でも結婚は、世間に向けて、夫婦としての役割を果たしますっていう宣言。でもその世間がなくなったわけでしょう? 結婚にももうなんの意味もない。だから、結婚しよう。ここで」 「いいけど、意味がなさすぎて、何をしたらいいかわからないね」 「私も」 以前の恋人ごっこのよう。今度は結婚ごっこになった。でももうマニュアルはない。だから、結婚ってなんだろうって、ふたりで考えるしかなかった。 「社会や法律が理由じゃない、だれよりも強い結びつきの結婚だよ。覚悟はできてる?」 そう訊いてくる亜実の目を見つめて、 「もちろん」 強くその手を握ると、また亜実は吹き出す。 「ねえ」 「なあに?」 「たまには幹夫から目を閉じて」 目を閉じて、少しだけ漏れる呼気を受け止めると、呼吸は柔らかく奪われる。お互いの鼻が、右に、左にと擦れて、甘い空気で胸を満たす。 地球の滅亡のこと、亜実はもっとショックを受けるかと思ってた。僕はこの先のことを考えるとどんよりしてしまうのだけど、亜実にはそれもないようだった。彼女は常に目の前にある喜びだけを拾い集めている。 ゆっくりと目を開けると、目の前の亜実は、僕を見つめていた。 「無重力部屋へ行かない? いまならふたりきりだよ」 亜実は蓮華座を解いてすぐに立ち上がるけど、僕の足は痺れていて、少しふくらはぎを揉みほぐす。もう他人でもないのに、目の前に過る金の産毛に、少し照れを感じる。 無重力部屋へ向かう通路。混み合ってた頃はいろんなカップルが連なって、上を見ると知らない子がいて、下からは知らないひとが来て、クスクスと笑い合っていた。いま僕の頭上を上っているのは亜実だからいいけど、と思う一方で、僕に夢を見せた男の言葉を忘れたわけじゃない。僕が古澤幹夫ではなくて、亜実も中江亜実じゃない可能性。だったらいま僕の目の前にいるのはだれなんだろう。僕と彼女はただの友人同士かもしれないし、あるいは他人、あるいは姉弟かもしれない。 通路を上り始めると、すぐに暗闇に包まれる。足元にレクレーションルームの仄かな明かりが見えるけど、それもふたりの顔を照らすには乏しい。 「明かりを取りに戻る?」 「えっ? どうして? 真っ暗な方がドキドキしない?」 そうだった。亜実がそういい出すことくらい、いい加減わかっているはずなのに。 手探りで上り詰めて、真っ暗闇の無重力部屋で、声だけを頼りに手をのばす。声は壁に反響してどこから聞こえるかもわからない。僕を呼んでケタケタと笑う亜実の声が聞こえる。 「他のカップルも起こしてこようか」 なんてことをいい出す。 亜実はよく僕の嫉妬心を弄ぶ。ひとの群れの中で、自分の姿を目で追わせる。僕は本当に嫉妬していて、それを必死でこらえてるんだから、そうやって試すのはやめて欲しい。本当に、本当に、本当に亜実のことだけが好きなんだから。 「嫌だよ、そんなのは。今日ぐらいはふたりきりでいようよ」 そういっている鼻先を、亜実の髪の毛が通り過ぎて、僕はすぐに手を伸ばす。亜実も僕の手を取って、顔を寄せてくるのがわかる。指先がするすると絡まると、 「すみません、どなたですか?」 声色を使って、亜実が聞いてくる。 「ごめんなさい。それが自分でもよくわからなくて」 肉体は地球上の活動のために手に入れた器官。宇宙に出たらそれはもう意味がない。その肉体同士が、地球的な文脈でお互いの存在を確かめあっている。 暗闇の中で伸ばした手は、どこへ向いているのかもわからなくなる。右手で自分の左手に触れて、ようやくそれがどこにあるのかわかる。頭の中に自分のいまのポーズを思い浮かべるのもままならない。そこに亜実の体が飛び込んできて、その接触でようやく自分の体をイメージできる。亜実がいなかったらきっと、僕は僕の形なんかわからなくなっている。 「でもこの暗闇で、あと何日か過ごしたら、こうやって触れたこの感触が手の感触だか足の感触だかわからなくなるよ、きっと。だってほら――」 と、亜実は僕の手の指の一本をつまんで、 「私が幹夫の何指をつまんでるか、わからないでしょう?」 そういって亜実は僕の体のあちこちに触れる。ここは? じゃあ、こっちは? その両手は僕の顔を掴んで、柔らかく濡れた皮膚に押し当てる。 「今日はここで寝る」 「うん、いいけど、おなかの子の成長が……」 「大丈夫だよ。幹夫は優しいから」 いつかこういった気がする。 僕たちは恋人でも友達でもない、ただの幹夫と亜実だ、って。 でもいまはもう、幹夫と亜実ですらない。 地球がなくなるって、こういうことだったんだ。 * モニターのアラートに気がついたのは亜実だった 画面の隅のアイコンにインジケーターが灯る。カーソルを合わせると小さなウインドウが開き、いくつかのアイコンが並ぶ。そこに『EMERGENCY』の文字を見つけて、マウスを持った亜実の手をとってクリックを促すと、そこに現れたのは72時間以内に目的地を設定するように示すアナウンスだった。 ニニギの目的とする植民星は、MK1221、YM0219、FK0804の3つの候補が挙がるが、情報が少なく、絞りきれていなかった。本来ならば地球からの情報を元に決定されるのだけど、その情報が断たれている。そもそもこの移民計画は杜撰だ。予算をつけて、開発、打ち上げることが目的で、その先のことは考えられていないに等しい。 「このアラート、無視したらどうなるの?」 ――一般的には、無視した場合も何かしら選択はされると思うけど、運用が杜撰すぎてわからない――と、答えようと思ったけど、相手は亜実だ。 「無視したら面白いことになるかもとか思ってないよね?」 「よくわかったね」 いや、よくわかったねじゃなくて。 距離でいえばMK1221がいちばん近い。4年後にシリウスの重力場を利用して方向転換して更に4年、合計8年でたどり着ける。同様にYM0219は50年、FK0804は2百年といわれている。いまの船の老朽化具合を見れば、いちばん近いMK1221を目指すしかない。ただ、候補が3つあることからも分かる通り、いちばん遠いFK0804が最も地球環境に近く、MK1221は生物が住めるかどうかすらわからない。 「じゃあ、間をとってYくんで」 「間を取ればいいってもんかなぁ」 「だって、考えるにしたって情報はないし」 「それはそうだけど」 「あ、そうだ」 「何?」 「簀巻座の座長に聞いてみようか? いまごろまだ宇宙空間を漂ってると思う」 「ああ、いいかもしれない」 「たぶん、『間を取ってYくん』って答えると思うけど。たいして考えないから、あのひとも」 「ダメじゃん」 とはいえ僕にもまったく決め手がない。もっと詳細なデータがあればとも思うけども、そのデータを見たところでわかるとも限らないし。でもどんな方法であれ、72時間以内に僕が決断するしかない。だから―― 「夢で投票してもらおうと思う」 「夢で?」 亜実が目を輝かせる。 僕を起こした男に聞いたことを亜実に教える。投票するにしても、どんな夢を見せて投票すれば良いのかわからないけど、悩んでいる時間もない。いまそれを決めるしかない。 イワナガ塔23区で起きた悲劇のこともすべて伝えると、亜実はいった。 「その23区のひと全員殺したのって、たぶん、幹夫に話してくれたそのひとだよ」 ドライな反応に面食らっていると、亜実は続ける。 弱者は慣れてる。奪われることに。耐えることに。そうやってしか生きることができなかったから。ここまで生きてきたのなら、心はもう、とうに死んでる。だから、奪われたくらいでは死なないし、殺さない。でもそれは、生きるというには程遠い。 「ごめん、その発想はなかった」 「ああ、ごめんごめん。こっちもそんなに真剣には考えてない。思いつきでいっただけ。投票ってどうするの? Yくん、Mくん、Fくん、どれが好きですかー、って聞くの?」 確かに思いつきで話しただけかもしれないけど、切り替えの速さにも戸惑う。 「そんなぼんやりした投票でいいんだったら、僕がサイコロを転がして決めるよ」 「いいかもしれないけど、たぶん、サイコロがないよ。どこにも」 「そうだね。亜実はどれがいい? やっぱ、間を取ってYくん?」 「私は、このままずっと夢を見て宇宙を漂いたい」 「じゃあ、いちばん遠いFくん?」 「もっと遠く。目的を定めず、永遠に」 「そんなには宇宙船が保たないよ」 「2百年は保つんでしょう?」 「公称では5百年っていわれてる。だけどたぶん、そんなには保たないと思う」 実際に5百年は原子力電池の寿命で、それよりも早くいろんなところが崩壊するんじゃないかな。 「じゃあ、宇宙船が崩壊するまででいい。夢を見て、漂いたい」 「崩壊したあとは?」 「別に知らない。じゅうぶんだよ、それだけ生きられたら」 最初は冗談かと思っていたけど、亜実は本気だった。 「でもそれじゃあ、僕たち地球人は何も残せないね」 「そんなことはないと思うよ。三葉虫だって化石を残してるんだし」 「でも人類が残さなきゃいけないものは……」 「何? 人類が残さなきゃいけないものは?」 改めて聞かれても、何も答えられなかった。 確かに8年後にMK1221に降りたって、そこで生活できるとはかぎらない。着替えだってすぐになくなるし、食べ物が手に入る保証もない。8年の睡眠と、その後50年の苦悩があって、その果てに全滅するんだったら、船が崩壊するまでの数十年、運が良ければ5百年、夢の世界で人生を謳歌したほうがいい。 「僕と亜実だけだったらそれがいちばんいいと思う」 そう答えると亜実は得意げに頷く。 「人類が残すべきものは『夢』だと思うよ。どこに到達したかじゃなくて、どこを目指していたのか。それさえ残せたら、滅びていいと思う。どうして滅びたのか、何が失敗だったか、あるいは逆に、どんな幸せを謳歌したのか。その物語こそが、人類が残せる宝物だと思う。幸いなことに、私たちの夢は記録されている。それがだれかの手に渡れば、私たちが消えた世界で、夢だけは生き続ける」 「わかるよ。もちろん」 でも、他のひとを巻き込んでいいかどうかは躊躇する。 だから、現実の惑星を目指したいか、夢の中でずっと暮らしたいか、夢の中で投票を募りたい。亜実をマスターにして。 マニュアルを読んで、亜実の冬眠装置を夢の管理人に設定する。 亜実を横たわらせて説明していると、「いっしょに」と手を伸ばしてくる。 「だーめ」 「けちー」 「ちゃんと聞いて。まずは赤い光が点滅してる時、脳波にベータ波が誘導されているので、このときに『覚醒トリガー』を設定します」 「覚醒トリガーって何?」 「起きたいと思った時に目にするもの。それを見たら目が覚めるんだって」 「へえー。幹夫は何にするの?」 「教えたらイタズラするつもりでしょう?」 「けちー」 「――それを設定したら入眠開始です。青い光とともにシータ波が誘導され半覚醒状態になります。このときに思い浮かべたものが、他のひとの夢にも反映されます――だそうです。わかった?」 「わかった。わかったけど、あと30分だけ起きてちゃダメ?」 亜実は両手を挙げてパタパタと手招きする。 「いいけどさあ」 「いいけど? いいけど、何?」 「地球にいるときと変わらないね、僕ら」 30分だけ、亜実と僕は小さな巣箱の中で重なり合って、互いの呼気に染まった。 少し小さいニニギの人工重力のなか、亜実の身体は5月の風。ペダルを漕いで加速していくと、風が僕を追いかける。スプリントを終えて、またスプリント。あと15分だけ。あと7分30秒だけ。永遠に半減していくオマケの時間のなかで、僕は亜実の纏った風に溶けていった。第7章 夢の中の古澤幹夫
ふと気がつくと、足元には大理石のフロアが広がっていた。 天井は高く、シャンデリアが光る。テーブルには箱型のソファ、列柱の向うには開放された空間。縦長の窓のフレームが陽の光を切り分け、その外には緑が見える。 レセプションがあり、藍色の上品な制服を着たひとたちが働いている。 柱のそばには古伊万里の色鮮やかな壺、壁には様々な絵が掛けられている。流木に飾られた花。壁一面のタペストリー。大型のグランドピアノと、そこに音を奏でる赤いドレス。陽の射す方へと進んでみると、遊興にふける人々の喧騒が聞こえる。 その先は中庭へと続く。いや、屋根があり、室内だとわかる。まるで外にいるのと変わらない広さ。小型のバスほどの飛行船が舞い、その船体には『ホテル&リゾート・木花咲耶』の文字が見える。 ラウンジにはトロピカルなバーカウンター、噴水、巨大な観葉植物、ペイズリー型の中庭を囲んで建物があり、階ごとにギャラリーが巡る。ドーム状の天井は、その全面が輝き、ゆるやかなアーチの底部には外へ向けて窓が開かれている。おそらくあの向こうは宇宙。これが亜実が夢の中に描き出している移民船、いや、ホテル&リゾート・木花咲耶なんだ。 そして僕はいつの間にか空色のジャケットを羽織っている。白いチノパンに、首のボタンをはずしたコバルトブルーのシャツ。裾はズボンの外に出して、足に靴下はなく、素足に革のローファー。裾を折り上げ、座るとくるぶしが見える絶妙の裾丈。ジャケットの上には謎のカーディガンを肩に掛ける。これは普段は着ているものなのか、最初からアクセサリーなのか。 こういう絵を雑誌で見たことがある。彼女の誕生日に午後休をとって青山のフローリスタで買った花束を助手席に置いてボンネットに片手をついて摩天楼に沈む夕日を眺めてるひと。 ――彼女が仕事を終えるのが17時。友だちと週末の予定を話しながら、制服をロッカーにかけて、靴を替える。簡単にメイクを直して、オフィスビルを出ると、時計の針は17時25分。その時間にあわせて僕は、青山通りから外苑東通りへと車を走らせる―― そういう世界にいま僕は降り立っている。 中庭にはプールがあり、その一部は砂浜のように波が打ち寄せている。いや、砂浜のようにではない。そこには、紛れもない砂浜があった。プールサイドには南国風のパラソル、青いマットが敷かれたビーチチェア、水着姿のカップルが座るその傍らにはココナツに傘を飾ったカクテルが置かれる。水着のまま入れるコテージ風のレストラン、ラジオから聞こえてくるカルチャー・クラブ、デュラン・デュラン、エア・サプライ。プールの周りには起伏のある道が作られ、バナナや棕櫚など南国の植物が茂り、その枝にはオオサイチョウが止まる。飾り付けられた象の背に乗って移動するひとたち。まるで鈴木英人のイラストのように風が煌めいて見える。 絶対的権力は絶対的に腐敗するという言葉が思い出される。だけどここには権力者はいない。ただ受益者がいるだけ。しかも夢の中だ。昨日と同じことを延々と繰り返したところで記憶にも残らないし、飽きも来ない。そしてこの美しい虚構は、この先もずっと綻びることなく続く。 だけど―― 「亜実! ちょっと待って!」 確かにここは夢の中だ。だけどこれを搭乗者たちに見せてどうしようというのか。 「みなさんもここで暮らしたいですか?」 と聞けば、こぞって賛成するに決まっている。 だけど僕たちは、搭乗者にそんな投票をさせようとしているのか? そうじゃないはずだ。夢を見続けるか、現実を生きるか、ふたつを提示して選んでもらうのが趣旨なんじゃないのか? 「亜実! これじゃ投票にならないよ!」 呼びながら歩いても、その姿はない。 ガラス張りのシャワールームではカップルが楽しそうに囀りながら汗を流す。恥じらいもしないその肌が水滴を弾いて、足元にできる虹。赤いペディキュアがそれを横切る。畜生。なんで太陽がないのに虹が出てるんだ。光源はばらばらなのに、やけにくっきりした影が落ちてるし。いや、そういうことじゃないんだ。なんでこう、寝てるときの思考ってのはまとまらないんだ。こんな状態で投票させられて、まともな判断ができるわけがない。 亜実の姿を探していると、目の前にコダックのラボがある。なんてことだ。胸の中に西海岸の風が吹く。これがあれば写真の現像もできるし、フィルムも売っている。気がつくと僕の手にはキヤノンのオートフォーカス機、EOS620が握られている。学校を出たあと、長いことアルバイトしかしてなくて、ギターもカメラもずっとだれかのお下がりを使っていた。勤め先のライブハウスの先輩のコネでレコード会社に中途採用、初めての海外旅行、ロサンゼルスに派遣された時、生まれてはじめて組んだローンでカメラを買った。それがほんの1年前。フリートウッド・マックのアルバム『枯木』のジャケ写はベースのジョン・マクヴィーが撮った。僕もいつか、そうやってアルバムを作るんだと思っていた。コダックEPPの発色が好きで、車のボンネットばかり何枚も撮った。だけどまだフィルムにして20本も撮ってない。そのカメラが僕の手に帰ってきた。 気がつくと僕は、夢中になってシャッターを切っている。右手親指のレバーでフィルムを巻き上げるこの感触。知らず知らずのうちに涙が頬を伝う。 地形は立体的で入り組んでいて、なだらかなスロープから地下街に入るとそこは夜の世界。電飾で飾られた立木、ネオンサイン、ファイアーダンスショーのレストラン。店の前に立てた篝火の肌に届く熱と、舞い上がる火の粉。焼けた肉の匂いのなかに、パイナップルとココナツの甘い匂いが混じり、すれ違うひとからはコパトーンが香る。木の看板のトイレのサインはありがちなピクトグラムではなく、環境にあわせてデザインされている。 トイレに入ると、手入れが行き届いていて美しい。イワナガ塔にあったのは便所。こっちはトイレ、いや、化粧室、あるいはパウダールームか。トイレなのに芳醇な花の香。ひとはここに何色の思い出を残すというのか。近づくと自動で蓋が開き、洗面所は手をかざすと自動で水が出る。それはまるで魔法。ここはもう別文明の世界だ。 いやでも、こうじゃないんだよ、亜実……こういうことじゃ……。 たしかに僕が移民船に乗る前に夢見ていた宇宙船はこれだけど、これじゃあすでに宇宙でも何でもないじゃないか。ただの最高の新婚旅行だよ。普通に結婚して普通に新婚旅行に行けば良かったんじゃないか。もう地球の滅亡とかそんなのはいいから。いや、いいからってことはないな。滅亡してるんだから、新婚旅行には行けないんだけど。だからってこれは。 目の前のハンバーガーショップでアボカドバーガーを頼むと、ポケットにはいつの間にか諭吉でいっぱいの財布が入っている。肉もバンズもアボカドもたっぷりのバーガーが、信じられないくらい安い値段で買えて、夢だとわかっているのにびっくりしてしまう。 それをベンチで食べていると、僕と同い年くらいだろうか、サラサラの髪をした品の良い女性が「となり、よろしいですか?」と声をかけてくる。 幅広の紺の襟、白のトップに、胸の前で結ぶ大きめのリボン。膝下までの白いスカートの裾には3本の青いライン。紺色のリボンが一周した藁の帽子。白いデッキシューズ。そして肩には謎のカーディガンを羽織って袖で軽く結ぶ。このカーディガンは普段は着ているものなのか、最初からアクセサリーなのか。僕はイソギンチャクガニのハサミの上でしか発見された例がないというイソギンチャクを思い出す。 「どうぞ」 僕はそのひとに席の半分を譲る。 「はじめまして。佐藤真由美といいます」 二匹のイソギンチャクガニが肩を並べる。 「ああ、どうも。古澤です。ところで、お聞きしてよろしいですか?」 「はい、なんなりと」 まずは正体を探らなければいけない。このひとは果たしてこの移民船の搭乗者なのだろうか、それとも亜実が見せているイメージなのだろうか。 「あなたは、どちらから来られました?」 「愛知県の第8章 大草原の古澤幹夫
普段よりも、ずっと体の重い朝。 なかなか昨日の記憶が戻ってこない。目の焦点も合わず、耳だけで朝の喧騒などを探してみると、卒業した小学校の校歌が流れている。 ――どこなんだ、ここは。 少し手足に痺れがある。 「おはよう」 明るい女の声がささやく。 「目覚ましの音楽、小学校の校歌にしたんだ。あなたのことだから、またどうせハードロックにするんだとばかり思ってた。ツェッペリンか、ディープ・パープルか」 目覚ましの音楽……? そういえば床につく前にカセットテープを用意した気がするけど、あれは何だったんだっけ……。視界はぼやけたまま。ゆっくりと目の焦点を合わせても、何も見えない。 「まだ、はっきりとは見えないはずよ。ちゃんと覚醒するには2~3時間はかかるよ。あなたのほうが寝付くのが遅かったぶん目覚めも遅いのかな。私、すぐ寝ちゃったもん。冬眠装置に入ってすぐ」 冬眠装置? ということは、つまり? 「すぐに思い出すと思うけど、簡単に説明するね。ここは、太陽系外の深宇宙へ向かう移民船ニニギの中。搭乗者数は2万1千人。ほぼ全員が日本人。大きくふたつのブロックに分かれていて、私たちの部屋があるのはイワナガ塔と呼ばれる居住区。いまは地球を出て16年。どうして今日目覚めたかわかる?」 「いや、わかんない。でも思い出せそう。なんだっけ。記念日か何か」 「おお! すごい! ちゃんと覚えてた!」 そうだ。今日は結婚記念日だ。毎年この日だけ起きて食堂で乾杯してるんだった。 しばらくとりとめもない話をしていると、冬眠装置のハッチが開く。 「おはよう! 私の名前はわかる?」 「ええっと……亜実?」 「うわあ」 「はずれた?」 「ショックだわー。結婚記念日に夫に名前間違えられるって」 亜実じゃないんだ……じゃあ、亜実ってだれなんだ……。 「亜実って、簀巻座の踊り子でしょう? 私に似てるっていう。でもだからって名前を間違えるのはないと思うよ。ちなみに、自分の名前はわかる?」 「古澤幹夫。古い澤。澤は難しい方の字で、ミキオは木の幹の幹と夫で、幹夫」 「そっちは正解。じゃあ、あらためて自己紹介。私は葉子。小学校の頃からいっしょだったのよ。はじめまして。古澤くん。3年生の時は1組でした。もういちど私のこと、好きになってくれるよね?」 「葉子……」 銀河少年隊と大草原の小さな家が好きだっていってた秋山さん。そういえば、銀河少年隊のヒロイン、金星人アーミアのぱっちん留めをあげたことがあった。 ――銀河少年隊のだったから買ったけど、よく考えてみたら使わないからやるよ。 そういって渡したけど、本当はわざわざ買ったんだよ。 ――こんなのつけないよ。 そういって口をとがらせていたけど、ずっと筆箱にしまっててくれた。 「せっかくだから、『秋山さん』から始めない? もう一度告白されたい」 「あ、そうだ。告白。年賀状で告白したんだった」 「思い出した? あの年賀状、弟からすごいからかわれたんだよ?」 「あれ、中2だっけ? 中3? 受験の最中じゃん」 「卒業を控えて焦ってたんじゃないかな。高校は別だったし、高校の3年間は年賀状しかつながりはなかったけど、でもお正月が来るたびにドキドキしてた。私、そこそこもてたんだよ、高校の頃。告白されたこともあったし。年賀状しかもらってないのに『付き合ってるひとがいます』って断ったのよ? 大学が決まってからだよ。『会いたい』って、幹夫からいってきたの」 そうだ。たしか沙也加に会う前だ。じゃあ、沙也加と付き合っていた記憶ってなんなんだろう。 「あの誘い、断られるとばかり思ってた」 「断るわけないじゃない。待ってたんだから」 葉子は涙を浮かべて、少しむくれた顔をした。 「小学校の頃のこと、覚えてる?」 「藤枝小でしょう? 覚えてるよ。どんなこと?」 「幹夫だけだったんだよ、私の夢のこと聞いてくれたの」 「そうだっけ? どんな話?」 「宇宙に移民して、大草原の小さな家みたいに、自分たちで家を作って、そこで家族と暮らすの」 「それ!」 思わず葉子を指差した。 僕が宇宙に憧れるようになったのは、葉子にその話を聞いてからだった。 葉子とふたり、食堂へ向かった。 そういえば、去年も、一昨年もこうして食堂へ向かった。 記念日にはワインが出るからと、毎年結婚記念日にだけ目を覚まして。 「去年いっしょに起きてた田中さん、覚えてる? あのご夫婦って、ふだんはクリスマスに起きてるんだって。去年はあれ。なんだっけ? 25年の。銀婚式? それで起きてたらしいんだけど、私たちもそんなに先じゃないんだよ、銀婚式。まだ二十代なのに」 食堂はホテル木花咲耶ほどじゃなかったけども、僕が夢で見たニニギの食堂よりはずっときれいだった。食事もペレットではなく、数種類の冷凍食から選べて、レンジで温めるとそれなりの料理にはなった。だけど、楽しみにしていた結婚記念日のワインは、葉子のぶんだけで、僕のぶんはエラーになって出なかった。 「コンピューター、壊れたのかな?」 「部屋に帰ったら端末で調べてみよう」 葉子と食事のトレイを持ってテーブルに座る。 小さなボトルワインを紙コップふたつに注いだ。 「去年もこの席だったね」 「思い出した?」 「うん。なんとなく」 葉子は「裸で座ってるひとがいたから」といって、共有スペースの椅子には座らなくなっていた。だけど、この椅子とこのテーブルだけは、結婚記念日のたびに綺麗に拭き上げて利用した。だれに文句をいうでもなく、ただ嫌悪感だけをその眉に浮かべて。このテーブルのまわりだけ、ゴミを綺麗に片付けた。 葉子は亜実に似ている。あるいは逆かもしれない。亜実は葉子に似ている。だけど性格は多分反対。いまも葉子は「今日は記念日だから」といって、だれもいないこの移民船の中でちゃんと正装している。 「どうしたの?」 「ちょっと夢のこと思い出してた」 「それ、去年もいった」 「そうだっけ?」 「ギタリストになって云々って。でも私、幹夫にギタリストの夢をあきらめさせたこと、後悔はしてない。あのまま夢を追ってたら、移民船の審査にも通ってなかったんだよ?」 「そうだね。僕もたまに考えるよ。もし僕があのとき葉子に電話してなかったら、人生どうなったんだろうって。中江亜実やテトラポットが出入りしているっていう『千駄ヶ谷の集い』に顔を出すようになって、破滅的な人生送ってたんじゃないかなって」 「えっ? なに? もしかして私のこと天使っていった?」 「うん。いった。葉子は僕の天使。破滅から救ってくれた」 「それじゃあ、あとでご褒美ちょうだい」 「ご褒美って?」 「肩揉んで」 そうだ。亜実とは違うんだ。葉子は「キュービィロップ半分になったら交換こ」とはいわない。 ――中江って子は嫌い。顔は似てるけど、私とは正反対だと思う。 はじめて簀巻座の公演を観た時、葉子はそういっていた。 「簀巻座のニュースたまに見るけど、なんで逮捕されないのかわからない。今日の舞台だって、たまに見えてたし。見えちゃいけないものが。客だってそれを観に行くんでしょう? そんなのは芸術じゃない。ただのポルノよ。文芸だったらわかるんだけど。たとえば谷崎にしても、川端にしても、ああいう書き方だったらわかるし、知的好奇心も満たしてくれるじゃない。でも簀巻座はそうじゃないでしょう? 自分たちは芸術だって思ってるんだろうけど、ぜったいに認めない。一流になれなかったものが、エロに逃げてるだけ。そうでしょう? あんなの、ぜったい芸術じゃない。見世物」 「うん」 簀巻座のメンバーにはよく薬物疑惑が持ち上がっていた。葉子は芸能界の薬物汚染をひどく嫌っていたし、ポールが逮捕されてからはビートルズも聴かなくなった。海外のミュージックシーンを侵すどす黒い禍の中から、豊かな音楽性が生まれ、空港はその澱と上澄みとを分ける。僕がささやかな体験を話すと、「私の前ではいわないで」と、嗜められた。葉子はその『破滅』から、僕を救ってくれた。 「私と似てるっていうから興味はあったんだけど、あれじゃあダメよ。雑誌で話題になって調子に乗ってるみたいだけど。脚本もわけわかんない。あんなものだったら私が書ける。よっぽど面白いものになると思うよ。幹夫でも書けるんじゃない?」 葉子は神田の小さな印刷会社に努めていて、そこで版下を作っていた。元から読書好きで、無類の川端好き。僕も薦められて短編を少し読んだことがある。 「物語にはセオリーがあるから。そこを押さえて多少の技術さえあれば、だれにだって書けるのよ。コンビニのバイトと同じで、要はそれを職業にするか、しないかってことでしょう? その最低限の技術さえないひとが同人とか小劇団とかやるんだと思うの」 こういう話を神田の喫茶店で大声でするのが、僕の悩みのタネでもあった。 「私、何か間違ったこといってる?」 「いや、そのとおりだと思う」 小学校の頃からずっと変わらない。これが僕の帰るべき場所。世界でいちばん大好きな人、葉子。 部屋に戻って、端末を叩いてみると、移民船ニニギに5人の古澤幹夫が搭乗していることがわかった。そんなにありふれた名前でもないのに、わずか2万人程度の搭乗者の中に5人も。その5人すべて、イワナガ塔に。 「こっちの古澤幹夫さんが、この日に覚醒してるから、データがおかしくなったんじゃない?」 と、葉子は乗客名簿を指差す。 「なるほど」 と、頷いてみるものの、どうしてデータがおかしくなったのかまではわからない。 僕はただ画面の端でずっと点滅しているアラートが気になる。 葉子に断ってインフォメーション画面を表示させると、日本政府との定期連絡が三日間エラーが出続けていることがわかった。 「どういうこと?」 「調べてみないとわからない。通信機器の故障かもしれない」 まずはログを見てみる。日本政府とは定期的に連絡を取り合っている。他にも米国の宇宙局や各国の天文台にもPINGと呼ばれる信号を飛ばし、超光速通信のチャンネルを保守している。そのPINGに対する応答が少しずつ途絶えていることがわかる。つまり、突然こちらの通信機器が故障したわけではなく、地球のありとあらゆる機関が、時間をかけて機能を停止している。 「滅亡してる。日本政府が」 「滅亡?」 葉子の手前、「地球が」とはいえなかったが、おそらく、地球が滅亡している。 「念のため予備の通信機を起動してみる」 予備の通信機を起動させるには管理パスワードが必要だった。管理パスワードはニニギ全46ブロックの合議によって発行される。それには各ブロックがまず代表を決めなければいけない。それには長い話し合いが必要になるし、実質そのパスワードを発行する方法なんてない。似たようなことは何度も経験している。仕様を作る時に、それがどう運用されるか想定されていないために起きるミスで、現場ではよくあること。それが移民船の運用なんていうクリティカルなところで発生するとは。 画面はパスワードの8桁の文字を求めてくる。 でも僕は――でも僕はこのパスワードを知っている。 「もく星号が墜落した年の、雨の日……」 「なにそれ? 管理パスワード?」 ――1、9、5、2、0、6、0、6。 管理者権限が開放される。 「パスワード、知ってたの?」 「知ってた。パスワードだけじゃない。これから起きることもすべて知ってる。夢で見たんだ。これからこの船で殺し合いが始まる!」 パニックになりかける僕を葉子がなだめる。僕は夢で見たことを葉子に話す。亜実のことは少しはしょったけど、これから起きることは、すべて。 「それってでも、夢なんでしょう?」 「でもパスワードは合ってた。入力できるのは数字だけじゃないから、偶然はありえない」 宇宙に出たパイロットがよく、意識の拡張が起きたと報告している。70年代のサイケデリックではありふれた話だし、最近のアニメでも、宇宙戦争に巻き込まれた少年たちが超常的な知覚に目覚めるものがあった。僕にもそれが起きているのかもしれない。 「でも、日本が滅びるっていうか、地球が滅びるって、最初からいわれてたことだし、大丈夫よ。私たちは新しい星で、また文化を芽吹かせればいいんだから」 「うん。確かにそうなんだけど、国がないってことは、僕たちで秩序を維持しなければいけないってことなんだ」 たとえばYM0219に降り立ったとして、そこで何かトラブルがあったら、警官がそれを制止し、それを裁くための裁判を開かなければいけない。だけどこの移民船には警官も裁判官もいない。その資格があるものはいても、政府から認定を受けた警察や裁判所はない。トラブルが起きた際に日本の法律で裁くにしても法に定められた手順というのをもう守りようがない。もちろんそれは些細なことで、合議によってどうするか決めてしまえばいい。だけどその合議にも根拠はない。しかも論理的な話し合いができる人間なんか限られてる。決めたことに抜け道があれば、それを利用して身勝手に振る舞うものは出てくる。だれかの身勝手が成り立つとわかったら、だれも規則になんか従わない。 「だから、そうならないように。みんなで決まり事を作ればいいんじゃない? 移民星に着く前に、一部だけ人工冬眠から覚醒させて」 「殺し合いになるから、止めたほうがいい」 「殺し合い? 話し合うだけでしょう? それも夢で見たの?」 「見たよ」 「夢よ、そんなものは」 「たとえば何家族かが起きて、法律を作ろうっていって話し合って、その中でトイレが詰まったみたいなトラブルがあったらどうする?」 「たかがトイレじゃない。詰まらせたひとが掃除すればいい」 「それがだれかわからなかったら?」 実際にはトイレどころか、テレビゲームの順番待ちですらトラブルが起きてる。トイレには汚物を擦った跡か血痕かもわからない汚れがある。シャワー室のガラスはすべて割られて、フードディスペンサーは半分が壊れている。そんななかで、ひとはお互いを信じ合えるものだろうか。 「だれのせいかわからない、アイツに違いない、でも認めない。当番だからおまえが掃除しろって揉めたら? それでもだれかが掃除しなきゃいけない。だれかが嫌々掃除する。トイレを汚したやつは本人が認めないだけで、おそらくみんな『アイツだ』ってのは知ってる。その『アイツ』って指弾されてるのが、謂れなき自分だったら? そこでまた次のトラブルが起きたら?」 「そこまで揉めるんだったら、トイレくらい私が掃除する」 「ダメだよ。それだけはぜったいに。そこから綻びる」 「そうかなあ」 「だれかが嘘をついているんだよ。その嘘を知りながら苦役を引き受けてるひとがいるのに、そいつは黙っているんだよ。協調性のない嘘つきが混じってて、不信感が広まって、葉子はその状況で、ひとりで艦内を歩ける? ひとを信じることってできる? もしそれで葉子に危害を加えるものがいたとしたら、僕が正気でいられると思う?」 「でも、殺し合いまでは……」 殺すよ、僕は! 葉子に危害を加えるものがいたら! いや、危害を加えなくても、その可能性があるってだけで殺すよ! 殺すのは他のだれかじゃない! 僕なんだよ! ……でも、いえるわけがない。いったところで、僕の危惧が伝わるわけがない。だって葉子は、そうやってみんなと協調して暮らしてきたんだから。僕の友だちのなかにだって本物のクソはいた。そいつらが何をしてきたか、葉子は知らない。そいつが、付き合ってた彼女の妊娠がわかったとき、何をいって、何をしたか。初めて出会った日の飲み会で、何をしたか。じゃあ僕は、それを聞いてそいつと付き合いをやめたかっていうと、そんなこともない。「あんまり無茶するなよ」って笑って、その日もいっしょに飯を食ったんだ。そいつだけが特別じゃない。そんなのは普通にいるし、だれも指弾してこなかった。ある意味それが、僕らの協調性だった。それが壊れたときどうなると思う? だれか気に入らないやつがいて、2~3人でつるんで、「あいつをひどい目に合わせてやろう」って思ったとき、何が起きると思う? だけど、無駄なんだ。いっても。 「……うん。そうだね。夢でしかないから。葉子と揉めるくらいだったら、イワナガ塔の一部を覚醒させてもいいよ。でも、万が一の事が起きたら……」 「万が一でしょう? 起こしたひとたちが殺し合うとしたら、それはそのひとたちの責任でしかないし」 違うんだよ。まわりにいるだれかが殺し合って、それを目にして人類に絶望したとしたら、僕らは正気でいられるのかな。現実に、この船で起きているトラブルを僕も葉子も見ないようにしているじゃないか。葉子は殺人って見たことないでしょう? もちろん僕もだけど、それが何十って数で身の回りで起きた時、ひとはどうすると思う? 「私は、ひとを信じたい」 葉子を押し切って、反対することだってできたんだと思う。 「わかった」 どうすれば良かったのだろう。 葉子は、これから23区で何が起きるか知らない。 僕が知ってることだって、夢でしかない、現実ではあんな事は起きないって信じたい。 だけど事件は起きた。 イワナガ23区で起きる惨劇を目の当たりにして、葉子は何度か呼吸困難を起こした。パニックになり、眠りについた殺人者をそのまま閉じ込めようとしたこともあった。殺人犯を放送で教え、それがさらなるパニックと憶測を呼んだこともあった。僕はモニターなんか見ていられず、葉子をなだめるだけで手一杯になった。 そして最後に生き残ったのは、最初の殺人を起こした奴。 僕はそいつがのうのうと人工冬眠に入るのが許せず、他のものの人工冬眠を解いて、そいつを糾弾させようとした。夢の通りだったら、だれかが全員の人工冬眠のスイッチを切る。そうなるくらいだったら、せめて最後くらいは抗わせたい。数の力さえあれば、そいつが糾弾され、捕縛され、そこに彼らの自治が完成していくような気がして。だけど僕の些細な望みは、打ち砕かれた。 コノハナ23区の壊滅後、人工冬眠装置の脳波誘導を使って、葉子の気持ちを落ち着けて、僕にはふたつの選択肢が残されていた。 ひとつめは、管理マニュアルに沿って、全搭乗者に夢での投票を呼びかけること。 もうひとつは、僕の独断でニニギをYM0219に向けて、到着までに僕自身の手で、新しい法体系を作り上げて、それを絶対の法として、搭乗者全員に守らせること。 当然僕は後者を選んだ。 それから僕の、夢を見ない15年が始まった。 管理者パスワードを使って、全員の人工冬眠の起床設定を伸ばして、YM0219到着までは覚醒しないようにセットした。 葉子を寝かしつけて、いよいよ法律作りにかかる。 もちろん法律なんか作ったことがない。 とりあえず、新しい環境でも日本の法律が適用されること、裁判所など必要なものは移民先で用意してよいということ、代議士の選任方法、代議士の権限、この法が正当である根拠、などを決めて、全員の署名を偽造した。 それから、宇宙移民が生き延びるためなのでしょうがないと思うのだけど、遡及法をありに設定した。これによって、代議士の合議で法が設定されたら、その法は過去に遡って適用されることになる。法の精神だとかいわれたらよくわからないけども、全滅するよりはマシだ。 それと、僕が代議士に選ばれなかったら困るので、『代議士の長である町長は、市民の中の最年長者が自動的に選任される』という法を書き加えて、15歳ほど歳を取ることにした。 とはいえ、ひとりで15年起きているのは辛かった。 葉子を起こそうかとも思ったけど、移民船に乗る前に語らったふたりの夢を思い出して躊躇われた。子どもを作るのは新しい星についてからと約束していた。 自分だけが目覚めている宇宙船の中で、3日目くらいには、様々な妄想が脳裏を駆け巡る。僕はすべての部屋、すべての人工冬眠装置をコントロールできる。僕はいま、ローマのカリギュラ以上の絶対的な権力を手にしている。 乗客リストの中から中江亜実の名前を探したら、全艦で5人の中江亜実が搭乗していた。その全員がコノハナサクヤ塔にいる。もしかしたらこの中のひとりが簀巻座の中江亜実かもしれない。彼女を起こして訊ねたら、何か知っているかもしれない。彼女を起こして訪ねたら、無重力室に連れて行ってくれるかもしれない。 4日目。葉子を起こした。 理性的な目的は二の次だった。肉体に操られるままに吐息を交え、戸惑う彼女の肩に頭を押し当てて泣いた。自分の使命の正当性がもうわからない。それでも、新しい星では、長老としてみんなを統べたい、トラブルを可能な限り減らしたいと、思いの丈を語ると、葉子も賛同してくれた。 15年の退屈は、本を読んで凌ぐことにした。本は他の搭乗者からこっそり借りて、こっそり返した。葉子もその程度の不正なら見逃してくれた。40日間しか提供されないはずの食料も、端末の操作でなんとかすることができた。だれかの部屋で任天堂の最新型のゲーム機を見つけて遊び倒した。 15年の月日が矢のように流れて、僕と葉子は43歳になった。データで見る限り僕たちが最年長だ。新しい星で過ごすはずの青春の日々を、こんな形で奪って申し訳なかったが、イワナガ23区の惨劇を知っている葉子は、理解を示してくれた。そして葉子と僕の間にはふたりの子どもがいた。上の子は10歳、さくら。下の子は7歳、てるる。どちらも女の子だった。彼女たちには搭乗者登録がなかったので、予備の部屋を見つけて、搭乗者登録を偽造した。彼女らのブロックまでは少し離れていたが、人工冬眠に入ってしまえば距離は関係ない。やっくん星まであと35年、ようやく僕たちは人工冬眠の眠りについた。 そしてやっと、夢を見るようになった。 暗い博物館の地下。 壁一面の本棚や資料棚。 夢を見ることが久しぶりすぎて、僕は本当にそこに来たのかと思った。 机の上には様々な資料が並べられて、台座の上の赤茶けた地球儀を、部屋の灯りがぼんやりと照らす。机の上には無数の茶色い染み。地球儀の周りには、虫眼鏡、ピンセット、補修用のパテと12色の絵の具。包帯、注射器、錠剤の瓶。 その地球儀を亜実が修復していた。 「亜実。何してるの、こんなところで」 「あ。幹夫、久しぶり。もう来ないのかと思った」 亜実の顔には泣き腫らした涙の跡がある。 「うん。ごめん。これは?」 「地球を修復してるの。少し放射能汚染がひどいけど、生物は死滅してないし、もうすぐ復旧できそう」 赤茶けた地球儀には不器用にパテが盛られ、修復したあともまた壊れ、セロハンテープや糊で不器用に修復が重ねられている。彼女は口にはしないけど、きっと泣きながらこれを修復しているんだ。ひとりで。 「そうか。亜実が修復してくれてるんだ」 「うん。ニニギに戻ってたの?」 「そう。15年起きてたから、歳取っちゃったよ。ごめんね。勝手にいなくなって。もうすぐやっくん星に着くんだけど、どうする? 起きる?」 「いまは無理。もうすぐ地球が蘇るの。やっくん星にはあなただけで行って。そして、あなただけでも、地球に帰って」 地球に帰ってったって、そんなボロボロの地球。亜実が修理したところだって、ひどくなってるけだじゃないか。もう何もしないほうがいい。夢の中でまでそんなに苦しむんだったら、目を覚ましたほうがいい。 亜実の顔にはもう、シリウスで見た恍惚の表情もなかった。ただ無表情に、もくもくと壊れた地球にパテを盛り、色を塗る。 「帰れないんだよ、亜実。ニニギには重力圏から離脱するような性能はないから、やっくん星に降りたらそこが終着駅だよ。それに、重力帆を広げて減速して下りるから、ニニギ全艦で着陸することになると思う。亜実のいるブロックだけそのままっていうふうにもできないんだ。約束を破って悪いけど、亜実も起こすことになる。でもきっとやっくん星はいい星だから。気にいると思うよ」 「知ってる。でも、そこでいっしょに暮らしてはくれないんでしょう?」 「ごめんね。僕はどうやら、現実世界に妻がいたみたいなんだ」 亜実はまた机の上のセロハンテープを取って、取れかけた島を貼り付ける。そうするとまた、隣の島が剥がれ落ちて、亜実が涙をこぼすと、机の上の茶色い染みの隣に、新しい水滴が広がる。 「いっしょに修復するっていったのに、守れなくてごめんね」 「いいよ」 亜実が鼻をすすりながら教えてくれる。 「もう見えてきたよ。やっくん星」 頭上のガラスのドームに、地球に似た青い星が見える。 「ほんとだ」 亜実は、大粒の涙を零しながら、優しい笑顔を僕に向ける。 「さよならだね」 部屋にサイレンが鳴り響く。 地面が揺れる。 本棚がガタガタとゆれて、資料が落ちてくる。 「早く逃げないと、誘爆するよ」 「誘爆?」 鳴り響くアラートの中で目を覚ました。 船の振動が激しい。 葉子はまだ眠っている。 端末から緊急覚醒モードにして葉子を覚醒させる。モニターにコノハナサクヤ塔の事故がアナウンスされているが何が起きたのか情報がない。すぐに目を覚ました葉子が、目眩のする頭を押さえながら、船の振動に意識を向ける。 「どうしたの、これ」 「コノハナサクヤで事故が起きてる。火事か何か。まだよくわからないけど、誘爆するかもしれない」 「他のひとたちは起こさなくてもいいの!?」 「わからない」 とにかく、すべての隔壁と部屋のロックを解除して、どこからでも端末にアクセスできるよう開放し、子どもたちのいる第1ブロックを目指す。搭乗者を起こすかどうかの判断は、いまはつかない。 第6ブロックから第5ブロックへ移る時、巨大な振動、轟音。急に発生したGに身体を取られたあと、次の瞬間、人工重力が消える。 「どうしたのこれ!?」 「コノハナサクヤ塔との連結が切れたんだと思う」 ただ、まだ完全には切れていない。コノハナサクヤで起きているだろう爆発音が躯体の振動として伝わってくる。時折、躯体を打つ衝撃がある。連結部のワイヤーが暴れているのかもしれない。コノハナサクヤ塔との接触があれば大事故を引き起こす。 「第1ブロックに入ったらすぐに隔壁を閉める。開けっ放しだと、どこかのブロックに穴が開いただけで、全艦に影響が出る」 第3ブロック。もうすぐ子どもたちの部屋にたどりつく。そろそろ決断しなければいけない。 「葉子は子どもたちの部屋へ。第1ブロック3層C列の8!」 開いている部屋に入り、全人工冬眠装置を緊急覚醒モードにセット。コノハナサクヤの系統へはもうアクセスできない。向こうの人工冬眠装置が反応してるかどうかわからない。 「緊急事態です。コノハナサクヤに重大事故がありました。だけど落ち着いて行動してください。移民先の星はもう目の前です。落ち着いて行動してください」 僕が端末を操作している部屋の冬眠装置も開く。 緊急覚醒モードで起こすので、細胞に損傷が出る可能性があるが、もしブロックごとに分離するようなことになったらだれかが起きてコントロールするしかない。 人工重力がなく移動もままならないなか、壁を蹴るようにして部屋を出て、第1ブロックへ向かう。隔壁を越え、すぐ目の前の部屋に入る。 「端末をお借りします!」 住人は戸惑っているが、無重力で体が浮き上がり、僕にかまっている余裕もない。 「緊急事態です! ただいまより全隔壁を封鎖します!」 アラートが次々と表示される。すべてのポップアップを消して、外部モニターにつなぐと、燃え盛るコノハナサクヤの機体が映る。 「コノハナサクヤ塔で火災発生! 爆発の恐れがあります! イワナガは影響を最小限に食い止めるべく、すべての隔壁を封鎖します。ブロックを移動しているひとはすみやかに元のブロックへもどってください。1分以内に隔壁を封鎖します!」 時計を見ると昭和124年、10月4日、午前11時18分。 この時計が1分進んだら隔壁を閉じる。 コノハナサクヤをモニターで見ながらその1分を待つ。 炎に飲まれた艦内に亜実の姿が見えた気がして、思わずマイクに向かって声を上げる。 「亜実! 亜実! 起きているか! 幹夫だ! コノハナサクヤの火災は中央から広がっている! できる限り艦の両端に逃げるんだ! 隔壁を閉じれば爆発に巻き込まれずに済む! 聞いているか!? 管理パスワードはもく星号が墜落した年の雨の日! 亜実! 君自身だ! 逃げて!」 コノハナサクヤへのアクセスはもう遮断されていた。声が届くとも思えなかったけど、胸の中の不安を抑えるにはそうするしかなかった。モニターの中のコノハナサクヤから閃光が放たれ、ちぎれ飛んだ瓦礫がイワナガの船体を叩く。イワナガの船体も大きくたわんでいる。折れるのも時間の問題だ。 「隔壁を閉じます! このままだと船体が折れてしまう可能性があるので、ブロックごとに分離させます! あとは各艦で移民星を目指してください! 管理パスワードは、1、9、5、2、0、6、0、6。もく星号が墜落した年の、6月6日。船の操作法は端末ですぐに調べることができます! みなさんどうか希望を捨てないでください!」 燃え盛るコノハナサクヤ。誘爆が広がる。イワナガ塔の躯体がぎしぎしと悲鳴を上げている。限界だ。 イワナガ塔をブロックごとに分離。 マニューバ起動。全艦の電力系統が切り替えられる。赤い非常ライトの中、第2隔壁が降りる。コノハナサクヤの爆発の光が展望室の窓からイワナガの船内を照らす。その放射熱がソファのナイロンを溶かす。消火剤が噴霧され、防護壁が降りる。 アラートが出ている。確認すると、コノハナサクヤ塔のアクシデントにより減速制御が不全で終わっている。YM0219が迫っているのにまだ光速の1%を超える速度がある。減速マニューバ起動までのカウントダウン表示。緊急用の重力帆を上げようとしている。全員を起こしたのは失敗だった。 「葉子! 減速マニューバが起動する! 子どもたちと人工冬眠装置に入って!」 全艦内ブロードキャストのまま葉子に呼びかけ、そのまま艦内へ向けて叫ぶ。 「全艦に案内します! 重力帆制動がかかります! 急激なGが発生します。モニターがある側の壁に押し付ける力が働きます! 人工冬眠装置内では対G制御が働きます! 各自できるかぎり人工冬眠装置内へ!」 部屋のふたりは同じ冬眠装置へと入る。僕もアナウンス後に空いた冬眠装置にと手をかけるが、同時に重力帆が広がり、YM0219の重力を捉える。減速。その加速度で壁に叩きつけられる。そのイワナガ号を慣性で追い越したコノハナサクヤ号が音もなく爆発、ゆっくりと四散していく。その無数の瓦礫が分離したイワナガを襲い、23のブロックの内3台が巻き込まれ、コントロールを失う。 重力帆を使っての減速。すでに光速の1%まで減速されているとはいえ、それでも瞬間最大で5Gの加速度がかかる。船体がきしみをあげる。視界になかったYM0219が急激な速度で眼前に迫ってくる。それを追い越す間際にアンカーを打ち込む。重力帆とアンカーによる二重の制御でまたGの方向が変わる。子どもたちは大丈夫だろうか。僕たちは地球のGを知っているけども、子どもたちはニニギの0.8Gの重力しか知らない。まずは8時間かけて光速の0.5%まで減速し、その後20時間かけてYM0219を周回する軌道に乗せる。その間数回の重力帆制動とアンカーの打ち込みが発生し、急激なGがかかる。もはやその方向を予測することはできない。僕は最初の8時間を耐えられるのか? モニターを見ていると、同様のオペレーションを行うブロックのいくつかが崩壊していくのがわかる。別のブロックが打ち出したアンカーが、僕たちのブロックをかすめる。 そのあと――どうやら僕は、気を失っていたらしく、何が起きたのかはわからない。 目が覚めたのはイワナガ第1ブロックがYM0219周回軌道に入った頃。 僕が目を開けると同時に、葉子と子どもたちふたり、大粒の涙を流した。 * YM0219の周回軌道へ入ったブロックは、わずか3機だった。人数にして千数百人。そのなかでも搭乗者の相当数が減速時の操作に耐えられなかった可能性がある。ここからの大気圏突入にもまだリスクがある。第一ブロックは先頭の外壁が厚く、安全性は高いが、コノハナサクヤの爆発で船体に傷が入っていたら、そこから崩壊する。しかし、かといってここにとどまるわけにもいかない。データを見る限り、高度は少しずつ下がり、外壁の温度は上昇を始めている。着陸地点に川のある平野を選んで、すぐに着陸モードへと移行する。木花咲耶ではずいぶん長い夢を見ていた気がするけど、こちらが現実だ。何をするにしても常に死と隣り合わせている。 大気圏突入後、案の定船体の一部は剥ぎ取られる。しきりにアラートが鳴っている。外壁は二重化され、その間に工作機械や資材が積み込まれているが、その一部が失われているらしい。その部分のパラシュートも失われるだろうから、バランスが取れないままでの着陸になる。だけどここに来たらもう祈るだけ。35年の眠りなんかにつかず、家族と暮らしていれば良かったかもしれない。何もない宇宙空間ではあっても。子どもたちがいれば物語を作って聞かせることができた。シリウスでの出来事が夢じゃなかったら、亜実が光り輝く宇宙船に乗って助けに来てくれるのに……。でも、亜実は……。 熱に包まれたのはわずか20分あまり。その20分にいままでに神や仏に捧げた祈りを遥かに超える祈りを捧げた。その祈りが地球まで届くのか、あるいは、星系を越えてまで神は偏在するのか。それに僕は、無神論者じゃなかったのか。 大気圏突入マニューバが走り始めて22分15秒後、パラシュートが開き、イワナガ塔第1ブロックは広い平野の川のすぐそばに着陸した。 すぐに大気が調査されるが、不思議なほどに地球と似ていた。 まさにシリウス星にて予測された通りで、僕の中にふと、シリウスでの出来事は何だったのかという疑問が湧き上がる。これが現実ならば、シリウスも現実でなければ辻褄が合わない。 着陸後、ブロック両側のハッチが開き、居住棟の展開が始まる。イワナガ号で部屋として利用していたものが、そのままクレーンで降ろされて居住用のコテージになる。 上陸したものたちは、久しぶりに感じる生の重力に涙を零した。 外壁は半分近くが失われていたが、残った外壁の中には旋盤や工作機械、建設資材、発電機など、生活に必要な資材が多数詰まっていた。6輪のビーグルや自走式の伐採装置、着替えもあれば、機織り機のようなものもある。あるいは、地元協賛企業のグラスやタオル。タオルには企業名、電話番号が書かれている。まるで冗談のように無意味なその文面を見て、みな笑い、そして、涙を零した。搭載された物資は決して、完璧といえるものではなかったが、文明を再生するために必要なものは一通り揃えられていた。 周回軌道にいた他の2機のブロックが無事に着陸できたかはわからない。遠く離れたところに着陸していたとしたら、僕らが再び出会えるのは数百年後かもしれない。その時にはもう地球から来たことなど忘れ、別の国のもの同士として出会うことになる。いずれにしてもここからはこの星の自然と、それから時間との戦いだ。僕らはすぐに地質調査を開始する。同時にどのような資材が必要になるかを洗い出し、町の発展計画を練る。 僕がでっち上げた法律は功を奏し、僕が最年長だからということで町長に選ばれる。おそらく他のグループも同様、最年長者がわけもわからず町表に祭り上げられているだろう。子どもたちは移民局の手続きミスで移民に選抜されたことにして、代表の僕と葉子が養子として引き取るという形を取った。 生きてこの星までたどりついたものは2百名足らず。イワナガ1区は空室も多かったが、それでも4百は搭乗していた。つまり半数は急減速時のGで、あるいは人工冬眠装置の事故で命を落としたことになる。しばらくは悲しみに暮れることになるが、僕たちは前を向くしかなかった。 僕たちはまず、新しい町に名前をつけなければいけなかった。 いくつかの案が挙がった。ニニギで降臨したことで「ニニギ」という案があったが、「語感が悪い」という理由で却下。ならばと、日本神話にちなんで「ニュー・高千穂」という案も出たが、これはホテルの名前のようだと却下された。なかには「コスモ薬丸」というのもあった。つまりなぜかみな、ホテル&リゾート・木花咲耶での出来事をちゃんと記憶しているということだった。この記憶がほかのひとたちに刻まれているのは、僕の記憶とは矛盾したけども、そのあたりはもう自分でも混乱していてよくわからない。いずれにしてもこの案は、町の名前らしくないと却下され、ならばと、「イワナガ」という案も出たが、人々の記憶の中には木花咲耶での思い出が強く刻まれているらしく、イワナガよりもコノハナをという声がそれを圧倒した。 着陸したイワナガ塔の船体の前には、『木花町』と書かれた看板が立ち、この日を木花歴元年、1月1日と定めた。 暦を定めた時点では1年の長さはまだわかっていなかったが、わずか数日後には天文班の手で、おおよそ220日という推定値が上がってきた。しかし「それでは誕生日や記念日を祝えない」との割とどうでも良い理由で、1年の長さに関しては地球暦を採用することになった。1年は365日となり、しかもご丁寧に4年に1度、無意味に閏年が挟まる。 この星は緑が多く、宇宙船の機材を用いてバイオマス燃料を合成することができた。旋盤などの他各種工作機械を用いて、簡単な工作機械も組み立てられた。移民に選抜されたものの多くがなんらかの専門技能を持っており、地質班によって鉄鉱石が発見されるまでもそう時間はかからなかった。 緑も多く、土地も肥え、田畑を作れば、肥料もなく植物が育った。羊のような生き物の家畜化にも成功し、衣服の調達にも目処がついた。 ここでの生活に不安が感じられたのも最初の1年だけ。この星の自然や天候を把握するとともに、不安は期待へと変わっていった。住人は道を築き、自分たちの家屋を好きな場所へと移動させた。木花町は僕たちが予想したよりもずっと速いスピードで町としての体裁を整えていった。 不思議なもので、住人の多くは地球からテレビを持ってきていた。 アパートなり自宅なりを引き払う時に、手放すのも惜しくて持って来たのかもしれない。そのすべてが、人工冬眠している間に半世紀の月日を経てはいたが、技術班にいるソニーやシャープに勤めた生え抜きが難なく修理してくれた。また、インフラ班の活躍で、大通り沿いの家には100ボルトの電気が引かれ、ビデオデッキでも持っていれば、修理されたテレビを使うことができた。だがそれも一部だけのことで、多くの家庭では、しばらくはテレビは思い出の品として飾られるだけになっていた。 しかしインフラ班に続けとばかりに、技術班もその腕を活かし、イワナガ塔の放送設備を改造してテレビ放送を開始した。移民船ニニギには異星文明との接触を想定し、地球の様々なメディアが搭載されていたが、そのなかにはテレビの放送を1年分まるまるクォンタム・メモリに記録したものがあった。 「なんの意味があるんだよ」 と、呆れながらも、それを発見した日は朝までテレビに耽った。 木花歴2年、昭和57年に放送された水戸黄門が再放送された。それまで時代劇など何の興味もなかった若者が、ブラウン管の中の御老公たちの活躍に涙を流した。 この星の1日の長さは地球よりも2時間ほど長かったが、技術班は上手に調整して、地球の感覚と変わらないタイミングでテレビを放送してくれた。人々はテレビの放送に合わせて生活するようになった。東京ローカルのCMを見て、関西弁の男が「東京のほうが田舎臭いわ」と笑った。機械班が印刷機を、化学班がインクを、調査班は新聞を作り、テレビ欄を設け、人々はドリフの大爆笑やアメリカ横断ウルトラクイズを心待ちにした。 ニニギに搭載された旋盤やフライス盤などの工業製品の精度はかなりのもので、しかもそれを使える技術者が搭乗者のなかにちゃんと含まれていた。その気になればバイク程度は作れる、と技術班は豪語したが、人々は昭和の町並みを再現することに腐心した。地球にいた頃は、笹の葉の模様が入った昭和の板ガラスなんかダサい、時代はクリアなサッシ、みたいな流れがあったのに、加工班が昭和板ガラスを作ったとき、市民はみな涙を流した。窓のくるくる回して締める鍵。あれが再現された時、「くるくる回す鍵だ!」とみな大喜びしたが、その正式な名称はだれも知らなかった。 宇宙に来ているのに、UFO番組を見て『火星に異星人の基地がある!』と騒ぎ、『念じただけで曲がった!』とスプーンを見せる。やがて彼らは1999年の7の月に訪れる世界の滅亡に備えると、地下に巨大なシェルターを作り始めた。なかにはアニメで見た巨大ロボットを作りたいといい出すものまでいる。 「昔、ガンダムっていうロボットアニメが放送されてたんだ」 そういって町のものはこぞってガンダムの絵を描いたが、どれひとつとして正しいガンダムらしいものはなかった。 その脈絡はもはや計り知れなかったが、案外これが、幸せの正体なのかもしれない。 木花町では、思ったほどのトラブルは起こらなかった。遡及法が功を奏したのもあると思う。理性的に振る舞っていないと、いつ後付けで法改正されて裁かれるかわからないというのは、良い緊張感を生み出していた。法としてどうなのかというのは置いておいて、この町には伝統がない、従うべき道徳や、互いに監視し合う視線もないのだから、その代替として必要だったと思っている。 ただ、遡及法は危険だった。 たとえば嫌いな奴がいて、そいつが川でおしっこをしたのを確認した次の日に、『川でおしっこをしたら死刑』という法律を作れば、合法的にそいつを死刑にできた。もちろん、そんな恣意的な運用はしないことを前提とはしているのだけど、代議士たちの法解釈や運用にはやや危ないところが感じられた。正直ちょっと、これはまずいんじゃないかなと思うような罪で裁かれたひとが何人かいる。これはもう少し法が整備され、国が強固になったら、まっさきに改正しなければいけない。 それと木花町では基本的にものの所有、私有化を禁止した。イワナガに積んであった資材はそもそもが町の共有財産だし、それを用いて作られたものも個人の所有に帰すことはしなかった。土地や生き物、この星で発見したありとあらゆるものに所有権を認めなかった。いったんすべては町の共有財となり、そこから分け与えられる。 宇宙に出て共産主義か? と、眉をしかめるものもいるかもしれないけども、いまの環境で発見者が所有権を自動的に得てしまうような制度を認めてしまえば、乱開発を招く。いまの僕たちには政府がない。都市計画は自分たちで立てなければいけないし、そのためにはお互いの権利を慎重に規定するしかない。 もちろん、未来永劫いまの制度を維持する気はない。社会が変わり、必要とするリソースが変われば、分配や所有の概念は変わる。奈良時代中期、墾田永年私財法が出されたように、市民の欲望を開発に利用することだって考えられる。 所有の禁止に関しては、個人が宇宙へ持ってきたものは含まないことになった。このため、テレビを持っている家庭と持っていない家庭とで、やや不公平感が現れている。テレビでの娯楽提供に偏りがちな技術班への批判が見られるようになった。地球から持ってきた資産が、この街の人々の均質性を壊してしまっている。便利な道具が新しい暮らしの足枷になるというのは、皮肉なものだった。 あとは、家庭とは何かという定義が曖昧になっている。繁殖目的で宇宙に出されてしまった僕たちは、自動的にペアで生きるように運命づけられている。だけどなかには、家庭内で不仲になるひともいるわけだし、そんなひとたちが別れたいと考えた時に、住むべき家がないという問題が生じる。そしてここだけの話、内々に相談されて知ったのだが、とても文章化できないペアが混じっている。これはちょっと深刻すぎて、面白おかしく書けることでもないので割愛する。いや、面白くないから割愛されるというのは本人にとってはたまったことではないだろうけども、これは僕が町長として、しっかり耳を傾けて解決していくしかない。正直にいえば、この件への対応が僕の町長としての仕事のすべてだった。 このように、そもそもいっしょに暮らしているひとが、恋人なのか夫婦なのか、あるいは友だちでしかなかったのか、誘拐犯と被害者なのかというのがはっきりしない。そしてそれぞれが、自分は古澤幹夫なんじゃないか、中江亜実なんじゃないかという記憶をうっすらと持っている。これを家庭という画一的な単位で扱えれば楽なのだけど、場合によってはそれが家庭内の犯罪を隠蔽してしまう。また、次の世代が育った時に、家をどう用意するかというのは深刻な問題になる。いまはドリフの大爆笑や川口浩シリーズの放送に技術リソースを使ってればよいのだけど、これが家や車を作らなければいけないとなったときに、その職能をどう育て、確保していくかという問題が生まれる。 そして、娘のさくらが16になる頃には、父親としての不安が生まれる。 恋もしたい年頃だろうに、まわりには30代の既婚者か、3~4歳の小さい子しかいない。恋ばかりが人生だとも思わないけども、同年代の知り合いがいないというのも不憫だ。しかし、こればかりはもうどうしようもない。 この2百人の町で、青春マンガさながらの恋愛劇が見られ、その登場人物が口にするような苦悩を人々は口にする。思えば学校には外側があった。3年すれば卒業できた。この町が持つ最大の弱点は、逃げ場がないところだった。 この6年で、この町には多くの涙が刻まれた。無数の涙があった。世界を壊しているのは涙だった。それは表立って事件、事故になることもなく、涙によって空いた穴は、また涙で埋め合わされた。そして涙は物語となって、天駆ける星になった。 この街は虚構だ。 いや、すべての街が虚構だ。 そんななか、僕と葉子と娘ふたりは、町外れの丘の上に自分たちの力で家を建て始めていた。町を離れることに不安がないわけじゃない。町長としての仕事もある。だけどいつまでも僕だけが、強い影響力を持っていれば良いわけでもない。大草原の小さな家は葉子の夢だったし、娘たちにもそんな生活を通して伝えたいものがあった。共有資材のなかからテントとキャンプセットを取り出して、家族で丘の上で寝泊まりしながら家を作った。 家のそばには畑も作った。船の中にあった豆の苗、かぼちゃの種とを植えて、手探りで農業を始めた。やがて僕は正式に町長の座を降りて、農業に専念した。自分たちで作れないものは、採れた野菜を町で売って、そのお金で買ってきた。丘の上の家には行商のひとも来るようになって、中古のテレビを手に入れた。テレビはずっと昭和57年の番組を流し続け、娘たちはテレビに夢中になった。南の虹のルーシー、ときめきトゥナイト、おちゃめ神物語コロコロポロン。これらのアニメから娘たちは地球の生活を思い描いた。 「どれがいちばん地球っぽいの?」 「ときめきトゥナイトだけど、魔界は存在しない」 「ええーっ!」 僕は毎回見逃している魔境伝説アクロバンチの最終話を今度こそ見ようと心に誓う。毎年のようにそう思っては、見逃してしまう。 そんなある日、管理班のひとが家にやってきた。 「古澤さんの家は、イワナガ東区のほうに設定されてます。公平を期すためにどちらかの権利を手放してもらいたいのですが、いかがなさいます?」 どちらかといわれるなら、みんなで作ったこの家を残したい。まだ雨漏りがすることもあれば、未完成なところもあるけど、こっちは葉子がずっと憧れ続けた『小さな家』だから。それは妻も娘も同じだった。 「そうですか。ただしこちらはイワナガの機材を用いて作成されているので、所有権を主張できません。この町の共有財産となり、自由にひとが出入りできることになりますが、よろしいですか?」 「いや、所有権は確かにそうだけど、占有権みたいなものは?」 「残念ながら、法で設定されているのは所有権のみで、占有権に対する言及はありません。イワナガ東区にある居住棟でしたら、規則によって所有権が発生します」 そうだった。自分たちが住む居住棟のことまでは考えていたが、勝手に建てた小屋のことは考えていなかった。私有物禁止は、もう少し慎重に吟味すべきだった。 「ただ、いままでと同じで、所有権がないからといって、他人が自由に中に踏み込むことはないと思うのです。でも、何かトラブルが起きた時に、木花町の方ではいっさい保護することができなくなります」 1日だけ判断を待ってもらった。 木花町は犯罪も少なく、安全な町だった。僕が基礎を作ったのだから、そうそう酷いことは起きないだろうという自負はある。だけど年頃の娘をふたり持って、法的に保護されないとわかっている家には住めない。娘たちはそれでも、自分たちで作った家に住みたいと泣いたが、僕と葉子でふたりを説得した。 丘の上の家で眠る最後の夜。 夢のない深い眠りに落ちていると、さくらに起こされた。 「おとうさん」 「どうした? 眠れないのか?」 「お別れをいいに来たの」 「お別れを?」 そういうとさくらは目配せして、表へと出ていった。妻もてるるも眠りに落ちている。外へ出ると巨大なオーロラがあった。地球を発った日の前日がこうだった。青白い荷電粒子のカーテンに、さくらのシルエットが浮かぶ。 「なんだ、これを見せたかったのか?」 さくらはただ黙ってオーロラを見上げている。それは天駆ける星が、悲しみとともに降らせた涙だった。さくらの背中を通して、初めてその意味を知った。 「あのね、おとうさん。わたし、シリウスに帰るの」 「シリウスに?」 「わたし、シリウスから来たの。でももう帰らないといけない」 「いや、待って。帰るって、どういう意味だ?」 手を伸ばそうとすると、さくらの足元から青白い光が吹き上がる。 「さようなら、おとうさん」 僕の目の前でさくらが巨木へと変容していく。体のあちこちから芽が出て成長し、足元から出た枝はそのまま土に潜り、根を張っていく。 「待って! 行かないで、さくら!」 さくらから伸びる枝はどんどん伸びて、太く、ひとつに融合して、巨木へと成長する。幹は伸び、その先は枝分かれを繰り返し、無数の葉を伸ばす。さくらはオーロラの中で風に葉を揺らす巨木になっていく。その幹の太さはもう数メートルにもなり、オーロラの光を纏って青白く光っている。 ――いままでありがとう。 最後のさくらの声は、胸の中に直接響いてきた。 「行っちゃだめだ!」 次の瞬間、巨木にまとわりついていた光が天へ上っていくのがわかった。 「さくら!」 いったいどうしてこんなことに……。 なすすべもなく、その場にうずくまって号泣していると、玄関のドアをあけて葉子が出てくる。 「これは……? もしかして、さくらなの?」 葉子の問いかけに、僕は何も返すことができない。 次の日は雨だった。次の日も、またその次の日も。雨漏りも酷いし、薪もなくなってきた。もうここにはいれない。さくらを失って1週間後、名残惜しくて離れることのできなかった丘の上を離れて、僕たちは町に戻った。 町へ戻ると、人々はせわしなく走り回っていた。 「どうかしたんですか?」 通りすがるひとに葉子が訊ねる。 「天変地異が来る! この前からイワナガのコンピューターがアラートを鳴らしっぱなしだ!」 「天変地異というのは?」 「わからん。でもこの雨だ。大洪水じゃないかといわれている」 血相を変えて走り回るひとの姿に、てるるは怯える。 「大丈夫よ。みんなで作った町だから、そんなに簡単に壊れたりしないから」 葉子がてるるをなだめていると、町外れの方から男が駆けてきた。 「巨木があった! あの木があれば箱舟を作れる!」 巨木!? それはさくらが変容した木のことか!? 「待ってくれ! その木を切ろうというのか?」 「ああ、時間がない。すぐにイワナガの倉庫からチェーンソーを!」 「ダメだ! あの木を倒してはいけない!」 僕が止めるのも聞かずに人々は木を切る準備に奔走する。 僕はさくらが天へと帰っていった丘へと走る。 すでにもう何人かの男が斧を持って、その幹に打ち込んでいる。 「待ってくれ! 娘なんだ! その木は僕と葉子の!」 すぐに機材を積んだトラックが走ってくる。自走式の大型のチェーンソーが荷台から下ろされ、僕は斧を持った男たちの腕を掴むが、引き倒される。 「おとうさん!」 葉子とてるるも駆けつけている。 僕は何度も、何度も、斧を持った男の腕を掴んでは、地面に転がされる。 雨は激しくなる。雲間には雷鳴が轟く。 大型のチェーンソーがゆっくりとさくらの木に近づき、その幹に回転する鋼のチェーンを食い込ませる。 僕は思わず耳をふさぐ。 「やめてくれ……その木は僕の娘なんだ……」 ずぶ濡れの雨の中、さくらの木が悲鳴をあげて切り倒される。 巨木が大地を叩いて、その地響きが長く続く。 長く、長く、いつまでも、いつまでも、その地響きが止むことがない。 その鳴り止まぬ地響きに、男たちが戸惑う。 次の瞬間、遠くの山が火の手をあげる。 「噴火だ……」 「あれが天変地異?」 「シェルターに逃げ込め! 早く!」 男たちが消えて、僕ひとり雨に打たれる丘にてるるが駆けてくる。 「おとうさん!」 「てるる……」 羽織った布のずれを直していると、葉子もすぐに駆けつける。 「火山が噴火してる。あれがきっとイワナガが予測した天変地異だ。巻き込まれないうちに――」 巻き込まれないうちに――そこで僕は、言葉に詰まる。 シェルターにはさくらの樹を倒した連中がいる。それでも―― 「僕たちもシェルターに」 そう絞り出すと、葉子は柔らかく微笑む。 「いいえ、私たちはシェルターには入らないわ」 葉子とてるるとで、戸惑う僕の手を取って駆け出す。水たまりの泥をはねて、町外れのシェルターを通り過ぎ、木花町の目貫き通りを抜けると、そこにはイワナガ塔の第1ブロックが静かに横たわる。瓦解したイワナガ号の前で振り返り、葉子は僕に告げる。 「これで宇宙に出るの」 「これで?」 イワナガには大気圏突入性能はあるが、離陸機能はない。あったとしても外壁はもうぼろぼろだし、中の居住棟はすべて引きずり出され、パーツも様々に流用されている。これはもうイワナガではなく、その第9章 帰還者・古澤幹夫
僕は光となって虚空を飛んだ。 そしてシリウス付近で移民船ニニギを見つけた。 ニニギは元の二重螺旋ではなく、そのどちらかの鎖を失った一本鎖だった。残されたのはおそらくイワナガ。先頭ブロックの重力帆が中途半端に開いている。 「てるる、おとうさんを届けて。あの船に」 「わかった」 てるるに告げると僕の体は加速して、ぐんぐんとイワナガ塔に近づく。その第12ブロック。展望室の窓が見える。光を曵きながらその横に並ぶと、中にいるひとがすぐにこちらの姿に気がつく。亜実だ。人工重力のないイワナガの中で窓に手をついてこちらを眺めている。 「じゃあおとうさん、わたしはこれで」 「うん。てるるはどうするの? さくらみたいにシリウスへ帰るの?」 「わたしは、地球へ行く。おとうさんとおかあさんの故郷の星」 「そうか。じゃあまた会おう」 「おとうさんも地球に帰るの?」 「うん。亜実って子と相談してからだけどね」 「わかった。それじゃあ、しばしのわかれだね」 「ああ。しばしのわかれだ」 光に包まれた僕の体はイワナガ塔へと突入する。そしてそのまま壁を越えて、床を越えて、僕の部屋の人工冬眠装置の中へ。 藤枝小学校の校歌が流れ始める。 僕は光の中でくちずさんでいた。 「幹夫! おはよう! 人工冬眠覚醒プロセスに入って20分。バイタルも問題ない。あと10分くらいで気圧の調整が終わってハッチが開くよ」 亜実の声だ。 人工重力がなく、冬眠装置の中で僕の体は浮き上がっている。 「コノハナサクヤ塔はどうなったの?」 「わからない。急に人工重力が消えて、私の冬眠装置だけアラートが鳴って起こされたの。てっきり幹夫が起こしてくれたんだと思ったんだけど、幹夫の冬眠装置が止まってて……それで……何やっても開かないし……覚醒モードにしてみても反応はないし……私、幹夫は死んじゃったんだとばかり……」 そうか。何度かこうやって冬眠装置の中で目を覚ました気がする。正直もう、僕がどの古澤幹夫だったかわからないけど、いまの僕の財産は、その古澤幹夫としての記憶だけ。だけど宇宙の暗闇の中では、それだけあれば十分だ。 冬眠装置のハッチが開くと同時に亜実が抱きついてくる。 「ごめんね、心配掛けて」 「ダメだよ。幹夫のせいじゃないから、ごめんねなんていっちゃ」 それよりも―― 「人工重力が消えてどのくらい経ったの?」 「わかんない。まだ数時間だと思う」 このままだと、胎児の成長に影響があるかもしれない。 「なんとかしないと。管理画面を見て調べてみる」 モニターを覗いて、管理者権限でアクセス、船の状況を確認する。 亜実がいっていた通り、数時間前、正確には4時間23分前にコノハナサクヤ塔が失われたことがわかる。僕の胸の中に、木花町の丘の上でさくらの木が倒されたときの記憶が蘇り、痛みが走る。あれはこのことを示していたのかもしれない。 「コノハナサクヤ塔はどうなったの?」 亜実が不安げに訊ねる。 「おそらく、シリウスへ行ったんだよ」 「シリウスに?」 「そう。夢の中で、みんなでそう決めて、投票して、たまたまシリウスへ行きたい派が上回ったコノハナサクヤはシリウスへ行って、たまたまシリウスへ行きたい派が負けたイワナガが残されたんだ」 まるで亜実がいいそうなことをいってる。それを僕がどのくらい信じているのか、自分でもわからない。 「そうか。じゃあ、よかった」 と、亜実は微笑む。 「私たちはどうなるの?」 「どうなるんだろう」 速度を見ると、もう光速度の1%まで減速している。イワナガ単体でそこから再加速する性能はない。コノハナサクヤを安全に切り離すために減速したのかもしれない。そう考えながら管理ページを確認していると、ブロック喪失時の対処法が書かれている。 「亜実、これ」 亜実に指差して、ふたりで読み始める。リビルド・マニューバと書かれたその内容は、事故でいくつかのブロックが失われたときの対処法だった。当然のように塔の片方全体が失われたときのことまでは想定されていない。 どうする? でも、やるしかない。 リビルド・マニューバを起動すれば、各ブロックを切り離して、組み替えて、左右の塔の長さを揃えて、再度回転させて人工重力を発生させることができる。すなわち、全23ブロックのイワナガを、12ブロック2本鎖に再編成する。 「奇数だからひとつ余るけど、どうなるの?」 「機関部のある先頭ブロックが重いから、そこに2ブロックを連結して、あとはバラストで全体の重さを調整するみたい」 「よかった。23区を捨てるのかと思った」 頷きあって、リビルドを開始するが、すぐにエラーが表示される。 先頭ブロックの重力帆が開いていて邪魔になっている。 「どうするの?」 「切り離すしかない。電気系統の故障だと思う。手動操作もできるはずだから、行ってみる」 「私も!」 「ダメだよ。何かあったときに管理画面で操作してもらわないといけないから」 隔壁を開いて第1ブロックへ、第2層のエアロックで宇宙服を着込む。 「ぜったい帰ってきて。私を置いていかないで」 亜実はずっと繰り返している。 「うん。わかった」 モンキーレンチを一本握って、ストラップのカラビナをリストバンドに掛ける。 ヘルメットをかぶり、エアロック内へ。減圧。自分の呼吸音だけ聞いて、顎に触れるヘルメット枠が呼気に湿るのがわかる。音が消えていく。僕の体が発する生体のリズムのほかは、足元から響く音だけ。亜実の足音がかすかに伝わってくる。 「幹夫、聞こえる?」 亜実からの通信が入る。 「聞こえるよ。心配しないで待ってて」 「うん。待ってる。死なないでね」 「死なないよ。僕、夢の中で50歳くらいまで生きたんだよ。だから、ちゃんと帰ってきて、その続きを生きたい。だから、必ず帰ってくる」 「私も。私も幹夫といっしょにおばあちゃんになりたい。50歳とか、60歳とかになったら、自分のこと好きになれると思う。だから、必ず帰ってきて」 そうか。亜実がやっと生きるっていってくれた。自分のことを好きになるっていってくれた。だったら僕は、どんなことがあっても死ぬわけにはいかない。 「うん。いっしょにおじいちゃんおばあちゃんになろう」 室内気圧を示すインジケーターがグリーンを示す。ハッチを開き、宇宙へと出る。 マニュアルに沿ってゆっくりと外へ出たつもりでも、体は思わぬ方向に回転を始め、すぐに方向感覚を失う。視界にあるイワナガ船体に手を伸ばし、体の回転を止める。少し遠くに開きかけた重力帆が見える。ちょうど展望室から見える辺りだ。黒光りする薄い膜が、支柱の重量に反応して巻き取られ、絡みついている。あれを畳むのはもう無理だ。放出させて切り離すしかない。たった1本の重力帆を捨てたからといって、地球で減速できなくなるわけじゃないけど、そうやって肉体を切り離しながら生命を維持していくのにも限界がある。でも考えてみれば、あの帆があったところで、イワナガはもう加速できないんだ。リビルドを終えて人工重力を発生させたあとは、僕たちにはもう何もできない。 だけど、亜実。僕たちはそこで、おじいちゃんとおばあちゃんになるんだよ。 僕たちはただそこで、生きるんだよ。 支柱のそばへ来る。ライフワイヤーの長さは十分。処置が終わったら、帰りは巻き上げればいい。支柱の根本にも幕がかかりわかりにくいが、おそらくハッチが完全に開かずに支柱が引っかかっている。まずはハッチを完全に開いて―― モンキーレンチで支柱の根本に触れたときだった。 イワナガ第1区から伸びた重力帆の支柱が勢いよく外へ飛び出し、広い帆を広げた。帆は僕の足を取り、そのまま虚空へと跳ね上げる。不意に生じた回転力に翻弄され、目の前の景色は一定方向に流れ続ける。その中でイワナガ塔の姿がみるみる小さくなる。ライフワイヤーが僕の腰を強く引き、その感覚が僕の内臓に伝うが、次の瞬間にはその感触も消え、僕の体は放り出される。支柱は腕を広げ、僕の体を打つ。アラートが鳴り出す。空気が流れる音がしている。宇宙服のどこかに穴が空いている。目の前に黒い帆が広がり、僕の体はその上を転がる。ヘルメットごしに顔面に衝撃が走る。ゴーグルが砕けている。亜実、ごめん。僕は死ぬ。 「幹夫ーっ!」 亜実の絶叫が聞こえた。 真空の宇宙に、亜実の声が。 次の瞬間、光り輝く透明の亜実の体が僕をめがけて飛び込んできた。 「亜実!?」 「行っちゃダメ! 戻ってきて!」 亜実の体は僕をすり抜けて通り過ぎる。 僕も亜実の姿を探して手を伸ばすけど、その手はどうしても重ならない。 イワナガ塔の姿はどんどん小さくなっていく。 不意に開いた重力帆の制動を受けて、イワナガの船体は大きく折れ曲がっている。そして折れ曲がりながらもイワナガではリビルド・マニューバが働き、ブロックの組み換えが始まっている。だけどそれも、重力帆に引かれてあちこちで衝突が起きている。そして音のない爆発。もう無理だ。終わったんだ、何もかも。 「ごめん、亜実」 空気がもうない。肺から出せる声ももう終わった。 だけど次の瞬間、僕たちは光に包まれていた。 僕の魂は僕を抜け出して、虚空に漂う僕の体を見ていた。 「僕、幽体離脱したことありますよ」 というと、大体のひとは訝しがるし、たまに羨むひともいるのだけど、僕にとって幽体離脱というのは―― 違う。そうか。これが幽体離脱なんだ。 その体を亜実が抱きとめる。 亜実も僕も、その体は光り、透き通っている。 「僕たちは死んだの?」 ――違うよ。 宇宙の味を感じる。 ――宇宙は甘いんだよ、どこまでも。 大気圏を抜けるまではありとあらゆる雑味、えぐ味に塗れていて、だけど外気圏を出ると同時に口に残らない甘さがただずっと通り抜けていく。 それは星のかすかな甘味よりも更にかすかな、空間に薄く広がる甘み。 口で味わうとわからなくなる。 全身を広げて受け止めていると、肌が受け止めた感覚が、舌先に甘味を思い出させる。 遠くの星で生まれた物語の断片を蘇らせるように―― ――死んだんじゃないとしたら、僕たちはどうなったの? ――死んだんじゃないよ。それを超えたんだよ。 亜実がイワナガ塔を指差す。 そこにはシリウスの船の姿があった。 シリウスのひとたちの手でイワナガ塔が修復されていく。 失われていたコノハナサクヤ塔も、光の中から1ブロックずつ取り出され、連結される。 ――戻ろう。イワナガ塔へ。 ――うん。そして、地球へ。 * 昭和98年、11月10日。 減速プロセスを終えて惑星周回軌道へ入った頃、搭乗者全員、人工冬眠から覚める。 搭乗者は三々五々起き出して、人工重力も消えたなか展望室に集まり、あるいは各自の部屋のモニターで、これから降り立つ星の様子を眺める。その星は、赤茶けた大地に、雲も海もなく、木々の気配もない。 ――私たちは何星を選んだのだろう。 そんな記憶も曖昧なまま、訪れた星に感じた絶望と、あらためて地球に置いてきた家族、思い出の大きさに涙を流すひとがいる。泣き崩れるもの、叫ぶもの。そのなかにぽつり、またぽつりと、その星の様子に不審を抱くものが出始める。 赤茶けた大地に、うっすらと見知った大陸の輪郭があった。 どことなく見覚えのある地形のそばには深い海溝が走り、そこにばかり目を取られているとわからないが、オーストラリア、インド亜大陸、ヨーロッパ大陸の輪郭を見つけたものが、静かに声を上げ始める。 「地球だ……」 ついさっき、絶望のあまり地球へ帰りたいと願ったものがまた深い絶望に打ちひしがれる。人類はとうとう、行く場所も、帰る場所も失った。 艦内のモニターがすべて点灯する。 そこには地球に送り出した偵察機からの映像が流れる。 それは核戦争で滅びた都市の様子。 そこに移民星に到着したときを想定した、場違いな明るい音楽が流れる。その音楽と現実との対比は人々の胸により大きな悲しみを広げるが、続くアナウンスがそれを打ち消す。 「当艦、移民船ニニギは現在、物質界にイワナガ塔、アストラル界にコノハナサクヤ塔と、ふたつの世界にまたがって停留してあり……おります」 噛んだ。亜実はダンスは一流だったが、演技や科白はてんでダメだった。原稿を手にして読んでるだけなのにたどたどしい。 モニターに移民船ニニギの姿が映し出される。 地球側に、二重鎖に再編成したイワナガ、空に向かって、未知の金属の輝きを湛えるコノハナサクヤの姿があり、架け渡された梯子の先には緑に輝くもうひとつの地球が見えた。移民船ニニギの姿はまさに天へと架ける梯子だった。コノハナサクヤには新しい地球から上がってきたシャトルが鳥の群れのように取り付いている。更に一機、また一機とその枝に取り付いては、乗員を乗せた鳥がまた離れていく。 僕と亜実はイワナガ塔第12ブロックの自分たちの部屋から、艦内へアナウンスを送っていた。亜実のおなかの子はたぶん29週。もうずいぶんと妊婦らしいシルエットになっている。 「私たちも」 古い地球から持ってきたコンテナを開けて、荷物を揃えた。EOS620とBOXYのボールペン。亜実はいくつかの化粧品とアクセサリー。ふたり、晴れの日のために取っておいたパンツを履いた。 部屋の扉を開けると、あの日シリウスで迎えてくれた蝶の羽のひとたちが見える。無重力の廊下に浮かぶと、手を添えてくれて、そのまま身を任せるだけでコノハナサクヤへと導いてくれる。 胸のなかには、外の景色まですべて思い浮かぶ。 数多くの宇宙船がニニギを取り囲み、いろんな姿をしたひとたちが僕らを見守っている。あの日、シリウスで見た飛行体のすべてがここに集まっている。そして僕たちの姿を、宇宙全域に向けて発信している。 僕たちはコノハナサクヤ塔から、成田行のシャトルに乗った。 シャトルはあの日のままだった。 あれから40年経ったはずなのに、僕らに流れた時間はほんの数ヶ月だと思う。 藍色の空から、薄青の空へ。温度と音のある大気に翼を浮かべて、花咲き乱れる成田に降りると、空港はあの日と同じ、沙也加と木村さんが迎えに来る。 「まさか帰ってくるとは思わなかった!」 沙也加が僕と亜実の肩を同時に、両手で抱きしめる。 「こっちでは何年経ったの?」 「こっちは昭和58年のままやで。あのときの地球がこっちに再現されとうねん」 昭和のままという言葉に良い印象はなかった。木村さんがいうとおり、空港内はあの日のまま。僕を育て、僕を閉ざしていた檻に、僕はまた戻ってきたんだ。だけど、何かが違う。ただ息を吸っただけで胸がときめく。深呼吸をしていると亜実が袖を引っ張る。その指差す先にはコンビニがあった。僕たちはすぐに駆け込んで、キュービィロップとカプッツェル、ピケ8を買った。 エントランスを出ると、一面の花畑だった。そこには蝶が舞い、蜂が飛ぶ。 「毛虫もおるで」 毛虫も、蛾も、ヘビも、オケラも。 「せっかく来たんやから、ちょっと寄っていってもええか?」 木村さんはそういって、成田闘争で死んでいった仲間たちの慰霊碑へ向かった。僕たちの背後にコノハナサクヤからのシャトルが次々と舞い降りる。その白銀の翼が柔らかく風を起こすなか、膝までの花に埋もれるように、小さな慰霊碑があった。 「花持ってきたんやけど、あんまり意味なかったな」 木村さんは花に埋もれた慰霊碑に、更に花を添え、手に下げていたウイスキーを回し飲み、ボトルに残る琥珀の水をかつての仲間たちに捧げた。 エントランスに戻り、木村さんの車に乗って、千駄ヶ谷を目指した。 僕と亜実のアパートはもうない。財産もなにもない。もしかしたら戸籍もないかもしれない。荷物は小さなカバンだけ。それでも、ここを発ったときとは違う安心感がある。僕たちはまた、地球という大きな器官の一部になる。 京葉道路の左手には青い海が広がる。かつて僕が見ていた海より、もっと青い海が。 「宇宙はどうだった?」 助手席の沙也加が聞いてくる。 「たくさん夢を見た」 どちらへ聞いているのかもわからない質問に、亜実が答える。 「40年経っただけなのに、もっと長い時間を過ごしたようで、でも戻ってきたらこうでしょう? もう、何がなんだか」 「地球はどうだったの?」 「古い地球は核戦争でたいへんなことんなったけど、こっちはもう、平和なもんよ」 亜実はキュービィロップの袋を開けて、そのひと粒を僕の口に放り込む。そして半分まで溶けた頃に、僕の顔に口を寄せる。 「変わらないね、あんたたち」 沙也加が呆れて笑っている。 そう。変わるのはこれから。 僕たちは、この新しくなった地球で、おじいちゃん、おばあちゃんになる。 アパートを借りるまで、木村さんの部屋に世話になった。 沙也加の家も部屋がひとつ開いているというし、沙也加も亜実もそちらでもいいというのだけども、夫の浩二さんの手前、僕が少し気まずい。 仕事はバーチャル・ガバメント・ネットワーク端末、VGNで探した。 「これで仕事を分け合うと、ヤクザの独壇場になりませんか?」 「いままでの入札制やとそうかもしれんけど、いまは仕組みがぜんぜんちがうで」 そういって木村さんはVGNについて説明してくれた。 入札は、金額を指定するのではなく、プランを提案するらしい。 プランというのは、提示された事業に対してどんな計画を立て、その中でだれがどんな仕事をするか、そこで得られたお金をどう分配するか、などが記されたもの。そうやって集まったプランの中から最も理にかなうものが選ばれる。そこに集まるものは決して合理的なものばかりじゃない。職を失ったひと、障害のあるひとを雇用するプランあるし、提示された事業そのものを再構築して、福祉優先に最適化されたものもある。そこには多くのひとの夢が語られていた。プランの審査は複数の団体が行い、意見の偏りをなくし、審査中は情報の多くが匿名化されて議論される。 「もう上意下達の世界やないねん、ここは。核戦争で国は滅んで、俺らしか残っとらんし、俺らがどんな世界を作りたいかっちゅうことを反映していくしかないねん」 僕が夢の中で何度も失敗してきたことが、ここでは現実になっていた。おそらくそれは、亜実が泣きながらひとりで修復してくれたからなんだと思う。 「でもまあ、課題はあるねん。山積しとんのよ、そのへんに。でも、それで文句いうたってしゃあないやん。だれかがそうせえゆうたわけやないし、自分たちで決めなあかんやん。もしそれで喧嘩になって戦争になるんやったら、別に人類滅んでええのよ。だって、そうやんか。SFとか見ても、この宇宙には、滅びるべき文明と、残っていくべき文明があるやん。もし地球が滅びるべき文明やったら、さっさと滅んだほうがええよ」 まくし立てたあとで、木村さんは続ける。 「俺はそうは思うとらんけどな」 12月、僕の仕事も決まった頃、 「鼻血が止まらない」 と、朝からずっと亜実はタオルを顔に当てている。 木村さんの車を借りて都心の大きな病院へ。精密検査のあと、宇宙放射線による急性の白血病だと聞かされる。その場で推測される余命を知らされ、僕は足元に崩れ落ちる。 本人も自分の病状のことは、うすうす感じていたという。 「病院嫌いだったし、しょうがないよ。死んじゃったらごめんね」 「ごめんねじゃないよ。なんとかしようよ。僕たちは宇宙から帰ってきたんだよ? おばあちゃんになるんじゃないの? 自分を好きになるんじゃないの?」 僕たちにはシリウス星人の知り合いがいるし、この地球はアストラル界の地球だ。 白血病なんかで死ぬもんか。 陣痛促進して、早めに生んで、場合によっては帝王切開で子を取り出して、それから薬で治療すればまだ間に合う。可能性がゼロじゃないなら手を尽くしたい。 「ねえ、亜実。まだ間に合うから」 「いいんだよ。宇宙に出る時に、命なんか捨てたんだから。それよりも優しくして。最後の瞬間まで、私を甘やかして」 昭和59年、1月30日。 木村さんのアパートで亜実の出産。 沙也加と、その知り合いの看護師、木村さんが手配した助産師さん。 去年、病院に行った時に余命として宣告された日をもう過ぎている。 わかっていたことだけど、止血しても、止血しても血が止まらない。 沙也加と僕とで寄り添って、手を握って、亜実を勇気づける。 奮闘の末、亜実の子の泣き声が響く。助産師さんの手から僕に、タオルに包まれた子を渡されて、亜実の目の前に差し出す。 「亜実。女の子だよ。亜実の子だよ」 亜実は力なく、僕の手の赤ん坊に視線を寄せる。 「やっと会えた……」 顔を青白くしたまま、亜実は微笑む。 「これが私の、覚醒トリガー」 覚醒トリガー? ほんの1秒だけ微笑んだ次の瞬間、亜実が目を閉じると同時に、世界は暗闇に包まれた。 夢? ここまでが亜実の夢? じゃあ、どこからが? 暗闇に亜実の声が聞こえる。 ――そう。ここまでは私の夢。この先は、あなたが作って。先にシリウスに帰るね。 「待って、亜実!」 ――さよなら。 「行っちゃダメだ! 僕を置いていかないで!」 やけに明晰な夢。でも、明晰夢だったらただの明晰な気がするだけの夢だ。 僕は戸惑いながら、暗闇で目を開ける。 目の前に見えたのは、病院の手術室の白い壁だった。 広尾の日赤医療センターの産科。分娩台に亜実が横たわっている。 看護師たちの動きが慌ただしくなる。 僕の腕から赤子が取り上げられ、 「お父さんはこちらへ」 促されるままに廊下に出され、ベンチに座っていた沙也加が僕に振り返り、訊ねる。 「亜実は!?」 わからない…… でも亜実は、おそらくもう…… 「君が幹夫くん?」 見知らぬスーツの男が声をかけてくる。 「こちら、亜実のお父さん」 「根岸です。亜実のことではご迷惑おかけしています。亜実はどうなりました?」 僕は混乱したまま首を振る。 何をどう説明したら良いかわからない。 宇宙へ行ったのに。 シリウスに降り立ったのに。 亜実の最後が伝えられたのは、その30分後。 泣き崩れる僕の肩を沙也加が抱き留めると、窓の外には静かに雪が降り始めた。 亜実が紡ぎ出した幻想は白い雪となって、少しずつ、少しずつ東京の街を覆った。 宇宙の静寂の、その片鱗がまっしろに街を包むと、不慣れな雪道に静かに響くチェーンの音と、雪に走り回る子どもの声に、 「しーっ」 人差し指をいっぽん立てて、その不器用な包帯を幾重にも、幾重にも、この街に重ねる。この力に満ちた静寂と、恍惚の中で、きっと僕たちは何度も、何度も、生まれ変わってきた。 息を引き取ったあとの葬儀の段取り、親戚への連絡は、突然現れた亜実の父と名乗るひとが取り仕切り、僕はただ慌ただしく変わっていく目の前の景色を眺めていることしかできなかった。 葬儀の席。喪主は亜実の父。広尾の斎場の前、中江亜実の通夜を示す黒い文字が掲出されると、それなりに知られた名前を目にして、通行人が中を覗き込む。その一瞬で、だれもが亜実とともに宇宙を旅した夢を見た。 小さな箱のなか、花に埋もれて荼毘に付す亜実。そういえばこの口に、バラの花を詰めた。そういえばこの箱で、ふたりで眠った。彼女の青ざめた寝顔を見ながら、起こすべきか、寝かせておくべきか、まだそんなことを考えてしまう。 だけどもう、帰るべき肉体はない。 楽しい夢だけを見て、おやすみ、亜実。 別れを告げると、また涙が溢れてきた。 通夜の夜も更けると、喪主の方から僕に話しかけてきた。 「亜実の子は僕と妻とで引き取ろうと思う。沙也加さんの話では、君の子ではないというので問題はないと思うが、ただ法的には君が内縁の夫ということになる」 急に現れたくせに、何をいっているんだこいつは。 ――ダンスはうまいの? ――うまいよ。小さい頃はバレエ習ってたの。 僕は亜実と、世界でいちばん強く結ばれた結婚をしたんだ。こんなやつに亜実と僕の子を渡せるわけがないじゃないか。 「あの子は僕の子です。亜実が設定した覚醒トリガーは、亜実と僕の子なんです。亜実が僕を父親だと認めたんです!」 ――裕福だったんだ。 ――そう。お父さんに捨てられるまでは。 このひとが亜実と、その母親を捨てたんだ。それから亜実はずっと苦労して来たんだ。自分の身を削って生きて、貧乏だから医者には行かないって、それでここまで来てしまったんだ。 「あんたなんかに渡せるわけないじゃないか!」 食って掛かる僕を沙也加が抑える。 「あんたが亜実の何を知っているというんだ! 今頃出てきて父親だって顔だけするのかよ! ぜんぶお前のせいだろうが!」 「どうしたんですか?」 斎場のひとがふたり、僕のそばに来る。 「いえ、大丈夫です。なんでもありませんから」 根岸って男が斎場のひとを払う。 僕は泣いた。ただただ悔しくて、泣いた。 亜実が持病を持っていることなんて、ちゃんと気にかけていたらわかっていたことだった。いや、わかっていたはずなんだ。亜実の手を引いて病院に連れていく機会なんか、何度もあったはずなんだ。亜実が飲んでる薬のことだって知っていた。後悔しっぱなしだ。後悔しかない。あと半年早く知り合ってたら、あと1か月でもいい、そうしたらこんなことにはならなかったのに。 葬儀のあと、沙也加が間に入ってくれて、僕と亜実の父親とで話して、亜実の子は僕と沙也加とで引き取って育てることにした。沙也加は夫の浩二、息子の啓介と暮らしていたけど、そこに何故か僕と娘とでお邪魔することになった。根岸という男は、ならば経済的支援をと申し出てきたが、断った。亜実と僕の子は、番外編 残留者・岬沙也加
1 メルクル
学校の校舎の向こうに、始めてオーロラを見た日。昭和42年。私はまだ高校生だった。 青白く光る夜空を見上げて私は――勝った――と思った。 私が鉄槌を下すまでもなく、みんな死んでいく。 『死だけは公平だ』といっただれかの言葉にずっと違和感があった。死は公平なんかじゃない。決まって弱いものを狙ってやってくる。それがどうだろう。いまやっと死は強き者に牙を剥こうとしている。持つ者からは奪い、持たざる者の悪夢を終わらせる。あいつらが私たちから奪って築いた幸福が終わる。やっと。やっとだ。やっと人類に死が訪れる。そのときめきは私の胸いっぱいに広がった。 人類滅亡が予見されたのは、五年まえ。 私はまだ小学五年生。あの日から不安が社会を覆い、犯罪は増え、人々は働くことを辞めた。不安のなかでの小学校卒業。意義のない高校受験。だけど否応なく繰り返される日常のなかで、いつしか絶望は空気に変わっていた。ひとびとはまた仕事に就いて、お金を貯めた。 その矢先のオーロラだった。 ――にゃあ 星空から見下ろす私の足元、メルクルはしっぽを立てて、一声だけ鳴いた。 明日からまた犯罪が増えるよ。メルクル。 ――だけど沙也加 うん、なあに? ――世間には絶望が渦巻いているだろう? ――きみら女子高生がうっかり外を歩くと、ひどい犯罪に巻き込まれるよ わかってる。このさきどんな苦労をするかなんてわからない。 また取り付け騒ぎも起きるだろうし、トイレットペーパーだって売り切れる。 だけど、私の勝ち。 地球の滅亡とともに、みんな死ぬ。 あれから更に五年。 私は二十歳、メルクルは十三歳になった。 地球は未だ滅びず、自暴自棄になったひとたちは、自暴自棄な五年を過ごした。 私は自暴自棄になって受けた大学に奇跡的に受かって、自暴自棄に上京、自暴自棄にひとり暮らしをはじめ、自暴自棄に男の部屋に転がり込んでいた。2 マーフィ
日曜の朝、カレーを食べた。 子どものころ、一日置いて冷めたカレーは好きだった。妹もそう。友だちもみんな。中学生になってクラスで聞いたら、私も、じつは私も、と声が上がった。 「冷めたカレー、みんな好きだっていってたよ」 うちに帰って、母親にも話してみたのだけど、反応は鈍かった。 東に向いた窓のカーテンの隙間を縫って、朝の光が白い三角形を描く。その先端が私の枕元を離れるころ、鳥のさえずりも消える。車の喧騒に驚いた鳥は私のなかに逃げ込んで、胸の隙間に身を震わせる。私の巣は、ほころんだ青い掛け布団。目を覚ますと、隣で寝息を立てていた彼の姿はない。 彼――3 楠浩二
「じゃあ、初恋は名前も知らないその子なんだ?」 「いや、初恋なんかじゃないですよ。6歳ですよ、まだ」 「いやいや、6歳でも、あるじゃないですか、保育園の先生を好きになったー、とか」 大学の二年、二十歳になった頃にマーフィと半同棲みたいな生活が始まった。 何度かテレビの撮影現場も見せてもらったし、もしかしたらいつか放送作家の仕事がまわってくるかもしれないとも思った。嬉々として番組のアイデアを語ったこともある。バラエティ番組でラウンドガールみたいなものをしないかと誘われたことはあったけど、水着の仕事だったので断った。私の身長は一六五。ラウンドガールはともかく、モデル事務所に登録しておけば、何かのきっかけでテレビに出るのも夢じゃないと勧められた。だけど私は、肩の高さが左右で違う。 それに、作品で勝負したかった。ショート・ショートやコントや人情噺を書き溜めていたし、私はそれがマーフィに劣るなんて思っていなかった。マーフィも素直に褒めてくれたし、大学にはちゃんと通いながら企画や短編を書いた。アイデアは次々と湧いて出た。そうこうしているうちに回ってきたのはラジオ企画、『あのひとに会いたい』のヤラセのリスナー体験談だった。 こういう思い出がある、こんなときに世話になったひとがいる、そういうものを――でっちあげでいいから何か書いて欲しい――というのが依頼内容。雅文からその話を聞いて、目の前に花が舞った。チャンスが回ってきた。ここから私の快進撃が始まる。そう思ってすぐにペンを握ったものの、自分で好きに書くのは得意だったはずなのに、お題を出された途端、何も書けなくなった。 『あのひとに会いたい』 頭のなかで思い描いてみるのは、 ――むかし、海で溺れかけたとき助けてもらって……だったり ――高校時代、バレー部のキャプテンに憧れていた……だったり どこかのドラマや漫画で見たようなパターンの焼き直し。 ひらたくいえば、駄作ばかり。 そういえば、私以外のひとたちが普段どうやって生きているか、何を考えているか、私は知らない。消えてなくなれと願った世界で、他人がどう生きているかなんて興味がなかった。 それでも私はすがりついた。学校でもそのことばかり考えた。時間はいくらでもあった。卒業できなくても、それまでにテレビの仕事に就くつもりだったから、授業はどうでも良かった。それなりの仕送りがあった。食費は彼の財布から出したから、バイトなどしなくてもそこそこ自由にやっていけた。 どうせ人類は滅びる。 私は好きなことだけやって生きて、そして、死ぬ。 買い物に出て、晩ごはんの材料と、ハイライトをふたつ買って、マーフィがいないマーフィの部屋に戻って、原稿に向かう。彼の没になったコントを読んで、煙草に火をつけてみた。はじめての煙草は喉に絡んで、咽た。思わずこぼれた涙が、不安を連れてくる。大学を出るのはまだ二年以上先。でも、そのあとはどうするんだろう。 日が落ちる頃、わくわくしながら異常気象のニュースを見る。世界はどんどん綻びていく。あるところでは寒冷化が進み、あるところでは地盤が崩落して、私の二年後の暗闇に歩調を合わせるように、世界は滅びていく。 そうだ、滅びろ。みんな苦しめばいい。泣けばいい。 なのにその一方で、生の不安は収まらない。万が一生き延びたとき、私はどうすればいいんだろう。世界は滅びる。その終焉を見守るって覚悟を決めたのに、なぜなんだ。何にも起きなれなければ、自分だけ死ねばいいだけじゃないか。だけどそう考えると涙が溢れて来る。 自分だけ死ぬのは嫌だ。それじゃ負け犬のようだ。みんな死ねばいいんだ。みんなで死ぬんだ。でも妹には死んでほしくない。妹と――いるかどうかわからないけど――その彼だけは助かって、新しい時代のアダムとイブになってほしいなんてことも妄想した。だけどそれもその後の苦労のことを思うと悲しみに変わる。みんな滅んでしまえば悲しみもないのに、だれかが生き延びると考えると、その生活を想像して泣いてしまう。人生ってのは、本質的に悲しみなのかもしれない。 滅びろよ、さっさと。世界。 滅びるって決まってからが長いよ。世界。 結局、ネタなんか出なかった。 それでも、この仕事だけはものにしたかったから、私はうっかり自分のことを書いてしまった。それをラジオで、自分の口で話すなんて思ってもみないで。 「その隣のベッドの子も小児麻痺だったの?」 「うん。それはそう。お母さんにも聞いた」 やっと克服した幼い日の傷を、思い出したくはなかった。 いや、克服なんかしてない。やっと忘れたんだ。それなのに。 「でももう、メルクルさんの障害はほとんどわかりませんよね?」 「ええ、でも、まっすぐ立つと肩の高さが違うし、足の太さも違うんですよ、左右で」 「そうなんですか?」 小学校の低学年の頃、松葉杖が手放せなかった。 四年生から松葉杖なしでも歩けるようになったけど、運動はダメで、歩くときもびっこをひいていた。男子からはいじめられた。いじめがひどくなると、女子も距離をおくようになった。 小学校を卒業して、となりの校区の中学へ通って、高校も県外の高校へ通って、東京の大学に入った頃に障害も目立たなくなり、ようやく過去を断ち切れた。つい二年前の話だ。今も水着は着れないし、夏になっても長袖。スカートもロングしか穿かない。モデルのオーディションなんか糞食らえだし、走ること、ひとと並んで立つことにすら恐怖を感じる。克服なんかしてない。ラジオで話したら、またクラスの連中が嘲笑を浴びせてくる。克服なんかできるわけがない。だけど――メルクルだから。私は岬沙也加じゃない。投稿家のメルクルだから。そう言い聞かせて必至にマイクの前に留まるけど、それでもどんないじめを受けたかは話せなかった。 「まあ、いろいろありましたよ」 「いろいろって、たとえばどんな?」 「まあ、いろいろ」 限界だった。 昔の自分のことを思い出すと死にたくなる。 でも今は違う。死ぬのは私じゃない。みんな死ぬんだ。人類滅亡の日がわかるなら、その前日に私が殺しに行きたい。あの日、まぼろし探偵の替え歌で私を揶揄したクラスの連中全員、死ねばいい。 ――後半は、何を喋ったか覚えていない。 収録が終わるとディレクターが声をかけてくれた。 顔色が悪いけど大丈夫? タクシー呼ぼうか? その声は聞こえていたけど、頭のなかで意味を拾えなかった。 それからどうやってタクシーを拾って、どうやって乗ったか、頭が真っ白になって何も覚えていない。部屋に戻ると、雅文はトランクスにランニング姿で《スターむりむりショー》を見ていた。 背中から抱きついてながめたテレビのなかの由美かおるは綺麗だった。でも彼女だって私のクラスにいたら、あの歌を歌っていた。だれの顔を見てもそう思う。世界中のだれもが、私のクラスにいただれかの顔に似ている。この笑顔は、本当は私のことを笑っているんだ。このひとたちは、みんな。 「どうだった? 収録」 「うん。楽しかった」 親しくなれば心を開くなんてのも嘘だ。 「良かった」 汗に浮いたメイクの上を涙が流れる。 「自分を切り売りしてたら、身がもたないよ」 彼の背中が、私の心臓に声を伝わせる。 それでも私は傷ついてるだなんて、悟られたくなかった。 傷つかないよ。プロなんだから。 「煙草ちょうだい」 彼は咥えていた煙草をつまんで、肩越しに私の口元に差し出してくれた。 煙草を好きになったきっかけ。これもいつか話すことになるのかな。 放送の三日後、菰田さんからの電話。 ラジオ局に《私が探していた子》から電話がかかってきた、と。 ある程度は予期していたことだった。 「松本ディレクターが、《再会編》を録ってもいいっていってるんだけど、どうする?」 私が探していた子。会いたい気持ちと、忘れたい気持ちは半々だった。 名前も知らない彼は、私と同じ苦労をしてきたかもしれないし、そんなこと何も気にせずに乗り越えてきたかもしれない。会えばいろんなことを思い出す。 「このまえの収録、大変だったんでしょう? 松本さんも無理はしなくていいっていってたし、断るなら断ってもいいのよ」 でも、それでも私は顔をつなぎたかった。 この腐って果てていく世界の中で、今日、明日生きていられるのは、いつか私が書いたコメディがだれかに届くと信じているからなんだ。いつかバカみたいに視聴率を取って、ざまぁ見ろっていうんだ。 私はせいいっぱい明るい声を作って、 「もちろんやりますよ」 そう応えて、受話器を置いた。 事前の打ち合わせは、帝国ホテル。 その日のために、三着目のよそ行きの服を買った。 ロビーでの待ち合わせ。 そこに現れたのは、背が低く、杖をついた、顔もすこし歪んだ青髭面の男だった。 落胆した。 彼は柄物のジャケットを羽織って、足元は運動靴。ネクタイは曲がって、ショルダーバッグを斜め掛けにしている。外見だけで何かを判断できるわけはないのだけど、彼がこの外見のせいでいじめられ、卑屈になり、いまも世間と折り合いをつけられずにいることは容易に想像できた。 男は、松本ディレクターの「お待ちしていました」の言葉に、頭を下げた。 「4 古澤幹夫
「ちゃんと卒業できたら、正社員で雇うよ?」 雅文がろくに働かないのが申し訳なくて、私はよくワイルドダックの手伝いに入っていた。その実質的な社長、菰田さんに正社員に誘われて、ここにいればコネも広がると思って、少し出遅れたけど綿密な単位計画を練り始めた。 ワイルドダックはカメラクルーを中心とした会社で、ほかにも菰田さんの伝で企画やマネージメントなども引き受けていた。マーフィの名前を頼って来る仕事も少なくなかった。雅文の手に余る仕事はフリーのライターに回し、憧れの仕事は卒論に集中しなければいけない私の頭上を超えていった。でもいまは大丈夫。このままでいい。私は、卒業後のことを考えて、免許を取った。現場へもたびたび駆り出され、簀巻座という謎の舞踏集団の撮影ではレフ板を持った。 私はほとんど自分の部屋へは帰らず、雅文の部屋に寝泊まりするようになった。雅文は夜遅くまでバーや居酒屋で飲んだ。仕事も学業も充実はしていたけど、慰めて欲しいときに慰めてくれるひとはいなかった。 楠浩二とはその後何度か会って、クリスマスの少し前に告白され、オーロラが美しく舞うイブの夜は、彼と過ごした。 クリスマスの日、部屋に帰ると一人でケーキを食べ尽くした雅文がいた。無精者の雅文がクリスマスの飾り付けをして、私の帰りを待っていた。いままであんまり愛されていた感覚はなかったけど、裏切ってみて初めて、もしかしたら彼も私のこと思ってくれてたのかもしれないと思った。 心から申し訳ないと思った。だからこそ、このまま関係を続けるわけにもいかない。その場で別れようと切り出したけど、 「沙也加は俺の弟子だよ。別れるとかそういう関係じゃない」 といって、腕をたぐり寄せられた。 ――弟子だったらいいか。 煙草の臭いの吐息に咽て、快楽に身を任せながら、今度は浩二になんて説明しようかと考えて、考えて、大海を泳ぎながらの思考はまとまるはずもなく、次の日、浩二に別れ話を切り出して、私って本当にクズだなって思った。 「やっぱり、雅文とは別れられないから」って。 浩二は雅文のような強引さはなく、喫茶店でお茶を飲みながら、じゃあ仕方ないね、自暴自棄にならないでね、って言われて別れたけど、一週間後くらいかな。雅文がいない夜、寂しくなって電話を掛けた。 まあ、本当に私ってクズだなって思う一方で、高校時代の自信のない私ってなんだろうって思った。モテるとかモテないとかはあんまり意識しないほうだったし、気にしないようにはしてたんだけど、そういうのは関係なくって、「ボーリングに行こうよ!」というのと大差ない感覚で関係って結べちゃうものなんだなって。でも、私が変わったってわけでもない。自信がないから人にすがるんだと思う。《あの人に会いたい》の案を考えていた頃の私が見たらどう思うだろう。 ――もう自分で飛ぶことは諦めたの? そう自問しながらも、それからよくいろんな子とボーリングに行くようになった。それが当たり前になると、自分がクズだなんて感覚もなくなっていった。だから正直にいうと、古澤幹夫と会ったときだって、最初に思ったのは、「どうやってこの子を落とそう」だった。 簀巻座のプリマ、中江亜実とはよく飲み明かした。 「ダメなんだよ私、だれかいないと」 このときやっと、親しくなると本音って出るものなんだな、と思った。 「わかるけどさ。マーフィをダメにしてるのあんただって言われてんだよ?」 酒の力も大きい。 「知ってるー。菰田さんもいってたー」 でも、私ごときでダメになるんだったら、最初からそれだけのものでしかなかったんだと思う。マーフィ富樫がダメになったら、メルクル沙也加があとを継げばいい。 その亜実から、千駄ヶ谷で定期的に怪しいパーティを開いているひとがいると紹介され、身ひとつで乗り込んでコネを広げた。煙草とは違う煙の臭いも覚えたし、大人のお薬も口にした。 単位はすこし足りてないのに。学業に専念するなんてこともできなかった。この頃はもう作家になるための活動より、ワイルドダックの一員として飛び回ることが楽しかった。深夜番組にスタッフを派遣し、雅文の台本をチェックして、スタジオを押さえ、機材を保守した。 そんななかで知り合った古澤幹夫はアマチュアバンド、マルコフ・チェインズのギター弾き。飄々としたポーカーフェイスで、超絶なテクニックを見せた。 マルコフ・チェインズの音はガチャガチャして聞くに耐えなかった。方向性もパンクだかヘヴィメタルだかわからない、ヴォーカルにも色気のない、要は取るに足りないバンドだった。そのなかで幹夫だけ、ルックスが良かった。いや、ルックスはともかく、マルコフ・チェインズの味は、彼の縦横無尽な演奏によるものが大きい。音楽性も哲学生もなにも感じさせないバンドのなかで繰り出される幹夫の厭らしい指使いは、音楽というよりはかくし芸だった。 でもこの芸があればこそ、彼らを深夜番組のコーナーに押し込むことができた。彼は左手のハンマリングだけで器用に音を出して、高速でアルペジオを奏でた。 念のため菰田さんに 「うちでマネージメントしても良いですよね」 と確認すると、 「まあ、手始めの実験台としてなら」 という返答が帰ってきた。 彼らにはまだ、バンドとしてのアイデンティティはなく、ただ時々集まって演奏しているグループに過ぎなかった。いまなら古澤幹夫ひとりを引き抜いても、遺恨は残さずに済む。 新宿のバーで、彼に話した。 「あなただけだったら、うちでデビューさせられる。でもほかは無理。それでもバンドでやりたい?」 すこし身を乗り出す幹夫を見て、雅文の部屋に転がり込んだときのことを思い出した。 私はだれかに認められたくて、デビューしたくて、それで雅文にすがったんだ。肉欲はあった。だれかに認められたかったし、男性に興味もあった。もちろん、不安や恐怖感も。だけど恋愛感情なんてなかった。肉欲と、出世欲と、承認欲と、性的な興味と、ライバル心と、胸のなかで混ぜ合わせたら、いつの間にか恋愛感情になっていた。 私の胸の底の肉塊は、幹夫のことも同じだと思っている。またひとを見くびっているのだと思う。デビューをちらつかせたら、彼はなびく。私にすがる。私は認められて、それで私は満たされる。 「沙也加さんは、僕のギターをどう思いました?」 幹夫は燦光に煌めく瞳を私に向ける。だけどこの場合、おだてれば良いのか、正直に足りてない部分を話せば良いのか。その温度感はまだつかめていないけど、おだてるのは苦手だ。 「宴会芸だと思う。まだ色がない」 「色?」 「味がしない。喜びも、苦しみも、悲しみも、何もない。それじゃダメだよ」 思ったことをストレートに口にしてしまうのは学生の頃から。ずっとそうだった。何も考えずに合いの手だけ入れれば済むような話にも、つい真面目に答えて、よく話の腰を折った。 「それでもデビューできるんですか?」 「宴会芸でいいんだよ。テレビに出るのは。本物はもっと別のところを目指す。だから本物を目指すんだったら、テレビなんか選んだらダメ。そうなったら、あなたの音楽はいつまでも見つからない」 それから、どんなバンドが好きか、何を聞いて育ってきたか、しばらく話した。 まだ二十歳になったばかりの彼は、水割りに少しだけ口をつけて、オレンジジュースを頼んだ。 「スクリュードライバーで」 バーテンに声をかけて、 「ちょっとウォッカ入るけど、いいよね?」 幹夫に確認を取ると、 「ええ、ちょっとだったら」 と、おずおずと答えた。 幹夫は音楽を語る。好きなバンド、好きなジャンル、好きなライブハウス。だけどたった三年長く生きただけ私の経験が、彼を遥かに上回った。もちろんそんなものも、三つ上の先輩には遥か及ばないのだけど。 「ロックを聴くようになったのって、何がきっかけですか?」 「ラジオが好きだったから。幹夫は?」 「同じです。中学に入ったときラジオを買ってもらって、それでずっと」 「どんなギタリストが好き? クラプトン? ジミヘン?」 「ああ、どっちも好きです。でもいちばんはリッチー・ブラックモアかな」 「ディープ・パープルの?」 「そうです。あと、エース・フレイリー。キッスの。なんか、自分といちばん似てる気がする」 「ほう! 音からわかるの?」 「ええ、なんとなく」 他にもいくつかバンド名が挙がったけど、概ねハードロック・ヘヴィメタル系。私の趣味とはすこし傾向が違った。 「岬さんはどんな音楽が好きなんですか?」 「サムラ・ママス・マンナってわかる?」 幹夫は首をひねる。 「そこから、ソフト・マシーンに行って、サード・イアー・バンド」 「イギリス系ですか?」 このあたりのマニアックな話が通じる相手はそんなにはいないし、彼もあまり興味は示さなかった。 「そう。あとはデヴィッド・ボウイかな。わかりやすいところでいうと」 プログレ中心に聞いていた私のなかで、ボウイだけは特別だった。当たりまえ過ぎて、あまり口にはしなかったけど、《屈折する星屑の上昇と下降、そして火星から来た蜘蛛の群》は、私の好きなアルバムの五指に入った。 深夜二時を過ぎた頃、店を出てタクシーを止めた。 彼の部屋は善福寺。タクシー代を心配するので、 「じゃあ、うちにおいでよ、代田だから」 そう聞いて「えっ?」と、言葉を詰まらせる、そのリアクションにときめいた。 タクシーの後ろの席で、「彼女がいたらごめんね」と、最初の段階を超えた。 二週間ぶりに戻った自分の部屋からは、私の知らない私の臭いがした。 「興味があったら電話をちょうだい」 名刺を渡して別れて、幹夫からのアクションを待った。 数日後、「バンドの曲じゃなくて、僕の曲を聞いてください」と電話がかかってきた。 渋谷で待ち合わせて、行きつけの喫茶店へと向かう。幹夫は人混みを躱して歩く私を、子犬のように追いかける。 「マルコフ・チェインズってどういう意味なの?」 「マルコフ連鎖っていう言葉があって、そのことですけど、知りませんか?」 「知らない。幹夫くんって頭いいの?」 「どうだろう。知識は狭いけど、それなりには」 彼が東工大に通っているということは、あとで知った。 ライオンという喫茶店で彼のテープを聞いた。彼のヴォーカルは頼りなかったけれど、次々と現れる色とりどりのフレーズには心躍った。それになによりも、歌詞が良かった。宇宙的で、神秘性があって、哲学も感じた。ロック界を見渡すと、ジギー・スターダストだ、ドアーズだ、と何かしら宇宙づいている。彼が好きだといったエース・フレイリーにしても設定としてはジェンダル星から来たことになっている。それと同じ匂いを感じさせながら、その奥には日本語歌詞がもたらす情緒があった。 「この歌詞は幹夫が書いたの?」 「あ、それはマルコフ連鎖による自動生成」 「自動生成?」 幹夫は大学のコンピューターを使って、稲垣足穂の小説から歌詞を自動生成したんだと語った。足穂の《ヰタ・マキニカリス》のデータを入力して、それをランダムに結合させて歌詞にしたのだ、と。 「でも、ランダムって。それで歌詞になるの?」 「プログラムを作って走らせると、コンピューターはずっと吐き出し続けるんですよ。自分でもわかってない文章を延々と。その中から意味のある部分を探すんです」 「足穂を選んだのはどうして?」 「先輩が入力したデータがあったんで。あと、宮沢賢治と、梶井基次郎と、安部公房と……ぜんぶ違う印象の文章になるんですよ」 そういえば、デヴィッド・ボウイも同じような手法で歌詞を書いたと聞いたことがある。それでもランダムはランダムだろうと訊ねると、幹夫はいった。 「人間もランダムな作用で生まれたんですよ。だから小説を切り刻んで、ランダムに紡ぎ直したら、そこから人間が生まれてくるかもしれないじゃないですか。僕はただ、探すんですよ。言葉から生み出された、次の時代の人間を」 なるほど、と思った。確かに、ランダムに吐き出されただけにしては、幹夫の歌詞はまとまりがあった。 「たとえば『宇宙はオレンジの海の骸』って、コンピューターは意味を知らないんですよ。僕が見て、はじめてその意味がわかって、僕の中にもはじめてその映像が浮かんで、それが音になる。そこに生まれるのは違う宇宙なんです」 それからすぐ、菰田さんがワイルドダックをやめて、実家へと帰った。 富樫雅文との間のトラブルだと、噂話で聞いた。男と女の関係があったとか、なかったとか。ひとの噂なんて嘘か本当かわからないし、気にしたってしょうがない。仮に雅文が菰田さんと何かあったとしても、私だって浩二と二股をかけているし、幹夫とも定期的に会って、お互いの欲求を満たしている。それに、菰田さんが実家に帰ったってことは、別れたってことでしょう? そうは思ったけど、 「菰田さんと何かあったの?」 と訊ねて、帰ってきた言葉は、 「おまえだっていろいろやってるだろう」 だった。 悔しかった。悔しがる権利もないけど、悔しいものは悔しい。 「私がどうだろうが、関係ないじゃない!」 ついかっとなって、声を上げた。 「菰田さんがいなくなって、会社がバラバラになったらどうするつもりなの!? 正社員だけで20人いるのよ!? みんな露頭に迷えばいいっていうの!? 雅文が社長をやってくれるの!?」 と、いってもしょうがないことをいって、 「うるさいよ! おまえにとって、俺ってなんなんだよ!?」 と、言われてもしょうがない言葉が返ってきた。 「じゃあ、私はなんなの?」 なんだこの会話。 冷静に考えるまでもなく議論にも何もなってないとわかっていながら止められない。雅文の口から出てくるのも似たような言葉。議論になりようもないから、ほかの言葉をぶつけるしかない。その日はむしゃくしゃして、幹夫に電話を掛けて、幹夫はつかまらず、浩二の部屋に駆け込んで酒を煽った。 「大丈夫? 何かあったら力になるから、ヤケを起こさないでね」 そういってくれる浩二に、 「私、雅文とは別れるかもしれない」 と口走った。 でもそれも口先だけ。ワイルドダックは富樫抜きでは回らなかったし、仕事の話をつないでいるうちに、「またやり直そう」という話になって、断りきれずに殺風景な彼の部屋に戻った。またふたりでパズルのピースを合わせる。私が上になると、テレビの上のポンパ鳥と目が合う。電源をポンと入れると、すぐに画面がパッとつく。それだけの部屋に、私は戻ってきた。 菰田さんがいなくなってから、ワイルドダックの事務方の舵取りは私がすることになった。正社員になって一年が過ぎた頃。たしかに雅文は、作家さんとして使うのは悪くなかった。 幹夫は何かと理由をつけて私の部屋に来るようになった。 連絡もなしに来るものだから、約束がある日は幹夫をひとり部屋に置いてでかけて、そのまま朝まで飲んでいることもあった。 亜実とふたり、三鷹にできたロイヤルホストでビールを煽りながら、幹夫のデモテープを聴かせると、亜実もその歌詞には魅了された。 「幹夫のことが一番好き」 そういうと亜実は、 「ほかのふたりとはどうするの? 別れるの?」 と訊ね返す。 「幹夫を幸せにしてやれる自信がない」 というか、正直にいうと一対一のつきあいが怖い。ひとりを失えばすべてを失う。そこから引き返そうと思ってももう戻れないわけでしょう? 「いや、でも、いまの三股が彼にとって幸せなはずだってないんだから」 「それはそうなんだけど」 自信がないのは事実なんだよ。一対一でちゃんと愛し合える自信が。雅文とも浩二とも、そんなに真剣な付き合いじゃない。別れようって言われたら、ケッとかいって、捨て台詞でも吐いて部屋を出ればそれでいい。でも、幹夫は違うんだよ。なんでこんなに夢中なのか、自分でもわからない。 「男って、どう思うと思う?」 「どう? どうというと?」 「三股かけてる尻軽女から、『ほかのふたりとは別れるから、ちゃんとお付き合いしましょう』って言われたら」 「それ、実質プロポーズだよね?」 「いや、プロポーズまでは行かないんだけど」 「行かなくないよ。プロポーズだよ、それは」 亜実はおどけて笑ってみせる。 「沙也加は結婚に憧れてるんだよ」 「そうかなぁ」 「しかも沙也加のなかにあるのは、彼の煙草を買って帰って、晩ごはんの準備して待ってるような、昭和のお母さん像。古風な子なんだよ、本当は」 「違うよ、それは。ぜったい」 でも、仮にそうであったとしても、そうやって育ってきたんだ。しょうがないよ。あるいは、だからこそ逃げ出したいっていうか。 それで亜実のアドバイスに従って、少しづつほかのふたりとは距離を置いて、精算して、――『自分はもうクリーンだ、昔の私はいろいろあったけどいまは違う』といえるようになってから、ちゃんと告白する――という路線で行こうと決めた。 部屋に帰ると幹夫がいる。 冷めたカレーを食べて、シンクに皿を戻して、テレビを見てる。 うちのテレビは14型のモノクロ。画面が出るまで30秒はかかる。彼は振り返り、「おかえり」って、テノールの声が私を蕩かす。いつか告白するんだと決めたせいか、急にその存在が大きくなった。昨日まで感じなかったときめき。それを隠したくて、そっけなく振る舞って、 「お留守番ご苦労さま。いい子にしてた?」 そう声をかけると、私の体をその腕に絡め取る。 息を切らせた天井の向こうに星空を見たあと、彼を駅まで送って、亜実に電話して、「この調子で行ってみる」とはいったものの、その一週間後には浩二の部屋にいた。 少しづつでいい、急に「幹夫だけだよ」なんていったら、向こうも戸惑うから、なんて思いながら、三股の関係はそれからも続いて、5 ディレッタント
浩二とふたり、絵本のサンプルを持って出版社に出向いた。 編集のひとは彼の絵を見て、「ステキですね」「癒やされますね」といってくれるけど、それじゃあ出版できますか? という話になると色良い返事は返してこない。 「編集長とも相談しておきます」 なんどその言葉を聞いたかわからない。それでも食い下がると、 「これだけ作れるんだったら、ご自身で出版されるのもありだと思いますよ」 などと言われる。自分で出版すればいいんだったら、こんなとこには来ない。 「どんな企画の持ち込みですか?」 「弊社の出版物をお読みになりましたか?」 いえ、今回は準備不足で、ええ、ごもっともです、小さく消え入りそうに相槌を打って、 「ワイルドダックさんは、どういう立場で絡んで来られるんですか?」 そう言われて、まあたしかに、ワイルドダックが絡むのは変だと思った。これじゃあ障害者を食い物にしようとしてる怪しい芸能プロダクションだ。私は運転手だけやって、編集部には顔を出さないほうがいいかもしれない。 浩二の青髭面の顔が鼻水を垂らす。音のするような強いまばたきをしながら、どもった声で、「今日はどうもありがとうございました」と握手の手を差し出すけれど、編集のひとはその手に気づかないふりをした。どこの編集部の反応も似たようなものだった。露骨に嫌な顔をするひともいる。私がそうだったように。 出版社の玄関を出ると浩二は、ごめん、本当にごめんと、涙を流して謝るけど、謝らなきゃいけないようなことは何もしてないよ、浩二は。 泣きながらとぼとぼと歩いた外堀通り。車の音にかき消されながら、《ドン・ガバチョの未来を信ずる歌》を大声で歌った。 事務所に戻ると、ヤクザものが応接に居座っていた。 社長を出せといっているらしいが、マーフィとは連絡がつかず。 仕方なく私が事情を聞いてみると、簀巻座の借金が焦げ付いているので建て替えろ、という話だった。法的にはどんな義務が? とは頭を過ぎったが、そんな話が通じる相手でもなさそうだ。 「いや、でも、いまは社長がいないので、詳しいことは……」 「じゃあ、なんで俺に説明させた!? あんたが判断してくれるんじゃないのか?」 すでに表には警察が駆けつけているが、手をこまねいて中には入ってこない。 「あんたが判断して決済するって、念書を入れてくれ。そうしたら帰る」 私が戸惑っていると、 「警察に来てもらってるんですよ!」 とスタッフが割り込んでくれる。するとその言葉を待っていたかのように、 「民事に警察が介入するのかよ!」 ヤクザものは表に聞こえるように声を上げる。 ――しょうがない。 ドン・ガバチョ大統領には悪いけど、この世界に明日なんかない。 その場をスタッフに変わってもらって、給湯室に行って、包丁を持って、その手が隠れるようにタオルを巻いた。応接に戻ると、私の手元を見てスタッフが青ざめる。ダメだよ、そんな顔したら。バレちゃうから。 「ああ、あんたか、良かった。この女じゃ話にならねぇ。念書書いてくれ、念書」 私の足が、ヤクザものに向かうまでの刹那。事務所は水を打ったように静かだった。時が止まっているよう、って文章では書いたことあるけど、こういうことをいうんだ。私は笑顔を絶やさず、胸の中には不思議な高揚感がある。男がちらと私の手を見る。まくし立てていた言葉が途切れ、私の顔を伺う。 バレたかもしれない。 それでつい焦って、包丁で刺すときに「死ね!」といってしまった。 刃先は男の腹筋に触れるが、男が体をよじらせるとその先端はシャツを裂いて、体の外にこぼれる。切先は赤い。威勢の良かった男が「ひやぁあああああっ」と変な声をあげておののく。 「鳴いてんじゃねぇ! 死ね、クソがっ!」 飛びかかった瞬間、表のドアが開いて警官ふたりが飛び込んでくると、ヤクザものはそのふたりの間をくぐる。 「逃げるなあっ!」 意識することなく、腹から声が出た。 「ひ、ひと殺し!」 警官ふたり、狼狽しながら私の前に立ちはだかる向こう、ヤクザ者の声が遠のいて行く。 「うるせぇ! まだ殺してねぇ! 人殺し呼ばわりすんなら明日また来いやぁ! お望み通り殺してやらぁ!」 心臓の音が聞こえる。耳が熱い。凄まじい高揚感。包丁を握った手がガタガタと震えている。 その後、傷害の現行犯で赤坂署へと連行されて、事情聴取された。被害届が出されたら立件されるらしいが、被害者がだれかもわからず、警官も少し困っていた。事務所のひとがあれこれ手を回してくれたのか、私を迎えに来たのはとある番組の大物プロデューサーだった。 亜実にも話を聞くと、借金で首が回っていないのは事実のようだった。 ワイルドダックと簀巻座とは直接の契約はなかったが、協賛企業を通していくつか接点があった。数ある関係先のなかでもうちが狙われたのは、女性ばかりの会社だからじゃないかと警察の人はいった。 亜実はいつになくしんみりした顔を見せた。劇団員のひとりが覚せい剤で検挙されて、銀行が融資を引き上げて、そこからは火の車。もうどうすればよいかわからないと、被りを振った。 「どうするの?」 と、聞いたら、 「ストリップでもなんでもやるよ。まな板ショーでも、花電車でも」 と、力なく答えた。 「それでもいいの?」 「簀巻座の演出だよ? 服を着てるか着てないかだけで中身は変わらないよ」 って。これだからもう。芸術家ってやつは。 「でも、ストリップはちょっと待って。スポンサー探してみるから。ストリップに行かれちゃうとスポンサーの探しようがなくなる」 「あてはあるの?」 「ないわけじゃない」 これだけの会話で、亜実は察したようだった。 「幹夫くんを裏切っちゃダメだよ」 「うん。わかってる」 わかってるけど、もういいんだ。こんな世界。どうせ壊れてなくなっていくだけ。そこにどんな幸せがあるっていうの。そういうと亜実は、 「私はゆっくりと時間を掛けて、世界を修復したい」 と、静かに漏らした。 それから、簀巻座のスポンサー探しが始まった。 番組のプロデューサー、ディレクターを通して、芸術に興味のあるスノッブな金持ちを紹介してもらって、簀巻座のフィルムを見てもらった。その反応は、浩二の絵本を売り込んだときと概ね同じ。それでも、どうしてもと押すと、みなそろって同じものを要求してくる。そして決まって、要求に応えたところで、スポンサーになってはもらえない。 クソだな、世の中は。 次に紹介された相手は殺そう。 そう決めてしまうともう、惨殺死体候補は現れることはなかった。 でも、簀巻座のスポンサー探しってのも嘘だ。AのためにBをやりたいと強く信じてるときには、たいがい見えない目的Cがある。私はたぶん、芸術がわかる女、そこに魂を捧げる女として自分を売り込みたいだけなんだ。各界の有力者につないでもらって、ホテルのバーで会食して。でもそれも口実か。世界なんか滅びるって、それだって口実だ。生きていく。それも口実。幸せになる。しかり。金持ちになりたい。この世界に君臨したい。ちやほやされたい。服を着てると、嘘を吐かれてるような気がする。 けっきょく簀巻座はストリップまでいかないギリギリのところに踏みとどまり、一部好事家の口コミ人気に支えられて、なんとか糊口を凌いだ。 私はだんだんと、自分の部屋で過ごす日が増えた。 そばにはいつも幹夫がいた。 こんなクズのような私に、幹夫は優しい。 汗をかいたあとの、パイナップルにも似た甘い匂い。ふたりの汗が混じった匂い。 体に変化が現れたのは、それからすぐ。早朝、不意に目が覚めて、そのまま眠れない日が続いた。横になったまま、蛍光灯のひもを見上げて――そういえば小学生の頃、自分のことは男だと思っていたことが胸に浮かんできた。 私は背も高いし、女らしいとこもない。きっとペニスが生えてないタイプの男なんだ。高学年になって、それなりに体に変化が起きても、そういうタイプの男だと思った。遺伝子の話を聞いても、なるほど私の染色体はXXYで、Xが一個多いから女のような現象が起きるんだなと思った。 高校を出て、上京して、それなりに自分を女だと認めざるを得なくなったいまも、自分に女としての機能なんかないと思っていた。自分が子どもを抱いてる姿なんて想像できなかった。それでも万が一にも子どもなんかできたら、認めざるを得なくなるから、気をつけてはいた。それなりに。 毎月の憂鬱が遅れて、二週間、三週間。もしかしたらと思う。だけど、受け入れるのが怖くて四週間、一月が過ぎた。 どうしよう。 何度こうやって蛍光灯のひもを見上げて考えただろう。 そろそろ決めなきゃいけない。自分のことを知らなきゃいけない。妊娠検査薬を買って、もし子どもができていたら……、できていたらどうする? いや、考えたくない。そんなことは起きるはずがない。 六週間。薬局へ行かなきゃいけないと思いながら、薬局が視界に入ることすら恐ろしくなる。明日行くから、今日は仕事に行こう。今日ははずせない会議。今日はひとと会う約束。八週間。 日記をつけておけば良かった。だれの子かわからない。 三人のなか、雅文か、浩二か、幹夫かでいえば幹夫だ。三人のなかだけならそうなる。 そのまま三ヶ月が過ぎる。 もう薬局にも病院にも行きたくない。 仮に子どもができていたとしても、いや、もう確実にそうなんだけど、何も気が付かなかったふりをして、このまま生みたい。 というか、滅びろよ、世界! あと半年で! 「もしかして、来てないの?」 朝方、ひとりで泣いていると幹夫に訊かれた。 ずっと夜をともにしてるし、それは気づくか。 「来てないって、何が?」 「いや、なんでもない。ごめんなさい」 私がとぼけたら、幹夫はそれ以上追求することもなかった。でももう隠せない。次の日、薬局で検査薬を買って、亜実の部屋に行った。 「なんで私の部屋でそれをやるの?」 と亜実は呆れたけど、 「怖いから」 と答えて、もう三ヶ月、あるいは四ヶ月来てないと話すと、彼女は眉をしかめた。 検査はするまでもなかった。 「妊娠してる。どうしよう」 親はだれ? 生むの? 生まないの? そう問い詰められるかと思っていったら、亜実は何も言わずに抱き寄せて、私のかわりに泣いてくれた。 「大丈夫だよ。沙也加のやりたいように決めて。沙也加が子どもを生んで、男たちがみんなそっぽを向いたらふたりで育てよう。だから、決めていいよ。心配しないで。沙也加が自由に」 「三人も彼氏がいたのに、頼れるひとがひとりもいなかった。三人もいるせいで。私が優柔不断なせいで」 「違うよ、沙也加。頼っていいんだよ、三人とも。三人だけじゃなくて、この世界全部、頼っていいんだよ」 「でも」 幹夫には最後に話そうと思った。 まずは浩二に。 もう男と女の関係は終わりだって伝えなきゃいけない。 あの日と同じ、帝国ホテルのロビーで待ち合わせた。 浩二は杖をついて、深いグレーのスーツを着て姿を見せた。 「ごめんね、大事な話があって」 「僕もだよ。ずっと言おうと思ってたんだ」 私が浩二の手を取ると、小さく、枯れた声で、「ありがとう」って聞こえた。 対面でソファに掛けて、バナナジュースをふたつ頼んだ。 話さなきゃ。そう思っただけで涙が出てくる。「子どもができた」そう伝えるだけなのに、もしかしたら今日で永劫の別れになるかもしれない。私がバカだから。何も考えて来なかったから。 「あのね……」 一言目が口に出ると、もう次の言葉はしゃくりはじめた。口を開こうとしても、ただ震えるだけ。 「お腹にね……」 ぼろぼろ、ぼろぼろと、涙が止まらない。 浩二は身じろぎもせずに聞いてくれてる。私の口からは嗚咽が漏れる。二度。三度。収まるのを待って、その隙きに言葉を接いだ。 「子どもがいるの……」 浩二は頷きながら、私と同じように涙をこぼしはじめる。 「うん。おめでとう」 おめでたくなんかないよ。世界は滅びるんだよ。そんななかで子どもができたって。しかも、だれの子かもわからない。 おしぼりを頬に当てて涙を受けた。鼻を通る息が後頭部の痛みになって抜ける。涙に溺れた視界のなか、浩二は前かがみになって、身を乗り出す。 「あの。もしかしたら君はもう、僕のそばを去っていくつもりかも知れないけど、決めていたことだから言わせて」 きれいに髭をそった口元が、ゆっくりと確かめるようにして言葉を並べた。 「僕と結婚して欲しい」 意味がわからなかった。頭の中で何度も繰り返して、主語と目的語を探した。だれが? だれと? まさか私と? 「子どものことは驚いてるけど、それは関係なく。もし君が良ければ、そのお腹の子ともども、僕の家族になってほしい」 私は、声をあげて泣いた。 浩二は私の横に座って、ぎゅっと胸に抱いてくれた。6 啓介
ひとを天秤にかけたくなかった。雅文と幹夫に話を聞いて、それから決めるのは嫌だった。ふたりがどういうかで、浩二への返事を変えたくはなかった。 私は浩二と結婚して、男の子を生んだ。 生まれた子には、啓介と名付けた。 浩二と暮らすようになって、私の乱れた生活もだいぶ収まって、世界の崩壊はどこか遠くの出来事になった。来年の干支の動物がどこそこの動物園で生まれたというニュースに続けて、地磁気の異常と南極の氷床の崩落が伝えられる。 世界のどこかでは戦争が続いていて、食料を奪い合い、とある国では飢餓が多くの命を奪っていった。こうやって少しづつ人口は減っていく。いまの世界人口、四〇億がまかなえなくても、一億なら、一千万ならこの地球で生き残っていけるかもしれない。その一千万は誰かが選ぶわけでもなく、ただ殺し合いの果てに生き残った一千万なのだと思う。そしてその殺し合いはもう始まっている。どこかの商社のエリート社員が、日本のために買い占めた食料で、どこかの国は飢饉に見舞われ、内戦が置きて、人が死ぬ。 どこかの神社に奉納された草鞋、市民の清掃ボランティア、世界の滅亡。そうやって緩やかな死が生活の中に織り込まれていった。 私は啓介が生まれてから不味くなった煙草をやめてしまった。 亜実がいったように、私はお母さんになりたかったのかもしれない。でもうちでは、浩二がお母さん業の半分をこなすし、私の仕事も相変わらず、クレイジーな働き方は良し悪し併せてお父さん的。ワイルドダックはすこしだけひとが増えて、私は社長になって、仕事はハンコと飲みが中心になった。 気がつくともう、アンテナも延ばしていない。 「岬さんは懐メロしか聞かない」 新入りのスタッフがそう囁いては笑う。 啓介が三歳になるころ、千駄ヶ谷の木村さんから「こんど幹夫くん、《江戸のバカ》のライブで飛び入りで演奏するで」と聞いて、何年かぶりにライブハウスに出向いた。 昭和58年、6月4日。吉祥寺。 ライブ会場で亜実の姿と、幹夫の姿をみつける。 親友、中江亜実も私に似たクソだった。あれこれ注文をつけて、幹夫にも注意を促して、でもたぶん、このふたりは付き合うことになるだろうという、妙な確信があった。 なぜなら、亜実も私と同じように、彼の詞に惹かれていたから。 ――彼の詞からは違う宇宙が生まれる。 私も亜実も、それを信じていた。 幹夫の出番は後半。それまでは客席の後ろで人熱れに体を温める。休憩の時間を終えて、私が化粧室から戻るころには、幹夫と亜実の距離は半分に縮まっていた。 やれやれだな。いくつになっても幹夫はネンネだから、クズにばっかり引っかかるんだよ。 幹夫は出番に備えて、三度笠をかぶって息を整える。 「地蔵に赤いはちまき。それは、隠密同心集合の合図である」 リードギターのMCとともに後半の幕が開け、幹夫がステージに上がる。 そういえば、いってたよね、亜実。 ゆっくりと時間を掛けて、世界を修復したいって。 あのときはピンと来てなかったけど、幹夫とならできるよきっと。 だから幹夫、亜実を宇宙へ連れて行って―― それからわずか3ヶ月。 昭和58年、8月27日、ふたりは宇宙へと旅立った。7 屈折した星屑
通い慣れたライブハウスは、壁のポスターまですべて頭に入っていた。 昨日はなかったポスター、はじめて見るフライヤー、それも連続した時間の中で目にすると音を奏でる。Vo、Gt、Ba、Dr、並んだ名前から音の傾向を探る。まだ音楽プロデューサーのまねごとをしていた頃。営業で訪ねた静かなホールにも、いろんな音が鳴り響いていた。 啓介が生まれて足が遠のいていたライブハウスは、フライヤーもポスターも刷新されて、もうあの頃の音楽は聞こえなかった。新しい世代の、新しい音楽、聞き知らぬ奏法の曲がグルーブを疾走らせる。過ぎた日の笑い声を木霊に聞くような懐かしさと、そこに紛れたかすかな疎外感。 開演前、幹夫と言葉を交わす。 あの頃と同じ、他愛もない話。 ふたりの目の前の果実が、何も言わずそれを聞いている。 静かなイントロから、一曲、二曲とプログラムが進む。 前半のセットを終えて、休憩時間に入ると、狭い化粧室の前には人の列ができる。 見知らぬ友だち同士のお喋りが、聞くともなく耳に入る。 ――ギターかっこ良かったよね ――あれ、ライト・ハンドでしょう? ヴァン・ヘイレンがやってるやつだよね そう。ヴァン・ヘイレンで一躍有名になったライト・ハンド奏法。でも幹夫のほうが少しだけ早いんだよ、ヴァン・ヘイレンより。 人生にはいろんな可能性があった。あのまま幹夫をプロデュースすることもできたかもしれない。だけど、私は私の人生を選んだ。いや、選んだんじゃない。無数の私が絶滅して、いまの私ひとりがなんとか生き延びた。だから、後悔はない。この生き延びたたったひとりの私に託すしかない。 トイレのドアを閉めると、喧騒はマイナス3あとがき
この作品は、公開順はどうなるかわかりませんけど、僕が小説らしい小説を書いた5本目の作品です。最初は『余命3時間のスーパーハッカー』というタイトルで、元軍人の老人と、余命3時間のスーパーハッカーが、国分寺の拠点から六本木の人工睡眠塔を目指すというバディものでした。……こうやってログラインを書いてみると、これで仕上げても良いかなって気はするんですが、正規軍と反乱軍が戦っている中を3時間で国分寺から六本木へ、というのは、どう書き直しても無理がありました。 そこで書きたかったのは、記憶もおぼろになった老兵が、外部記憶装置とかすかな自我を頼りに正規軍の不正を暴くという、夢も現実も分けようのない世界のお話でした。プロットをいじっているうちに、相棒の余命が18時間だったら成立することがわかったものの、『余命18時間のスーパーハッカー』だと、いまいち面白みがない、と、今にして思えばわりとどうでも良いことで悩んだ挙げ句、昭和の宇宙旅行のお話に変えてしまいました。要は、夢と現実とが不可分で、自分がいま夢を見ているのか現実を生きているのかわからない話を書きたかったのです。それにプラスして、別にもうひとつ、宇宙移民先で法律を作るお話が書きたくて、そちらと融合する形で仕上げました。 設定が少し飛び抜けているので、そこを自然に見せるために、できるだけリアルに、大人の物語に仕上げようと思ったのですが、写実主義~自然主義で書くと、どうしても大人の肉欲的な話を避けられず、そこには嫌悪感がありました。 物語中には、比喩的に、もしかしたらこのシーンはこういうことをしているのでは、この人たちはこういう関係では、と感じさせる場面があると思いますが、書いている方としては、蜂蜜は蜂蜜、花弁は花弁としてそのままのイメージで読んでもらって構わないというスタンスです。あるいは逆に、蜂蜜が比喩なら、あるいはオーロラや宇宙、人工睡眠だって比喩かもしれない、という受け止め方もできますし、その間のどこに視点を据えるかは読み手に委ねたいと思っています。 それにしてもこの、昭和58年という設定には苦労しました。主人公の古澤幹夫は昭和30年生まれの設定で、僕より10歳年上にあたります。なので、『遠足でおやつを分けてもらった』と書いても、僕の体験とはずれるんです。自分の体験ではおやつの定番はノースキャロライナキャンディやカールや森のどんぐりやダイナミンツなどになるのですが、10年遡るとそのあたりのお菓子ってまだ出てないんですよ。黄金糖やミルキーしかなくて、他にはたぶん、僕の地方だと黒棒や丸ボーロ、レモンケーキなどがおやつの定番だったように思います。しかし、果たしてそれを遠足に持っていくのか。 平成5年の宇宙移民にすれば幹夫は僕と同い年になるし、ずいぶん書きやすかったと思うんですが、タイトルに付くのが昭和か平成かでは、雰囲気ががらっと違いますよね。『平成5年』といえば、今につながる30年間の時代の初期、そこから新しくなにか拓けてくるイメージですが、『昭和58年』は、それまで背負ってきた昭和という時代の総決算的なイメージになりますよね。 そこからちょっと進めて59年になるとオーウェル先生や村上春樹先生の作品と重なってしまうし、60年を超えると昭和の終末感が濃くなりすぎる、57年よりも遡ると僕のイメージがどんどんあやふやになる。ということで、ぎりぎりイメージが固まりそうな58年に定めました。58年でしたら、僕もリアルで18歳ですし、ちょうどアニメーターを目指し始めた頃、アンアンやノンノ、たまに流行通信を買うようになって、おおた慶文や鈴木英人や永田萌といったイラストレーターに憧れを感じていた時代、と、記憶の隅に残っていることもあれこれありました。 ちょうどファミコンが発売された年。小学生の頃から親しんだタイムボカンシリーズの7作目、イタダキマンが始まり、また、終わった年です。フジテレビは「楽しくなければテレビじゃない」というキャッチフレーズを掲げ「軽チャー」路線に舵を切り、オールナイトフジを皮切りに男性向け深夜コンテンツが充実してきた時期。経済成長も終わり、バブルが始まる前。この先また成長に転じるのか、ここから下るのかという踊り場だったと思います。白物家電の普及率がほぼ一〇〇%に届き、物質的には満たされ、商品には『付加価値』が求められるようになり、新たな意味や新たな価値が求められる中、それまでの文化をメタな視点で再解釈しながら、社会全体がサブカルチャー化して行った時代。日本の社会は、その頃に肉体を完成させ、精神的な成長へとシフトさせて行きました。その分かれ目となるのが昭和58年なのだ、と大胆にもここでいい切っておきます。 この作品のルーツを探れば、人工冬眠中に見た夢の話はどこぞにあった気がしますし、宇宙の味云々は稲垣足穂的でもありますし、古澤幹夫という同名の主人公を使い回すところなんか、ガルシア・マルケス的な匂いもあるかもしれません。あるいは全体に漂うドゥルーズ&ガタリ感。 「じゃあ、この作品の最大の特徴は?」 と、問われるとやや不安になるところはありますが、自分としては、実はバーチャル・ガバメント・ネットワーク端末VGNが作品の核ではないかと思うのです。それをいうと学生時代の恩師も、漫画を描いていた頃の編集の人も「だったらそこを中心に掘り下げるべきだ」というような気がしますが、いいんです、これで。VGNに関しては、この塩梅が僕の書きたかったものなんです。 僕が書くものの特徴として、スロースタートでどんどん速度が上がっていって唐突に終わる、というのがあるのですけど、今回のもそんな感じです。第8章の駆け足ぶりは、自分で読み返してもこれで良いのかしらと思うのですが、中江亜実と古澤幹夫の話を宙ぶらりんにしたままここを膨らませるわけにもいかず、じゃあ書かなきゃいいじゃないかといわれると、だって書きたいんだもんとしかいえず、こんな形で割り込ませてしまいました。 と、そんなわけで、あとがきもまた唐突に終わるのですが、最後になりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。 では僕は、宇宙を修復する仕事に戻らなければいけないので、これで。
©sayonaraoyasumi novels
この作品の著作権は井上信行が有しています。著作権者の許可なく複製、配布、改変することを禁じます。
This work is copyright 2023 Nobuyuki Inoue. It may not be reproduced, distributed, or modified without permission of the copyright holder.
This work is copyright 2023 Nobuyuki Inoue. It may not be reproduced, distributed, or modified without permission of the copyright holder.
| 著者 | 井上信行 |
| 出版 | さよならおやすみかぶしきがいしゃ |
| 出版日 | 2021年 9月 25日 |
| 使用ツール | でんでんコンバーター, VSCode, PowerPoint, PhotoShop |
| HOME PAGE | https://sonovels.com/ |
⚪
🐹
🐰
🐻
⬜