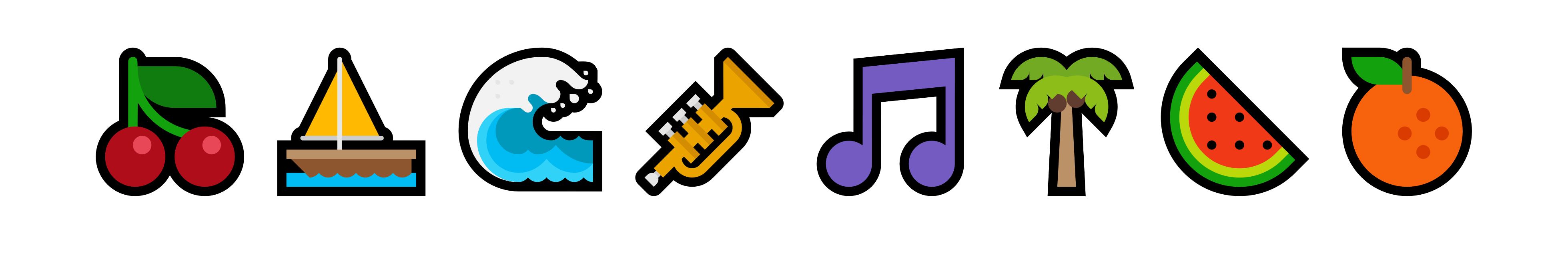- 第一部・アクロス・ザ・ユニバース
- 一・タイムパトロール隊がある通学路
- 二・伝説の視聴覚教室ライブ
- 三・迷える高校生活
- 四・消えた思い出
- 五・ラ・カルナバル
- 六・若気の至りバスターズ
- 七・小さな恋のメロディ
- 八・尻出しゲロゲロ魔王
- 九・あいつが消えた夜
- 十・アクロス・ザ・天神
- 第二部・フル・スチーム・アヘッド
- 十一・照和
- 十二・変態七拍子
- 十三・夢見るセラミック人形
- 十四・あの日にかえりたい
- 十五・亜璃朱の飛行船
- 十六・双子の鳥
- 十七・メカニック兄ちゃん
- 十八・パッションブラッド・リバイバル
- 十九・ロック・ミー・ナウ
- 二十・フル・スチーム・アヘッド
- 第三部・レッツ・ドゥ・ザ・タイムワープ
- 二十一・僕たちの世界
- ボーナストラック
- アンコール
- あとがき
第一部・アクロス・ザ・ユニバース
一・タイムパトロール隊がある通学路
高校へ通う道の途中に、タイムパトロール隊の事務所があった。 ガソリンスタンドの五叉路を斜めに入って二つ目の信号、小さな雑居ビルの三階。 別名、タイムパトロール・ぼんクラー。昨日も隊員ふたりが福岡空襲跡地に侵入、逮捕されたとニュースで流れた。 親友の田村に聞くと、 「銀河連邦のなんとかって組織に属してて? 時間の流れを乱す? 異界のなんたらと戦ってる? らしいよ」 と、首をひねりながら教えてくれた。 彼ら曰く―― 『時の流れが狂ってる。本来なら空襲跡地には天神コアやアクロス福岡、天神イムズといった近代的なビルが立ち並んでるはずだ』 ――って。 まあ確かに、戦後八十年も経つんだから、本当はそうやって発展していてもおかしくはない。だけどかつて天神と呼ばれたあたりには、いまだに瓦礫の荒野が広がっている。 僕の名は、古澤幹夫。 古澤の澤は難しい方の字だけど、小学校の頃から『沢』でいいと教えられているので、いまでもよっぽどのことがない限りは『古沢』としか書かない。小6のとき、沢の字の『尺』を左下から上にのぼって折り返せば、さんずいからそのまま一筆書きで書ける事に気がついた。得意になって姉に言うと、 「古の字は口から書くと、古沢ぜんぶ一筆で行ける」 と返されて、さすがは姉だ、と思った。 だけど、そうやって書いた文字は兄の字に似ていた。 僕には双子の兄がいた。 字が下手で、言葉も下手で、計算もうまくできなくて、ずっと隣のクラスでからかわれていた。僕と同じ顔の兄がからかわれるのを見るのは辛かったし、いたたまれなかった。それに、僕もたまに辛く当たった。 中学に入ると、兄は《見えないクラス》に通うようになって、僕は胸をなでおろした。これでもう兄の不憫な姿を見なくて済む。学校へは母が車で送り迎えする。もう僕が手をつないで登校せずに済む。やっと開放されたんだ。そのときの気持ちはいまも胸の底に沈んでいる。 ちなみに高校二年。趣味はギター。軽音楽部。まあ、どうでもいいか。 午後、まどろんだ運動場に響くボールの音。それに続く歓声。きっとだれがいちばん美しく金属バットを鳴らせるか競争しているのだと思う。それは高校生の最も美しい瞬間でもあった。 僕は六時間目、歴史の授業。 秋山さんの、気怠げに顔を覆った横顔を眺めていた。 「……が見ていた景色には、ちょうど高良内ニュータウンから高速に向かうあたりの……」 首を振って、 「……あるいは高良川あたりの、まばらな町並みが広がっておったんだねえ」 頷く。 秋山さんも自分の居場所のない、自分の世界の住人だった。 親友の田村とふたり、校門を出て長い影を引きずる通学路。 「アクロス・ザ・福岡?」 「いや、ザはいらない。アクロス福岡」 「よく覚えてるな、あいつらの言ったこと」 「うん。なんか、聞き覚えがある気がして」 ――なんとなくだけど、天神コアも、天神イムズも、なんか聞き覚えがあった。 「それはあれだ。おまえもあっち側のひとってことだ」 「は? なんでそうなるの?」 「ちわー、タイムパトロール隊でーす! 時間の歪みを直しに来ましたー、っつって」 「三河屋かよ」 「本当の世界では、僕はあなたとおつきあいしてましたー! 僕とおつきあいしてくださーい!」 「なんだそれ」 興味なさげに切り捨ててはみたけど。もしかして田村は知ってるんだろうか。僕が秋山さんのことチラチラ見てるの。 「あと、でっかいドーム球場があるらしいよ。あいつらの話が本当なら」 「球場って? クラウンライター・ライオンズの?」 「いや、大洋ホエールズ」 「わけわかんない」 でこぼこの舗道。田村のチャリは低速でゆらゆらと傍らを走る。 「でもタイムパトロールってことは、だれかがタイムスリップしてるってことだろう?」 「そうなるよね」 「できるの? 時間移動みたいなこと」 「普通に考えるとできないよね」 「だろう? だろう? だろう?」 人差し指で三回指差す田村。うざい。 「でもさあ。てことは、だよ」 「てことは?」 「普通に考えなきゃできるんだよ」 「あ、そうか」 と、田村は一瞬だけ納得しかけるが。 「あ、いや待って。普通に考えなければできるの?」 「できるだろう。対偶だから」 「はあ? じゃあさあ、俺、子ども産めないよね、男だから。普通に考えたら」 「そうだね」 「普通に考えなかったら産めるの?」 「産めるだろ」 「それって、考えただけで変わるの?」 「まあ、論理的には」 「論理? 論理なんか?」 という田村の疑問符の背後、夕日が落ちて夜になって、朝になった。 「で? 学園祭の曲は決めたの?」 田中先生はクリームパンを小さくちぎって食べながら聞いてきた。 「ボカロ曲にしようと思います。いちばん盛り上がりそうなんで」 軽音楽部顧問。自称、ショパンの小間使。 「ボカロっていうと、千本桜とか?」 「古いですね、先生」 「そりゃあそうよ。専門は十九世紀だから。むしろ新しいくらい」 「そのうち出ますよ。ボカロ曲でショパンコンクールに優勝する奴」 「そうね」 流された。 「ちょっと弾いてみて」 先生はクリームパンの最後の欠片を口に放り込んで向き直った。 「何がいいですか?」 「何が弾けるの?」 「美人教師@水泳教室とか、レディオアクティビストとか」 「わかんない。ノクターンで」 「ノクターン?」 「ショパン」 「ギターで?」 「ピアノでお手本弾いてあげる。真似して弾いてみて」 ノクターンと言われてもピンと来なかったけど、音を聞いたらわかった。とりあえず、つまづきながら追いかける。 「ショパハラですよ、これ」 「オリジナルはやんないの?」 「痛いだけですよ、オリジナルなんて」 ピアノを弾きながら僕に向けた先生の目。 「挑戦しないで流行りものを追いかけてるだけの若造が痛くないとでも?」 厳しいなぁ、田中先生は。 今日、あるいは明日、あるいは昨日には意味がある。でも、翌日って言葉にはあまり意味がなかった。僕の暮らしには特別な日がどこにもない。翌日ったって、その続き。昨日と今日とで教室を比べても変わりはない。僕らが帰れば、水洗便所のようにまたきれいになる。 それに比べたら職員室は田舎の汲み取り便所だ。匂いも糞もこびりついている。 その職員室で―― 「うんこうんこうんこ ぶりぶりーぶりぶりーぶりぶりー」 中村先生は僕の詩を音読した。 「まあ、こういう詩があってもいいとは思うんだよ、わたしは」 「そうですか? 僕はないと思います」 「じゃあなんで書いたんだね」 「うんこと煙草のヤニは同じ色だなって」 「だったらそれを書くのが詩だろうが」 「わかるひとはわかってくれますよ。それが詩ですよ」 「違うな。みんな真面目に書いてるのに、おまえだけだぞ」 そういって先生が指し示した藁半紙の束の一番上に、秋山悠子の名前があった。そこにあるのは授業で書いた『詩』。しかも、秋山さんの。とたんに動揺する。 「いやー、だって先生、授業で詩って。みんな、どんなの書いてます?」 読みたい。秋山さんの詩を読みたい。先生。秋山さんの。 「たとえばだなぁ……」 選ばなくていい! 一番上の! 「あーもう! ぱっ! と、これ! っつって、一番上の!」 「ああ、これか。本人に言うなよ。読んだって」 「わかってます」 両手に受け止めた藁半紙は、名前の部分が折り曲げられていた。 だけどそれはすぐに秋山さんの声で歌い始めた。 ――タイトル、赤い花。♪
赤い花が 咲いたの いつも見てた 裏土手 背の高い 緑の 影に隠れて ドアをあけて 呼んだの 赤い花 咲いたよと 雨上がり 青空を 眺めているよ 恋心 みたいに 胸の中に しまって 洗濯物 ほしたの 水溜りの上 しあわせは たくさん あふれては いるけど だれにも 届かない 赤い花ひとつ 卒業式の帰り 自転車押すあの子と 4年後に またねと 約束をした しあわせは たくさん あふれては いるけど だれにも 届かない 赤い花ひとつ♮
このときの気持ちをどう表現すれば良いかわからない。 胸の中にメロディがあふれて、止まらなくなった。二・伝説の視聴覚教室ライブ
僕がグラミー賞を獲ると豪語するようになったのは、それからだった。もちろんグラミー賞なんか本気じゃない。秋山さんの書いた詞で歌いたい。それだけ。それにグラミー賞は万能だった。古澤幹夫はグラミー賞を獲る男だ。大学には進学しない。専門学校だろうがアルバイターだろうが音楽はできる。無茶も、傲慢も、自堕落も、すべてグラミー賞が正当化した。 そんな折だった。 「やらかした」 田村が顔を歪ませてスマホを僕に見せてきたのは。 「やらかしたって、何を?」 「リアル住所バレた」 ツイッターのタイムラインには、デフォルトアイコンのアカウントから送られてきた田村家の写真が並んでいた。 「バレたって、だれにバレたの?」 「わからん。こいつ。プロフ見てもよくわかんね」 「ていうか、なんでよ」 事情は複雑なようで単純だった。 好きなアニメを批判してるアカウントにウザ絡みしているうちに住所を調べられて、写真を晒されたらしい。 「それ、訴えればいいんじゃないの?」 「そうなんだけど、訴訟って未成年でもできるの?」 「わかんない」 「親にバレたくないし」 まあ、そりゃそうか。 僕のタイムラインからも、田村のウザ絡みのツイートは見ることができた。改めてログを読んでみるけど…… 「これは怒るよ、だれでも」 「まあな。でも煽ってんだから、怒るのが正解でしょ」 その才能をドヤられても困る。 「でもさあ、これ」 「あー、それはー」 「ニーチェの言葉を引用って、おまえ……ろくに知りもしねぇくせに……」 「あーあーあー、聞こえなーい」 ――これは痛いわw ――リプつけんな ――絵に書いたような大失態wwwwww ――草生やすな それからだった。 僕と田村のタイムラインに『若気の至りバスターズ』の広告が流れてくるようになったのは。 「親友がいたんだよ、池田っていう」 「いつの話?」 「小学校」 「で?」 「そいつ恋愛のこととかさっぱり興味なくて」 「あー、いるいる」 「好きな子がいるって教えたら、それからずっとからかわれるようになって」 「それで」 「絶交した」 「好きな子と?」 「いや、池田と。好きな子とは結局話せずに終わったけど」 「あー」 田村はチャリを漕ぎながら、ニヤニヤと次の言葉を待つ。 「僕、あいつと一生絶交したまんまなのかな」 「知らねえけど」 そこで少し途切れた言葉の先を、今度は僕が待つ。 「告白するの?」 いきなり図星かよ。 「相手は権丈?」 「はあ?」 なんでそうなるのかな? 「なんか、ずっと見てるから」 権丈を? 僕が見てるのは、その先の席だよ。気づけよ。 「よりによってゴンはないよ」 「いや、わからん。おまえのことだから」 告白っていろいろだと思うんだよ。コンビニで万引しましただって告白だし、じつは宇宙人なんですだって告白だし。でも高校生が告白っていえば、「好きです」ってことだろう? 告白=好き。告白なんかしない最初からオープンな好きってないのかな。 「どう好きなんだろうって思う」 「なにが」 「中三のとき、谷光さんのことが好きだった。そのときと、どう違うのかな、って」 田村はチャリのブレーキをカチャカチャと鳴らした。左右交互に鳴らして、口笛まで吹いて。 「なにその音楽」 田村は首をひねって、口笛を続けた。 タイムパトロール隊の前を通りかかると、デジタルサイネージにニュースが流れていた。 『逮捕されたのは、タイムパトロール隊久留米支部所属・八重樫浩一――』 久留米支部という言葉に、僕と田村は足を止めた。 「ここじゃん」 「ここだね」 八重樫浩一とテロップの入った犯人はカメラに向かって吠えた。 『福岡大空襲跡の中心に、伝説が眠っている!』 モニターの一瞬暗くなった画面に田村のニヤけた顔が映る。 「ないわー」 「ないよねー」 モニターの向こうの八重樫隊員は表情を崩さずに続けている。 『ショウワだ。ショウワがあるんだよ!』 ショウワ……? 「ショウワっていうと、元号の?」 「だろうね。一九四五年に廃止された最後の元号」 「おまえよく年まで覚えてるな」 その田村の納得したようなしてないような顔の背後、夕焼けは一気に焼き上がり夜になり、朝になった。 学園祭ライブで、一曲だけ最後にオリジナルをやりたいと伝えると、下級生がくすくすと笑った。 「言うと思ってました」 「YouTubeに公開してるやつですか?」 「公開してるのって……」 どれだろう。 「犬が交尾してた、って奴」 あ、それだめ、やばい奴。♪
犬が交尾していた 犬が交尾していた 僕は逃げ出した 逃げてひとり泣いた 犬が交尾していた 犬が交尾していた 僕は逃げ出して おかずにして泣いた 甘い声を胸に 思い出して泣いた♮
「いや、あれはない」 「あれ、好きなのにー」 「でもあれ、ほら、若さゆえの過ちだから」 再生回数はそこそこだったけど、一時の気の迷いっていうか。 「でもそれが先輩じゃないですか」 「どんなだ」 「犬ってだれのことですか?」 「えっ?」 「先輩のクラスのひとですか?」 「いや、犬だよ。だれのことって、何?」 「田村先輩から聞いたんですけど……」 「あ、待って、なんで田村から?」 「ゴンっていうひとのことチラチラ見てるって」 見てねぇよ。 それにしても、地球が回っていることと宇宙が回っていることは、どうして等価じゃないんだろう。相対論的には同じっていうけど、運動エネルギーは違うだろう。 「先輩はあれですか? 清純な女子が好きとかですか?」 なにそれ。目の前に清純な女子と不純な女子がいたら清純な方に惹かれるだろうけど、 「清純とか不純とかの基準ってなに?」 というか、なんでこの話になったんだっけ? 後輩が脱線してるすきに、学園祭でオリジナル曲を歌うことは決まった。決めた。そのオリジナル曲は歌詞を公募することにした。それも決めた。ワンチャン秋山さんが応募してくれるかもしれない。 「じゃあ、チラシとポスターを作らないとですね」 ああ、うん。 それから地球が一二〇度ほど回るころ、チラシの案を練った。 ――あなたの言葉を歌にするチャンス! 違うな。 ――作詞家への登竜門! これも違う。 ――最優秀作は古澤幹夫がステージで歌います! これも。 ――秋山さん! 僕はあなたが大好きです! まあな。そう言いたいのはやまやまだけど。引くだろ、それ。 という、数々のクレイジーな案を押しのけて、最後にはわりと普通のコピーを選んだ。 愛するひとへ。 あなたの言葉を貸してください。 僕にはメロディしかありません。 でもそれを見るなり、後輩たちは「キャー」という奇声を発した。 「告白じゃないですか、これ」 「ぶっちゃけこれを歌詞にしちゃうのじゃ駄目ですか?」 いや、待って、ちょっと照れくさい。 「いいから、各クラスに配ってきて」 「愛するひとへ――」 「読むな」 「恥ずかしいです、先輩」 「いまいちばん恥ずかしいの僕だから」 チラシを各クラスに配って、部室前に投稿箱を置いた。 一週間の期間を過ぎて、投函されたのは一通だけだった。 「たぶん、先輩のクラスのひとだと思います」 「えっ? 見たの?」 「投函するとこは見てないけど、赤い腕時計してる……」 秋山さんじゃん! 「髪型は?」 「めっちゃ食いつき良くないですか?」 「あ、いや、ええっと」 その日は特別だった。それから学園祭という特別な日まで、やっと地球の自転に意味が生まれた。いままで何のために回ってたんだ、地球。 学園祭当日。 体育館や講堂は使えず、視聴覚教室が僕たちのステージになった。 小さなステージの上から、秋山さんの姿が見えた。来てくれたんだ。やっぱりあの詞は、秋山さんが書いたんだ。 わざと起こす小さなハウリング、プラグノイズ。昨日の夜練習したMCから、セットリストに入る。 ――ボカロ曲は盛り上がった。 BPMを上げれば上げるほどに客の熱気が上がっていく。 ほとんど早口言葉のようになってしまっているのに、ちゃんと歌ってるひとが何人もいる。三曲目、秋山さんも笑っている。四曲、五曲とレパートリーを披露する。 行ける。これなら。湿度計が僕たちのテンションを示した。 「えー、次の曲で最後になりました」 「ええーっ!?」 観客は声をあげるが、嬉しい悲鳴だ。 「最後はオリジナル曲をやります」 ざわつく観衆。だけど全員の鼓動はひとつ。 「歌詞は、みなさんからの公募で決めたものです」 ステージに注がれる期待の視線。この熱気、醒めないうちに―― 「聞いてください……」 秋山さんに捧げるこの曲―― 「桜田門でもう一度」 ――最初はA。ダウンストローク。♪
世間知らずのキミひとりで――♮
――そして、D。♪
ポウハタン号に向かったとき♮
――ドラムのフィルインから、一気にギヤを上げる。♪
ふりしきる蝉の声に ひるがえる星とストライプ 頬に涙して訴える 八十八士の同胞に 背を向けて心無い 裏切りの条約にキミはサインする ボクの胸の中 せめぎあう 井伊直弼と 悪いナオスケ 通商条約 ただ一つが 答えなんて 信じられない 桜田門でもう一度 ふたりの気持ち 確かめたい 反対派 処するキミに ボクの思い 届けてあげたい ボクは直訴の訴状を持ち 同胞たちの先頭に立つ 少し濡れた春の雪が 水戸藩浪士のマゲに積もる とどろく銃声を合図に ボクはしずかにカタナを抜く 護衛の群れかきわけて キミをめざしてボクは土を蹴る ふたりはもう 引き返せない 桜田門に 来たんだもん 通商条約 ただひとりで 結ぶなんて 信じられない 桜田門でもう一度 ボクの気持ちを 打ち明けたい 血だらけで 逃げるキミの 白い首に ささやいてあげたい 桜田門でもう一度 ふたりの気持ち 確かめたい 反対派 処するキミに ボクの思い 届けてあげたい♮
Let me hear you!♪
桜田門でもう一度♮
――観衆の歌声が響く。♪
ふたりの気持ち 確かめたい 反対派処するキミに ボクの思い 届けてあげたい♮
――バスドラを唸らせ、もういちどギヤをトップまで上げる。♪
桜田門でもう一度 ふたりの気持ち 確かめたい 反対派 処するキミに ボクの思い 届けてあげたい♮
調を変えてどこまでもどこまで駆け上がる長い長いロングトーン。幾重にも刻んだアウトロ。腕を振り上げてフィニッシュを決めると、狭い視聴覚教室が拍手と歓声の渦に呑まれた。 「ありがとう、みなさん!」 汗が髪を伝う。 「えー……」 ざわめきは醒めやらない。 「この歌詞を書いてくれたひとが、客席にいると思うんだけど……」 改めて教室を見渡すが、秋山さんはいない。 「ええっと……」 次の瞬間、ひとりの女子生徒が駆けてきてステージに上がった。 僕のマイクを奪う。 「二年三組、権丈弓子です! 桜田門でもう一度、いかがでしたかーっ!」 ゴン!? 「この歌詞はわたしが書きましたーっ!」 おまえだったか!三・迷える高校生活
世界中多くのひとが地動説を信じていると思う。だけど地球儀を見てどっちに回ってるかすぐに答えられるひとは少ない。僕のカンでは、7割くらいは間違った方を答える。ましてや日蝕の影がどっちに動くかなど、並の人間に答えられるわけがない。日蝕は関係ないけど、この際それも関係ない。 「やられたよ」 田村が言った。 「今度はやらかしたんではなく?」 「えっ? なに? 2回めなの?」 僕の隣でゴンも聞いていた。 「文化祭、親父も見に来てたんだよ」 「ほう」 なんだ、ほのぼのとした話じゃないか。 田村はクラスで催した『ゾンビのスパゲッティ屋さん』でゾンビのウエイターをやった。ゾンビ映画を見ながら、ゾンビが運んできたスパゲッティを食べながら、ゾンビ映画を見る。ホラー映画好きの前原くんのアイデアだ。 「お父さん、スパゲッティ食べてったの?」 そう聞いたのはゴンだった。 「うん、まあ、顔は合わせないようにしてたんだけど……そのときのだと思う」 「そのとき! ゾンビ田村が目にしたものは! だだーん!」 ……乗ってこない。 田村がバツの悪そうな顔で見せてくれたのはツイッターのタイムライン。親父さんのインタビュー動画がアップされていた。 「なにこれ」 ゴンが笑いをこらえながら、鼻の下に指を当ててたずねる。 「なんか、田村の身辺情報を探ってアップしてるやつがいるんだって」 僕も笑い話にしようかと思ったけど、視界の隅の田村は憔悴していた。僕のリアクションが遅れ、ゴンも笑顔を潜ませた。 「どうするの? 訴える?」 「無理」 インタビュー動画の最後、インタビュアーの「この動画、ツイッターに公開してもいいですか?」の声に、田村の親父は快くOKを出していた。 「なんでOKしてんだよ、も~!」 田村の泣きそうな声。そう装ったのか、本当に泣きそうなのか、僕らははかりかねた。 高校生男子にとって、父親のインタビュー動画を勝手にSNSにアップされるほどの屈辱はなかった。しかもその動画のなかで親父は勝手に家族構成を喋り、初恋の想い出を語り、テンプレートを作って眉毛を整えていることまで暴露した。 「眉毛は知ってた」 「テンプレート使ってたんだ」 だけど決定打はその直後。 『女子高校生ともなると、体はもう大人だねぇ』 「うわ、最低」 「くっそ、あの親父。二度と口聞いてやんねぇ」 「親父さんには言ったの? なんでインタビュー受けてんだよって」 「言ったらツイッターで絡まれてるのがバレる」 いや、絡んでるのおまえだろう、というツッコミはさておき。 「でも言わなかったら、エスカレートするよ」 「そのうち向こうも調子に乗って盗聴器とか仕掛けてくるかもしれないじゃん」 「わかってるよ、そのくらい」 苛立ちながらタイムラインを遡る。 その画面の下部には《若気の至りバスターズ》のロゴがアニメーションしている。 そのキャッチコピーを田村は―― 「……あなたのその歴史……なかったことにしませんか……」 力なく読み上げた。 「そのロゴ、たまに見るけど、なんなの?」 ゴンがたずねてくるけど、僕らも詳しいことは知らない。 軽音楽部の部室。 田村に引きずられそうになる気分を引き戻したのはゴンだった。 「バンドやりたいね」 ――って、楽器も弾けないのに。 「ヴォーカルやりたい、でしょ」 「ひとりで歌ったってしょうがない。バンドやりたい」 軽音でちゃんとドラムが叩けるのは一年の進藤くんひとりだった。 ベースは何人かいたし、なんならギターから転向させることもできた。あるいは僕がベースでもいい。みたいな話を、そういえば以前もしたことがあった。そのとき、「従兄弟が、ギター弾きなんだけど」と、進藤くんが語ったのを覚えている。 「めちゃくちゃ巧いんだけど、ベースのことすごいバカにしてたんす。『だれでも弾けるベース』って」 「ははは」って、笑ったと思う。僕は。 「気持ちはわかるけど、言っちゃいけないよね」 「わかるんだ、先輩」 「あ、ごめん、わかるっていうか、そういう時期ってあるよねって意味で」 いまにして思うと、人生でも一二を争う失言だった。 「従兄弟のバンド、結局はベースが辞めちゃって、そのあとすぐ解散したんす」 その話をしたのがもう三ヶ月前。それから進藤くんとの間には壁を感じていた。 ゴンはすっかり調子づいて、自作の詞をいくつか見せてきた。でもなんか子どもっぽい。秋山さんの詩を読んだときの衝撃はなかった。 その一編を見せられたとき、ちょうど部室に進藤くんがいて、「見てもいいですか?」と聞いてきたので無下にもできず、その場で簡単にコードを当ててみせた。 「タイトルは?」 「防波堤」 「タイトルはちゃんと書いておいたほうがいいよ。作詞者の名前も」 「どうして?」 「名前とタイトルがあって、はじめて作品になる」 詞をながめて、音を組み立てる。♪
あなたとかわした♮
――CからG♪
しょっぱいKissが♮
――Am、F 進藤くんもテーブルを指で鳴らしてリズムを取った。♪
海の香りと信じていた 子どもの頃♮
――ここまでがAメロ一回めっぽい♪
町に帰っていくつかの 恋もしたけれど 傷つくたび 思いだした 防波堤♮
――Aメロ二回。AABC AABC C。 「主人公の子、キス早くない?」 「いいんだよ。ファンタジーだから」♪
海は好きかと 聞くあなたに カナヅチだったわたしは 首を振って答えたっけ♮
「Bメロのラストはハイトーンで伸ばしたい」 ゴンがそれらしい注文をつけてくる。ゴンのくせに。 「じゃあ、こんな感じで」 「わかった。歌ってみる。最初からお願いできる?」 「歌うの?」 そう聞くと少しだけ目線を投げて、硬い表情に笑顔を取り繕ってみせた。 照れるんだな、ゴンでも。 「それじゃあ」 進藤くんはドラムセットの前に座り直し、不意に倒れかかってくるシンバルを受け止めて笑った。ゴンも笑った。進藤くんはたぶん、ゴンの緊張をほぐすためにわざとやったんだと思う。 一年生のくせに、なんでそんなに気ぃまわせるんだ。 人生二周目かよ。 その日は三人で校門を出た。 「文化街のラ・カルナバルって知ってる?」 聞いたことはある。 「フォーク喫茶だっけ?」 「いや、フォークに限らないけど、演奏もやってるバー」 「それってライブハウスとは違うの?」 「うん。喫茶店がメインみたい。マスターはライブハウスやりたがってるけど」 「やればいいのに」 「ライブハウスにできる物件は高いんだって」 「そんな理由?」 「だいじなことだよ」 演奏ができるんだったら、ましてや客が聞いてくれるんだったら、僕らはタダでもいい。だけどライブハウスのオーナーともなればそうもいかない。電気代だって、機材のローンだって、家賃だってある。 「マスターに会ってみる?」 「えっ?」 「デモ音源作って聞いてもらう?」 「えっ? ちょっと待って? それってわたしも入ってる?」 ゴンが戸惑っているけど、僕はどう答えればいいかわからない。 「もちろん」 進藤くんは親指を立ててみせた。 正直いうと、ゴンの詞には魅力を感じなかった。僕がつけた曲もありきたりで、何度か弾いてみるとなんとなくパクリ感があった。これをひとに聞かせるのもなあ、と。 「曲、作り直さない?」 「えっ? どうして? わたしは好きだよ?」 素人の意見は聞いてない。 「僕も好きだよ」 進藤くんまで。 キミらがなんでそんなに盛り上がってるか知らないけどさ。 「田中先生の意見も聞いてみない?」 渋々了承を取る。 「というか、デモ音源の作り方をよく知らない」 「このまえの、スマホで撮影したのでいいんじゃないっすか?」 まあ、僕がYouTubeに上げてるのもそうだけどさ。テキトウにギター弾いて、歌って、スマホで撮影してるだけ。それをデモ音源と呼べるのかどうかもわからない。OBが作ったものは、ちゃんとDTMソフトも使ってヴォーカルもスタジオ録音に近いものが入っていた。それに比べて僕たちのは―― 「これって、ノートにマンガ描いてジャンプに応募するようなもんじゃない?」 「最初はそこからで良くないですか?」 いや、だからー、最初はいいだろうけどー。 で、田中先生にはテキトウにスマホで撮ったヴォーカルとギターとドラムだけの音源を聴いてもらったんだけど、先生は、 「一歩踏み出したね」 と、笑顔を見せた。 「曲としてはどうですか?」 「可能性のカタマリ」 可能性と聞いて褒められたような気がしたけど、すぐに進藤くんが 「伸びしろだらけってことですね」 と言い直した。 「要はあなたたちがなにになりたいか、よ。来年の文化祭でスターになりたいのか、プロデビューしてミュージックシーンを席巻したいのか、あるいは大切なひとに思いを届けたいのか」 そう。そこなんです。届けたいんです。秋山さんに。 「歌詞はだれが書いたの?」 そして、そこなんです。 「わたしが書きました!」 ゴンが右手を上げる。 果たしてゴンが歌詞を書いて、秋山さんに僕の想いが伝わるでしょうか。いいや、伝わるはずがない。むしろマイナスだ。そんなことを思ってたら、田中先生は少しうーんと唸ったあと、顎に指をあてて言った。 「2番の歌詞が駄目」 不意の批判にゴンの表情が曇った。 「1番で情景描写は十分。2番はもういらない。たとえばここ―― ふたりで歩いた 海沿いの道で 追い越す車 埃にむせた海岸線 これも情景描写でしょう?」 「あ、はい。駄目ですか?」 「好きになったんでしょう、この主人公の子は?」 「ええ、そうだと思います」 「でも、情景しか見えてこない」 「はあ……」 「高尚な詩を書こうと思っちゃ駄目。伝わらなきゃしょうがない。伝わる言葉を選ぶの。中村先生に見せる詩じゃないの。あなたの友だちに聞かせる詩なの」 ゴンが圧倒されている。 「エピソード選び直してみて」 ふだん威勢のいいゴンが何も言い返せず、言葉を噛み締めていた。 「歌ってさあ、繰り返し繰り返し歌われるんだよ。こんなにたくさん言葉を使わなくても、たとえば『粉雪』だったら『粉雪』だけで伝わる。それが歌でしょ?」 「厳しいですね、田中先生」 「あんまりズバズバ言うと潰れますよ」 「潰れていいよ。プロになっても苦労するだけだから。早めに潰れたほうがいい」 次の日、ゴンは学校を休んだ。 僕と秋山さんの席の間に、ぽっかりとした虚無が居座った。 田中先生のせいだ。 いくらなんでも、早めに潰れたほうがいいはショックだ。 念の為ラインを送った。 返事はなかった。 翌日。 ゴン、僕の顔を見るなり、 「昼休み、音楽室に行くからつきあって」 これはもしかして、殴り込みか? 血の雨が降るのか? そう思うほどには真剣な表情が読み取れたのだけど、秋山さんが見ている傍で「つきあって」という言葉は謹んでほしかった。 「音楽室に一緒に行けばいいの?」 言い換えてみた。 「そう。ギター弾いて」 ギター? 念の為に進藤くんも誘ってみた。 「ついでだから、ヤギも連れて行っていい」 「ヤギ?」 「青柳」 ああ、青柳か。 「メェメェ鳴く方じゃなく?」 「ヤギ、ベース弾ける」 流された。 「ああ、うん。知ってる」 ていうか、なんか知らん間にバンドができてるなぁ。 「じゃあ、四人で乗り込みますか、音楽室に」 「ラ・カルナバルで演奏するときの予行演習っすね」 って、いつの間にそういう流れになったの? 先輩を立てる気、ないの?四・消えた思い出
ゴンが書き直してきた歌詞は、正直そんなに良いとは思わなかった。すごく安直で幼い感じになって、むしろ最初のほうが良かった。田中先生にはそこを突かれるんじゃないかと思ったのだけど、先生の評判はえらく良かった。指摘したとおりにゴンが直してきたから、自尊心が満たされたんだろう。ピアノが弾けたところで性根は高校教師、俗物だ。 「いい、覚えておいて」 田中先生はゴンの目を見据えた。 「情景描写なんかやったら駄目」 まさかのセリフが飛び出したな。 「たとえば『桜が散る』と書くときも、情景であってはいけない。それを見たときの気持ちを書くの」 「受験失敗してフラれて辛い、とかですか?」 「その気持を通して描く」 「難しいなあ」 「ひとによってそれは『いざ舞い上がれ』だし『花吹雪キラキラ』だし『秒速5センチメートル』だし、重要なのはそこよ」 歌詞じゃないのが混じってた気がするけど。 「歌詞って奥深いっすね」 「楽曲も同じだよ。『海は広いな』って歌詞を読んで、海は広いですーなんて曲をつけたってしょうがないじゃない。そう感じた背景を音にするの」 「つまり、どういうこと?」 「あー、仕事終わんなーい、むしゃくしゃするー、外出てみるかー、おおっ! 海だっ! 潮騒! 潮の香り! 今までの気持ちはなに!? どどーん! ざっぱーん! みたいな」 「ええっと」 まあいいか。 「とりあえずその言葉を胸にグラミー賞を目指します」 「あーっはっは!」 田中先生はわざとらしく笑った。 「グラミー賞なんてバカの祭典、目指したってしょうがないよ」 「すごいこと言いますね、先生」 「ステージでギター壊すやつがバカじゃないとでも?」 「それはそうかもしれないけど」 「ドラッグやってステージで暴れてギター壊して、『バカじゃありません』なんて言うやつがいたら、そいつのアタマでピアノ叩き割ってやるわ」 という田中先生の不当に冷徹な視線の向こうで、夕焼け空が夜空に変わり、新しい朝が来た。 希望の朝だ。 昨日までどんよりと沈んだ顔をしていた田村が、妙にウキウキと話しかけてきた。 「あのさあ、古澤」 「なんだよ、気味悪ぃなぁ」 「学園祭のこと覚えてる?」 「視聴覚室でのライブだろう? もちろん」 「そっちじゃない。クラスの出し物のほう」 「ああ……あれは……ええっと……」 やばい、思い出せない……なんでだ? 記憶喪失? 「無理に思い出さなくてもいい。たいしたことじゃないんで」 とおりすがりの古賀くんが、 「それはあれだよ」 と、助け舟を出そうとしてくれたが、その船もすぐに難破した。 「……えー……なんだっけ……?」 ふたり同時記憶喪失? 古賀くんは石井くんに声をかけるが、石井くんも同じ。井出くんも同じ、弥永さん、岩田さん、五郎丸くんと声をかけるも同じ。すぐに秋山さんも気がついて、こちらを振り返る。ここ数日、ゴンとばかりつるんでいたけど、僕の心臓は確実に秋山さんのことを覚えていた。女子の間にも、あれ? おかしいね、という声が広がっていく。 「なんで?」 写真が残っているはずと、各自スマホをチェックするがそれらしい写真は見当たらず。ならばスケジュール帳をと思ったが、全員のスケジュールは白紙だった。 「ハッキングされてる?」 「いや、まってまって、最近のハッカーってひとの記憶まで消すの?」 「わからん。どういうこと、田村」 そう聞いても田村は得意顔をするだけで教えてくれなかった。 秋山さんは首をすくめて、口を押さえて静かに笑う。その笑顔を胸に焼き付けたまま昇降口へ出ると、田村が背中を叩いてきた。なんかニヤニヤしていて気持ちが悪い。 昇降口を出ると自転車置き場へと消えて、僕が校門へ達する頃には追いついてベルを鳴らす。 「学園祭のこと思い出した?」 「いや。さっぱり。何か知ってんの?」 「知ってるも何も。俺が消したんだよ、みんなの記憶を」 「はあ? どうやって?」 「これ」 田村はスマホを差し出した。 なんでもないツイッター画面。 「一番下」 一番下……そこには広告があった。 「若気の至りバスターズ?」 「そう。ここに頼んだ」 「はあ?」 「ログを消してもらえるのかと思ったら、記憶も記録もすべて消してくれた」 「はあ? 消してくれたって、なんの記憶を?」 「それそれー」 「それってどれよ」 「自分でも覚えてないんだよ。自分で消した《若気の至り》がなんだったのか」 「なにそれ。ひどくない?」 「学園祭関連だったことは覚えてる。あとなんか、ツイッター関連。まあ、なんかやらかしたんだと思う」 「はあ?」 さっきから「はあ?」しか出てこない。 「それ、迷惑じゃない? 自分の記憶だけ消しとけよ」 「まーそう言わずに。それに迷惑ったって、忘れてなんかデメリットある?」 「デメリットって……思い出がなくなるっていうか……」 「でも言わなきゃわかんないわけだし」 「そうだけど、なんか釈然としない」 ここ数日の俺って、どう見えてた? と田村が聞いた。 ずいぶん落ち込んでたのは覚えてる。親友なのに何もしてやれなかったことも。そういうのを自分で解決するしかなかったのだと思うと、仕方ないのかとも思えた。 「それって、いくらくらいかかるの?」 「ものによるらしいけど、今回のは二千円」 「二千円かー」 とは思ったけど、田村を追い詰めたのは僕かもしれないし。 「おまえはいいよな」 「いいって、なにが?」 「彼女できたし」 「彼女って?」 田村はそれ以上語らず、呆れた目で僕を見る。 「ゴンは違うって! あいつこそ僕の汚点だよ! 現在進行形の!」 たしかに僕の人生におけるゴンの比重は大きくなっていた。だけど、秋山さんが好きであることに変わりはない。どんなに仲良くなろうが、『好き』ってのは次元が違う。それに理想を下げたくない。ゴンと付き合ったってバカにされるだけだから。田村だって、僕をからかいたいだけだろう? あんなやつと付き合う物好きがいるって。 昼休みの部室で、たまにゴンとふたりきりになった。 以前は昼休みでもひとがいたのに、最近みんなどこで何をしているのか。 「あのさあ」 「なに?」 「好きな子がいるんだよ、クラスに」 ひと月前だったら、こういうことは田村に相談してた。 「もしかして、告白? いいよ。いまならだれもいないし」 「は?」 おまえじゃねぇよ。 「ごめん、冗談。どうしたの、急に」 やり辛いなぁ。まあ、慣れたけど。 「なんていうか、あんまりおまえと付き合ってる風に見られたくない」 「それな」 なにそれ、ひとごと? 「じつはね、女子の間でも噂になってんの、わたしたち」 「ヤバ……それ、みんな知ってる?」 「多分そう。嫌がらせ受けてるし。じつは」 「嫌がらせ?」 「あんた、自分では知らないだろうけど、モテるんだよ」 「あ、いや、えっ?」 ゴンはゾウさんギターで不器用にアルペジオを奏でている。 「だから、もし本命がいるんだったら、さっさと告ってくっついて」 「いや、そうやって簡単に言う」 「あんたが本命とくっついてくれたら、ターゲットはそっちにいくから」 「ターゲットって?」 「嫌がらせの」 いや、ちょっとまって、それ、どうすればいいの? ゴンに向き直ったところに、下級生の女子が部室に入ってきた。 「あの、ごめんなさい。荷物だけ取りに来ました」 巾着一つ掴んで、そそくさと部室を出る。刹那、廊下の笑い声が聞こえる。ちらりとこちらを見て会釈する顔。みんなこの部屋に入るのを避けていたんだと、いま気がついた。 「わかった」 「わかったって、何が?」 「僕とおまえ、つきあってると思われてる」 「だからそうだってば」 なんてこった……。 「おまえはそれでもいいのかよ」 「へっへっへ。彼氏できたみたいで楽しい」 「はあ?」 「はじめてなんだ、こういうの」 まあ、僕もそうだけどさ。違うよね、彼氏彼女とは。 「ねえ、ギターっていくらするの? いちばんやっすい奴」 切り替え、早ぇ。 ゴンはゾウさんギターでG7のコードを押さえて、ガチャガチャとストロークした。 田村からゲームに誘われて、ボイスチャットで話した。 3D酔いを警戒して、「ゲームは1日1時間って決められてるんだ」と言ってはじめたエイペックスってタイトルのアクションゲーム。最近では2時間、3時間ということも少なくなかった。おかげでいつも聞かれる。 「親は大丈夫?」 って。 「うん。先に寝たみたい」 デュオでふたりプレイ。 「ゴンとはどうなの?」 田村から聞いてくる。 「困ってる。ちょっと」 「そうか。何でも相談して」 田村がリードして、僕は周囲を警戒しながらあとを歩いた。 「本当は秋山さんが好きなんだよ」 初めて言ったと思う。秋山さんのこと。 「でもこのままじゃゴンとつきあってるみたいだ」 「さすが、ミュージシャンは――」 田村被弾。 「ふざけんな、クソッ」 「ミュージシャンは? ミュージシャンはなに?」 背後からの攻撃、一瞬だけ見えた敵影。翻弄されているうちにまた被弾。 「クソ、クソ、クソ、クソばっかだな!」 「僕も自分の歴史を消したい」 「はあ?」 「重いよ。好きでもない子と仲良くするの」 田村は足を踏み外し、なすすべもなく蜂の巣にされた。 ――でもこの景色を覚えてる気がする。 どこだろう――篠山城址公園――? 石垣から蹴落とされた田村を見たことがある……。五・ラ・カルナバル
ゴンとふたり、塔屋の冷たい壁にもたれた。 「幹夫もおとなになったら髭生えるの?」 ゴンとは同じ小学校だったけど、一度も同じクラスになったことはなかった。中学でもずっとそう。同じクラスになったのはこの春。付き合いは短いけど、共通する話題は多かった。 ふたりでギターを買いに行って、部屋に上がってチューニングして、彼女の弟から「姉ちゃんの彼氏?」と聞かれて、それからのふたりは軽音部の部室を避けて、昼休みは屋上で過ごすようになった。 「どうかな。親父は毎日剃ってるし、生えるんじゃないかな」 「じゃあ、いまのうちに触っておいていい?」 「ああ?」 ふたりはまるで幼馴染か、同い年のきょうだいに見えたと思う。 「あと二~三年幹夫に彼女ができなかったら、つるつるの顎に触れたのわたしだけってことになるね」 高校生活はあと一年半。受験のことを考えると半年。それまでに告白しないと、ゴンのこの言葉は現実になる。 「さわっれいいけろ、うにうにすうらー。やめおー」 ってゆーか、ひとをまたぐな。おかしいだろ。 ゴンは僕の頬を両手でつかんだまま顔を近づけてきた。 スッという鼻息が聞こえる。5センチばかりの距離に迫る瞳。左右どちらに焦点を合わせたらいいんだろう。好きでもないのに、体は反応してる。気取られたくなくて腰をずらしてみるけど、ゴンは不意に顔を寄せて、柔らかくてさらさらとした頬を僕の頬に合わせた。 「少年のほっぺた」 囁く声が首筋に触れた。 頬が離れると、大きな顔が目の前にあった。 「キスされるかと思った」 「しようと思ったけど、噴き出しそうになったからやめた」 「そんな理由?」 じつをいうと、キスまでだったらいいかなって気はしていた。恋心なんて無くても、経験として。ゴンだってそんなノリなんだと思う。だから、この機会に。 「ちゃんとやってみよう」 体を起こして、ゴンの肩に手を置いた。ゴンは僕の横に座り直して、僕の二の腕のあたりに手を添えて静かに目を閉じた。軽く閉じた口。笑いをこらえて震えていて、それを見てると僕もつい笑いが溢れた。 軽く肩を揺するとゴンは目を開けて、僕の胸を叩く。 「ひどい。笑わないで」 「ごめん。ちょっと立ってみて。やりなおし」 そういって立ち上がって、またゴンの肩に手をおいて顔を寄せてみたけど、今度はふたり同時に噴き出してしまった。 ラ・カルナバルは文化街と呼ばれる通りのはずれにあった。大通りに近く、車の音が響く。 店を開ける前の時間にアポをとって、年老いたマスターに会った。薄暗い店内。アップライトのピアノと小さなステージがあった。 「連れてきたよ」 進藤くんが言った。 「ああ、見ればわかるよ」 老人は笑った。 僕とゴンと進藤くんとヤギ。ゴンが緊張しているのがわかった。 「緊張すると声がシャープする。まずはくつろいで」 そういうと老人はテーブルを指した。 椅子に座って、マスターが淹れたお茶を飲むと、進藤くんが口を開いた。 「十年後も僕たちはここにいるんだよ」 ――って、これだ。一言目に意表をついて耳目を集める。どこでその話術を覚えたんだ。 「思い浮かべて、その日のことを。そのとき、今日のことを思い出すんだよ。――緊張したな、ガチガチになってろくに話もできなかったな、って」 ゴンは静かに頷いている。 「その十年でアルバムも出したし、喧嘩もした。失恋もした。弾ける曲も増えた。レパートリーはどれもオリジナル曲。どの曲にも思い出が詰まってる」 という進藤の野郎の話を、僕もうっかり聞いてしまった。あろうことか、僕の胸の中にもその景色が広がって来やがった。同時にまわりの空気、ゴンにまとわりついていた硬い空気がほぐれていくのがわかった。 「そんななかで、ラ・カルナバルでの凱旋ライブ。オープニング曲は、最初にここを訪ねたとき、マスターの前で歌った曲」 ゴンが頷く。 「タイトルは……?」 進藤くんがゴンに水を向ける。 「防波堤」 少し照れたように言って、一息おいて続けた。 「わたしたちの大切な曲です。聞いてください」 その瞬間、スポットライトがゴンを照らした。 緊張はした。 学園祭だったらバカだと罵られても勲章になる。だけど今日は違った。真面目にやるのは苦手だけど、失敗はしたくなかった。演奏はまずまずだったと思う。ゴンの緊張も歌い出すとどこかに飛んでいって、最後は涙を浮かべながら声を舞い上げていた。それはどこまでもどこまでも伸びる天使の声だった。 歌い終えると、マスターの拍手。 僕らは高校生だ。かたやマスターは多くのバンドを見てきたひと。拍手は義理かもしれない。だけどそれでも嬉しかった。 「孫がね――」 僕らがテーブルに戻るのを待って、マスターが語り始めた。 「まだ小学生なんだが、バンドに憧れていてね」 その孫がどんな曲を聴いて、だれそれに憧れていると、ボソボソとした声は少し聞き取り難かったけど、孫の名前がミチルくんだというのはわかった。 「僕もそうでした。わかります」 「何年生ですか?」 「四年生かな? 来週ここでバースデイパーティをやるというんだ」 マスターは煙草を取り出して、口にくわえた。 「えっ! うらやましい、こんな店でできるなんて!」 「あー、それで……」 マスターはくわえた煙草に火も付けずに箱に戻して、少し聞き取り不能のむにゃむにゃした言葉のあとに、「一曲歌ってくれんか?」と続けた。 「一曲って……」 「僕たちでいいんですか?」 「ああ。ギャラはフライドチキンとケーキくらいしか……」 むにゃむにゃふにゃふにゃ。 一応僕は古株だしリーダーのつもりでいたので、まわりの顔を見渡して反応を見た。みんな乗り気だ。断る理由もない。 「やります!」 と声をあげたのは進藤くんだった。なんで肝心のところまで持っていくかな。 「曲はなにがいいですか?」 「ああ、なんでも好きなものを。まかせるよ」 マスターはカウンターでオレンジジュースをいれた。 「ほい。ギャラの前払いぶんだ」 背の高いグラスに透明な氷が入ったオレンジジュース。 「ありがとうございます!」 僕らはストローをくわえて、バンド名と演奏する曲について語り合った。バンド名は『血みどろ太陽族』になりかけたが、誕生日の席には不向きだろうということで、『パッションブラッド』になった。 曲はどうする? 小学生が盛り上がる曲ってなに? ボカロ? アニソン? いっそ校歌のロックアレンジは? ゴンが静かに聞いているなか、僕とヤギとで案を並べた。 制して、進藤。 「違うよ」 あ、また持っていく気だな。この野郎。 「演奏するのは、僕たちのデビュー曲、防波堤だよ」 ええーっ? 小学生相手にオリジナルのラブソング? 引かれないかぁ? とは思ったけど、となりのゴンの照れ笑いが妙に気持ちをくすぐってきやがるので、まあ、それで行くしかないと腹をくくった。 と、僕たちが青春を謳歌しているその間、親友の田村はピンチに陥っていた。 土曜日昼下がりの通学路。なにが起きたのかはわからなかったが、田村のチャリが歩道に乗り捨てられていた。無造作に横たわっている。いったいなんで。 「幹夫ーっ! 幹夫っ!」 考えていたら声が聞こえた。 というか、金魚売りのような呼び方はやめてくれ。 背後から走ってきた田村は息を切らし、 「これ、預かってくれ」 と、かばんを渡してきた。 「どうしたの?」 「追われてる」 そういうとすぐに走り出した。 「このかばんは!?」 アニメやゲームだったら、このかばんのなかに秘密組織から盗み出した設計図かなにか、あるいは敵と戦うための道具が入っているはず……と考えていると、もうずいぶん先まで走った田村から声が返ってきた。 「重くて邪魔だから!」 それだけ? 重いから持たせただけ? 訝る僕の横を赤いアルファロメオが追い越し、交差点の向こう、走る田村の前に鼻先を突っ込んで、ドアを開けて拉致して行った。 なんだそれ。 友だちが拉致られる現場を初めて見た。 松尾芭蕉だったら一句詠んでる場面だ。 いや、悠長にしている場合でもない。僕は乗り捨てられていたチャリにまたがった。 車を追わないと……。 でも、行き先……行き先は…… そのとき、脳裏に篠山城址公園が浮かんだ。 そこで田村が石垣から落とされる様子を、僕はどこかで見た気がした。 しかし友人が車で拉致されて、果たして百人中何人が躊躇せずに車を追えるだろう。相手はヤクザかもしれないし、あるいは逆にスーパーの買い出しに付き合わせたいだけの家族かもしれない。追いかける理由があるとしたら、『話のネタになる』くらいだ。つまり―― 追うべきだ。 チャリを漕いで十分。篠山城址公園に来た。なぜか記憶にある石垣へと走ると、田村と男の姿があった。アルファロメオを運転していた男だろう。どこか見覚えがある。石垣の端へと追い詰められる田村。たしかにこの景色だ。このあと田村は蹴落とされるんだ。 しかしそれがわかったところで、果たして百人中何人が躊躇せずに飛び出せるだろう。相手は明らかにヤバいやつだ。 でも親友を見捨てるのか? ――僕は見たんだ、田村が蹴落とされるのを! ――見たって、どこで!? ただの白昼夢だろう!? ――予知能力かもしれない……あるいは、タイムループしてるんだよ! ――そんなの、非科学的だ! ――あそこから蹴落とされたら、田村は死ぬかもしれないんだぞ? ――いくらなんでも、そんなひどいことはしないよ。 ――見捨てるのか!? そのすきにも男はじりじりと田村を追い詰めてる。 「自分でやったことだ。自分で責任を取れ」 かすかに声が聞き取れる。 責任ってなんだろう。でも話をしてるってことは、冷静だってことじゃないか。 逆に僕が飛び出したらあいつを刺激して、それが引き金になって田村が蹴落とされるかもしれない。これがタイムループの二周目だとしたら、一周目に経験したのはきっとそれだ。僕が飛び出してしまったがために、田村を死なせてしまったんだ。 ここは、飛び出さずに冷静に見守るのが正解だ。 ……と思ってたら、田村が蹴落とされた。 あっけねぇ。 田村、死んだ。目の前で。あーあ。 男はしばらく堀の底をながめたあとで踵を返した。 僕の方へ向かってくる。 逃げなきゃ。でも、考えがまとまらないし、足に力も入らない。 いや、待て。逃げたら怪しまれる。僕は何も見てない。 男は僕の目の前に迫る。 「おまえも。同じ目にあわないようにしろよ」 そう言って男は通り過ぎて行った。 あの顔……思い出した。 タイムパトロールのひと――久留米支部のデジタルサイネージで見たひとだ。 警察に電話したほうがいいのかもしれない。 いや、まずは家族に訃報を……いや、死んだとは限らない。 携帯を取り出して、1……1……と押してみて、あとは0、0を押すんだ、と思いながらも躊躇して7を押す。 午後、一時、五十、三分、二十秒を、お知らせします…… 時報聞いたってしょうがねぇ! 男の影が消えたことを確認して、恐る恐る僕は淵のそばへ来て底を覗いて見たけど、田村の死体は見えなかった。 茂みの裏かもしれない。 やっぱり警察には電話しなきゃ……震える手で携帯を握りしめる……1……1…… 午後、一時、五十、八分、ちょうどを…… 時間が知りたいんじねぇ! 僕の脳裏に漫画の一コマが浮かんだ。 ――ひとは、どんな嫌なことでも忘れることができる そうだ。忘れよう。嫌なことを忘れてしまえば、何度でも前を向くことができる。 僕は念の為、乗り捨てた田村のチャリについた指紋を拭って、その場をあとにした。 田村が死んだ翌日、マスターの孫のバースデイパーティが開かれた。 早めに入って、ドラムをセットして、リハーサルして、「客は8人だし、子どもだから」と、マスターはアンプのボリュームを決めた。 「客が多いと、音が吸収されるんだよ。そのぶん音量を上げないといかん」 小さな楽屋には雑多に衣装や機材が積み上げられていた。ライトがたくさんついた小さな鏡台、ケーブルの束。楽屋から見る子どもたちは楽器を見て目を輝かせている。 「はじめてのステージが主役って、ついてるよね」 僕が言うと、 「バカなのあんた?」 と、ゴンが呆れた顔を見せた。 「主役はミチルくんでしょ。忘れちゃだめですよ、先輩」 進藤の野郎にも諌められる。 というか親友が死んだ翌日に、僕は何をやっているんだろう。 会場ではハッピーバースデイの歌声が聞こえる。 拍手、笑い声。 しばらくしてマスターが呼びに来る。 「またせたね。出番だよ」 カーテンで区切られただけの楽屋。 楽器を持って登場すると子どもたちの拍手が轟く。 ゴンはラメの入ったドレス、ほかは黒い服で揃えてきた。ゴンが小さく手を振って挨拶すると、子どもたちは声を交わす。主役じゃないのはわかってるけど、僕にはゴンが主役に見えた。 「ミチルくん、誕生日おめでとう! それから、ミチルくんの誕生日のお祝いに集まってくれたみんなも、ありがとう!」 ゴンのMCに会場が沸く。 「今日はじつは、わたしたちパッションブラッドの初めてのライブです。つまりわたしたちの誕生日でもあります。それでどんな曲を歌うかみんなで考えたんだけど、わたしたちの歌を歌うことにしました。ラブソングだから、もしかしたらまだまだピンと来ないひとも多いと思うけど、いつか好きなひとができたときに思い出してください」 好きなひとという言葉に反応する子たちがいた。くすくすと笑い合っている。そういえば僕もこのくらいの歳には好きな子がいたことを思い出した。 「それじゃあ、聴いてください。わたしたちのデビュー曲。防波堤」 照明が落ちて、進藤くんがスティックでカウントを取る。 スポットライト。 ベースが走りだすと、その音圧に子どもたちは体をのけぞらせる。 ゴンがゆっくりと、マイクを上げる。透明感のあるヴォーカルがゆっくりと速度を上げて、羽ばたきだす。♪
あなたとかわした しょっぱいKissが 海の香りと信じていた 子どもの頃 町に帰って いくつかの 恋もしたけれど 傷つくたび 思いだした 防波堤 海は好きかと聞くあなたに カナヅチだったわたしは 首を振って答えたっけ もういちど 髪を染めよう あの日の 風の色に もういちど 空を仰ごう あの夏の空を わたしがこぼした ちいさい涙に ふたり同時に ごめんね言って 笑ったよね アイス半分わけあって 約束をかわした ありがとうを 言いそびれた 防波堤 星座をあててと聞くわたしに とまどいながらあたなは 教えてって笑ったっけ もういちど うたを歌おう 泣きむしのわたしに もういちど うたを歌おう あの夏の空に もういちど 髪を染めよう あの日の 風の色に もういちど 空を仰ごう あの夏の空を♮
子どもたちの拍手は割れんばかりだった。 だけど僕の高揚感はそれに勝った。僕が言うのもなんだけども、バンドの技術は高校生レベルを超えてる。ゴンの歌唱力も一週間前と比べても格段にアップしている。行けるかもしれない。このバンドなら。進藤くんが言ったように、十年後、二十年後、僕たちはトップを走っているかもしれない。 だけど、それなのに田村は―― パーティの帰り。 進藤くんらと別れ、ゴンとふたり。 「恋の相談がしたいから、ライン教えてって言われたの」 ゴンは僕にスマホを見せた。ラインに並ぶ噴き出し。パーティには女の子も三人来ていた。そのなかのひとりだという。 「へぇー、ちゃんと答えられるの?」 上の空だけど。返事はできた。 「うん。できる限りのことはする。勉強のことも見てほしいって言ってた」 ゴンは少し化粧していた。子どもたちからしたら輝いて見えたと思う。いつの間にか憧れられる側にいることに、戸惑いもあったし、責任も感じた。 「このバンドで、本当にちゃんとデビューしたい」 ゴンの言葉を聞いて、不意に涙が流れた。 「……って、なんで泣いてるの」 「わかんない」 嬉しさもあるけど、田村が死んだからかもしれない。 死んだ田村のことを忘れて、喝采を浴びたせいかもしれない。 なんかもういろいろで抱えきれない。 「昨日、田村が死んだ」 「えっ?」 ゴンは怪訝な顔をする。 「なにそれ」 「いや、なにそれって、なんでもない。本当に死んだんだよ、目の前で」 「ふーん」 ふーんって、事情を知らないからそりゃそうだろうけど。ふーんって。僕はどうすればいいんだよ、もう。六・若気の至りバスターズ
田村は死んでなかった。 学校で、田村が大怪我をして入院していると聞いて、ゴンとふたりで見舞いに行った。先生の話では、ひとりで遊んでいて足を踏み外したと本人が言っているとのことだったけど、嘘だと思う。 「よう、元気?」 田村はベッドに横になって漫画など読んでいた。 「ああ、来たんだ。仲いいなあ、おまえら」 ベッドの横には椅子が一個しかなくて、僕もゴンも遠慮してふたりで田村を見下ろしたまま話した。 「ひとのことはいいから」 そう言って釘を刺すと、鼻で笑った。 「おまえを蹴落としたの、ニュースに出てた男だろう?」 「ああ。見てたんだ」 ゴンが不思議そうな顔を向ける。 「警察に届けたほうがいいよ。また起きるかもしれないし」 「いや。それなら大丈夫」 「大丈夫? なんでそう言い切れる?」 「俺が時間操作して狂ったぶんを、俺の手で修復してきたから、もう大丈夫だよ」 ゴンは、「こいつ、なに言ってんの?」みたいな顔で僕を見るけど、僕にもさっぱりだ。 田村はつぶやくようにぼそりと言った。 「あいつの名前。ギルデンスターンっていうんだと」 「は? どこのひと?」 「しらんけど」 「それでその、ギルデンスターンがどうしたの」 「そいつタイムパトロール隊の隊員なんだけど、俺のせいで時空に裂け目ができたからっつって、裂け目に蹴り落とされた」 そこまでは見た。いや、裂け目は見てないけど。ていうか、なにそれ。 「裂け目って?」 「なんか、亜空間に通じる穴? みたいなとこに落とされて――」 ゴンが、「このひと、アタマ打ったんじゃない?」って顔で僕を見るけど、僕もそれを疑っているところ。まあ、もう少し聞こう。 「そのなかで――」 「亜空間で?」 「そう、亜空間で、魔物っぽいのがうじゃうじゃいたから、目からビーム放って倒すの」 どうすればいいのだろう。田村は割と平気でひとを担ぐ男だ。うっかり乗ってしまうとはしごを外されかねない。でもちょっと乗りたい。全力で釣られてすげぇーって言いたい。 「出してみて。ビーム」 ゴンの醒めた問いかけが炸裂。 「それが、こっち戻ってきたら出なくて」 「やっぱり嘘じゃない」 「いや、嘘じゃないって。そいつらに背中やられたから見てよ」 「そいつらって、亜空間のモンスター?」 「そう。モンスター。爪で、ガーッって」 そう言って見せてくれた田村の背中は、大きくえぐれていた。 ゴンが息を呑んだ。 しかもえぐれているだけではない。大きな穴が空いて、向こうには星空が見える。虹色に光り、傷のまわりの空間は歪んでいるようにも見えた。ていうか、なにこれ。 「それ、痛くないの?」 「えっ? 痛くないけど、どうなってる?」 「あ、穴が開いてる……お医者さんはなんて言ってるの……?」 「まあ、若いからすぐに治るだろうって」 「それ、この傷のことじゃないよ。ほかの傷の話だよ」 とりあえずスマホに撮って本人に見せてやった。 「おお! これよこれ! 亜空間! 俺が戦ったとこ!」 いや、おまえもうちょっと他の感想あるだろ。背中だぞ、おまえの。亜空間とつながってんだぞ。 「てことは、よ」 「てことは?」 「この中でならビームでるんじゃない? 目から」 「でも、そんなこと言ったって自分の背中じゃ、試しようがないじゃん」 「おまえらが試せよ」 「はあ?」 とりあえず、田村の背中にできた亜空間に顔を突っ込んでみた。 「フンッ! って眉間に力入れてみ」 眉間に力…… 「フンッ!」 出た。 「すげぇ! ビームでた!」 「だろう? だろう? だろう?」 ゴンもやってみた。 「でたっ! すごい!」 えー、その日僕とゴンは、友人田村の背中にできた亜空間に顔を突っ込んで、目からビームを出しました。 「俺、生まれ変わったら俵万智になりたい」 「なに記念日だ、今日」 塾があるからと、ゴンが帰ると、行き違いに秋山さんが訪ねてきた。 「あ」 と、秋山さん。 「あ、どうぞ。もう帰るんで」 僕はひとつしかない椅子を譲った。 「ひとりで来たの?」 田村が聞いた。 「うん。みんな部活とか塾とかあって行けないって。でも週末には来れるんじゃないかな」 「週末って。そんなには入院してないよ」 いや、おまえ、自分の背中の穴、過小評価してる。 「今日の授業のノート見る?」 「ああ、うん」 秋山さんはかばんから出したノートを開き、田村は携帯で写真を撮った。秋山さんがページをめくって、田村が撮る。僕には田村のシャッターに合わせた秋山さんの息遣いが聞こえた気がした。 秋山さんとふたり、病院を出た。 田村から事故の詳しい話を聞いて混乱しているかと思ったけど、秋山さんはそんな素振りは見せなかった。 「弓子、幸せそう」 秋山さんは言った。 ――あ、そうか。塾だから先に帰ったんだ。やっぱり今日も一緒だったんだ。羨ましい。わたし、彼氏できたことがない。 そんな言葉を聞きながら、どれほどに自分の気持を打ち明けたかったか。 「ゴンは田村の次に仲のいい友だちかな」 少しだけ予防線を張ってみた。 「いいなあ、そういうの」 あ、そう来たか。 「わたしは無理だろうな」 「無理ってなにが? 友だちになるのが?」 「そう。わたし、アンドロイドだから、友だちできないの」 秋山さんは独特な感性を持っていた。不思議な内面世界がある。 「そうなんだ。じゃあしょうがないね」 笑って流して、 「でも友だちだったらたくさんいるでしょう? クラスの連中とか」 そう言うと秋山さんは、 「そうだね」 って、軽く微笑んで返してくれた。 秋山さんのなかで僕は、言葉をひとつも受け取らないひとのレッテルが貼られたんだと思う。だから、急いで友だちになるしかないと思って、 「ノートを買って帰らないといけないんだけど……」 切り出してみた。 「あ、はい」 気のない相槌。 「いっしょに文房具見ていかない?」 ダメ押し。でもこれ、ほぼ『僕とデートしてください』と同義語なんじゃないかな。 「ここからだと、どこ? エマックス?」 後手、秋山悠子、3六歩。 「一番街にも文房具屋あったよ。なんとか書店」 それから少し秋山さんは黙りこくった。そしておもむろに。 「田村くんが退院してから、四人でYouMeタウンに行かない?」 って、田村、関係なくない? 「入院してるのに、悪い気がして」 何が悪いの? 僕といると田村に悪い? あいつ、背中に穴空いてんだぞ? 関係ないけど。胸の中に疑惑が生まれる。もしかしたら秋山さんは田村のことが好きなのかもしれない、と。でもまさか。田村だぞ? 帰宅部のアニメ好きの、ツイッター炎上常習者だぞ? 「弓子にも悪いし」 しばらく途切れた秋山さんの言葉が、再接続された。 「ゴンって呼ばれるの、嫌がってたんだよ、以前は」 「そうなの?」 「うん。権丈って苗字も嫌いだって。秋山とか竹下が良かったって」 コインパーキングをショートカットして大通りへ。 「でも最近そうでもないみたい」 地面を磨り上げて足をほうりだして、ふたりは歩いた。 「古澤くんのおかげなのかな」 一番街の入り口で秋山さんと別れて、文房具屋へ向かった。 筆記具のコーナーで試し書きするカップルの姿が目に入る。「好きだよ」「わたしも」なんて書いてる気がして、僕は消しゴムのコーナーに移動する。 いろんな消しゴム。昼のパン代を節約してよく買ってた。次に買う消しゴム、その次の消しゴムと当たりをつけてきた。チョコレートの匂いのする明治チョコレート型の消しゴムがお気に入りだった。洒落で齧って、それから使わなくなって、どこに行ったのかわからない。 店を出ると、謎の二人組がいた。 「あいや待たれい!」 「待たれよ、青少年!」 ……なんだそれ。 「われら、若気の至りバスターズ!」 もしかしてあの、SNSのバナーで見かける…… 「われらがそなたの若気の至り、塗り替えて進ぜよう!」 アプリだと思ってた…… 「いや、要らないんで、帰ってください」 「いやいやいや! たった二千円で過去を消せるのですぞ!?」 「消したい過去なんかない」 「五千円コースだったら、過去の書き換えもできるのですぞ!?」 「えっ?」 「あなたはいま、悩んでおられる」 「明治チョコレート型の消しゴム、なぜ齧ってしまったのか」 いや、そっちじゃない。 「過去に戻って、書き換えてはみませぬか!?」 「暗い過去もー」 「犯罪歴もー」 若気の至りバスターズは僕を囃し立てながら、僕の周囲をぐるぐる回った。 「賭けの失敗も消えてなくなーる」 無敵じゃねぇか、それ。 「取り戻せーる」 「ぱっぱやー」 迷いはあった。もしあの歌詞募集のチラシを書いた日に戻って、秋山さんのハートを狙い撃ちできるキャッチを書けていたら……。でも、財布の中には二千円しかない。貯金箱にはそれなりのお金はあるけど、いつかちゃんとしたギターを買うための資金だ。秋山さんへの再チャレンジか、ちゃんとしたギターか……。 「迷っておられますね~!」 くそう、見透かしてやがる。 「われらはいつも、あなたのSNS画面の一番下で、あなたのクリックを待っております!」 僕の背後から耳元に囁きかける。 「明治チョコレート型の消しゴム……取り戻してみませんか~」 「だからそっちじゃねえ!」 振り返ったとき、若気の至りバスターズの姿はそこにはなかった。 僕たちの予想に反して、次の日には田村は退院。ぱっくりと開いた背中の亜空間も姿を消していた。 「要はエイペックスと同じよ」 授業の始まる前、田村は高角砲を飛ばした。 「異世界に入ると、ドロップシップから降りるときみたいに降下するのよ。で、地面みたいなとこはあるけど、基本はジェットパック装備。自由に飛べんの」 「それで、目からビーム出してモンスターを倒す、と」 これ、まわりの連中が聞いたらエイペックス初心者の会話だ。目からビームってなんだっちゅう話ではあるけど。 昼休みもその話の続き。 まわりの連中も興味を持つんじゃないかと、田村はあえての大声で話すけど、反応は鈍かった。それどころか―― 「うるせえよ!」 怒鳴り声が聞こえてきた。 肩をすくめて、頭を下げてみせるけど、その仕草がまた癇に障ったらしい。 「田村さあ。聞いたんだけどさあ。おまえのせいで俺たち、学園祭の思い出がないんだよ。それ、どう思ってる?」 田村は北上くんに詰められて、僕の顔を見る。おまえが言ったのかよって顔。 このことを知っているのは僕と、せいぜい、ゴン、秋山さん。僕が話したんじゃないと言えば、ゴンか秋山さんを責めることになる。 「過去を消したって、なんのために消したの?」 ほかの生徒も田村に詰め寄る。こうなるともう、歯止めは効かなかった。 「どんな過去を消したの? 犯罪歴?」 「本当はこの学校にいられないようなこと、やったんじゃないの?」 人垣ができる。 「いや、俺も思い出せないんだから聞かれても困るよ」 田村は周囲に集まる顔に視線を振り分け、たじろいでいる。 「無責任だろう、それ!」 「自分がなにやったかわかってんのか!?」 「わかってるよ……」 そりゃそうだ。記憶と記録を消したってだけの単純な話だ。 「なんにもわかってねえよ!」 ええーっ、とは思ったけど、これ、うっかり反論できないやつだ。 「古澤はどう思ってんだよ、楽しそうに話してたけどさ」 やべ。こっち来た。 「まあ、良くはないよね」 「ハッ」 笑顔で吐き捨てるけど、でもこれ、本気で怒ってるパターン。 「なにそれ。甘やかしてんの?」 笑みを消して真顔で囁く。ひとの脅し方をよく知っていらっしゃる。んもう。 「おまえはいいよな、ライブの思い出ちゃんと残ってるし、ゴンと付き合い始めたんだって、それがきっかけだろう?」 もちろん、そうではない。だけどうかつに言い返したらこっちがタコ殴りだ。しょうがない。降りかかる火の粉は払うしかない。 「僕だって、田村のやったことは最低だと思うよ。なんとなく話合わせてやってたけどさあ。エイペックスと同じってなあないよ」 最低だな。僕は。 僕に詰め寄ってた連中が田村に向き直る。 田村の心細い顔。 「そりゃねぇよ、セニョ~ル」 って、ココロの声が聞こえてきた。 言いたいことはわかるよ。でもさあ、田村、そんな、ゲーム感覚でひとの人生を……ねえ……ほら……。 5時間目、6時間目、田村の姿が見えなかった。 田村に何かあったら、背中を押したのは僕だ。 掃除をさぼって自転車置き場へ。田村の自転車がある。まだ校内にいる。いや、歩いて外に出たかもしれない。SNSを見るけど、田村の書き込みはない。 ――屋上にいる! 報告してくれたのはゴンだった。 急いで屋上へ上がると、田村と、若気の至りバスターズの二人組の姿があった。また時間を操作しようとしている。 「田村!」 呼びかけると田村は振り向きもせずに、中指を立てて見せた。気持ちはわかるけど、カチンと来た。 「もとはといえばおまえが悪いんだぞ!」 クソ! 引き止めなきゃいけないのに何を言っているんだ僕は。 田村は天を仰いだ。 若気の至りバスターズの二人組が田村の両側で不思議なポーズを取ると、田村の体は光の中に消えていった。 「いまのは何?」 ゴンが不安げに聞いてくるけど、そんなの、僕にもわからない。七・小さな恋のメロディ
朝起きて「朝だ」って思うやつはまあ、いると思うんだ。じゃあ「今日だ」って思うやつは? それもいるかもしれない。「ついに今日のこの日がやってきた!」って。でも「その翌日」って思うやつはいない。要は、どの翌日よって話じゃない。 だけど最近朝起きて、たまに思う。 どの翌日だ。今日は。って。 昨日までのことを振り返って確かなのは、田村と秋山さんとが微妙に親しいこと、田村は最低でも一回、時間を遡って歴史を書き換えていること。 「それってつまりさあ」 「つまり?」 「おまえ、時間遡って秋山さんに告ってない?」 「はあ? なに言ってんのおまえ」 「いや、僕が聞いてるんだけど」 「なに言ってるかわかんねえ。だいたい告白は向こうからだし」 「えっ? あ? はあ?」 「いや、言ったじゃん。もうずいぶん前だよ」 聞くんじゃなかった。 田村の話から察するに、時間を遡った本人は、遡ったことを覚えていないらしい。もちろんクラスの連中も知らない。僕は昨日――たぶん昨日――田村が若気の至りバスターズの導きで時空の間に消えて行くのを見たから、僕とゴンは知ってる。それからのことを田村が覚えてないってことは、つまり、どういうことなんだ? 「いつから付き合ってるんだっけ?」 「言ってなかったっけ?」 「聞いたかもしれないけど、もういちどお願い」 本当は聞きたくもない。 「中学の卒業式で。あいつの友だちに呼び出されて、裏門から出たら、あいつが待ってて」 辛ぇー。聞きたくねぇー。 「そんなこと、僕の世界線では起きなかった」 「知らねえよ」 「僕、いつからこのこと知ってるんだっけ?」 「高一の夏には話してるよ。海に行くって話したとき」 「てことは僕は、おまえと秋山さんがつきあってるのを知りながら……」 「知りながら……? なんかしたの?」 「あ、いや、ええっと……秋山さんのこと好きになった?」 「なんで疑問形?」 「自分の感情に自信がない」 僕が言うと、田村は口の端で笑った。 「そういうことか。まあ、わかるよ」 秋山はアイドルだもんなあ。そんな子とつきあってんだから、みんな羨ましがるよなあ。おまえもそうなんだろう? 悔しいのう古澤ぁ。ギター弾けんのに残念だなぁ。 口にこそ出さないけど、そういうことだろ、田村が言いたいのは。 「おまえ、ゴンがいるじゃん」 「はあ?」 ていうか世界線変わっても、その関係は変わってないんだ……。 田村はどの時点から人生をやり直したんだろう。もし僕がそれよりも過去に遡れば、僕が秋山さんと交際することだって叶うんだろうか。とは思うけども、いまの僕はそんなにいまが嫌いでもない。この時代。この空気。この瞬間。 ゴンと歩く放課後の通学路。 学校を離れてふたつ角を曲がるとゴンは手をつないできた。昨日も、一昨日も、この角を曲がるのを合図に手をつないだ。僕もこの角を曲がる前に、かばんを反対の手に持ち替えるようになった。 ひとを好きになったときの気持ちは知っていたけど、好きになられたときの気持ちも悪くないと思った。お互いに好きになったときの気持ちはもっと違うんだろうな、とも。新しい歌詞を書いたときのゴンは、キラキラしていて、翼があるようにさえ見えた。 次の角、ちょうどタイムパトロール隊の事務所の前で田村と出会った。田村の押す自転車を挟んで、秋山さんの姿がある。 「よう」 手を挙げるふりをして、つないだ手を離した。 僕はまだ秋山さんへの思いを捨てきれずにいた。 「何してるの?」 ゴンがたずねると、秋山さんは少し照れたように答えた。 「ちょっと遠回り」 遠回り。ふたりきりで? なんのために? 問えない問を胸の中に繰り返していると、照れ笑いの八重歯がこぼれた。このふたりはこのまま行けば恋人同士の関係になる。時間を操作してチートで交際し始めたくせに。でもそれも微笑ましいとすら思い始めた。 「金文堂に消しゴムを買いに行ってたの」 「こいつ、明治チョコレートの消しゴム買ったんだぞ。小学生かよって」 微笑ましいは取り消し。気がつくと僕は、何もかも奪われているじゃないか。田村が時間操作して秋山さんを奪ったのは事実だ。僕の歌詞募集に秋山さんじゃなくてゴンが応募してきたのも田村のせいなんだ。 「その消しゴム、こんど見せてー」 ゴンが口にした次の瞬間、赤いアルファロメオがタイヤを鳴らして僕たちの間に走り込んだ。 悲鳴を上げる秋山さんとゴン。僕と田村は息を飲んで、怒鳴ろうかと思った声を一時保留する。相手はヤクザかもしれない。怒鳴るにしても、それを確認してからだ。そう決めて暗いフロントガラスを覗き込む。 ――というかこの車、見たことがある気がする。 ドアを開けて降りてきた男を見て、田村は言った。 「ギルデンスターン?」 「だれ? しってるひと?」 と、秋山さん。その答えは僕の口から。 「いや、わからない。でもしってるひとだ」 「それ、どっちなの?」 ゴンのツッコミ。 男はポケットからドラゴンボールレーダーのようなものを取り出して、苛立たしげに言い放つ。 「この四人のなかのだれかだ。だれかが時間を操作している」 僕とゴンは思わず田村の顔を見た。釣られて秋山さんも。 「俺?」 田村が自分の鼻を指差して小首を掲げる。 次の瞬間、路肩のゴミ箱が開いて巨大な影の塊が飛び出してきた。 「尻出しゲロゲロ魔王!」 ギルデンスターンの声に僕らは驚いて復唱した。 「尻出しゲロゲロ魔王!?」 「空間の歪みが臨界を超えた! こちら側に出られたら為すすべがない!」 ちょっとなんのことかよくわからないけど、ゲロゲロ魔王を中心に亜空間が広がっていく。足元に広がる虹と宇宙の光と闇にゴンと秋山さんは戸惑うが、 「チャンスだ」 とギルデンスターンはひとこと。チャンスってなに? ギルデンスターンは胸の前に腕を水平に構えると目からビームを発して尻出しゲロゲロ魔王に浴びせ始めた。はあ? 苦しみもがき出す尻出しゲロゲロ魔王。はあ? しかし、その動きを制するには至っていない。はあ? 「おまえたちも!」 「はあ?」 おまえたちもと言われても、真似して腕を構えてみるが何も起きない。手をこまねいているとゴンが目からビームを出して尻出し魔王に浴びせている。 「どうやったの、それ」 「腕のポーズは関係ないみたい。眉間に意識を集中すると出る」 関係ないんかい! 「出た! ミルクボーイ内海のこれで出た!」 田村は手を直角に構えてビームを出した。 ゴンが受けてるけど、なにそれ。ていうか、ええっと。 「ゲッツ!」 出た! ポーズ関係ない! ゲッツでも出る! 「これ、なんか覚えてる」 と、田村。 ついには戸惑っていた秋山さんもにこにーポーズでビームを放つ。 「にっこにっこにー」って。 なーんかこう、なーんかこの世界線の秋山さんって、田村の影響受けてる気がする。 魔王がもがきだしてからは一瞬だった。 光、あるいは闇だったのかもしれない。穢れた体から眼底にかかる圧が吹き出し、魔王はその体をふたつに引き裂かれた。 魔王から広がった亜空間の闇が消えたとき、そこに残されていたのは瓦礫と化した町並みだった。僕たちのまわり三十メートルほど。車も建物も電柱、並木、生け垣、すべて破壊され、廃墟となり果てていた。 「これは……?」 愕然とあたりを見渡すゴン。秋山さんは言葉を漏らすこともなく、そのまま静かに顔を覆った。 「逃げるぞ」 ギルデンスターンは僕らに目配せするが、僕も田村も返事を躊躇った。 「警察が来て、この状況をちゃんと説明できるんだったらここに残れ」 ゴンは表情を変えずに涙を流している。 秋山さんは顔を覆ったまま静かに頷いて、顔を上げて僕らを促した。 ギルデンスターンは僕たちを、ラ・カルナバルに案内した。 「知ってます、ここ」 僕が言うと、 「知ってる」 と、ギルデンスターン。 「おまえたちは監視対象だ」 重いドアを開けると、薄暗がりのホール。上目遣いに見やるマスターに、 「すまない。また世話になる」 とだけ告げると、マスターは顎をしゃくって僕たちを中へと招き入れた。 ギルデンスターンとマスターとは旧知の仲のようだった。テーブルに通され、田村と秋山さんには事情を説明した。ギルデンスターンはドラゴンボールレーダー状の機械をテーブルに置いて、お手上げの仕草をして見せた。 「さっきの余波でイカレたみたいだ」 「それは?」 ゴンが興味を示す。 「時間の歪みを感知するディストーション・デテクターだ」 ディストーション・デテクター……。 「それって、正式な英語ですか? 和製英語ですか?」 と、ゴンは聞き返すが、なぜそこを気にする。 マスターが人数分のコーヒーを入れて、僕たちは角砂糖のキャニスターとミルクのボトルを回した。 「おまえたちのバンドは、あれからどうなった」 ギルデンスターンが僕に聞いた。 「どうって、バンドとしては活動してないけど……そんなことまで知ってたんだ」 「絶賛新曲準備中です!」 割り込んで、ゴン。 「そうか」 素っ気ないギルデンスターンの返事。マスターが隣の椅子に腰を下ろした。 「こいつも昔はバンドをやっていたんだ。俺の娘と」 しゃがれた声で告げる。 「そうなんですか?」 「昔の話だ」 「娘さんはどこに行かれたんですか?」 ゴンの質問にマスターは答えず、ただギルデンスターンの返事を待った。田村も秋山さんも、それぞれのカップを持ったまま耳をそばだてている。 「あいつはたぶん、ショウワにいる」 昭和……? 「こっちの世界にはいない。こっちは時間を書き換えられた嘘の世界だ。あいつは本当の世界――いまもショウワで弾き続けているよ」 「昭和ということは、一九四五年以前の世界ですか?」 「いや、本当の世界では一九七八年までショウワはあった」 「元号制は廃止されなかったんですか?」 「ああ、そうだ。こっちは嘘の世界だ。俺たちは偽りの世界の中にいるんだ」 そう話していると、マスターが割り込む。 「わからんぞ。どっちの世界が本物で、偽物なのか」 話が複雑になってきた。 この世界が偽物だと言われても、ここで生まれて育った僕たちにとって、この世界は本物だ。ある日突然、タイムパトロール隊のひとたちが言うように、天神にコアやイムズやアクロスといったビル群が現れて、それを本物だと言われたところで、それは僕らにとっては嘘の世界だ。 「その本物の世界では、いまも元号が使われてるの?」 「そうらしい」 「それって、年齢とか数えるときどうするの?」 「わからん。都度計算するんじゃないか?」 「めんどくさそう」 僕は御免こうむるよ、そんな世界。 ギルデンスターンは目を細めて笑うと楽屋のカーテンを開けて、物置を漁った。そして一本のギターを抱えて、差し出して言った。 「相棒のギターだ。一曲やってくれ」 戸惑う僕らにサムズアップとともに笑顔を見せて、スポットライト。 マイクのラインを足元にするするとたぐって跨ぎ、MCが始まる。 「ええっと、今日はいろんなことがあって、まだ混乱中ですが、ちょっとブレイクして歌を披露したいと思います。みなさんもちょっとだけクールダウンして、これからの冒険に備えてみませんか? えー、曲はこないだわたしと幹夫で完成させた新曲です。バンドメンには一度披露したきりかな?」 僕はギターをチューニングしながら、左手で2と示す。 「二回。二回ですね」 秋山さんはゴンに向かって、小さな拍手を送っている。 「準備大丈夫?」 ゴンの声にOKの合図を返す。 「それじゃあ、聞いてください。 パッションブラッドの新曲。 ――空」 2小節のアルペジオから、ストローク。 そして、歌声。♪
窓辺にとまる 小さな鳥に ほほえみ返し まとめた荷物 ふたり暮らした 部屋の片隅 あの日の空を 思い出してた つよく生きろと 手を握りしめ 小さな声で サヨナラ まだ行かないで つよくなるから わたしひとりに しないで 星空に 泣いたあの日 花の名前も 鳥の名前も 教えてくれた あなたに もうすぐわたし 旅に出るのと ちいさな花を 捧げた ちいさな花を 捧げた 大空に 歩きだすの 大空に 歩きだすの♮
やっとわかった。 僕はゴンのことが好きだ。 いますぐにでも抱きしめたいほどに。八・尻出しゲロゲロ魔王
ゴンの部屋は狭い階段をのぼった二階にあった。 小さな庭をのぞく窓。その空を映したような青いギター。島村楽器で買ったエレキの入門セットが、綺麗に揃えて置かれていた。 「だいぶ覚えたよ」 と笑って、コードを押さえる。 「おお、すごい」 ゆっくりとストロークすると、6弦がミュートされた和音が響く。舌を出して、もういちど握り直して、 「ちゃんとしたアンプがほしい」 と、またストロークする。 「でも、大きい音は出せないでしょう」 「音量はそうだけど、でも、これだよ?」 と、ゴンは入門セット付属のミニアンプをぷらぷらさせて見せた。 「ちゃんとしたアンプだと、安いのでも六千円はするよ」 「そうかー。お年玉待つしかないかー」 「親戚多いの?」 「あんまり多くない方。多分平均よりちょっと下」 「平均って、お年玉の?」 「そう。雑誌に乗ってた。ブルースハープはいくらするの?」 「ピンキリだけど、二千円くらいからかな」 「じゃあ、そっちにしようかな」 「なにが欲しいの」 「なんでもいい! 島村楽器に行きたい!」 わかる。だれの人生にだって島村楽器に行きたくてしょうがない時期がある。 「じゃあ、明日行こうか」 「やったぁ!」 それからゴンが弾いてみてとギターを渡すので、定番のスモーク・オン・ザ・ウォーター、デイ・トリッパー、ウォーク・ジス・ウェイとリフを弾いてみせて、その日の別れ際、ふたりはキテレツ大百科のエンディングを奏でた。 僕とゴン、秋山さんと田村、放課後、ラ・カルナバルに立ち寄るとにわかに慌ただしかった。 ノートPCを閉じてギルデンスターンが立ち上がった。 「尻出しゲロゲロ魔王が出た。おまえたちはここにいろ」 慌ただしくかばんを肩に掛ける様子を見て、僕らは互いの顔を覗いた。 「行きますよ、僕たちも」 そう口にしたのは田村。 「勝手にしろ」 ギルデンスターンは背中で言い放った。 薄暗い喫茶店から光の中へ飛び出すと、気を緩めた瞳孔に光が溢れる。 「国鉄の方だ」 コインパーキングへ向かうギルデンスターンを尻目に、僕らは走り出した。 「俺、先行するわ」 と、チャリの田村。 その背中を見送って僕らも走りだす。だけど息がもったのは最初の信号まで。あとは僕とゴンと秋山さんとで歩いた。ふだんのままのバス通り。柔らかいクラクションが追い越す。 「それにしても、尻出しゲロゲロ魔王ってネーミング、ひどくない?」 ゴンがたずねた。 「あれ、暴走族を珍走団って言いかえるのと同じなんだって」 「あー、そういうことかー」 「どういうこと?」 「魔王ハドラーみたいなネーミングにすると、うっかり憧れるひとが出てくるでしょう?」 「魔王ハドラー?」 「あ、ええっと、大魔王シャザーンみたいな?」 「なにそれ」 「魔王オディオとか?」 「なにそれ。ゲーム?」 国鉄の駅付近で田村、ギルデンスターンと合流。 田村は周囲を警戒し、ギルデンスターンはPCでだれかと連絡を取り合っている。 足元に黒い影が疾る。気にも留めずにギルデンスターンのPCを覗いていたら、駅で悲鳴が上がった。何かが駅ビルに激突した。砕け散るガラスと壁。 「来た」 動揺が走る。通行人がみな振り返り、駅からは叫び声と破壊音が連続する。 「尻出しゲロゲロ魔王?」 田村がたずねる。 「ああ。敵影は5つ」 「そんなに?」 PCを見ながらギルデンスターンが告げると、駅舎を中心に足元に亜空間が広がりだす。だけど前回のそれとは違った。まるでメルヘンの世界。嘘くさいお花畑とお菓子のオブジェが展開していく。 「なんだこれ!?」 ポップでカラフルなフロア、極彩色の池の水、ファンキーな動物たち。 「異世界って、いろんなステージがあるんだな!」 すぐに敵の一体が頭上を横切り、上空からビームを放ってきた。 「向こうもビームを撃つんだ……」 「どうする?」 頭上を横切った敵はすぐに駅向こうの物陰に隠れた。 「気を取られるな。囮だ。周囲を警戒しろ」 囮? 尻出しゲロゲロ魔王って、そんなに高度な戦術を使うの? 「俺が陽動する。釣られて出てきた奴を田村と古澤で叩け」 試合は5対5。数は拮抗するが、こちらはゴンと秋山さんがほぼ素人だ。 「四人は固まって動くんだ。人数がいればそうそう突っ込んでは来ない」 そう言うとギルデンスターンは前方へと展開する。 「戦闘は俺と古澤にまかせて。素人だと気取られないように、無駄な動きは控えて」 田村が指図するけど、無駄な動きったってわかんないよ、普通。 「敵が見えたら撃って。それ以外では撃たない。無駄に撃つと、こちらの位置を知らせることになる」 「わかった」 後ろで怯えているだけになるかと思ったゴンと秋山さんだったが、覚悟は決めているようだった。 ギルデンスターンの交戦音が聞こえる。ビームの射点から敵は二匹だと推測される。 「あと三匹はどこにいると思う?」 「駅ビル。おそらく背後から回り込んでくる」 田村と僕とは同じ意見だった。 そのとき、ゲロゲロ魔王一体の撃破音が轟く。地響きと衝撃波。建物越しにもその体から漏れ出す闇の光圧が目を眩ませる。 「なにこれ? なんで暗いのに眩しいの?」 それは……闇の光と呼ばれているもの…… 「放射能みたいなもん。照度は高いけど、可視光の範囲じゃないから見えないんだよ」 言うなよ、田村。おびえてるじゃん、ふたりとも。 「悠子、ゴン、先行して」 田村が秋山さんのことを悠子って。悠子って。 「一匹はギルデンスターンにまかせる。残りの三匹は回り込んで背後を取りに来る。俺が後方に展開しておびき出すから、そこを狙って。古澤は護衛を」 「わかった」 だれの護衛かわからんけど、護衛、わかった。 ハンドサイン、秋山さんとゴンが先行、駅ビルへ突入。そのとき。 「ぎゃーーーーーーーっ!」 ゴン秋山組が悲鳴を上げ、乱れるビーム音。 「うそつきーーーーーっ!」 「なにが背後から回り込んでくるだーーーーっ!」 裏の裏をかかれた? 「ちょ、マジでやばいんだけどっ!」 「責任取れ田村ぁーーーーっ!」 急いで助けに入ろうとするが、そのままゴン秋山組、一体撃破、続いてまた遠くで撃破音。おそらくギルデンスターンだ。 これで三匹は仕留めたのか? だとすると残り二匹。となれば流石にもうこちらの優位だ。だけどいまの戦闘でゴンと秋山さん負傷。足と腕に亜空間の穴が空いたような傷。痛みはないが、力が入らないという。 ゴンと秋山さんを物陰に隠して、田村と僕とで周囲を警戒する。途端、衝撃音。駅舎の北。おそらくギルデンスターンの近く。だけど彼が無事でいるかどうかはわからない。どうする? 行くか、ここで待つか。 戸惑っていると、 「来た、背後だ。正面から抑えるから回り込んで」 田村に言われるがまま、駅ビルを抜けサイドのドアから敵の背後へ。挟撃。4体目撃破。その断末魔が轟く中、足を引きずりながらギルデンスターンが戻ってきた。 「大丈夫ですか!?」 「俺は大丈夫。それより、悪いニュースと、もっと悪いニュースがある。どっちから聞きたい?」 「良いニュースはないの!?」 「とりあえず悪いニュースから……」 「悪いニュースは……俺がもうビームを打ち尽くしたこと……」 あれ打ち尽くすなんてことがあるんだ。 「もっと悪いニュースは?」 「敵が分裂した……」 「敵が?」 「分裂?」 そう言っているすきに重低音の羽音が聞こえはじめた。 巨大な蜂のようなものが大群で迫ってくる。 「分裂してこうなったの!?」 「ああ。ここで抑えるしかない」 抑えるったって、この数を!? ゴンと秋山さんも支え合って立ち上がり、決死の攻防が始まる。 次から次へと迫りくる尻出しゲロゲロ蜂の攻撃。一体一体はそれほどでもないが、向こうは数で圧倒する。何匹かは僕の目の前まで達し、尻から針を出して攻撃してきた。ゴンの悲鳴。気を取られていたら僕も被弾。田村、連撃するも撃ち漏らしも多い。四人とも肉弾での防衛を強いられる。 「無理だろ、これ!」 「頭上にも! すごい数だ!」 「こんなの! 勝てるわけがない!」 僕らが死にものぐるいで防衛するなか、メロディが聞こえてきた。 「この曲……」 振り返るとギルデンスターンは力なく壁にもたれて座り、ギターを弾いている。 「ギター?」 「こんなときに?」♪
窓辺にとまる 小さな鳥に ほほえみ返し まとめた荷物♮
しかも僕らの歌! 「なに歌ってんだこの煮込み大福野郎!」 ゴンが怒鳴る。 「まずそう! 煮込み大福、まずそう!」 秋山さん、リアクション、変。♪
ふたり暮らした 部屋の片隅 あの日の空を 思い出してた♮
いったいなにに酔いしれてんだ、このひとは。 「ざけんじゃねーぞっ!」 秋山さんも尻出しゲロゲロ蜂に押されながら怒鳴る。 「アニメじゃねぇんだぞ! おまえも戦えーっ!」 秋山さん、案外的確。 ゴン、応戦しながらギルデンスターンを足蹴にするが――♪
つよく生きろと 手を握りしめ 小さな声で サヨナラ♮
ギルデンスターンは、涙を流しながら唄を歌っていた。 「ふざけんなーっ!」 「JASRAC仕事しろーっ!」 僕と田村はその、なんというか、ただがむしゃらに戦うしかなかった。 巨大な尻出しゲロゲロ蜂の最後の一匹が倒れると、あたりを覆っていた異世界のフィールドは消え失せた。そして、そこにはもう町がなかった。周囲百メートルを超えて瓦礫と化した町並み。 「これって……」 「ここに住んでたひとたちはどうなったの?」 駅舎と駅前のマンションはぎりぎりその形を保っているが、外壁は吹き飛び、大きな亀裂が縦横に走っている。窓にはガラスもなく、窓だった穴に風が吹き抜ける。 「もしかして、福岡大空襲跡と言われてる場所って……尻出しゲロゲロ魔王と戦ったあとなの……?」 ゴンのその問いにギルデンスターンは答えなかった。ただ―― 「あそこはこことは違う。荒野の中心にはショウワが残っている」 とだけ教えてくれた。 「ショウワって?」 「本来の俺たちの歴史だ」 「本来の歴史……」 「だれも時間操作なんかしない世界。そこに行けば、あいつにも会えるはずなんだ」 あいつ……おそらく、いっしょにバンドをやっていたローゼンクランツというひと。でもいまの僕の胸にはなにも入る隙間がない。 遠くにサイレンが響いている。上空にはヘリの姿もある。僕たちが異世界で戦っている間ここでなにが起きていたのか、僕たちは知らない。 「テレビ局かな?」 「ここはあえて、被災者を装って保護されたほうがいいんじゃない?」 「気にするな。記憶は混乱して、すぐに忘れるさ」 「忘れるかなぁ」 瓦礫のなか、ラ・カルナバルまで歩いた。 「死んだんだよ。あいつは。睡眠薬で」 歩きながらギルデンスターンは語った。 「睡眠薬?」 「それって、自殺?」 ヘリの音にときおり声はかき消される。 「あいつの親父さんには、消息不明とだけ伝えてある」 「いやいや」 「気づくでしょう」 「まあ、当然な。警察からも連絡が行ってる。だが、時間なんていくらでも巻き戻せる。要は、なにを信じるかだ」 ギルデンスターンは上着を脱いで、肩に掛けた。弱い陽の光に舞う風に、戦いで火照った肌を晒した。 「あいつは、自分のいない世界に旅立ったんだよ」 「じゃあ、巻き戻したらいいんじゃないですか、時間を」 「でもタイムパトロール隊だからできない、と」 「タイムパトロール隊は関係ない」 「それじゃあ、どうして?」 頭上をヘリが飛び交うなか、ギルデンスターンは目を伏せたまま歩いた。 「五千円で好きなように歴史が変わってしまう。そんななか、あいつはあいつの意志で消えた。それがあいつと俺との間の、たったひとつの事実なんだよ。それすら守れなかったら、この世界になんの意味がある」 そうか。その気持はわからなくもない。だけど。 「でもどうして自殺なんか?」 「わからん」 小さな空白。 「友が死を選んだんだ。その理由を聞いて、本当にその気持をわかったと言えるのは、同じ理由で自分が死を選ぶときだけだ」 質問をして、ギルデンスターンが答えて、そうやって歩いていたのに、いつの間にか僕たちは問いかける言葉をなくしてしまっていた。 「わかったふりはしたくない」 喧騒をなくした街に、瓦礫を踏む小さな足音。 「あいつが死んだのは、バンドを辞めて四年ほど経った頃だ。夫も子どももいた。なんの予兆もなく、夜中に部屋で薬を飲んで、そのまま逝ってしまったって、あいつの夫から聞いた」 どうしてギルデンスターンがそんなことを話しだしたかはわからなかった。だけど重い足を引きずりながら聞くには、相応しかった。 「朝起きると床に倒れていて、机の上には俺が贈った詩集が置かれていたと、律儀にも俺に返してくれたんだ、彼は」 バス通りに横たわるバスの残骸。 「そのとき、つい聞いてしまった。――どのページが開かれていた? ――って」 「そしたら?」 「――わからない。ページは開かれていたけど、気にせずに閉じてしまった――って、泣き崩れられた」 だれかに語られて耳に入る言葉だけが、胸のなかで事実になる。千の悲劇、万の死があってもなにも響きはしないのに。 翌日にはもう、久留米駅周辺に規制線が張られた。そこはすぐに『久留米空襲跡地』と呼ばれるようになり、立ち入りが規制された。 そして僕たちは、そこで起きたことを忘れてしまった。九・あいつが消えた夜
ブルースハープの予算は3千円。 バス代を節約して、ショッピングモールまで自転車を走らせた。 島村楽器で壁に飾られた憧れのギターを目にするけど、やっぱり0の数が多い。「試されますか?」と声を掛けられて、恐れ多くて遠慮して、僕は新しいピックを買った。 ゴンは弾きたくてウズウズしてたけど、ボディに傷なんか入れられたらたまんないし、なんとかなだめて、楽譜のコーナー見せて、アクセサリーのコーナー見せて、それからブルースハープ、平たく言えばハーモニカのショーケースに連れて行った。 ゴンはいちばん安い税込み千円ちょっとのハーモニカをふたつ買って、ひとつを僕にくれた。買い物は口実。ふたりは島村楽器に来たかっただけ。その島村楽器だって口実。 「それじゃあ、おかえしに」 と、グルメストリートに誘ってパフェをふたつ注文した。僕の財布には、いつか使うだろうと入れていた五千円札があったけど、それを崩した。 いつもおしゃべりが尽きなかったゴンが、黙々とパフェを食べて、残り半分くらいになったころ、 「あのね、古澤くん」 と、苗字で呼んできた。 はたと浮かれていた気持ちが椅子に座る。そういえばちゃんと告白してなかった。もしかしてゴンに告白させてしまうのかな。と、そんな気持ちで、 「なあに?」 と返すと、 「わたし、謝らなきゃいけないことがあるの」 と、深刻な表情を見せた。不安がさっと胸の前を過る。 「これを言うと嫌われるかもしれないけど、いつか言わなきゃいけないことだから」 ゴンはパフェを食べていた手をテーブルの下にしまった。 「わたしね……」 言葉を詰まらせて……僕も体を固くして耳をそばだてた。 「零夫くんのこと……あなたのお兄さん……いじめてたの。小学生のころ」 緊張が一気に混乱に変わった。 ――なんだ、兄のことか。 そう言って笑いたいのはやまやま。兄をせせら笑った連中のなかにゴンもいたんだ。その悔しさと、自分でもつい歩調を合わせていた日のことが込み上げてきた。 「ごめんなさい! 本当にごめんなさい!」 兄のことなんて外では忘れて過ごしてるし、もう僕に双子の兄がいるなんてだれも知らない。知らないとばかり思っていた。 「ほんとうは零夫くんに直接言わなきゃいけないの!」 ゴンは頭を下げるけど、どう答えていいかわからない。 「いいよ、気にしなくて」 上の空、言葉だけが口を滑る。 「兄はそういうの、わからないんだよ。何を言われたってわかんないんだよ。放っておくしかないし、いまは幸せだから、そっとしておいてあげたいんだよ」 そっとしておいて欲しいのは兄の気持ちではなく、僕の気持ちだ。 「いいんだよ、本当に。みんなやってたし、僕だって流されたくらいなんだから」 でも、だけど、と、静かに頷きながらゴンは泣いた。 「大丈夫。いつか忘れる。時間が忘れさせてくれる」 窓から射す陽に雲が横切ると、肌にまとわりついていた熱がさっと消える。陽が薄らいだぶん、悲しみが増す。日蝕と月蝕とが同時に来ることはないって、先生が言ってたのを思い出した。 それじゃあ最短でどのくらいのインターバルでそれが連続するのだろう。日蝕の30分後に月蝕、なんてことがあるのか。あるいは数日、数週間待たなければ来ないのか。あるいは数ヶ月。数年。 今日のこの悲しみは、いつになったら消えるんだろう。 家に帰ると、兄が箱に入ったまま出てこなくなったと姉が嘆いていた。 「別にそのままにしておけばいいよ。箱に入りたいだけなんだから」 「でも、ごはん食べないと」 「お腹が空いたら出てくるよ」 「それっていつよ。夜中に出てきて騒いでお母さん起こすの? それともあんたが起きてごはんの用意してあげるの?」 姉は苛立ち、呆れ、怒り、悲しんでいた。 しょうがない。 僕は手近なダンボールで船をこしらえた。 ふたを開けて底を抜いて手で抱えただけの船だけど、たったそれだけで僕は海賊になった。見てくれこの船。ここは大海原。ほら、聞こえてくるだろう、海賊たちの声が。 よーそろー! 「レオー! レオのふねはどこだー!」 ガイコツマークの帆に風を受けて、僕の船は進む。 「風穏やかなれど、波高し! 野郎ども! 準備はいいか!」 零夫が蓋を開けて、ちらっと僕を見た。 「みーつーけーたー! そこにいたのかー! さーて、どうしてくれよう!」 兄はワクワク期待しながらも戸惑ってる。 「零夫ー。そのままだと海賊にやられちゃうよー。ライダーベルトで戦うんだ、零夫ー」 そう言ってあげると兄は箱を飛び出して、おもちゃ箱からライダーベルトを探り出して、また箱へもどった。 「な、なんだとっ! そのベルトはっ! まさか変身する気じゃないだろうな!」 兄の変身ポーズ。 「くそう、このままじゃ返り討ちだー! 逃げるぞ、野郎ども!」 兄は箱のなかでぴょんぴょん飛び跳ねる。 「とりかじいっぱーい!」 急旋回に船体は傾き、甲板に波がかかる。 「うわー甲板が水浸しだー! 魚がビチビチ打ち上げられるー!」 次の瞬間―― 「幹夫、零夫、早くしなさーい!」 階下から声が聞こえ、兄が振り返る。 「海の魔女がきた! どうする? 零夫」 そう聞くと兄は、おもちゃ箱に駆け寄って塩ビの人形を一つ取り出して僕に見せた。 「おっ! ナイスアイデア! でも使い方がわかんない。これをどう使うの?」 兄は階下を指差す。 「そうか。わかった。どうやって使うか見せて」 「うん」 兄は満面の笑みで頷いた。 新しい曲を作った。 ゴンとふたり、ブルースハープを吹いた。 ふたりはクラスでも公認の仲になった。 田村から秋山さんとの進展も聞いたけど、僕はゴンとの進展を正直には語らなかった。ふたりだけの秘密が増えていった。僕たちは約束と、ありがとうと、ごめんなさいに使えるおまじないを覚えた。 「また新しいコードを覚えたよ」 「新しいリフを覚えたよ」 「新しい曲を弾けるようになったよ」 そう聞く度にゴンの部屋を訪ねて、また新しいコード、新しいリフ、新しい曲を教えて、ある日窓辺で庭を見下ろしてゴンが言った。 「林檎の実がなったよ。ほら」 ゴンが指差した先には、まだ小さな林檎の実があった。それはこの幸せな日々の結実だった。だけどこの先の幸せをなにも保証してはくれない。 「どうしよう、これから」 「どうする?」 「どうすればいいと思う?」 不安のキャッチボール。僕たちの前には不安ばかりが横たわる。学校のこと、家庭のこと、進学のこと。それに加えてゴンの不安には、秋山さんのことがあった。 「いまでも悠子のことが好き?」 恐る恐るたずねる。 「そんなことないよ。弓子がいちばん好きだよ」 このところ僕は、ゴンという呼び方を改めて、名前で呼ぶようになっていた。きっかけは田村にも秘密。だけど元をたどれば秋山さんに言われたからだ。 「わたし、本気になったら絶対辛い思いするから、本気になりたくなかった」 小さなりんごを眺めたまま、ゴンは口にした。 「わたしが悠子にかなうわけないんだよ。向こうはアイドルなんだから。あの子だったら幹夫といても嫌がらせなんかされないし、みんな納得するんだよ」 多くは語らないけど、いまも嫌がらせは受けているようだった。「誰から?」と聞いても、「気のせいかもしれないから」と口をつぐむ。 「でもそういうのは、表面的なことでしょう?」 僕もまた、育ち始めたばかりの林檎に視線を落とした。 「そうだけど。男は外見しか見ない。みんな」 「みんなってことはないよ。僕が秋山さんに惹かれたのは、顔やスタイルじゃない」 「えーっ。信じらんないなー」 ゴンはおどけて笑った。 「だったら他にもいい子いっぱいいるよー」 「ほかの連中のことは知らないけど、僕が彼女に惹かれた理由は違う」 欺瞞でもなんでもない。僕が秋山さんを好きになったのは―― 「彼女は、とてもいい詩を書くんだよ」 「詩……?」 「現国の授業で詩を書いたことあったでしょう? あのときの詩、秋山さんのをたまたま読んで、それで……」 ゴンの目から大粒の涙が流れ出した。 どうして? 一瞬の戸惑い。僕の胸にあった言葉がすべて溢れて、その混乱のあと悟った。僕は、人生で最大の失言をしてしまった。 「いや、でもそれで詩の魅力に目覚めて、それで弓子の詩にも出会えたんだから」 急いで取り繕うけどゴンの涙が止まらない。顔がみるみる歪んで、足元から崩れていく。 「ごめん、ねえ、弓子、ごめん。そんなつもりじゃない。僕は弓子が好きだし、弓子の詩が一番好き。だからねえ、弓子。本当にごめん」 それから30分、1時間、ゴンは声にならない声を発しながら泣いた。 なんとかなだめて、言いくるめて、彼女の家をあとにすると、目の前に若気の至りバスターズのふたりがいた。 「あいや待たれい若人よ!」 僕は聞こえるように舌打ちして横をすり抜ける。 「ひとを泣かせておいて、そのままにしておくおつもりですかい? そいつぁ感心しませんぜ、お兄さん」 「うるさいなあ! 放っておいてくれよ!」 「あーあ、キレちゃってもう」 「ぜんぶ自分が悪いってわかってんじゃないのかい?」 「わかってるよ! わかってるけど、どうすりゃいいんだよ!」 「おおっと! よくぞ聞いてくださいました!」 「こんなときこそわたくしら、若気の至りバスターズの出番!」 あーもう! イライラする! 「過去を消すなら二千円~」 「二千円~」 「書き換えるなら五千円~」 「五千円~」 僕のまわりをくるくる回る若気の至りバスターズ。その影が僕に蝕を作る。その日蝕と月蝕とが、幾重にも僕を闇に染めた。 憔悴の夜。 夜中に何度も目を覚まして、ラインを見て、メッセージを送った。 僕が優柔不断だったばかりにこんなことになってしまった。 明けて月曜、学校を目指さずゴンの家まで自転車を漕ぐ。 途中、若気の至りバスターズの二人組とすれ違う。 残念ながら、おまえたちにかかずらわってる暇はない。 目的地へ着いた。 だけど……ここへ……僕は何をしに来たんだろう。 だれの家に来たんだろう僕は。 表札には権丈とある。 だれだっけ? 何かすごく大事なことを忘れてる気がする。この家のひとに関するとても大事なことだ。 とにかく呼び鈴を鳴らす。 中学生くらいの男子が顔を出す。見覚えがあるような、ないような。 「いまだれもいません。僕も学校に行くので、玄関締めますよ」 表札にある名前は三人。 「この名前は、ご両親?」 「そう。それに僕です」 少年は玄関を締めて、鍵を掛ける。 ――歴史が書き換わっている。 さっきすれ違った若気の至りバスターズの仕業だ。 奴らが、だれかの願いを叶えて、別の世界線に来てしまったんだ。 でも、だれが、何を願って、どんな世界線から、どんな世界線へ? ――あいつは、自分のいない世界に旅立ったんだよ ギルデンスターンが言った言葉が思い起こされる。 いや、関係ない。ギルデンスターンが言ったのはローゼンクランツのことだ。それにもしこの家のひともそうだったとして、それってだれ? この家にいたのはだれ? ふと庭を見ると、立木がある。林檎がなっていたはずだ。知っている気がする。昨日見ていた気がする。それを見ながら、だれかが泣いていた気がする。 「林檎はどうなった!?」 小さくなっていく少年の背中に問いかけるが、一瞥しただけ。 「林檎がなってたと思うんだけど! ねえ! 林檎!」 記憶を追いかけてもどんどん消えていく。 どうすればいいんだ! 僕は! いったいどうすれば!十・アクロス・ザ・天神
ビートルズにアクロス・ザ・ユニバースって曲があって、その曲のなかでジョン・レノンは「だれも僕の世界を変えることができない」と歌っていた。その意味を、僕はずっと《信念》だと思っていた。信じたものはなにがあっても、だれであっても変えることができないんだって。 でも、だれだったかな。だれかといっしょにその歌を歌ったとき、そのひとは《あきらめ》って言ったんだ。 だれも僕の世界を変えることができないから、僕は僕の世界のなかで生きていくしかない。しょうがない。これが世界だ。前を向こう、って。 その言葉に僕は寂しさを感じた。だけど同時に、それは強さでもあるような気がした。 そう言ったのがだれだったか、もう思い出せもしないけど。 「諏訪町に新しい事務所ができた」 ラ・カルナバルに広げていた荷物を片付けながらギルデンスターンが言った。 「新しい事務所は九州地区統括だ。いまより情報が入る」 少し上気したギルデンスターンを尻目にマスターは新聞を読んでいる。 「僕も見学させてもらっていいですか?」 思わず口にすると、マスターがちらりと顔を伺った。 「構わんが、部外者に見せられる情報は限られるぞ」 「それって、入隊しろってことですか?」 「しろとは言わん。おまえの自由だ」 タイムパトロールって世間では狂信者扱いされてるし、もっと強引に勧誘してくるものだとばかり思ってた。返す言葉を選びあぐねていると、ギルデンスターンが振り返って人差し指を立てて見せた。 「いや。むしろ入隊するな。事務所にも来るな、絶対に」 ギルデンスターンはなにか思いついて、ひとりで納得していた。 いや、教えてよ。僕にも。なにか企んでるんだったら。 春日市――福岡の南にある衛星都市の自衛隊官舎に、従兄弟の家族が住んでいた。 従兄弟は五つ上。小さい頃から漫画を描いてて、この春だったかな、ヤングサンデーで連載を始めたと連絡が入った。 今更ながら、 「何か手伝えることがあったら言って」 と伝えると、 「それじゃあ、ベタ塗りでも。いちど遊びにおいでよ」 と返信が来た。 それを伝えるとギルデンスターンは、サムズアップしてみせた。ナイスプレイだ。従兄弟の方から誘ってきたのは大収穫だ。ナイスプレイ。大収穫。ナイスプレイ。案外、語彙が少ないギルデンスターン。 決行は翌月、第一金曜日。たまたまその日はタイムパトロール隊の福岡空襲跡地襲撃の予定日だった。僕はタイムパトロール隊には入隊しなかったので、そんな計画は知る由もない。たまにラ・カルナバルでギルデンスターンと会っていたけど、バンドの話しかしたことがない。 「およそ三百人でショウワに乗り込む」 「三百人!?」 「前回は二十人。すべて公安に逮捕された。しかも半分は宿を出た時点で拘束された」 「マークされてたってこと?」 「そう。今回は人数をかき集めたが、その動きも漏れていると思って間違いない」 「それでもやるんですね」 「そうだ」 「逮捕されたらどうなるんですか?」 「すぐに釈放される。バカの烙印を押されて、テレビで晒される」 近頃、世間は彼らのことを「タイムパトロール・ぼんクラー」とか「タイムパトロール・オタオタマン」とか呼んでいて、それでメンバーが集まりにくくなっているそうだ。 「怖気づいたか?」 いや、怖気づくのとは違うでしょ。 「やりますよ。僕もショウワの世界、本当の世界に行ってみたいから」 というか、バカは勲章だよ。ギター叩き割るのと一緒で。 「ああ、上手くいったら、ショウワで会おう」 ギルデンスターンによると、僕はまだ公安の監視対象外だという。それを活かして、自衛隊官舎の従兄弟の家に泊まり、混乱に乗じて単独で福岡空襲跡の中心、ショウワを目指す。 従兄弟を騙すことになるけど…… 「何かあったら、五千円で時間を巻き戻してやりなおしてもいいですか?」 「だめだ」 にかっと笑ってサムズアップが返ってくるかと思ったらこれだ。 「冗談に決まってるじゃないっすか」 立場ないじゃん、もう。キレそう。 自衛隊の官舎は名前ほどの勇ましさはなく、閑静な佇まいを見せた。 車で駅まで迎えに来てもらって、久しぶりに会った従兄弟と、漫画のことを語り合った。彼はキングダムが面白いと、ずっとそればっかりを語り、部屋では生原稿や来週掲載ぶんのゲラ刷りを見せてもらった。いまはまだネームを描いているところで、一週間後に来てくれたらベタ塗りの作業を頼めるという。 夕食は叔母が作ってくれた。うちではあまり食べたことのないレバニラ炒め。鉄の味がする柔らかな肉は、喉を通すときに少し抵抗があった。 「叔父さんは?」 「今日は遅くなるって」 「いつも遅いの?」 「そうでもないけどな」 従兄弟が答えると、叔母さんが渋い顔で重ねる。 「タイムパトロール隊・チキチキドンドンに動きがあるみたい。それでみんな駆り出されてるのよ」 チキチキドンドンは初めて聞いた。 「もうほんと迷惑。タイムパトロール隊なんて狂信者の集まりでしょ?」 と、眉をしかめてみせる叔母に、作り笑顔を返す。 「なんでああいうのに騙されるのかしら。幹夫くんも気をつけないとだめよ」 「ああ、はい」 僕の下手くそな作り笑顔に、叔母も笑顔の繕い方を忘れたような不器用な笑みを返した。 ギルデンスターンによれば、ショウワの世界にはもうひとりの自分がいて、探して融合したら、そこからまた自分の生活をやり直すことができるらしい。そこには空襲跡地もなく、本来の歴史通りの世界がある。そしてきっと、僕が失ったものがある。 目覚ましは6時にセット。僕はブルースハープを入れた小さなかばんを抱えて眠りについた。 早朝。 目覚ましの音で従兄弟が起きないか不安だったけど、目覚ましが鳴る前に目が醒めた。 あたりはまだ薄暗い。 寝間着代わりのジャージから着替えて、かばんを背負う。静かな部屋を抜けて、廊下、玄関。靴を履いてドアを開けると、黒いSUVが停まっていた。 エンジン音が聞こえる。叔父の車だ。 躊躇しているとドアが開いた。 逃げたら怪しまれる。 それに逃げて走ったところで、天神までは10キロ近い。 ――急用ができたので帰ります そんな嘘で逃れられるだろうかと考えていると、意外にも、 「市街地へ出るんだったら乗せていくよ」 という叔父からの提案。 市街地……博多のほうだろうか。ここよりはずいぶん天神に近い。 「お願いします」 車はいくつかの検問を越えて北上。ものの十五分ほどで空襲跡地のフェンスまで来た。 こんもりとした小さな丘の陰に車を停めて、叔父は言った。 「フェンスには触れないほうがいい。取り付いたらすぐに警備隊がくる。この先にタイムパトロール隊が掘った穴が残ってるから、それを探すといい」 叔父には僕がショウワを目指していることは見透かされていた。 「奴らは三隊に分かれて突破を試みると目されているが、うち一隊は武装している。事態が動き出したら、公安もマスコミもそっちに釘付けになる。そのすきを狙うといい」 「叔父さんは大丈夫なんですか? こんなことして……」 「心配するな。公安にも自衛隊にもおまえたちの味方はいる」 空襲跡地を囲んだフェンスは、小さな神社が祀られた丘を避けてその背後を通る。朝露に濡れた草地に放り出されて、フェンス沿いに背を屈めて穴を探した。見つけたのはフェンスの境目にぎりぎり開けられた小さな抜け穴。地面に体を沿わせて、泥まみれになって穴を通った。 フェンスを越え、壁際に体を隠していると、遠くにヘリの姿が見えた。 銃声が轟く。 時計はもう9時。始まったんだ。 僕は身をかがめ、瓦礫や草むらの残る大空襲跡地を走り、ショウワを目指した。第二部・フル・スチーム・アヘッド
十一・照和
やばい。また気を失ってたみたい。 「気が付きましたか」 って、白衣の男のひとがいるけど、ここたぶん救急車の中だ。サイレンが聞こえる。 「あの。もう大丈夫なんで」 どのくらい経ったかわかんないけど、わたしはオープンキャンパスに行きたいの。 「これが見えますか?」 救急隊員が指をかざして見せる。 「これというのは?」 ただの指? 見た感じ、ドーナツを刺してるわけでもないし、もしかして指先に小さい文字が書いてあるとか? でも、そんなに動かされたら読めないでしょ。 「指を止めてもらえますか? 見えません」 「あ、はい。いや、指が見えてれば大丈夫です」 あ、なんだ。 「最初から『指が見えますか』って聞いてくれたらいいのに」 「ええ、そうですね。次からは気をつけます」 次って。 漫画とかドラマとかで見る限り、女子高校生って気を失いがちだと思う。だけどわたしのまわりで気を失った子なんか見たことない。わたしばっかり、これでもう三回目。 「貧血だと思います。念の為お医者さんに診てもらうよう手配しますね。お名前を伺ってもよろしいですか?」 医者かあ。あんまり好きじゃないなあ。 「秋山悠子。秋の山に、『ゆう』は悠久の悠。有給休暇じゃないほう。県立西町高校、二年三組」 「西町……?」 「久留米の」 「ああ、すみません。久留米だと明善とか久大附設くらいしかわからなくて」 「ケッ」 「あ、ごめんなさい。バカにしたわけじゃ――」 「あ、こちらこそ。いまの『ケッ』は、他意のある『ケッ』じゃないです」 久留米から福岡まで電車で小一時間。わたしの通う高校はそんなにメジャーじゃない。でも、久大附設だったら徒歩圏内なのを、わざわざわたしに向いてる高校を選んだんだ。ささやかなプライドがある。 博多駅近くの診療所に運び込まれたのがもうお昼すぎ。 待合室は混み合っていたけど、急患だからか、先に診察室に通された。 「あー、秋山さん。秋山悠子さんね。具合はどう?」 「良くはないです。ずっと」 「どこか悪いの?」 「うん。あちこちがもうボロボロで」 「じゃあ、ちょっと診させてもらおうかな」 あんまり意味ないと思う。 「わたし、アンドロイドなんです」 「ああ、はいはい」 聞いてくれないし。 「ちょっと血圧が低いくらいで、とくに目立った所見はないように見受けられます」 ああ、そうですか。 「今日は天神で何してたの?」 「専門学校のオープンキャンパスに行く予定が、道に迷って」 「ああ、あのあたりは慣れてないと方向感覚が狂うからねぇ」 「あれーとか思って歩いてたら、『照和』って名前の喫茶店があって、あー、ここだー、って」 「ほーう」 と、医者は語尾を伸ばして上げた。 「その歳で照和を知っているとは珍しい」 「友だちが言ってたんです。天神に照和っていう伝説のライブハウスがあるって」 「マニアックだねえ、その子も」 ほーう、ってのもっかい聞きたい。 「古澤幹夫っていうんです。グラミー賞を獲るって言ってるから、覚えておくといいですよ」 「ほう、そいつぁすごい。覚えておこう」 ほう。ほう、か。ほーうが良かった。あ、そうだ。 「ひとつ質問してもいいですか?」 「ああ、かまわんよ」 「ここの診察代、払わないといけませんか?」 先生がわたしの目を見て、は? みたいな顔をする。 「べつに、大した診察もしてないのに金なんか払えるかーとか、そういう意味で言ったわけじゃないです。なんていうか、勝手に救急車に乗せられて、勝手に病院に運び込まれて、勝手に診察代を取られるんだったら、それは詐欺と同じなんじゃないかな、と」 「あー……」 先生はなんか言おうとして、言葉を引っ込めて、 「まあ、大した診察はしとらんがね」 だって。 結局、オープンキャンパスへは行けなかった。 お父さんが車で迎えにきてくれるというので、博多駅周辺をぶらぶらと歩いて、近くの公園で時間を潰した。公園にはすぐ近くのアニメ学校の生徒が来て、仮面ライダー論議に花を咲かせていた。 わたしは日向ぼっこ。今日もバッテリーの電圧が低い。ベンチに座ってぼんやりしているだけで気を失いそうになる。お父さんが公園に来たとき、わたしは寝てたか、気を失ってたか。睡眠と気絶の違いって、よくわかんない。 「悠子、帰るよ」 「うん」 「荷物持った?」 「うん」 お父さんのバンはシボレーっていう外国車。大きな車体のなかはガラクタだらけだった。このガラクタは、完成に至らなかったわたしの妹。意識は出来てるみたいで、 「お姉ちゃん、また倒れたの?」 と、聞いてくる。 「うん。もうバッテリー、駄目みたい」 妹の名は、みー子である。体はまだない。 「わたしのを使いなよ。ちょっと古いタイプだけど」 「でも、うっかり触ってあなたのこと壊したくないし」 「平気だよ。もう壊れてるから。はははは」 はははって。気楽な妹だなぁ。 「あのね、お父さん」 車は高速へ。ゆっくりとカーブを曲がる。 「どうした」 「バッテリーがもう駄目になったみたい」 「そうか。前に換えたのっていつだったかな」 「中三」 「二年でもう駄目かあ……わかった。すぐ手配するよ」 「ありがとう。照和の前で立ちくらんだのも、バッテリーのせいだと思う」 「遠出をするときはお父さんにも言ってくれたらいいのに」 「えーっ」 お母さんとオープンキャンパスに行くって子は何人かいる。でも、お父さんと行く子はいない。わたしにもお母さんがいたらよかったんだけど、でもアンドロイドにとっては、お父さんとお母さんっていっしょか。 「あと、それとね、お父さん」 「なんだい?」 「バッテリーのなかに、だれかいる」 「えっ? それはどういう意味?」 「照和の前で立ちくらんだとき、見えないだれかがわたしを揺さぶって、そのひとがわたしの中に入ってきたの」 「へえ、見えないってことは、透明人間なのかな」 「うん。そのひと、まだわたしのバッテリーのなかにいる」 「わかるんだ」 「うん。なんかね。ハーモニカ吹いてる。そのひと」十二・変態七拍子
部屋に戻って、コンセントに電源をつないで、バッテリーをとりはずしてみた。 このなかにひとが入っている。不思議だ。ある意味、わたしが飼っているのだとも言えるし、逆に監視されているとも言える。 女子高生の体に潜り込むなんて、おそらくどっかの変態のおっさんだろう。新しいバッテリー買ってもらったら、このまま警察に持っていくしかない。 しかし、それにしてもそそっかしい変態である。わたしはアンドロイドなのだよ。ふつうの女子高生の生活が覗けると思ったら大間違いだ。 とは言えわたしだって、お風呂には入る。アンドロイド用の入浴剤入りだけど。それから、トイレにも行く。まあ、構造は人間と同じだからな。あと、愛らしい仕草でごはんも食べるし、かわいいパジャマ着て夜は眠るし、あと、女子高生型アンドロイドだから女子高生がすることはたいがいする。だからキミがわたしの体で欲情しようと思えば、いくらでもできるわけだよ。 どうしたもんかな。 とは思うけど、でも見られるのも悪くない。 クラスメイトやお父さんには見られたくない。でもバッテリーの中に入ってるのは見ず知らずのおっさんで、ここから出ることもできず、ここで人生を終えるひとだ。そのひとが、わたしに触れることもできずにもがいてるんだよ? だったら見せてやりたい。わたしがどんなに厭らしく、えげつないか。それで欲情できるなら欲情しろ、変態。 耳を当てると、ハーモニカの音が聞こえる。 聞いたことある曲。 ビートルズだね。アクロス・ザ・ユニバース。古澤くんが弾いてたの聞いたことある。 シェイクしてみると、しばらく曲が途切れた。 頬を当てると普段よりちょっと熱を持ってるかな? でもそれ以外には変わったようにも思えなくて、手近にあった掃除機にセットして使ってみた。 がががー。 まあ、掃除機は問題なく使える。いや、でもまてよ。ちゃんと使えるってことは、故障はしてないってこと? てことは……インバーターかなあ。 食事の準備が終わって、食卓についた。 アンドロイド用の味付けはどれも薄くて、お父さんはいつも醤油を足した。 「お父さん、あのね」 「ああ、ごめん。醤油かけすぎちゃったね。せっかく悠子が作ってくれたのに」 「醤油じゃなくて。わたしのバッテリー。なんか、くたびれてるの本体じゃなくてインバーターみたい」 「ああ、それじゃ電解コンデンサかな。あれも劣化するからね」 「新しいの買って」 「うん。こんど嘉穂に行ったとき見ておくよ」 「うん」 まあ、だいたいは口約束。パーツセンターにはちょくちょく行ってるくせに、わたしが頼んだものを買ってきてくれるのは稀。ネットでなんでも買える時代に、何ヶ月も待たされる。 「それまでは、バンのなかに使えるのがあるはずだから、それで代用するといいよ」 バン。そっけないなあ。みー子のこと、車呼ばわりだ。 「わかった。探してみる」 「みー子、入るよー」 ドアを開けると、みー子は明かりをつけてくれる。 「あ、お姉ちゃん、どうしたの?」 「電解コンデンサ、余ってない?」 「わかんない。何に使うの?」 「インバーター用。どれかわかる?」 「円筒形のやつでしょう? いくつかあったと思う。テキトウに持っていって」 しばらくみー子のなかでコンデンサを探した。あれこれ棚を開けて、パーツを手にとってみるけど、目線は泳いで気持ちも定まらない。見つけたところでさあ。どうせわたし、駄目なんだよ。 「バッテリーのなかのひとはどうなった?」 みー子が聞いてくる。 「たぶん、まだいると思う」 「えーっ。なんか気持ち悪くない?」 「うん。ちょっと。もしかして、ほかのひとの体にもいるのかな、小さいおっさん」 「いないいない。いるわけない」 まーそうだよねー。でも、ほかのひとの体のことはよく知らない。 「だよねー」 自分の体は分解して隅々まで調べた。古くなったパーツとか、動いてないパーツとか、組み立てるときに余ったパーツとか、たくさんある。よくこんなんでわたしちゃんと動いてるなって思う。考えないようにはしているんだけど、ふとしたきっかけで不安が吹き出すことがある。わたしが生きてることって、なにかの間違いなんじゃないかって。 「人間になりたい」 「またそれ?」 うん。わたし、みんなと同じになりたい。 「人間になったら、修理しなくても勝手に治るんだよ」 わたしは傷ついたら、傷つきっぱなし。 「わたしからしたら、お姉ちゃん、人間にしか見えないけどね」 「うん。ごめんね。わたしだけ人間になって」 「あーもう。それも気にしないでって。お父さん、わたしにもちゃんと体を作ってくれるよ。いつか」 バッテリーのせいでよく意識低下が起きた。 ソファでうとうとしてると、お父さんに肩をゆすられた。 「悠子、ちょっといいかい?」 「なあに? バッテリー?」 「いや、駆動系の動力炉だけど」 そっちか。 「セバスチャンの動力炉と交換してもいいかな」 えっ? ポンコツ執事と? 「向こうはずっと働き詰めだろう? 悠子は学校から帰ったら動力炉は休ませればいいから、そのほうがリソース効率がいい」 セバスチャンの動力炉って、すごく旧型じゃない? 「それだと、体育がある日困る」 「じゃあ、体育のある日だけはセバスチャンのと交換したらいい」 「えーっ」 でもしょうがないか。わたしが買った部品でもないし。 「わかった。でもその代わり、自転車にブースターつけて」 「自転車にブースターかあ……芸がないなぁ」 「芸なんかどうでもよくない?」 「通学が辛いんだったら定期券を買ってあげるよ。久大線で通うようにしたらいい」 「えーっ?」 「それでいいだろう?」 「やだー。旧式の動力炉はやだー。久大線もやだー」 はっきりと断ったけど、朝起きたら動力炉は勝手に取り替えられていた。 「お父さん! 勝手に改造しないでって言ってるでしょう!」 「勝手にじゃないよ。昨日断ったよ」 「改造しないでって言った!」 「そうだったかなあ」 「動力炉もとにもどして!」 「そう! それなんだよ! 見たら悠子も気にいると思うよ」 お父さんは意に介さず。手を叩いてセバスチャンを呼んだ。 「ゴヨウデショウカ、ゴシュジンサマ」 うぃーんとキャタピラ足をうならせて執事ロボ登場。 「見てくれ! 執事ロボ・セバスチャンⅡだ!」 セバスチャンはムキムキマッチョに改造されてた。 「そんなぁ……」 思わず口に出た。こんなことのためにわたしの動力炉は奪われたんだ……わたし、壊れても修理してもらえないのに。こんな……こんなもののために……。わたしは悔しくて泣いた。 お父さんはわたしをなだめようと、自転車にブースターを付けてくれたけど、やっぱりブースターなんか要らない。動力炉返して。 とは言え。とは言えだよ。 ブースター付きの自転車は最高に気持ちよくて、普段25分かかる通学路を20分程度で走ることができた。びゅんびゅんと、風が気持ちいい、月曜日。悠子。 飛び込んでくるクラスメイトを躱す廊下。相変わらず朝から騒がしい教室。無理に出ていこうとする男子とすれ違い、席へ。授業が始まるまで10分。やることもない。いつものように顔を覆って待っていると、胸の中のハーモニカが鳴り始めた。どうしたんだろう、急に。 顔を上げると、古澤くんがいた。 目が合うと、更に高らかに鳴り響く。 なにこれ? それからもずっと。古澤くんが近くを通るたび、声を聞くたびに、思い描くたびに胸の中のハーモニカが鳴った。正確にいうと、バッテリーの中に住んでる変態のおっさんが裸でハーモニカを吹き鳴らし踊っている。 もしかして、おっさん、古澤くんに恋をした? さすが変態だ。雑食だな。わたしちょっとそれ応援できない。いや、でもちょっと見たい。どっちがどう、なにをするのか。 4時間目は体育。あちゃーって感じ。 お父さん、体育がある日は動力炉を交換したらいいって言ってたけど、朝っぱらにそんな時間があるわけない。しかもよりによって持久走。千二百メートル。そして案の定、リアクターのオーバーロード。お弁当の時間はパスして保健室。5時間目も保健室。お弁当持ってきてもらって食べた。 「おっさん、変なんだよ。みー子」 学校のことをみー子に報告するのがわたしの日課。 「変って、何が?」 「古澤くんを見ると、ハーモニカ吹き鳴らすの」 「えっ? それってもしかしてさあ、恋じゃない?」 「やっぱりそうだよねー。古澤くん、おっさんまで虜にしちゃうんだ」 「あ、いや、おっさんじゃなくて。お姉ちゃん」 「えっ?」 「恋してるの。お姉ちゃんだよ、たぶん」 「わたし? わたしがだれに?」 「だれにってその、古澤くんに」 「えっ? でもわたし、アンドロイドだよ?」 「関係ないよ。お姉ちゃん、人間と同じ構造してるから、恋だってするよ」 「そうかなあ」 恋なんかしたことなかったけど―― 「照和ってライブハウスの前でピピッて来たんでしょ? 天神のにぎやかな街で古澤くんが弾いてた曲が流れてきてー、都会のイメージと古澤くんのイメージがピピッてなってー、それから意識するようになったんだよ」 「えーっ。そうかなぁー」 「ラジオで似たような話、してたよ」 そうか。ラジオか。 みー子はこの車から出たことがない。世間のことはすべてラジオで知った。あとは小さな窓から見える町並み。それが、体を持たないみー子の世界だった。 「アンドロイドも同じなのかな」 「わかんない。でも、ラジオのリスナーの半分くらいはアンドロイドだと思うよ」 「そうだね」 あ、いや、まって。そうなの? みー子はラジオをつけてくれた。 「夜聴くラジオは夜が似合うし、昼聴くラジオは昼が似合うね」って。 そう。ラジオはいつもそう。ひとりで聴くラジオはひとりが似合うし、みんなで聴くラジオはみんなが似合う。ラジオの電波を選りすぐっていると、コンコン、と窓を叩いて 「悠子、ちょっといいかな」 と、お父さんの声。 「いいけど、どうしたの?」 星の降る夜に向かってドアを開いた。 「消化器系の部品が足りないんだ。少しパーツを借りてもいいかな」 「消化器? それどうするの?」 「セバスチャンにも食事をさせてみようと思ってね」 またセバスチャン。 「わたしのはどうなるの?」 「そうだなあ。野菜が消化しづらくなると思うけど、まあ、咀嚼したものがそのまま出るくらいだから問題はないよ。別にひとに見せるものでもないし」 「それはそうだけど……また人間から遠ざかる……」 「またそんなことを。悠子はもうじゅうぶん人間だよ。人間だったら、セバスチャンの気持ちもわかるだろう?」 「うん。わかるけど」†
ある夜、目を閉じたとたん、 わたしは星ひとつ無い、 真っ暗な闇の夢に、落ちて行きました。 そこには、わたしの意識の火が ちらちらとひらめいているだけで ほかには何もありませんでした。 わたしが暗闇の中に、最初の光をみつけると、 せきを切ったように、たくさんのうずまき銀河が生まれ、 わたしはその銀河の一つに、 吸い込まれていきました。 星々が織り成す光の渦 すくい上げてみると、 それは長い長いほうき星の尾。 その尾をたどって、わたしは 一人の星に出会いました。 星はわたしに言いました。 ほうきぼしの尾の先は、50億年前の光。 わたしが夢に落ちて、もう50億年の時が流れ そしてこの星のゆく先に、 まだ何十億年もの時間が流れているんだって。 星の光流れる銀河の川面 星はわたしに聞ききました。 「もっと深い夢に落ちてみる?」 わたしが小さくうなずくと、 星の引力がわたしを捕まえた。 星はわたしを飲み込んでいく わたしは一直線に、どこまでも、 どこまでも深く、深く、落ちて行ったのでした。†
次の日は個人面談。 「リハビリテーション専門学校はどうだった?」 と、中村先生。 「それが……間違って天神まで行って……歩いて折り返そうと思ったら、貧血で倒れて……」 「ああ、そうだったな。あのときがそうか」 人間はあまり物覚えがよくない。アンドロイドでも圧縮率の高いアルゴリズムを使っていると、記憶のディティールが下がったりするけど、中村先生やクラスの子たちを見てると、その比じゃない。 「ちなみに、どうしてリハビリテーションを?」 「わたし、アンドロイドだから。人間に奉仕したいんです」 「ああ、そうだったな。だけど心配だよ」 「何がですか?」 「秋山の健康状態。ひとの健康を心配している場合でもないと思うんだがね」 「うん。でも、それがアンドロイドだから」 アンドロイドだから。 人間の古澤くんには、人間の権丈弓子という彼女がいた。 弓子は友だち。とても歌が上手い子。自分で歌詞まで書いているし、古澤くんが曲をつけているらしい。だれもが羨む公認のカップル。なのにわたしは、恋をしてしまった。いわゆる横恋慕。 古澤くんが視界に入ると、胸の中の裸のおっさんがハーモニカを吹いて踊りだす。いいや、違う。胸のなかにいるのは、たぶんわたし。裸でハーモニカを吹いているのはわたし。なんてあられもない。変態だ。きっと、わたし。 で、その古澤くんと弓子はいつもふたりで話をしている。回帰型ニューラルネットワークのエラーのせいか、ハートが飛び交って見える。たぶん、漫画やアニメと混同してんだと思う。 人間の恋愛のことは漫画で知った。ファッション雑誌からもあるけど、それよりも漫画。わたしにとって、ファッション雑誌はグラマーで、漫画がリーダー。恋愛と漫画は不可分。ハートやバラが見えるの、そのせいだ、きっと。だけどさあ、みー子。アンドロイドの恋の話はだれも知らないんだよ? わたし、どうすればいいの? 3時間目が終わって、古澤くんと弓子が新曲のこと話してて、昼休みに部室でどうこうって、それ聞いちゃったらわたしもどうにも抑えが効かなくなって、お弁当食べたそのあと、軽音部の部室についていった。恋ってやばいよ。なんでこんな非合理的なことやってんだろう。そもそも横恋慕だし。いや、でもほら。人間じゃないから、アンドロイド枠ってのがワンチャンありかもしれない。 部室に入ると、何人かが振り向いて、『へ』とか『ほ』みたいな顔をする。右から順に、へ・へ・ほ・へ・ほ・ほ・へ。部外者が来たときの顔って、どんなシチュエーションでもたいがい同じ顔。へかほ。こういうのどこで覚えるのかな。とりあえずわたしはすまなそうな笑顔で、「はじめまして」の『は』。 古澤くんと目が合う。 途端、わたしの胸の中の裸のわたしが、ハーモニカを吹いて踊りだす。変態、秋山悠子名物、裸ハーモニ――弓子がちらりとこっち見た。なんか馬鹿にされた気がする。気にしないで、わたしのことは。見てるだけが好きなの。 「とりあえず、撮ってみる?」 と。古澤くん。 「うん。流して最後までやったのチェックしたい」 あとはモブ。 「じゃあ、僕のスマホで」 「喉バッチリ。どの曲から?」 「新曲。ガラス石」 「OKー。じゃあ、ワンツーで」 モブたちの静寂。 ワン、ツー、で、曲が始まる。♪
海風にゆれる とりたちの声 まだ冷たい水を 手のひらに掬う ガラスの小石 砂にならべて 終わった恋の話 指で弾いた 寂しさばかり 詰め込んだサマータイム 片思いのまま 溺れたびーどろ 枕かかえて 瞼はらした さびしがりやの わたしをみつけて 昨日までふたり それぞれの恋 気にも留めないで 笑っていたけど ビーチサンダル 片手に下げて 波の音に紛れて 指を繋いだ 戸惑いばかり 溢れ出すサマータイム タオル肩にかけ 差し出すレモネード 椰子の木陰で 肩寄せあった 君に出会えた 青いガラス石 枕かかえて 瞼はらした さびしがりやの わたしをみつけて みつけて みつけて♮
詩はよくわからないけど、恋の歌だというのはわかった。 ラストはか細い声で切なく訴える。 胸を締め付けられた。 これが、ココロか。十三・夢見るセラミック人形
わたしのなかのハーモニカ吹きは、古澤くんのことよりも、弓子のことを求めているような気がした。それにわたしなのに、わたしの知らない曲を吹く。データベースと照合して、ああ、なるほど、この曲かーって。 みー子に話したら、 「それ、古澤くんの生霊なんじゃない?」 って答えが返ってきた。 生霊? 「っていうか、生霊に取り憑かれたアンドロイドっているの?」 「わかんない。ぐぐってみる」 便利だな、みー子。このへんにあるガラクタぜんぶみー子なんだ。わたしより高性能なんじゃないかな。 「いない。生霊に取り憑かれたアンドロイド、お姉ちゃんが世界初だよ」 「おお!」 持久走で倒れてからだと思う。右脚股関節のカムリングに異常が出てる。無理にひねっちゃったからたぶん、シャフトが何本か折れたんだと思う。ずっと足首の不調を庇ってきたから、金属疲労が溜まってたんだ。 修理しなきゃいけないんだけど、お父さんにはできるだけ会いたくなかった。 内臓だったら外されてもいいけど、腕とか足を取るって言われたら学校でどう説明したらいいかわかんない。右脚のシャフトが折れたなんて言ったら、セバスチャンの脚部と交換しようなんて言われるかもしれないし。 ――セバスチャンは手仕事が多いからね。脚は飾りでもいいんだ。悠子は移動する必要があるだろう? だったら交換したほうがリソース効率がいい。 なんて言って。 セバスチャンの脚部はキャタピラ。そんなのと交換したらみんなから白い目で見られるし、自転車にも乗れなくなる。 昼夜逆転してるお父さんを起こさないように、静かに晩ごはんの準備。セバスチャンも寝てる。ていうか、おまえが働けよ。執事なんだろう。もう。 野菜は咀嚼したものがそのまま出てしまって、なんかもったいない気がするから、お肉とご飯だけ。彩りがない。でも、お肉美味しい。タレが染みたごはんも最高。焼肉のタレって、アンドロイド用の麻薬かなんか入ってんじゃないかな。 「悠子……」 焼き肉食べてたらお父さんが起きてきた。なんか気まずい。 「晩ごはん食べてたの。今日は焼き肉だよ」 「ああ、美味しそうだね。そんなことより、悠子」 やだ。お父さんの話なんか聞きたくない。 「お父さんのぶんの野菜、切ってあるよ。持ってこようか?」 「悠子の健康管理アプリから、ずっとアラートが送られてくるんだけど、シャフトが折れてるんじゃない?」 気づかれてた。 「わかんない。折れてるかもしれない」 「そのままにしておくと、股関節に負担がかかって、最悪、脚取れるよ」 やだ。言わないで。わかってるよ、そんなこと。 「左足に体重かけてるから平気」 「セバスチャンの脚部と――」 「脚は換えない!」 思わずテーブルを叩いて立ち上がった。 「わがまま言わないで。そのままだと壊れて使い物にならなくなる」 「イヤなの! 壊れてもこの脚がいいの! あんな足つけたらみんなからガンタンクって呼ばれる!」 「ガンタンクとは違うよ。セバスチャンの足回りはクリスティー式サスペンションだから、時速80キロは出せるんだよ」 「そういう問題じゃないの! 人間なの! 人間として暮らしてるの! その暮らしを奪わないで! 学校に行きたいの! 友だちと話をしたいの!」 もうやだ。涙が止まらない。アンドロイドでも涙は出るんだ。でもこれもお父さんが、悲しいときはこうやって泣くようにプログラムしたからなんだ。 「気持ちはわかるけど」 気持ち? 気持ちってなに? そんなのわたしにもわかんないよ。なんでお父さんにわかるんだよ。 「悠子はアンドロイドだよ」 言うなぁーっ! そんなことはわかってるから、言うなぁーっ! 「悠子の幸せは、お父さんが一番わかってる」 そんなわけない! ぜったいにそんなわけない! もうやだ。涙が止まらない。ノード検索ぜんぶエラーになる。エラーだらけ。ログが真っ赤だ。ねえ、古澤くんっ! ハーモニカを吹いてよ! いますぐ! このままじゃわたし……このままじゃ……! その日の夜は、みー子のなかで眠った。 「お父さんが来てもドアを開けないで」 「わかった。ぜったい開けない」 わたしの気持ちの揺れをみー子はすぐに察してくれた。 「ごめんね」 「ごめんねって、なにが?」 「わたし、いつかみー子にも人間の体を作ってあげようと思ってた」 「えっ!? お姉ちゃんが?」 「うん。でもなんか、もう無理」 「アップダウン激しいなぁ。その理由は? 理由を教えて」 「わたしたち、人間にはなれないんだよ」 「そりゃそうだよ。でも、だから? って感じ。別にならなくていいしさ。人間になんて」 「ごめんね。なにもしてあげられなくて」 「だからあ。わたしはべつにいいんだよ。このままで。お姉ちゃんの問題だよ。だってお姉ちゃん、恋をしているんでしょう?」 ――恋。 「それをかなえて欲しい」 「わたしが、恋をかなえる?」 「体とか関係ないよ。ココロの問題でしょう? 恋の話なんて、ラジオでしか知らないけど、それをお姉ちゃんにかなえてほしいの」 「そんなこと言ったって、わたし、アンドロイドだよ?」 「お姉ちゃんの物語には続きがあるんだよ。アンドロイドとして生まれて、クラスメイトの生霊が憑いて、その先があるんだよ」 「でも、古澤くんには彼女がいる」 「どうでもいい! わたし知らないもん、そんなひと!」 「知らなくったって、いるんだよ。実際に」 「ラジオしか知らないの。わたし。だから――」 午後4時のチャイム。 「九州芸術工科大学?」 中村先生を廊下で呼び止めて、進路のことを話した。 「無理でしょうか」 「いや、まだ一年以上あるから、目指してみるのは悪くない」 「じゃあ、それでお願いします」 「だけど、なんで」 「わたしはわたしを修理したい」 「またその話か」 先生はまだわたしがアンドロイドだって話を信じてはいなかった。だから、 「妹にも人間の体を作りたい」 と言うと、呆れたようにため息を漏らした。 「三年は理クラにするか?」 「はい。それで」 ――もうお父さんに頼りたくない。ふたりで家を出るんだ。ふたりで暮らすんだ。†
星の中には、『あたたかさ』だけがありました。 そしてその『あたたかさ』の中には、 『あたたかさのひと』がいたのです。 あたたかさのひとは、光をまるめて、 小さな土のかたまりを作っていました。 きたるべき時に、ひとの形となるように、 小さな土のかたまりを作っていたのです。 やがて、たくさんの土のかたまりは、 まぶしい光をはなちはじめ、 星は太陽になりました。 輝き始めた太陽の中、 土のかたまりは呼吸をはじめました。 土のかたまりは口々に言いました。 ぼくたちは人間になった! 人間おめでとう! 土くれのひとに、わたしは聞いた。 「これからどこへ行くの?」 「みんなココロなしだから、どこへも行かないの」 「あなたにはココロがあるの?」 わたしは首をよこにふる。 「そうか。じゃあどこにあるの?」 こたえあぐねて天をあおぐと そこには太陽が輝いていました。 足元には荒涼とした砂漠が、どこまでも広がり その砂の星で、あたたかさのひとは言ったのです。 「土くれのひとが、ココロを手に入れるまで、 わたしたちは風の中に、水の中に、大地の中に住まおう。 そしてまた会いましょう、土くれのひと。 またどこかで出会ったら、お互いに再会の挨拶をかわそう」 あたたかさのひとは精霊になって、 星のすみずみまで散らばって行きました。 やがて大地から、草木が芽吹きました。 空には雲が立ち上り、雨を降らせ、山河を築き、海へと注ぎました。 空には鳥が歌い 辛いときと、楽しいとき、 さわやかなときと、どんよりしたとき、 いろんな気持ちの間をさまよって、 やがて土くれのひとはココロを手に入れたのでした。†
目を覚ますと、両腕を天井から吊られていた。 薄暗い部屋。 どうしたんだろう。 革紐から手を抜いて足元を見ると、そこにわたしの足はなくて、寸胴のコーヒーポットにキャタピラをつけたような脚部に置き換わっていた。やられた。脚だけは嫌だって言ったのに。これじゃもう学校に行けない。絶望して涙が出る。何度目だろう、こうやって泣くのって。 「オメザメデスカ、オジョウサマ」 セバスチャンの声が聞こえる。自動扉が開いて、姿を現す。 「ゴシュジンサマハ、オデカケニナラレテマス」 セバスチャンの無骨な体の下半身に、わたしの足がついていた。 胸のなかの古澤くんはもうハーモニカを吹かない。 わたしがこんなふうになったことに気がついているんだ。もう嫌いになったんだ。みー子、ごめん。めげそう。もう生きてるのやだ。わたしなんで生きてるんだろう。なんで生まれてきたんだろう。 でも悔しいことに、わたし、死ねないんだ。だってわたし、ロボット三原則――第三条、ロボットは己の身を守らなければならない――を、守るようにできてんだよ。自分の気持にさえ従えない。なんなの、この人生。 学校に電話をかけた。今日は休みますって。本当は辞めますって言いたかった。でもそんなこと言って家庭訪問されるのは嫌。 キャタピラの脚部は大きくて、今までと感覚が違う。部屋の中であちこちにぶつけた。段差があると躓く。戦車みたいにいろんなところを走れるはずなのに、上半身でちゃんとバランスを取ってないとすぐに転ぶし、転んだらセバスチャンを呼ばないとひとりで起き上がれなかった。セバスチャンはそんなに転んでなかったし、たぶんコツがあるんだと思う。だけどそれをセバスチャンに聞きたくなかった。 ぐぐればいいんだ。 ロボット、キャタピラ脚。 案の定ガンタンクの画像が出てくる。 クソ。クソが。クソクソクソ! ふざけるな! こんなもの、わたしの視界に入れるな! ――どうしてアニメのロボットは二足歩行なんですか? ――ロボットはキャタピラのほうが安定するのではないのですか? 何もわかってない! そんなこと言うんだったら、おまえがキャタピラで学校に行けよ! わたしはどうすればいいのよ! 自転車にも乗れないし、階段も上がれない! 二年三組の教室まで行けないし、椅子にも座れない! 学校に行ったって意味ないんだよ、もう! 胸のなかに静かにハーモニカがなり始める。 古いJポップ……記憶照合……岡村孝子……夢をあきらめないで…… 古澤くん……。音が震えてる。泣いてるのかもしれない。わたしといっしょに。 みー子のもとへ。わたしの脚部を見るなり、「どうしたの!」の声。そりゃあ驚くよね。この足じゃ。車の外にシートベルトをひっぱって、上半身を固定、持ってきた工具でキャタピラ足を切り離して、臍から上の半身だけでみー子のなかに潜り込んだ。 「お父さんにやられたの?」 「そう。セバスチャンに足をつけたかったんだって」 「セバスチャンって、執事ロボットの?」 「そう。いまあいつ、わたしの足がついてる」 「どうするの?」 「中学のときに使ってたのがあるから、それを取り付ける」 「ああ……」 みー子の少し沈んだ声。いつかみー子がちゃんとしたアンドロイドになるとき用に取っておいたものだ。 「ごめん、みー子。でもあなたのことはわたしが責任をもってアンドロイドに……てか、人間にしてあげる。だからいまは足を使わせて」 「うん。もちろん。もともとお姉ちゃんの足だもん。問題ないよ」 上半身だけになった体でガラクタの山から古い脚部を引きずり出す。なん本もコードがからまって、傷も油汚れもあるし、シャフトが少し曲がっている。だけど、わたしの足だ。この足で立つんだ。ぜったいに。 わたしが涙を拭うと、古澤くんがハーモニカを吹いてくれた。 ガッツだぜ、負けないで、何度でも……。 データベースから歌詞を照合。わたしが歌うとみー子も声をあわせた。 負けないよ。負けるわけがないよ。わたし、人間になるんだ。人間になって、こんな家、出ていくんだ。十四・あの日にかえりたい
足がちゃんと動くようになったのは夜明け前、5時くらいだと思う。わたしの旧型のリアクターですっかり温まっていた室内の空気も、少しづつ流れ込む外気と混じり合った。あとは充電さえ済ましたら、いつも通り学校へ行ける。 「少しだけ眠るね」 「うん……おやすみ……」 みー子も眠たそうだった。 睡眠2時間半。プラグを抜いてみー子の外に転がり出る。やっぱり足があるっていい。こうしてほら、転がってるセバスチャンの足を蹴飛ばせる。部屋に駆け込んで急いで着替えて、ブースター付きの自転車にまたがる。 二足歩行、最高! 新しい足……というか取り付けた古い足はローティーン向けの製品、ジョイントを最大まで延ばしても、身長は2センチ低くなった。傷が多くて、厚手のタイツを履いた。塗装も剥げてところどころ凹んでる。でも、昨日まで動かなかった足を自分で動かしたんだ。わたしはついに、大きな一歩を踏み出した。 学校まで18分。始業まで10分。いつもと違う一日が始まる。バッテリーのなかの古澤くんも、今日はポルカを吹いてる。踊りだしそう。ドアをあけて席へ。弓子がわたしの顔を見つけて、開口一番、 「昼休み、ちょっと話がある」 って、深刻な表情。 話ってなんだろう。 古澤くんのハーモニカが止まった。 学校でいちばん空に近い場所。屋上。塔屋の上。弓子の背景には秋の凛とした空があった。 「古澤くん、あなたのことが好きなんだよ、本当は」と、弓子が切り出した。 いきなり来た。 「でもわたし、彼とつきあってるの」 苦悶の表情で続ける。 知ってるけど。どうしてそんな話するの? 「あ、うん。そうだと思った」 静かに返すと、ひとつ息を呑んで、弓子はわたしの目を見た。 「どのくらい不安かわかる?」 不安? いきなり聞かれても……とは思ったけど…… 「うん。わかる気がする」 わたしがそう言い終えるやいなや、 「じゃあもう、軽音部室に来ないで」 弓子は低い声で吐き捨てた。 リアクションに困る。さっきわかるって言っちゃったし、否定はしにくい。でもここで「ああ、はい、そうします」なんて言ったら、そっちのほうが喧嘩だよね。 「どうしてそんなこと言うの?」 おずおずとたずねると、弓子は涙を流し始めた。泣きながら、作り笑顔で、 「ごめん。いまの嘘。忘れて。わたし、どうかしてた」 そう言って頬の涙を拭う。 でもそれはないよ、弓子。なんなのそれ。 「忘れてって。そういうのズルくない? わたしに荷物背負わせて、じぶんは泣いて『忘れて』って、ひどくない?」 「ごめん。本当にごめん」 弓子が無理して貼り付けていた笑顔が消えて、悲しみだけが残った。 ずるいよ、それは。わたし、なにを察すればいいんだよ。 「わたし、アンドロイドなんだ。本当に。だから恋愛は無理なの」 なに言ってんだろう、わたしも。 「わたしもたぶん、古澤くんのこと好きなんだと思う。でもそれって、そういうふうにプログラムされてるだけなの。だから、わたしじゃ無理だから。古澤くんのそばには、あなたがいてあげて」 やばい。今度はわたしが涙が出てきた。でももう引き返せない。 「見て。ほら」 ブラウスを開けると胸にはハッチがある。涙の雫がてんてんと落ちて、開くと中の機構が見えた。 「これがバッテリー」 手も声も震える。 「記憶装置用で85ボルト。動力用のリアクターはこの裏側。こっちの細い線が排熱用のダクトで、水冷式になってて、指先に熱を送ってるの」 弓子は頬に涙のあとを残したまま、目を見開いてわたしを見てる。 「珍しいよね、アンドロイドって」 小さく頷くだけ。かなり混乱してるみたい。わたしは涙が止まらない。もう無理。言葉にならないよ。ずるいよ、弓子は。 古澤くんが胸のなかでハーモニカを吹いてくれるから、生きるって決めたのに。 独り占めするなんて。ずるいよ、弓子は。 もういちど古澤くんのギターを聞きたかった。 弓子と別れたあと。胸のなかにいる古澤生霊がハーモニカで慰めてくれるけど、もう惑わせないで。アンドロイドなんだから、恋なんかしないよ、本当は。命だってないんだよ。生きてるってわたしが思いこんでるだけだし、恋だって幻想なんだから。わたしの感覚なんて嘘なんだよ、ぜんぶ。 自転車を押して泣きながら帰った。 泣いてると、胸から何かこみ上げてきて悲しみでいっぱいになるけど、これだって人間と同じ悲しみかどうかわからない。人間がどうやって悲しむかも知らない。わたしはただ悲しんでるふりしてるだけなんだ。でも悲しいんだよ。止まらないんだよ。 「みー子、ごめん」 部屋に帰らず、制服のままみー子のドアを開けた。 「わたしもう、生きるの無理」 みー子はなにも言わない。電気をつけてくれただけで。 「生きるとは言わないか。アンドロイドだし。でももう、なにも感じたくない」 ドアを閉めると電気が消える。 「ねえ、みー子」 返事がない。あらためてあたりを見渡すと、わたしが足を引きずり出したガラクタの山が崩れてる。絡んでた配線も切れてる。 「みー子?」 返事がない。 「みー子! ねえ、みー子!」 みー子がいない。わたし、自分の足のためにあの子を壊しちゃったんだ! どうしよう。考えてもなにも浮かばない。あの子を生き返らせるアイデアもなければ、肉体を持たなかったあの子の顔も姿も浮かばない。なにもかもだめじゃん! なにやってんだよわたしは! あーもう! なんでっ! なんでっ! なんでっ! みー子のなかで暴れていたらお父さんが呼びに来た。 「どうしたんだ、悠子。感情回路がアラート出しっぱなしだよ」 うるさい。ふざけるな。ロボット三原則なんかなかったら、おまえなんか殺してる。 「おいで、悠子。食事ができているよ」 「いやだ。行きたくない。いやだ」 だけどわたしには逆らえない。 ――ロボット三原則、第二条。ロボットは人間の命令に服従しなければならない。 どうしてわたしはっ! 「感情回路も修理しよう」 「いやだっ!」†
夜、星空をあおぐと、星々の光の中から、 無数の宇宙船があらわれました。 宇宙船は、いろんな時代、いろんな星から、 土くれのひとにプレゼントを持ってきました。 火の使い方、 薬のはたらき、 お金の仕組みから、 時間のあやつり方まで。 宇宙から来たひとたちは言いました。 「新しい星、地球へ行こう」 「生まれたての星、地球へ行こう」 「この星は、死後に訪れる星として、 偉大な土くれの星として、 地球を回る星として残そう」 やがて地球へ移り住んだ土くれのひとたちは、 めざましい発展を遂げはじめました。 山を削り、川をせきとめ、海を埋め立て、 空には飛行機が飛び交い、 雨風さえも自在に操り、 星をゴミでいっぱいにして やがて星のあちこちで戦争を始めました。 あるとき、戦争で死んだひとりの兵士が、 月の荒野で目を覚ましました。 上空に浮かぶ無数の宇宙船 兵士はそれを、神様の乗り物だと思い、 束の間、喜び、 その後、3日間ほど自分の運命を呪い、 3日間ほど涙を流し続けました。 その後の3日間を、無言で過ごしたあと、 その足元の土の中に、精霊を見つけました。 精霊は再会を喜び 微笑んでいました。 兵士の目からポロポロとこぼれる涙が、 雨のように精霊をぬらすと 銀河系の、すべての光が兵士に降り注ぎました。 兵士は思いました。 もう一度地球へ生まれ変わろう。 あのひとたちの子どもとして、 あのひとたちの親として生まれ変わり 精霊たちとの約束を果たそう。 飛び交う戦闘機の下で 降り注ぐ薬莢の雨の中で 泣き叫ぶ子どもたちの中で 都市をなめる炎の中で ぼくにすべてをあたえてくれた精霊と このうずまき銀河の、すべての星と 果たせなかった約束を果たそう。 わたしは100億年の夢から目覚める。 小さな赤ん坊として ありがとうを言うために。†
目を覚ますと、気持ちはおだやかだった。 あの男がなにかしたんだ。 胸のなかには古澤くんのハーモニカだけが聞こえる。知ってる曲。ビートルズのイエロー・サブマリン。学校に行かなきゃ。 玄関を出ると、みー子のバンがある。みー子、いなくなったんだそういえば。でも、それってどういうことだっけ。ブースター付きの自転車。いつもの並木道。廊下ですれちがう男子と肩がぶつかる。鞄を落として、中身がこぼれるけど、わたしにはその意味がわからない。 教室には古澤くんがいた。弓子もいた。不安げに目を伏せる。 いっそ爽やかだった、その世界は。 「昨日はごめん、わたしちょっと混乱して」 昼休み。屋上、塔屋の上で弓子は言った。 「昨日もここで話しをしたことは覚えてる」 胸のなかにはずっとイエロー・サブマリンが流れていた。 「大丈夫? もしかしてまだ怒ってる? 昨日のこと」 怒る? どうしてそんなことを聞くのだろう。 「弓子、あなたはアンドロイドのことをなにも知らない。アンドロイドに感情はないの」 弓子の表情がみるみる崩れて、わたしの両肩を抱く。 「悠子は人間だよ。少なくともわたしにとっては。親友だよ」 声が震えてる。どうしたんだろう。 「そうですか。嬉しいです」 弓子の目からまた涙が溢れる。 「ハンカチがあります。用意します。少し待ってください」 「わたしのせいだったら、わたしのせいだって言ってよ!」 弓子は声を上げて泣き崩れる。 わたしは―― 「なかな……い……で、ゆ……みこ……」 あれ? 「き……みを……さが……す……ために……ここに……きた」 弓子がわたしを見上げる。 「いまのはソフトウェアの不具合です。気にしないでください」 「ぜんぶ……ぼくが……すくうから……なか……ないで……」 わかった。バッテリーだ。バッテリーがわたしを乗っ取ってる。 「幹夫……?」 「ゆみこ……も……あきやま……さん……も……」 「不具合です。気にしないでください。ハンカチです。涙を拭いてください」 差し出したハンカチを弓子が受け取ると、わたしの腕は勝手に弓子を抱きしめた。彼女の鼓動がわたしの胸に流れ込んだとき、わたしは体の制御を完全に奪われた。 「大丈夫。僕を信じて」 「幹夫?」 「もうひとつの世界から来た」 「もうひとつの世界って?」 「並行宇宙? 僕にもよくわからない。自分の体に戻るはずだったのに、なぜかこうなった」 「こう? こうって、どう?」 「わからない。ギルデンスターンってひとを探している」 「ギルデンスターン?」 「それと、ローゼンクランツ。バンドをやってると思う」 「わかった。それで悠子を救えるの?」 「うん……だから、ふたりの行方を……」 「わかった」 弓子がわたしを見つめて涙ぐんだまま目を閉じる。軽く閉じた唇が震えている。 わたしは弓子の肩を抱いて、そのままシステムエラーに身をまかせた。 その翌日。 「ついさいきん『隠れ家』でライブをやってたって。ローゼンクランツ」 と、弓子。 「隠れ家……? どうしてわたしにそれを?」 「幹夫に言ったの。文化街のフォーク喫茶、レイニーワールド。ギルデンスターンのこともそこで聞けばわかると思う」 そう言って弓子はハーモニカを手渡してきた。 「わかった? わかったらCの音を出して」 「いっさいわかりません。C? Cとは?」 戸惑っていると腕が勝手に上がって、ハーモニカを口に当てた。 ぷー。 260ヘルツ付近にピークのある振動音。 またバッテリーがわたしを乗っ取ってる。 「システムエラーです。気にしないでください」 弓子が親指を立ててみせると、わたしの体は勝手にビートルズのイエローサブマリンを吹き始めた。十五・亜璃朱の飛行船
文化街。わたしは小さな雑居ビルの一階、寂れたフォーク喫茶の前にいた。 レイニーワールドの朽ちかけた看板には、小さく『旧・HALO SAINT』の文字がある。ぼんやりと眺めていると、男が声をかけてきた。 「まだ営業時間外だよ」 少し離れたところから声をかけて、ゆらゆらと歩いてくる。 「追っかけかい?」 ポケットに手を入れたまま、荷物もない。 「こんな身なりだが、バンドのことは詳しいんだよ。プロモーターをしてたこともあってね。紹介してあげようか?」 訛りの強い独特のイントネーション。 「近くに行きつけの店があるんだ。そこで、どう?」 いわゆる、ナンパ。 統計的な推定から、声を掛けてきたこの男がクソ変態野郎だというのはわかった。こうやって何人も誘って、何人も弄んできた男だ。だけど男が言う行きつけの店、未知のその世界は、わたしの閉ざされた世界の出口のような気がした。わたしの世界は闇。光があるとしたら、この男が通う行きつけの店なのかもしれない。 「その店は――」 どこにあるのか、訪ねようとしたそのとき。 「お待たせ! ごめんね遅れて」 知らない女が声をかけてきた。男を睨みつけ、 「だれ? 知ってる人?」 ハスキーな低い声でわたしにたずねる。 「知らないひとです」 もちろんこの女も知らない。男はそれを確認することもなく、舌打ちして背を向けた。その影が角を曲がるのを待って、女は言った。 「バンドの追っかけもいいけど、このへんは物騒だよ。気をつけて」 はい。そうは思ったけど、声には出なかった。答える義務もない。それに追っかけじゃない。ここに来た理由はわたしにもわからない。ただバッテリーが放つ微弱な信号に駆られただけ。 「店に何か用?」 女は玄関の鍵を開けながらわたしに聞いた。 用なんかない。こっちが聞きたいくらい。それなのに―― 「ギルデンスターンを……」 つい口に漏れる。 でもこれもバッテリーのせい。それなのに、気持ちが乱れ始める。 郵便受けのチラシを持った手を把手にかけて、「へえ」と、わたしの顔を覗く。 「ギルデンスターンを探してるの?」 その目がわたしの気持ちを探している。 だけどわたしが? ギルデンスターンを? なんでそんな素性も知らないやつ。バカバカしい。 ここにいたってしょうがない。用なんてなかったんだ、最初から。 なのに、足が動かない。わけもなく体が震えてくる。 「たすけて……」 またバッテリーのエラーだ。 涙がこぼれてきた。 どうなっているんだ、わたしの体は! 女は優しい目を向けて、息を漏らした。 「話を聞くよ。入って」 涙が止まらない。 バッテリーのせいで。 バッテリーのなかの生霊のせいで。 女は看板を出して、空いたスペースに体を滑り込ませた。 開店前の薄暗いバー。ブレーカーを上げて明かりを灯す。 エアコン、換気扇、留守番電話。 「こんな話、聞いたことある?」 背の高いグラスにオレンジジュースを注いで、女は話し始めた。 「この世界は、ふたつの世界線に分離したの」 穴の空いた透明な氷。黒いストロー。ガラスのテーブルトップは、汗をかいたグラスをさかさまに映した。 「ひとつは昭和が存続した世界。つまりこの世界。もうひとつは元号を捨てて、西暦を採用した裏世界。どっちが本当の世界ってことはなくて、どっちに住んでるひとも、自分の世界が本物だと信じてるんだって」 部屋の片隅にはアップライトのピアノ。壁のキースヘリング。女はグラスを傾けて、氷を回しながら言った。 「想像してみて。もうひとつの世界で、自分は何になって、何をしているか」 もうひとつの世界……。 わたしの胸のなかに、人間になったわたしが思い起こされた。 ――わたしは無理だろうな。 ――無理ってなにが? 友だちになるのが? ――そう。わたし、アンドロイドだから、友だちできないの。 その世界で、わたしには人間の彼氏がいて、アンドロイドの話も他愛のない嘘。 女は静かに問いかける。 「この世界が、なぜふたつに別れたかわかる?」 いきなり聞かれても、わかるはずがない。推測するとしたら、そもそもこの宇宙が表裏のない四次元球体だから。観察される反物質の量が圧倒的に少ないことから、反宇宙の存在が予測されている。 と、考えていたら、 「多くのひとたちは、この分裂は戦後の混乱がもたらしたものだというけど、わたしに言わせたら大きな大間違い」 という不可解な答え。 多くのひとが? 戦後の混乱? 大きな大間違い? 「この分裂の原因は、日本初の元号が定められた大化の改新にまで遡る」 なんなのそれ。 「国の定めた暦がひとを支配したときからずっとこの世界は、いいや、この宇宙は分裂しているんだ」 人間の会話には脈絡がない。まさかの日本史の話だった。しかし神代以降の日本史で宇宙の構造に言及するのは趣深い。続きの言葉を待っていると、女はわたしの目を覗き込んだあと聞いた。 「あんた、アンドロイドだね?」 なにも話してないのに、どうしてそれが? 「しかも、バッテリーに異常がある」 そんなことまで…… 「……どうして、わかったんですか?」 「わかるよ。わたしも昔そうだった」 このひともアンドロイド……? 昔ということは、いまはそうではないの? 「地下にわたしが使ってたのと同じバッテリーがある。試してみる?」 まって、理解が追いつかない。それに試すといっても、試してなにがあるというの。バッテリーが復活したところでなにも変わらない。それに、どうしてこのひとは…… 「どうしてそこまでしてくれるの……?」 女は親指を立てて、地下室へと降りる小さな階段を示した。 「言っただろう? わたしもあんたと同じだったんだよ」 スマホで足元を照らし階段を降りる。地下一階にも別のカフェがあった。古い壁紙の匂いをくぐりながら、女は続けた。 「あんたくらいの歳で、ヤケを起こしてね。もしかしたら、もう一つの世界のわたしは、あんたがやろうとしたことをやったかもしれない」 わたしがやろうとしたこと……。 「だけどもしそうだとしたら」 階段に響くブーツの音。 「わたしはその、もうひとりのわたしを助けに行きたい」 地下二階は暗闇。スマホの光が部屋を舐める。 「ここだ」 白い小さな光のなか、ブレーカーをあけレバーをあげると、昭和レトロな懐かしい喫茶店が姿を表した。 「ここがわたしたちの『隠れ家』、第二の照和だ」 ここが……ローゼンクランツがライブをやった…… 不思議な形のテーブル。ブラウン管状のものが埋め込まれ、両側にはレバーとボタンがついている。その上にはアルミの灰皿と、丸い貯金箱状の謎の装置。 「天神の照和は知っているだろう? 伝説のライブハウスだ。そこが78年に店を閉めて91年に再開するまで、わたしと八重樫はここを拠点にしていたんだ」 78年、91年、ともに無効な数値。 「それだと70年代にはバンド活動を行っていたことになります」 「ああ、そうだよ。とっくに還暦は過ぎてるからね」 なるほど、そういうことか……。 「本当なら孫がいる歳だ。時間に置いていかれたんだ。淋しいもんだよ」 たしかにここには、同じ時間がずっと繰り返し、繰り返し流れている。 そういえば……。 「さっき言っていた、八重樫というのは?」 「八重樫はわたしの弟子だ。いまもあの頃を忘れてないなら、ギルデンスターンと名乗っているはずだ」 ギルデンスターン!? 「そのひとは、どこに?」 「死んだよ。睡眠薬を100錠も飲んで」 ローゼンクランツは静かに答えた。 何度も問われ、何度も答えてきた問いに返すように。 「おいで。こっちだ」 指し示した壁に小さな柵のある入り口。扉はないがエレベーターだ。 「昭和初期のものだが、なんとか稼働している」 ドアの横には下向きの三角のボタンがあるだけ。だけどここは地下二階。いったいどこへ続いているのだろう。促されるがまま乗り込むと、エレベーターはがたんと大きく揺れて、不安定な速度で下り始めた。 「このビルは元号が変わるたびに1フロアづつ沈み込んでいるんだ。一階レイニーワールドが令和、地下一階には平成の時代に一世を風靡したHALO SAINT、そして地下二階が隠れ家、第二照和」 女は柵の向こうを通り過ぎていく部屋を指差し、説明を続けた。 「三階、喫茶室・大正浪漫、四階、ジャズ喫茶・Mae Jeanと続き、最下層は地下二四六階、和風居酒屋・ヤマタイカ」 印象は西鉄の駅前にありがちな雑居ビル。ただしこちらは地下。ところどころ営業しているらしき店がある。エレベーターはゆっくりと下り、年号とこのビルにまつわる話が続いた。しばらく降りると、出口は正面ではなく左右に開く。 「このフロアは……?」 「南北朝時代。右が南朝、左が北朝」 なるほど。 「朝廷が北朝と南朝に分かれ、それぞれに天皇を立て、元号もそれぞれに設定した」 聞いたことはある。こんな形で目にするとは思っていなかったけど。 「しかし、驚くのはまだ早い」 いや、驚いてはいない。呆れてるだけで。 「最大の秘密は地下二四五階、串焼きの白雉と地下二四四階、スナック朱鳥の間にある」 白雉・串焼き・地下二四五階、朱鳥・スナック・地下二四四階……聞いたことはとりあえず覚える性格なので、それ以上はもうやめてほしい。 「そこにあるのは失われた年号、亜璃朱」 やめてほしい。 「西暦でいうと六五四年と六八六年のあいだ、そこには三十二年の巨大な空洞がある」 次の瞬間、わたしたちを乗せたエレベーターの小さな箱は巨大な空洞へ出た。ナトリウム灯の黄色い明かりが順に灯り、そこに眠る巨大な構造物を浮かび上がらせる。 「これは……? 飛行船?」 エレベーターはその巨体の脇をゆっくりと降りて、眼下に見下ろしていた船はいつの間にかわたしたちの眼前。足元の床はそのランディングデッキで止まった。 「日本神話において天の磐船と言われたものだ。私たちはこれを、《亜璃朱の飛行船》と呼んでいる」 アリスの飛行船! 名称にメルヘンなイメージを感じたけど、これもニューラルネットワークのエラーだ。元号名と飛行船という語句が接続しただけ。まったく……人工知能ってものはやっかいな性質をしている。 船内は火焔型土器の文様に彩られ、壁にはチブサン古墳の極彩色の抽象画の趣もあった。材質は金属……もしかして神話にあるヒヒイロカネだろうか。障子で区切られた一角もある。おそらく、それぞれの時代で改築を重ねられて来たのだろう。丹塗の棚から、女は真鍮のホーンが絡まったような不可思議な物体を取り出した。 「あった。これだ」 デザインのベースは古墳時代の意匠を感じさせる。 「楊忌威滅垂法吽だ」 ヤンキー・メタル・ホーン! 楊忌威滅垂法吽。たしかに書いてある。『ホーン』と聴こえたが『法吽』だ。どんな意味だ。とりあえず密教法具カテゴリーに記録したが、果たして正しいのかどうか。 「米ぬかと蘇を火焔型土器に詰めた古代バッテリーと一体となっている」 そんなものがバッテリーになるんだ。 「これを装着するんだ」 わたしが? 「かつて昭和の暴走族は、こいつを車に装着してパラリラやっていたが、本来はこの飛行船を浮かび上がらせるためのものだ」 こんなものでパラリラやってたんだ。 女は私の古いバッテリーを外し、楊忌威滅垂法吽を装着してくれた。 「ホーンの開口部は背中のほうにまわしておいた」 やっぱりホーンじゃない。 「行くぜ! まずは定番の、ゴッドファーザー・愛のテーマ!」 パパラパラパラパラパラパー! 背中から大音量のゴッドファーザー・愛のテーマが! 「なにが聞きたい? 好きな曲を鳴らせるぜ」 って、べつになにも。 「定番は、ラ・カクラチャだな」 パーパラパパパーパー! パパパラパラパーパー! 「うるさいわっ!」 「フッ。いまのはアンタの声のほうがうるさかったぜ」 うざっ。このひと、うざっ。 「ていうか、あなた、なにもの?」 「やっと聞いてくれたな」 あ、そうか。こっちから聞くの待ちだったんだ。 「私はローゼンクランツ。ギルデンスターン八重樫の師にして盟友。ギタリストだ」 ということは、古澤くんが探していたひと……? 「わたしは秋山。秋山悠子。秋の山に、『ゆう』は悠久の悠。有給休暇じゃない方。県立西町高校、二年三組」 「西町高校か。そのむかし女子校だったところだろう?」 知ってるんだ、このひとは。 「古いバッテリーは持って帰るといい」 ローゼンクランツはわたしに古いバッテリーを手渡した。 「こいつからもかすかに音楽が聞こえる。だがもう必要ない。おまえには最強最大の動力炉を組み込んだ」 最強……最大…… 「なんでも好きな曲を鳴らしたらいい。自分を鼓舞するための、自分だけの曲を」 そうか。わたし、生まれ変わったんだ。 「わかった」 「ああ。楽しみな。人生を」 わたしはその場で、嵐の《Monster》を鳴らした。 小学校の頃大好きだったドラマの主題歌。 これが、わたしを導く、わたしの音楽。テーマソングだ。十六・双子の鳥
福岡空襲跡中心。『照和』と書かれた朽ち果てたドアを見つけ、そのドアをくぐった先にこの世界はあった。僕は肉体を失い、霊体だけでそこにたどりついた。 戸惑い、外に飛び出した矢先、秋山さんと遭遇。気を失い倒れかけていた彼女の肩を支えようとしたら、いつの間にか僕は彼女のバッテリーに侵入していた。 それからの冒険が現実か幻覚かわからない。いま確かなのは、秋山さんの中から取り出された僕が、仮初の肉体を失ってしまったこと。ここはまだバッテリーのなか。どこかに放置されたのだろうが、そこがどこかもわからない。 「お困りのようですね! お若い方!」 そこに現れたのは、若気の至りバスターズ。いや、その姿は見えないのだが―― 「わたくしたちが、力になりましょう!」 なんで聞こえるんだ……ここはバッテリーのなかなのに。 「わたくしたち、あなたのココロに直接語りかけています」 「ちなみに、あなたのココロの声も聴こえてます」 なんてこった。 「ココロに直接話しかけられるんだったら、ココロに直接姿を見せりゃいいだろうに」 「姿を見せるのは高難易度なのです!」 「届けられるのは声と臭いのみ!」 はあ? 「ほーら! 臭いもこの通り!」 臭っ! 「やめろっ! なんの臭いだ!」 「昨夜のディナーが体内で消化吸収された残りカス!」 ウンコじゃねえかよ。 「では、歌います」 はあ? 「曲は、タマネギ」 なんでだよ。♪
タマネギ 悲しみを わたしに 教えて 涙を 流したいの すべてを 焼き焦がす 真夏の 太陽に 壊れた わたしを 抱いて 風の吹く 夕暮れに あいつらは きたの わたしから なにもかも 奪い去った イナゴ 収穫 前にして 夢までも むしりとられて 仰いだ空から 涙 すがすがしい 夜開けまえ かなしみは きたの いつも一緒にいた 牝牛 ミルク出なくなった タマネギ 悲しみを わたしに 教えて 涙で わたしを 染めて 涙で わたしを 染めて♮
「いや、だから、なんで歌うんだよ」 「そんなのはわたくしたちの勝手です!」 「脈絡ねえんだよ、脈絡!」 「暴れてるとウンコ踏みますよ」 「片付けろよ!」 くそう、なんなんだこの世界は。 「こっちの世界は時間操作されてない世界だって聞いたのに……」 「あーっはっは! そんなことで驚かれては困ります!」 「バッテリーのなかにまで追いかけてくるのか! と、驚いて欲しい」 「うるせえ。忘れてたわ」 「そしてあなたはこの、バッテリーの中から出たいと思っている!」 「しかし、出る方法がない!」 見透かしてやがる。 「かまわねーよもう。待つから。出られるまで」 「待つ!? 待っているスキにもバッテリーは放電して――」 「残量0になると、あなたの魂も消えてしまうのですぞ!」 「そうなの?」 「あ、ええっと、はい」 もっと自信持って言ってくれよ。 「でも、あんたらが助けてくれるとしてもさ。金、取るんだろう? 二千円か五千円か知らんけど。持ってないんだよ、金」 「だいじょうぶ! ここはバッテリーの世界!」 「お金の代わりに、電力で支払っていただきます!」 マジで? 「過去を書き換えるだけなら、2000ミリAh、過去に戻るなら5000ミリAh」 ええっと、それがどのくらいの量かしらんけど…… 「とにかく僕をバッテリーの外に出して!」 「ところが残念!」 「我らにできるのはあなたを過去へ戻すことだけ!」 「だめじゃん」 「いいえ、要は簡単です」 「このバッテリーが製造される以前に戻れば良いのです!」 「なるほど!」 と、理解の早い僕が納得した次の瞬間には、僕は十年の時を一気に駆け戻っていた。 僕は真新しいバンのなかにいた。 秋山さんがみー子と呼んでいたバン。車内に溢れていたガラクタはなく、シートにはまだ新車の匂いがある。助手席の箱のなかには無造作に放り込まれた人形の手足が見える。 ここから出なきゃ。 ドアの把手に掛けようとした手が、するりと通り抜けた。 そうか、僕は霊体なんだ。通り抜けられるんだ。 とにかく急いで自分の体に戻らないと、また間違ってひとの体に入ってしまったら、今度こそ出る方法がわからない。 秋山さんの家ということは久留米大学近く。霊体なのでひとに見つかることはない。坊さんともすれ違ったけど気づかれることはなかった。駅を探した。久大線久留米大学前から列車に乗って久留米へ。この世界では国鉄はなくなり、JRという謎の私鉄線に変わっていた。 池町川に沿って小さなガードをくぐって、水天宮入り口の交差点へ。このあたりは元の世界となにも変わらない。中学の同級生、いちぢく少年・井上が勝手に実を採っていたいちぢくの木も同じ場所にある。 急いで自宅へと戻ると、小さな庭で遊ぶ7歳の僕と兄がいた。 どっちが僕だろう。 「幹夫ー」 部屋の中から母の声がする。 「「あー!」」 どうしてふたりとも返事をするんだ! 「零夫ー」 「「あー!」」 だからなんで! 靴に名前が書いてある。 が、ふたりとも「みきお」と「れお」ばらばらの靴を履いている。 ちゃんと自分の靴を履けよ! これでは判別がつかない。が、シャツの名前を見ると向かって右が「みきお」で左が「れお」。これだ! 右が僕だ! よし! 両手で肩をつかむと僕の体は幹夫の体に吸い込まれて行く。吸い込まれながらズボンに書かれた名前が目に入る。 ――れお ちょっとまて! 僕が選んだのはどっちだ! 七歳の肉体に宿ると、目の前に僕……いや、零夫の姿が見えた。 その目が僕を捉える。 「スコップ取って。零夫」 れ、れおぉ……? そんなぁ……。 いやしかし、冗談で言ってる可能性がある。 「零夫じゃないよ」 そういうと僕の顔をした少年は笑い転げる。 「じゃあ、じゃがいもだ」 なんでじゃがいもになるんだよ! 「零夫はおまえだよ」 そう言ってやると、少年は目を釣り上げた。 「おかあさん!」 立ち上がって玄関へと駆けて、 「ねえ、おかあさん! 零夫がヘンだよ! ちゃんとしゃべってる!」 秋山さんの体に入ったとき、僕は僕でありながら、だんだんと秋山さんの思考と同化していった。おそらく今回もそうだろう。いまの肉体は七歳。思考はいまのところはなんとか高校生のまま。だけどこれもやがて七歳の僕に同化していくのだろう。 もしこの世界の零夫が、もとの世界の零夫と同じだったら、僕は読み書きも計算もおぼつかない人生を歩むことになる。だけど僕の意識が残っているうちは大丈夫なはず。いまなら三角関数もわかるし、元素周期表も暗唱できる……この記憶が残っているうちに、いろいろ覚えないと…… 零夫になった僕は、幹夫の僕と手をつないで学校に行った。 家を出て最初の角で、幹夫は手を振りほどく。 僕は路傍の鉢植えのアロエが気にかかる。葉っぱを数えないと気がすまない。立ち止まると、幹夫が僕の足を蹴る。 「行くぞ。零夫。学校におくれる」 別にいいよ、学校なんて。僕にはそんなものより重要なものがあるんだ。奇数なんだよ、この葉っぱは、いつも。 三角関数も元素の周期表も知っているのに、肉体は零夫のものだった。背後霊のように後ろについているだけ。わずかながら零夫の行動に意識を投影することはできたが、逆もあった。零夫の思考がときおり僕を乗っ取る 学校に行くとゴンがいた。 そうだ。僕はゴンに会うためにこの世界に来たんだ。 「ゴン!」 駆け寄るとゴンが怯える。 零夫はゴンにとってどういう存在だったんだろう。空気感がわからない。それでも抑えきれずにゴンの腕を握ると、その袖は泥で真っ黒に汚れた。 自分の手を見ると真っ黒だ。 そういえば通学路でアロエをとった。アロエの葉が偶数なのは許せなかった。偶数は尖っていないからだ。果肉をほぐしながら学校に来て、それをどうしたか覚えてない。ゴンから手を払われて、先生を呼ばれて、怒られた。 放課後。大きなボウル型の発泡スチロールを叩いている子がいて、バンドのことを思い出した。ギターがあれば僕も音を合わせるのに。体でリズムを取っていると、頭に発泡スチロールを被せられた。そしてドラムのように叩かれた。最初は面白かった。だけど、手や足まで叩かれて痛かった。痛みはどんどん増していった。発泡スチロールを取ると、叩いていたのはゴンだった。目が合うと棒を背中に隠して、 「わたしじゃないよ!」 と、となりの男子を指差す。 泣いた。 泣くとまたみんな騒ぎ出す。 「ゴンが泣かせた!」「こいつのせいだ!」って、みんなでゴンを指差す。 「わたしじゃないよ! わたし2回しか叩いてない!」 悔しくてつかみかかったら、ゴンは倒れた。 ゴンは肘を擦りむいて、そのぶんも怒られて、家に帰るとお母さんからまた怒られた。 泣いて箱に入ってたら、お姉ちゃんから引きずり出された。 夜、ふとんに入ると、オモチャ箱の人形が僕の体を訪ねてきて、僕のなかでパーティを開いた。足の裏に入口がある。人形たちは僕のなかでお茶を飲んで、ケーキを食べた。 「ちょっと、足が壊れたんで、この子の足をもらって帰ろう」 「それじゃあわたし、心臓が弱いから心臓をもらうわ」 「いやいや、心臓はよくない。死んでしまうだろう」 「だいじょうぶだよ、機械の心臓に置き換えてあげたらいいんだ」 「まあ。それは良い考えね。それじゃあわたし、おぺにぺにをいただこうかしら」 「それはいい。僕も半分いただこう」 目を覚ましてオモチャ箱を覗くと、バラバラになった僕の体が転がっていた。人形たちが親指を立てて笑ってみせた。やったね。ナイス。 「あんたのせいでけがしたんだからね」 ゴンは肘の絆創膏を見せながら言った。 「はんせいしてる?」 僕はそのことばの意味もわからずにうなずいた。 「じゃあ」 そういうとゴンは、僕のランドセルから国語の教科書を取り出して、 「びりびりにやぶってみて。やぶったらゆるしてあげる」 と言って笑った。 手には棒を持ってるし、叩かれたくなかったから、教科書を破った。でも、ゴンが笑ってくれた。僕も笑った。 次の日は、ランドセルに牛乳をこぼしてみてって言われた。こぼした。その日から僕のランドセルは牛乳の臭いになった。 校門を出たらもうひとりの僕がいた。幹夫だ。 友だちと話をしていたので手を握ったら振り払われた。 みんなが大笑いしている。僕も笑ったら、蹴られた。 水天宮に行きたいと思った。 土手を歩いていると、大きな車が来て僕を乗せた。 車は川沿いを走って、それから曲がって、真っすぐ走って、曲がって、曲がって、足元には箱があった。箱には人形の手足があった。 「興味があるか、少年」 運転しているおじさんが聞いてきた。 わからない。でも、この子を見たことがある気がする。箱のなかには生気のない顔があった。 「それは俺の娘だ。もうすぐ完成する」 そうか。このひとの娘はロボットなんだ。まだできてないんだ。 車が止まって、僕は部屋に連れて行かれた。 部屋には人形がたくさんならべてある。仮面ライダーもウルトラマンもある。壁にはアニメの絵がたくさん貼られている。すごい。こんな場所があるなんて。思わず奇声を発する。僕はテーブルの上に寝かされて、手足をおさえられた。 「すぐに終わる。怖くないから暴れないでね」 おじさんはウルトラマンの人形をひとつ僕にくれた。 そしてドライバーを取り出して、僕のおなかの蓋をあけた。 機械をカチャカチャ言わせて、何かを取り外している。それから足も。ふともものあたりの蓋をあけて、何か取り出した。オモチャたちからもらった部品がどんどん取り出される。 「大丈夫だよー。新しい機械と換えてあげるからねー」 新しい機械……。 「そうだよー。悪いやつと戦えるようになるよー」 そうか。僕、強くなるんだ。 「あー、これは……」 おじさんの声が躓いて、アームつきのライトで僕の胸の中を照らす。 「わかったぞ、少年。少年が本来の力を発揮できないのはこのせいだ」 そう言うとおじさんは、胸の中身をぐいぐいとひっぱった。 「バッテリーのなかに異物が入っている。取り出しておくから、これはキミが持っておくといい」 おじさんが取り出したのは、銀色に輝くハーモニカだった。 しばらく眠ったあと、水天宮の社で目を覚ました。 僕はボロボロに切り刻まれた人形だった。ハーモニカを持ったまま、体を動かすことも、まばたきすることもできなかった。すぐにひとが集まってきて、救急車とパトカーとがやってきた。 街一番のオモチャ屋に運ばれて、修理された。 工場の作業着のままのお父さんが来て、 「何があったんだ」 と涙を流した。 「オモチャたちにもらった体を取られた」 僕が言うと、お父さんもお母さんもあっけに取られた。 お姉ちゃんもおどろいている。 「あんたがちゃんと話してるの、はじめて聞いた」 ぽっかりと開けた穴のような口で言った。十七・メカニック兄ちゃん
お父さんは退職金を前借りして、機械の体を買ってくれた。 そして中学になると、僕はエイペックスに出会った。ファーストパーソンビューのシューティングゲーム。 友だちができた。 三年、西町高校を受験。合格。この春から、高校生になった。 小学校の頃に同じクラスだった権丈弓子が、また同じクラスになった。 僕は乱暴な権丈、ゴンのことが、大嫌いだった。 そして親友田村とつるむようになったのも、その頃。 「聞いたんだけど!」 それが田村が僕にかけてきた第一声。 「なに、いきなり」 「きみが、パルオだって!」 パルオは僕のエイペックスでのID。YouTubeにも同じ名前で動画を投稿している。ランクは最高位、プレデター。まあ、アンドロイドなので当然なのだけど。 家は貧乏だったけど、ボディの修理や買い替えはなんとか両親が工面してくれた。はっきりとは言わないけど、僕のボディの維持にもう数千万はつぎ込んでいる。古いアルバムを見ると両親ともにサーフィン好きだったことがわかる。だけど、物心ついてから両親がサーフィンに出掛けたのを見たことがない。僕が奪っているのだと思う。両親の自由を。 僕のエイペックスのランクは、そんな環境に支えられてのものだ。 「こんどいろいろ教えてよ」 田村は言うけど、僕にとっては教えるほうが難しい。 「なんで始めたの、このゲーム」 「なんでって、なんだっけ」 配信かな。なんとなく見てたYouTubeで、自分と同じアンドロイドとしか思えないものがいて、それで興味を持った。最高位まで達したいまの感覚で言うと、上位の半数はアンドロイドだ。並の人間で太刀打ちできるはずがない。 エイペックスをプレイしながら、田村とはよくチャットした。 「ゴンの家さあ」 「ゴンって権丈?」 「そう。ミロ、水で薄めるって」 「はあ?」 「もったいないから、牛乳半分、水半分って」 「あいつんち、貧乏だもんな」 ゴン。ゴンって呼ぶなと、小学生の頃殴られた記憶がある。 あいつはテストの答案も、名前の欄を折り曲げて提出していた。 二年、クラス替え。秋山さんと出会った。 秋山さんは清楚だった。 おっとりしていた。 静かに話し、笑い、自分の世界を持っていた。 だけど僕には、彼女も僕と同じ、アンドロイドのように思えた。 なぜかはわからない。ただ、そんな気がした。 夜はエイペックス。 凡人田村のキルレシオも上がって来た頃。 「こんど、バーベキューやるんだけどさ。古賀たちと」 「で?」 「おまえも誘えってうるさいの」 「なんで?」 「おまえが来ると、女子誘いやすくなるって」 「はあ?」 と、言ってみたが、気分は良かった。アンドロイドなのに。笑みが漏れた。 「なんつってな」 なんだよ、それ。 「ちょっと信じた?」 「僕はアンドロイドだ。記録するだけで、評価はしない」 とか言いながら、気がつくと遥か低ランクの相手に撃ち負けていた。 「うひょ」 田村はなぜか僕が負けると喜ぶ。味方じゃないのか。 昼は学校で打ち合わせ。 バーベキューメンバーには秋山さんも権丈も入っていた。だけど、 「肉は俺たちで用意するから」 そういって割り振られたなかに権丈は入ってなかった。 「でも、悪いから」 と、権丈は曇った笑顔を作る。 「いいよ、おまえは」 「どうして?」 田村は言葉に詰まった。 「またあとでしようか、この話は」 新しいステージが開放されて、マッチングを待つ間に話の続き。 「あとっていつのつもり?」 「あいつのいないとき」 「ゴンからしてみたら肩身が狭いだろう」 「あいつんち、本当に貧乏なんだぞ」 「知ってるよ」 「割り勘にしたら、金額抑えるしかないだろう? せっかくのバーベキューなのに。主催なんだよ、俺」 「そうかもしれんけど、金で楽しむもんじゃないだろ」 「どうかなあ」 そうして『あとで』と言ったその日は訪れないまま週末になり、結局ゴンは姿を見せなかった。 「弓子、どうしたんだろう」 紙のトレーを手に持って、秋山さんは言った。 「古賀くんが……」 となりにいた女子が耳元に囁いたけど、内容までは聞こえなかった。 田村の顔を覗くと、 「まあ、いろいろあるんだよ」 と、肉を一切れ口に放り込んだ。 その翌日、月曜日。始業前。 古賀くんが席についていると、ゴンが背後から鎖で首を締め始めた。 ちょうど古賀くんと話していた田村は、 「ちょ」 とだけ声を発したまま椅子を引いた。 「死ねよ、クソが」 そう言って鎖を二重に巻きつけた手の甲は白く変色し、古賀くんは「プ」と音を発したまま、みるみる青ざめていく。 まさか殺したりまではしないだろう。 みんなそう思ったと思う。 あるいは、だれか止めるはずだ、と。 そんななかで動いたのは秋山さんだった。 ゴンに駆け寄って、顔を胸に抱きとめて、ゴンの右手の鎖を解き始め、それを見たクラスのみんなは胸をなでおろした。 「びっくりしたー」 「古賀くん、死んでしまうのかと思ったー」 と。 だけど秋山さんはそんな期待など裏切って、解いた鎖を自分の手に巻いた。 「ひとりで抱えないで」 秋山さんは手を震えさせ、古賀くんの首にかけた鎖を引く。鎖の一端はまだゴンが握っている。さすがにこれはやばい、と、僕が立ち上がると田村も立ち上がってふたりを抑えた。 古賀くんは気を失い、そのまま保健室に運ばれた。その間、秋山さんはずっとゴンを抱きしめていた。 放課後、秋山さん、ゴン、田村に僕、その他バーベキューに関わったひとたちが職員室に呼ばれて、最終的には古賀くんの保護者まで駆けつけての大波乱になったが、不思議と刑事事件にはならなかった。 「あいつはキズがあるから」 と、田村が言ったが、キズの中身までは教えてくれなかった。 ときどき自分が何者かわからなくなる。 いや、よくよく考えてみると、自分が何者か知っているひとなどいない。 ある程度の地位、役職につけば、まわりのひとが「このひとはこういうひとだね」って評価をくれる。それまでは何者でもない。 とは言え、多くの人は「自分は自分である」くらいの自覚はある。 困ったことに、僕にはそれがない。 だれだっけ、僕は。 「そもそもこの世界に生まれ落ちた記憶がない」 「いや、みんなそうだって」 「そのレベルじゃないんだって」 「いや、レベルとかじゃなくて、覚えてないって。生まれたときのことって」 いや、でも僕はアンドロイドなんだ。覚えていないのはおかしい。 「秋山さん、僕と同じだと思うんだよ」 「同じって?」 「アンドロイド」 「は? おまえがいうアンドロイドってどういう意味?」 「いや、そのまんま」 「あれただゲームがべらぼうに得意だって言いたかったわけじゃないの?」 告白したのは夏だった。 期末考査の最終日。 朝っぱらからセミの声がうるさいが、あれはぜんぶ雌を呼んで鳴いているんだ。そんななかで告白。セミか、僕は。でもまあ、これを逃すと夏だろう? 夏休み中は会えないだろう? 9月になると学園祭とかいろいろあるだろう? でもまあ、セミの考えも似たようなもんだよな。 「わたし、交際とかよくわからないから」 秋山さんは目をそらしたまま、困ったようにこたえた。 「あ、じゃあ、教えます」 「いや、そういうのも違うよねー」 「じゃあ、デートだけ」 「でもデートって、付き合ってるみたいだし」 「じゃあ、一緒にどこか行きませんか?」 「うん。まあ、それだったら」 「あ、ありがとう! どこがいい?」 「別に、どこにも行きたくないっていうか」 「プールとかは?」 「えーっ? いきなりー?」 まあ、そうなるよな。 「いや、なんていうかな。上津町のプールだったら四百円だしと思っただけで……」 「えっ!? そうなの!?」 あ、乗ってきた。ツボがわからない。 太陽が幾度か沈んでは浮かび、デート……いや、一緒にプールに行った当日、秋山さんは学校指定とは違う市販の水着姿だった。 「それ、似合うね」 僕は普通の学校指定。油断した。 「お父さんがこれがいいって」 「お父さんと買いに行ったの?」 「だって、水着って高いんだよ?」 「あ、うん、そうだけど」 もし僕の読み通り秋山さんがアンドロイドだとしたら、胸元か太ももに継ぎ目が見えるはずだ。だけどそんなにまじまじと見つめるわけにもいかない。手で触れることができたら確実なんだけど。 「もう、こっち見るの禁止」 秋山さんは鈴のように笑う。 「えっ? どうして」 「わたしが見れないのに不公平」 秋山さんは首をすくめて笑った。僕はその文脈のつながらなさに人間っぽさを感じた。 僕と田村はキャンペーンにつられて別のシューティングゲームを始めていた。 「なんかその話聞いてさあ、ずっと秋山の父ちゃんが一緒にいるみたいだった」 フォートナイトってゲーム。なぜかこっちは田村のほうがうまい。 「それが狙いなんだよ。親父さんの影をチラつかせておく」 「うっそー。つれねー。あー、駄目。また死んだ」 「脈ないよ、それ。ていうか、本気出してないだろ」 「本気だよ。あ、ゲームのこと? いや、出してるって。秋山さんも。ていうかさあ、嫌だったら断ると思うんだよ」 「断れない子だっているよ」 「でも、秋山さんだよ? モテるんだし、断ればいいんじゃないの? あーっ!」 「モテるのと、はっきり自分を通せるのは別問題だよ。あーっ!」 「じゃあ、押すしかないか」 「はあ? うわ無理」 「はあってなに? 右だよ、そこ」 「おまえ、それでいいの? その気もない相手を落とっ! してっ! 満足なの?」 「だって、そうやっ、ちょいまっ! そやって誰かが落とすんだろう? たまたまそれが僕だって話じゃん。それが駄あーっ! 駄目だっあーっ! たら、秋山はずっと恋愛しないままってことだよ」 「そうはなんないよ。だれか好きになるよ」 「それが僕ってことだろう? うへ」 「案外、ゴンだったりしてよっしゃあっ!」 「ゴン!?」 そういえば例の事件の日に抱き合ってたけど。でもあれ、そういう意味じゃないよ。 「ぎゃっ!」 「ああ、ごめん」 このところバッテリーが不調で、日に数回ほど急激な電圧低下にみまわれた。 「たまにやるよな、それ」 「ああ、うん」 普段の生活に支障はないんだけど、ゲームだと困った。反応の遅れが死を意味する。それでなんどか田村を死なせてしまった。 「幹夫には相談しないの? 秋山さんのこと」 「えっ? あいつには教えないよ」 「なんでよ」 なんでって……なんかイヤなんだよ。 リビングへ降りると、幹夫と姉ちゃんが奨学金の話をしていた。姉ちゃんの申請が通ったらしく、これで家計も楽になるねって。 「今日はもうゲームは終わったの?」 「ああ、うん。終わった」 バッテリーの話をしたかったのに、そのタイミングじゃない。 「どうしたの? 何か話があったんじゃないの?」 「ちょっとバッテリーの調子が悪くて」 「そう……また修理に出すんだね」 家族はみんな節約している。だけど、僕のボディのことになると気を使ってくれた。 「いや、修理に出すと代用機が必要になるから……」 「じゃあ、どうする? 新しいの買うようなお金はないと思うよ」 「ネットで色々調べてるよ。なんかわかったら教える」 80ボルト以上でまる一日稼働できるバッテリーは20万円以上した。 粗悪品なら5千円からある。メルカリだと更に安かったけど、バッテリーが安定しないと制御系にも影響が出る。いちど3万円クラスのミドルレンジ製品は買ったけど、使い物にならずに引き出しに眠ってる。だから、いざとなればこれが代用機にはなる。 とりあえず試しに取り付けて寝てみたけど、悪夢にうなされた。 バッテリーってたまに悪霊が宿ってるっていうし、だから安かったのかもしれない。十八・パッションブラッド・リバイバル
気がつくとゴンは軽音部に入っていた。 幹夫とバンドを組んで、学園祭でオリジナル曲を演奏するらしい。 オリジナル曲なんて痛いだけで大失敗するに決まってる。 しかもよりにもよって、どうしてゴンなんだ。あんなクソ女。あんなゲロ女。なんであんな女とくっつこうとしているんだ、幹夫は。僕にあてつけるためにわざとやっているのか。 と、甘く見てたら、いつの間にか秋山さんもあいつらのバンド、パッションブラッドに興味を持っていた。なんで秋山さんまで。さっさとゴンとくっつけよ、幹夫。 でもこれで僕が秋山さんと交際して、幹夫がゴンと交際したら、二股みたいだ。いや、だからって同じ相手を好きになりたいわけじゃないけど。 とにかく、幹夫はさっさとゴンとくっつけばいい。 だけどいくらそう願っても、幹夫とゴンの将来が思い描けなかった。僕に見えるのはゴンがいない未来だけ。なぜなんだ。 高二の秋も終わりかける頃、三本松公園近くを歩いていると、小さい頃に聞いていた曲が聞こえてきた。小学校にあがりたての頃に見ていたドラマの主題歌。しかも、大音量でチープな演奏。だけどその少しずつ近づいてくるビートに、なぜか魂が揺さぶられる。吸い込まれるように角を曲がった先、目の前から歩いてきたのは秋山さんだった。文化街の川沿い。 「古澤くん……どうしたの、こんなところで」 「ええっと、音楽が聞こえたので」 「もしかして……これ?」 そう言って秋山さんは、両手を腰に当ててみせた。 パー パー パーラ パーラパー! パー パー パーラ パーパパーッ! その胸から大音響が響き渡る。 「な……」 不覚にも「な」しか言えなかった。しかもなんの「な」なのかもわからない。 「これがわたしの、最強最大の動力炉、楊忌威滅垂法吽」 ヤンキー・メタル・ホーン! 「いままでわたし、やりたいことなんかなかったんだけど、ようやく前を向けるようになったの。この楊忌威滅垂法吽で」 「すごい!」すごい! すごい!「すごい!」 言葉とモノローグの二重奏だ。 「それはよかった!」 「見たい?」 あ、ええっと……聞きたい、ではなく、見たい? 「見たいというと?」 「わたしね、アンドロイドなんだ」 「あ、うん、ええっと、ええーっ!」 急に来たので驚くタイミングを間違えた。 「どうしよっかなぁ。ここで見せるの変だよねー」 テンション高ぇ。これがヤンキー・メタル・ホーンの力か? 「どうしよっかなぁ」 わかった。見せたい、と。 「あの、僕の家まで歩く?」 「ええ~っ! 古澤くんの家に~っ!? どうしよう!?」 テンション高ぇ。 徒歩移動10分。 たまにアロエを見て立ち止まる秋山さん。 浮かれて田村にラインを送る。 ――秋山さん、アロエ観察中。 写真付きで。 幹夫はバンドの練習で出払っていた。 この時間だと家族もいない。 「お邪魔します」 だれもいない家の玄関。 急な階段。スカートも気にせずに先に上がろうとする。 「あ、まって、ゴミがあるかもしれないから」 そう言って先行したけど、でもお互いにアンドロイドだし、スカートのなかが見えたって、なんならパンツのなかが見えたってなんてことはない。機械じゃないか。こういうのにエロスを感じるのって、人間が仕込んだ勝手なプログラムだ。 部屋に入って、幹夫の荷物をどかして、場所を作った。 「じつは、僕もアンドロイドなんだ」 「あ、やっぱり? そう思ってた」 だよね。アンドロイド同志ってわかるよね。 「だから、クラスの連中が言うようなエロって、よくわかんなくて」 「ああ、わかる。わたしもそう」 だよねー、はははー、とか言って、アンドロイド同士でも会話は途切れた。アニメみたいに。 「アンドロイド同志で一番恥ずかしい部分ってなんだろうね」 言葉が途切れたからって、この話題ってのもどうかな。 「うーん……ソースコード?」 秋山さん、華麗にレシーブ。 「あー。わかる」 「関数名が jikanShutoku() になってるーとか指摘されたら立ち直れない」 「わはは。秋山さんらしい」 「ちーがーうーっ。たとえ話ーっ」 僕のソースにもきっと恥ずかしいコードがたくさん紛れ込んでる。関数名とかじゃなくて、if文のネストが深いとか、文字列を埋め込んでるとか、そのレベルで。だけど、いつかきっと、僕と秋山さんにもお互いのソースコード見せ合う日が来るんだと思う。 ――参照エラー起きてる。 ――見ないで、んもう。意地悪。 ――悠子の参照エラー、僕は好きだよ。 なんていうクソエロい妄想をしている間に、秋山さんは布製の保護カップを外し胸のハッチを開けてバッテリーを取り出して目の前に差し出してくれていた。赤と青のケーブルで秋山さんの体内につながり、バッテリースペースの後ろに基盤が見えた。細くて柔らかな配線パターン、褐色のフラットケーブル、それが僕の目に触れていることを気にも留めない。僕がヤンキー・メタル・ホーンを手に取ると、秋山さんは大音量でパラリラ音を鳴らして驚かせた。 「びっくりした? すごいでしょ」 「そんなことしてると落とすよ?」 「だめだめ。壊れちゃう。もうやんない」 と、言いながらまた鳴らす。本当にうれしいんだな。 「古澤くんも試してみる?」 「えっ?」 「予備のバッテリーない?」 そう言うと秋山さんは勝手に引き出しを開けてバッテリーを引っ張り出した。 「ちょっと付け替えてみよう」 って、秋山さんのほうから。 バッテリーを付け替えてあげるとき、秋山さんの意識は途切れた。ほんの一瞬だけ基盤のパターン、チップの製造番号、ディップスイッチを観察できた。グリスで手入れされたコネクタは柔らかくケーブルを吸い込んだ。僕の胸にヤンキー・メタル・ホーンを取り付けるときも同じだったんだと思う。僕もその一瞬だけ、彼女に命を委ねた。 かくして装着したヤンキー・メタル・ホーンの威力は凄まじかった。 「なんだこれ……?」 装着しただけでビートを感じる。 「鳴らしてみて。バスの8番と9番にMIDI信号送るの」 まずは定番のゴッドファーザー。 パパラパラパラパラパラパー! 「すげえ!」 「なんでも鳴らせるよ」 それじゃあ…… パパー パパー パパパーパ パパー 「知ってる! 電子戦隊デンジマン挿入歌、銀河ハニー!」 なんでわかる。 「これは?」 パーパーパーパーパーパーパー パパッパー 「スナッキーで踊ろう!」 すげえ。ていうか、秋山さんがすげえ。 「どこ製のデータベース使ってるか教えて」 「次は?」 「ああ、ええっと……」 そのとき、脳裏に流れてきた音楽があった。♪
あなたとかわした しょっぱいKissが 海の香りと信じていた 子どもの頃 町に帰って いくつかの 恋もしたけれど 傷つくたび 思いだした 防波堤♮
胸に浮かんだその曲が、ヤンキー・メタル・ホーンを轟かせた。 「それは……?」 「これは……僕が思い出さなきゃいけないもの」 「なにそれ、面白そう」 いや、面白いことじゃない気がする。僕が少し考えていると、秋山さんのテンションも落ち着きを取り戻した。 「そろそろ返して。滅垂法吽」 「ごめん。これ、もう少し貸しててくれないかな」 「えーっ。それはいやかなー」 「思い出さなきゃいけない歌があるんだ」 「歌って?」 「わからない。だけどそれが、僕がこの世界に生まれてきた理由のような気がする」 「なにそれ。わたしたちが製造された目的は人類への奉仕だよ」 「そうだけどさ。でも僕には特別な理由がある」 「わかった。わかったけど、それ、返して」 「でも秋山さんに使命がないんだったら、僕が使ったほうが役に立つし」 「古澤くん……」 「なに?」 「軽蔑する。そんなひとだと思わなかった」 軽蔑……。軽蔑くらいでこのバッテリーが手に入るなら。 そのとき、表でクラクションが鳴った。一回、二回。間をおいて、もう一回。次は絶え間なく、断続的に何度も。 「お父さんだ」 窓の外を見ると外国車らしきバン。 「行かなきゃ」 秋山さんはハッチを閉じて保護カップを装着。 「ごめんね! いつか返すよ! ぜったい!」 声をかけたけど、睨み返しただけ。外装のジッパーを閉じて部屋を出た。 次の日、秋山さんは学校に来なかった。 「なんかあったの?」 と、田村。 「昨日どこにいたの? 秋山と」 「文化街でばったり会って、うちまで……」 「なにかしたの?」 「別になにも」 何もなかった。秋山さんはお父さんのバンで家に連れ戻された。田村に話したのはそこまで。彼女のお父さんのことは覚えてる気がする。もしかしたら、僕が思い出さなきゃいけないのはそのことかもしれない。だけどそんなことよりも、僕は昨日からずっとゴンのことが気になっていた。 幹夫とゴンは屋上にいた。ふたりの距離はクラスメイトの距離じゃない。 でも、幹夫って僕だろう? よりにもよって、なんでゴンと。 ふたりはたぶん、今度のライブのことを話しているんだと思う。会話の合間にゴンのスキャットが聞こえる。その声には艶やかさがあった。空に一筋の色が舞うような。ココロを奪われていると、スキャットはいつしか歌声に変わっていた。 それは、昨日脳内に流れた曲……。 パッションブラッドのデビュー曲だ。カフェ・ラ・カルナバルでのライブ……。少年のバースデーパーティ……。 ――タイトルは……? ――防波堤 ――わたしたちの大切な曲です。聞いてください なんなんだ、この記憶は? そのとき―― パパパパパパーパー! パーパパパパーパー! 胸のなかのヤンキーホーンが奏でた。 いや、まてまてまて。なんで鳴るんだ。くそっ。 その音であいつが振り返る。幹夫も気がついた。まずい。 胸を抑えるが、音は消えない。僕はその疼きを抱えて、塔屋に駆け込んだ。 刹那、 ぎょういん! ぎょういん! 緊急警報をお知らせします! 緊急警報をお知らせします! スマホの警報が鳴り始める。 今度はなに? 階段を降りると生徒たちは騒然としている。 校内放送のアナウンスが鳴り出す。 『ただいま、久留米大学近辺に尻出しゲロゲロ魔王が発生しました。全校生徒は直ちに、身の安全を確保してください』 尻出しゲロゲロ魔王!? 説明は!? 田村からのライン。 ――なんか聞いたことある気がするんだけど、なんだっけ? ――なんだっけ。おまえと倒した気がする ――フォートナイト? ――いや、違う。リアルだと思う ――リアル!? リアルって、現実ってこと!? 上空にヘリの音が轟く。 テレビ、ネットともにニュースを伝え始める。 窓の遠くに火の手が上がるのが見えた。 すぐに、 ――魔王の正体がわかった と、田村からリンクが送られてきた。 その動画に写っていたのは、巨大化して街を破壊する秋山さんの姿だった。 なんでこんなことに? 避難する生徒とは逆に、屋上へと向かう流れもある。僕も思わず彼らに続いた。ここから久留米大学までは3キロ。遠くに破砕音が轟く。火球が閃き、ヘリを撃墜する。生徒たちの息を飲む声。巨大な光弾が次々と吐き出され爆発が巻き起こる。ここは安全圏だろうと思っていると、爆発は秋山さんからはるか離れたところでも起きる。 「やばい」 「ここも射程に入る」 「どうするの?」 次の爆発でネットが切断される。どのページもローディングアイコンから進まない。 「だれかラジオを!」 とは言うものの、ラジオだっていまはインターネット経由だ。ネットがなければもう情報がない。目視で秋山さんを確認しながら逃げるしかない。だけど、逃げると言ってもどこへ? そこに―― 『魔王は九大前駅付近から国道322号線を市街地方面へと移動中』 校内放送がラジオを流し始める。 だれかが気を利かせてくれたんだ。 DJローゼンクランツ――ラジオ好きには馴染みの声が戦況を伝える。 『武装はクソ高出力の粒子砲らしきものが一門。また、両腕に機銃銃装備。大口径の実弾をクソ連射できる模様。射程範囲不明。粒子砲は最大で15キロの到達が確認されている』 射程、15キロ……。 ここは余裕で射程範囲内。しかもこちらへ向かっている。 『魔王はわたしの48番目の弟子、秋山悠子だ。あいつの胸には楊忌威滅垂法吽が装備されている。コンタクトしたい。だれか協力を』 秋山さんが、ローゼンクランツの弟子? 田村も屋上に来る。 「なんでおまえまで」 「安全な場所がない。魔王が見えない場所じゃ、いつ死ぬかわからん」 粒子砲の連撃。轟音がパノラマとなって頭上を駆け抜け、余韻が遠雷の尾を引く。連続する爆発音と衝撃。ラジオからも遅れてその音が響く。気圧差で生まれた風が窓を揺らす。 『わたしだ! ローゼンクランツだ! 攻撃をやめろ!』 ラジオの声が絶叫する。ハウリングが聞こえる。どうやら久大附設、久留米商業、南筑高校などもラジオの音声を魔王秋山さんに向けているらしい。幾重にもその木霊が響く。 『おまえは魔王じゃない! おまえは秋山悠子! わたしの教え子だ!』 果たして届いているのか。秋山さんの攻撃はやまない。重い機銃音が轟くと、砕け散った家、砕け散った舗装が白煙となって街を横切る。 『聞こえているなら、ともに轟かせろっ! この曲をぉっ!』 ラジオは《Monster》を流し始める。 わずか二小節でその曲が魔王秋山さんの胸を捉えた。 ゆっくりと動きが止まる。その足取りは混乱を映し、乱れ、震える手で胸を押さえる。膝が揺れる。鳴り響く《Monster》。次の瞬間、僕の胸の楊忌威滅垂法吽も《Monster》を奏でだした。秋山さんはゆっくりと、その顔を僕に向ける。同時に屋上にいる生徒たちの視線も僕へと集まる。 「なんでおまえから……?」 田村が僕に顔を向ける。楊忌威滅垂法吽がやまない。ラジオに呼応して鳴り続ける。 「なんでって……もらったんだ……秋山さんに……」 「もらった? なんでおまえが?」 なんでって…… 「僕のせいじゃない」 「おまえのせいかどうかは聞いてないよ。何が起きたかって聞いてんだよ」 秋山さんは態勢を立て直し、目の前のビルを掃射しながら、ゆっくりとこちらに近づいてくる。白煙のなかの巨大な影。ガトリングの連射音が不定期に轟く。 「僕が貸したバッテリーに悪霊が宿っていて、おそらくそのせいで……」 「おまえの脳内設定なんかどうでもいいんだよ!」 「脳内っ……そんなんじゃない! 本当に秋山さんは……わかった! 父親に改造されたんだ! うちから無理やり連れ戻されて、そのあと……」 「だから、なんでいつもひとのせいなんだよ、おまえは!」 響いていた他校の校内放送がひとつ、またひとつと途切れる。秋山さんに破壊されたんだ。屋上から退避を始める人の波に押されながら、僕と田村は続けた。 「違う! 聞けよ! 僕だって被害者だ! おまえら僕をいじめたじゃないか! 邪険にしたじゃないか! 仲間はずれにして、中学に入ったらもう僕のことなんか忘れてただろう!?」 田村はもう何も言わない。 白煙のなか、秋山さんが校舎前に達した。その身長は高く、目の前にちょうど秋山さんの膝が見える。秋山さんが腕を向けると、手首に輪と並ぶ銃口が覗いた。 終わった。 「逃げろよ……田村……」 せめておまえは。 「好きだったんだよ、俺も。秋山のことが」 田村の瞳から涙がこぼれた。 「おまえが言ったことなんてぜんぶ知ってるよ!」 その涙も拭かずに声を荒げる。 「あいつの家庭のことも……アンドロイドだってことも……知っててもなにもできなかったんだよ! なのに最後の最後に逃げ出せって!? なにもできないくせに逃げることだけはできましたって!? ふざけんなよ……なにもできないんだったら、せめて逃げないでここにいたいんだよ……」 田村は僕の肩に手をかけて訴えた。 何を聞いても混乱するばかり。思考がまとまらない。 「僕のせいだっていうの?」 絞り出し、聞いてみると、田村は胸の底に湧き上がる気持ちをいくつか押し殺し、口を開いた。 「いや、おまえはもういい」 「もういいってなに?」 「おまえには責任能力がない。ここから消えてくれ」 田村が僕の肩から手を離すと、僕のズボンのポケットからハーモニカがこぼれ落ちた。 目の前の景色が崩れた。世界が意味のないモザイクに変わっていく。僕は――零夫に戻った。次の瞬間。 「バトンタッチだ。零夫」 僕が落としたハーモニカを幹夫が拾い上げた。❡
僕は零夫が落としたブルースハープを拾い上げた。 すでに進藤くんもヤギもスタンバイを終えている。アンプ、スピーカー、すべて軽音部員の手で視聴覚室から運び出してきた。 「準備は?」 「ばっちり」 曲名、きみの翼。 Cメロ、サビからのスタート。 「リードたのむ。弓子」 弓子は軽く頷くと静かに、深く息を吸い込んだ。♪
ずっと隠し続けている 苦い傷跡も 飲み込んだ嘘も 古い街が押し付けてきた いわれなき罪と デタラメな未来♮
ドラムのフィルイン、弓子のリフ、ベースが走り出し、音圧は瞬間にピークに達する。♪
はるか5千フィートの空 わき上がる雲に 立ち向かうならば はるか遠いこの街から 祝福を贈る きみの翼に テディベアひとつ 本棚に残し 荷物消えた部屋 カレンダーに『さよなら』 交わした言葉 胸のなかにリフレイン 気づいてはいたさ 今日の日がくること 君がいるから 生きると決めたのに 語りあった夢のすべて 嘘だったなんて 信じたりしない 涙こらえ耳をふさぐ 君の生き方が 正しいとしても 空の青さが 窓にあふれても いつか降り出す 雨の予感におびえた 勇気ひとつを 奮い起こせなくて 無力さばかりを 噛み締めたベッドルーム 君とつむいだ 夢が眩しすぎて はるか5千フィートの空 わき上がる雲に 立ち向かうならば はるか遠いこの街から 祝福を贈る きみの翼に 語りあった夢のすべて 嘘だったなんて 信じたりしない 涙こらえ耳をふさぐ 君の生き方が 正しいとしても ずっと隠し続けている 苦い傷跡も 飲み込んだ嘘も 古い街が押し付けてきた いわれなき罪と デタラメな未来♮
演奏を終えると、そこに秋山さんの姿はなかった。 上空にヘリが舞っている。 ロープから降りてくる姿があった。 ギルデンスターンだ。 「遅れてすまない。こっちの状況は?」 僕の足元には人形のように力なく倒れた、零夫の姿があった。 「僕にもよくわかりません。秋山さんが超巨大尻出しゲロゲロ魔王になって、街を破壊しました」 「そうか」 「どうします?」 「どうって、出たとこ勝負だ」 「はあ?」 「ちゃんと計画的に生きられる性格だったら、こんな人生選んでない」 そりゃあそうか。 「感動の再会なのに、つれないっすね」 そう伝えると、露骨に面倒臭そうな顔をされた。十九・ロック・ミー・ナウ
僕の手にブルースハープが戻ってきた。零夫が隠し持ってることは薄々感づいていたけど、無理には取り返せなかった。だけど諦めてはいなかった。弓子が僕にくれたものだから。ブルースハープが戻ると同時に、『向こう』で経験したことをいろいろと思い出した。 ローゼンクランツとギルデンスターンに感動の再会はなかった。まるで昨日会った友人と駅でまた出会うような気楽さでふたりは話した。僕たちにその内心を覗くことはできなかったけど、きっとそこにも物語があるのだと思う。僕たちは隠れ家・第二照和を拠点とした。 「もしかして、僕たちが向こうの世界で倒した尻出しゲロゲロ魔王も、秋山さんみたいにもとは人間だったんですか?」 「どうだろうな。考えないようにしてるよ」 「いや、考えなきゃだめでしょう」 「考えてどうする? もと人間だったら倒すのをやめるか? 魔王秋山の力を見ただろう?」 「ええ。でも、言葉は通じないんですか? 説得したいです」 「幹夫。おまえは愚かだ」 「愚か?」 「逆に自分が説得される可能性を考えてもいない」 「僕が説得される? それはないでしょ。相手は破壊の限りを尽くす魔王ですよ?」 「それだよ。俺が言ってるのは」 「それ?」 「一方的に説得することが決まっている説得など、暴力と同じだ」 「同じじゃないでしょう」 「おまえが言っているのは、秋山悠子の父がやってたことと同じだよ」 そうかなあ。同じかなあ。だってどう考えたって人類のほうが……あれ? でも…… 「……見てたんですか? どこかで」 「ああ。おまえとはアンテナが違う」 アンテナ、か。 『大阪、名古屋、東京、その他日本各地で魔王発生中。警戒警報の出ている土地では、地域の防災担当の指示に従ってください。繰り返します。大阪、名古屋、東京、その他日本各地で魔王発生中……』 あの日から、秋山さんに触発されたかのように日本各地で魔王が発生した。高校生の魔王化は韓国、フィリピン、タイと波及し、最新のニュースではヨーロッパ、パリ郊外にも発生したという。その数を抑えることはもう不可能と思われた。 魔王が発生した場所には空間のゆらぎが残り、そのゆらぎのなかでは目からビームを撃つことができた。魔王討伐を志願するものは、このゲイザーガンと呼ばれる技工を身につけた。 「そのゲイザーガンって、ちゃんとした英語ですか? それとも和製英語ですか?」 弓子は和製英語に厳しい。 「魔王秋山を倒させはしない」 ローゼンクランツが言った。 「あの子はわたしの48番目の弟子だ。おまえらなんかにやらせてたまるか」 「じゃあ、どうするんですか? 説得はギルデンスターンが反対してますよ」 「好きにさせておけばいいよ」 「好きにって。そんなこと言ってたら街が破壊される」 「いいよ。その力があるってことは、その権利もあるのさ」 「悠子は、わたしが憧れたひとなんです」 弓子が言った。 「わたしが古賀を殺そうとしたとき、彼女も古賀を殺そうとしてくれた」 あれ、やっぱり殺す気だったんだ。 「だから、悠子が世界を滅ぼす気なら、わたしも世界を滅ぼしたい」 「はあ? ゴンも魔王になるの?」 「魔王になんかならない。人間のまま、この手で」 「ハッ! 最高の回答だね!」 ローゼンクランツが足を組み替えた。ギルデンスターンも静かに頷いているし、僕もそうだと思った。他に部屋にいたのは、ヤギ、田村、進藤くん。どうせ敵う相手でもない。好きにさせておくのが理にかなってるような気がしたけど、ただひとり、進藤くんだけが反対した。 「本当に彼女は、世界を滅ぼしたいんだと思いますか?」 「だって、実際に滅ぼそうとしてるじゃない」 弓子も冷静ではあった。 「古賀先輩を殺そうとしたとき、殺人者になりたかったですか?」 「なりたいわけないじゃない。ただ殺したかったの。殺したいのは事実なの、いまでも!」 「なにをすべきか、その答えが必要ですか?」 「必要」 「明日も、明後日も、このことを考えてはいけませんか? 悩み続けてはいけませんか? 世界が苦しいなら、その苦しい現実をずっと受け止めるという選択はできませんか?」 「あんたにはできるだろうけど、わたしには無理!」 弓子は秋山さんのことを『憧れ』と語っていた。言葉にはそのぶんの質量があった。 「喧嘩はやめろよ」 ギルデンスターンが制する。 「わたしだって、喧嘩したくてしてるわけじゃない」 「みんなそうですよ」 「だから、みんなそうだとしたら、どうするの、って話でしょ?」 呆れたようにローゼンクランツが溜息をつく。 「わかった。埒が明かない」 そんなことはもう、みんなわかっていた。でも、どうすればいいのか。 「あいつのいないとこで、あいつのことを決めちゃいけないんだよ。だれも」 兄の部屋には内側から鍵をかけることができなかった。 だから兄は、ひとりになりたいときに箱に入るしかなかった。 兄にとって、箱のなかのオモチャは自分の一部だった。 「レオー。秋山さんを助けに行くよー」 箱が揺れた。箱のなかで兄が向き直ったのだと思う。 「助けるのに、レオが持ってるラッパがいるんだ。それがないと秋山さん、お話ができないんだよ。返してくれるかな?」 返す気配がないことはすぐにわかった。 あれ以来、兄も笑わなくなっていた。 僕はあらかじめシャツのなかに仕込んでおいたダミーのバッテリーを取り出してみせた。ゲーミングPCのように七色に光る特製バッテリー。それをボタンで操作してみせると、兄は興味を持った。 まずは楊忌威滅垂法吽を魔王秋山さんに返してやりたいと、ローゼンクランツが言った。それをどう届けるか。その準備が整うかどうかというときに、ことは動いた。魔王秋山さん出現。場所は前回姿を消した場所、西町高校グラウンド。 「楊忌威滅垂法吽は?」 「持ってきました。これを届けるんですね?」 ローゼンクランツから秋山さんへ、そしていつの頃からか兄、零夫の手に渡っていたヤンキー・メタル・ホーン。 「ああ、地上からは難しい。空から向かう」 「空?」 ローゼンクランツとパッションブラッドの四人、凡人田村とで照和のエレベーターに乗り込んだ。この地下には亜璃朱の飛行船が眠っている。 「亜璃朱の飛行船を浮上させるエネルギーは音だ。特定の周波数を増幅し、その音圧によって浮かび上がる」 「だから僕たち、パッションブラッドが選ばれたんですね」 「そう」 それと「面白そうだから」という理由でついてきた田村。 「ずいぶん遅いエレベーターですね」 来なくても良かった田村がケチをつける。 「ああ、昭和初期のものだからな」 飛行船のフロアまで三分近くかかった。かつて秋山さんのバッテリーだった頃に訪れた記憶が、かすかに残っていた。搭乗。ブリッジへ。 「こちらギルデンスターン。聞こえるか、ローゼンクランツ」 地上待機のギルデンスターンから通信が入る。 「聞こえている。どうした」 「魔王秋山悠子が使い魔を召喚した。三百体ほどがこの上空を覆っている。気をつけろ」 「ああ、わかった。ディメンションフィールドは?」 ディメンションフィールド、すなわち魔王が展開する亜空間。 最近はだれかがカタカナ語を口にするたび、みんな弓子に注目するようになった。 「それは正しい英語ですか? それとも和製英語ですか?」 注文通りの弓子の質問。 「展開中だ。ゲイザーガン可用を確認した」 ローゼンクランツが連絡を受けている間にセットアップが完了した。 「どの曲をやる?」 ヤギが聞いた。 「新曲を」 進藤くんが答える。 「新曲、すごいしっとりした曲だけど大丈夫?」 「いいんだよ。この戦いを通して、僕たちのアルバムを完成させたい」 「そんな理由?」 そんな理由――だけどそれは、僕たちにとって重要なことだった。 曲名、花束。 弓子のギターソロから。 静かに曲がスタートすると、同時に亜璃朱の飛行船もその身を空に浮かせた。♪
信号にも 気づかず 歩き出す 影を みつけた メールを 見ていた 視界のはしっこ トラックが 急停止した あの日まで わたし たぶん 世界なんてなくなれと 思っていた とっさに電話して 救急車呼んで ずっと手を握り 呼び続けた ねえ いまもそうだよ わたし 世の中の役に 立ちたいなんて 思ってなんかないけど 病室の花の 水をかえるために 長い坂道 自転車こいだ なくなれと願った この世界の中を だれよりも早く 駆け抜けていた 大切なものを 見つけたとか そんなんじゃないけど 毎日 涙が 止まらなかった おこづかい はたいて 小さな 花束 買ったの あの日 着ていた カーディガン色の ベージュの リボンで飾った いつもの笑顔に 今日も 会えると思って叩いた 病室のドア 呼び止める声に ふりむいてみると 泣き腫らした目の 看護師さん ねえ 何が違うの わたし 駆け足で過ぎた この5日間 迷ってばかりいたけど あなたが語った 言葉拾い集め 花の名前を たくさん覚えた すれ違う風のなか 子どもたちの声が わたしの肩をなで 駆け抜けていく 泣けば泣くほど 空が青くて さよならとひとこと 言えなかったこと また思い出した さよなら 閉ざされたドアを たたけもせずに 花束かかえて 座り込んだ さよなら おばあちゃんが 愛した この世界は 何もできない わたしを選んだ さよなら わたし 途方にくれること 覚えた さよなら おばあちゃん いつかまた 会おうね さよなら さよなら♮
優しく、静かに、船は浮かび上がる。愛する人を迎えに行くのには最高の船出だ。そのつま先が地を離れるのを待って動力炉始動。船体随所に取り付けられたホーンが低い共鳴音を発する。躯体をつなぎ停めていた数十のチェーンが外れ、ランディングデッキが畳み込まれる。頭上に重なる二四四層のフロアが開き、2曲、3曲とセトリを進めるたびに高度が上がっていった。 「歌はもう大丈夫だ。あとは自力で飛べる」 天井から射す光が飛行船本来の色を浮かび上がらせる。 船内には遮光器土偶型のメカが動き回っていた。 「ちょっとまて。これはなんだ」 「それは、土師氏の開祖、野見宿禰が出雲国より呼び寄せた土部に、埴土をこねて作らせた埴輪だ」 その説明、最後の「埴輪だ」だけで済ませられなかったか? 地上へと浮上。船体が軋み、悲鳴を上げる。 「古代のマシーンだ。離陸はおそらく一度が限界だね」 その一度が怪しいほどに船体のあちこちで崩壊が始まっている。 「腐ってやがる」 田村が言うから、 「それでも世界でもっともおぞましい一族のなんたらかんたらかーっ」 僕も乗ってみた。 「やめときゃよかったな」 と、笑い飛ばすローゼンクランツ。やめるってなにを。 地上へ出て空中待機、ランディングデッキを伸ばし、取り残された人々を保護。ギルデンスターンも合流した。 「尻出しゲロゲロ魔鳥の群れがこちらに向かっている」 また尻出しゲロゲロか。 「ゲイザーガンで迎撃すればいいんですね?」 「無理だ。数が多い。それにデッキからだと死角もある」 ギルデンスターンは悪いニュース専門。対するローゼンクランツは、かすかな希望をもたらす。 「大丈夫だ。ソニックウェポンを使う」 地下空洞から地上へ、八百メートルの高度差はおよそ90ヘクトパスカルの気圧差を生む。更に高度を上げる。ヒヒイロカネの輝く船体が風を曳いて舞い上がる。千四百年ぶりの空ヘ。 「高度一二〇メートル」 「もっと高く飛べんのか」 「大丈夫。駅前のウェリスタワーさえ避ければ問題ない」 ウェリスタワー――藤井フミヤや鳩山邦夫が所有していると言われている久留米で最も高いビル……。視界、クリア。南へ回頭すると尻出しゲロゲロ魔王と化した秋山さんの姿が見える。それを覆う黒雲に見えるもの、それは群れなす尻出しゲロゲロ魔鳥。数秒後、船はその群れのなかへと突入した。 「兵毘威滅垂法吽稼働準備!」 ローゼンクランツが声を上げる。 「へびぃ・めたる・ほーん・かどう・じゅんび」 埴輪が復唱する。 どんなテクノロジーだ。 艦内にアラート音が響き渡るなか、デッキ中央のハッチが開き何者かがせり上がってきた。スポットライト。どこからだ。いや、いい。この際どうでもいい。フロアからせり上がってきたのは――それは――火焔型土器デザインのギターを抱えたローゼンクランツだった。 デッキに備えられた、アルテック・ランシングの巨大なスピーカーが唸る。 スポットライトのなか、ソロで響かせるファズの効いた野太い弦の響きとグリッサンド。 何を弾く気だ? 僕たちが戸惑っていると、ローゼンクランツは弓子にリードを促す。 マイクスタンドを固定。 「こっちも準備OK! リクエストは?」 リズムを刻み始める進藤くん。 「《きみの翼》を」 ローゼンクランツの真っ赤に染めた唇が微笑む。 前回の魔王秋山戦で弾いた曲だ。弓子が力強く頷き、ヴォーカルが走り出すと、艦体に仕込まれたホーンが共鳴する。 ドラムが入り一気に加速。ホーンで増幅された音圧が大気に歪みを生み出すと、音は刃となって尻出しゲロゲロ魔鳥の翼を切り裂く。その切り裂いた闇をまた、音圧が噛み砕く。 出番のないギルデンスターンと田村がツイストを踊るなか、ローゼンクランツが髪を前後に揺らす。どこまでもBPMを上げる進藤くん。負けずに追いかける僕と弓子のツインギター。同じフレーズは二度とは弾けない一期一会のベースライン。ローゼンクランツは五拍子の別の曲弾いてるし、なんでもありだな。なに弾いてんだ、僕ら。 風を切って溢れるビートとメロディ。 空に垂れ込めていた尻出しゲロゲロ魔鳥の暗雲は、光に噛み砕かれるようにして消えていった。 汗に濡れたシャツがべったりと肌に貼り付く。 気がつくと魔王の姿がない。 「秋山さんはどこへ?」 「ディメンションフィールドのなかに消えていった」 「クソみてぇな演奏だったからな。よほど耳障りだったんだろう」 いちばんクソみてぇな演奏をしていたローゼンクランツが笑った。 「ディメンションフィールドってのは……?」 凡人田村が、凡庸にたずねた。 「尻出しゲロゲロ宙域。そこに、魔王秋山悠子がいる」 ネーミング……。二十・フル・スチーム・アヘッド
「さっきの兵毘威滅垂法吽で限界を超えちまった」 このまま尻出しゲロゲロ宙域を目指すべきか、仕切り直すべきか、高床式の制御室で、僕たちは話した。 「着陸したらもう、次はない」 この船のことをいちばん知っているのはローゼンクランツだった。その彼女が、行くしか無いと主張する。 「再度姿を現すのを待てばいいのでは……?」 弱腰……いや、冷静なのは田村。 「田村少年。だったらきみはここに残って次のチャンスを待てばいい」 ローゼンクランツは睨みつける。 「俺たちは自分の手でチャンスをもぎとって来たんだ。ほかのやり方を知らない」 ギルデンスターンも考えは同じだった。 「ゴンはどうなの?」 「悠子に楊忌威滅垂法吽を届けたい。たとえ何があっても」 弓子は静かに自分の決意を噛みしめる。 「何があっても、って、尻出しゲロゲロ宙域だぞ? 行ったことあるのか?」 「ないけど」 「人類はまだだれも行ったことがない」 「はあ?」 平凡で凡庸な凡人のリアクションだが、命さえかかってなければ田村だってノリツッコミで返していただろう。 「人類はまだだれも行ったことがない、すなわち、楽しい」 こんなことを言い出す僕のほうがおかしい。 「いや、待てこら。そこ、酸素あるのか? 温度はちゃんとしてんのか? 重力あんのか? 飛行船飛べんのか?」 「細かいな、田村少年」 「おまえらが大雑把すぎるわ」 「リアクター全開!」 「聞けよこら!」 「待ってて、悠子!」 「ゴンも!」 「ワープ!」 「ワープすんな! どんなテクノロジーだ!」 と、凡人田村が無用な心配をしているすきに、亜璃朱の飛行船は尻出しゲロゲロ宙域へとワープアウトした。そこは―― 「空気あるじゃん」 「なんであるんだよ!」 「温度25度、湿度50%」 「快適じゃねえかよ!」 と、田村がキレるくらいに思いのほか快適だった。 「思い出すよなあ、田村」 「なにを?」 「はじめてエイペックスやった日」 「俺は思い出さねぇ」 「つれねえなぁ」 「音波探知機に敵影発見、左前方33度、魔王だ」 制御室中央の水鏡に敵影が映し出される。 「秋山か?」 「おそらく」 「船を接近させろ」 ローゼンクランツが伝声管で伝えると、船は回頭を始める。 「埴輪が操作してんのかね」 と、ローゼンクランツは暢気に笑う。 「いや、知らないのおかしいでしょ」 と、田村がツッコむが、そこは同意。 スラスターの応力で船体が軋みをあげる。ブリッジのすぐそば、巨大な光の帯がかすめる。 「粒子砲だ」 ギルデンスターン。 帯電した粒子の帯に船体はわずかに引き寄せられた。 「魔王までの距離は?」 「28キロ、接触は15分後」 「そこまでもつかな」 「有効射程はせいぜい2キロだ。最後のその1分持ちこたえればいい」 ギルデンスターンが渋い顔で決めるが、 「その後どうやって帰るの?」 田村が水を差す。 「それは……あー……それ系はローゼンクランツが……」 「そういうのを考えるのがおまえの仕事だろ。信頼してんだよ、こっちは」 「いや、帰りのことは考えてなかった」 渋い顔は崩さないが、本気で危機に直面した渋さだ。 「どうすんの、それ。ひどすぎない?」 「まあ、いまは魔王を倒すことだけ考えるんだな」 と、言いながら目を泳がせるギルデンスターン。 「いや、それじゃ駄目でしょ」 「これだから凡人を船に乗せるのは反対だったんだ」 ギルデンスターンが唇を噛んでテーブルを叩いてみせると、水鏡のレーダーモニターに波紋が広がった。そんなギルデンスターンを醒めた目で見る田村の前で、波紋は消えずさざ波立ち、やがて大きな波になる。 「これは……!?」 船全体が振動している。ギルデンスターンが水鏡を両手で押さえると、船を囲む無数の敵影が見えた。次の瞬間、衝撃が船体を駆け抜けてアラートが鳴り始めるが、田村は醒めた目を浮かべたまま。 「何が襲ってきた?」 「尻出しゲロゲロ魔竜の大群だ! すぐにデッキへ!」 「尻出しゲロゲロ魔竜!」 ブリッジに緊張が走るが、田村は「なんかもう駄目だこいつら」みたいな目で呆れてる。そろそろうざい。 「こっちはもう兵毘威滅垂法吽を使えん。肉弾戦になる」 「ゲイザーガンで……?」 ギルデンスターンは静かに頷くが、その肩越しに田村の醒めた目がある。 警報が轟くなか、デッキへ。 すでにローゼンクランツが応戦中。 尻出しゲロゲロ魔竜の数は見えているだけで数千……いや、万のオーダーになるかもしれない。 「1万匹いるとして、わたしたち7人でそれぞれ1匹1分で倒したとして、23時間48分!」 弓子はアバウトすぎる数字を弾いてみせるが、田村はツッコむこともなく隣で立ち尽くしている。 「そんなに倒せるか~い」 耐えきれず自分でツッコむ弓子。 「もう一度だけ兵毘威滅垂法吽を使う」 「できるのか!?」 無表情の田村。 「世界中にわたしの弟子が48人いる。悠子を省いても47人。そいつらに協力を仰ぐ! わたしはDJブースに向かう! おまえたちは演奏の準備だ!」 突っ立ってるだけの田村。 「田村先輩うざいっ!」 気にしない田村。 「演奏の準備!? 尻出しゲロゲロ魔竜が襲いくるデッキで!?」 「田村っ! どけよ!」 「やるしかないですよ! やりますよ、先輩!」 「ふんがー」 意味のない音を出す田村。 「曲、曲、曲どうしよう……」 「敵だ! 左! 弓子!」 ヤギが反応してゲイザーガンで仕留める。 ――What’s up My Guys! 館内のスピーカーがハウリングとともにローゼンクランツの声を鳴らす。放送が始まった。田村、視界に入るけど無視。 ――元気にやってるかおまえらーっ! おまえらの愛すべきマスター、ローゼンクランツ様から一生でたった一度のお願いだ! 「ヘイロックスター! って曲」 「えっ? なんでその曲を知ってるの!?」 左右から襲いくるゲロゲロ魔竜。ゲーザーガンで応戦するが、その翼が船体を打つ。 「ネットに残ってた」 更に一匹。ギルデンスターンがインターラプト。ついでに田村被弾、よたよたと左舷へフレームアウト。 「よっしゃあっ!」 ――おまえらの音楽を届けて欲しい! ローゼンクランツが遠く地球のリスナーに声を届けると、船体が大きく傾く。 「左舷に突っ込んできた!」 傾いた床を滑って田村戻ってきた。 「大丈夫ですか!?」 「船のことはまかせろ」 田村そのまま右舷へフレームアウト。 ――座標は! 尻出しゲロゲロ宙域! ヤギ、弓子、準備完了。サムズアップ。ボリューム最大。 船体から無数の棒がせり出し、棒は傘のように開く。パラボラだ。そのパラボラが遠くに見える地球へと向けられる。 ――さあ! 楊忌威滅垂法吽を轟かせろ! かつて深夜のラジオで暴走族たちをアジテイトしたローゼンクランツの声が響く。 地球ではその声に呼応し、引退した暴走族たちが30年ぶりに改造車を車庫から出して、セルモーターを吹かす。そうして準備が整ったマシーンから順に、パラリラの音を響かせる。 その音を捉え、亜璃朱の飛行船のパラボラが開く。 船体のホーンからパラリラの音が響く。ひとつ、またひとつのパラボラが、遠く地球で奏でられる楊忌威滅垂法吽の轟音を捉える。パラリラパラリラ、パラリラパラリラ、鳴り響く楊忌威滅垂法吽。そのなかで、亜璃朱の飛行船が輝き始める。 ――いまだ、ゴン! 音楽を! シンバル連打からのフィルイン、ドライブ!♪
ウォウオウ 俺はロックスター 夢は Rock ‘n’ Roll Hall of Fame 振り返らないマイ・ウェイ 悔いは残さないぜ まばらに入ったオーディエンス 声の限りのスクリーム ギターヘッドのフォトグラフ 愛しのマイ・ダーリン ヘイ カリスマ・ロックスター あなたの歌を聞かせてよ 傷だらけのレスポール ぎゅんぎゅん泣かせてよ♮
間奏。ドラムソロ。 船体に取り付けられた48のホーンが次々と音の波動を放ち、射線上のゲロゲロ魔竜を焼き払う。が、被弾も大きい。躯体に取り付いた魔竜をギルデンスターンがゲイザーガンで射抜く。最後は肉弾。ギターを叩きつける。田村いたので排除。♪
俺の歌を聞きたいかい Come on Baby Now Here we go! 今日はおごるぜメニューをほら シャンパンはどうだい 気前良さもミ・リョ・ク トキメキがほしいの あなたが今日はシュ・ヤ・ク 歌い明かしましょう 熱いハートでシャウトする だけどココロはロンリネス 妻と子が待つスイートホーム ココロの絆創膏♮
「これがやりたかったんだ、これが」 はあ? 「歌をバックに最終決戦」 ギルデンスターンはサムズアップを見せるが、こんな曲で――って、傾いたフロアを田村が転がっていったぁぁぁぁっ! 田村ぁぁぁぁぁぁっ!♪
ごめんね今日はすっからかん 客の入りが悪すぎた 明日のステージは完売だ 寿司でも食いに行こう 嘘をつくなアホ亭主 どこのビッチに貢いできた 娘連れて出ていくぞ いい加減にしろ つれないことを言わないで キミが心のささえなんだ あんがい打たれ弱いんだ 言葉に気をつけて♮
頭上に魔竜。急降下を避けきれずにヤギ被弾。続いて進藤くん、ドラムセットごと魔竜に吹き飛ばされる。ローゼンクランツもデッキに出て応戦するが多勢に無勢。ホーンも次々と破壊されている。残るホーンは推定7つ。プレイヤーは僕と弓子のみ。あと、どこかに田村。 「音楽がある限り、わたしたちは死なない!」 ローゼンクランツが吠える。♪
ヘイ カリスマ・ロックスター あなたの歌を聞かせてよ 傷だらけのレスポール ぎゅんぎゅん泣かせてよ 俺の歌を聞きたいかい Come on Baby Now Here we go! 今日はおごるぜメニューをほら シャンパンはどうだい 気前良さもミ・リョ・ク トキメキがほしいの あなたが今日はシュ・ヤ・ク 歌い明かしましょう ヘイ カリスマ・ロックスター ヘイ カリスマ・ロックスター♮
ラストはスキャット、息が続く限りのファルセットシャウト、どこまでもどこまでも転調し音階を駆け上がる。亜光速ストロークに100オクターブのグリッサンド。ホーンはすべて破壊され、すでにローゼンクランツもギルデンスターンも倒れている。あといつの間にか田村も倒れてたけど、それは置いといて敵は残り一体。 このアウトロで倒す! 僕と弓子とで! 死闘の果て、尻出しゲロゲロ魔竜の最後の一体が倒れたとき、僕らのヒットポイントも尽きた。 船の被弾も大きく、もはや飛行船と呼べる形を成してはいない。 ラスボスを前に、すべての力を出し尽くした。 ローゼンクランツも深手を負い、それでも声を絞り出すが…… 「音楽がある限り……」 と、そこまでで息絶えた。 目のまえに尻出しゲロゲロ魔王、秋山さんの姿がある。 だのに、すべての音が尽きた。 僕は膝を付き、ポケットからブルースハープがこぼれて、転がった。 終わりだ……。 僕の胸が宇宙の闇に染まりかけたとき、ブルースハープに近づく影が見えた。 零夫だ。 いつ乗り込んだんだ。 零夫がブルースハープを拾い上げた。 そうか。おまえがいたんだったな。 「零夫……バトンタッチだ」❡
ハーモニカを拾った! だけど! みんな死んでる! 海賊が来たんだ。皆殺しにあったんだ! まずい! 僕が戦わないと、このままでは地球も破壊される! いや、でも、戦うったって、武器がないじゃん。おもちゃ箱を持ってくるの忘れてたし、お父さんもお母さんもいない。 無理。戦えない。でも、ハーモニカだったら吹ける。 パープー……。 この音が好き。 吸って吐くだけで音楽になる。 パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! 音楽ってたぶん、音の出る呼吸だ。 パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! うおおおおおっ! 無敵だぞ僕は! 息してるだけだぞ! 息してるだけでパープーだぞ! 僕がハーモニカを吹いていると、ローゼンクランツがゆっくりと立ち上がった。 「よくやった、零夫」 「えっ!?」 「おまえのハープの音色で、わたしは蘇った」 「マジかっ!」 「ああ、あとはわたしにまかせな」 「すげえ! 生き返った! すげえ!」 ローゼンクランツはヘッドホンを装着、指を鳴らすとマイクがせり上がってきた。かっけー。なんだそれ。 ――地球に残った能無しども! パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! ――ローゼンクランツは―― パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! 「うるさいわ!」 「すげえ! 生き返った! すげえ! すげえ! すげえ!」 「何度も驚くな! 一回で驚け!」 「すげえ!」 「驚けえぇっ!!!」 「すげえぇっ!!!」 「驚けえぇぇぇぇぇぇぇぇっ!!!」 「すげえぇぇぇぇぇぇぇぇっ!!!」 ――ローゼンクランツは、死の底から這い上がった! すなわち生き返った! どういうことかわかるか? パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! ――一生のお願いを……もういちど使えるってことだ! マジかっ! すげえ! マジかっ! ――さあ、リスナーのみんな! この船、亜璃朱の飛行船に……力を! パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! パパパプー! パパパプー! パパパプー! パパパプープープー! 「うっさいわーっ!」 しーん…… 船の上のひとたちはみんな死んでいる。幹夫、田村、ヤギ、進藤くん……みんなもうピクリとも動かない…… それにパラボラはぜんぶ壊れてる。 「ひゃっほう!」 「喜ぶな!」 地球のみんながどんなに応援してくれたって、もう届かない。パラボラないし。 魔王秋山さんが目の前に見える。魔王はガトリングの腕をこちらに向け、ミサイルハッチがすべて開いた。 「死にますよ、僕ら」 「急にテンション下げるなーっ!」 「捨てられるね。ゴミだから」 つい口の端に漏れた本音。 それをローゼンクランツは聞き逃さなかった。 「そうじゃない。零夫少年」 「じゃあ、どうなの?」 「声を上げろ。『ここにいる』と、ただそれだけでいい」 「それだけ?」 「あとはまかせるんだ。この宇宙に!」 「よっしゃあああああっ! まかせるのはとくいだ! よっしゃ! よっしゃ! よっしゃあああああっ!」 僕はハーモニカを吹いた! 「さあ! 渾身の力で!」 「僕は! ここだぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ! ここだぁっ! ここだぁっ! ここだあああああっ! オナラプー! なんとかしろ、宇宙ーっ!」 その音はDJローゼンクランツのマイクを通してラジオ電波になって全宇宙を駆け巡る。すると次の瞬間、空間の一点が輝き始めた。 「来た……」 ローゼンクランツの目が輝く。 来た? なにが? 「知らん」 「知らんのか」 輝きはみるみる大きくなり、ひとつのシルエットを浮かび上がらせる。 自動車だ。しかも見たことがある。その自動車が―― 「古澤くん」 僕に話しかけてきたーっ! すげえ! 自動車がーっ! 「そこに落ちてるラッパをわたしにちょうだい」 落ちてる? あ、あった。幹夫ががめてったやつ。 「おまえは?」 「みー子。秋山みー子。悠子お姉ちゃんの、生まれることのなかった妹」 しらんけど。 パー(レ) プー(ミ) パー(ド) パー(ド) パー(ソ) 僕がハーモニカを鳴らすと―― パーッ(D4) パーッ(E4) パーッ(C4) パーッ(C3) ……パーッ(G3) みー子がクラクションで応えた! すげえ! すげえ! 思わずラッパを拾って渡すと、みー子は大きく口を開けてそれを飲み込んだ。 みー子の体から音楽が轟き出る。 小さい頃に聞いたドラマの主題歌。 《Monster》だ! 「ありがとう」 みー子の声! 「ガラクタだって、役に立ちたいんだよ。だれにも見向きされなくても」 ラッパのリズムに合わせて無数のコードが触手のように伸びだした。 触手は飛行船の躯体を剥ぎ取り、みー子のなかに取り込み、車はみるみるその姿を変える。そこに現れたのは、もうひとりの巨大な秋山さん、肉体を得たみー子だった。 「すげえ! すげえ! すげえ! すげえ!」 「空間転移装置稼働!」 みー子のまわりに光が渦をなす。 「乗員全員を退避させる!」 「そんなことできるのっ!?」 「うん! なんだってできる! 零夫くんも退避を!」 「やだ! 僕はこのままがいい! 最後まで見たい!」 「わかった。次元振動波発生!」 みー子の腕に装着されたケーブルが回りだし、空間を歪ませる! 光が溢れ出し空間を歪ませると、そのゆらぎのなかに僕の町が見えた! 「すげえ! すげえ! すげえ!」 乗員はみんな光の粒になって地球へと帰っていく。 ――それを見届けて、光に包まれたみー子は、魔王に語りかけた。 「お姉ちゃん」 魔王の腕が下がる。 「みー子……?」 大きいみー子はその手にラッパを掲げ、魔王に近づいていく。 「これ、お姉ちゃんのココロだよ」 「会いたかった。みー子」 「うん。わたしも」 鳴り響く《Monster》。 魔王を覆っていた幾重もの闇を超えて、みー子の光の体が魔王のなかに溶けていく。 光と闇とをはげしく撒き散らして、僕のまえで悠子とみー子はひとつになり、やがて亜璃朱の飛行船は光と闇が作り出す渦に噛み砕かれた。 放り出された宇宙の闇。無限の時間、無限の空間が僕をつかまえて、僕の手からハーモニカが滑り落ちた。 幹夫……。 バトンタッチだ。 ハーモニカを返すよ。 さよなら……。 幹夫……。第三部・レッツ・ドゥ・ザ・タイムワープ
二十一・僕たちの世界
「車がある! こっちだ!」 暗い山道、懐中電灯の光が宙に揺れる。 「見つかったらしいぞー! おーい!」 闇に濡れた木々の間に、いくつかの声がこだまする。 舗装路のはずれ、枯れ葉の積もる道の奥にシボレーの大型のバンがあった。 駆けつけると、すぐに田村も姿を見せた。 息を切らしたまま懐中電灯で中を照らし覗き込む。 そのなかに、眩しげに手のひらをかざす秋山さんの姿があった。 ドアを開けて秋山さんを保護。 「零夫は?」 「いない。外に出たのかもしれない」 「ひとりで?」 バンのなかには僕のブルースハープが残されていた。 探索を続けると、沢の近くに何者かの影が倒れていた。 そのかたわら、弓子が懐中電灯を持ったまま、力なくうつむいている。 「見つかったのか?」 弓子は何も言わない。ただ涙を流して、僕の手が肩に触れると崩れるように座り込んだ。 そこには、人形になった僕が横たわっていた。 静かに雨が降り出し、森の木々はざわめき、そのしずくを葉に湛えた。 上空に報道のヘリのライトが見える。 腰に下げたラジオが行方不明の少年少女発見のニュースを伝えている。 慣れてる……という言い方は変だけど、僕にとっては覚悟していた景色だった。 「弓子。終わったんだよ」 長い長い物語の果てに、僕らは結末を迎えたんだ。 弓子はうずくまったまま、その運命を拒絶するかのように肩を震わせた。 雨の隙間から、零夫と歌った若気の至りバスターズの歌が聞こえる。 ――過去を消すなら二千円~ ――書き換えるなら五千円~ うっかりこらえようとしたせいで、涙がこぼれた。 もういちどやりなおしたい。零夫と手をつないで学校に通ったその日から。こんな事件が起きるきっかけすらない、真っ白な時間から。 ひとが集まってきた。 田村、進藤くん、ヤギ、それにギルデンスターンにローゼンクランツ……。 みな押し黙って口を開かない。 決めたよ。僕は。こんな現実、僕には受け入れられない。 「ねえ、弓子」 声を絞り出す。 「こんな結末、納得できない。時を戻そう。もう一度やり直すんだ」 ギルデンスターンがすぐに反応する。 「やめろ。また魔王を生み出すことになる」 踏み出すギルデンスターンをローゼンクランツが制する。 「あいつらは魔王を倒したんだ。魔王を生み出す権利だってあるのさ」 「しかし……!」 凡人田村はただただ言葉を選び倦ねている。 でもこれは僕たちの問題。僕たちが決めることだ。 「やり直そう。弓子」 その言葉を聞いたギルデンスターンの深い溜息。 弓子は、「うん」と、静かに、ゆっくりと頷いた。 「でも、過去からじゃない。やりなおすとしたら、この瞬間から」 「この瞬間?」 「わたしたちは何度でもやりなおせる。いま、この瞬間から、何度でも」 弓子はポケットからブルースハープを取り出した。その真白き輝きが闇を切り裂く。いつか島村楽器でペアで買ったブルースハープ。弓子の宝物。それを動かなくなった零夫の手に持たせると、奇跡が起きた。 零夫の指がピクリと動いて、その次の瞬間、零夫は人間になった。 「生き返りやがった!」 ローゼンクランツが叫んだ。 「へ?」 と、凡人田村がおかしな声を出す。 「ここで生き返るって、おかしくない?」 だけど僕たちは知っていた。この奇跡が起きることを。 「知っていたとかじゃなくて」 零夫は立ち上がり、にっこりと笑うと、ブルースハープ……ハーモニカを口にあてた。 「おかえり、零夫」 「おかえりって」←田村 パープー。 「おかえりなさい。みんな待ってたんだよ、きみのこと」 「はあ?」←田村 パープーパープーパープーパープー! 水滴に濡れた懐中電灯の明かりが、雨の線を浮かび上がらせる。 「さあ、フィニッシュを決めよう!」 パープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープーパープー! パパパプー! パパパプー! パパパプー! パパパプープープー! 「うっさいわーっ!」 ローゼンクランツが笑顔で怒鳴った。その目には涙も浮かべて。 「なんかすごい予定調和っぽくない?」←田村 弓子はギターをかかえてチョーキングの効いた音をひとつ奏でた。 ぎゅわわわわわぁ~ん! 「やりなおそう。この瞬間から」 「わけわかんねぇ」←田村 「田村おまえもう、帰れよ」 フロアライトの光線が立ち上がる。雨の降る深夜の森に光を撒き散らすミラーボール。僕たちパッションブラッドのステージが始まる。 「それでは……」 僕のアドリブに重ねて弓子のMC。 「わたしたちは、時間なんか遡らなくても、いま、この瞬間から。何度でもやりなおせる。何度でも。何度でも……」 リズム隊も軽く音を重ねる。 「……そんな思いを歌にしました。聴いてください。リスタート」 ブルースハープを弓子に渡す。❡
前奏―― ポップなイントロのあいまを、ツインギターが駆け回り、メロディの扉を開く。 ストローク!♪
ただいま 長い旅の終わりに たったいま この街に戻ったの 涙は 遠い海に捨てたの いろんなドラマ ひとりで乗り越え またいだ 高い敷居の向こう 懐かしい スープの香りがする ごめんなさい 言いそこねたわたしに 手料理ならべ 涙のスパイス もういちど この坂道を シャツのボタンあけ 走りおりる 追いかけた わたしの夢は また最初から リスタート ただいま 親不孝でごめんね たったいま みんなにも会ってきた 遠くまで 走ったらそれだけで 見つかるなんて 信じた何かを もういちど ここで探すの 通り過ぎてった いざこざなんて アルバムの 中に閉じ込め また最初から リスタート♮
雨は、万雷の拍手にも似ていた。 曲を終えると、濡れそぼつ悠子の姿があった。 悠子は力なく近づいてきて、 「ふざけるな……」 そうつぶやくと、顔にかかる雨のしずくを拭って、握りしめたロープを零夫の首に回した。 「なんでこんなやつ、生き返らせたんだ!」 かがみ込む零夫に引きずられながら、悠子は両手に力を込める。 「わたしはこいつに人生を奪われたんだ!」 涙ながらに訴える。 不意を突かれてだれも動けない。 わたしはわけもわからず悠子に駆け寄り、その肩を抱きしめた。 「ごめん。悠子」 悠子の手が緩み、零夫の体が地面に倒れる。 「うるさいよ! 離せよ弓子! 死ねよ! みんな死ねよ!」 悠子は抱き寄せるわたしの手を払おうと、肩を揺する。 「なにがグラミー賞だ! なにもなかったように忘れんのかよ! 歌ってんじゃねえよ、クソがっ! わたしだけだよ! これからも、ずっと、苦しむのはあああっ!」 最後は絶叫。そのまま大声で泣き崩れた。 頭上高くに跳ねる雨の音が、その声を吸い取っていく。 「なんなんだよもう! 死ねよーっ! ふざけるなあああああっ!」 その声は雨の音と混じり合い、どこまでも、どこまでも響き渡った。この雨雲が、この雨が、この夜が悠子の声だった。わたしは為すすべもなく悠子を抱きしめた。雨に奪われた体温を、少しでも戻したかった。 ごめんね。なにもしてあげられなくて。 ただただ悲しくて、頬を濡らしたまま、胸のなかに溢れる歌を吐息に漏らした。 木々のざわめきの間、歌はかすかな風にのって森に染み込んでいく。 どんなに願っても、なにも変わるものはない。 ただ現実ばかりが続いていく。 だれも僕の世界を、変えることはできない。 ならば捧げよう。この人生を、憧れたあなたのために。アンコール
みなさん、どうもありがとうございましたー! サブヒロイン役、パッションブラッドのヴォーカル、権丈弓子です! 本日はさよならおやすみノベルズ第7回公演、『憧れの秋山さんに捧げる冒険』お手にとっていただき誠にありがとうございました! それじゃあ、恒例のヤツ、行ってみよう! いかれたメンバーを紹介するぜぇ~っ!! まずは正ヒロイン、秋山悠子~! 秋山です、今日はみなさんどうもありがとうございました~! こうしてみなさんと時を過ごせたこと、一生の思い出にします! お次はバンドメンバー、人生二周目! ドラムスの進藤くーん! 人生二周目とか言われてますけど、たぶん三周か四周目です。 本日はどうもありがとうございました! 同じくバンドメンバー、ベースのヤギこと青柳くーん! メエメエ鳴くほうじゃありませーん。 みなさんの声援に感謝いたします! それから、ヒロイン秋山悠子の師、DJローゼンクラーンッ! 愛してるぜーっ! みんなーっ! タイムパトロール隊の謎の男、ギタリスト、ギルデンスターン八重樫浩一! またいつか、どこかでお会いしましょう! そして中村先生と田中先生~! 詩はココロ! 人生にパッションを! どうもありがとうございましたー! 若気の至りバスターズのおふたり~! ご声援、まことに有難き幸せ! またどこかでお会いしましょうぞ! 古賀くん石井くん弥永さん、それから下級生のみなさーん! みなさんにお会いできて光栄です! これからも応援よろしくおねがいします! それからヒロイン秋山悠子の妹役、秋山みー子ー! はーい! みなさん楽しんでくれましたかー! これからも応援よろしくねー! 従兄弟とその家族~! 本日はどうもありがとうございました! そして主人公の兄、たまに主人公役の古澤零夫~! 短いあいだでしたが、同じ時間を過ごせたこと、ココロより感謝いたします! そして主人公! パッションブラッドのフロントマン、古澤幹夫~! えー、本日はどうもありがとうございました! ホームページのほうに過去作のキンドルへのリンクや試し読みコーナーを用意させていただいていますので、ぜひ「さよならおやすみノベルズ」で検索して御覧ください。 では、マイクをこの物語の真の主人公、権丈弓子にお返しします。 えー、はい。それでは最後になりましたが、アンコールにこの曲を聞いてください! わたしたちの新曲…… 緑の旗。 ――バンドの四人を残し劇団員はける。 客電落とし、ヴォーカル、権丈弓子にスポット。 弓子のアフタービートのカッティングと幹夫のタッピング。 サスペンションライト。♪
緑の旗を 立てましょう 意味なんか ないけど 誰かがそれを みつけて 意味をおしえて くれたら 二人の甘い 生活は 旗の下で 始まるの イライラ しないでね 意味を さがさないでね あたしは あなたの お嫁さんに なったの この緑の 旗の下 二人で手を ふればいいわ あたしたちを みつけた 旅人を 迎えましょう 今日から きっと毎日 ごちそうを 作るわ デコボコの テーブルに オレンジ色の クロスかけ ふぞろいな 皿とボウルに ごちそうを ならべるの キノコソテー 食べながら 旅人は こう言うわ ここはまるで 妖精の おうちみたい ですねって あなたがちょっと 食べかけた パンのかけら ほおばって あたしは こしをつきだし 笑いながら 言うのよ はんぶん 正解 はんぶん ハズレ 緑の旗を 立てましょう 意味なんか ないけど 誰かがそれを みつけて 意味をおしえて くれたら 二人の甘い 生活は 旗の下で 始まるの♮
それではまたどこかでお会いしましょう! DJ、ローゼンクランツ! You guys are amazing! Thank you so much! どうもありがとう!あとがき
このたびは《憧れの秋山さんに捧げる冒険》、お手にとっていただきありがとうございました! 今作は古澤幹夫シリーズの第三弾になります。主人公名が同じってことは、続編なの? 平行世界での出来事なの? と思われそうですが、実はそんなには関係がなくて、たまたま主人公の名前が同じだと考えるのが世界観に近いかなと思います。あるいは手塚治虫先生のスターシステムのようなものでしょうか。すべての古澤幹夫にロック好きのエレキギター弾きという点は共通していますが、舞台にした年代は違いますし、物語的なつながりもありません。 また、気になるのは前作《憧れの竹下さんに捧げる冒険》とのつながりだと思いますが、これも不思議なことにほぼほぼつながりがないんです。にもかかわらず舞台は同じ、登場人物もけっこう被ってるし、三部二十一章の構成も同じだし文体も似たりよったり、文字数ベースで2割ほどこちらが多いのが違うくらい。 だけどこれには理由があります。 前作《憧れの竹下さんに捧げる冒険》は、物語もプロットも捨てて魂の赴くままに手癖だけで書きたい! と思って書き始めたものでした。なので、書いているときはもう楽しくてしょうがなかったんですが、いざリリースして冷静になって読んでみると、やっぱなんか雑だな、と思ってしまいました。後半の水槽脳とか、遣隋使とか、神武東征とかの話は要らなかったんじゃないかとか、ラスト何が起きたのかわからなすぎるんじゃないかとか、いったん公開を中止して書き直そうかとまで思ったんですが、はたと、書き直すくらいだったらもう1本書けばいいじゃないかと思いついて書いたのが今作、《憧れの秋山さんに捧げる冒険》なのです。 しかし不思議なくらい別物に仕上がりました。あ、いやこれも書いたひとがそう思ってるだけかもしれませんが。 前作から踏襲したのは文体や世界観のほかに、『キャラクターの容姿を描写しない』というポリシーがあります。外見とエピソードをいっさい関連付けたくなかったんです。また、原因と結果を結びつけたくないというか、安易な教訓を導きたくないために、物語的なラインも意図的に断ち切っています。 前作の話はここまでにして、お気づきの方も多いと思いますが、今作ではビートルズのアクロス・ザ・ユニバースとイエロー・サブマリンを下敷きにして書いています。下敷きと言っても筋書きを持ってきたとかではなく、遠くにBGMとして流しておく程度のものです。作中での言及もあるので、読みながら脳内に流れてきた人も少なくないかと思います。第一部がアクロス・ザ・ユニバースのイメージ。タイトルそのままですね。第二部はイエロー・サブマリンで、タイトルのフル・スチーム・アヘッドは同曲中のガヤです。これらの曲について書くと、今作のテーマをここで繰り返してしまうことになるので避けますが、いまあらためて歌詞を読み直して、ビートルズの凄さを思い知らされています。いや、みんな凄いんですよ。ビートルズばかりでなく、ドアーズも、レッド・ツェッペリンも、そして僕が名を知らないようなバンドの中にも凄い人はたくさんいた、そして、いるんですよ。 それと、告白になりますが、このお話に出てくるライブハウスの照和、実は行ったことがありません。第一部で散々引っ張っておいて、第二部でようやく出てくるかと思いきや肩透かしを食らわせたのは、そういう理由なんです。書こうにもよく知らない。取材して書けばいいじゃんと思われるかもしれませんが、表面的なことを舐めただけで書くのも違うと思いました。普段、最低限の取材はして書いているつもりではあるんですが、こういうものは『書くための取材』だけじゃいけないと思い、自制しました。 なぜ行く機会がなかったかと問われると、だって照和って僕が13歳から26歳まで閉まってたんですよ。26過ぎてからも幾度か福岡あたりへ行くことはありましたが、残念ながら照和へは行かぬままでした。舞台の方だと、ぼんプラザホールや西鉄ホールには行ったことがありますが……照和は、長渕剛の歌のなかでしか知らない、まさに僕のなかでは伝説のフォーク喫茶です。 今作は書き溜めていた詩の供養にもなりましたし、何もかも放出してしまった感じです。古澤幹夫シリーズはもしかしたらもう一本書くかもしれませんが、ここまで濃い内容にはできないんじゃないかって気もちょっとしています。もし本作を気に入っていただけたならば、次の作品もぜひ気長に待っていただけたらと願っています。 では、別れは惜しいのですが、今日のところはこれで。これからも、いま、この瞬間にタイムワープを続けたいと思います。 本日は本当にありがとうございました!⚪
🐹
🐰
🐻
⬜